解説記事2022年05月30日 SCOPE 過払金債務免除の貸金業者、借主の滞納税に第二次納税義務(2022年5月30日号・№932)
債務免除の「合理的な理由」主張も認められず
過払金債務免除の貸金業者、借主の滞納税に第二次納税義務
借主から過払金返還債務の免除を受けた元貸金業者(原告)が、借主の滞納国税について第二次納税義務を有するか否かが争われた裁判で、東京地裁民事51部(岡田幸人裁判長)は令和4年5月17日、納付告知処分の取消しを求めた原告の請求を棄却した。
東京地裁は、本件債務免除には、「実質的にみて、当該無償譲渡等の処分により第三者に帰属することとなった経済的利益がなお滞納者に帰属しているものとして当該第三者に対して納税義務を課すことがかえって公平を失することとなるような特段の事情は認められない」との判断を下した。
東京地裁、無償譲渡等の処分該当性を否定すべき特段の事情なし
本件は、貸金業者であった原告が、借主から過払金返還請求を受けたため、和解契約を締結して過払金返還債務等の一部の免除を受けたところ、処分行政庁から、原告は借主の滞納国税に係る第二次納税義務を負うとして納付告知を受けたことから、当該告知処分の取消しを求めた事案である。
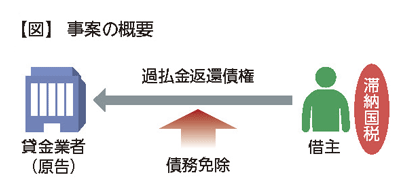
東京地裁は、本件の債務の免除が国税徴収法(以下、「徴収法」)39条の「債務の免除」に該当するかどうかについて、まず、「本件債務免除は、本件和解契約に基づき、原告が本件滞納者に所定の期限までに本件解決金(20万円)を支払うことを停止条件として、本件滞納者が原告に対して有するその余の債権を放棄し、これにより原告が当該債権に係る債務の免除を受けるというものであるから、契約による債務の免除として、その外形から、徴収法39条1項所定の『債務の免除』に該当することは明らかである」と指摘した。
その上で、「本件和解契約及びこれに基づく本件債務免除に至る経緯に照らし、本件債務免除が、実質的に対価性を有するものであるとは認められないし、本件和解契約締結日ないし本件解決金支払日の時点において、本件債務免除に係る債権が、客観的にみて実質において無価値であったことを認めるに足りる証拠もなく、他に、実質的にみて、本件債務免除により消滅した上記債権に係る経済的利益がなお本件滞納者に帰属しているものとして、本件債務免除の相手方である原告に対して納税義務を課すことがかえって公平を失することとなるような特段の事情が存するものとも認められない」として、本件債務免除は、徴収法39条の「債務の免除」に該当するとの判断を下した。
債務免除のきっかけは処分行政庁からの照会
原告は、本件和解契約の締結、つまり本件債務免除には、過払問題の早期解決のためという「合理的な理由」がある旨主張したが、これに対して東京地裁は、「徴収法39条所定の無償譲渡等の処分該当性を否定すべき特段の事情が認められるか否かについては、実質的にみて、当該無償譲渡等の処分により第三者に帰属することとなった経済的利益がなお滞納者に帰属しているものとして当該第三者に対して納税義務を課すことがかえって公平を失するものといえるか否かという観点から検討すべき」として、本件債務免除に特段の事情が認められないのは前記のとおりとした。
また、「原告は、平成22年11月15日に本件滞納者から分割金の支払を受けたのを最後に、本件滞納者とは交渉がなかったところ、平成28年12月に処分行政庁から本件滞納者との間の取引についての照会を受けるや、直ちに本件滞納者に連絡を取り、その時点で生じていた具体的な過払金等の額を伝えることなく和解契約を締結することを持ち掛け、本件滞納者との協議が整った後、本件和解契約書を本件滞納者に発送するのと同時に処分行政庁に対して上記照会に対する回答書を送付して本件滞納者との間の取引内容を開示し、その後、本件滞納者からその署名押印のある本件和解契約書の返送を受けた後、速やかに本件解決金を本件滞納者に支払い、これにより、本件解決金の額を大きく上回る110万円近い過払金債務の免除を受けたことが認められ、このような経緯に照らせば、原告は、本件滞納者の本件滞納国税に係る滞納処分として、本件過払金債権が差し押さえられ、その全額が取り立てられることを回避する目的で、本件滞納者との間で本件債務免除に係る条項を含む本件和解契約を締結するに至ったことがうかがわれるところであり、原告の上記主張はその前提を欠く」とも指摘している。
第二次納税義務成立要件満たし処分適法
そして、東京地裁は、処分の適法性の判断にあたり、第二次納税義務が成立するための要件として、「①滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること、②滞納者がその財産につき、無償譲渡等の処分をしたこと、③無償譲渡等の処分が、当該国税の法定納期限の1年前の日以後にされたものであること、④徴収不足が、無償譲渡等の処分に基因すること、⑤無償譲渡等の処分により受けた利益が現存すること」を挙げた。
その上で、上記①の要件について、「本件滞納者は、本件処分日の現況において、本件滞納国税の総額を徴収するに足りる財産を有していなかった」、②について「本件滞納者が、原告に対する本件過払金債権を放棄したことは、徴収法39条の『債務の免除』に該当する」、③について「上記債務の免除がされたのは本件解決金支払日(平成29年1月27日)であり、本件滞納国税に係る最も遅い法定納期限は平成16年6月10日である」、④について「被告は滞納処分により本件過払金債権の全額を差し押さえることによってしか本件滞納国税を徴収することができなかったところ、本件債務免除によって不可能となった」、⑤について「原告が本件債務免除により受けた利益がその後消滅したこともうかがわれず、本件処分日において現に存するものと認められる」として、5つの要件すべてを満たすことから、処分は適法との判断を下した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























