解説記事2022年06月20日 ニュース特集 非上場株式評価における総則6項適用事案(2022年6月20日号・№935)
ニュース特集
土地等だけでなく非上場株式にも
非上場株式評価における総則6項適用事案
財産評価基本通達における総則6項の適用に関しては、令和4年4月19日の最高裁判決が記憶に新しいが(本誌928号等参照)、非上場株式の評価に対して総則6項が適用され、裁決で争われた事案も見受けられる。最初に紹介する裁決では、請求人らが「S1+S2」方式を選択して非上場株式を評価したことに対して、総則6項が適用されている。審判所は、両者の評価額のかい離は2分の1に満たないものであったが、請求人らが実施した新株発行及び資産運用の一連の行為は相続税の負担を軽減する目的であったと判断し、原処分庁の更正処分を支持している。もう1件は請求人が行った類似業種比準価額による評価と、民間の評価機関における鑑定評価とのかい離が10倍あったというもの。審判所は、原処分庁の総則6項適用を支持しているが、同事案についてはすでに相続人らが総則6項の適用を不服として提訴が行われている。
原処分庁、株式保有特定会社を前提に純資産価額方式で評価すべき
最初に紹介する裁決は、相続等により取得した非上場株式(本件株式)の評価方法が争われたもの(関裁(諸)令3第3号)。請求人らが相続等により取得した同族会社(本件法人)の株式の評価において「S1+S2」方式を選択して相続税の申告を行ったところ、原処分庁が評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして総則6項が適用されている。
請求人は「小会社」に該当と主張
請求人らは、評価通達が小会社について定める併用方式により評価すべきとし、1株当たりの評価額を1,858円であると主張。予備的には、評価通達が株式保有特定会社について選択的に定める「S1+S2」方式により、1株当たり2,274円と評価すべきと主張した。一方、原処分庁は、同族会社が評価通達189なお書により、株式保有特定会社と判定されることを前提に、本件株式については同通達189−3ただし書で株式保有特定会社について定める「S1+S2」方式により評価することが著しく不適当と認められる特別の事情があるとして、総則6項を適用し、純資産価額方式で評価すべきと主張。評価額は1株当たり3,443円としている(表1参照)。
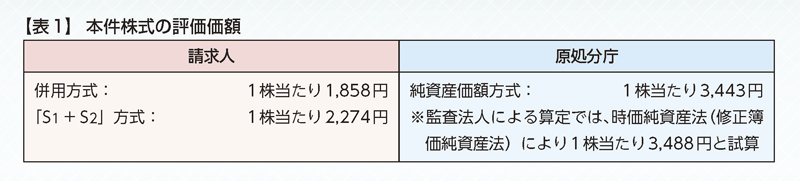
株式保有特定会社判定回避への対処を評価通達189なお書で規定
株式保有特定会社の株式の価額は、評価通達189−3において、納税義務者の選択により、純資産価額方式又は「S1+S2」方式のいずれかによって評価すべきものと定められている。
また、評価通達189なお書では、課税時期前において合理的理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、その変動が株式保有特定会社に該当する評価会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、その変動はなかったものとして当該判定を行うものと定めている。この取扱いが定められているのは、株式保有特定会社の株式に該当するか否かの判定が総資産価額に占める株式等の保有割合によって行われるため、例えば、課税時期直前に借入れを起こして総資産価額を膨らませるなどの操作により、評価通達189(2)に定める判定基準を回避することで株式保有特定会社の株式として評価されないこととなる結果、時価がゆがめられるようなケースにも対処する必要があることによるものとされている。
新株発行及び資産の運用に係る一連の行為は相続税の負担軽減が目的
まず、審判所は、同族会社の株式保有割合は相続直前に被相続人に対して行った新株発行前の時点で50%以上であり、株式保有特定会社に該当していたとした上で、評価通達189なお書に該当するかどうかについて検討を行っている。
審判所は、実際に行われた同族会社の資産構成の変動をみると、新株発行は同族会社の貸借対照表における資産の2倍を上回り、かつ、被相続人が預金として保有していた上場株式の売却代金相当額の大半を出資するというものであり、これにより同族会社が調達した資金を含めた資産の運用では、証券投資信託、外国債及び低解約特約付の逓増定期保険に充てられる一方で、評価通達189(2)に定める株式保有特定会社の判定の基となる株式等に該当する資産にはほとんど充てられず、それまで同族会社では行っていなかった配当も新株発行の直後に行っていることが認められるとした。これらの一連の行為は、金融機関との相談を受けて行われたことは明らかであり、請求人の主導の下、相続税の課税価格を圧縮し、相続税の負担を大きく軽減することを直接の主たる目的として行われたことは否定し難いものというべきであるとした。
株式保有特定会社に該当
審判所は、同族会社は評価通達189なお書に該当する事情があると判断し、株式保有特定会社に該当するか否かの判定では、新株発行及び資産の運用に係る一連の行為による資産構成の変動がなかったものとして判定することには合理性が認められると指摘。同族会社は、資産構成の変動がなかったものとして判定すると、株式保有特定会社に該当することになり、適用される評価通達に定める評価方法は、純資産価額方式と「S1+S2」方式との選択になるとした。
「S1+S2」方式の選択は租税負担の実質的な公平を著しく害する
請求人らは、「S1+S2」方式を選択して評価することについて著しく不適当と認められる特別の事情がないとして、総則6項を適用すべきでないと主張したが、審判所は、①同族会社が相続直前にした新株発行による被相続人からの資金の調達及びその資金を含む同族会社の資産の運用に係る一連の行為は、相続税の課税価格を圧縮して節税することを直接の主たる目的としてなされたものと認められる、②本件株式の価額を「S1+S2」方式により評価すると本件資金の額と大きくかい離することとなるが、新株発行から相続開始までの短期間に本件株式の客観的交換価値が下落した気配はなく、本件資金の客観的な交換価値が損なわれたことをうかがわせる事情もないことから、「S1+S2」方式による評価額が相続開始時の本件株式の客観的交換価値を適正に示しているとみるのは極めて困難である、③本件株式の価額を評価通達が定める純資産価額方式により評価すると、新株発行時の払込金額などと近似しているといった事情の下において、「S1+S2」方式の選択を許すことは、請求人らと同等の措置を採らなかった他の納税者との間で租税負担の実質的な公平を著しく害する結果になるとし、特別の事情があるとの判断を示し、請求人らの請求を棄却した。
評価額は2分の1を下回る価額ではないが
また、請求人らは、併用方式による評価額は、純資産価額方式による評価額と比較して2分の1を下回るほど低い価額になってはおらず、著しいかい離があるとはいえないから、特別の事情はないなどと主張したが、審判所は、純資産価額方式による株式の評価額は、併用方式による評価額、また、「S1+S2」方式による評価額との差額についても、2分の1に及ぶかい離はないが、その金額自体は請求人らと同等の措置を採らなかった他の納税者との関係において租税負担の実質的な公平を問題にすべき水準というべきであるとしている(表2参照)。
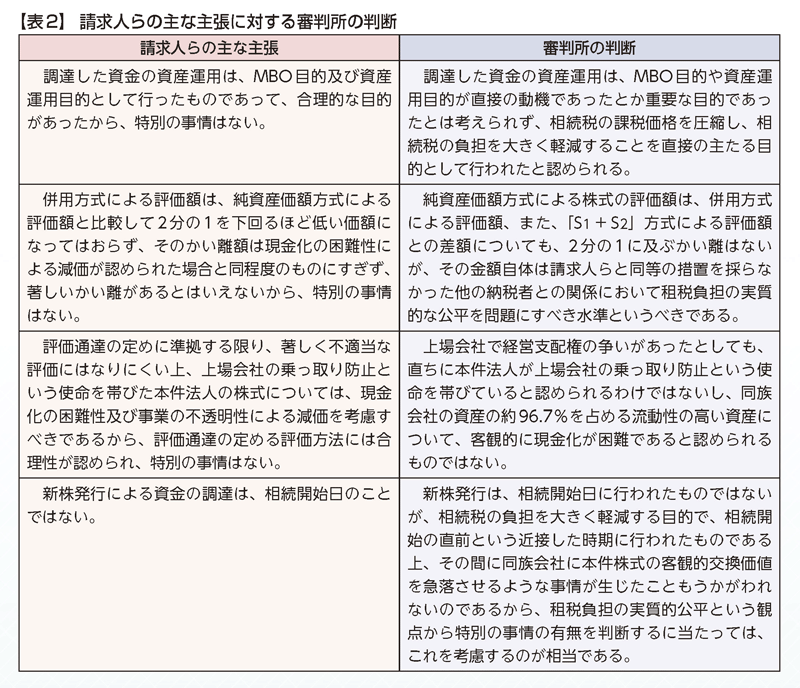
類似業種比準価額と鑑定評価のかい離は10倍
次に紹介する裁決事例は、請求人が相続により取得した取引相場のない株式を類似業種比準価額により評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が総則6項を適用し更正処分を行ったため、請求人が原処分の全部の取消しを求めたものである(仙裁(諸)令2第3号、仙裁(諸)令2第4号)。
請求人は、相続により取得した取引相場のない株式について、類似業種比準価額により1株当たりの価額を8,186円と評価したが、原処分庁は評価通達の定めにより評価することが著しく不適当であるとする特別の事情があると認められるとして、総則6項に基づき、民間の評価機関に株式の鑑定評価を依頼し、本件算定報告書における株式60,000株の鑑定評価をもとに1株当たりの価額を80,373円と評価(表3参照)。評価には約10倍ものかい離があった。
【表3】事案の経緯
| 本件の被相続人Aは生前、薬局の経営等を業とするB社の代表取締役を務めており、Aと医薬品卸売業を主な事業内容とするC社との間で、B社のC社に対する売却・資本提携等を前提とする協議を進め、平成26年5月29日基本合意書を締結。基本合意書では、Aは、AとA以外のB社の株主が保有するB社の全株式60,000株を取りまとめ又は買い集めた上でC社に譲渡すること、また、譲渡価格は63億408万円(1株あたり105,068円)とすることとされた。 しかし、Aは平成26年6月11日、基本合意に基づく譲渡に至る前に死亡。Aの死亡後にB社代表取締役になったAの妻Dは、C社との間で、B社株式の譲渡についての交渉を改めて開始。DはB社株式を取りまとめ、Dが保有するB社株式60,000株を、C社に対して63億408万円(1株あたり105,068円)で譲渡することになった。 請求人(相続人)らは、類似業種比準価額により1株当たりの価額を8,186円と評価し、相続税の申告をしたが、原処分庁は総則6項に基づき、民間の評価機関に株式の鑑定評価を依頼し、本件算定報告書における株式60,000株の鑑定評価をもとに1株当たりの価額を80,373円と評価した。 |
請求人は、相続により取得した取引相場のない株式について、評価通達に定める類似業種比準価額とすべきであり、原処分庁が、総則6項を適用した評価額による更正処分は、①評価方法に合理性がない、②相続開始前における株式譲渡の協議は株式の売買予約ではなく、のれん等の無形資産の価値が顕在化したことを示すものではない、③申告した評価額と当該協議の価格との間にかい離があることをもって特別の事情があるとはいえないから違法であるなどと主張した。
総則6項に基づく更正処分を予測できないとはいえず
審判所は、類似業種比準価額は総則6項を適用した評価額及び当該協議の価格と著しくかい離しており、相続開始時における相続した株式の客観的な交換価値を示しているものとみることはできないと指摘。そうすると、相続した株式については、評価通達の定める類似業種比準価額を形式的に全ての納税者に係るすべての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価すべき特別な事情があるとの判断を示した。その上で株式譲渡価額及び基本合意価格をもって、主観的事情を捨象した客観的な取引価格ということはできないのに対し、総則6項を適用した評価額はDCF法を採用し、適正に行われたものであり合理性があることから、相続税法22条に規定する時価であると認められるとし、総則6項の適用は適法であるとしている。
そのほか、請求人は、相続株式について、評価通達に基づき計算した額を超える価額による更正処分は予測できなかったから、国税通則法65条4項に規定する正当な理由があると主張したが、この点について審判所は、相続税の申告の時点において、総則6項の定めが存在しており、また、総則6項の趣旨は相続税法22条の「時価」の解釈として、評価通達に定める評価方法を画一的に適用することによって、適正な時価を求めることができない結果となるなど著しく公平を欠くような特別な事情があるときは、個々の財産の態様に応じた適正な評価方法によって「時価」を算定できるものとしたものと解されるとした。
その上で、審判所は、評価通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価すべき特別な事情があることからすれば、総則6項の定めに基づいて、相続株式通達評価額を超える価額による更正処分は予測できなかったとまではいえないとし、請求人の主張を斥けた。
なお、本件については、相続税回避行為がみられない中での非上場株式に対する総則6項の適用を不服として相続人(請求人)らがすでに訴訟に踏み切っている(本誌878号参照)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























