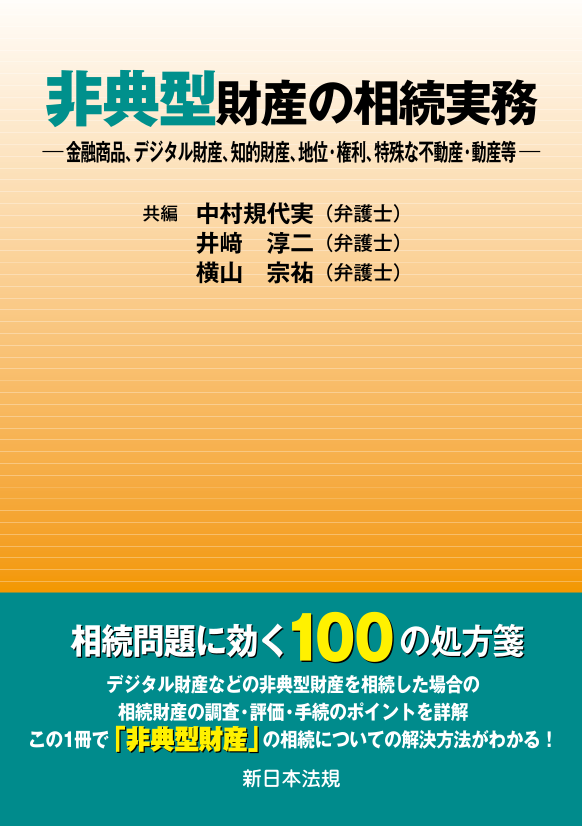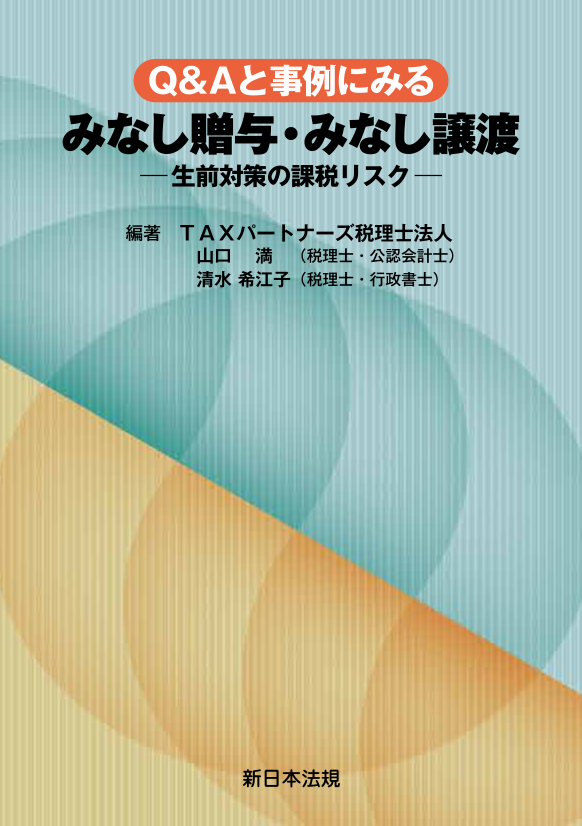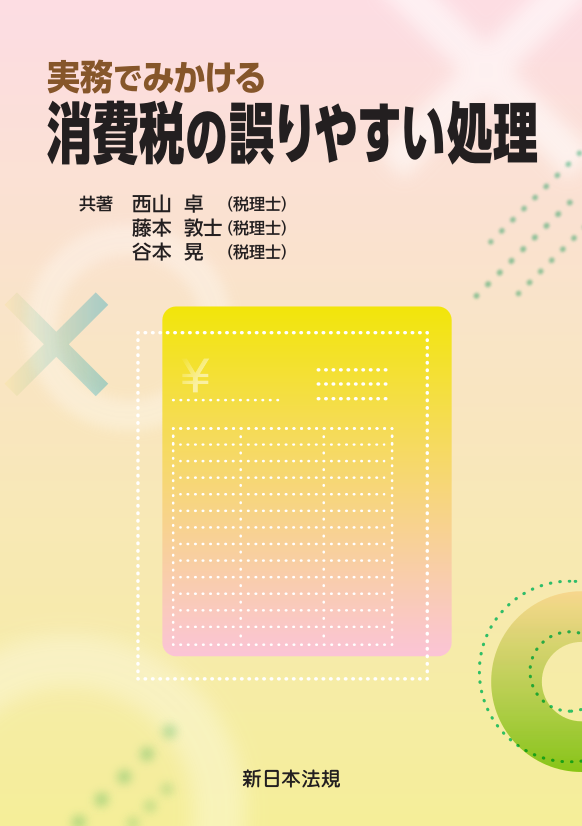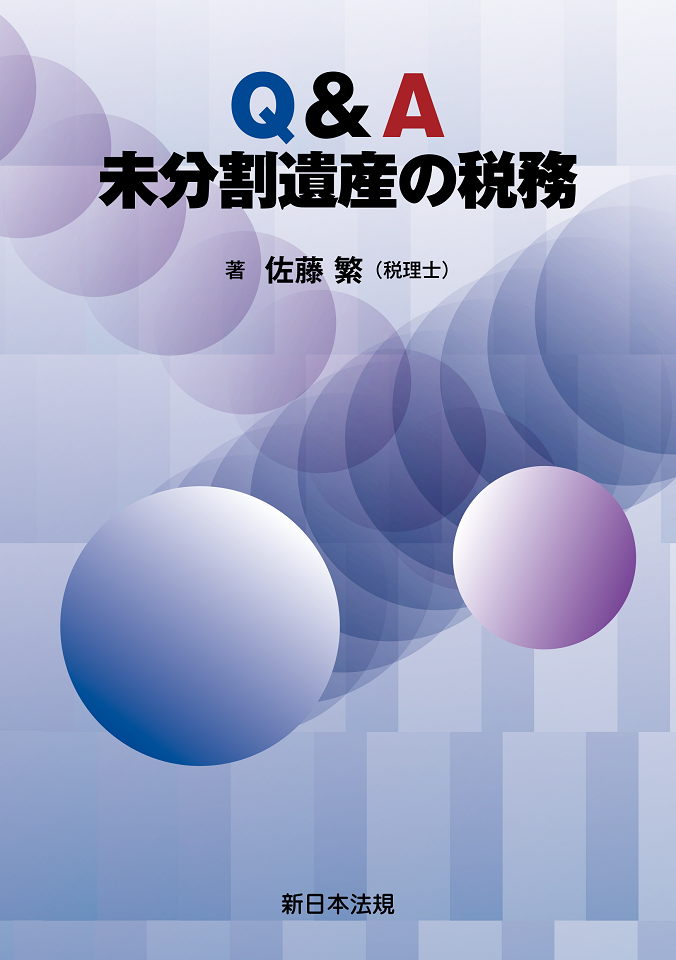税務ニュース2022年08月19日 公表サイトのみでの登録番号取得は不可(2022年8月22日号・№943) インボイス制度、登録番号記載書類等は仕入先から入手が必要
周知の通り、インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者から登録番号が記載された適格請求書の交付を受け、それを保存していなければ仕入税額控除が認められない(経過措置あり)。自社に関わる全仕入先が完全な適格請求書を発行してくれれば問題はないが、制度を不知の仕入先等への対応に手間と時間を要する事態も十分に想定される。記帳業務を多数手掛ける実務家からは、顧問先が仕入先から受ける請求書に登録番号の記載なく消費税が請求されている場合、法人であれば登録番号は必ず「T+法人番号(公開情報)」となるため、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で検索して適格請求書発行事業者かを判断してしまえば済むのではないかとの意見も聞かれる。また、国税庁ウェブサイトに掲載されているインボイス制度に関するQ&Aの問79では、家賃などの毎月請求書が発行されない費用は、契約書と通帳の“合わせ技”で適格請求書の要件を満たすことを認めているが、法人貸主について不足している情報が登録番号だけであれば、同公表サイトから直接情報を補完してしまえばよいではないかという意見もある。
そこで本誌は、仕入先法人の登録番号が手元資料で確認できない場合に、仕入先に確認依頼をせずに公表サイトで番号を直接確認することで、仕入税額控除に必要となる情報を補完することが可能か、課税当局に取材した。しかし、課税当局によると、公表サイトは登録番号を文字通り“確認”するために使用することは全く問題ないが、検索した番号をもって情報を補完したとするのは不可とのことだ。仕入先には適格請求書の交付義務が課されているため(消法57条の4①)、仕入先から登録番号が記載された適格請求書を入手すべきというのがその理由だ。複数の書類により適格請求書の記載事項を満たすことは可能ではあるが、仕入先との間で情報共有する何らかの書類等が必要ということになる。
実務家としては、制度導入に伴う手間を極力減らしたいところではあるが、後々のトラブルを回避するためには、顧問先と仕入先との間の“共有情報”となる形式で登録番号の取得を依頼するという対応が必要になろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.