解説記事2022年08月29日 SCOPE 非営利型一般財団法人には、利子配当等の源泉所得課税あり(2022年8月29日号・№944)
公益法人改革に伴う税制改正の内容争うも敗訴
非営利型一般財団法人には、利子配当等の源泉所得課税あり
非営利型の一般財団法人が、支払いを受けた利子及び配当等に係る源泉所得税を非課税とすべきとして争っていた事件で、東京高裁第7民事部(矢尾和子裁判長)は令和4年7月28日、一審に続き納税者敗訴の判決を下した。
公益法人制度改革に伴う税制改正前には、旧公益法人が支払を受ける利子及び配当等が非課税とされていたことから、納税者側は、非営利型の一般財団法人に非課税規定が適用されなくなった当該改正について、違憲、無効を主張していたが、東京高裁も一審同様に、「公益法人と非営利型法人との課税上の取扱いの区別を設けた立法目的に合理性が認められ、目的との関連で区別が著しく不合理であることが明らかということはできない」などとして、納税者の主張を斥けた。
公益法人と非営利型法人との取扱いの区別は、著しく不合理にあらず
公益法人制度改革では、登記のみで設立することができる一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団・財団法人」)が新たに設けられ、更にそのうち行政庁による公益性の認定を受けた法人として、公益社団法人及び公益財団法人(以下「公益法人」)が設けられた。
そして、同改革に伴う平成20年度税制改正により、公益法人については収益事業課税方式が適用される一方、公益法人を除く一般社団・財団法人については、原則普通法人として全所得に課税することとされた。ただし、非営利型法人(法人税法2条9号の2)については、「公益法人等」(同法2条6号)に含まれるものとされ、収益事業課税方式を適用することとされた。
一方、所得税については、旧公益法人が支払を受ける利子及び配当等については、所得税を課さないこととされていたが、改正により、公益法人については非課税とされた一方、公益法人を除く一般社団・財団法人については、非営利型法人も含めて、所得税が課税され、源泉徴収されることとされた。
本件は、非営利型法人に該当する一般財団法人である原告が、原告の収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等については非課税とされるべきであるなどとして、源泉徴収された所得税の還付を求めて争った事案である。
立法行為の違憲・無効主張するも認められず
一審の東京地裁は、法令の規定上、非営利型の一般財団法人である原告が支払を受ける本件預貯金利子等については、その支払の際所得税が源泉徴収されること、また、原告は公益法人等に該当するため収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課されず、本件預貯金利子等に係る所得税については二重課税の問題は生じないから、原告の法人税の額から当該所得税の額を控除することも、還付を求めることもできないとして、原処分は適法との判断を下した。
原告は一審で、①利子及び配当等につき所得税が課されない公共法人等に非営利型法人を含め、あるいは、②非営利型法人が支払を受ける利子及び配当等について源泉徴収された所得税の額を法人税の額から控除し、それでも控除しきれない部分については還付する内容の改正をすべきであったのに、これと異なる不適切な法改正を行った本件立法行為は違憲、無効であるなどとも主張した。
これに対し東京地裁は、最高裁昭和60年3月27日判決を引用し、「裁判所は、基本的には立法府の裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきであるから、その租税法の立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された課税要件等の定めが同目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができない」と判示。その上で、「公益法人については、それ以外の一般社団・財団法人に比して、その高い公益性の保持が制度的に担保されているといえることからすれば、公益法人と非営利型法人との間の課税上の取扱いの区別は、公益性の差異を踏まえ、公益目的事業の促進と、適正かつ公平な課税の実現との調整を図るという目的との関連で著しく不合理であることが明らかということはできない」として原告の主張を斥けていた。
優遇措置不適用は、納税者の選択の結果
これに対し控訴人は、控訴審で、①現在は、租税法の定立について、立法府の裁量的判断を尊重する基礎を欠いており、上記最高裁判決の判断基準を適用すべきではなく、②本件は、(a)課税される主体が公益法人か非営利型法人かといった社会的身分による取扱いの区別であり、(b)控訴人が自らの意思や努力によって認定を受けることが困難な公益認定法人性の有無という事由による区別であり、(中略)、取扱いの区別の合憲性を厳格に判断すべきであるなどと主張した。
しかし、東京高裁は、上記東京地裁判決と同様の判示をした上で、「公益法人と非営利型法人との課税上の取扱いの区別を設けた立法目的に合理性が認められ、目的との関連で区別が著しく不合理であることが明らかということはできない以上、控訴人が公益法人制度改革に伴う税制改正に伴って課税上の優遇措置を受けられなくなったのは、控訴人自身が公益法人ではなく一般財団法人への移行を選択した結果であって、控訴人が自らの意思や努力によって選択することのできない事由による区別とはいえない。」などとして、控訴人の主張を斥け、控訴を棄却した。
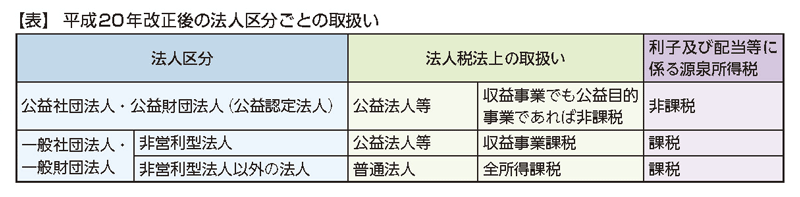
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























