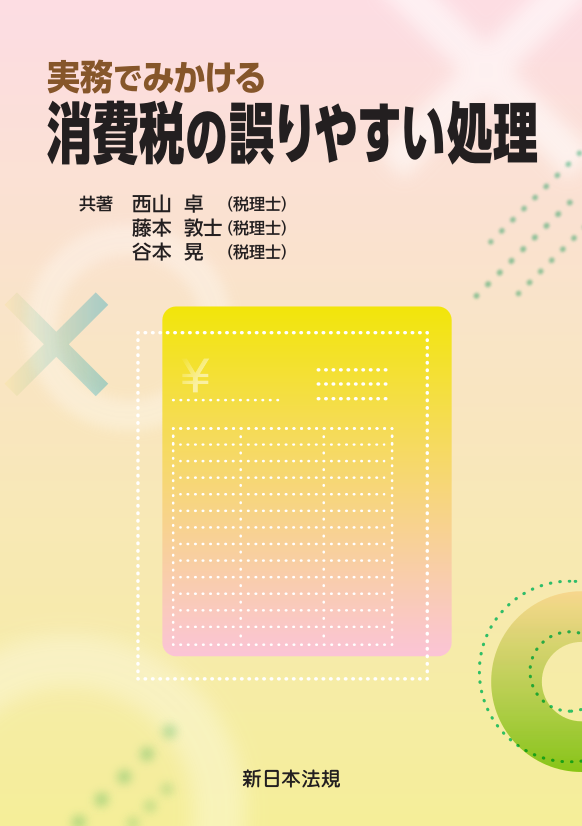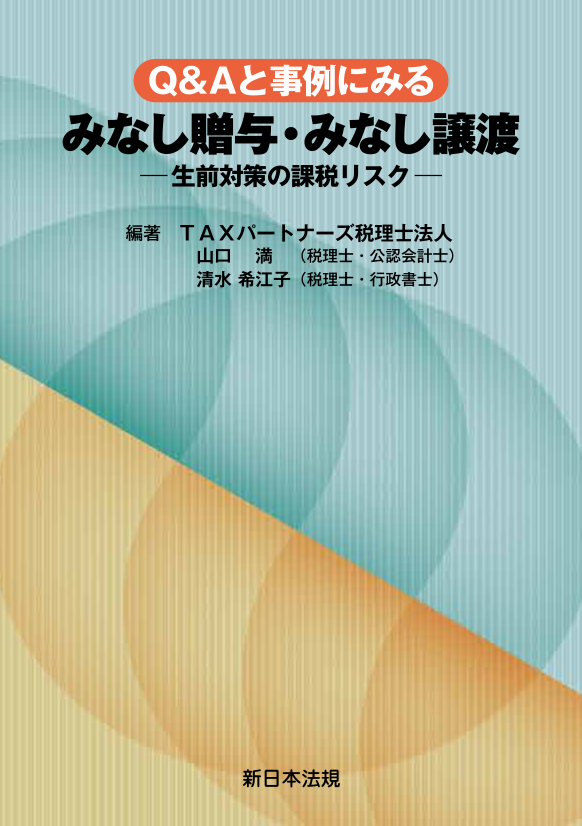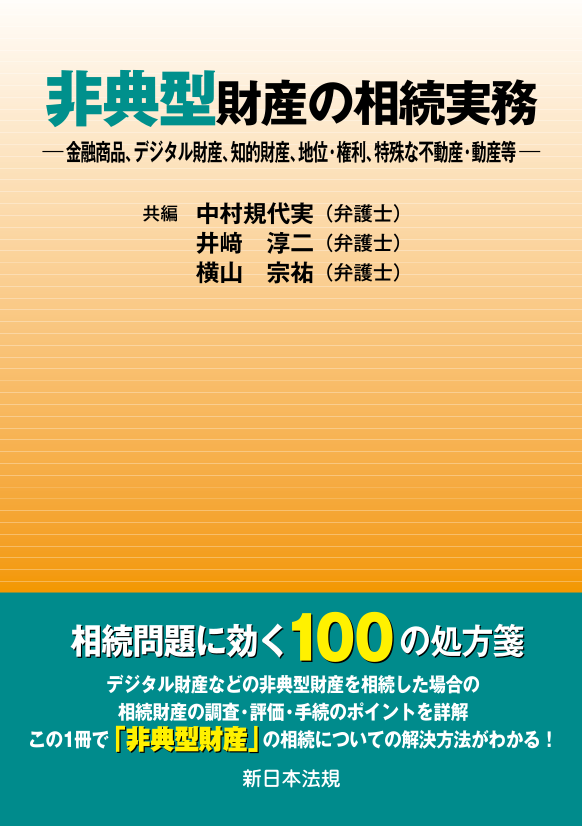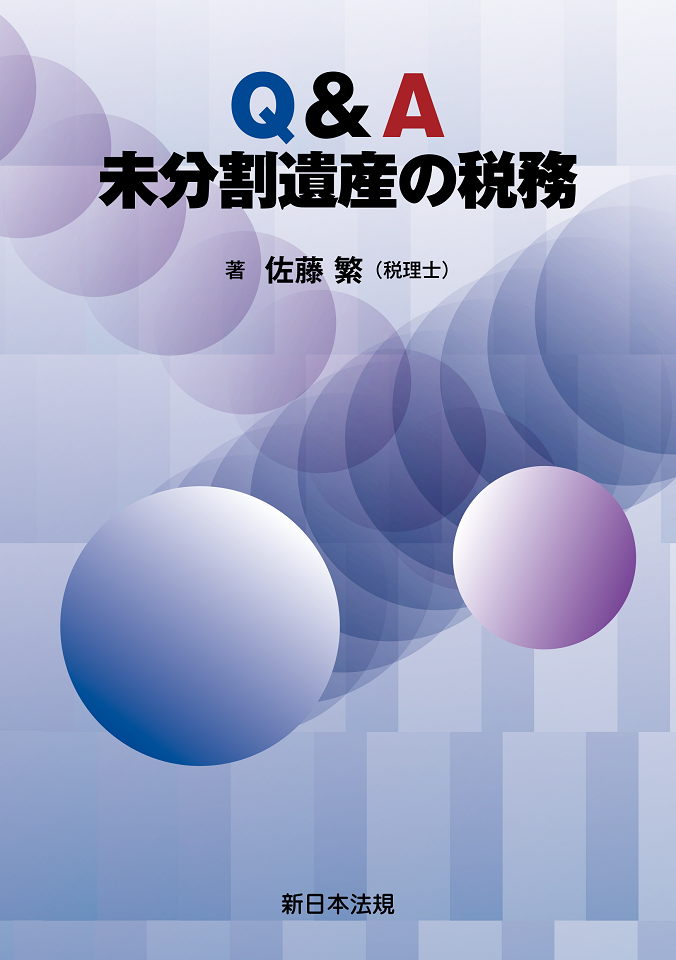解説記事2023年02月13日 ニュース特集 特集 デジタル課税を巡る議論の最新動向(2023年2月13日号・№966)
ニュース特集
セーフハーバー等、OECDが年末に文書公表、R5年改正法令等に反映へ
特集 デジタル課税を巡る議論の最新動向
令和5年度税制改正では、デジタル課税第2の柱(ミニマム課税)の法制化が決まったが(本誌961号4頁~参照)、税制改正の内容にダイレクトに影響を与えることになるのが、OECDが昨年12月末に公表したミニマム課税に関する「セーフハーバー(SH)及び罰則緩和」と題された文書だ。
OECDは、経過措置としてのCbCRを利用した「SH」を提示し、経過期間(2026年12月31日以前に開始する事業年度)におけるトップアップ税額が零とみなされる条件を明確にするとともに、ミニマム課税の複雑さを考慮し、「罰則緩和」として、導入から暫くの間は罰則や制裁を緩和する方針を打ち出している。SHの内容は令和5年度改正法令にそのまま盛り込まれ、罰則緩和については運用面での対応が図られる可能性がある。
また、令和5年度税制改正では、ミニマム課税の所得合算ルール(IIR)において、「国別実効税率」「トップアップ税額」等の記述を求める情報申告制度が導入されるが、トップアップ税額がなければ税務申告は不要となる一方、情報申告制度に基づく「特定多国籍企業グループ等報告事項等」は税務当局に提出しなければならないことも確認されている。
このほかOECDは、第1の柱について昨年12月から利益Bに関する市中協議を行っている。市中協議文書では、利益Bの対象を、有形財のバイセル取引に加え、販売代理店及びコミッショネアの取決めに係るグループ内取引としているが、日本企業の間では、両者があたかも同一のものとして取り扱われることには違和感があるとの声も聞かれる。利益Bに関する市中協議は今回が「最初で最後」と見られ、OECDは本年半ばまでの決着を目指すとしているだけに、利害関係者の意見がどの程度反映されることになるのか、注目される。
本特集では、デジタル課税の国内法制化に大きな影響を与えるOECDにおける議論の最新動向をレポートする。
令和5年度税制改正&第2の柱
セーフハーバー
大綱に所得合算ルールを掲載、OECDのモデル・ルールに沿った内容に
昨年12月末にOECDが公表したデジタル課税第2の柱(ミニマム課税)に関する3つの文書(「セーフハーバー(SH)及び罰則緩和」「情報申告」「税の安定性」)はいずれも重要な内容を含んでいるが、令和5年度税制改正との関係で注目されるのが「SH及び罰則緩和」だ。
令和5年度税制改正大綱では、末尾に【付記】として紙幅を割いて所得合算ルールの内容が書き込まれている。名称は「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)」とされ、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用する(2月3日に国会に提出された税制改正法案では、「(仮称)」は削除された)。その内容はOECDが公表済みのモデル・ルールの内容に沿ったものとなっており、日本が独自に足したり引いたりしている箇所は、少なくとも重大なものについてはないと解される。
企業にとって所得合算ルールの最大の問題は、法域別の租税負担割合(ETR)計算の複雑さだ。分母の所得、分子の税額ともに、会計数値をベースに特有の調整計算を行う必要がある。各国の経済界からは、例えばドイツ、フランス、米国等の高税率国については、どう考えてもETRが15%を割り込むことはないため、何らかの方法でETR計算を除外することが不可欠、との主張がなされていた。
経過措置としてのCbCRを利用したSHでトップアップ税額は零に
OECDから提示されたのは、経過措置としてのCbCRを利用したSHであり、①収入金額や税前利益額に着目したデミニマス基準、②簡易ETR計算、③実質ベースの所得控除による適用除外、の3つからなる。経過期間(原則として2026年12月31日以前に開始する事業年度)について、①~③のいずれかを満たす場合には、トップアップ税額は零とみなされる。
①は、ある法域における総収入金額が1,000万€未満かつ税前利益が100万€未満である場合をいう。収入・利益の意義について、所得合算ルールにおける特有の調整計算を行うことなく、適格CbCR(適格財務諸表に基づき作成されるCbCR)のデータが利用可能となる。
②は、ある法域における簡易ETRが、右記の通り、各年の区分に応じ、それぞれに掲げる率以上となる場合をいう。
・2023年及び2024年に開始する事業年度:15%
・2025年に開始する事業年度:16%
・2026年に開始する事業年度:17%
簡易ETRにおける分母の所得は、適格CbCRの当該法域の税前利益を使用し、分子の税額は適格財務諸表における税金費用(すなわち、「CbCRの発生税額」+繰延税金費用。ただし、所得合算ルールの対象税額とはならないもの及び不確実な税務ポジションは含まない)となる。特に分母の所得について所得合算ルールに特有の詳細な調整計算を行う必要がない点、実務的には歓迎されよう。簡易ETRの率が年々高くなるのは、後年度になれば納税者のシステム開発、グループ内の準備も進み、導入当初ほどの簡素化措置は不要になるとの発想によるものだが、当初は20%程度のバッファーレートとなる(=簡易ETR計算の結果、20%以上とならなければ、トップアップ税額は零とはならない)との観測もあったため、15~17%で決着したことは、企業側にとっては若干のサプライズであろう。
③は、所得合算ルールに基づき算出した実質ベースの所得控除額(有形資産や給与の一定割合)が適格CbCRにおける税前利益以上となる場合をいう。「以上となる」ということは、トップアップ課税の対象となる超過利益は発生していないということであるため、ETR計算はそもそも不要となる。これは、OECD事務局に対し欧米企業が強くプッシュした案とされる。実質ベースの所得控除額の算出自体が新しい概念であるため、真に「簡素」と言えるかどうかについては議論の余地があるところだが、オプションが多いに越したことはないと言えよう。
SH文書の内容は政省令に書き込まれる可能性大
以上を踏まえた上で税制改正大綱を確認すると、【付記】三2において「一定の国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準を措置するほか、所要の措置を講ずる。」との記載がある。
順序としては、与党税制改正大綱の決定後に、OECDからSHの文書が発出されたことになるが、税制当局は税制改正大綱の決定前にSH文書の公表を見込んでいたということだろう。
したがって、上記①~③については、令和5年度改正事項として、政省令にそのまま盛り込まれると考えるのが自然であり、今後、具体的な条文を確認する必要がある。ただし、OECDにおける議論の動向を踏まえ、用語の意義等について解釈の齟齬が生じないかも含め、一つ一つ確認しながら準備する都合上、年度末に政省令がフルセットで整備されず、一定期間、遅延する可能性も指摘されている。
罰則緩和
ミニマム課税の複雑化に配慮し、経過期間中は罰則や制裁を緩和
OECDは公表した文書「セーフハーバー(SH)及び罰則緩和」のうち後段の「罰則緩和(penalty relief)」とは、所得合算ルール(IIR)等のミニマム課税が非常に複雑な制度となっていることを考慮し、導入から暫くの間は、ルールに不慣れであると「合理的」に言える場合などには、罰則や制裁を緩和しようというもの。
所得合算ルール等のミニマム課税は、会計数値を出発点としながらも、実効税率の計算において、分母の所得及び分子の税額について特有の調整計算を行うほか、ジョイントベンチャーを有する場合、子会社に第3者が出資している場合等の特殊ルールがあるなど、非常に複雑な制度となっている。企業からは、導入から暫くの間は、悪意なく記入ミス、計算間違いなどをする可能性があることから、厳格に罰則や制裁を科すのではなく、一定の“お目こぼし”が必要ではないかとの指摘がある。
日本の3月決算法人は令和6年度~8年度に渡り罰則緩和のメリットを享受
これを受けて同文書では、経過期間における罰則緩和について定めている。
具体的には、「税務当局は、納税者がグローバル・ミニマム課税の正確な適用を確保するため“合理的な手法(reasonable measures)”をとったと見なす場合には、経過期間においては情報申告の提出に関連し、罰則や制裁は課さないこととすべきである」としている。
経過期間とは、2026年12月31日以前に開始し、かつ、2028年6月30日以前に終了する事業年度をいう。日本の所得合算ルール(IIR)が令和6年度(2024年4月1日)から開始することを踏まえれば、3月決算法人については、令和6年度(2024年度)、令和7年度(2025年度)、令和8年度(2026年度)の3事業年度に渡り、罰則緩和のメリットを受けることができると考えられる。
なお、OECDの文書には、(納付遅延に基づく)トップアップ税額の利子相当分については、救済の対象にならない旨の記載がある。
「ルールへの不慣れ」が原因でも罰則緩和、法令には記載せず運用で対応も
では、どのような時に“合理的な手法”をとったと言えるのだろうか。
文書では、具体的な定義は行わないとしつつ、ルールを理解し、また、ルールに準拠するための適切なシステムを誠意をもって構築したと説明できる場合には“合理的な手法”をとったと言えるとし、税務当局が事実及び状況に基づき判断するとした。例えば以下の場合が該当するとしている。
・ミニマム課税の計算過程について税務当局に完全に情報を開示する場合
・事実の間違いがその状況においては合理的である場合
・誤りの原因が施行当初期間におけるルールへの不慣れにあると合理的に言える場合(個別の算術的エラー、転換エラー)
・ルールの要求が不明確であり、多国籍企業の行動がそのルールの合理的な解釈に基づく場合
・多国籍企業の行動が、当年又は将来年におけるトップアップ租税債務の減少につながらない場合
一方、罰則緩和は、租税回避(avoidance)、詐欺(fraud)、濫用(abuse)には適用されない。
今後の注目ポイントは、これが令和5年度税制改正で導入された日本のIIRにおいてどのように反映されるかという点だ。大綱【付記】には、例えば以下の記述がある。
・(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)について)質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
・(情報申告制度について)特定多国籍企業グループ等報告事項等の不提供及び虚偽報告に対する罰則を設ける。
基本的には、あからさまに法令で「情状酌量を行う」「お目こぼしを行う」とは書きにくいことから、運用面で何らか対応することになると考えられる。企業、実務家としては、税制改正法案成立後、通達や当局解説等で、どのような説明がなされるのかを確認する必要があろう。
情報申告制度
情報申告書は税務申告の別表のようなものとの指摘も
このほか、令和5年度税制改正では、所得合算ルール(IIR)において、「国別実効税率」「トップアップ税額」等の記述を求める情報申告制度が導入されるが、この情報申告制度と税務申告との違いが分からないとの声が企業から挙がっている。
令和5年度税制改正大綱によると、デジタル課税第2の柱・所得合算ルール(IIR)における申告及び納付の部分は、「特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の申告及び納付は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月……以内に行うものとする」とされている。一方、情報申告制度の部分でも、「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他必要な事項等(特定多国籍企業グループ等報告事項等)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月……以内に……納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。」とされており、確かにこれらの記述からは税務申告と情報申告制度の違いは見えにくい。
情報申告制度では「国別実効税率」「国際最低課税額(すなわちトップアップ税額)」等を記述するとされ、税額の計算過程を詳述する書類に見える。実際、昨年末に公表された「GloBE情報申告」と題するOECDの市中協議文書には、日本の情報申告制度のひな型ともいうべきものが掲載されているが、そこでも、実効税率の分母・分子に係る各種の調整計算の過程、トップアップ税額の計算過程等に関する記載が「数値込み」で求められている。そうなると、情報申告書は税務申告の別表のようなものであり、「税務申告との差分がないのに、なぜ別の制度となっているのか」というのが企業側の指摘である。
トップアップ税額零なら申告不要、特定多国籍企業G等報告事項等は要提出
この点については、例えて言うならば、移転価格税制におけるローカル・ファイルと国別報告事項(CbCR)の関係のようなものであると理解するのが適当だろう。
国外関連取引に係る基本的な事項を記載したローカル・ファイルは、平成28年度税制改正を踏まえ、税務申告の期限までに準備することとされた(同時文書化)。税務当局の求めに応じ、提出する必要がある。ただし、ローカル・ファイルはあくまでも取引の「点」の情報であり、グループ全体のリスク・アセスメントという観点からは、「面」の情報であるCbCR(あるいはマスターファイル)が別途必要とされた。CbCRは同じく平成28年度税制改正で導入され、事業年度終了後12か月以内に提出することとされた。税務当局に提供されたCbCRは、租税条約により関係する国に連携される。
税務申告は、基本的にトップアップ税額及びそれに対応する法人税額の記載を求めるものである(点としての最終結果)。大綱によれば、トップアップ税額がなければ提出を要しない。他方、情報申告制度は、IIR等に係るグループの「全体情報」を求めるもの(面としての情報)である。本誌の取材によれば、トップアップ税額が生じない場合でも、情報申告制度に基づく「特定多国籍企業グループ等報告事項等」は税務当局に提出する必要がある。
令和5年度税制改正法案を確認すると、IIRは法人税法本則として位置づけられ、かつ、申告納付(新法法82の6)と情報申告制度(新法法150の3)は条項の記載位置からして全く別の制度として創設されることとなる。
情報申告書で他国に連携される情報を限定すべきとの意見も
また、上述のOECD市中協議では、情報申告制度の枠組み自体が協議の対象となっている。グループの構成事業体に関する各種情報は機密情報であり、条約方式により守秘義務は課されるものの、企業としては、むやみやたらと詳細な情報を子会社所在地国の当局と連携したいとは考えていない。
そもそも、情報申告書に個別の構成事業体の情報を1つ1つ書き込むことが現実的なのか、国別の情報で足りるのかという重大な懸念・指摘もある中で、企業からは、他国に連携される情報については、その他国に必要な範囲のみとすること、ミニマム課税以外の目的に使用しないこと、問い合わせ・税務調査も、現地子会社に対してバラバラと行うのではなく、親会社に一元化すべきなどの意見が出ている。
国会に提出された税法では、情報申告制度の詳細にまでは踏み込まない。OECDでの議論の結末が、そのまま政省令で規定される事項に反映されることになりそうだ。
第1の柱
利益B
利益Bの対象範囲を広げたい米国、日本企業からは利益Bに懐疑的な声も
令和5年度税制改正での国内法制化が決まった第2の柱に対し、「第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)」については、2023年前半の署名開放に向けて、引き続き制度の詳細について議論が継続しており、昨年12月から利益Bに関する市中協議が行われている。これに先立つ2021年10月の政治合意では「国内の基礎的なマーケティング及び販売活動に対する独立企業原則の適用について、低キャパシティ国のニーズに特に焦点を当てながら、簡素化・合理化する」とされており、今回の市中協議はこれを具体化するものである。
第1の柱については利益A(国家間の利益配分)の議論が先行していたが、税務行政において調査官の教育不足や比較対象取引(コンパラ)の不足など、キャパシティの低い国、特にアフリカ諸国から移転価格税制の簡素化への強い要望があり、ようやく議論が本格化してきた。
基礎的なマーケティング及び販売活動を行う販社を巡っては、その機能リスクを巡り国家間で見解の相違が起きやすく、納税者も税務紛争に巻き込まれることが多いとされる。こうした紛争の解決に投じるリソースをできるだけ減らしたいとの米国政府の思惑もある。米国企業も、利益Aで影響を被る以上、利益Bによって少しでも税の安定性を確保したいとの思いがある。これらのプレーヤーからすると、利益Bの対象範囲(スコープ)はできるだけ広い方が良いということになり、利益Aとパッケージで早期に妥結すべきという主張になる。
これに対し、日本企業の立場は微妙と言える。米国企業のように、利益Bの幅広い適用に期待を寄せる声がある一方、特に販社を巡る重大な税務紛争に直面していないとして、利益Bの有用性を疑問視する声もある。全体的な傾向として、日本企業は利益Bに対しやや懐疑的であると言える。
プライシングには、「共通の検索基準」に基づく簡易な解決策を提供
今回の市中協議文書では、まず、利益Bの対象について論じた上で、利益Bに該当する取引の場合には、OECDが今後準備する「共通の検索基準」に基づき、それらの取引に係るプライシングついて、簡易な解決策を提供する。
具体的には、(1)マトリックス方式と(2)メカニカル方式の可能性が提示されている。前者は、例えばX軸は資産集約度、Y軸は売上高営業費用比率といった指標を用い、XやYの数値のレンジに応じグラフ内に多数のマス目(マトリックス)を作り、利益B対象販社のX・Yの数値が特定のマス目に該当する場合、それに応じて予め定めた利益率等によりプライシングが定まるという方式である。(2)は、イメージとしては、回帰分析の結果を利用しつつ、利益B対象販社について特定指標Xの数値を代入すれば、機械的に利益率等Yが定まるというものである。
いずれも簡易な形でTNMM(取引単位営業利益法)を適用することが念頭に置かれており、市中協議文書では、「利益Bのスコープ内の多くのケースでは、売上高営業利益率が最適なネット利益指標であると考えられる」(パラ69)とされている。
バイセル取引、販売代理人・コミッショネア取決めに係るG内取引が対象
気になるのは利益Bの対象だ。市中協議文書では、パラ14において財(有形財を念頭)のバイセル取引に加え、販売代理人及びコミッショネアの取決めに係るグループ内取引が対象になるとし、それら活動に従事する検証対象企業を販社と呼んだ上で、具体的な要素を概略以下の通りパラ18で詳述している。【X%】とあるのは数字が未定であることを意味する。
a)取引に係る責任、権利義務、経済的に重要なリスクの引受け等に係る分担等を示した書面による契約を用意すること。
b)販社は主としてその居住地国で販売活動を行わなければならないこと(他法域顧客への売上が年間のネット売上高のX%を超えないこと)。
c)製造、研究開発、調達、ファイナンシング活動に従事しないこと。
d)販社が経済的に重要なリスクの引き受けに繋がるリスク支配機能を遂行しないこと。
e)それ自体が独立企業間価格で補償されるような市場での販売権の創出・獲得に関連する活動等を行わないこと。
f)販社がユニークで価値ある無形資産の創出に繋がるような戦略的な販売及びマーケティング活動を行わないこと。
g)販社の顧客のいずれもがネット売上高のX%を超えないこと。
h)補助的な活動は許容される(年間のネット売上高に占める小売売上高/販売及び広告費がX%を超えない等)。
i)販社の年間の営業費用が年間のネット売上高のX~X%の範囲にあること。
j)引き受けるリスクが限定的であること(例:限定的なマーケット/信用/在庫/製造責任/為替リスクしか負わないこと等)。
部分的にベリー比の採用を認めるべきかどうかも焦点に
その上で、市中協議文書では、利益Bの手法に頼らずとも他の最適手法が見つかる場合やローカル市場国にコンパラが見つかる場合には利益Bの対象外とするべきかどうか、あるいは、有形財だけではなくデジタル財を取り扱うべきか、ソフトウェアの取り扱いをどうするかについて、納税者の意見を募っている。
米国企業のように、利益Bの対象を広く考えたい勢力からすれば、パラ18で列挙された要件に対しては、利益Bの範囲を不当に狭める恐れがあるとして不満の声も出てこよう。
他方、日本の商社などは、販売代理人及びコミッショネア取決めに従事することが多く、そのプライシングにはTNMMではなくベリー比を使うことが多い。利益は売上ではなく、営業費用に対して感応度が高いためである。したがって、利益Bの対象に、バイセル取引と販売代理人・コミッショネア取決めがあたかも同一のものとして取り扱われることについては違和感があるとの声が聞かれる。
利益Bは強制適用ではなく、納税者の選択制としてはどうかとの議論もある。市中協議文書では、仮にこれらがすべて利益Bの対象となったとしても、部分的にベリー比の採用を認めるべきかどうかについての議論も行われている。
OECDは本年半ばまでの決着を目指すとしており、今回が「最初で最後」の市中協議になると見られるだけに、利害関係者の意見がどの程度反映されることになるのか、注目される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.