解説記事2020年01月20日 特別解説 のれんと無形資産の重要性①~主要な欧州企業ののれんやその他の無形資産の計上の状況~(2020年1月20日号・№819)
特別解説
のれんと無形資産の重要性①
~主要な欧州企業ののれんやその他の無形資産の計上の状況~
はじめに
20世紀は大手製造業による大量生産、大量消費の時代と言われる一方で、21世紀は知的財産をはじめとする無形資産の時代と言われて久しい。ある一定金額以上の有形固定資産がもれなく財務諸表に計上される一方で、無形資産は自己創設のれんの計上が禁止されるなど、財務諸表に計上されているものはほんの一部であり、無形資産の全貌やその価値を財務諸表上の会計情報から読み取ることは難しいとも言われている。それでは、世界各国の主要な企業において、どれほどの無形資産が計上されているのであろうか。本稿では、のれんやブランド、商標権等の耐用年数を確定できない無形資産(会計処理は、いずれも償却を行わず、減損テストのみ)を中心に調査分析を試みた。本稿では、欧州(欧州大陸及び英国)、米国及び我が国(IFRSを任意で適用して財務諸表を作成・公表する企業。以下、「IFRS任意適用日本企業」という。)の主要な企業を選び、2回に分けて、のれんを含む、無形資産の計上の状況の調査分析を行うこととしたい。
調査の対象とした企業
今回の調査対象とした企業は、欧州の企業については、ストックス(STOXX)欧州600指数(注)の構成銘柄に選ばれている銘柄の中から、主要な企業100社(主に欧州大陸の企業)を選定するとともに、ロンドン証券取引所に上場し、FTSE100の構成銘柄に選ばれている企業(主に英国の企業)のうち、特に多額ののれんやその他の無形資産を計上している企業25社を抽出して調査を行った。また、米国企業については、S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)株価指数銘柄に選定されている主要な米国企業100社を調査の対象とした。さらに、IFRS任意適用日本企業は、のれんやその他の無形資産の計上額が特に大きい一部の企業を選び、欧米の主要な企業と比較するために、数値や比率を掲載した。
なお、調査の対象とした決算期は2018年12月期が多いが、2019年3月期等の企業も一部含まれている。米ドル、ユーロや英ポンド、スイス・フランといった各国の通貨から円貨への換算は、各社の決算期末日現在の為替レート(T.T.M)で行っている。
(注)ストックス(STOXX)欧州600指数とは、STOXX社(スイス・チューリヒに本拠を置くインデックス・プロバイダー。ドイツ取引所のグループ企業)が算出する、ヨーロッパ17か国における欧州証券取引所上場の上位600銘柄により構成される株価指数。流動性の高い600銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型指数である。
主要な欧州企業ののれん計上の状況
ストックス(STOXX)欧州600指数の構成銘柄に選ばれている主要な欧州企業100社のうち、のれんを計上していなかったのはスウォッチ・グループ1社であり、のれん計上額が大きかった企業の上位10社は、表1のとおりであった。
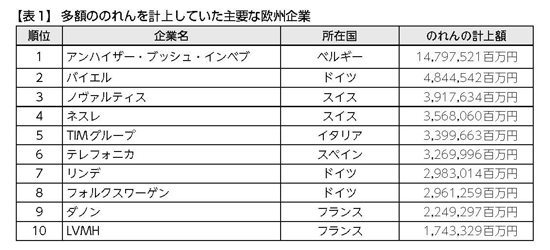
ビールの「バドワイザー」や「ミラー」ブランド等で知られるアンハイザー・ブッシュ・インベブ社が他社を大きく引き離しての1位であった。2位のバイエルは、モンサント社を合併したことにより、今期に大きくのれんの残高が増加している。なお、IFRS任意適用日本企業でいうと、第1位のソフトバンクののれん残高が、4,321,467百万円、第2位の武田薬品工業(アイルランドの同業シャイアー社を買収したことにより、のれんの残高が大幅に増加した)の残高が4,161,403百万円となっており(いずれも、2019年3月末日現在)、表1でいえば3位、4位に相当する。
次に、のれん計上額の連結純資産額に対する比率を見てみると、調査の対象とした100社のうちの12社が、100%を上回っていた(表2参照)。
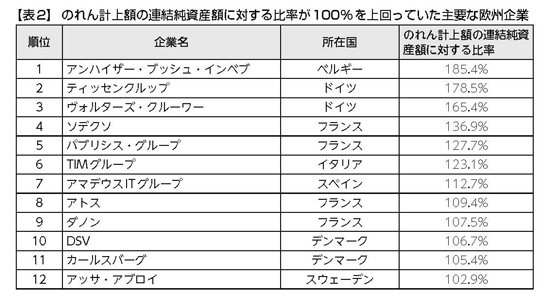
ちなみに、我が国のIFRS任意適用企業でのれんの計上額が連結純資産額を上回っていたのは調査対象とした194社のうち10社であり、それらのうちのほとんどが、すかいらーく等、IFRSを適用して新規に上場した企業であった(ちなみに、武田薬品は80.6%、ソフトバンクは48.0%であった)。
さらに、のれん計上額の連結総資産額に対する比率が40%を上回っていた主要な欧州企業を列挙すると、表3の12社であった。
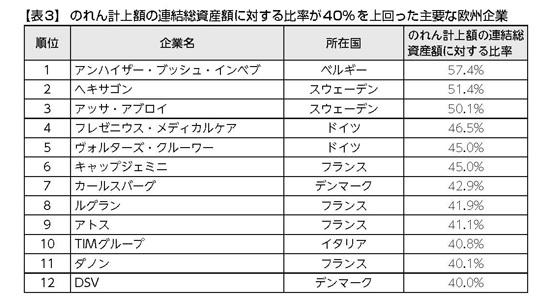
のれんの残高だけで連結総資産額の過半を上回った会社が3社、40%を上回った会社が12社も存在することには驚かされる。
多額ののれんを計上している企業は、企業結合や買収に積極的な企業がほとんどであり、その結果としてのれん以外の無形資産(企業結合を通じて取得した無形資産)も多額に計上していることが多い。
表1で列挙したのれんの計上額上位10社について、のれん以外の無形資産も含めた、無形資産計上額の合計と連結純資産額並びに連結総資産額に対する比率を示すと、表4のとおりであった。
あらゆるランキングで群を抜いて1位となっているアンハイザー・ブッシュ・インベブ社は、のれん以外の無形資産も5兆円弱計上しており、のれんと合計した無形資産全体での計上額の合計は実に20兆円に迫る。そして、無形資産の計上額は、連結総資産額の4分の3を上回っていた。
さらに、表4で列挙されている各社のほかに、無形資産計上額の連結純資産額、及び連結総資産額に対する比率が高かった会社(無形資産計上額の連結純資産額に対する比率が100%を上回り、かつ、連結総資産額に対する比率が50%を上回る会社)を列挙すると、表5のとおりであった。

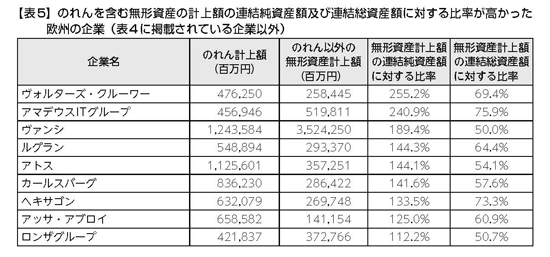
アンハイザー・ブッシュ・インベブ社ほどの規模はないものの、アマデウスITグループ、ヘキサゴン、及びヴォルターズ・クルーワーの3社は、無形資産計上額が連結総資産額の70%~75%前後となっている。
次に、表4、表5に掲載している19社のうち、のれん以外の無形資産の計上額が5,000億円を上回っていた12社について、その主な内容を示すと、表6のとおりであった。
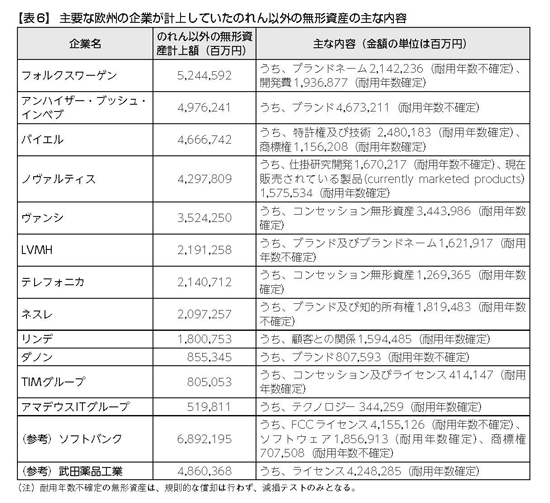
表6の各社が計上しているその他の無形資産の内訳をみると、ブランド、ライセンスや商標権等の耐用年数が確定できない無形資産(毎期の償却は行わず、減損テストのみ)が多額に計上されている例が目に付く。本稿の表にこれまで何度も登場しているアンハイザー・ブッシュ・インベブ社の場合、のれんとブランドで合計19兆5,000億円弱、連結総資産の4分の3超が非償却の無形資産で占められていることが分かる。インベブ社の連結純資産の額が8兆円弱であることを考えると、投資先の企業やブランドが大きく毀損して減損損失が発生した場合の影響の大きさは、想像するに余りある。
さらに、英国ロンドン証券取引所に上場しているFTSE100銘柄に選定されている主要な英国企業で、のれん、及びその他の無形資産の計上額の連結純資産額に対する比率が100%を上回っており、かつ連結総資産額に対する比率も50%を上回っていた企業は、以下の表7のとおりであった(グラクソ・スミスクライン社とユニリーバ社は、連結総資産額に対する比率は50%弱であるものの、連結純資産額に対する比率が極めて高いため、例外的に表7に含めている)。
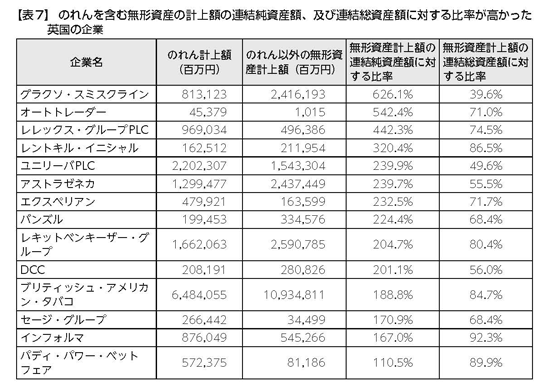
表6までで取り上げた欧州大陸の主要な企業に比べて、FTSE100構成銘柄の英国の企業はのれんを含む無形資産の計上額に対して純資産額が小さく、その結果として連結純資産額の3倍を上回る無形資産が計上されている企業が4社もあった。また、無形資産の計上額が連結総資産額に占める割合も、欧州大陸の企業に比べて全体的に高く、インフォルマ社とパディ・パワー・ベットフェア社は実に90%。レントキル・イニシャル社やブリティッシュ・アメリカン・タバコ社、レキットベンキーザー・グループといった、我が国でも知名度が高い大企業でも軒並み80%を上回っていた。これは驚くべき数字と言えるであろう。
なお、インフォルマ社及びブリティッシュ・アメリカン・タバコ社の連結貸借対照表を要約して示すと、次のとおりである。
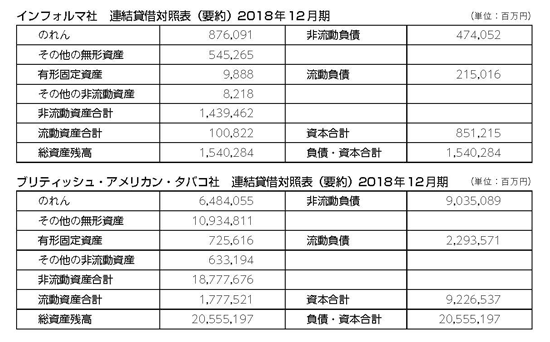
有形固定資産やその他の資産の計上額に比べて、のれんやその他の無形資産の計上額が突出して大きいことが分かる。
さらに、表7に掲載した各社のうち、5,000億円以上ののれん以外の無形資産を計上していた各社、及びレレックス・グループPLCについて、のれん以外の無形資産の主な内容を示すと、表8のとおりであった。
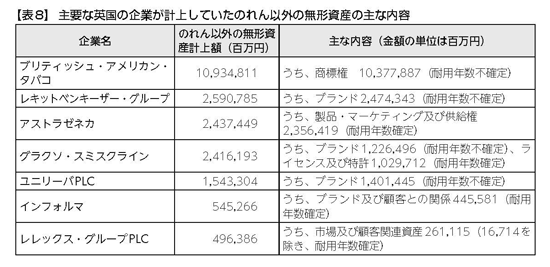
欧州大陸の主要な企業と同様に、ブランドや商標権等の耐用年数を確定できない無形資産(いずれも会計処理は非償却で減損テストのみ)が、計上額の多くを占めていることが分かる。
トーマスクック社とカリリオン社の状況
ここ数年で経営破綻し、欧州や英国の資本市場に大きな衝撃を与えたのが、カリリオン社とトーマスクック社である。
両社のホームページに掲載されている最後のアニュアルレポートから、のれんやその他の無形資産の計上額や、のれんを含む無形資産合計額の連結純資産額、及び連結総資産額に対する比率等を示すと、次のとおりであった。
なお、金額の単位は百万円である。
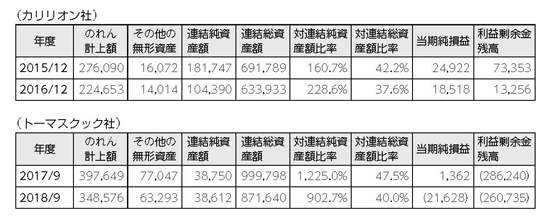
表1から表8までで取り上げてきた各社に比べると、カリリオン、トーマスクックの両社によるのれんやその他の無形資産の計上額の絶対額は、それほど突出して大きいとは言えない。しかしながら、見かけ上は黒字でも資金繰りがひっ迫して破綻したカリリオン社に対して、トーマスクック社の場合には、のれんを含む無形資産の計上額が連結純資産額の9倍から12倍に達しており、利益剰余金も多額のマイナスとなっていて、破綻のかなり前から危険水域にあったことが伺える。
終わりに
次回は、S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)株価指数銘柄に選定されている主要な米国企業100社を主な調査対象として、今回と同様の分析を行うこととしたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























