解説記事2023年06月26日 SCOPE 来年以降の住宅ローン減税、省エネ基準の証明書が必須(2023年6月26日号・№984)
証明書は住宅取得者自身が申請する場合も
来年以降の住宅ローン減税、省エネ基準の証明書が必須
令和4年度税制改正では、住宅ローン減税については省エネ性能に応じた借入限度額の上乗せ措置が導入された。省エネ基準に適合しない住宅に比べて省エネ性能が高い住宅の場合にはより高い控除額の適用を受けることができる。ただし、令和6年1月1日以降に建築確認を受けた新築住宅について住宅ローン減税の適用を受けるには、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要になる。令和5年中までの入居であれば、省エネ基準に適合しない住宅であっても借入限度額は3,000万円となっているが、令和6年以降は、原則として住宅ローン減税の適用を受けることはできない。証明書については、確定申告書に添付することになるが、注文住宅であれば、建築主が申請して取得することになるなど、これまでの制度とは異なっているので留意したい。
令和6年以降、省エネ基準に該当しない新築住宅は適用対象外
令和4年度税制改正により、住宅ローン減税については、適用期限が令和7年12月31日まで4年間延長されるとともに、会計検査院による平成30年度検査報告での指摘により控除率がこれまでの1%から0.7%に引き下げられている(本誌911号9頁参照)。
これに加え、令和7年4月から住宅や小規模建築物を含めたすべての建築物が省エネルギー基準の適合義務の対象になることを踏まえ、税制についても省エネ性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が導入された(図参照)。通常の省エネ基準に適合しない住宅であれば借入限度額は3,000万円だが、省エネ性能が高い住宅が高いほど借入限度額が多くなる仕組みとなっており、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であれば借入限度額は5,000万円となる(令和5年入居分まで)。
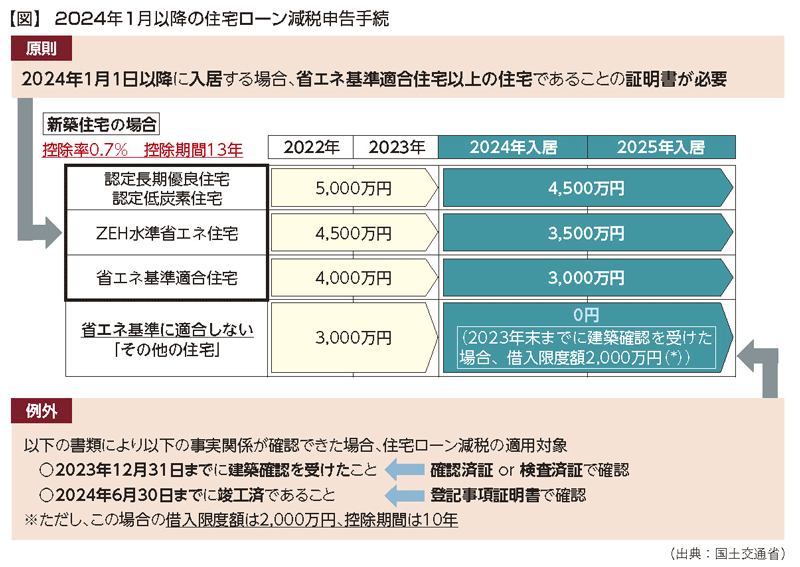
ここで気を付けなければならないのは、令和6年1月以降は、省エネ基準に適合しない新築住宅の場合、原則として住宅ローン減税を適用することができない点だ。対象となるのは「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」であり、いずれかに該当することを証明する書類が必要になる。
設計住宅性能評価書では申請できず
件数的に適用が多いと思われる「省エネ基準適合住宅」及び「ZEH水準省エネ住宅」については、①建設住宅性能評価書の写し、又は②住宅省エネルギー性能証明書のいずれかを確定申告の際に添付して提出する必要がある。建設住宅性能評価書とは、住宅性能表示制度上の証明書のこと。登録住宅性能評価機関が発行する。なお、住宅性能評価書には2種類あるが、「設計住宅性能評価書」では申請できないので要注意だ。
また、住宅省エネルギー性能証明書とは、住宅の省エネ性能に特化して証明する住宅ローン減税用の証明書のこと。令和4年度税制改正時に制度が導入された。登録住宅性能評価機関のほか、登録された建築士事務所に属する建築士などが発行することができる。
個人での証明書取得は困難
これらの証明書については、分譲住宅であれば家屋の引き渡し前に証明に必要な家屋の調査が完了している必要があるため、売主等が申請することになるが、注文住宅の場合は、建築主等が申請することになる。証明書は、一般の住宅取得者単独で取得することは困難であるため、国土交通省では、住宅販売会社、設計者、施工者等の協力が不可欠であると関連団体等に呼びかけている。
省エネ基準に該当しない新築住宅に一定の例外措置
原則として、令和6年1月以降に新築住宅に入居する場合には、省エネ基準適合住宅以上の住宅であることの証明書が必要だが、①令和5年(2023年)12月31日までに建築確認を受けたことを確認済証又は検査済証で確認、あるいは②令和6年(2024年)6月30日までに竣工済であることを登記事項証明書で確認できた場合には、令和6年又は令和7年の入居であっても住宅ローン減税を適用することができる。ただし、この場合の借入限度額は2,000万円、控除期間は10年に引き下げられることになる(控除率は0.7%)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























