解説記事2023年07月03日 ニュース特集 法人税法132条の2の適用で一連の組織再編成を否認(2023年7月3日号・№985)
ニュース特集
未処理欠損金額の付け替えと認定
法人税法132条の2の適用で一連の組織再編成を否認
新たに法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)が適用された事案が判明した。青果物等の売買等を行う株式会社である請求人が完全子会社と組織再編成上の「適格合併」として行った吸収合併に対して法人税法132条の2が適用され、被合併会社からの繰越欠損金の引継ぎが否認されたものだ。本件は審査請求が行われているが、国税不服審判所においても、一連の組織再編成は、未処理欠損金額を合併した旧子会社から請求人の会社に付け替えることを意図したものであり、通常は想定されない不自然な組織再編成というべきであるとして請求人の請求が棄却されている(大裁(法・諸)令4第5号)。その後、本事案は大阪地裁に提訴されており、決着は司法の手に委ねられている。
新設分割後に吸収合併し、約14億円の未処理欠損金額を引き継ぎ
本件は、請求人が行った法人税等の確定申告について、原処分庁が、損金の額に算入した適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額は当該合併が「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(法人税法132条の2)に該当するとして、更正処分等を行ったというものであり、これを不服とした請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。
請求人は、青果物等の売買等を行う株式会社であり、平成27年7月に実施した無償減資により中小法人となっている。請求人は完全子会社であるB社を吸収合併し、同社が有していた未処理欠損金額約14億円を引き継いだが、この吸収合併の前には、B社を分割法人、C社を分割承継法人とする新設分割が行われていた(図表1参照)。新設分割では、C社に青果物輸入事業に関わる資産・負債が承継されている。
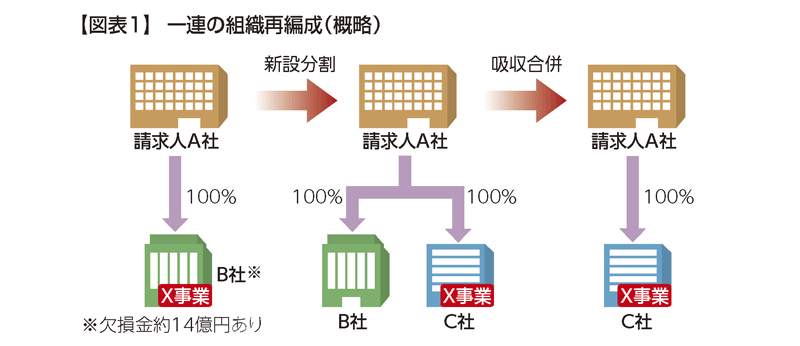
グループ内の適格合併を否認の対象とせず
請求人は、B社(旧子会社)が行った会社分割及び請求人とB社との合併は、グループ全体の一連の組織再編成の一環として行われたものであり、新旧子会社の事業の収益力向上という合理的な事業目的があるものであって、請求人の税負担の減少を意図したものではなく、また、法人税法132条の2は、法人税法57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)3項に規定する適格合併法人に係る被合併法人の有する未処理欠損金額の合併法人への引継ぎ制限を受けない場合には適用がないなどと主張した(図表2参照)。
【図表2】当事者の主な主張
| 原処分庁 | 請求人 |
| 〇未処理欠損金額は、法人税法57条3項に規定する適格合併に係る被合併法人の有する未処理欠損金額の合併法人への引継ぎの制限を受けないものであるが、法人税法132条の2は、次のとおり、引継ぎの制限を受けない場合にも適用がある。 ・法人税法132条の2は、組織再編成に係る租税回避を包括的に防止するために設けられた規定であると解され、その文言上も組織再編成に係る特定の行為又は計算を否認の対象から除外していない。 ・法人税法57条3項は、グループ外の法人が有する未処理欠損金額を利用した租税回避行為を防止するために設けられた規定であるにとどまり、適格合併に係る被合併法人の有する未処理欠損金額を利用したあらゆる租税回避行為を前提として網羅的に定めたものとはいえない。 |
〇法人税法132条の2は、次のとおり、法人税法57条3項に規定する適格合併法人に係る被合併法人の有する未処理欠損金額の合併法人への引継制限を受けない場合には適用がない。 ・法人税法57条3項は、グループ外の法人をグループ内に取り込んだ上で未処理欠損金額を利用する等の租税回避を防止する趣旨の規定であり、同項は、実態を伴ったグループ内の適格合併を否認の対象とはしていない。 ・適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額を利用する等の租税回避を防止することを目的とした個別的否認規定として法人税法57条3項が存在する以上、納税者としては、その適用がない場合には適格合併における合併法人への未処理欠損金額の引継ぎが否認されることはないと考えるのが自然である。 |
欠損金の付け替え目的での合併にまで引継ぎは認められず
本件の組織再編成については、法人税法57条2項の規定に基づく未処理欠損金額の引継ぎにより、法人税法132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するか否かが争点となっている。
本誌が入手した裁決事例によると、審判所は、ヤフー事件の最高裁判決(平成28年2月29日第一小法廷判決・民集70巻2号242頁)を踏まえ、「法人税法57条2項は、適格合併であることを要件として被合併法人の有する未処理欠損金額の引継ぎを認めた規定であるところ、適格合併には、大別して、企業グループ内の適格合併と共同事業を営むための適格合併がある。そして、企業グループ内の適格合併については、共同事業を営むための適格合併よりも適格合併と認められるための要件が緩和されているため、その未処理欠損金額の引継ぎを無制限に認めると、例えば、大規模な法人が未処理欠損金額を有するグループ外の小規模な法人を買収し完全子会社として取り込んだ上で、当該法人との適格合併を行うことにより、当該法人の未処理欠損金額が不当に利用されるおそれなどがある。そこで、そのような租税回避行為を防止するため、法人税法57条3項において、適格合併が共同事業を行うための合併として法人税法施行令112条3項で定めるものに該当する場合又は企業グループ内の適格合併が行われた事業年度開始の日の5年前の日など同法57条3項柱書に規定する日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として同令112条4項で定める場合のいずれにも該当しない場合には、同法57条3項各号に掲げる未処理欠損金額の引継ぎを制限している」との見解を示した。
その上で、審判所は、完全支配関係にある法人間で行われる合併の場合、適格合併の要件として従業者従事要件及び事業継続要件は要求されていないものの、法人税法57条3項と同様、企業グループ内の法人の有する未処理欠損金額の無制限の利用を許容する趣旨とは解されないとした。加えて、未処理欠損金額の引継ぎの趣旨が、適格合併の場合には、移転資産等に対する支配が継続されていることから、基本的に欠損金額の繰越控除が前提とする各事業年度の間に経理方法に一貫した同一性が継続維持されているとして、合併の前後を通じた事業年度間の所得の金額と欠損金額を平準化することを認めて、従前の課税関係を継続させることにあると解されることからすれば、法人税法57条2項は、例えば、適格合併が企業グループ内の法人の有する未処理欠損金額の企業グループ内の他の法人への付替えと同視できるものである適格合併の場合にまで、未処理欠損金額の引継ぎを認めることを想定した規定ではないと解するのが相当であるとした。
繰越欠損金の分離は財務状況の改善とならず
本件については、請求人は組織再編成について、事業の収益力向上等が目的であり、金融機関や業界からの悪い評価につながっていた未処理欠損金額を事業から分離する必要があったとするが、繰越欠損金は企業会計上表示される観念的な数額にすぎず、これを有する法人と分離したとしても、債務とは異なり法人の財務状況の改善を伴うものではなく、繰越欠損金を事業から分離することが事業の収益力を向上させるために必要なものであったとは認められないとした。
また、B社(旧子会社)が保有していたほぼすべての資産、負債、雇用契約その他の権利義務関係が、未処理欠損金額を除き、C社(新子会社)に引き継がれていることからすると、組織再編成は、未処理欠損金額を旧子会社から請求人に付け替えることを意図したものであり、この意図に基づくものでなければ、これを行う必要のないものであって、通常は想定されない不自然な組織再編成というべきであると指摘。本件組織再編成は、法人税法第57条2項の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものであって、同規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものであるから、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するとの判断を示し、請求人の請求を斥けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























