解説記事2023年09月11日 ニュース特集 第1の柱、利益Bに関する公開討議草案・第2弾のポイント(2023年9月11日号・№994)
ニュース特集
価格操作や軽課税国への利益移転を警戒し、利益率は狭いレンジに
第1の柱、利益Bに関する公開討議草案・第2弾のポイント
OECDは7月、経済の電子化に伴う課税上の課題、第1の柱の「利益B」に関する公開討議草案(第2弾)を公表した。昨年12月の公開討議草案(第1弾)の際には最初で最後のコンサルテーションとも言われたが、関係者からの意見が多数あり、その後、政府間でも議論が白熱したため、再度市中の意見を聞くこととしたもの。本特集では、利益Bに関する公開討議草案(第2弾)のポイントを解説する。
簡素化の観点から、定量基準に依拠した代替案Aを推す声が多数派
利益Bは、利益Aと異なり、多国籍企業グループの売上高や利益率に基づく閾値は設けない。したがって、サービスや(鉱物等の)コモディティを除く、財の販売及びマーケティングを行う取引が対象となり得る。具体的には、①販社が一以上の関連者から財を購入し、非関連者に卸売を行うというバイセルのマーケティング及び販売取引、②販売代理人やコミッショネアが一以上の関連者による非関連者への財の卸売に貢献するという販売代理人及びコミッショネア取引が、適格取引として利益Bの対象候補となる。日本企業からは、通常のバイセルの販社に比べ機能リスクが低い販売代理人やコミッショネアについては、利益Bの対象に含める必要がないのではないかとの指摘があったが、利益Bの対象を幅広く定義したい途上国等の意見も踏まえ、対象にされたままとなっている。
その上で、適格取引が真に利益Bの対象となるためには、a)当該適格取引が経済的に関連する性格を示さなければならない。すなわち、販社、販売代理人又はコミッショネアを検証対象企業とする場合、片側の移転価格手法によって信頼できる形での価格付けを可能とする必要がある。また、b)当該適格取引における検証対象企業にあっては、年間のネット売上高に対する年間の営業費用の割合が3%を下回ってはならず、また、【X】%を超えてはならない」とされている。
a)の趣旨は、利益分割法に代表されるより複雑な取引の両側検証とは異なり、TNMM(取引単位営業利益法)に代表される片側検証の対象となるような取引が利益Bの対象に相応しいということにある。また、b)は、売上に対する営業費用が異常に低い又は高いケースを除くことで、真に「基礎的な」販売及びマーケティング活動を行う販社を抽出しようというものである。
公開市中協議では、この部分について政府間で意見の相違があるとし、関係者の意見を募っている。代替案Aは、定量基準に依拠することで利益Bの趣旨である移転価格税制の簡素化を目指すもの。これによれば【X】%は30%となり、追加の要件は課さない。これに対し代替案Bは、定量基準だけでは独立企業原則に整合しない結果となる恐れがあるとして、さらに定性基準を組み合わせるべきとするもの。これによれば、【X】%は50%となり、さらに、a)b)を満たす場合であっても、検証対象企業が取引において「基礎的ではない」貢献をしている場合には、利益Bの対象外とする、ということになる。
企業側には、代替案Aは機械的に過ぎる、「基礎的」な機能すら満たしていない現地子会社を除外するために必要として代替案B又はそれに類する措置を推す声も一部あるが、代替案Bでは「基礎的でない」の解釈を巡って税務当局と紛争のリスクが残る可能性があり、移転価格税制の簡素化に繋がらないとして、代替案Aを推す声の方が多数派となっている。海外の企業も同様の傾向となっている。
「マトリックス方式」における利益率のレンジは「±0.5%内」に
ひとたび適格取引が利益Bの対象となった場合には、プライシングの議論に移る。
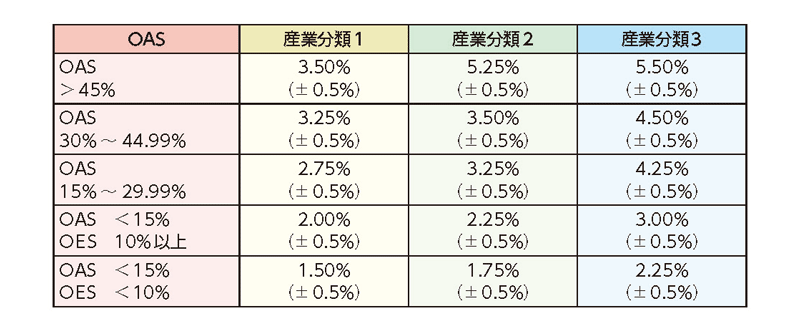
公開討議草案第1案の段階では、マトリックス方式とメカニカル方式(特定指標Xの数値を代入すれば、機械的に利益率等Yが定まるというもの)が提案されていたが、今回の第2弾ではマトリックス方式が採用されている。具体的には、上掲の表の通り、縦軸を要素集約度、横軸を産業分類とし、当てはまるエリアにおいて、予め定められた利益率を当てはめる(いずれも±0.5%内に収まっていれば足りるとのレンジの概念が採用されている)。
OAS(Net Operating Asset Intensity)とは純収入に対する純営業資産(固定営業資産+運転資本)の比率をいい、OES(Net Operating Expense Intensity)とは純収入に対する販管費の比率をいう。市中協議文書では、この数字に至った経緯についての説明が少ないため、にわかには評価しがたい部分があるが、企業の間では、「第1感としては、利益率はだいぶ高いのではないか。基礎的な販社にこれだけの利益率が必要だとすると、より機能リスクの高い子会社にはさらに利益をつける必要があり、グループ全体の利益配分が崩壊するのではないか」「利益率のレンジが狭いのではないか。実際の取引価格がこのレンジに収まっていなければ、期中・期末の価格調整又は申告調整により対応が余儀なくされるが、煩雑ではないか」「申告調整や職権更正等の場合、相手国側で対応的調整は適切に行われるのか」といった懸念が生じている。
本誌取材によれば、レンジが狭くなっているのは、レンジの中で価格操作を行い、タックスプランニングを行う(軽課税の国に利益をつける)企業への対応とのこと。途上国を中心に、さらに高い利益率、さらに狭いレンジを目指す動きもあり、要注意だ。
検証対象企業の機能リスクが低い場合には相応しい低い利益率に補正
また、重要なポイントとして、このマトリックスにはガードレイルが提案されている。すなわち、利益率の機械的な当てはめによって過大又は過少な利益率が適用されることを防ぐため、この利益率を適用した結果、ベリー比(売上総利益/販管費)が1.05倍〜1.5倍の範囲を超える場合には、1.05倍の水準まで引き上げ、又は1.5倍の水準まで引き下げる措置も講じられる。これは「裏付けメカニズム」と呼ばれる。例えば「産業分類2」かつ「OAS<15% & OES<10%」の検証対象企業については、利益率は1.75%(±0.5%)であることが求められる。仮に当該企業の取引における利益率が2%であればレンジ内に収まっているので、これでプライシングは終わりかというと、そうではないということだ。例えば当該取引に係るベリー比が1.8倍だとすると、1.5倍を超えているため、1.5倍となるように利益を調整する必要がある。結果として、当該企業の利益率は2%ではなく、1%代前半になるということもあり得る。これは、販売代理人やコミッショネアといった機能リスクの低い検証対象企業について、それに相応しい低い利益率に補正するための仕組みともいえる。スコープで販売代理人やコミッショネアを除外できない以上、プライシングで手当てするという発想である。途上国等からは、このような複雑な仕組みは不要との声も上がっているが、日本政府・企業としてはディフェンスが必要になるとみられる。
政府内では、利益B強制適用論が優勢
この他、公開市中協議では、「執行に係る考慮」の部分が完全な空欄となっている。その脚注を見ると、利益Bをセーフハーバーとするのか、強制適用とするのか検討が行われるようだ。企業側には、企業の選択制という意味でのセーフハーバーであるべきとの声もあるが、政府内では強制論が優勢な模様。
施行時期は定かではないが、別途公表されている包摂的枠組の7月のOutcome Statementでは、利益Bの最終報告書の内容を2024年1月にOECD移転価格ガイドラインに組み込むとしている。ガイドラインがそのまま法源となる法域もある一方、日本では通常、新たな移転価格算定方法の導入については、租税特別措置法の改正によって対応しているため、2024年1月施行というのは無理筋な話と言える。企業からは、子会社との取引の価格付けにダイレクトに関わってくるため、ガイドライン公表から数年間の準備期間は必要との声が上がっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















