解説記事2023年11月20日 ニュース特集 東京局管内でも法人税法132条の2を適用した組織再編成否認事案(2023年11月20日号・№1004)
ニュース特集
適格合併で想定されない組織再編成の手順に基づく不自然なもの
東京局管内でも法人税法132条の2を適用した組織再編成否認事案
大阪国税局管内の事案(本誌985号4頁参照)に引き続き、新たに東京国税局管内で法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)が適用され否認された組織再編成の事案が判明した。本件は、会社分割により事業や従業員を切放した後の分割法人を吸収合併した一連の組織再編成について、「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるとして、未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなさないとする法人税等の更正処分が行われたもの。本件は審査請求が行われているが、国税不服審判所においても、本件合併は、分割により子会社が行っていた事業を、請求人以外の法人に移転させ、あえて子会社について欠損金額のみを有する法人という形式を作出した上で、未処理欠損金額のみを請求人に引き継ぐものであるとして、法人税法132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するとの判断を示し、請求人の請求を棄却している(東裁(法)令4第101号)。本件は、現在、東京地裁に提訴されており、決着は司法の手に委ねられることになった。
会社分割後に吸収合併し、未処理欠損金額を引き継ぎ
本件は、請求人が適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が合併に係る未処理欠損金額を損金の額に算入することは、組織再編成に係る行為又は計算の否認規定における「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められるとして、未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなさないとする法人税等の更正処分を行ったものであり、これを不服とした請求人が原処分の取消しを求めた事案である。
請求人は、酒類、加工食品、農水産食品、冷蔵・冷凍食品、飲料等の製造、販売及び輸出入を業とする法人で、請求人の子会社を統括しており、完全子会社の事業を別の完全子会社に会社分割した上で事業を承継するとともに、その後、分割会社を吸収合併し事業の集約を図っていた(図表1参照)。
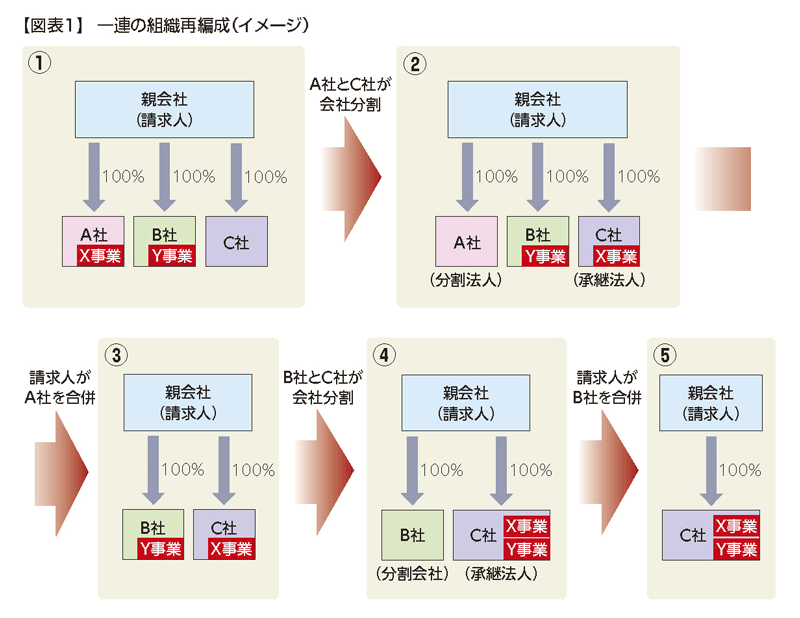
グループの事業集約という一連の組織再編成
請求人は、請求人と完全子会社との適格合併は、グループの事業集約という一連の組織再編成の過程で存続させる必要のなくなった子会社を消滅させるための合理的な事業目的によるものであるから、子会社が有していた未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして各事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たらないなどと主張。一方、原処分庁は、通常想定されない組織再編成の手順や方法に基づくもので、かつ、実態とは乖離した形式を作出するものであり、不自然なものであると認められるなどと主張した(図表2参照)。
【図表2】当事者の主な主張
| 原処分庁 | 請求人 |
| 請求人は、以下のとおり、各合併を行うことにより法人税法57条2項の規定を租税回避の手段として濫用し、法人税の負担を不当に減少したと認められることから、各未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして各事業年度の損金の額に算入したことは、同法132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。 (1)各合併は、次のことから、通常想定されない組織再編成の手順や方法に基づくもので、かつ、実態とは乖離した形式を作出するものであり、不自然なものであると認められる。 イ 請求人が、事業及び従業員が存在しない各社との間で各合併を行い、各未処理欠損金額を引き継ぐことは、事業の移転・継続という適格合併の実態を備えずに適格合併の形式のみを充足するものであり、また、事業実態を有しない法人との合併であるという点において通常想定されていない手順や方法に基づくものであり、不自然なものであること。 ロ 各社が各分割前に行っていた各事業自体は承継会社において継続しているにもかかわらず、各未処理欠損金額のみを各事業と分離し、各合併により請求人が引き継いでいる点につき、事業と未処理欠損金額が分離され、事業に係る未処理欠損金額のみが事業の移転先と異なる法人に帰属するなど、法の想定の範囲外であること。 (2)各合併は、請求人は、未処理欠損金額を引き継いで損金の額に算入することを目的として組織再編成の手順や方法を変更し、欠損金の使用期限が到来する前に吸収合併を行って、税負担を軽減しようとしていたと認められることなどから、税負担の減少以外に各合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由は存在しないと認められる。 |
各合併は、以下のとおり、法人税法132条の2に係る不当性要件を充足していないことから、各未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして各事業年度の損金の額に算入したことは、同条に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たらない。
(2)各合併は、請求人のグループの事業の集約という一連の組織再編成に係る行為であり、一連の組織再編成の過程で存続させる必要のなくなった子会社を消滅させる目的で行われたものであって、正に合理的な事業目的によるものである。 |
組織再編成を利用して税負担を減少させることが目的
審判所は、完全支配関係にある法人間の適格合併について、法人税法132条の2の適用の有無に関し、その「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」との要件に係る租税回避の意図があるか否か、同法57条2項の趣旨及び目的から逸脱しているか否かについては、組織再編税制の基本的な考え方(図表3参照)に基づき、事業の移転及び継続を含めて検討することが相当であるとした。
【図表3】審判所が示した「組織再編税制の基本的な考え方」
組織再編税制の基本的な考え方は、実態に合った課税を行うという観点から、組織再編成により移転する資産等の譲渡損益について、原則として、その計上を求めつつ、移転資産等に対する支配が継続している場合には、その計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものである。 |
分割会社は事業実態なし
その上で本件については、会社分割により事業実施に必要な資産・負債及び従業員のすべてが承継会社に承継・移転され、その一方で分割会社は有する資産・負債は税金関係のみで事業実態はなく、未処理欠損金額のみを有する法人となったと認められると指摘。組織再編税制における欠損金額の引継ぎは、被合併法人において移転資産等を用いて営んでいた事業が合併法人に移転し、その事業が合併後に合併法人において引き続き営まれることが想定されているものといえるところ、本件各合併の直前に各分割が行われて、各社が営んでいた各事業は承継会社に引き継がれ、各社は各未処理欠損金額のみを有する法人という形式が作出されており、その後、請求人は、各合併により各社が有していた各未処理欠損金額のみを各社から引き継いでおり、組織再編税制における欠損金額の引継ぎにおいて想定されている状況とは異なるものといえるとした。
したがって、審判所は、各合併は事業の移転先と欠損金の引継先が異なるという適格合併において通常想定されていない組織再編成の手順等に基づく不自然なものであり、本件未処理欠損金額を引き継ぐことによって請求人の法人税の負担を減少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由があったとは認められないとした。
加えて、各合併は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、法人税法57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)2項の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものというべきであり、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものと認められるから、本件未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして、当該欠損金額に相当する金額を各事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するとの判断を示し、請求人の主張を斥けた。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























