解説記事2023年12月04日 第2特集 消費税還付審査の集約etc. 当局の審理体制の変更点(2023年12月4日号・№1005)
第2特集
「審理担当者」を廃止した局も
消費税還付審査の集約etc. 当局の審理体制の変更点
令和5事務年度は国税当局の審査・審理体制の変更が目立つ。例えば、東京局は、センター対象署の調査担当部門が行う消費税還付審査事務を集約処理する試行を実施している。また、同局は、調査パフォーマンスの向上のみを目的としたエリア一体運営を取りやめ、内部事務のエリア一体運営を実施するため調査審理支援(CS)担当を設置している。大阪局は、所得税調査に「重加算税賦課判定表」を導入し、調査審理に係る事務負担の軽減を図っている。名古屋局は、各署の個人課税部門に配置していた「審理担当者」を廃止し、調査審理を行う統括官等を審理専門官がサポートする体制とした。
経験の浅い職員、深度ある審査を実施できないおそれ
東京国税局は、令和5事務年度において税務署の調査担当部門が行う消費税還付審査事務を集約処理する試行を実施している。試行の背景には、調査担当部門には経験の浅い職員が多く、深度ある還付審査を実施できないという懸念があったようだ。
試行の概要は、東京上野センター対象署(表1参照)の調査担当部門における消費税還付審査事務を東京上野署に集約し、同署に増設した消費税専門官(還付審査担当・集約)等が審査を行うというもの。
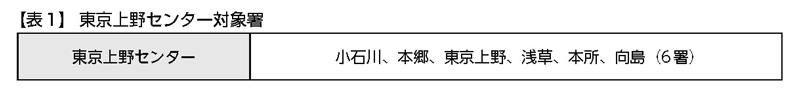
同局は、還付審査事務を集約することで、還付審査の均一化・効率化を図るとともに、調査部門の調査事務量を確保するとしている。
不正還付対応の審理専門官を増員し、審理体制強化
消費税還付審査集約の試行に加え、東京局は、局統括国税実査官(消費税担当)との連絡・調整を担当する消費税専門官を設置している。消費税専門官が実施する還付審査には多くの事務量を要し、統括国税実査官(消費税担当)への調査企画依頼が遅れていたことから、還付審査の情報を迅速に調査企画につなげることが狙いだ。
さらに、令和5事務年度は消費税不正還付事案を担当する審理専門官を1名増員し、審理体制を強化している。令和4事務年度においても消費税調査専担部署の設置署(新宿、東京上野、渋谷、豊島)に不正還付事案担当の審理専門官を配置して審理体制の強化を図ったが、消費税不正還付事案の増加で更なる対応が必要となった。
調査事務のみのエリア一体運営を取りやめ、3エリア解消
また、東京局は平成30事務年度から資産税調査のエリア一体運営を行ってきたが(本誌831号特集等参照)、令和5事務年度は調査パフォーマンスの向上のみを目的としたエリア一体運営を取りやめている。
調査事務のエリア一体運営では、限られた人的資源の中で調査事務量を有効活用するため、エリア内の調査優先度の高い事案を調査することで調査事績の向上が図られてきたが、エリア内に複数の統括官が配置されていることに伴い指揮命令や進捗管理に非効率が発生したという。この状況を踏まえ、令和5事務年度のエリア一体運営については、資産職員無配置署がある東京上野エリア、甲府エリアに限定して実施し、江東エリア、品川エリア、足立エリアを解消している(表2参照)。
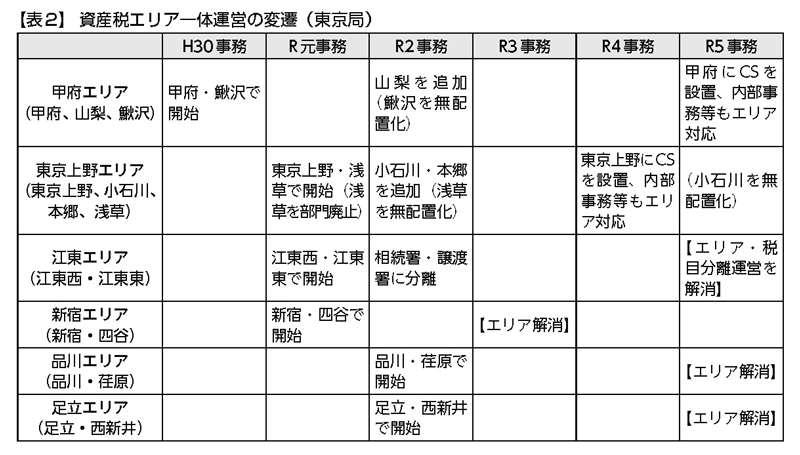
東京上野エリア、甲府エリアに調査審理支援担当を設置
一方で、東京局は令和4事務年度から調査事務のエリア一体運営に加え、内部事務のエリア一体運営を実施している。具体的には、東京上野署に審理担当者を集約配置し、調査審理支援(CS)担当として、エリア内の納税者等からの相談事務、調査優先度判定、更正の請求事務を行っている。
内部事務のエリア一体運営について、東京局は、CS担当間の助け合いにより効率的な処理、均質的な判断に一定の効果が認められると評価。令和5事務年度から甲府エリアにもCS担当による内部事務のエリア一体運営を導入した。
そのほか、資産税のエリア一体運営に関しては、令和5事務年度から神田署と日本橋署が資産職員の無配置署となり、麹町署(千代田区)、京橋署(中央区)による広域運営が実施されている。
隠蔽・仮装の自認事案、争点整理表に代えて判定表作成
大阪国税局は、所得税調査で「重加算税賦課判定表」を導入した(下掲参照)。導入の目的は、争点整理表の記載を簡略化し、調査担当者、調査担当統括官、審理専門官部門の事務負担を軽減すること。
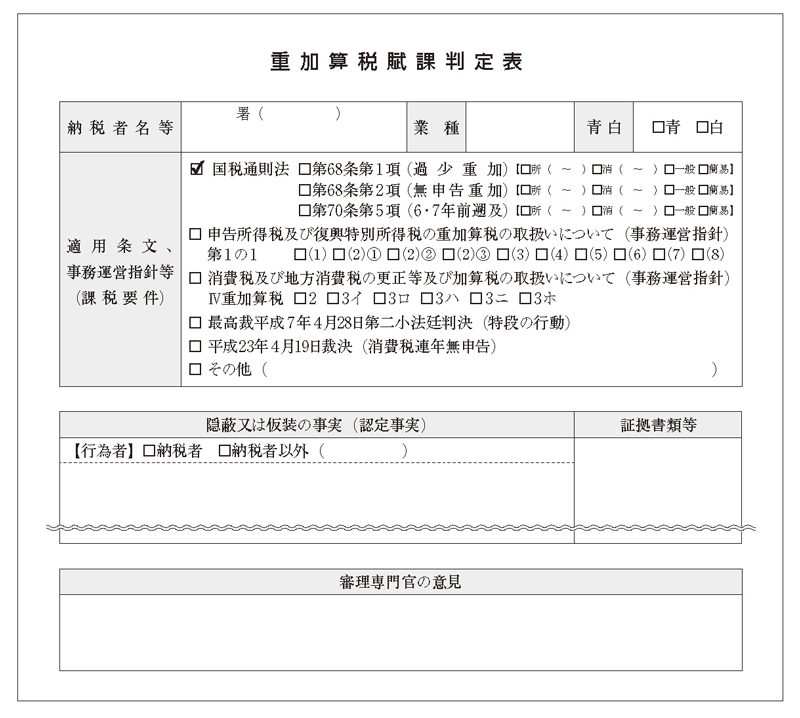
重加算税賦課判定表の作成対象は、重加算税賦課事案(重加事案で、偽りその他不正の行為により6・7年前の年分へ遡及する事案を含む)のうち、実際に争訟となる見込みがないと統括官等が判断した事案(納税者が隠蔽・仮装の事実を自認)であり、争点整理表に代えて重加算税賦課判定表が作成される。
納税者の行為と同視できる理由を記載
重加算税賦課判定表をみると、「課税要件」欄は、適用条文、事務運営指針、最高裁平成7年判決、平成23年4月19日裁決から選択。「認定事実」欄には、調査担当者が調査の過程で把握した隠蔽・仮装の事実が簡記され、隠蔽・仮装の行為者が納税者以外の場合は、納税者の行為と同視できる理由が記載される。
また、「審理専門官の意見」欄は、審理専門官が、証拠の収集・保全、事実認定、法令の適用が適切に行われているか検討した結果を記載する。
審理専門官の広域運営を拡大、統括官等に多角的な助言
名古屋国税局は、令和5事務年度において、各署の個人課税部門に配置していた「審理担当者」を廃止した。審理担当者の廃止により、調査審理には調査担当者・統括官等で対応し、審理専門官がサポートする体制となる(表3参照)。審理専門官の広域運営については、広域運営中心署を13署(岐阜北、大垣、静岡、浜松西、沼津、名古屋中、昭和、熱田、豊橋、刈谷、小牧、津、四日市)に拡大させ、審理専門官付職員を増員した。
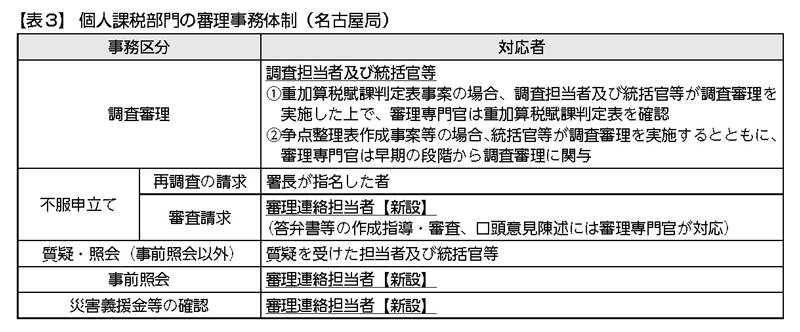
なお、審理専門官は、争点整理表作成事案に早期の段階から関与し、統括官等に審理面の多角的な助言を行うほか、争訟見込みのない重加算税賦課事案で統括官等が作成した「重加算税賦課判定表」の記載内容から重加算税賦課の適否を判断する。
「審理連絡担当者」が審査請求や事前照会などに対応
また、名古屋局は、審理担当者の廃止に伴い、各署に「審理連絡担当者」(令和5事務年度は、連絡調整官または総括(担当)上席)を配置している。審理連絡担当者は、①審査請求に関する事務(答弁書等の作成指導・審査、口頭意見陳述には審理専門官が対応)、②納税者等からの事前照会事務、③災害義援金等に関する確認事務、④会計検査院に関する事務を担当するほか、特に定めのない審理専門官との連絡事務に対応する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























