解説記事2020年02月03日 税制改正解説 令和2年度税制改正(連結納税とデジタル課税)(2020年2月3日号・№821)
税制改正解説
令和2年度税制改正(連結納税とデジタル課税)
一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部主幹 幕内 浩
令和2年度税制改正では、連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)、オープンイノベーション税制や5G税制の創設、消費税の申告期限の延長など、企業の競争力強化や納税環境の改善に資する措置が講じられる。また、与党大綱ではデジタル課税についても考え方が示された。本稿ではこれらのうち連結納税制度(とりわけグループ調整計算)とデジタル課税を取り上げる。なお、意見には筆者個人のものが含まれている。
Ⅰ 連結納税制度
経団連は毎年、税制改正提言を取りまとめ、公表している。連結納税制度については、機動的な事業再編の促進の観点から開始・加入時の時価評価課税や欠損金の持ち込み制限の緩和を一貫して求めてきた。個別の連結法人における修・更正が他の連結法人に影響を及ぼし、事務負担が生じている点はかねて認識されていたが、税制改正要望として強調するまでには至っていなかった。連結納税を選択するのは損益通算やグループ調整計算のメリットを享受するためであり、ある程度の事務負担は承知の上、という企業も少なくなかったからである。
とはいえ、平成14年度の創設から18年近くが経過する中、連結納税を採用する企業グループの数が思ったほど伸びていないこと、また、執行サイドにおけるニーズもあり、制度の簡素化の必要性が徐々に指摘されるようになった。2018年の秋に政府税制調査会において連結納税制度に関する専門家会合が設置された時点で、令和2年度税制改正における連結納税制度の見直しが事実上、方向づけられたといって良い。
かくして経団連は、開始・加入時の時価評価課税や欠損金の持ち込み制限の緩和といった従来の主張を維持しつつ、制度の簡素化は重要なるも、損益通算やグループ調整計算といった連結納税制度の既存のメリットが失われることのないようにすべき、との立場で専門家会合等の議論に参加することとなった。令和2年度税制改正に関する提言(2019年9月)でも同趣旨の主張をしている。
今回の改正で、これら意見は概ね反映されることになった。連結納税制度の後継制度であるグループ通算制度(原則として通算グループ内の各法人が個別に申告・納付)では、開始時において、親法人と子法人の完全支配関係の継続の見込みがあれば、時価評価課税は行われない。また加入時においても、現行制度では現金買収による100%子会社化は時価評価課税の対象となっていたところ、共同事業要件を満たせば対象外となり、前進といえる。欠損金についても、支配関係が開始・加入前に5年超継続している場合、又は共同事業要件を満たす場合は、グループ内に特定欠損金(自己の所得を限度として繰越控除可能な欠損金)として持ち込めることになる。支配関係成立後に新事業を開始する場合、構造的損失事業を有する場合等の欠損金の一部切り捨てや含み損の利用制限等の措置も導入されるが、現行制度に比べれば救済の余地は広がっている(もっとも、グループ通算制度からの離脱時については、新たに一定の資産の時価評価制度が設けられ、また、投資簿価修正の改組もあるため、その影響はプラス面・マイナス面含め充分アセスしきれていない部分もある)。
損益通算や欠損金の繰越控除も手法は異なるが維持され、かつ、個別法人における修・更正を遮断する措置も講じられた。連結納税を開始して間もない企業グループにおいては、連結親法人の開始前欠損金がまだ残っているケースがある。グループ通算制度を新規に適用する場合は開始前の親法人の欠損金は特定欠損金となるが(すなわち、グループ全体の所得に対し繰越控除できない)、連結納税からグループ通算制度に移行する場合は、連結親法人の開始前欠損金は、引き続き、グループ全体の所得と相殺できる。
グループ調整計算については、金額的なインパクトの大きい研究開発税制や外国税額控除等、重要なものについて維持された。加えて、受取配当益金不算入制度における負債利子控除の概算控除可など、簡素化も行われる。
グループ通算制度は令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。2年間の猶予は、システム開発や企業の準備期間を踏まえれば、長いようで短い。早期に政省令・通達含め、制度の詳細が明らかになることを期待したい。
税制改正の過程では、主としてグループ調整計算のあり方について議論が行われた。概要は以下の通りである。
1.研究開発税制
(1)連結納税制度
控除額は連結グループ全体で計算し、各連結法人にその個別帰属額を配分する。例えば総額型では、グループ全体の試験研究費の合計額に基づき増減試験研究費割合を計算し、税額控除割合を判定、グループ全体の試験研究費の合計額にその税額控除割合を乗じてグループ全体の税額控除限度額を計算するとともに、グループ全体の調整前連結税額の25%が控除上限額となる。こうして計算したグループ全体の税額控除可能額を各連結法人の試験研究費の額の比で按分した金額を各連結法人の税額控除個別帰属額とする。
(2)グループ通算制度
専門調査会報告書では上記のグループ調整計算について維持・廃止の両論併記となったが、グループ一体経営の現状に鑑み、維持されることとなった。グループ通算制度の下でもグループ全体で計算した税額控除限度額と控除上限額とのいずれか少ない金額が税額控除可能額となる。これを各法人の調整前法人税額の比で配分した金額を各法人の税額控除限度額とする。
個別申告方式の下では、損益通算後の所得がない法人(つまり調整前法人税額がない法人)に対して税額控除可能額を配分しても控除ができないことから、損益通算後(繰越欠損金控除後)に黒字の法人にのみ、税額控除可能額を配分することとなる。したがって、試験研究費を支出した法人と税額控除を受ける法人とが異なる局面が生じる可能性がある。ただし、通算グループ内で通算税効果額(グループ通算制度を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額に相当する金額として内国法人間で授受される金額)を授受することが可能であり、その授受する金額は益金不算入・損金不算入となる。
通算グループ内の他の法人において試験研究費の額や調整前法人税額について変動があった場合、原則として、確定申告書に記載された数値で固定される。ただし、減更正によって通算グループ全体の税額控除可能額が確定申告書に記載された税額控除可能額に満たなくなる場合には、税額控除可能額の目減り分を減更正を行った法人にチャージする等の法人税額の調整等を行う。
このことは、増更正によって税額控除可能額が増える可能性がある場合については、原則通り、税額控除可能額は当初の確定申告書の数値で固定されることを意味する。平成29年度税制改正で当初申告制度の見直しがあり、増更正の場合でも税額控除額を連動して増額できることになった経緯を踏まえれば、この部分については課題を残すこととなった。
2.外国税額控除
(1)連結納税制度
連結法人が各連結事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、その外国法人税の額のうち、連結控除限度個別帰属額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。具体的には、以下の手順で計算する。なお、外国税額について税額控除と損金算入のいずれを適用するかは、連結グループ全体で選択する。
〇連結グループ全体で連結控除限度額を計算
連結控除限度額=
当期の連結法人税額 × 調整連結国外所得金額/連結所得金額
・連結法人税額は、研究開発税制等の租特の適用前の金額
・連結所得金額は、繰越欠損金控除前の金額
・調整連結国外所得金額は、連結所得金額の90%が限度
〇連結控除限度個別帰属額を計算
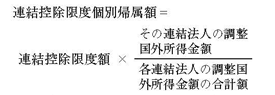
・調整国外所得金額は、調整連結国外所得金額につき各連結法人に帰せられる金額が零を超えるもの
なお、控除限度個別帰属額は、法人税のほか、地方法人税、道府県民税及び市町村民税の分がある。
〇個別控除対象外国法人税額を計算
納付した外国法人税額のうち、高率(35%超)負担部分及び対象とならない外国法人税額を除いた金額
〇連結控除限度個別帰属額の超過額・余裕額を計算
個別控除対象外国法人税額>連結控除限度個別帰属額→差額は超過額(3年間繰越)
個別控除対象外国法人税額<連結控除限度個別帰属額→差額は余裕額(3年間繰越)
超過額・余裕額は単体で管理(連結グループ内での相殺は不可)
(2)グループ通算制度
専門家会合報告書では、上記のグループ調整計算について維持・廃止の両論併記となり、税制改正の終盤まで議論が行われたが、グループ一体経営の実態に鑑み、こちらも最終的には維持されることとなった。
大綱では、通算グループ内の各法人の控除限度額の計算は、基本的に連結納税制度と同様とされている。なお、外国税額について税額控除と損金算入のいずれを適用するかは通算グループ全体で選択することとなり、法人ごとの選択は認められない見込みである。
通算グループ内の各法人の当期の外国税額控除額が期限内申告書に記載された外国税額控除額と異なる場合には、期限内申告書に記載された外国税額控除額を当期の外国税額控除額と見なす。その上で、当期の外国税額控除額と期限内申告書に記載された外国税額控除額との過不足額は、進行年度の外国税額控除額又は法人税額においてその調整を行うことになる。
すなわち、通算グループ内の他の法人における過年度の計算誤りにより数値の変動があった場合には、その変動後の数値により控除限度額を各事業年度で再計算するが(この再計算自体は、修・更正に該当しない)、税額控除額は当初申告額に固定し、税額控除額の変動額(不足分、超過分)は進行年度で調整する(不足分を控除額に加算、超過額を法人税額に加算)ということになる。
なお、通算グループ内の各法人が外国税額控除額の計算の基礎となる事実を隠蔽又は仮装して外国税額控除額を増加させること等により法人税の負担を減少させようとする場合には、この取り扱いは適用されない。
3.受取配当等の益金不算入制度
(1)連結納税制度
連結法人が配当等の額を受け取るときは、持株割合の区分に応じ、その配当等に係る以下の額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(表1参照)。

完全子法人株式等の判定については、連結納税か単体納税かに関わらず、100%グループ内で分散保有している株式を合算して100%となる場合は、完全子法人株式等として判定する。つまり、持株割合が100%の外国法人を経由して100%保有される内国法人の株式も、完全子法人株式等に該当する。一方、関連法人株式等や非支配目的株式等の判定においては、連結納税制度の下では、連結グループ全体で判定するが、単体納税においては、個社の持分のみで判定する。
関連法人株式等に係る負債利子控除は次の通り計算する。
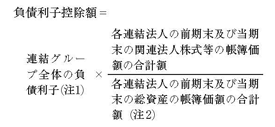
(注1)連結グループ内の法人に支払う負債利子を除く
(注2)連結グループ内の法人に支払う負債利子の元本となる負債の額を除く
なお、短期保有株式の判定は連結グループ全体で行う。
(2)グループ通算制度
専門家会合報告書では、グループ調整計算について維持・廃止の両論併記となったが、株式を分散保有している現状に鑑み、維持されることになった。持株割合の判定について、完全子法人株式等のみならず、関連法人株式等や非支配目的株式等についても100%グループ全体で判定することとなる(通算グループ全体での判定ではない)。ケースとしては少ないが、100%グループ内の外国法人を経由して内国法人の株式を保有している場合には、持株割合の区分が繰り上がり、益金不算入額が増加する場合がある。設例は図1の通りである。
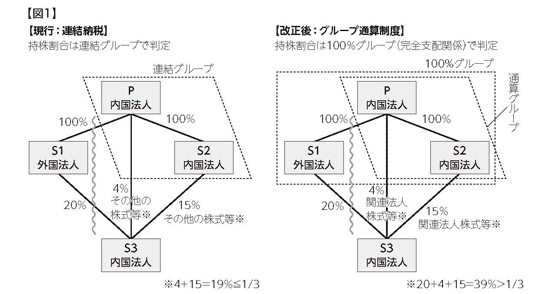
内国法人S3の株式について、100%グループ内の外国法人S1の保有分が加味されることになり、持株割合の区分がその他の株式等から関連法人株式等に繰り上がる。
関連法人株式等に係る負債利子控除については、関連法人株式等に係る配当等の4%が概算控除される。ただし、その一律適用によって大幅な税負担増とならないよう、その事業年度において支払う負債利子額の10%が上限となる。グループ通算制度における負債利子の総額はは、現行の連結納税の仕組みから類推すれば、100%グループ内の法人に支払った負債利子は含まれないと考えられる。
短期保有株式の判定は各法人で行うこととなり、これまでのグループ全体での判定は廃止される。
(3)単体納税制度
グループ通算制度を選択しない場合でも、持株割合の判定について、100%グループ全体で判定する取り扱いが適用される。これにより、単体納税制度においても、100%グループ内で株式を分散保有している場合には、持株割合の判定区分が繰り上がり、益金不算入額が増加する場合が想定される。図解すると図2の通りである。
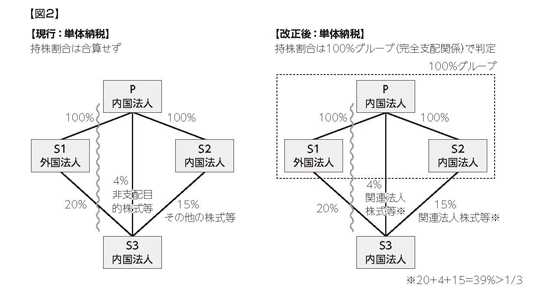
内国法人S3の株式について、内国法人P、外国人S1、内国法人S2のすべての保有株式が合算されることにより、持株割合の区分が関連法人株式等まで繰り上がる。
負債利子控除についても同様に、グループ通算制度を選択しない場合でも、関連法人株式等に係る負債利子控除について、従来の制度(利子×前期末及び当期末の関連法人株式等の帳簿価額の合計額/前期末及び当期末の総資産の帳簿価額の合計額)が廃止され、関連法人株式等に係る配当等の4%の概算控除が適用される。その事業年度において支払う負債利子額の10%が上限となる取り扱いも同様である。
4.外国子会社配当等の益金不算入制度
(1)連結納税制度
内国法人が外国子会社(原則として内国法人の持株割合が25%以上で保有期間が6月以上の外国法人)から受ける剰余金の配当等の額のうち、その配当等の5%相当額を控除した金額は、益金に算入されない。この単体納税の規定は、連結納税においても適用される。連結納税においては、持株割合は、各連結法人の持ち分を合算して判定を行う。
(2)グループ通算制度
専門家会合報告書では、上記のグループ調整計算について、維持・廃止の両論併記となったが、外国法人の株式を連結グループ内で分散保有している現状等に鑑み、あまり争点となることなく維持された。
持株割合は通算グループ内の各法人の持ち分を合算して判定する。国内配当のように100%グループでの判定に変更になるわけではない。課税済利益に対する二重課税の防止という意味では国内配当も外国子会社配当も趣旨は同じだが、外国子会社配当については国家間の課税権の配分という側面もあることから、国内配当とは若干異なる取り扱いとなった。
なお、単体納税制度においては、従来の取り扱いに変更はない。外国法人の持株割合は法人ごとに判定する。
5.寄附金
(1)連結納税制度
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、損金算入限度額を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額上、損金の額に算入しない。一般寄附金及び特定公益増進法人等への寄附金の損金算入限度額は、連結親法人の資本金等の額と連結所得を基に計算する。
[一般寄附金]
(連結親法人の資本金等の額×2.5/1000+連結所得×2.5/100)×1/4
[特定公益増進法人等への寄附金]
(連結親法人の資本金等の額×3.75/1000+連結所得+6.25/100)×1/2
(注)資本金等の額がマイナスの場合はゼロとして計算
(2)グループ通算制度
専門家会合報告書では、寄附金についてグループ調整計算を廃止する方向性が示される一方、「純粋持ち株会社等において、企業グループを代表して寄附金を支出している場合があることを考慮すると何らかの配慮をすることも考えられる」とされた。
改正後、グループ調整計算は廃止となり、各法人で損金算入限度額を計算することとなる。その上で、損金算入限度額の算定基礎である資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額とされた。自己株取得等により、資本金等の額が極めて少額である法人やマイナスである法人が存在し、法人規模を適切に反映した計算式になっていないとの指摘があったことを踏まえたものであり、上記「何らかの配慮」に対応するものである。
改正後の損金算入限度額の計算式は以下の通りである。
[一般寄附金]
{(資本金+資本準備金)×2.5/1000+所得×2.5/100}×1/4
[特定公益増進法人等への寄附金]
{(資本金+資本準備金)×3.75/1000+所得+6.25/100}×1/2
(3)単体納税制度
(2)と同様、単体納税制度においても、損金算入限度額の算定基礎である資本金等の額が資本金+資本準備金となる。
6.貸倒引当金
(1)連結納税制度
連結法人が各連結事業年度において、その連結法人が有する個別評価金銭債権又は一括評価金銭債権の貸倒れ等による損失の見込額として損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、個別貸倒引当金繰入限度額又は一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は、その連結法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算において損金の額に算入される。
この規定を適用できるのは銀行・保険業等のほか、連結法人が普通法人である中小法人(資本金1億円以下)に該当する場合に限られる(一定の大規模法人の支配下にあるものを除く)。連結子法人については、連結親法人も中小法人である場合に限られる。連結親法人が大法人である場合は連結子法人はいずれも貸倒引当金を設定できない。連結親法人が中小法人であり、かつ、連結子法人甲が大法人、連結子法人乙が中小法人というケースでは、連結子法人乙は貸倒引当金が設定できる。
これらの貸倒引当金繰入限度額を計算する場合には、連結法人が連結グループ内の他の連結法人に対して有する金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれない。
(2)グループ通算制度
まず、中小法人の判定については、通算グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合には、通算グループ内のすべての法人が中小法人に該当しないこととなる。
また、貸倒引当金繰入限度額を計算する場合には、法人が100%グループ内の他の法人に対して有する金銭債権は、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には含まれない。連結グループから100%グループへと判定対象が変更となるのは、受取配当益金不算入制度と同様である。
(3)単体納税制度
(2)と同様、単体納税制度についても、100%グループ内の法人間の金銭債権を貸倒引当金の設定対象となる金銭債権から除外する。
設例は次頁の通りである。
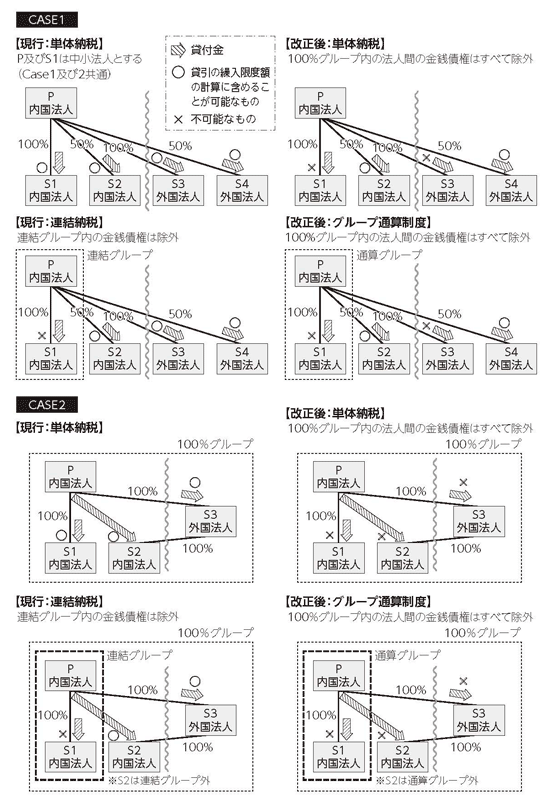
7.過大支払利子税制
【連結納税制度】
令和元年度税制改正を踏まえ、令和2年度から施行される新しい過大支払利子税制では、対象純支払利子等の額のうち連結調整所得金額の20%を超える部分の金額は当期の連結所得の計算上、損金に算入しない。但し、対象純支払利子等の額が2,000万以下の場合は、適用免除となる。対象純支払利子等の額と連結調整所得金額は、連結グループ全体で算出する。
【グループ通算制度】
専門家会合報告書では、上記のグループ調整計算を廃止する方向が打ち出されたが、特段の異論なく廃止が決まった。改正後は、損金不算入額は各法人において計算する。
ただし、2,000万円の適用免除基準は、濫用防止の観点から連結納税制度と同様、通算グループ全体で判定する方式を維持することとなる。
8.所得税額控除
(1)連結納税制度
連結法人が各連結事業年度において配当等の支払いを受ける場合には、これらにつき課される所得税の額は、配当等の元本の所有期間等に応じた一定の算式に基づき、その連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
配当等の元本が連結グループ内で移転した場合には、連結グループを一体として所有期間を計算する。つまり、元本を譲り受けた連結法人は、元本を譲渡した他の連結法人の所有期間を引き継ぐ。
銘柄別簡便法を選択した場合には、連結グループを一体として計算する。すなわち、所得税額控除の計算には、原則法と銘柄別簡便法があるところ、配当等の元本を株式及び出資、集団投資信託の受益権の2グループに区分し、かつ、配当等の計算の基礎となった期間が1年超のものと1年以下のものとに区分した4区分について、それぞれの区分ごとに原則法か銘柄別簡便法のいずれかの方法を連結グループ全体で選択し、計算する。
銘柄別簡便法の算式は次の通りである。銘柄ごとに計算する。
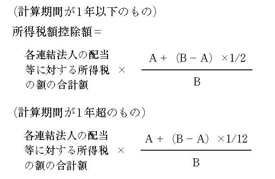
A:各連結法人が配当等の計算期間の開始時に所有する元本の数の合計額
B:各連結法人が配当等の計算期間の終了時に所有する元本の数の合計額
(2)グループ通算制度
所得税額控除額は、各法人において計算することとなった。その詳細は法令を確認する必要があるが、専門家会合報告書の議論を踏まえれば、銘柄別簡便法の上記算式を改め、通算グループ全体の数値を合計するのではなく、各法人で所得税控除額を計算することになると考えられる。なお、専門家会合の議論の途中では、資料において「現行制度では、連結グループ内で元本の譲渡があった場合、譲渡を受けた法人がその元本をもとから持っていたことにする取り扱いとされており、当該制度は現行制度のままとしてはどうか」という記述もあったことから(専門家会合第4回会合資料)、こちらについては維持される可能性がある。
9.資産の譲渡に係る特別控除
(1)連結納税制度
連結親法人又は連結子法人の有する資産が収用換地等された場合、連結所得の特別控除を適用できる(5,000万円と譲渡益のいずれか低い金額を譲渡日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する)。この5,000万円の定額控除限度額は、連結グループ全体で設定されている。
(2)グループ通算制度
グループ全体での定額控除限度額(5,000万円)の判定が維持される。その上で、グループの意義が、連結グループから100%グループへと変更となる。これにより、完全支配関係のある内国法人のうち外国法人を経由して保有するものも判定対象に加わることになるが、稀なケースと見られる。下記の単体納税制度の改正とあわせ、新しいグループ法人税制への移行と整理される。
(3)単体納税制度
単体納税制度においては、現状、法人ごとに収容換地等について定額控除限度額(5,000円)の判定を行っているが、改正後は、グループ通算制度と同様、100%グループで限度額の判定を行う。結果、定額控除限度額がグループ全体で見た場合、現状よりも縮減する可能性があるが、影響は軽微と考えられる。この改正は、新しいグループ法人税制への移行と整理される。
10.その他の租税特別措置
その他の租税特別措置については、それぞれの制度の目的や仕組み、グループ通算制度の趣旨等に配慮しつつ、修更正の他の法人への遮断措置を前提とした濫用防止のための措置その他所要の措置が講じられる。現段階ではその詳細は判明しておらず、法令を確認する必要がある。研究開発税制等の租税特別措置の適用停止措置(いわゆるムチ税制)については、令和2年度改正で一部、厳格化されたが、給与及び国内設備投資額については、当面、連結納税制度においては、グループ全体での計算が維持される見込みである。
なお、グループ通算制度における租税特別措置の取り扱いについては、グループ調整計算の維持・廃止を含め、令和2年度税制改正ですべての結論を出したわけではない。基本的には、期限の定めのある租税特別措置については、その期限が到来するタイミングで、グループ通算制度における取り扱いを個別に検討していくことになる。例えば、所得拡大促進税制(賃上げ及び投資の促進に係る税制)については現状、給与及び国内設備投資額の増加額を連結グループ全体で判定しているが、その取扱いを継続するのか否かは、期限の到来する令和3年度税制改正で議論されることになる(もちろん、所得拡大促進税制の存続や延長の是非自体も、議論される)。ムチ税制については個社ごとに計算すると抵触の恐れがある一方、所得拡大促進税制については個社ごとに計算した方が適用の余地が高まるとの考え方もある。今後、グループ一体経営との関係も含め、検討を進めていく必要がある。
グループ調整計算に関する主たる改正の内容をまとめると前頁表2の通りである。

Ⅱ デジタル課税
令和2年度税制改正では、自民党・公明党の税制調査会がデジタル課税についても議論を行った。年度の税制改正に直接結びつかない項目について取り上げるのは稀だが、2020年末の最終報告書公表に向けてOECD/G20、包摂的枠組で検討が進んでいることを踏まえ、与党としての考えをまとめ、発信する狙いがある。大綱では「安定的かつ予見可能な投資環境の構築」「企業間の公平な競争環境の整備」「新ルールの適用対象の明確化等」「過大な事務負担及び二重課税の防止」「法人税の引き下げ競争への対抗」の5つの視点が打ち出された。
1.安定的かつ予見可能な投資環境の構築
大綱では、一国主義的な課税措置をけん制しつつ、「今般の国際課税原則の見直しは、国際協調の下、各国が同様の制度を導入することで実効性が期待できる」とされた。この考え方は、政府・与党・経済界で軌を一にしている。
ただし、足元の状況は若干、不透明である。税制改正プロセスの最中だったこともあり、あまり当時はクローズアップされなかったが、昨年12月3日に米国のムニューシン財務長官がOECDのグリア事務総長宛に書簡を発出している。デジタル課税の議論には第1の柱(国家間の所得配分ルール及びネクサスルールの見直し)と第2の柱(ミニマムタックス)があるが、この書簡は第1の柱に対する懸念を述べるものとなっている。該当する部分を引用・和訳すると、以下の通りである。
多国間の合意が何であれ効果的なものであるためには、それが租税条約及び(又は)国内法の改定によって実施される必要がある。これには幅広い支持が必要である。我々は納税者との広範な協議を基礎に、さらなる税の安定性や実施可能性につき、幅広い支持があると結論付けている。
しかし、我々には、独立企業間の移転価格及び課税可能なネクサス基準-納税者が依拠してきた国際課税システムの長年の柱-からの潜在的な強制的乖離についての深刻な懸念がある。
そうは言いながらも、我々は、第1の柱をセーフ・ハーバー制度とすることで、納税者の懸念は対処され、第1の柱の目的を実質的に達成することができるかもしれないと信ずる。米国はまた、GILTI類似の第2の柱の解決策を全面的に支持する。
我々は、すでになされた作業を基礎としつつ、これらのラインに沿って、OECDと作業を行うことを楽しみにしている。
セーフ・ハーバーの詳細は不明だが、米国としては、第1の柱の制度設計には引き続き主体的に関与するが、その成果物を強制適用することについては(議会が通らない可能性があることも含め)強い懸念があることから、企業による新制度の選択の余地を残そうという意図のようである(ただしオプションではないとの解説もある)。米国のこの提案は、OECD事務局及び関係各国において、戸惑いをもって受け止められている。
当面の予定としては、1月末の包摂的枠組会合を経て、これまでの議論を踏まえた制度の大枠が公表される。検討の順序としては、米国の提案への対応よりも第1の柱の制度設計の大枠を固める方が先との見方もあるようだが、与党大綱でいう「国際協調」とも関連する部分であるため、引き続き動向を注視する必要がある。
2.企業間の公平な競争環境の整備
ここでは、第2の柱について、「軽課税国に利益を移転することで租税回避を行っている多国籍企業の税負担を適正化するなど……公平な競争環境を整備しなければならない」とされたことがポイントである。企業は、平成29年度税制改正で外国子会社合算税制が抜本的に強化された中で、さらに第2の柱の一環として所得合算ルール(外国子会社の所得を国際的に合意された最低税率までトップ・アップで課税)を導入することに対し、事務負担・税負担の両面で非常に強い懸念を有している(なお、所得合算ルールについては昨年12月にパリ・OECDで公聴会が開催されたが、各国の経済界も同様に制度の必要性について疑問を呈するとともに、CFC税制との重複の可能性を指摘している)。大綱に記載の通り、制度の対象を「租税回避を行っている多国籍企業」に限定することが極めて重要である。
3.新ルールの適用対象の明確化等
ここでは「対象となるビジネスの範囲を適切に限定しつつその定義を明確に定める」ことが重要とされた。昨年のOECD事務局の提案によれば、第1の柱における利益Aの対象は、消費者向けビジネスを行う一定の高利益率企業とされている。経団連は、比例原則の観点から対象の絞り込みを行うべきであり、中間財や医療用医薬品等を適用免除とするのが妥当である旨、OECDに意見書を提出している。昨年11月の第1の柱に関するパリ・OECD公聴会で興味深かったのは、米欧の企業のスタンスである。かつてはデジタル経済はリング・フェンス(囲い込み)ができないとし、新ルールは全業種に適用すべきと提案していたが、公聴会では、製薬、銀行、保険、テレコム等の各企業・団体から、適用除外を求める声が相次いだ。消費者向けビジネスの明確な線引きは、消費税の軽減税率の対象品目の線引き以上に困難とみられる。こちらも、今後公表される制度の大枠の内容が注目される。
4.過大な事務負担及び二重課税の防止
大綱では、「新しいルールの執行が企業に過度な事務負担を課さないように配慮する」とされた。この関連では、第1の柱では、上記公聴会において、ほぼすべての参加企業・団体からワンストップショップの提案があった。利益Aに関するOECDの事務局案によれば、ひとたび制度の対象となれば、グループ(又はグループの事業ライン)の残余利益の一定割合を売上等の指標に基づき各市場国に按分することになる。企業によっては100以上の法域で申告・納付が必要となることから、事務負担軽減の観点から、親会社所在地国の税務当局に申告・納付・税務調査等を一元化してはどうかというものである。国家主権の観点からすれば困難な部分もあると見られるが、独立企業原則から乖離し、定式配分の要素を取り入れた新たな所得再配分ルールを導入しようとしている時点で、従来の国家主権のあり方にすでに挑戦しているのであり、少なくとも検討の対象とすべきだろう。
第2の柱では、所得合算ルールにおける最低税率の判定について、課税ベースをどのように計算するか、いわゆるブレンディングをどの範囲で認めるかという論点が事務負担と大いに関わってくる。第2の柱の公聴会では、企業サイドからは、全世界ブレンディングを採用すべきであり、その際には、連結財務諸表を基礎に簡易に課税ベースを決定する必要があるとの意見が多く出された。第2の柱については今後、所得合算ルールの他、軽課税支払ルール等、他の要素についても検討が必要となる。春先には更なる市中協議が予定されている模様であり、経団連として引き続き対応していく予定である。
また、大綱では、「二重課税が生じないよう、強力な紛争防止・解決メカニズムを構築する」とされた。義務的仲裁制度の導入については途上国の懸念が依然として強い中(例えば第1の柱の公聴会でも、アフリカ税務当局の代表が反対を表明)、仲裁が難しい場合の次善の策について、検討が必要になるものと見られる。
5.法人税の引き下げ競争への対抗
ここでは、「投資を惹きつけるための法人税の引き下げ競争に歯止めをかけ、各国の税源を守る措置を国際協調の下で進めていくことが必要」とされた。米国が連邦法人税率を大幅に引き下げたことで(35%→21%)、日本の法人実効税率は再び主要国で最も高い水準となっている。与党大綱の趣旨はもちろん、理解できるが、わが国における更なる税率の引き下げは、時期的な問題はあるにせよ、経済界としては引き続き必要と考えている。この点については、大綱の別の箇所に「過度な法人税の引下げ競争に歯止めをかけることが急務になっている」との記述があることに注目している。問題なのは「過度な」引き下げであり、今後も税率引き下げの議論自体は行われるべきものと考える。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















