解説記事2020年02月17日 特別解説 我が国の上場企業による不正~第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析~(2020年2月17日号・№823)
特別解説
我が国の上場企業による不正
~第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析~
はじめに
年度の途中に年号が平成から令和に変わった2019年度。オリンパスや富士ゼロックス、東芝事件のような、会計・監査制度を揺るがすような大規模な会計不正こそ起こらなかったものの、後述するように、2019年1月から12月までに不適切な会計処理や不適切な行為等について第三者委員会報告書(第三者を含んだ社内調査委員会報告書を含む)を公表した企業は41社と、2018年度(29社)に比較して大幅に増加した。2019年度は、消費税率の8%から10%への引き上げが景気や企業業績に悪影響をもたらすのではないかと心配されたが、これまでのところはそれほど大きなつまずきもなく、景気や企業業績はおおむね堅調と言われている。しかしながら、表面上の華やかさとは裏腹に、水面下では不適切な会計処理が頻発し、相も変らず企業の謝罪会見と第三者委員会報告書の提出・公表が繰り返されているのである。
本稿では、2014年4月から2019年12月末日までの期間で、不適切な会計処理や不適切な行為について、第三者委員会報告書(第三者を含んだ社内調査報告書等を含む)を公表した企業を題材として、不正の発生原因や類型、特徴点を分析するとともに、2019年度に発生した特徴的な不正事例を3件取り上げて紹介することとしたい。
調査の対象とした企業
今回調査の対象としたのは、2014年4月1日から2019年12月31日までの期間に、不適切な会計処理や不適切な行為等について第三者委員会報告書(第三者を含んだ社内調査委員会報告書を含む)を公表した企業(以下、「報告書公表企業」という。)166社である(表1を参照。)。

これまでは、年間にほぼ30件のペースで不適切な会計処理に関する調査報告書が公表されてきたが、2019年度は41件と、大幅に増加している。なお、調査報告書が公表された事例のうち、得意先が要求するスペックを満たしていない製品を偽って納入していた、等の会計処理とは直接関係しない不適切な事例は、今回の調査の対象からは除いている。
次に、報告書公表企業の166社を、上場している市場等の区分ごとに分類すると、表2のとおりであった。現在、東証における市場区分の見直しや銘柄の整理等が検討課題として挙げられているが、3,700社弱の上場会社のうち、60%弱が東証1部となっている。当然のことながら、絶対数でみると東証1部に上場している企業(又はその子会社等)による不適切な会計処理が最も多いが、各市場の上場会社数の合計で除して比率を算出すると、東証1部が4.0%であるのに対して東証2部は4.5%、ジャスダック5.1%、マザーズが4.7%と、いわゆる新興市場に上場している企業のほうが、相対的に見て不適切な会計処理が起こりやすい傾向にあるという結果となった。

不適切な会計処理の分類と発覚の原因等
不適切な会計処理を生じさせた当事者を分類すると、表3のとおりであった。なお、表3の「元役員・従業員」の区分には、組織的ではない、個人的な不正行為(横領、着服等)を分類している。
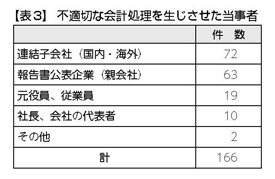
新聞報道等でもよく取り上げられているが、親会社に比べてガバナンスが効きにくく、監視の目が届きにくいとされる連結子会社(特に中国をはじめとする海外の子会社)で不適切な会計処理が発生した事例が多かった。次に、不適切な会計処理を形態別に分類すると、表4のとおりとなった。
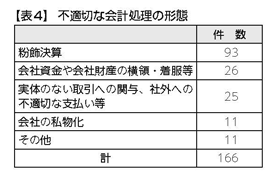
会社の業績、特に売上高や利益を実力以上によく見せることを狙ったいわゆる粉飾決算が過半数を占めていたが、その一方で、個人的な動機(ギャンブル等にのめりこんだ末の借金返済や、個人的な遊興費への充当等)による資金の横領や着服等も少なからず存在していた。また、国内外の連結子会社において、本社が十分に管理監督をしないままに現地の担当者に業務を任せきりにしていたり、未知の土地で取引の拡大を拙速に進めようとしたりした結果、不透明な取引や循環取引等に巻き込まれて多額の不良債権や損失が発生したような事例もあった。さらに、「会社の私物化」には、オーナー経営者や創業者が、取締役会の決議等を経ぬままに私情が絡んだ投資を行ったり、公私混同を行ったりしていたような事例が含まれている。
さらに、不正の具体的な内容を分類すると、表5のとおりであった。
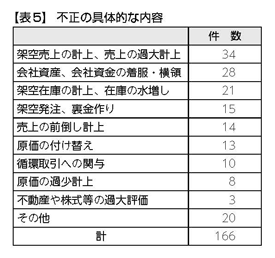
一つの不適切な会計処理事案の中に、表5の項目が複数含まれることはよくあり、むしろそのような事例のほうが多いが、ここでは便宜的に、それぞれの事案をどれか一つの項目に絞って分類している。架空売上の計上(前倒し計上)、会社資産や会社資金の着服・横領、及び架空在庫の計上という手法は、非常に古典的な、古くて新しい不適切な会計処理の技法であるといえる。
最後に、不適切な会計処理が発覚した契機を分類すると、表6のようになった。
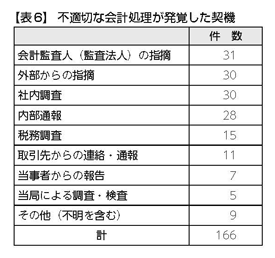
調査報告書上は必ずしも明記されていないが、表6の「社内調査」には、企業が自ら異変に気付いて行った自発的な社内調査のほかに、内部・外部から内密の情報提供を受けた上での社内調査も相当数、含まれているものと思われる。一般的には、不適切な会計処理を外部者が発見することは難しく、したがって不適切な会計処理を発見するためには内部通報のほうが有効であると言われることもあるが、今回の調査結果を見る限り、会計監査人(監査法人)や外部からの指摘、あるいは税務調査における指摘など、外部の第三者が介在したことをきっかけとして不適切な会計処理が発覚したケースがかなりの部分を占めていた。また、会計監査人が不適切な会計処理の兆候を発見して会社側に未然に是正を求めたようなケースや、不適切な会計処理が行われはしたものの、第三者委員会を設置しての調査が必要となるほどの規模になるまでの拡大は防いだようなケースも少なからず存在すると思われる。内部統制や内部的な自浄作用に加え、会計監査人等による外部からのけん制も、不適切な会計処理の抑止に一定の効果があるものと思われる。
2019年度に発生した特徴的な不適切な会計処理の事例
表1で紹介しているように、2019年1月1日から12月31日までの間に第三者委員会報告書が公表された不適切な会計処理にかかる事例は41件あったが、本稿では、2019年度に生じた不適切な会計処理のうち、大和ハウス工業、すてきナイスグループ、及び梅の花の3つの事案を取り上げて概要を紹介し、簡単にコメントをすることとしたい。
① 大和ハウス工業 調査報告書公表日 2019年6月18日
主な不正の内容 中国の関連会社(JV)における会社資金の横領
(事件の概要)
2019年3月13日、大和ハウス工業株式会社は、同社の関連会社であり、中国遼寧省大連市に本社を有する大連大和中盛房地産有限公司(以下「大連JV」という。)において会社資金約14億1500万人民元(約234億円)が不正に引き出されていたことを公表した。これに先立ち、大連JVは、同月12日、本件不正出金への関与が疑われる同社幹部2名及び出納担当者1名を、中国の捜査当局に業務上横領等の疑いで刑事告訴した。大連JVは、大連市の現地企業である大連中盛集団有限公司と大和ハウスとの合弁会社である。刑事告訴の対象となった前記3名は、いずれも中盛集団から派遣された者であった。
(コメント)
多角化によって業績が急速に伸び、「飛ぶ鳥を落とす勢い」と見られていた業界のリーディング・カンパニーが、進出先の中国で大きく躓いた事件であり、損失処理額の大きさも相まって、大きな話題となった案件である。ダイワハウスに対して提出された報告書では、ガバナンスや内部統制の充実、研修の実施など、数多くの再発防止策が並んでいるが、その中でも、外国での合弁会社の設立や日常の管理に関する勧告事項のポイントを以下に列挙してみたい。
(1)合弁会社の設立・管理
① 合弁会社管理の基本方針の策定、合弁契約及び定款への落し込み
② 合弁スキームの慎重な検討
③ 合弁パートナーに対する財務調査・人物調査
④ 合弁パートナーの問題発生時のバックアッププランの検討
(2)合弁会社の平時の運営
① 財産管理方法の見直し
・例えば、銀行を訪問する等して定期的に口座照合をすること、銀行残高証明書が正確であって偽造等をされていないことを作成者の署名、捺印や偽造の有無判定用のQRコードから確認すること等を実施する。
② 定款その他社内規則の整備、見直し
・定款その他社内規則における会議体の頻度、決裁権限、印章の管理方法、違反した場合の措置(解任、降格等)等のルールが整備・運用されているか見直しを行い、関係役職員に対しルールを周知する。
・現地法人駐在員が、当該企業の社内規定の整備等において本社管理部門に支援を求めることができるよう、本社における現地駐在員の支援システムを強化する。
③ 派遣駐在員の適切な配置
・派遣駐在員の配置を検討するにあたっては、派遣先の国のビジネス環境及び当該プロジェクトのリスクを考慮し、リスクが高いプロジェクトには、当該国での経験が深く、現地語が堪能な適任者を配置する。
④ 有事に備えた業務メールのモニタリング
⑤ 現地会計監査人が行う監査の品質確保に関する検討、選定プロセスへの関与
(3)現地の制度、法律、商習慣についての理解の向上
合弁パートナーの説明を鵜呑みにせずに、各種制度を日本人駐在員が調査し、モニタリングの充実を図ることができるよう、収集すべき情報の明確化と、収集した情報を共有する適切な仕組みについて検討する。
(4)現地法人・合弁会社の運営を支援する本社体制の構築
派遣先の国における他事例、有事対応参考事例、合弁パートナーの説明に係るセカンドオピニオンやベストプラクティスを情報収集し、蓄積して各現法駐在員に提供できるデータベースの構築を行う等、平時から、部門横断的にノウハウを共有し、有事対応のノウハウを蓄積する。
(5)親会社側における、有事に対応できる体制づくり
① 有事対応の責任部門(職務分掌)及び職務権限規程の策定
② 海外プロジェクト有事の際の本社取締役会や監査役会への報告基準の策定
③ 合弁や事業提携等における有事における、合弁を組成する合弁パートナー等の重要な関係者との交渉担当者の選任手続等、問題発生時にもオペレーションを維持するためのプロセスの準備
④ 有事に備えた本社管理部門による現地法人への内部統制構築支援
(6)海外グループ会社における有事を想定したケーススタディの実施
海外グループ会社におけるビジネスパートナーによる利益相反行為や不祥事の発生を想定し、海外グループ会社における有事対応の知見の蓄積、想定した具体的なケーススタディを行う。
② すてきナイスグループ 調査報告書公表日 2019年7月24日
主な不正の内容 連結範囲の操作による、売上高の架空計上
(事件の概要)
2019年5月16日に、すてきナイスグループに対し、金融商品取引法違反(平成27年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取引等監視委員会及び横浜地方検察庁による強制捜査が実施された。これは、実質的に支配下に置いていた会社に対して土地やマンション等を売却し、そのうえでこれらの売却先の会社を連結範囲に含めていなかったことによるものである。
(コメント)
すてきナイスグループによる不正発覚の契機は、証券取引等監視委員会による強制捜査であった。この事案は、創業家出身の元社長(H氏)の強大な影響力の下で、H氏が実質的にオーナーである会社(非連結)を使って益出しを行い、業績を取り繕ったものである。連結範囲外の会社に資産を売却して益出しする手法は以前に鐘紡が行った方法であるが、今回もまた繰り返されることとなった。これらの会計操作は、H氏の強い意向を受けて行われたものであり、すてきナイスグループ各社の役員陣も、H氏に対して物が言えない状態で、ガバナンスが形骸化していた。東芝事件や日産自動車のゴーン元社長が主導した不祥事もそうだが、いくらガバナンスの形式や内部統制の仕組みを整えても、強力な権限を持つトップがその気になれば、すぐに無力化されることがよくわかる事例である。
③ 梅の花 調査報告書公表日 2019年8月28日
主な不正の内容 店舗に係る固定資産の減損判定関連の計算にあたり、本社経費を恣意的に傾斜配賦して減損処理を回避
(事件の概要)
会社は、2019年4月期の決算手続を進めるにあたり、会計監査人から、会計処理に関する問題点、具体的には、店舗に係る固定資産の減損判定関連の計算にあたり、本社経費を恣意的に傾斜配賦していた点について指摘を受けた。すなわち、会社では、各期の決算手続の中で減損の兆候の有無を判定するため「店舗別損益」を作成し会計監査人に提示をしているが、2019年4月期の監査において、会計監査人は、会社の「店舗別損益」を確認する際、少額の黒字となっている店舗が多数存在している点に疑義を抱くに至った。そこで会計監査人の担当者が「店舗別損益」の根拠資料である「減損の兆候シート」について改めて検算したところ、本社費、本部費等の配賦計算の基礎となる間接費(購買物流費等)金額が財務会計数値と一致しないこと、配賦基準(店舗売上高や店舗人員数)に従って算出されるべき数値の一部が実態とは異なる数値で修正入力されていること等の異常が発見され、減損回避のための不正な操作が行われたのではないかとの疑念が生じることとなった。
(コメント)
飲食業チェーンを営む梅の花の経理担当者が減損の兆候が存在する店舗を試算したところ、想定よりも多数の対象店舗が存在することが判明したため、当初、巨額の赤字決算を免れるため監査上許容される範囲において損失発生を抑制すべく、可能な限り店舗に係る減損損失が少額となるよう作業を進めていたところ、翌期の事業計画を保守的に作成していたことから、多数に上った減損の兆候が存在する店舗のすべてについて、利益が増加する利益計画を作成すると、全体の事業計画において見込む来期の利益を超えてしまうという矛盾が生じざるを得ない状況となった。当時は、銀行から強い返済圧力を受けた直後で、一般従業員さえも会社の存続を危ぶむような状況にあったことから、巨額赤字を免れたいという経営者の意向に沿って、減損金額が少額となるよう、本社経費の配賦額を調整して減損処理の対象となる店舗を減らしたり、赤字幅を少なくしたりするという不適切会計処理に及んだ。固定資産の減損会計は、見積り期間が長期間にわたり、金額的な重要性が高く、かつ不確実性も大きい。「鉛筆を舐めれば損益はどうにでもなる」という会計上の見積りが持つリスクの大きさを如実に示している事例と言えよう。
終わりに
監査上の主要な検討事項(KAM)を中心とした監査報告書の透明化や持合株式に関する開示の強化、会計監査人が交代した理由のより詳細な説明など、企業の開示制度は着々と整備・進化が進んでいるが、それらを作成し、使いこなす側の企業の経営者や経理担当者、会計監査人や監査役等のマインドセットがなかなかそういった変化に追いついていけず、会計上の不祥事も減少するどころか、むしろ増加傾向にある。
将来的にAIやロボットが経理の現場にも導入されることが予想され、もうすでに業務の置き換えが始まっている企業も少なくないが、AIやロボットの導入によって機械的な処理ミスは減り、内部統制上の牽制機能(異常値の検出による不正の端緒の発見など)は向上する可能性が高いかもしれない。しかし、高度な判断や見積りが介在する項目や、いわゆる「組織ぐるみ」の不正に対応することまでは難しいであろう。不適切な会計処理に最も影響を与えるのは、生身の人間の感情である。時間はかかるが、生きがいをもって働ける職場環境の整備、風通しのよさの確保、組織を成長させ、倫理規範に反するようなやり方を戒めるような価値観の共有といった、泥臭いことを日々、地道に続けていくことが結局は不適切な会計処理を根絶するための近道であろうと思われる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























