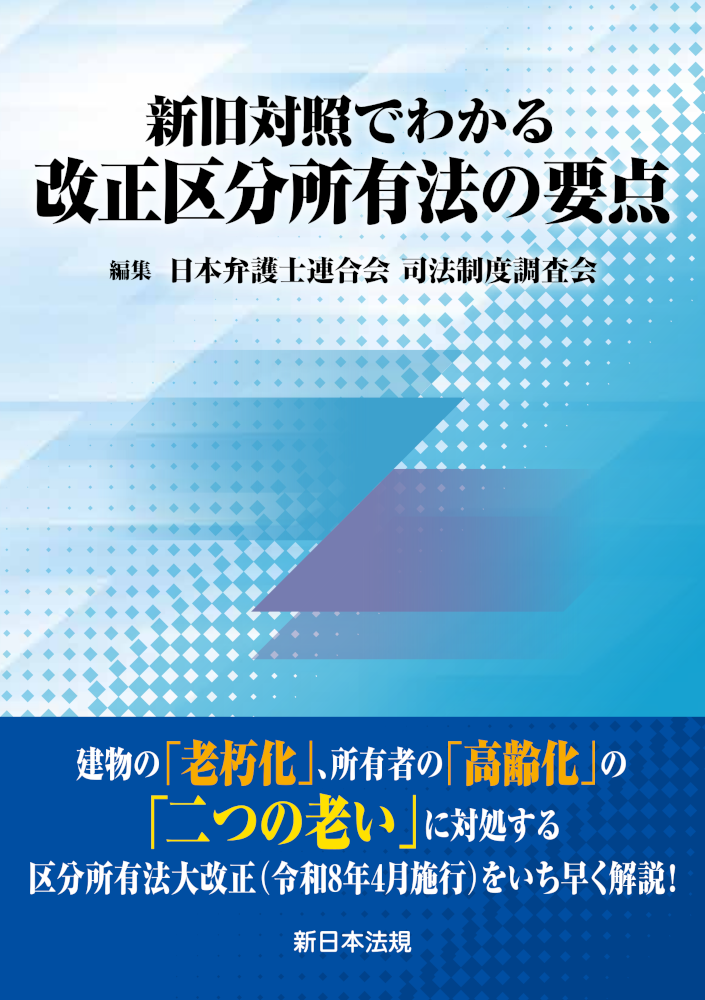解説記事2020年02月24日 未公開判決事例紹介 贈与税を巡る税賠事件、信義則上の義務違反を認容(2020年2月24日号・№824)
未公開判決事例紹介
贈与税を巡る税賠事件、信義則上の義務違反を認容
東京地裁、税理士に約140万円の損害賠償
読者からの反響が大きかった本誌823号(2020.2.17)16頁で紹介した税理士賠償請求事件の判決全文について、仮名処理した上で紹介する。
○納税者(原告)の会社の前代表取締役であった父の未払退職金について、顧問税理士(被告)の進言に従い債務免除をしたところ、贈与税等が課せられたとして、税理士に約600万円の損害賠償を請求していた事件。東京地方裁判所(杜下弘記裁判官)は、確定申告業務に係る委任契約上の義務に直接的に違反するとはいえないとしたが、贈与税が課税される可能性について明確にしなかったことについて、信義則上の義務を履行しなかった過失があると判断。原告の主張を一部認容した。(令和元年10月15日、一部認容)
主 文
1 被告は、原告に対し、140万9000円及びこれに対する平成30年9月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、575万9000円並びにうち475万9000円に対する平成30年9月29日から及びうち100万円に対する令和元年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、税理士である被告に対して平成23年度及び平成24年度の税務申告を委任したところ、原告が同各年度に係る税務調査の結果、贈与税のほか、無申告加算税及び延滞税を支払う義務を負うに至ったことについて、被告には委任契約上の善管注意義務違反があると主張して、被告に対し、委任契約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、贈与税、無申告加算税及び延滞税の合計額である375万9000円と慰謝料200万円並びにうち475万9000円に対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月29日から、うち100万円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である令和元年7月31日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 争いのない事実(証拠を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は、訴外株式会社E(以下「訴外会社」という。)の代表取締役であり、被告は平成18年から平成25年2月まで訴外会社の顧問税理士であった者である。
(2)訴外会社において原告の前代表取締役であった亡X(平成27年6月25日死亡。以下「亡X」という。)は、原告の父であり、亡Xは訴外会社の株主でもあった。
(3)被告は、訴外会社の代表者であった亡Xに対し、平成17年、相続時精算課税制度の利用を進言し、亡Xは原告に対して訴外会社の株式164株を生前贈与し、被告は、同贈与に係る贈与税について税務代理人として税務申告手続を行った。
(4)訴外会社は、平成19年に亡Xが訴外会社の取締役を退任するに当たり、亡Xに対する退職金として8950万円を支給することを決定したが、訴外会社は資金不足のため、同退職金の全額を支払うことができなかった。
(5)平成23年の時点における訴外会社の亡Xに対する未払退職金額は5000万円であったところ、被告は、訴外会社の決算対策として、訴外会社の代表取締役であった原告に対し、未払退職金について亡Xが債務免除することを進言した。
(6)亡Xは、被告の進言を受け入れ、訴外会社に対し、平成23年12月期に3000万円、平成24年12月期に2000万円の未払退職金債務を免除した(以下「本件債務免除」という。)。
(7)被告は、原告との委任契約に基づいて、税務代理人として、個人としての原告の確定申告を行った。
(8)亡Xは平成27年6月25日に死亡した(甲22)。
(9)原告は、平成29年10月、S税務署から亡Xの相続に関連して税務調査を受けた上、本件債務免除が相続税法9条及び相続税法基本通達9-2における同族会社の債務免除によるみなし贈与に該当するとして、贈与税の申告義務があると通告され、平成30年2月21日、平成23年分及び平成24年分の贈与税の期限後申告手続(以下「本件期限後申告」という。)を行った(甲5の1ないし甲6の3)。
(10)本件期限後申告の結果、原告が負うこととなった納税義務の内容は、以下のとおりである(甲7)。
平成23年分
贈与税:165万円
無申告加算税:30万5000円
延滞税:33万3800円
平成24年分
贈与税:110万円
無申告加算税:19万5000円
延滞税:17万5200円
2 争点
(1)被告に原告に対して本件債務免除によって贈与税が課税されることの説明をしなかったことが委任契約上の善管注意義務に違反するといえるかどうか(争点1)。
(原告の主張)
原告が、被告から本件債務免除によって原告が贈与税を負担する必要がある旨の説明を受けていれば、本件債務免除の方法は選択しないのであり、被告は原告に対して贈与税についての説明は何らしていない。
被告は、原告個人との間で税務申告についての委任契約を締結していたところ、このような重要な事項について何ら説明しないことは、委任契約上の善管注意義務に違反する。
(被告の主張)
訴外会社が同族会社であることから、被告は、原告に対して、本件債務免除によって原告が保有する訴外会社の株式価値が増加する場合には、その分贈与税がかかることになる旨の説明をした。
当時は業績の悪い訴外会社の決算対策が課題であったため、このような説明にそれほどの重点を置いていなかった可能性があるが、被告は原告に対して上記のとおり贈与税についての説明をしており、被告に委任契約上の善管注意義務違反はない。
(2)被告が原告に対して本件債務免除によって贈与税が課税されるとの説明をしなかったことが不法行為を構成するかどうか(争点2)。
(原告の主張)
税理士は、税理士法1条により「納税義務の適正な実現を図ることを使命」とされており、そのための高度の注意義務を負う。
被告は、本件債務免除によって原告に贈与税が課税されることを知りながら、その旨の説明をしなかったのであり、このような不作為は上記の高度の注意義務に違反する違法な行為である。
(被告の主張)
原告の主張を争う。
(3)原告の損害(争点3)
(原告の主張)
原告は、相続税、無申告加算税及び延滞税として合計357万9000円の納税義務を負っただけでなく、税務調査においてS税務署から複数回の事情聴取を受けた上、脱税者扱いをされて多大な精神的苦痛を被っており、これを金銭に換算すると100万円を下らない。
(被告の主張)
原告の主張を争う。
(4)損益相殺(争点4)
(被告の主張)
仮に被告に善管注意義務違反があるとしても、原告は本件債務免除によって亡Xの相続税を249万9000円減額する利益を受けており、原告に発生した損害については、この減額分の利益と相殺されるべきである。
(原告の主張)
本件債務免除の当時、訴外会社は経営難に陥っており、この状況においては亡Xの訴外会社に対する未払退職金に係る債権を低廉な価格で第三者に譲渡することにより、亡Xの相続財産を減少させ、相続税を減額することは容易であり、本件債務免除以外の方法により相続税の減額が可能である以上、被告の損益相殺の主張は認められない。
第3 当裁判所の判断
1 事実認定
(1)被告の業務内容
被告は、平成18年から平成25年2月まで、訴外会社の顧問税理士として、税務関係の業務に携わったが、その業務は毎月の帳簿管理を行った上、決算書をまとめ、法人税の確定申告を行うというものであり、その過程で決算対策についても税理士としてアドバイスするなどしていた(乙4、被告本人)。
また、被告は、税務代理人として、原告の平成17年分から平成23年分までの確定申告手続(甲3の1~5、甲4、8~13)、亡Xの平成17年分から平成24年分までの確定申告手続(甲14~ 21)を行っており、これらの業務は、被告が訴外会社の顧問税理士であったことから、その代表者や親族であった原告と亡Xの確定申告手続を行っていたものであり、申告単位で報酬を受領していた(被告本人)。
被告は、平成24年2月ころ、訴外会社の平成23年度の決算書をまとめるに当たり、訴外会社の財務状況が芳しくなく、金融機関からの融資を得られにくい状況にあったことから、訴外会社の代表者である原告に対し、本件債務免除によって当期純利益を捻出するという方策を進言し、訴外会社は同方策を実行した(乙1、2、4、被告本人)。
(2)本件債務免除に関する原告への説明
被告は、本件債務免除の方策を説明するに際し、原告に対して、本件債務免除により訴外会社の財務状況が改善され、亡Xの推定相続人である原告にとっても相続税が減額されるメリットがあることについて説明した(甲24、乙4、原告本人、被告本人)。
また、被告は、訴外会社の経理担当者に対し、原告が保有する訴外会社の株式価値が増加すれば、増加額に応じて贈与税が課税されることになることを認識しながら、原告個人に贈与税が課されるかどうかやその税額について、具体的なシミュレーションやこれに基づくアドバイスはしなかった(乙4、被告本人)。
この点に関し、被告は、本件債務免除により原告が保有する訴外会社の株式価値が増加する場合には、その分の贈与税が株主である原告個人にかかることになる旨の説明をしたと主張し、被告本人尋問においてもこれに沿う供述をするほか、財務状況が芳しくない訴外会社の株式価値がそれほど増加するとは考えていなかった旨供述する。
しかしながら、担税力は株式価値の相対的増加に見いだされるものであり、訴外会社に対する数千万円規模の債務免除により同社の株式価値が増加することは明らかであり、この点を意識して検討していれば、税理士である被告にとって、原告個人に贈与税が課税される可能性が高いことも明らかであったということができるから、一般論としてしか説明しなかったとの被告の供述は不合理であって信用することはできず、被告の主張を採用することはできない。
2 争点1(被告に原告に対して本件債務免除によって贈与税が課税されることの説明をしなかったことが委任契約上の善管注意義務に違反するといえるかどうか)についての判断
前記第2の1(3)のとおり、被告は、相続時精算課税制度の利用を進言し、亡X及び原告がこれを受け入れた結果、亡Xは訴外会社の株式164株を原告に生前贈与しており、前記1(1)及び(2)のとおり、訴外会社の決算対策のために被告が進言した本件債務免除の方策は、原告が保有する株式の価値を増加させることになると認められるから、これによって原告に贈与税が課税されることになることは容易に理解することができたということができる。
その一方で、前記1(1)のとおり、被告は、税務代理人として、平成17年分から平成24年分までの亡X及び原告(原告については平成23年分まで)の確定申告手続を行っていたが、訴外会社の顧問税理士が平成24年3月以降は被告から他の税理士へと交代し、平成27年6月25日に死亡した亡Xの相続税については、被告以外の税理士が申告手続を行っている(甲22)。
一般に、税務申告は税目ごとに行われるものであるから、所得税に関して確定申告手続の依頼を受けて同手続について委任契約を締結した税理士が、税目の異なる贈与税についての申告業務を行うべき義務を負うということはできないし、上記委任契約自体に基づいて、当然に、他の税目についての申告業務の依頼をするよう助言する委任契約上の義務を負うということもできない。
そうすると、被告が、原告に対して、贈与税について説明しなかったとしても、原告との間で締結した確定申告業務に係る委任契約上の義務に直接的に違反するとまでいうことはできない。
したがって、委任契約上の債務不履行による損害賠償請求権に基づく原告の請求は理由がない。
3 争点2(被告が原告に対して本件債務免除によって贈与税が課税されるとの説明をしなかったことが不法行為を構成するかどうか)についての判断
前記3のとおり、特定の税目についての申告業務について委任契約を締結した税理士は、委任者に対し、他の税目についての申告業務を依頼するよう助言する義務を当然に負うものということはできない。
しかしながら、委任者は他の税目について申告の必要性を認識しなければ、そもそも税理士に申告業務を依頼しようとは考えないのに対し、申告業務について依頼を受けた税理士は、委任者の財産の状況から他の税目についての申告の必要性を把握することができる場合があり、当該税理士が他の税目について申告が必要となることが確実であると認識すべき場合には、委任者に対してこのことを説明し、委任者が申告の要否について判断することができるよう助言する信義則上の義務を負うと解するのが相当である。
そして、故意又は過失によりこの義務に違反したときは、当該税理士に不法行為が成立する余地があるというべきである。
本件においては、前記第2の1(3)ないし(6)、(9)及び(10)並びに前記1(1)で認定したところによると、被告は、亡X及び原告に対し、相続時精算課税制度の利用を自ら進言し、同人らがこれを受け入れたことによって、原告は亡Xより訴外会社の株式の生前贈与を受けて同社の株主となっていたところ、被告は、訴外会社の代表取締役に就任していた原告に対し、同社の決算対策及び亡Xの将来の相続に係る相続税の減額を意図して本件債務免除を進言し、原告がこれに従った結果、上記の経緯で保有するに至った訴外会社の株式価値が増加し、贈与税を課税されるに至ったというのである。
そして、被告は、前記1(1)のとおり、平成17年ころから平成24年ころまでの間、同族会社である訴外会社の顧問税理士として財務状況を把握する一方、経営者であり株主である亡X及び原告の確定申告手続を受任し、同人らの所得の状況を把握する立場にあったということができる。
以上によると、被告は、税理士としての自らの助言に従うことにより、原告に贈与税が課税される可能性が高いことを把握すべき立場にあったというほかないのであり、原告に対し、上記可能性を明確に指摘し、申告の要否について検討するよう助言すべき信義則上の義務を負っていたというべきである。
そうであるにもかかわらず、被告は、前記1(2)のとおり、原告に対し、贈与税が課税される可能性について明確にすることなく、原告をして無申告のまま放置させるに任せたのであるから、少なくとも被告には上記信義則上の義務を履行しなかった過失があるというべきであり、被告による上記義務違反は不法行為を構成する。
4 争点3(原告の損害)についての判断
前記3で説示した被告の不法行為によって、原告は適時に申告していれば負担する必要がなかった無申告加算税及び延滞税を負担しており、これらの合計である100万9000円は被告の不法行為と因果関係のある損害であると認められる。
原告は、税務調査を受けたことにより精神的苦痛を被ったと主張するところ、原告が受けた税務調査は贈与税の申告をしなかったことを理由とし、4か月間にわたって行われたものであり(被告本人)、その結果として無申告加算税と延滞税を課された(甲5の1~ 3、甲6の1~ 3)ことからすると、適時に申告をしていればこのような税務調査を受けることは通常考えられないから、上記税務調査に対応するための原告の負担は、被告の不法行為と因果関係のある損害であるということができる。このような原告の有形無形の負担のうち精神的負担を金銭に換算すると、40万円をもって相当と認める。
また、原告は、贈与税が課税されることがわかっていれば、被告による本件債務免除の進言を受け入れなかったから、贈与税額も損害に含まれると主張するが、本件債務免除が行われた当時、訴外会社は赤字続きであり、金融機関から継続的に融資を受けて資金繰りを確保するために本件債務免除によって当期純利益を確保する必要があった(乙1、2、被告本人)と認められ、仮に贈与税が課されることがわかっていたとしても、本件債務免除を選択する可能性は否定されないから、原告の主張を採用することはできない。
さらに、原告は、本件債務免除の方法によらなくても、亡Xの訴外会社に対する未払退職金債権を低廉価額で譲渡する方法により財務状況を改善させることはできたと主張するが、これは訴外会社の財務状況を改善するための手法の選択の問題であり、実際に行われた本件債務免除との比較において、税務当局が最終的に行う課税面での評価の異同について立証されているとはいえないから、原告主張に係る手法があり得ることを前提としても、贈与税額自体を原告の損害と評価することはできない。
5 争点4(損益相殺)についての判断
被告は相続税の減税額分について損益相殺を主張するが、この主張は、本件債務免除により課税されることになった贈与税額分が損害と認められる場合に、同じ本件債務免除によって得られた利益としての相続税の減税額分を相殺すべきであるとの主張である。
しかしながら、前記4のとおり、本件においては、無申告加算税及び延滞税の額並びに精神的損害を金銭に換算した額をもって原告の損害と認めるから、被告の主張に係る相続税の減税額分について通算すべき対応関係は認められない。
したがって、前記4で認めた損害を前提とする限り、被告の損益相殺の主張を採用することはできない。
6 まとめ
以上によると、本件の事実関係の下では、被告が贈与税の申告の必要性について原告に指摘しなかったことは原告に対する不法行為を構成し、これによる損害は140万9000円と認めるのが相当である。
第4 結論
以上の次第で、原告の請求は、被告に対して140万9000円及び訴状送達日の翌日である平成30年9月29日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、この範囲で認容し、その余は棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第6部
裁判官 杜下弘記
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.