解説記事2024年05月06日 法令解説 企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の解説(2024年5月6日号・№1026) −有価証券届出書における個人情報の記載の見直し−
法令解説
企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の解説
−有価証券届出書における個人情報の記載の見直し−
金融庁企画市場局企業開示課開示企画調整官 上利悟史
金融庁企画市場局企業開示課専門官 鈴木彬史
1 はじめに
令和6年3月7日、事業会社の株式に係る新規公開(以下「IPO」という)時に提出される有価証券届出書において、ストック・オプション(以下「SO」という)の保有者の氏名・住所等が記載されるところ、このような個人情報の取扱いの見直し等を内容とする、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和六年内閣府令第十六号)(以下「改正府令」という」)が公布され、同年4月1日から施行された。また、これに伴い、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(以下「開示ガイドライン」という)が改正され、同日から適用された。
本改正は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」(2023年6月16日閣議決定)(以下「実行計画」という)において、IPO時に提出される有価証券届出書においてSOの保有者の氏名・住所等が記載されるところ、このような個人情報の取扱いの見直しを行う旨の提言がされたことを踏まえたものである。
本稿では、本改正について、パブリックコメントに対する金融庁の考え方なども踏まえて解説する。なお、本稿において、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解であることをあらかじめ申し添えておく。
2 改正の概要
(1)IPO時に提出される有価証券届出書における個人情報の記載の見直し
① 改正の背景
IPO時に提出される有価証券届出書では、IPO前2年間(脚注1)に発行された株式やSO(以下「株式等」という)の全取得者の氏名や住所、当該2年間における株式等の移動状況(移動を行った当事者の氏名や住所等)の開示が求められている(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)第2号の4様式記載上の注意(25)a(a)、b(a))。
これについて、スタートアップ企業を中心にプライバシー保護の観点から懸念の声が指摘されており、令和5年5月11日に公表された、自民党「『スタートアップ育成5か年計画』の実現に向けた提言」において、「新規公開時に提出される有価証券届出書等においてSOの保有者の氏名・住所等が記載される」ところ、この個人情報の取扱いの在り方を見直すことが提言された。その後、同年6月に閣議決定された実行計画においても、このような個人情報の取扱いの見直しを行う旨の提言がされている。
② 改正内容
IPO時に提出される有価証券届出書においては、過去の事件(脚注2)を踏まえた、平成元年の企業内容開示省令(当時)の改正により、上場前の不明朗な取引を牽制する観点から、IPO前2年間に発行された株式等の全取得者の氏名や住所等の開示が求められている。
(ア)使用人に関する記載
会社が、使用人に対し、その役務提供の対価として株式等を付与する場合には、付与対象者や付与の目的が明確であることから、基本的には不明朗な取引ではないと考えられる。また、使用人のプライバシー保護の観点を踏まえ、本改正では、株式等を付与された者が使用人(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、氏名・住所の記載を不要としている(開示府令第2号の4様式記載上の注意(24)c、(24)d(b)・(25)b(a))。
もっとも、会社の資本政策を投資家に明らかにする観点から、付与された使用人の人数や、使用人に付与された株式等の全体数の開示は必要としている(同様式記載上の注意(25)b(a))。
(イ)役員に関する記載
他方で、会社が、役員に対し、その役務提供の対価として株式等を付与する場合には、当該株式等は経営者に対するインセンティブ報酬という側面があると考えられる。そして、経営者がどの程度のインセンティブを与えられているのかという情報は、投資家の投資判断にとって重要であると考えられることから、本改正では、株式等を付与された者が役員(退任・退職者を含む。以下同じ)である場合には、引き続き、役員ごとに付与された株式等の数の開示が必要としている。
ただし、役員のプライバシー保護の観点から、住所の記載は不要としている(開示府令第2号の4様式記載上の注意(24)d(a)、(25)b(c))。
(ウ)「大株主等」(開示府令第2号の4様式記載上の注意(24)c)に含まれる役員又は使用人に関する記載
IPO時に提出される有価証券届出書の「株主の状況」の記載欄においては、所有株式数の多い順に50名程度の株主の氏名及び住所が開示される(脚注3)(開示府令第2号の4様式記載上の注意(26)b)。これについて、有価証券報告書の「大株主の状況」の記載欄においては、所有株式数の多い順に10名程度の株主の氏名及び住所が開示される(開示府令第3号様式記載上の注意(25)c)ことを踏まえ、本改正では、役員及び使用人が、所有株式数の多い順に10名の株主に含まれる場合には、「大株主の特定」(脚注4)等の観点から、引き続き氏名及び住所の記載を必要としている(開示府令第2号の4様式記載上の注意(24)c等)。
他方で、所有株式数の多い順に10名の株主に含まれない(すなわち、所有株式数の多い順に11名以下の株主である)役員及び使用人については、前記(ア)(イ)のとおり、役員については、役員ごとに付与された株式等の数の開示を必要としつつ、住所の記載は不要とし、使用人については、氏名・住所の記載を不要としている(同様式記載上の注意(26)b、c)。
また、本改正では、大量保有報告義務がある役員又は使用人については、引き続き、氏名・住所の記載を必要としている(同様式記載上の注意(24)c等)。これは、大量保有報告書においては、「他の提出者等と混同することなく同一人と判別できることが不可欠」であるため、提出者が個人の場合に市区町村までの住所の記載を求めている(脚注5)ことを踏まえたものである。
(エ)本改正後の届出書の記載例
本改正後における、IPO時に提出される有価証券届出書の記載例は図表1〜3のとおりである。(脚注6)
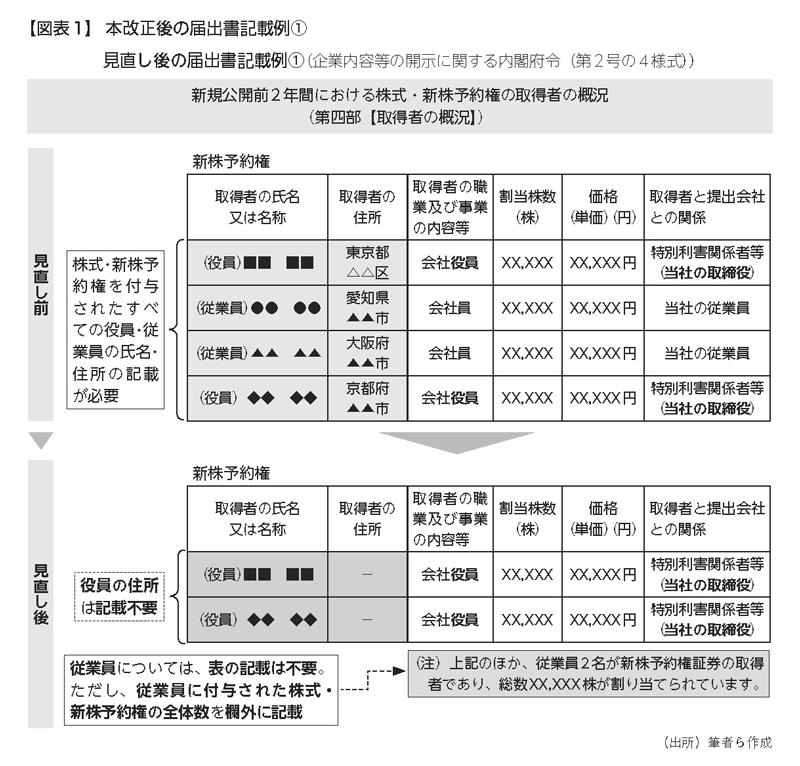
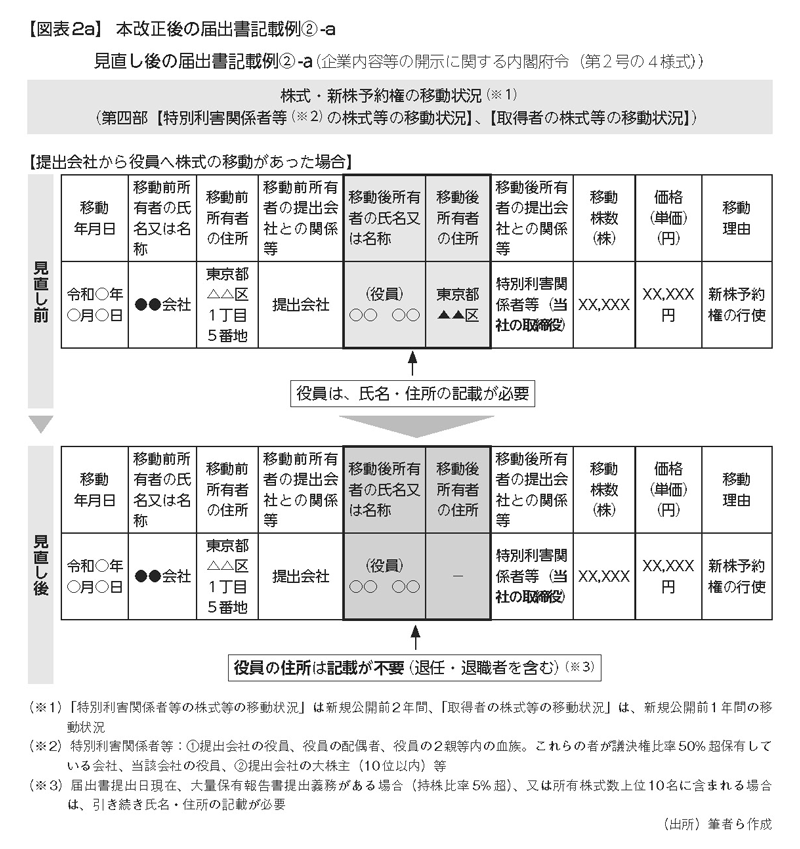
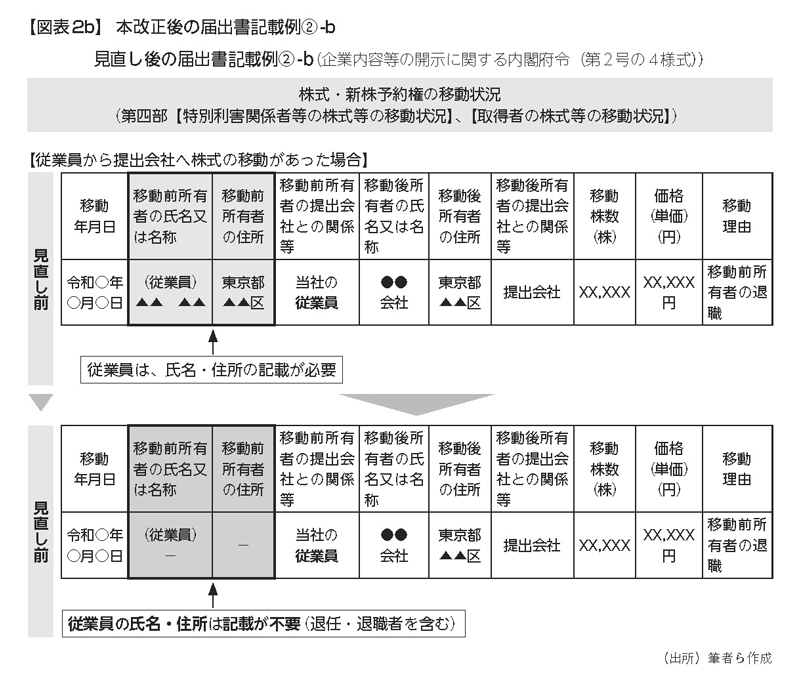
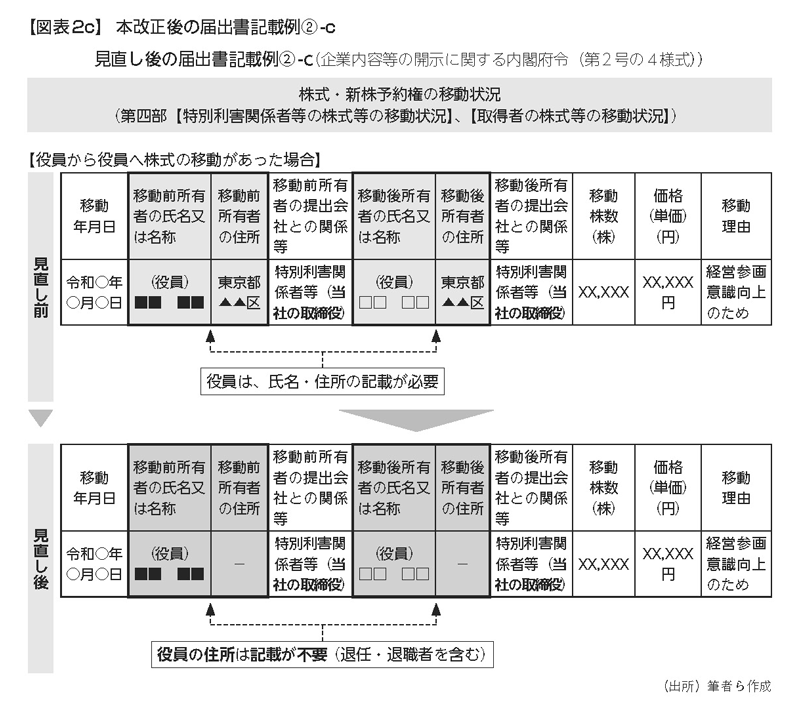
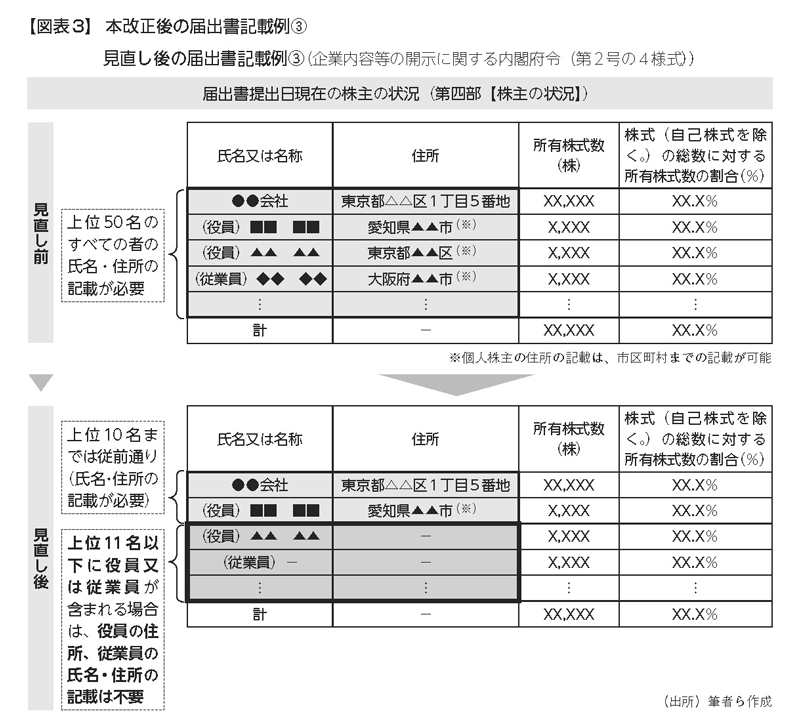
③ 本改正を踏まえた留意点
前記②(ウ)のとおり、本改正後も、役員又は使用人について、(i)大量保有報告義務がある場合又は(ii)所有株式数の多い順に10名の株主に含まれる場合には、引き続き、氏名・住所の記載を必要としている。このとき、(i)又は(ii)の場合に該当するかどうかをどの時点で判断する必要があるかが問題になる。
まず、(i)は、大量保有報告義務の対象について、金融商品取引法(以下「金商法」という)27条の23第1項では「株券……で金融商品取引所に上場されているもの」と規定されていることを踏まえると、IPOに係る株券の場合は、上場日時点で当該義務の有無を判定することが必要になる。そのため、IPOに係る有価証券届出書の提出時点(典型的には、上場承認日)において、予定される募集株式数・売出株式数を踏まえ、上場日時点で大量保有報告義務が生じる予定かどうかを判定することとなると考えられる。(脚注7 8)
また、(ii)について、有価証券届出書においては、基本的に届出書提出日時点の情報を開示することが必要であることから、届出書提出日時点で判断すれば足りると考えられる。このことは、「特別利害関係者等の株式等の移動状況」(開示府令第2号の4様式記載上の注意(24))、「第三者割当等の概況」(同様式記載上の注意(25))又は「株主の状況」(同様式記載上の注意(26))の記載欄のいずれについても同様であると考えられる。(脚注9)
(2)第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書の個人情報の見直し
① 改正の背景
第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書について、当該第三者割当の割当予定先が個人である場合は、「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該個人の氏名、住所及び職業の内容等を記載する必要がある(開示府令第2号様式記載上の注意(23-2))。
この場合に、会社が、退任・退職した役員又は使用人に対し、在任中・在職中の役務提供の対価として、株式等を付与する場合には、第三者割当の方法による募集又は売出しに該当する(開示府令19条2項1号ヲ)。そのため、当該募集又は売出しに係る有価証券届出書の「第三者割当の場合の特記事項」欄において、当該退任・退職した役員又は使用人の氏名、住所及び職業の内容等を記載する必要があり(開示府令第2号様式記載上の注意(23-3)a)、プライバシー保護の観点から懸念の声が指摘されていた。また、経団連「2023年度規制改革要望」(2023年9月12日公表)においても、プライバシーの観点から、「提出会社等の退任者・退職者に対して、在任中・在職中の職務への対価として株式等の第三者割当を行う場合も、有価証券届出書等において「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすべきである」旨公表されていた。
② 改正内容
そもそも、第三者割当の方法による募集又は売出しに係る有価証券届出書において、「第三者割当の場合の特記事項」欄を記載することが求められる趣旨は、第三者割当に係る割当先や目的等についての開示を求めることで、市場の公正性・透明性を確保する点にあると考えられる。もっとも、開示府令19条2項1号ヲ(2)〜(4)に規定する方法により、会社が、役員又は使用人に対し、その役務提供への対価として株式等を付与する場合には、報酬の支給の一種であり、割当先や割当の目的は明確であることから、「第三者割当」から除外され、「第三者割当の場合の特記事項」欄を記載することは不要となる。(脚注10)
確かに、会社が、退任・退職した役員又は使用人に対し、在任中・在職中の役務提供の対価として株式等を付与する場合には、退任・退職している以上、形式的には会社内での報酬の支給とはいえず、「第三者割当」に該当すると考えられる。しかし、この場合は、役員又は使用人への付与と同様、割当先や割当の目的は明確であると考えられ、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を求める必要性は乏しいと考えられる。
以上を踏まえ、本改正では、退任・退職した役員又は使用人に対し、在任・在職中の役務提供の対価として、株式等を付与する場合には、形式上は「第三者割当」に該当するものの、「第三者割当の場合の特記事項」欄の記載を不要としている(開示府令第2号様式記載上の注意(23-2)、開示ガイドライン5−9−2)。(脚注11)
3 おわりに
本改正は、役員・使用人のプライバシー保護の観点を踏まえ、IPO時又は第三者割当時に提出される有価証券届出書の記載事項の見直しを実施したものである。今後は、各会社において、今回の見直しを踏まえ、各社の事業内容に即した職位の重要性を踏まえた、役職員向けの資本政策を検討し、投資家にわかりやすく開示することが期待されよう。
脚注
1 最近事業年度の末日の2年前の日から届出書提出日までの間を指す(開示府令第2号の4様式記載上の注意(25)a(a))。
2 昭和63年に発覚した、未公開株式の贈収賄事件である。
3 なお、IPO時に提出される有価証券届出書「株主の状況」の記載欄において、所有株式数の多い順に50名程度の株主の状況の開示が求められているのは、IPO前の株式移動に関する開示に加えて、IPO時の株主も開示させることで、不明朗な株式移動に対する牽制効果を徹底する観点を踏まえたものと考えられる(松田春夫「企業内容開示省令の改正について(下)」(旬刊商事法務1179号20頁)参照。)。
4 参議院議員藤末健三君提出有価証券報告書における情報開示と個人情報保護に関する質問に対する答弁書 第163回国会(特別会)答弁書第15号 内閣参質163第15号 2005年11月4日(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/163/touh/t163015.htm)
5 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ報告」(2013年12月公表)18頁参照
6 なお、氏名や住所の記載が不要となる場合には、「−」等の記号を記載することが考えられる。
7 金融庁「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2024年3月7日)(以下「パブリックコメントに対する金融庁の考え方」という)No.5参照。
8 なお、IPOに係る有価証券届出書の提出日時点では、大量保有報告義務が生じる予定はないと判定された者について、その後の募集・売出株式数の変更(例えば、仮条件決定時の株式数の減少や、公開価格決定時の売出株式数の変更が考えられる。)により、当該義務が生じる予定があるという判定に変わる可能性もあると考えられる。このような判定の変更が生じた場合であっても、当初届出書提出日時点の募集・売出株式数を踏まえ、当初届出書において当該義務が生じる予定の者の氏名・住所を記載していれば、判定の変更が生じた時点で当初届出書を訂正する義務は生じず、当初届出書の効力発生に対する影響はないといえるかどうかが問題となる。
このような判定の変更により、上場後に大量保有報告義務が生じる予定の者が増えた場合には、「重要な事項の変更」(金商法7条1項前段)に該当すると考えられることを踏まえると、当該判定の変更が生じた際に、当初提出された有価証券届出書の該当事項を訂正する義務が生じると考えられる。もっとも、このような訂正は、当該判定の変更の起因となった募集・売出株式数の変更に係る訂正届出書において、募集・売出株式数の変更とあわせて行うことで足りると考えられる。
この場合において、例えば、当該判定の変更の起因となった株式数の変更が、仮条件の範囲外の一定の範囲で売出株式数を変更するものであるときには、上場後に大量保有報告義務が生じる予定の者を追記するための訂正は、当該売出株式数の変更と一体の訂正として、開示ガイドライン8−4ロ②により、当該訂正届出書の提出日又はその翌日にその届出の効力を生じさせることができると考えられる(パブリックコメントに対する金融庁の考え方No.6参照)。
9 パブリックコメントに対する金融庁の考え方No.7〜8参照。
10 神保勇一郎=平沢由里絵=森卓也=西原彰美「会社法改正に伴う金融商品取引法施行令、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の概要」(旬刊商事法務2259号)12頁参照。
11 この場合には、「第三者割当の場合の特記事項」欄について、「該当事項はありません。」等の文言を記載することが考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























