解説記事2024年09月16日 特別解説 のれんの計上の状況等の分析(2023年度)(2024年9月16日号・№1043) ~IFRS任意適用日本企業と日本の会計基準を適用する主要な日本企業の場合~
特別解説
のれんの計上の状況等の分析(2023年度)
~IFRS任意適用日本企業と日本の会計基準を適用する主要な日本企業の場合~
はじめに
我が国でIFRSの任意適用が開始されてから15年以上が経過し、IFRSを任意適用して連結財務諸表と有価証券報告書を作成・公表する日本企業(以下「IFRS任意適用日本企業」という。)の数も、株式時価総額が高い、国際的な優良企業を中心に着実に増加している。各社の2023年度の3月決算に係る有価証券報告書等がそろって開示されたのを受けて、本稿では、主要な日本企業ののれんの計上額や連結純資産に対するのれん計上額の比率、のれんの減損処理額等を調査して、全体的な傾向等の分析を試みた。具体的には、主要なIFRS任意適用日本企業、数は少ないが米国会計基準を適用する日本企業、及び日本の会計基準を適用する主要な日本企業(株式時価総額が高い企業)を対象として調査分析を行うこととしたい。
調査分析の対象とした企業
今回調査分析の対象としたのは、2024年3月期まで(2023年度)にIFRSを適用して有価証券報告書を作成・提出した主要な日本企業(主要なIFRS任意適用日本企業)の100社であり、いずれも最も直近の本決算での数値を用いている。
また、本稿の後段では、米国会計基準を適用して連結財務諸表を作成している日本企業6社と、2024年3月末日時点で東京証券取引所での株式時価総額上位300社にランクインしている日本企業のうち、IFRS任意適用日本企業と米国会計基準を適用する日本企業を除いた計100社(日本の会計基準を適用する主要な日本企業)も調査の対象として加え、IFRS任意適用日本企業や欧米で上場する主要な企業との比較も交えつつ、のれんの計上額等に関する調査分析を行っている。
主要なIFRS任意適用日本企業が計上したのれんの調査分析
のれんの計上額が大きい主要なIFRS任意適用日本企業を列挙すると、表1のとおりであった。なお、参考として、各社ののれんの計上額の連結純資産に対する比率も併記している。
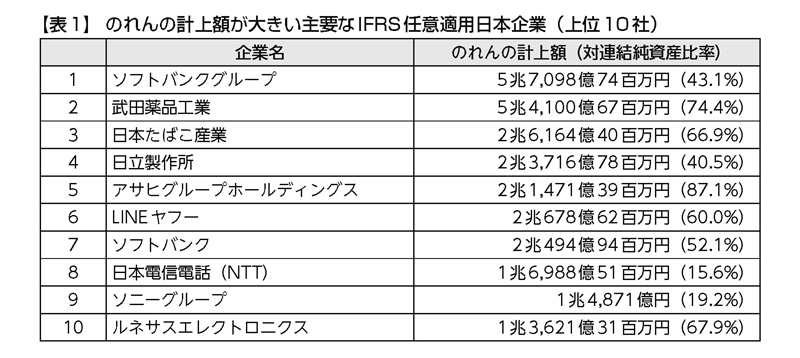
ソフトバンクグループと武田薬品工業によるのれんの計上額がいずれも5兆円超と群を抜いて大きく、3兆円台、あるいは4兆円台ののれんを計上しているIFRS任意適用日本企業はなかった。今回調査の対象とした主要なIFRS任意適用日本企業100社が連結貸借対照表上で計上したのれんの残高は合計で43.4兆円であったが、表1の企業10社の計上額は合計で26.9兆円に達しており、上位10社だけで調査対象企業全体の62%を占めていた。
次に主要なIFRS任意適用日本企業ののれんの計上額の分布を示すと、表2のとおりであった。全100社のうち、23社ののれん計上額が100億円未満であった(のれんを全く計上していない企業4社を含む。)。そして、のれんの計上額が1,000億円を超える企業は100社中53社と、過半数を若干上回る水準であった。
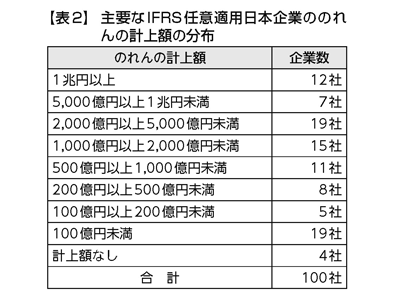
なお、2024年3月末日現在でのれんを計上していなかった主要なIFRS任意適用日本企業は、クレハ、中外製薬、豊田合成及び本田技研工業の4社であった。
次に、連結純資産に対するのれんの計上額の比率の分布を示すと、表3のとおりであった。
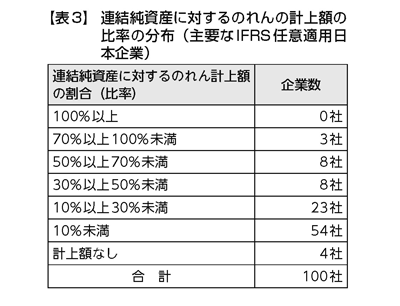
連結純資産に対するのれん計上額の割合が100%を超えたIFRS任意適用日本企業はなく、50%を超えた企業でみても、わずか11社に過ぎなかった。のれんの毎期定額償却を求められないために、日本企業の中ではのれんの計上額が一般的に大きいといわれるIFRS任意適用日本企業であっても、連結純資産に対するのれん計上額の比率が10%に満たない企業が全体の半分強(100社中の58社)を占めていることが分かる。
次に、今回調査の対象とした主要なIFRS任意適用日本企業100社のうち、2023年度においてのれんの減損損失を計上した企業は29社、計上額は合計で2,575億円であり、上位5社を列挙すると、表4のとおりであった。
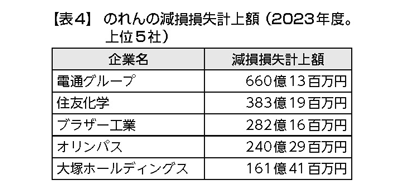
表4に掲載した各社のほか、事業の入れ替え、選択と集中が頻繁にあると考えられる大手総合商社などは、ほぼ毎期、10億円単位ののれんの減損損失を計上している。
のれんの減損損失計上額合計の2,575億円という金額は、のれんの残高合計(43.4兆円)と比較すると軽微ともいえるが、調査対象の100社のうち29社が減損損失を計上しているという事実は特記してよいと考えられる。
米国会計基準を適用する日本企業が計上したのれんの調査分析
のれんの計上額が大きい、米国会計基準を適用する日本企業を列挙すると、表5のとおりであった。また、表5では、のれん計上額の連結純資産に対する比率も併せて示している。米国会計基準を適用する日本企業の場合、のれんの計上額はそれなりに大きいが、さすがに我が国を代表する業界のリーディング・カンパニーが揃っているだけあって、連結純資産額がのれんの計上額をはるかに上回っていた。
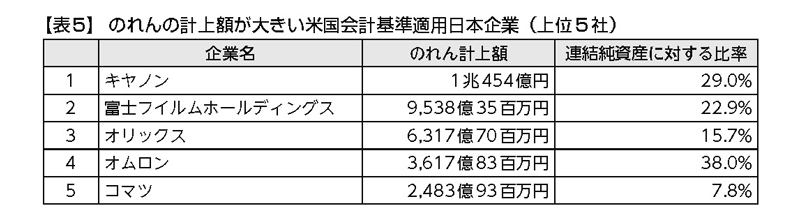
2020年3月期にはトヨタ自動車、2021年3月期からはソニーグループ、2022年3月期からはTDK、2023年3月期からはワコールホールディングス、2024年3月期からは村田製作所が米国会計基準からIFRSへ移行した。さらに、東芝は上場廃止となっている。歴史と伝統があり、かつては我が国における超一流企業のステータスでもあった米国会計基準を適用する日本企業の数は、ほぼ1年に1社のペースで櫛の歯が抜け落ちるように年々減少し、現在ではわずか6社(表5の5社及び野村ホールディングス)を残すのみとなっている。
日本の会計基準を適用する主要な日本企業が計上したのれんの調査分析
のれんの計上額が大きい、日本の会計基準を適用する主要な日本企業を列挙すると、表6のとおりであった。
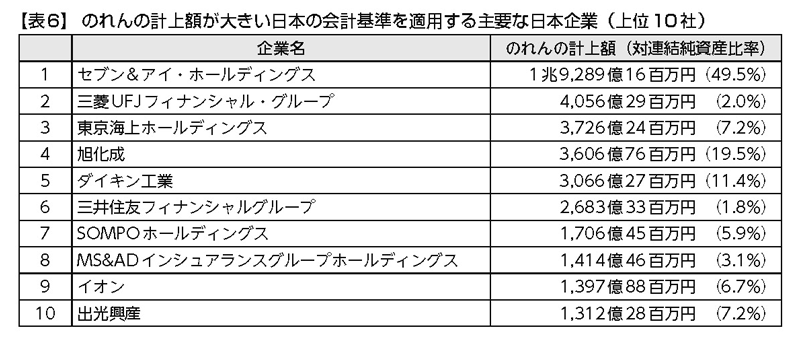
なお、参考のために各社ののれんの計上額の連結純資産に対する比率も併記しているが、セブン&アイ・ホールディングスを除けば、各社ともに20%に満たない水準であった。また、今回調査の対象とした日本の会計基準を適用する主要な日本企業100社ののれん計上額をすべて合計しても5兆519億円であり、IFRS任意適用企業で計上額が最も大きいソフトバンクグループ1社に及ばない水準であった。
また、1社当たりの平均計上額は505億19百万円であり、主要なIFRS任意適用日本企業(4,340億14百万円)の11.6%の水準であった。セブン&アイ・ホールディングスののれん計上額が飛び抜けて大きく、同社ののれん計上額を除くと、1社あたりの平均計上額は、312億円にまで低下することになる。
次に、日本の会計基準を適用する主要な日本企業各社ののれんの計上額の分布を一覧にすると、表7のとおりであった。
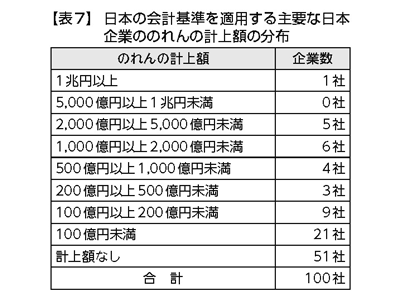
今回の調査分析の対象とした日本の会計基準を適用する主要な日本企業は、前述のように、株式時価総額で上位300位以内にランクインするような企業であり、日本を代表するような大企業が多いが、それでも、1,000億円以上ののれんを計上している会社が100社中わずかに12社であったのに対して、のれんの計上額が100億円未満の会社が21社、のれんを全く計上していない会社が過半数の100社中51社を占めていた。
なお、今回調査の対象とした、日本の会計基準を適用する主要な日本企業が2023年度において計上したのれんの減損損失は、100社の合計で50億円超(減損損失を計上した企業は5社)に過ぎなかった。IFRSとは異なり、日本の会計基準がのれんの毎期の定額償却を義務付けている影響が出たものと考えられる。
米国企業や欧州企業との比較
米国で上場する米国会計基準を適用する米国企業、IFRSを適用する欧州大陸で上場する欧州の企業、並びにIFRSを適用する英国で上場する欧州の企業のそれぞれについて、1社当たりののれん平均計上額を一覧にし、さらに主要なIFRS任意適用日本企業と日本の会計基準を適用する主要な日本企業のデータも追加して示すと、表8のとおりであった。なお、米国会計基準を適用する日本企業は数が少ないため(6社)に省略している。
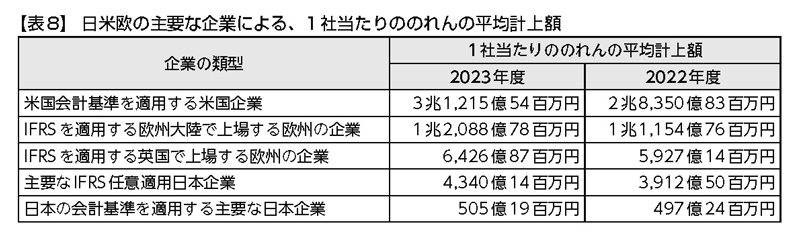
どの企業の類型も、2022年度に比べて2023年度はのれんの平均計上額が増加しているが、日本の会計基準を適用する主要な日本企業の伸び率が最も低くなっていた。
さらに、2023年度ののれんの計上額の分布について、日米欧の主要な企業を並べて一覧にすると、表9のとおりであった。
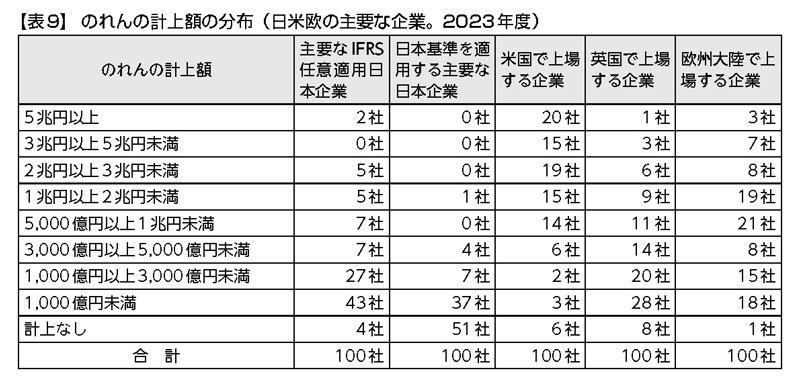
日本の会計基準を適用する主要な日本企業はもとより、のれんの定額償却を行わない主要なIFRS任意適用日本企業の場合であっても、のれんの計上額の水準は、ソフトバンクや武田薬品工業といったごく一部の企業を除けば極めて低いといえよう。また本稿前段でも調査したように、IFRS任意適用企業は、欧米の主要な企業と比較すると、「こまめに」減損処理を行い、過大なのれんが計上されることを適時に防いでいる傾向があるといえる。
コロナウイルス感染症が世界中を席巻し、経済活動が麻痺した一時期を除けば、世界中の主要な企業が計上するのれんの残高は増加の一途をたどっているが、前述のような要因により、日本企業が計上するのれんの金額は、欧米の企業と比較するとまだ全体的には抑えられており、企業結合による外部成長よりも内部成長を重視する傾向が強いといわれる我が国の経営者の気質が反映されているのではないかと考えられる。また、経済の回復に伴い、のれん残高の増加のペースが欧米の主要な企業で高まっている事実を目の当たりにすると、かねてより我が国の会計関係者が主張しているのれんの会計処理の見直し(非償却+減損テストを毎期定額償却に変更する)に向けた世界的な合意形成は、理論的にはともかく、実務的には極めて難しいと考えざるを得ない。
終わりに
2023年度における主要なIFRS任意適用日本企業による企業や事業の取得意欲は旺盛で、主要なIFRS任意適用日本企業全体で計上されているのれんの残高は、2023年度中に43兆円(11%)程度増加した。また、のれんの評価や減損が、監査上の主要な検討事項(KAM)として監査報告書に記載されるケースも多かった。また、今回の調査分析を行ったことによりあらためて分かったことは、日本の会計基準を適用する主要な日本企業が計上しているのれんの金額の少なさである。減損テストのみのIFRSや米国会計基準とは異なり、わが国の会計基準はのれんの毎期定額償却を求めているため、IFRS任意適用企業や米国会計基準を適用する企業に比べて、日本の会計基準を適用する主要な日本企業が計上しているのれんの残高が小さいであろうことはある程度事前に予想できたが、主要な企業100社のうち、のれんの残高が計上されている企業が半分未満の49社に過ぎないという結果には驚かされた。非常に雑駁な言い方にはなるが、「多額ののれんを計上しているような主要な日本企業の大半は、すでに日本の会計基準からIFRSに移行してしまった」ということが言えそうである。今回調査の対象とした、日本の会計基準を適用している主要な日本企業の顔ぶれを見ると、大手の金融機関(銀行、損害保険、生命保険)や小売業、不動産や建設業、鉄道、電力等のインフラ系の業種の企業がかなりの部分を占めていた。今回の調査対象とした日本の会計基準を適用している日本企業は、あくまでも株式時価総額が大きいごく一握りの「大企業」及び「収益性や将来性が高い企業」であり、日本の会計基準を適用する上場企業を網羅的に調査分析したものではない。今回の調査の対象外で、多額ののれんを計上している日本企業も存在するではあろうが、日本企業全体の傾向としては、おおむね前述のようなことが言えるものと考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























