解説記事2024年10月14日 第2特集 被相続人の兄弟姉妹の子、傍系卑属でも代襲相続は可能か(2024年10月14日号・№1047)
第2特集
最高裁が弁論、民法887条2項ただし書の解釈が争点
被相続人の兄弟姉妹の子、傍系卑属でも代襲相続は可能か
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したとき、被相続人の傍系卑属であっても代襲相続人となることができるか否かが争われた事件で、最高裁判所(渡辺惠理子裁判長)は10月1日、弁論を開いた。原審の東京高裁では、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書により、被相続人の傍系卑属であれば代襲相続人となることができるとの判断を示しているが、その判断が覆る可能性がでてきた。
ただし書では「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」
本件は、原告ら(X1、X2)が被相続人の死亡以前に亡くなっていた母(A)を代襲して被相続人の相続人になるとして、遺産である土地及び建物について、相続を原因とする所有権移転登記及び持分移転登記の各申請をしたところ、申請を却下する旨の決定が行われたため、原告らが本件処分は違法であるとして、その取消しを求めたものである。
原告らの母であるAは、原告らの出生後に、被相続人の母であるB(Aの叔母)と養子縁組をしたことにより、被相続人の妹となった(図表1参照)。相続人らの祖母とBとは姉妹であったため、養子縁組の前から相続人らは被相続人の5親等の傍系親族であった。なお、相続人らとB及び被相続人との間に養子縁組による新たな親族関係は生じていない。
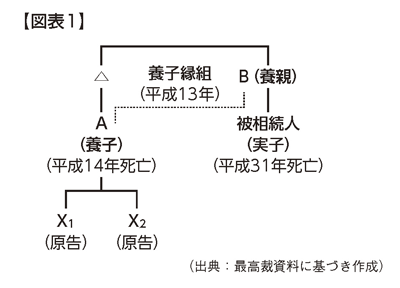
この裁判の争点は、被相続人の傍系卑属であれば代襲相続人となれるか否かである。原告らは、被相続人の妹の子であるが、民法889条2項は、同法887条2項を準用するところ、これによれば、被相続人の兄弟姉妹の子は、被相続人を代襲相続するものとされている。そして、被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続するためには、①相続開始以前に相続人(兄弟姉妹)が死亡するか、又は相続権を失っていることのほか、代襲相続人に求められることとして、②相続開始時に存在していること、③被代襲者の子であること、④被相続人との関係で欠格者でないことが必要とされている。原告らはこれらの要件は充足しているが、民法889条2項は、兄弟姉妹の子が代襲相続する場合について、同法887条2項ただし書の「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」という規定も準用しており、本件では、このただし書をどのように解釈するかが問題となっている。
原告らは、ただし書の「被相続人の直系卑属」を「被相続人の傍系卑属」又は「被相続人の血族」と読み替えるだけで足りると主張。一方、被告は、民法887条2項ただし書をこのように読み替えて準用するだけでは代襲相続人の範囲が拡すぎるとし、これらの者が少なくとも被相続人と被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の共通する親の直系卑属であることが必要であると主張している。
横浜地裁、共通する親の直系卑属であることが必要
1審の横浜地裁の判決(令和2年(行ウ)第53号)では、原告らの請求は棄却されている。
横浜地裁は、昭和37年改正前の民法889条2項によれば(図表2参照)、被相続人の兄弟姉妹の子である代襲相続人は、被代襲者(兄弟姉妹)の直系卑属であれば被相続人との関係を問題にすることなく代襲相続人になるという解釈がとり得たのに対し、改正後は、同法889条2項が同法887条2項ただし書をも準用することになったことにより、これらの者は、被代襲者(兄弟姉妹)の直系卑属であるだけでは足りず、被相続人との間でも一定の親族関係が必要になったということができると指摘。加えて、民法887条2項ただし書の趣旨は、被相続人の子の代襲相続の場合において、もともと被相続人と親族関係になり養子縁組前の養子(被代襲者)の子を代襲相続人から除外することにあり、養子縁組前の養子の子であっても、被相続人の直系卑属である者による代襲相続は認めるというものであると解されることからすれば、兄弟姉妹の代襲相続の場合には、同様に、養子縁組前の養子の子は代襲相続人から原則として除外されるが、被相続人の子の代襲相続人が問題になる場合に代襲相続人に求められる被相続人との親族関係(被相続人の直系卑属であること)に準ずる関係にある者として、代襲相続人が被相続人と被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の共通する親の直系卑属であることが必要であると解すべきであるとの判断を示し、登記申請を却下した本件処分は適法であるとした。
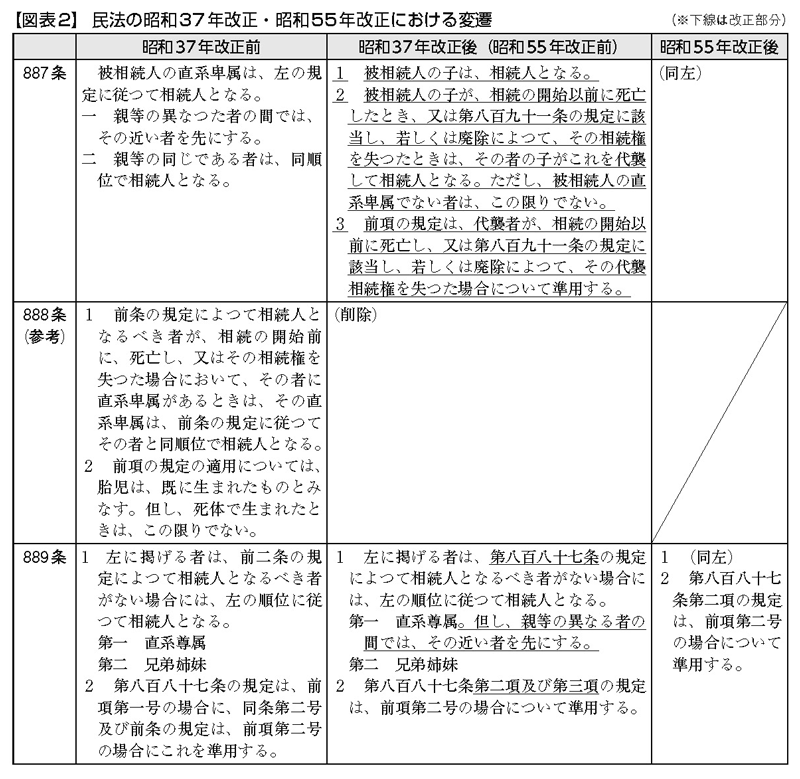
傍系卑属であれば代襲相続は可能、東京高裁では国が逆転敗訴
一転して2審の東京高裁の判決(令和4年(行コ)第146号)では、原判決が取り消され、国側が敗訴することになった。
東京高裁は、昭和37年の民法改正において、同法887条2項本文及びただし書が規定されて養子縁組前の養子の子について代襲相続を認めないことが明文化され、兄弟姉妹の代襲相続においても同項を準用する旨の規定が設けられたという経緯を踏まえると、同項ただし書の準用を認めた上で、当該規定の文言解釈として相当かつ合理的な範囲内で読み替えをするのが相当であると指摘。民法887条2項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」については、同法889条2項において兄弟姉妹の代襲相続に準用するに当たっては、「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であるとし、控訴人(1審の原告)らは、被相続人を代襲相続することができるとの判断を示した。
注目の判決期日は令和6年11月12日
今回、最高裁が弁論を開いたことで、この東京高裁の判決が覆る可能性がでてきた。弁論では、上告した国側は、横浜地裁の判決と同じく、代襲相続人が被相続人と被代襲者の共通する親の直系卑属であることが必要であると主張。代襲相続の範囲に傍系卑属を加えることになれば、相続人の範囲が拡がり、相続人の確定ができないなどのおそれがあると指摘している。
一方、被上告人(1審の原告)らは、代襲相続できないことになると、被相続人には相続人が存在しないことになると主張。相続が開始して5年間も土地等は放置され、被上告人らは被相続人の預貯金に手を付けられない状況という。令和6年11月12日に予定される最高裁の判決が注目される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























