解説記事2024年10月28日 第2特集 相続税、準備調査から着手まで当局は何をする?(2024年10月28日号・№1048)
第2特集
ネガティブチェック、聴取調査項目の事前照会……
相続税、準備調査から着手まで当局は何をする?
本特集では、相続税実地調査における準備調査から調査着手までの事務処理フローについて、東京国税局の資料に基づき紹介する。準備調査では「ネガティブチェックシート」を用いて課税価格等の減額要素を確認。事前通知から調査着手までの期間が長い事案では、「被相続人に関するお尋ね」等により聴取調査項目の事前書面照会を行うなどとしている。
Q
相続税の実地調査ではどのような事案が選定されますか。
A
相続税実地調査の対象事案は、追徴税額の最大化を図るため高額な追徴税額が見込まれる事案を選定し、統括官部門では指導育成対象職員一人当たり1件を目安に「特選事案」も選定しているようです。
また、無申告事案については、「相続税選定支援ツールRIN」に申告要否検討表回答内容、署内資料、局内保有情報及び照会回答等を入力して見込追徴税額を算出することで、より高額な追徴税額が見込まれる事案を選定するとしています。
なお、事案の担当者は、調査事務経験年数等に応じ、総遺産価額の階級を含む事案の内容、重加賦課見込の蓋然性などを勘案して決定されます。
Q
相続税実地調査における準備調査はどのように行われますか。
A
調査事案を担当者に交付する際、統括官等は、臨宅調査までの投下日数を示して準備調査を指示し、問題点、重加賦課見込の蓋然性、事案のポイント、調査実施上の留意点などを説明します。準備調査では、統括官等の助言・指示事項を踏まえ、土地や株式評価の適否の検討及び各種資料情報を念査し、把握した要調査項目等を「相続税準備調査書」に記載するとともに、「ネガティブチェックシート」(16頁表参照)を活用して課税価格等の減額要素を確認します。
なお、①文書照会に未回答の金融機関等に対する督促、②取引内容の解明が必要な金融機関等に対して文書照会を実施していない場合の追加照会については、把握した都度、速やかに実施するとしています。
準備調査から調査着手までの事務処理フローは、図を参照。
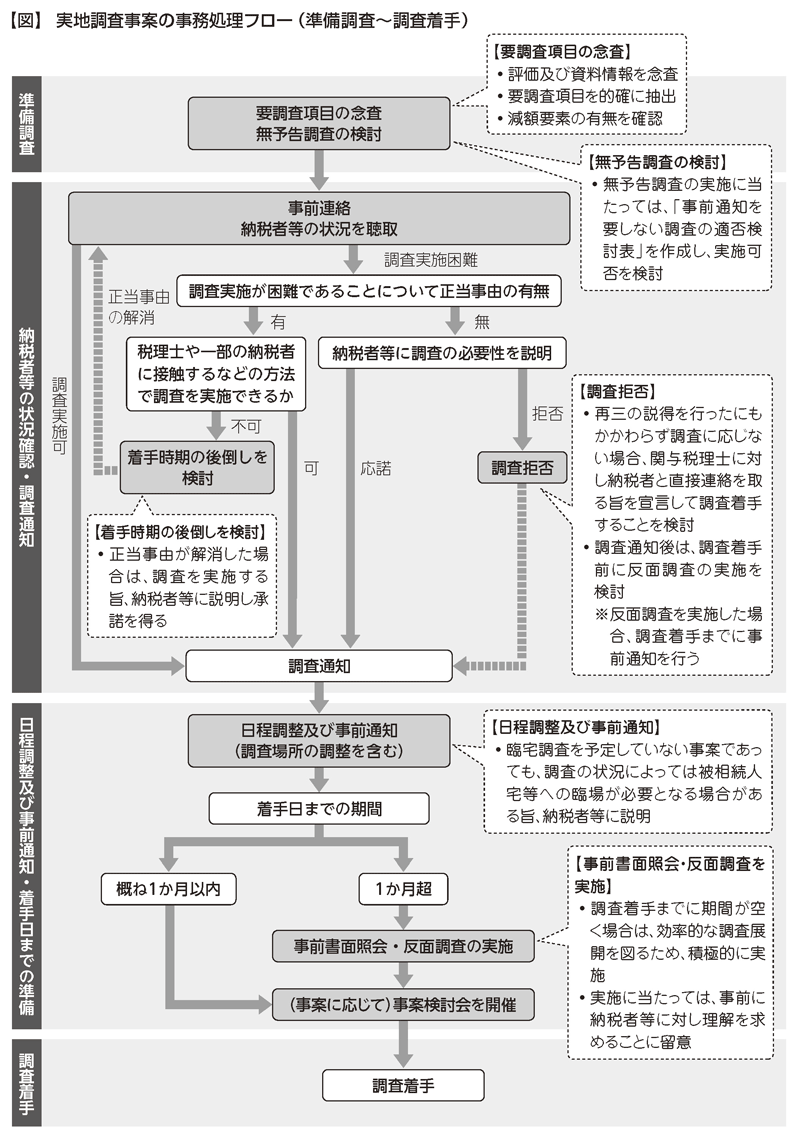
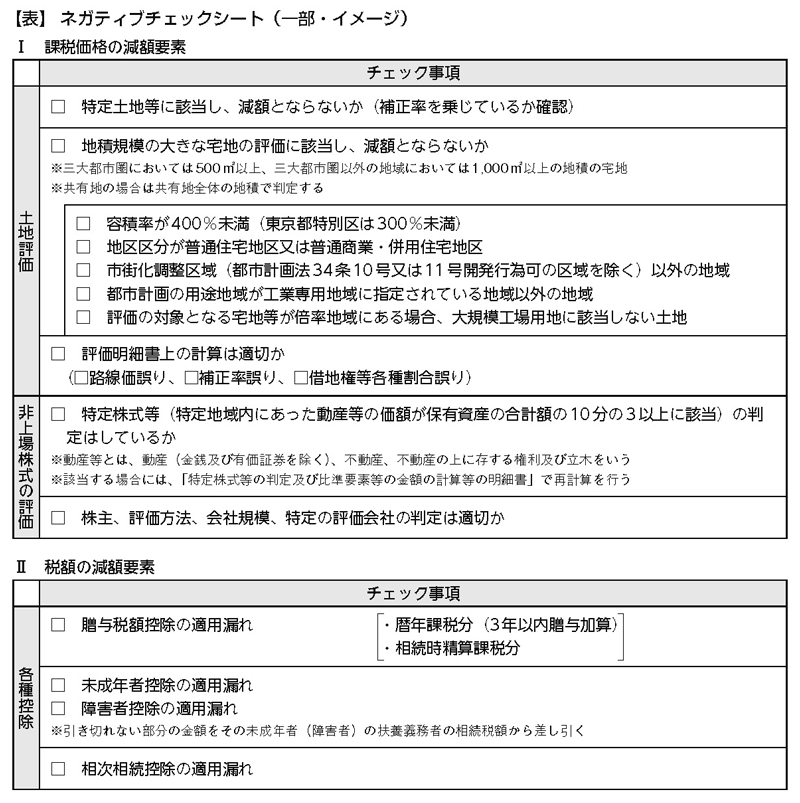
Q
事前通知等を電話で実施することが困難な場合の対応は?
A
電話による事前通知が困難な場合(①署内簿書等から電話番号が確認できない者、1週間程度の間、曜日、時間帯を変えて複数回電話しても連絡が取れない者)、統括官等は調査担当者に「連絡依頼票(臨場用)」を調査対象者の自宅又は事業所(納税地等)に差し置くよう指示します(納税地等が遠隔地にあるなど調査に支障をきたす場合は「連絡依頼票(郵送用)」を納税地等に郵送)。
なお、差し置き等を3回以上実施しても調査対象者から応答がない場合は、調査関係通達5−10(2)に該当するとして、「事前通知を要しない調査の適否検討表」が作成されます。
Q
事前通知から着手日までの期間が長い場合の対応は?
A
日程調整の結果、調査着手までに期間が空く(1か月超)事案では、「被相続人に関するお尋ね」「相続人に関するお尋ね」による聴取調査項目の事前書面照会や反面調査が実施されるケースもあるようです。
「被相続人に関するお尋ね」では、住所移転状況、職歴、趣味し好、病歴など、「相続人に関するお尋ね」では、被相続人からの過去の財産受贈状況、被相続人との貸借状況などが確認されます。
(参考)
| 〈被相続人に関するお尋ね:確認事項〉 住所移転状況(年月、住所、所有状況等(持ち家、賃貸、老人ホーム等の施設、親族宅))/職歴(年月、勤務先名・所在地、最終役職)/趣味し好等(国内旅行、海外旅行、ゴルフ、収集(書画・骨とう・貴金属・その他)等)/被相続人が生前に親族等から相続によって取得した財産等(亡くなられた親族等、相続した財産(不動産、上場株式、その他の株式(非上場を含む)、現金・預貯金、保険金、債務など)、相続税申告の有無、相続税申告書等の保管の有無)/病歴等(入院期間、入院先、病名、医療費を負担した方、医療費の支払方法、入院中に財産管理した方)/遺言書の有無等(遺言書の有無、遺産分割の方法(遺言書どおりに分割、遺産分割協議を行い分割、遺産分割協議中(係争中を含む))/相続財産の保管場所等 〈相続人に関するお尋ね:確認事項〉 住所移転状況/職歴/被相続人からの過去の財産受贈状況(受贈年月、受贈財産、受贈金額、受贈理由、贈与税申告の有無)/被相続人との貸借状況(貸借区分(貸付・借入)、貸借金額、貸借理由、返済方法、貸借残高、契約書の有無) |
Q
調査着手前には事案検討会が開催されるようですね。
A
実地調査に当たり着手する事案への理解を深めるため、①調査経験1・2年目職員の担当事案、②特選事案、③その他、特に特官・統括官等が必要と認める事案(重加賦課見込事案、要更正見込事案、調査困難事案等)については、調査着手前に事案検討会が開催されます。
特に、不正が想定される事案(特選事案を含む)や取引が複雑で解明を要する事案については、審理担当者等を交え、重加賦課要件を満たすために必要な証拠の収集・保全や質問応答記録書の作成を念頭に置いた調査先におけるシミュレーションが行われます。
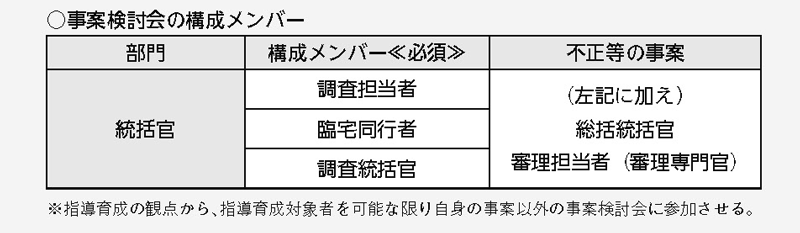
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























