解説記事2024年11月04日 特別解説 日本企業による会計監査人交代の理由(臨時報告書における開示例) その1(2024年11月4日号・№1049)
特別解説
日本企業による会計監査人交代の理由(臨時報告書における開示例) その1
はじめに
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされており、当該定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、会計監査人は定時株主総会において再任されたものとみなされる(会社法第328条)。これまで会計監査人が交代した場合、我が国では臨時報告書において適時開示が行われてきたが、会計監査人交代の理由が、「任期満了」といった形式的な記載にとどまり、「本音ベースの理由」が外部からは分からなかった。そこで、金融庁は2019年6月に企業内容等開示ガイドライン(以下、「ガイドライン」)を改正し、臨時報告書に会計監査人が異動した実質的な理由が記載されるよう、具体的な交代理由を例示している(企業内容等開示ガイドラインB基本ガイドライン(監査公認会計士等の異動理由及び経緯)24の5−23−21)。そして、実質的な異動の理由として、以下のようなものが挙げられている。
① 連結グループでの監査公認会計士等の統一
② 海外展開のため国際的なネットワークを有する監査公認会計士等へ異動
③ 監査公認会計士等の対応の適時性や人員への不満
④ 監査報酬
⑤ 継続監査期間
⑥ 監査期間中に直面した困難な状況
⑦ 会計・監査上の見解相違
⑧ 会計不祥事の発生
⑨ 企業環境の変化等による監査リスクの高まり
⑩ その他異動理由として重要と考えられるもの
開示ガイドラインは、2019年6月21日付で公布・施行された。ガイドラインの施行からは5年以上が経過したが、本稿では、2回に分けて、2019年6月21日以後、2024年9月末日までに提出された臨時報告書(会計監査人の交代に関するもの)についての全体的な傾向等を調査分析するとともに、2023年10月1日以後2024年9月末日までの直近の1年間に会計監査人の交代に踏み切った各社が、臨時報告書において開示した会計監査人交代に関する理由や経緯等に関する特徴的な事例を紹介することとしたい。
調査対象とした企業
本稿では、2019年6月21日以降、2024年9月30日までに提出された臨時報告書(会計監査人の交代に関するもの)のべ968社を調査対象とした(制度が改正されてから5年強の間に、会計監査人が複数回交代した企業も存在するため、「のべ〇社」と表現している。)。
全般的な分析
今回の調査の対象とした、臨時報告書を提出した企業(のべ968社)の市場区分等を示すと、表1のとおりであった。2022年4月4日より、東京証券取引所(東証)が市場区分の再編を行ったため、表1も再編前と再編後とに分けて記載している。一目瞭然であるが、旧ジャスダック市場や旧マザーズ市場、現在では主にスタンダード市場やグロース市場に上場する中堅の上場企業や新興の上場企業が、より頻繁に会計監査人の交代を行っている(あるいは、会計監査人が交代せざるを得ないような状況に置かれた)ことが分かる。
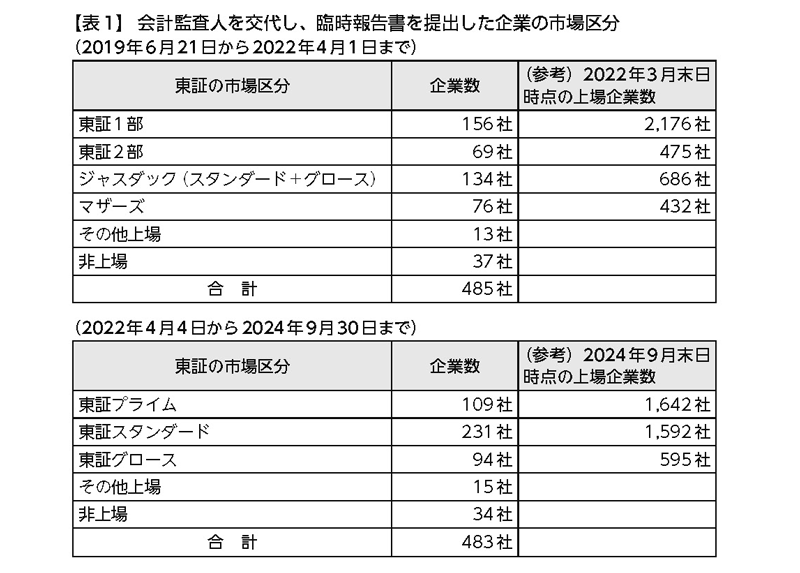
次に、調査対象とした企業が会計監査人の交代を行った時期(臨時報告書を提出した時期)を示すと、表2のとおりであった。
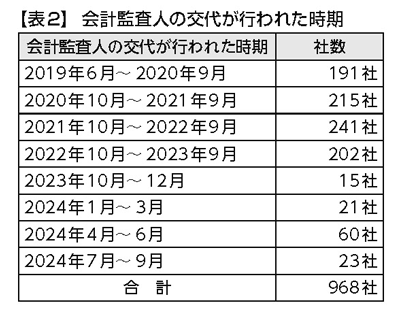
我が国の上場企業の決算期は3月である場合が多く、(会計監査人が選任される)株主総会は6月に開催されるため、必然的に会計監査人の交代に関する開示は毎年4月から6月にかけての期間に多く見られることになる。
1年というスパンで見ると、2019年度から2022年度までは年間200社強のペースで会計監査人の交代に関する開示が行われていたが、2023年度(2023年10月~2024年9月)に行われた会計監査人の交代は、これまでの半数強である119件にとどまった。
これまでに行われた会計監査人の交代について、前任監査人(上場会社との監査契約を解除した監査法人)と後任監査人(上場会社との監査契約を新たに獲得した監査法人)の属性を一覧に示すと、表3のようになった。
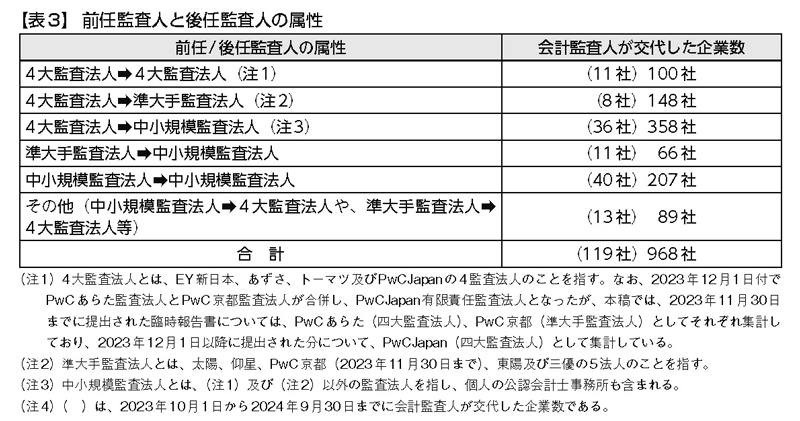
2020年3月期から有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」の「会計監査の状況」において会計監査人の継続監査期間に関する開示が始まったこともあり、制度が改正された当初の2019年6月から2020年6月頃までは、キヤノン、味の素、大和ハウス工業などの我が国を代表する大企業が、継続監査期間の長期化等を理由に、会計監査人を(4大監査法人から他の4大監査法人に)交代させる事例が目についたが、それ以後は、主に中堅規模以下の上場企業や新興の上場企業に対して4大監査法人が監査工数の増加等を理由として高額の監査報酬を提示し、それに耐えられなくなった上場企業が、規模に見合った報酬水準の準大手、あるいは中小規模監査法人を会計監査人として新たに選任するケースが目立つようになった。この傾向は、現在に至るまで続いていると言ってよいが、2023年10月以降は、4大監査法人による中堅上場企業との監査契約解除のラッシュが落ち着きつつあり、件数が減少してきている。また、中小規模監査法人から他の中小規模監査法人に上場企業の監査契約が移る事例も少なくないが、中小規模監査法人から準大手監査法人や4大監査法人に会計監査人が交代するような事例は、一部の例外を除くと少ない。今回調査の対象とした968社について、前任監査人(監査契約の解除)と後任監査人(監査契約の新規締結)の件数が多い上位の監査法人を列挙すると、それぞれ表4及び表5のとおりであった。
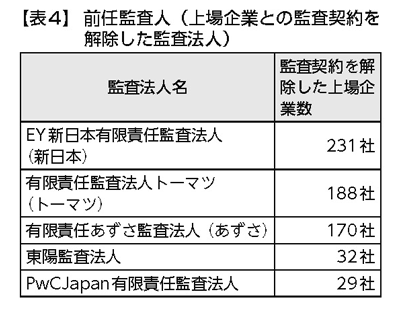
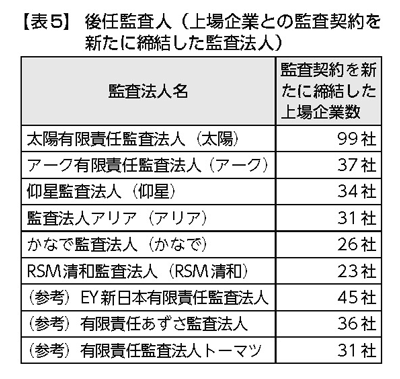
4大監査法人を構成するEY新日本、トーマツ及びあずさが多数の上場企業との監査契約を多数解除したことが一目瞭然である。後任監査人としては、準大手監査法人トップの太陽有限責任監査法人(太陽)の積極的な受注姿勢が目立つ。2024年6月末日現在、太陽の被監査上場企業(金融商品取引法・会社法監査の対象企業)数は350社となっている。
しかしながら、後述するように、太陽は被監査会社であった株式会社ディー・ディー・エスの平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第三四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類並びに令和4年3月第一四半期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したとして、金融庁から懲戒処分を受けた。当該懲戒処分には、契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(令和6年1月1日から同年3月31日まで)という項目が含まれており、この影響もあって、令和6年(2024年)に入ってからは上場会社の監査契約の新規獲得のペースに急ブレーキがかかっている。
太陽と同じく準大手監査法人の一角を形成する仰星監査法人は34社の上場企業の監査契約を新たに獲得し、中小規模監査法人のアーク、アリア及びRSM清和監査法人も上場企業との監査契約数を大きく伸ばしている。また、2020年10月に設立されたかなで監査法人は、2022年10月から2023年9月末日までの1年間に、10社を超える上場企業の監査業務を獲得し、その後も高水準の受注を続けている。4大監査法人を構成するEY新日本、あずさ及びトーマツは、一定数の上場企業の監査契約を新たに受嘱してはいるものの、その内容は大まかにいうと超大企業、IFRS任意適用企業、金融機関(非上場の金融機関も含む)及びグループ内監査人の統一に伴う受嘱等にほぼ限られている。
次に、調査対象の上場企業が会計監査人の交代に踏み切った主な理由を、企業内容等開示ガイドラインで列挙された項目(一部項目を追加)に即して分類すると、表6のとおりであった。
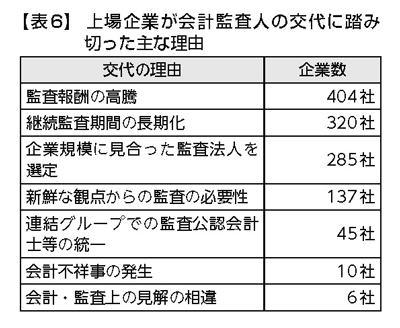
会計監査人交代の理由として複数の項目を列挙している企業については、それぞれの項目で1社としてカウントしているため、「企業数」の合計は調査対象の企業数(のべ968社)を上回っている。予想されたことではあるが、会計監査人から監査工数の増加等を理由として高額な監査報酬を提示されたことと、継続監査期間の長さ(あるいはその両方)を理由として会計監査人の交代に踏み切った企業が大部分を占めた。また、監査報酬の高騰を会計監査人交代の主な理由とした企業は、「事業規模に見合った監査法人を新たに選定した。」旨、継続監査期間の長期化を会計監査人交代の主な理由とした企業は、「新鮮な観点からの監査の必要性」を合わせて理由として開示している場合が多かった。
会計監査人が交代した企業の継続監査期間の平均値の推移
会計監査人が交代した企業の継続監査期間の平均値を時系列で示すと、表7のとおりであった。
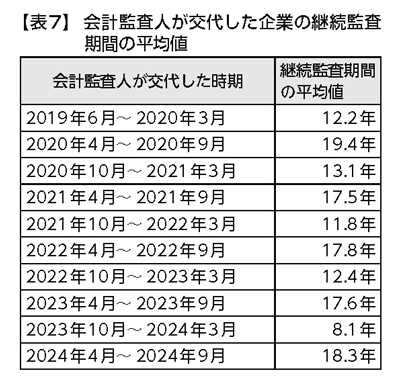
どの年度も、10月から3月までの期間に会計監査人が交代した企業よりも、4月から9月までの期間に会計監査人が交代した企業の方が、継続監査期間が平均で5~10年長いという結果が出た。前述したように、4月から9月までの期間に会計監査人が交代した企業は、3月決算の企業で、かつ6月の定時株主総会で会計監査人が交代した事例が多いのに対し、10月から3月までの期間に会計監査人が交代した企業の場合は、7月決算から12月決算までの企業の会計監査人が各社の定時株主総会で任期満了により交代した事例が一定数ある一方で、会計上の不祥事や見解の相違等の理由により、3月決算の上場企業において、期の途中で会計監査人が交代した事例も少なからず存在していた。そのような企業の場合には、一般的に上場以後の期間や会計監査を受けている歴史が浅い新興企業が多く、かつ、継続監査期間が短くなる(会計監査人が頻繁に交代する)傾向があるため、このような傾向が表れたものと考えられる。
次に、会計監査人の交代の時期が2019年6月から2021年9月まで、2021年10月から2023年9月まで、及び2023年10月から2024年9月までの区分で会計監査人の継続監査期間の分布を示すと、表8のとおりであった。
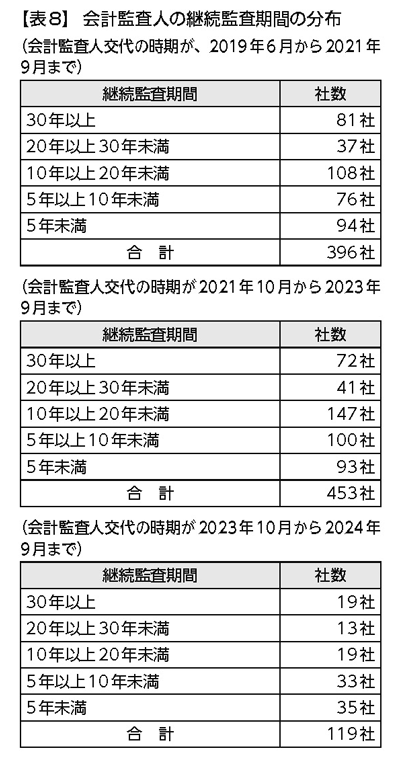
これまでは、継続監査期間が「10年以上20年未満」という期間が一番のボリュームゾーンであったが、直近の2023年10月から2024年9月までの期間については、継続監査期間が5年未満というカテゴリーに属する企業が最も多く、「5年以上10年未満」の企業も、「10年以上20年未満」の企業数を大きく上回っていた。前述の表7でも、2023年10月から2024年3月までの間に会計監査人が交代した企業の平均監査期間が8.1年とこれまでに比べて極めて短くなっている。今回調査の対象とした2023年10月から2024年9月までの期間においては、短期間で会計監査人を交代させた(あるいは、「交代させざるを得なかった」)企業がかなり多かったと言える。
監査法人に対する金融庁の処分
本誌No.1012(2024.1.29号)の同種の解説において、2023年1月から6月までの間に中小規模監査法人に対して金融庁の処分が3件(いずれも業務改善命令)下されたことを記載したが、2023年12月26日に、準大手監査法人である太陽有限責任監査法人に対して、金融庁から下記の処分が下された。
・契約の新規の締結に関する業務の停止 3か月
(令和6年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善。)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3か月
(令和6年1月1日から同年3月31日まで)
・併せて、同日、約9,600万円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定
さらに、2024年9月6日付で、爽監査法人(中小規模監査法人)に対し、公認会計士・監査審査会が検査結果に基づく勧告を行った。金融庁による処分の有無及びその内容は現在検討中と思われるが、公認会計士・監査審査会による「爽監査法人に対する検査結果に基づく勧告について」においては、「同監査法人の運営は、著しく不当なものと認められる。」とされていることから、業務改善命令等の何らかの処分が、今後金融庁から下される可能性が高いと思われる。
終わりに
今回は、臨時報告書における制度の改訂(会計監査人交代の理由の開示)がなされた後、現在に至るまでの5年強の間に提出された臨時報告書を題材として、会計監査人の交代やその理由に関する全般的な傾向の調査分析を行った。次回は、2023年10月から2024年9月末日までの間に提出された臨時報告書で開示された会計監査人交代の理由や経緯等のうち、特徴的な個別の事例を取り上げて、紹介することとしたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























