解説記事2024年11月18日 新会計基準解説 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の概要(下)(2024年11月18日号・№1051)
新会計基準解説
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の概要(下)
企業会計基準委員会 ディレクター 村瀨進吾
企業会計基準委員会 専門研究員 福江東晶
Ⅲ リース会計基準等(脚注1)の概要(承前)
6 貸手のリースの会計処理
貸手の会計処理については、リースの定義及びリースの識別並びに企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)との整合性を図る点を除き、基本的に企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第16号」という。)を踏襲している。
(1)リースの分類
貸手は、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースとに分類する(リース会計基準第43項)。また、貸手は、ファイナンス・リースについて、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースとに分類する(リース会計基準第44項)。
(2)ファイナンス・リースに係る会計処理
貸手は、ファイナンス・リースについて、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う(リース会計基準第45項)。
リース会計基準等では、ファイナンス・リースの会計処理について、収益認識会計基準において対価の受取時にその受取額で収益を計上することが認められなくなったことを契機としてリースに関する収益の計上方法を見直した結果、企業会計基準適用指針第16号で定められていた「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法」を廃止している。
① 所有権移転外ファイナンス・リース
貸手として行ったリースが所有権移転外ファイナンス・リースと判定される場合、貸手は、事業の一環で行うリースについて取引実態に応じ、次の(ア)又は(イ)のいずれかの会計処理を行う(リース適用指針第71項)。
(ア)製造又は販売を事業とする貸手が当該事業の一環で行う所有権移転外ファイナンス・リース
(i)リース開始日に、貸手のリース料からこれに含まれている利息相当額を控除した金額で売上高を計上し、同額でリース投資資産を計上する。また、原資産の帳簿価額により売上原価を計上する。原資産を借手の使用に供するために支払う付随費用がある場合、当該付随費用を売上原価に含める。
ただし、売上高と売上原価の差額(以下「販売益相当額」という。)が貸手のリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、原資産の帳簿価額(付随費用がある場合はこれを含める。)をもって売上高及び売上原価とし、販売益相当額を利息相当額に含めて処理することができる。
(ii)各期に受け取る貸手のリース料(以下「受取リース料」という。)を利息相当額とリース投資資産の元本回収とに区分し、前者を各期の損益として処理し、後者をリース投資資産の元本回収額として会計処理を行う。
(イ)製造又は販売以外を事業とする貸手が当該事業の一環で行う所有権移転外ファイナンス・リース
(i)リース開始日に、原資産の現金購入価額(原資産を借手の使用に供するために支払う付随費用がある場合は、これを含める。)により、リース投資資産を計上する。
(ii)受取リース料の会計処理は、上記(ア)(ii)と同様とする。
また、貸手は、事業の一環以外で行う所有権移転外ファイナンス・リースについて、次の会計処理を行う(リース適用指針第72項)。
(ア)リース開始日に、貸手のリース料からこれに含まれている利息相当額を控除した金額と原資産の帳簿価額との差額を売却損益として計上し、貸手のリース料からこれに含まれている利息相当額を控除した金額でリース投資資産を計上する。原資産を借手の使用に供するために支払う付随費用がある場合、当該付随費用を含めて売却損益に計上する。
ただし、当該売却損益が貸手のリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、当該売却損益を利息相当額に含めて処理することができる。
(イ)受取リース料の会計処理は、製造又は販売を事業とする貸手が当該事業の一環で行う所有権移転外ファイナンス・リースの(ア)(ii)と同様とする。
② 所有権移転ファイナンス・リース
所有権移転ファイナンス・リースに係る基本となる会計処理は、所有権移転外ファイナンス・リースと同様とする。この場合、「リース投資資産」は「リース債権」と読み替える(リース適用指針第78項)。
貸手における利息相当額の総額は、貸手のリース料及び見積残存価額(脚注2)の合計額から、これに対応する原資産の取得価額を控除することによって算定する。当該利息相当額については、貸手のリース期間にわたり、原則として、利息法により配分する(リース会計基準第47項並びにリース適用指針第73項及び第79項)。ただし、リースを主たる事業としていない企業においては、所有権移転外ファイナンス・リースに重要性が乏しいと認められる場合、利息相当額の総額を貸手のリース期間中の各期に定額で配分することができる(リース適用指針第74項)。
(3)オペレーティング・リース
企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「企業会計基準第13号」という。)では、オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことのみを定めていた。リース会計基準等では、貸手のオペレーティング・リースは、通常、貸手のリース期間にわたり時の経過とともに収益を計上することが取引実態を表すと考えられるため、原則として定額法により収益を計上することを明らかにしている。また、無償賃貸期間(例えば、フリーレントやレントホリデー)に関する会計処理を明確にし、収益認識会計基準との整合性を図っている。
具体的には、貸手は、オペレーティング・リースによる貸手のリース料について、貸手のリース期間にわたり原則として定額法で計上する。ただし、貸手が貸手のリース期間について、解約不能期間に再リース期間を加えて決定する方法による場合に、当該貸手のリース期間に無償賃貸期間が含まれるときは、貸手は、契約期間における使用料の総額(ただし、将来の業績等により変動する使用料を除く。)について契約期間にわたり計上する(リース適用指針第82項)。
ここで、「貸手のリース料」の定義では、貸手のリース料には、将来の業績等により変動する使用料を含まないとしている(リース会計基準第23項)。これは、企業会計基準適用指針第16号では、リース料が将来の一定の指標(売上高等)により変動するリース取引などが取り扱われていなかったことを受けて、当該取扱いを踏襲することを意図したものである。したがって、貸手においては、市場における賃料の変動を反映するように当事者間の協議をもって見直されることが契約条件で定められているリース料(リース適用指針第24項)は、将来の業績等により変動する使用料に含まれず、貸手のリース料に含まれると考えられる。
7 セール・アンド・リースバック取引
「セール・アンド・リースバック取引」とは、売手である借手が資産を買手である貸手に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリース(以下「リースバック」という。)する取引である(リース適用指針第4項(11))。
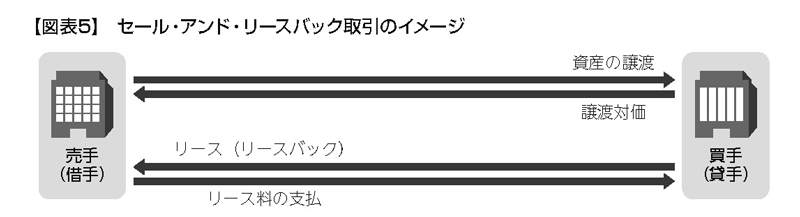
資産の譲渡とリースバックは形式上別個の取引であるが、これらの取引が組み合わされることで、次のような論点が生じる可能性があると考えられる。
(1)リースバックにより、売手である借手が、買手である貸手に譲渡された資産から生じる経済的利益を引き続き享受しているにもかかわらず、当該資産を譲渡した時点で譲渡に係る損益が認識される。
(2)セール・アンド・リースバック取引においては、資産の譲渡とリースバックが、パッケージとして交渉されることが多く、資産の譲渡対価とリースバックにおける借手のリース料との間に相互依存性があると考えられる。資産の譲渡対価及び関連するリースバックにおける借手のリース料が、それぞれ時価及び市場のレートでのリース料よりも高い(低い)金額で取引されることにより、一体としての利益の総額が同じであっても、資産の譲渡に係る損益が過大(過小)に計上される可能性がある。
リース会計基準等では、上記(1)の論点への対応としてセール・アンド・リースバック取引における資産の譲渡の取扱いを、上記(2)の論点への対応として資産の譲渡損益を適切に計上するための取扱いをそれぞれ定めている。
① セール・アンド・リースバック取引における資産の譲渡の取扱い
IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)においては、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」により収益が認識されると判断される場合、買手である貸手に移転された権利部分については権利の譲渡に係る利得又は損失を譲渡時に認識し、リースバックにより売手である借手が継続して保持する権利部分については権利の譲渡に係る利得又は損失を繰り延べることとされている。
これに対して、米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」(以下「Topic 842」という。)においては、売手である借手のリースバックがファイナンス・リースである場合、売手である借手が、譲渡した資産を直ちに買い戻していることと実質的に異ならず、売手である借手による資産の譲渡を資産の売却とすることが適切ではないとされる一方で、資産の譲渡がTopic 606「顧客との契約から生じる収益」(以下「Topic 606」という。)の収益認識要件を満たす場合には、収益をTopic 606の取引価格で測定して、原資産の認識を中止、すなわち、譲渡損益の全額を認識し、リースバックについては、オペレーティング・リースとして会計処理を行うこととされている。
IFRS第16号における会計上の考え方とTopic 842における会計上の考え方を比較衡量した結果、次の(ア)及び(イ)の理由により、Topic 842の定めを参考にセール・アンド・リース・バック取引に該当する場合の会計処理を定めることとした。
(ア)IFRS第16号の定めと同様の定めをリース会計基準等に含めた場合、資産の譲渡について収益認識会計基準などの他の会計基準等の定めにより損益を認識すると判断される場合であっても、当該資産の譲渡に係る損益の調整を求めることになり、収益認識会計基準などの他の会計基準等の考え方とは異なる考え方を採用することとなる。
(イ)IFRS第16号においては、リースバックにより売手である借手が継続して保持する権利に係る利得又は損失は売却時に認識しないため売却損益の調整が必要となる分、Topic 842のモデルよりも複雑となる可能性があると考えられる。
具体的には、セール・アンド・リースバック取引に該当する場合、次の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすときは、売手である借手は、当該セール・アンド・リースバック取引について資産の譲渡とリースバックを一体の取引とみて、金融取引として会計処理を行うこととし、そうではない場合には売手である借手は、資産の譲渡について収益認識会計基準などの他の会計基準等に従い損益を認識し、リースバックについてリース会計基準等に従い借手の会計処理を行うこととしている(リース適用指針第55項及び第56項)。
(ア)収益認識会計基準などの他の会計基準等に従うと売手である借手による資産の譲渡が損益を認識する売却に該当しない。
(イ)収益認識会計基準などの他の会計基準等に従うと売手である借手による資産の譲渡が損益を認識する売却に該当するが、リースバックにより、売手である借手が資産からもたらされる経済的利益のほとんどすべてを享受することができ、かつ、資産の使用に伴って生じるコストのほとんどすべてを負担することとなる。
② 資産の譲渡損益を適切に計上するための取扱い
収益認識会計基準では独立販売価格に基づく取引価格(対価)の配分を定めており、リース会計基準等においてもリースを構成する部分とリースを構成しない部分への対価の配分について独立販売価格に基づく配分を求めることとしている。これらの取扱いと整合するように、セール・アンド・リースバック取引において、資産の譲渡対価が明らかに時価ではない場合又は借手のリース料が明らかに市場のレートではない場合、当該資産の時価又は市場のレートでのリース料により譲渡損益を計上する定めを置くこととした(リース適用指針第57項)。
③ セール・アンド・リースバック取引に該当するかどうかの判断
我が国では、建設工事請負契約と一括借上契約が同時に締結される取引などにおいて、収益が一定の期間にわたり認識される場合、セール・アンド・リースバック取引の定めが適用されるか否かについて論点になり得るとの意見が聞かれた。この点、IFRS第16号においては、セール・アンド・リースバック取引の定めが適用される範囲、特に収益が一定期間にわたり認識される場合であってもセール・アンド・リースバック取引の定めが適用されるのか否かについて明確にされていない。
この論点について検討を行った結果、資産の譲渡により売手である借手から買手である貸手に支配が移転されるのは仕掛中の資産であり、移転された部分だけでは資産の使用から生じる経済的利益を享受できる状態にないのに対して、リースバックにより売手である借手が支配を獲得する使用権資産は、完成した資産に関するものであることから、譲渡された資産とリースされた資産は同一ではないと考えられるため、リース会計基準等では、セール・アンド・リースバック取引に該当するか否かを検討する対象となる資産の譲渡とリースバックにおいて、売手である借手による資産の譲渡が次の(ア)又は(イ)のいずれかである取引については、セール・アンド・リースバック取引として取り扱わないこととしている(リース適用指針第53項)。
(ア)収益認識会計基準に従い、一定の期間にわたり充足される履行義務(収益認識会計基準第36項)の充足によって行われる場合
(イ)企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第95項を適用し、工事契約における収益を完全に履行義務を充足した時点で認識することを選択する場合
8 サブリース取引
(1)基本となる会計処理
「サブリース取引」とは、原資産が借手から第三者にさらにリース(以下「サブリース」という。)され、当初の貸手と借手との間のリースが依然として有効である取引をいう。また、当初の貸手と借手との間のリースを「ヘッドリース」、ヘッドリースにおける借手を「中間的な貸手」という(リース適用指針第4項(12))。
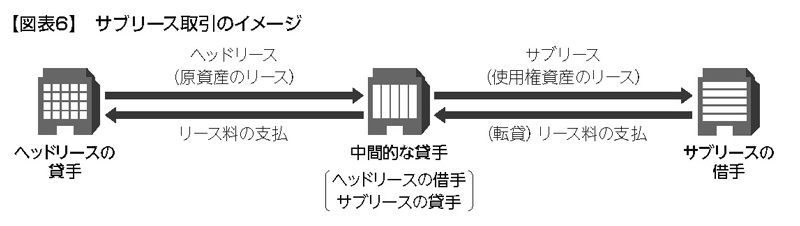
サブリース取引については、ヘッドリースとサブリースの契約は一般的に別個に交渉されており、中間的な貸手にとってヘッドリースから生じる義務は、一般にサブリースの契約条件によって消滅することはないことから、リース会計基準等では、IFRS第16号と同様に、原則として、ヘッドリースとサブリースを2つの別個の契約として借手と貸手の両方の会計処理を行うこととしている。
サブリースがファイナンス・リースに該当する場合、サブリースのリース開始日に、次の会計処理を行う(リース適用指針第89項(1))。
① サブリースした使用権資産の消滅を認識する。
② サブリースにおける貸手のリース料の現在価値と使用権資産の見積残存価額の現在価値の合計額でリース投資資産又はリース債権を計上する。
③ リース投資資産又はリース債権の計上及び使用権資産の取崩しに伴う損益は、原則として純額で計上する。
一方、サブリースがオペレーティング・リースに該当する場合、サブリースにおける貸手のリース期間中にサブリースから受け取る貸手のリース料について、オペレーティング・リースの会計処理を行う(リース適用指針第89項(2))。
ここで、IFRS第16号においては、サブリース取引に係る基本的な会計処理に対する例外は設けられていないが、リース会計基準等では、サブリース取引に係る会計処理の例外的な定めとして、中間的な貸手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合の取扱いと転リース取引の取扱いを定めている。
(2)中間的な貸手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合
我が国の不動産取引において、法的にヘッドリースとサブリースがそれぞれ存在する場合であっても、中間的な貸手がヘッドリースとサブリースを2つの別個の契約として借手と貸手の両方の会計処理を行い、貸借対照表において資産及び負債を計上することが取引の実態を反映しない場合があるとの意見が聞かれた。
審議の結果、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で我が国における例外的な取扱いを定めることとし、リース会計基準等では、中間的な貸手は、次の要件をいずれも満たす取引について、貸借対照表においてヘッドリースにおける使用権資産及びリース負債を計上せず、かつ、損益計算書においてサブリースにおいて受け取るリース料の発生時又は当該リース料の受領時のいずれか遅い時点で貸手として受け取るリース料と借手として支払うリース料の差額を損益に計上することを認めている(リース適用指針第92項)。
① 中間的な貸手は、サブリースの借手からリース料の支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に対してリース料を支払う義務を負わない。
② 中間的な貸手のヘッドリースにおける支払額は、サブリースにおいて受け取る金額にあらかじめ定められた料率を乗じた金額である。
③ 中間的な貸手は、次のいずれを決定する権利も有さない。
(ア)サブリースの契約条件(サブリースにおける借手の決定を含む。)
(イ)サブリースの借手が存在しない期間における原資産の使用方法
(3)転リース取引
「転リース取引」とは、ヘッドリースの原資産の所有者から当該原資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引をいう(リース適用指針第93項)。
企業会計基準適用指針第16号における転リース取引の取扱いについては、主に機器等のリースについて仲介の役割を果たす中間的な貸手の会計処理として実務に浸透しているため、リース会計基準等では、当該取扱いをサブリース取引の例外的な取扱いとして、企業会計基準適用指針第16号の定めを変更せずに認めている。
具体的には、中間的な貸手は、転リース取引のうち、貸手としてのリースがヘッドリースの原資産を基礎として分類する場合にファイナンス・リースに該当するとき、次のとおり会計処理を行うことができる(リース適用指針第93項)。
① 貸借対照表上、リース債権又はリース投資資産とリース負債の双方を計上する。
② 損益計算書上、支払利息、売上高、売上原価等は計上せずに、貸手として受け取るリース料と借手として支払うリース料との差額を手数料収入として各期に配分し、転リース差益等の名称で計上する。
なお、リース債権又はリース投資資産とリース負債は利息相当額控除後の金額で計上することを原則とするが、利息相当額控除前の金額で計上することができる(リース適用指針第93項なお書き)。
9 開 示
(1)表示
① 借手
リース会計基準等では、借手の会計処理をIFRS第16号と整合的なものとする中で、借手の表示についても、IFRS第16号と整合的なものとすることとし、次のとおり定めている(リース会計基準第49項から第51項)。
(ア)使用権資産について、次のいずれかの方法により、貸借対照表において表示する。
(i)対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目に含める方法
(ii)対応する原資産の表示区分(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産等)において使用権資産として区分する方法
(イ)リース負債について、貸借対照表において区分して表示する又はリース負債が含まれる科目及び金額を注記する。
(ウ)リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示する又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び金額を注記する。
② 貸手
リース会計基準等では、貸手の会計処理について、収益認識会計基準との整合性を図る点並びにリースの定義及びリースの識別を除き、基本的に企業会計基準第13号の定めを踏襲している。これを受け、貸借対照表における貸手の表示については、企業会計基準第13号を踏襲し、所有権移転ファイナンス・リースに係るリース債権と所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース投資資産は区分することとし、貸借対照表においてそれぞれを区分して表示する又はそれぞれが含まれる科目及び金額を注記することとしている(リース会計基準第52項)。ただし、リース債権の期末残高が、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しい場合、リース債権及びリース投資資産を合算して表示又は注記することができる(リース会計基準第52項ただし書き)。
損益計算書においては、IFRS第16号と同様に、次の事項を区分して表示する又はそれぞれが含まれる科目及び金額を注記することとしている(リース会計基準第53項)。
(ア)ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額)
(イ)ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(ウ)オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるもののみを含める。)
(2)注記事項
① 開示目的
リース会計基準等では、開示目的を定めることで、リースの開示の全体的な質と情報価値が開示目的を満たすのに十分であるかどうかを評価することを企業に要求することとなり、より有用な情報が財務諸表利用者にもたらされると考えられるため、リースに関する情報を注記するにあたっての開示目的を定めている。
リースに関する注記における開示目的は、借手又は貸手が注記において、財務諸表本表で提供される情報と併せて、リースが借手又は貸手の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える影響を財務諸表利用者が評価するための基礎を与える情報を開示することにある(リース会計基準第54項)。
この開示目的を達成するためのリースに関する注記として、次の事項を示している(リース会計基準第55項)。
(ア)借手の注記
(i)会計方針に関する情報
(ii)リース特有の取引に関する情報
(iii)当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
(イ)貸手の注記
(i)リース特有の取引に関する情報
(ii)当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報
開示目的を達成するために必要な情報は、リースの類型等により異なるものであるため、注記する情報は、上記の各注記事項に限定することを意図しておらず、これらの注記事項以外であっても、開示目的を達成するために必要な情報は、リース特有の取引に関する情報として注記する(リース適用指針第94項)。
ただし、上記の各注記事項のうち、開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については、記載しないことができる(リース会計基準第55項ただし書き)。
② 借手の注記
リース会計基準等では、借手の会計処理をIFRS第16号と整合的なものとする中で、借手の注記事項についても、IFRS第16号と整合的なものとしている。ただし、リース会計基準等は簡素で利便性が高いものを目指していることから、取り入れなくとも国際的な比較可能性を大きく損なわせない内容については、必ずしもIFRS第16号に合わせる必要はないと考えられるため、取り入れていない。
標準的な開示要求として、借手の注記事項を前頁の図表7のとおり定めている。
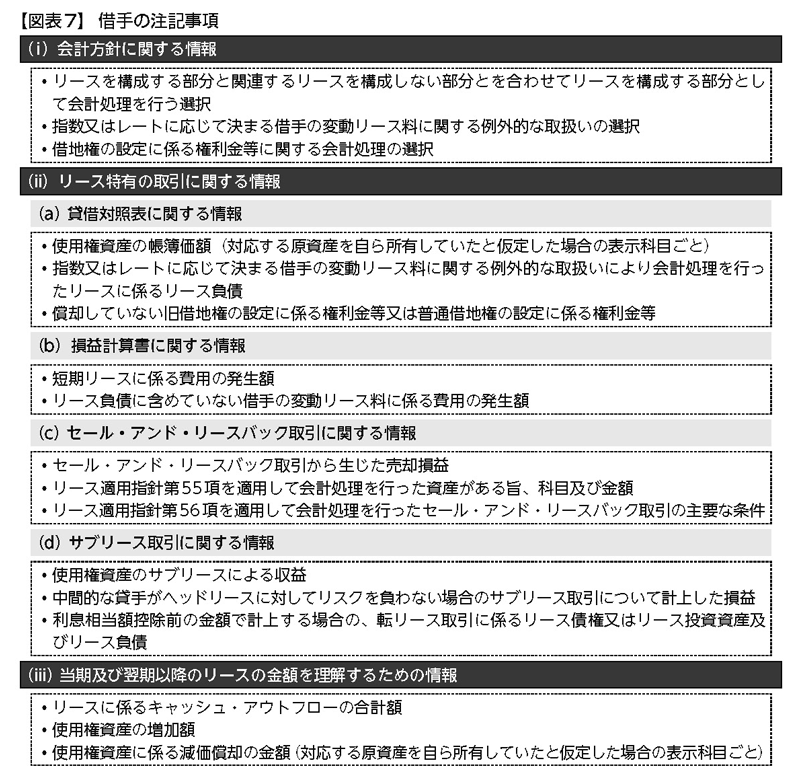
③ 貸手の注記
リース会計基準等では、貸手の注記事項についても、IFRS第16号と整合的なものとしている。標準的な開示要求として、貸手の注記事項を上記の図表8のとおり定めている。
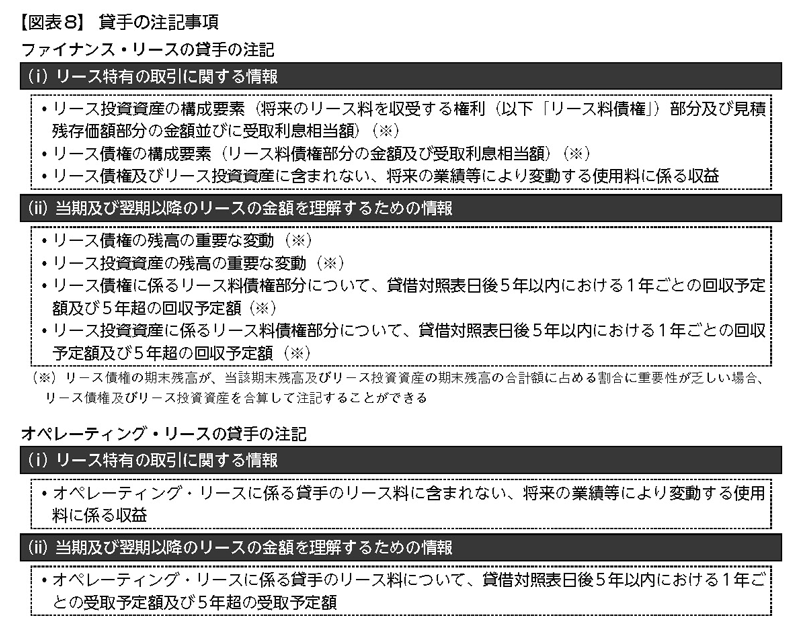
④ 連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における表示及び注記事項
連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表においては、「リース特有の取引に関する情報」(リース会計基準第55項(1)②及び(2)①)及び「当期及び翌期以降のリースの金額を理解するための情報」(リース会計基準第55項(1)③及び(2)②)について注記しないことができる(リース適用指針第110項)。また、個別財務諸表においては、「会計方針に関する情報」(リース会計基準第55項(1)①)を記載するにあたり、連結財務諸表における記載を参照することができる(リース適用指針第111項)。
10 適用時期等
(1)適用時期
リース会計基準は、公表後2年半程度経過した2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する。ただし、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができる(リース会計基準第58項)。
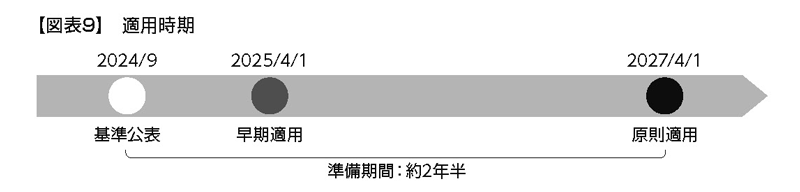
(2)経過措置
リース会計基準等では、経過措置について次のとおり定めている(リース適用指針第113項から第137項)。
① リース会計基準等においては、企業会計基準第13号を定めた時の経過措置について継続して適用できる。
② リース会計基準等においては、IFRS第16号において経過措置が置かれている趣旨を考慮し、我が国の会計基準を基礎とした場合に関連すると考えられるIFRS第16号の経過措置を取り入れるとともに、我が国特有の経過措置を設けている。具体的には、次の経過措置を設けている。
(ア)適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する経過措置
(イ)リースの識別に関する経過措置
(ウ)借手に関する次の経過措置
(i)ファイナンス・リース取引に分類していたリース
(ii)オペレーティング・リース取引に分類していたリース等
(iii)セール・アンド・リースバック取引
(iv)借地権の設定に係る権利金等
(v)建設協力金等の差入預託保証金
(エ)貸手に関する次の経過措置
(i)ファイナンス・リース取引に分類していたリース
(ii)オペレーティング・リース取引に分類していたリース等
(iii)サブリース取引
(オ)国際財務報告基準を適用している企業に関する経過措置
(カ)開示に関する経過措置
11 リース会計基準の実務への適用を検討する過程における実務上著しく困難な状況に対する別途の対応
リース会計基準の実務への適用を行う過程でリース会計基準の開発時に想定していなかった事態に備えることができるように、収益認識会計基準の公表時における対応(収益認識会計基準第96項)と同様に、リース会計基準の実務への適用を検討する過程で、リース会計基準における定めが明確であるものの、これに従った処理を行うことが実務上著しく困難な状況が市場関係者により識別され、その旨企業会計基準委員会(ASBJ)に提起された場合には、公開の審議により、別途の対応を図ることの要否をASBJにおいて判断することとしている。
脚注
1 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「リース適用指針」という。)を以下合わせて「リース会計基準等」という。
2 見積残存価額とは、貸手のリース料の現在価値と貸手のリース期間終了時に見積られる残存価額で残価保証額以外の額をいう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























