解説記事2025年01月06日 ニュース特集 Q&Aで読み解く令和7年度税制改正大綱(Ⅰ)(2025年1月6日号・№1057)
ニュース特集
103万円の壁は123万円に
Q&Aで読み解く令和7年度税制改正大綱(Ⅰ)
自民党税制調査会及び公明党税制調査会は令和7年度税制改正大綱を決定した(今号17頁参照)。法人税関係については、例年に比べて税制改正要望項目も少なく、衆議院選挙があり日程もタイトであったことから、大きな改正は少なかったものの、中小企業経営強化税制の見直しや防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の導入時期が決まっている。また、少数与党となったことで国民民主党との間で「103万円の壁」の見直しに着手したが、与党の税制改正大綱取りまとめまでには折り合いが付かず、123万円に引き上げるだけにとどまった。ただし、税制改正大綱には、三党の幹事長合意を踏まえ、「自民党及び公明党としては、引き続き、真摯に協議を行っていく」ことが明記された。税制改正法案提出まで、あるいは国会審議の中で修正される可能性も高そうだ。
本特集では、第一弾として所得課税及び資産課税を中心に令和7年度税制改正大綱のポイントをQ&A形式で解説する。
所得課税
「123万円」は消費者物価指数の基礎的支出項目を指標に算定
Q
いわゆる「103万円の壁」については、123万円に引き上げられるとのことですが、国民民主党の主張する「178万円」とは大きく開きがあります。この「123万円」の数字の根拠を教えてください。
A
所得税の基礎控除の引き上げ、いわゆる「103万円の壁」の見直しについては、178万円への引き上げを主張する国民民主党との間で交渉が決裂したことにより、12月20日に取りまとめた令和7年度税制改正大綱には、基礎控除を現行の48万円から58万円、給与所得控除を現行の55万円から65万円とそれぞれ10万円ずつ引き上げることとされ、結果として、現行の「103万円」から「123万円」となった。
この「123万円」は、最後の基礎控除引き上げを行った1995年(平成7年)の消費者物価指数の基礎的支出項目(食料、家賃、光熱費、保険医療サービスなどの必需品的なもの)を100とした場合に、2023年に120.5%に上昇していることを踏まえた数字となっている。一方、国民民主党が主張していた「178万円」は最低賃金を指標としたものであり、政府の試算によれば、国税及び地方税を合わせておよそ8兆円弱の減収見込みとなるため、財源の確保ができない中、両者は税制改正大綱取りまとめまでに折り合いを付けることができなかった。ただ、与党と国民民主党は引き続き協議を行うとしているため、今後、修正される可能性も高いといえる。
なお、自民党税制調査会の宮沢洋一会長は、123万円への引き上げによる減収見込み額は6,000億円から7,000億円程度としており、財源を確保しなくても対応できる引き上げだと述べている。
基礎控除、住民税は現行どおり
Q
住民税に関して、基礎控除の引き上げは行われたのでしょうか。
A
基礎控除については、現行の48万円から10万円(20%程度)引き上げ、58万円としている。住民税に関しては、税収減に強く反対する都道府県の意向を踏まえ、現行どおりとなっている。今回の見直しの結果、基礎控除の額は下表のとおりとなる。
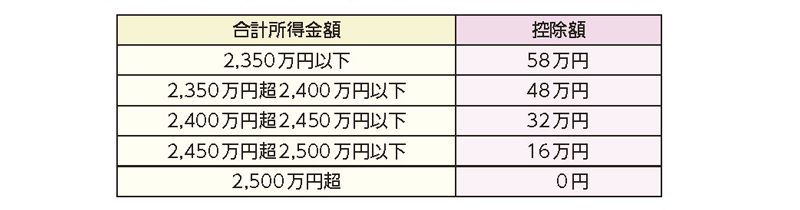
大学生の子の給与収入が150万円を超えても段階的に控除可
Q
新たに特定親族特別控除(仮称)が創設されるとのことですが、どのような制度なのでしょうか。
A
特に大学生のアルバイトの就業調整への対応として、19歳から22歳の子の給与収入が150万円(合計所得金額85万円)までは親が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられるというもの。仮に大学生年代の子の合計所得金額が85万円を超えた場合であっても、控除が受けられなくなるのではなく、段階的に逓減する仕組み(下表参照)が導入される。
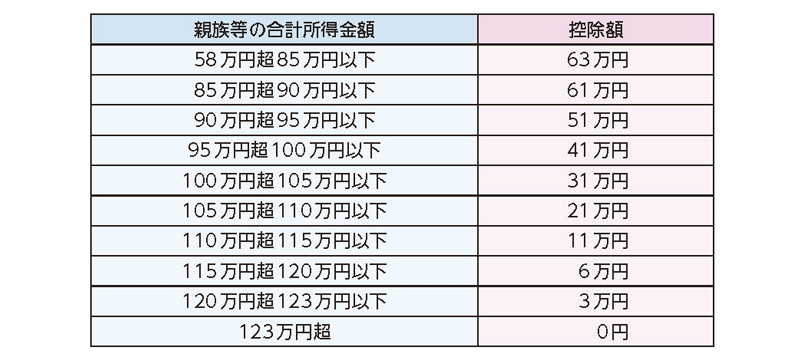
令和7年末の年末調整で対応
Q
基礎控除等の見直しは、令和7年分の所得税から適用されるとのことですが、法律が改正されるまではどのように対応すればよいのでしょうか。
A
例年どおり税制改正法案が令和7年3月末までに成立すると仮定した場合だが、当然、令和7年1月から3月は現行法に基づき源泉徴収を行うことになる。その後も、システム改修や事務フローの見直しなどがあるため、4月から改正後の法律に従い源泉徴収事務ができるわけではない。このため、令和7年12月末の年末調整で対応することになる。また、個人事業者等であれば、令和7年分所得税の確定申告で還付を受けることになる。
なお、給与所得控除及び特定親族特別控除(仮称)については、個人住民税も見直されることになる。こちらは令和8年度分の個人住民税から適用されることになる。
令和6年度税制改正大綱に明記された高校生年代の扶養控除見直しは先送り
Q
令和6年度税制改正大綱では、高校生年代の扶養控除の見直しとして、現行の国税38万円を25万円(令和8年分以降)に、地方税33万円を12万円(令和9年度分以降)に引き下げる旨の方向性が示され、令和7年度税制改正で結論を得るとされていましたが、どのような結果となりましたか。
A
令和7年度税制改正では、結論を先送りにしている。税制改正大綱では、高校生年代の扶養控除及びひとり親控除については、令和8年分の所得税及び令和9年度分の個人住民税は現行制度を維持し、令和8年度以降の税制改正において、各種控除のあり方の一環として検討し結論を得ることとされた。
子育て世帯に対する住宅ローン減税等の拡充は引き続き実施
Q
先行実施されていた子育て世帯等に対する住宅ローン控除や住宅リフォーム税制の拡充は、令和7年以降も継続されるのでしょうか。
A
令和6年度税制改正では、扶養控除の見直しが行われることを前提として、子育て世帯(18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者)に特化した政策税制として、住宅ローン控除については、令和6年の入居分に限り、新築等の認定住宅については500万円、新築などのZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅については1,000万円の借入れ限度額を上乗せするとともに、床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和されている。また、既存住宅のリフォーム税制(工事費用の相当額の10%を税額控除)についても、令和6年に限り、子育て世帯等が行う一定の子育て対応改修工事が対象に加えられている。
いずれも令和6年分に限り、先行実施されたものだが、令和7年分についても引き続き、実施されることになった。
また、令和6年度税制改正大綱では、子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充として、新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずることとされていたが、この内容で令和8年分の所得税から適用されることとしている。
企業年金のない場合もiDeCoの拠出限度額が月額6万2,000円に
Q
iDeCoの拠出限度額が7,000円引き上げられるとのことですが、企業年金に未加入の場合も同じですか。
A
今回の見直しでは、勤務先の企業年金の有無等による拠出限度額の差異を解消する目的から、第2号被保険者(会社員等)のiDeCo独自の限度額を廃止し、企業年金の拠出額との合計に対する共通限度額に一本化した上で、前回の拠出限度額設定時からの賃金上昇率を勘案して月額7,000円引き上げる。厚生年金に加入している第2号被保険者の限度額は月額6万2,000円、国民年金の第1号被保険者の限度額は月額7万5,000円となる。また、iDeCoによる支援が最も必要となる企業年金のない第2号被保険者については、iDeCo独自の限度額を廃止したことにより、現行の月額2万3,000円から月額6万2,000円と大幅に引き上げられる。
スタートアップ企業への再投資、実質2年間は非課税に
Q
令和5年度税制改正では、株式譲渡益を元手にしてスタートアップ企業へ再投資した場合には非課税となる措置が講じられています。同一年内での投資が要件となっていますが、複数年に延長されることになるのでしょうか。
A
エンジェル税制については、令和5年度税制改正において、スタートアップへの再投資に係る非課税措置が創設されている。保有株式を売却し、自己資金による起業やプレシード・シード期のスタートアップへの再投資を行う際、再投資した分の譲渡益には課税を行わないというものである。この点、非課税措置を適用するには、株式譲渡益の発生した年に投資を行う必要があるが、実際には元手となる所得が発生してから十分な再投資までに1年以上要しているエンジェル投資家が多いほか、一度起業した会社を売却してから次の起業まで複数年を要している連続起業家も多く、「同一年内」に投資し、非課税措置の適用を受けることは難しいとの課題があった。
このため、令和7年度税制改正では、譲渡益発生年の翌年にスタートアップ投資を行った場合、譲渡益発生年に遡って投資額に相当する金額を譲渡益から控除する繰戻し還付制度が創設される。したがって、実質的に非課税となる再投資期間が2年間ということになる。
NISA、つみたて投資枠におけるETFの最低取引単位が1万円以下に
Q
NISAについてはどのような見直しが行われますか。
A
令和5年度税制改正で抜本的拡充・恒久化が図られたNISA制度だが、令和7年度税制改正では、利便性のさらなる向上策が講じられることになる。
現行制度では、NISAのつみたて投資枠の対象ETFには、最低取引単位が1,000円以下という要件があり、定額購入方式のみが認められている。この点、現状、売買単位当たりの価格が1,000円以下のETFは存在していないほか、市場価格は変動するため、毎月定額の購入契約には不向きであるとの課題が指摘されている。このため、最低取引単位を1万円以下に引き上げるとともに、定額購入方式だけでなく、最大口数買付け方式も可能にする。これにより、例えば、毎月〇円以内で購入できる最大口数を購入することが可能になる。また、金融機関変更時の即日での買付けも可能にする。現行では、口座開設の申し込みから買付けが可能になるまで1~2週間を要するが、その間に買付意欲を失うケースがあるとの指摘がなされていた。
退職所得課税の見直しは令和7年度改正も見送り
Q
「退職年金の5年ルール」の見直しが行われるとのことですが、以前、話題となった退職所得課税制度の見直しはどうなりましたか。
A
令和7年度税制改正では、いわゆる「退職年金の5年ルール」に規制が入ることになった(本誌1054号参照)。現行制度では、先に確定拠出年金の一時金を受け取った後、退職一時金を受取るまでの期間が5年以上経過していれば、いずれも退職所得控除を満額利用することが可能になっているが、課税の公平性の観点から「10年内」に見直すこととしている(令和8年1月1日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用)。
一方、政府が令和5年6月に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」に盛り込まれた退職所得課税制度の見直しについては、昨年度に引き続き令和7年度税制改正大綱には盛り込まれなかった。ただし、大綱には「勤続年数が20年を超えると1年あたりの退職所得控除額が増加する仕組みが転職の増加等の働き方の多様化に対応していないといった指摘もある」と明記されており、退職金や私的年金等のあり方は、あるべき方向性や全体像の共有を深め、具体的な案の検討を進めていくとされている点、留意したい。
給与所得と公的年金等控除の合計額の上限を280万円に
Q
厚生労働省において、在職老齢年金制度の見直しが行われていますが、これに伴う改正は予定されていますか。
A
公的年金等控除は、給与収入がある場合でも適用されるため、同じ収入でも給与収入のみの納税者と、給与収入と公的年金等の双方を有する納税者で税負担に差が生じている。今後、在職老齢年金制度の見直しが行われた場合、給与と年金の年間合計が600万円以上の収入がある場合には、一定の年金受給者は公的年金収入が増加することになり、現行よりもさらに税負担が拡大し、働く意欲が阻害されるのではないかと指摘されている。このため、給与所得控除と公的年金等控除の合計額の上限については280万円とする方向だ。なお、この改正は、在職老齢年金制度の見直しが行われた後、令和8年度税制改正で法制化するとしている。
今後も信託を利用した節税スキームには迅速に対応
Q
法人課税信託を利用した株式交付に対する課税の見直しが行われるとのことですが、同様の節税スキームに対する国の対応を教えてください。
A
令和7年度税制改正では、法人課税信託に係る所得税の課税の適正化が行われる(令和7年4月1日以後に効力が生ずる法人課税信託について適用)。今回の見直しは、法人課税信託(受益者等の存しない信託)は受益者等が指定され、法人課税信託に該当しなくなった場合には、受益者等は受託法人から信託財産の帳簿価額(簿価)を引き継ぐとされていることを踏まえ、株式の譲渡時まで課税の繰り延べが行われていることに対応するものだが(本誌1054号参照)、税制改正大綱では、今後も、信託等を利用することでストックオプション税制の要件を満たさずに同じ税優遇効果を生むスキームに対しては迅速に対応するとしている。
資産課税
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は2年間延長
Q
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、自民党税制調査会では、政府から適用期限で廃止するとの提案を受けたとのことですが、最終的にはどのような結果となりましたか。
A
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、現行の1,000万円とされている非課税限度額を維持したまま、適用期限を令和9年3月31日まで2年延長することになった。令和5年度税制改正では、次の適用期限の到来時には、利用件数や利用実態等を踏まえ、制度の廃止も含め改めて検討が行われるとされていたが、現在、「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)の最中にあることが勘案された。
なお、令和5年12月時点における同非課税措置の契約数は7,736件と依然として低迷している。同様の仕組みである教育資金の一括贈与の非課税措置(令和8年31日まで)の契約数26万2,159件と比べてみてもその差は歴然となっている。
贈与の直前に役員に就任していればOK
Q
法人版事業承継税制の特例措置の役員就任要件が見直されるとのことですが、個人版事業承継税制の事業従事要件についても見直しが行われますか。また、同税制の適用期限の延長はありますか。
A
役員就任要件とは、贈与の日までに、後継者が役員に就任して3年以上経過している必要があるというもの。現行の法人版事業承継税制の特例措置を適用する場合には、令和6年12月末までに後継者が役員に就任している必要があるが、コロナや物価高騰等の急激な経営環境の変化により事業承継の具体的な検討が進んでいない中小企業等が多く、役員就任要件を満たすことができないとの指摘がなされていた。このため、令和7年度税制改正では、贈与の直前において役員であればよいことに要件を緩和する。また、個人版事業承継税制についても、法人版と同様、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり、特定事業用資産に係る事業に従事していたとする事業従事要件があるが、これを「贈与の直前」に見直すこととする。これらの改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
そのほか、適用期限は、税制改正大綱においては中小企業の円滑な世代交代をするための極めて異例の時限措置であることを踏まえ、今後とも延長しないことと明記されている。
相続に係る所有権の移転登記の登録免許税の免税措置は2年延長
Q
相続登記の義務化に伴い、登録免許税の減免措置などが講じられていますか。
A
令和7年度税制改正では、相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されることになったが、相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)に伴う登録免許税の減免措置は何ら手当されていない。
新型コロナの印紙税特例は令和7年8月末まで
Q
新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限については、再び1年間延長されたのでしょうか。
A
公的貸付機関等又は金融機関が新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書は、令和7年3月31日まで印紙税が非課税とされているが、令和7年度税制改正では、令和7年8月31日まで非課税措置を延長することとされた。今回は1年間の延長ではなく、5か月間の延長である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























