解説記事2025年01月20日 特別解説 監査法人に対する金融庁の行政処分(2025年1月20日号・№1059)
特別解説
監査法人に対する金融庁の行政処分
はじめに
2023年(令和5年)は金融庁による監査法人への行政処分が多数行われた年であったが、その傾向は2024年に入っても大きく変わっていない(次頁表を参照)。監査法人や公認会計士の自主規制団体である日本公認会計士協会(JICPA)は、上場会社の監査を実施する監査法人に対して高い規律付けを求めるべく、上場会社監査事務所登録制度を2023年4月から運営しているが、残念ながら、その運営開始後も行政処分を受ける(公認会計士・監査審査会による処分勧告も含む)監査法人が後を絶たない。本稿では、公認会計士・監査審査会(CPAAOB)について、組織の概要や検査の位置付け等を簡単に説明した後、金融庁やCPAAOBのウェブサイトに掲載されている文書をもとに、各監査法人に対して下された行政処分(処分勧告を含む)に共通する点や特徴的な点等を調査分析することとしたい。
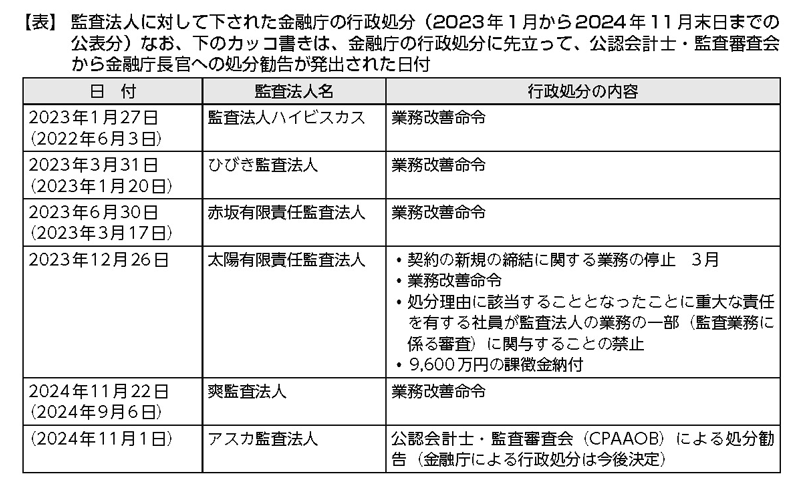
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)による検査
公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は、公認会計士法に基づき、会長及び委員9名以内で構成される合議制の機関として、金融庁に設置されている。
CPAAOBの主な業務は以下のとおりである。
あまり知られていないが、公認会計士業界への入り口と言える試験の実施を担当しているのがCPAAOBである。
・監査事務所に対する審査及び検査等
・公認会計士試験の実施
・公認会計士等に対する懲戒処分等の調査審議
・諸外国の関係機関との連携・協力
CPAAOBの主な活動状況については毎年「公認会計士・監査審査会の活動状況」としてとりまとめられ、ウェブサイト等で公表されている。
CPAAOBは、日本公認会計士協会(JICPA)から品質管理レビューに関する報告を受けてその内容を審査し、必要に応じて監査事務所やJICPA等に検査等を行っている。この審査及び検査等の結果、JICPAにおいて品質管理レビューが適切に行われていなかったことが明らかになった場合や、監査事務所において監査の品質管理が著しく不十分であったり、法令等に準拠していないことが明らかになったりした場合には、業務の適正な運営を確保するために必要な行政処分その他の措置を金融庁長官に勧告することになる。
ここで、品質管理レビューとは、JICPAが監査事務所の監査の品質管理の状況を調査し、必要に応じ監査事務所に対して改善勧告を行うもので、CPAAOBは、品質管理レビューの結果について、JICPAから報告を受けている。
そして、CPAAOBは、JICPAからの報告について、JICPAの品質管理レビューが適切に行われているか、監査事務所の監査業務が適切に行われているかどうかを確認する。CPAAOBは、必要があると認める場合には、JICPA又は各監査事務所に対して報告又は資料の提出を求める(審査)。
審査の結果等により、JICPAの事務の適正な運営を確保する必要があると認める場合や公益又は投資者保護のために必要かつ適当と認める場合には、JICPA、監査事務所又はその他監査事務所の監査業務に関係のある場所(被監査会社等)に対して検査又は報告徴収を行う(検査)。そして、審査又は検査の結果、必要があると認められる場合には、監査事務所の監査業務又はJICPAの事務の適正な運営を確保するために必要な行政処分その他の措置について金融庁長官に勧告することになる。
本稿では、これらのプロセスに基づいて発出された金融庁長官に対する処分勧告及びそれを受けての金融庁による行政処分の内容や特徴、それに至った原因等を調査分析することとしたい。
6件の行政処分事例の内容分析(各事例に共通する指摘事項や特徴的な指摘事項等)
冒頭の「はじめに」で掲載した表に含まれる6件の行政処分(処分勧告含む)事例のうち、準大手監査法人である太陽有限責任監査法人に対して下された処分は、法人全体の品質管理体制等の法人運営に関するものではなく、個別の監査業務における所属公認会計士の対応の不備に対するものである点で、他の5件の事例とは若干色合いが異なる。
すなわち、監査対象会社の売上の過大計上や貸倒引当金の過少計上等に起因する訂正報告書の監査業務について、業務執行社員による監査補助者の指導・監督の不十分及び審査体制の不備(監査結果の検証が不十分)が行政処分の対象となった。
その他の中小規模監査事務所の5事務所は、いずれも総論として、「法人運営が著しく不当」と評価されている。
以下では、各事例について、「業務管理体制」「品質管理体制」及び「個別の監査業務」のパートに分けて、重要と思われる指摘事項をピックアップするとともに、各監査事務所に共通する項目やそれぞれの監査事務所固有のものと考えられる特徴的な指摘事項を調査分析することとしたい。
① 業務管理体制
(各監査事務所に共通してみられた主な指摘事項)
・内部規程等の整備・運用を含め、適正な水準の監査品質の確保に向けた実効的かつ組織的な業務管理体制を整備・運用することに対する最高責任者や品質管理責任者の意識が著しく不足していた。
・社員間の相互牽制・相互監視機能を重視する風土が欠如しており、組織的な業務管理体制を構築できていなかった。
・最高責任者は、経験豊富な各社員を過度に信頼し、業務の実施において特段の問題がないと思い込んでいた。
・各社員が主体的に監査業務に関与する姿勢が不足していた。
・監査実施者において、監査の基準や現行の監査の基準が求める手続の水準に対する理解が不足していることを認識できていなかった。
今回事例として取り上げているような中小規模の監査事務所の場合、少数の構成員の自主性を尊重するあまり、時には忖度も働いて、どうしても品質管理や業務の執行が属人的になりやすい。その結果、監査事務所の品質管理や個々の監査業務の品質にばらつきが生じ、時に馴れ合いや緊張感に欠けた状態となり、監査上の失敗等も見逃される恐れがある。たとえ中小規模の監査事務所であっても、上場会社の監査を実施するような場合には、監査上の対応や品質にばらつきがあってはならず、組織的に一体となって対応しなければならない。パートナーシップ制である以上、各パートナーがお互いの能力と人柄、業務を信頼するのは必須ではあるが、「過度の信頼」や「思い込み」は監査上の判断の甘さや監査の失敗につながりかねないことに留意することが必要であろう。
(特定の監査事務所に特有と思われる指摘事項)
・監査調書や資料の改ざんやその秘匿など、検査への対応が不適切であった。
・職業的専門家としての倫理観が欠けていた。
・最高責任者は、法人内において、外部検査等での指摘の回避を最優先事項とし、職業的専門家としての誠実性、信用保持を軽視する風土が形成され、蔓延する状況を助長・放置していた。
・業務執行社員が監査報告書日後の追加的な監査手続の実施、監査調書の事後的な作成や改ざん等を指示し、監査補助者が当該指示を躊躇なく実行していた。
・職業倫理の遵守を重視する組織風土の醸成に向けて、最高責任者がリーダーシップを発揮していなかった。
・業務執行社員が、人的資源が不足している状況について十分に考慮することなく、監査契約の新規の締結又は更新を行い、また、十分かつ適切な監査証拠を入手していない状況において監査手続を終了させていた。
監査調書の事後的な追加、改ざん、検査官に対する情報の隠蔽等が複数の監査法人の検査で立て続けに検出され、監査法人業界に衝撃が走った。
「職業的専門家としての倫理観が欠けていた」「業務執行社員が監査報告書日後の追加的な監査手続の実施、監査調書の事後的な作成や改ざん等を指示し、監査補助者が当該指示を躊躇なく実行していた」といった生々しい記載からは、裏切られた検査当局の激しい怒りが伺える。
② 品質管理体制
(各監査事務所に共通してみられた主な指摘事項)
・審査担当社員は、業務執行社員との討議や関連する監査調書の検討を十分に実施することなく、監査チームによる重要な判断とその結論には問題がないものとして審査を完了させていた。
・審査担当者の適格性について評価していなかった。
・審査担当者は、監査チームが実施した実証手続、会計上の見積りや不正リスク対応等に係る監査手続に関し、監査チームとの討議や関連する監査調書に基づいた検討を十分に行うことなく、監査チームによる重要な判断およびその結論には問題がないとして審査を完了させていた。
品質管理体制のパートでは、各法人ともに、審査の不十分さや深度不足が指摘されていた。ここで、「審査」とは「審査担当者によって監査報告書日以前に実施される、監査チームが行った重要な判断及び到達した結論についての客観的評価をいう。」と定義されている(品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」第13項(1))。なお、「審査担当者」とは、「審査を実施するために監査事務所が選任した社員等、監査事務所内の他の者又は外部の者をいう。」とされており、業務を執行する社員は審査担当者になることができない。審査担当者はこれまでの業務上得た知見や経験を活かし、監査チームからは独立した立場で、監査チームが実施した業務を客観的に評価することが求められるが、力及ばず、審査の深度不足が数多く指摘される結果となった。
(特定の監査事務所に特有と思われる指摘事項)
・業務執行社員又は補助者が事後的に作成した監査調書を監査ファイルに差し込む等したうえで、その旨を秘したまま検査官に当該監査ファイルを提出した。
・監査ファイルの最終的な整理後における監査調書の差し替えなど、監査法人の方針及び手続に従わない監査調書の変更を防止するための実効性のある措置を講じていなかった。
・法人全体の情報管理に係るセキュリティ責任者及び各監査業務に係るセキュリティ担当者を任命していなかった。
・被監査会社から入手した電子データを各人の個人PCに保存していたほか、社員及び職員が、個人のメールアドレスに、監査法人の業務に関連する電子メールを転送していた。
・社員報酬に関する方針及び手続を定めておらず、各社員の報酬額の決定に際し、各社員の監査業務の品質等に関する評価を反映させる態勢を整備していなかった。
・社員総会等での所定の承認を受けることなく、利益相反取引が行われていた。
4大監査法人や準大手監査法人と比較すると、大規模なIT投資をすることが資金的に難しい中小規模の監査事務所でのITシステム導入は遅れていると見られており、監査業務に従事しているすべての専門要員に対してすべての中小規模監査事務所が業務用のPCを貸与しているとは限らない可能性がある。また、中小規模の監査事務所の場合、常勤職員だけでは人手が足りずに、多数の非常勤職員と契約して監査業務を回している場合も多く見受けられる。そのような場合には、たとえ非常勤職員に対して監査事務所所定のPCを貸与している場合であっても、非常勤職員が常勤職員と同じような頻度で貸与PCを開くとは限らず(そうでない場合の方が多いと思われる)、業務用のPCに比べると安全性が脆弱な私用PCやメールアドレスを利用して業務上の連絡や書類のやり取り等を行う場合も少なくないと思われる。不必要なデータをPC内(特に私用PC内)に保存したり、個人のメールアドレスに業務上のメールを転送したりすることは、データ漏洩やウイルス感染等のリスクを高めるため、問題があると考えられる。
個別の監査業務
(各監査事務所の個別の監査業務に共通してみられた主な指摘事項)
・業務執行社員及び監査補助者が、監査の基準や現行の監査の基準が求める手続の水準の理解が不足していた(特に収益に関する不正リスクの評価及び対応に係る手続)。
・被監査会社(経営者)の主張を批判的に検討していないなど、職業的専門家としての懐疑心を十分に発揮していなかった。
・業務執行社員が監査補助者を過度に信頼して適切に業務を実施していると思い込み、監査補助者への適切な指示、監督及び監査調書の深度ある査閲を実施していなかった。
・業務執行社員は、担当する監査業務に十分な時間を確保し得ないため、監査補助者からの説明と自らの理解が合致しているかを確認するにとどまるなど、担当する監査業務への主体的な関与が不足していた。
・業務執行社員及び監査補助者が監査業務に費やすことができる時間が不足していたことから、リスクの水準に適合した適切な監査手続が実施されているかどうかについて慎重に検討していなかった。
個別の監査業務に関する指摘において最も多くみられたのが、「職業的専門家としての懐疑心を十分に発揮していなかった」というものであった。公認会計士は、職業的専門家として、被監査会社や経営者の主張を鵜呑みにするのではなく、豊富な知識と経験、健全な常識と倫理観に裏打ちされた職業的懐疑心(Professional skepticism)を発揮しなければならない。職業的懐疑心とは、誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し、監査証拠を鵜呑みにせず、批判的に評価する姿勢をいう。このことはすべての公認会計士が頭と心に刻みつけているはずであるが、様々な制約や事情等のために、十分に発揮することが難しい。
(特定の監査事務所の個別の監査業務に特有と思われる指摘事項)
監査報告書の日付が不適切、監査報告書のその他の事項区分の検討が不十分、経営者確認書が未入手といった指摘事項が見られた。
(個別業務で複数の監査事務所が監査手続の不足や不備を指摘された主な項目)
重要な虚偽表示リスクの評価、収益に関する不正リスクの評価及び対応、関連当事者取引の注記、継続企業の前提の検討、監査上の主要な検討事項(KAM)、棚卸資産の評価、固定資産の減損、資産除去債務の検討、繰延税金資産の回収可能性、監査役等とのコミュニケーション、仕訳テスト等に関する指摘が、複数の監査事務所が手掛ける個別の監査業務で指摘されていた。
終わりに
2、3年前に比較するとペースは落ち着いてきたとはいえ、中小規模の監査事務所による上場会社の監査業務は増え続けている。幸い、従前の東芝やオリンパス事件のような大規模な会計上の不祥事・監査の失敗は、ここ数年は生じていないが、上場企業の監査業務を手掛ける中小規模の監査事務所の品質管理の水準が「著しく不当」な状態のまま向上しないことは、将来的な監査の失敗の温床となりかねない。
人的な制約、時間的な制約、資金的な制約等、監査品質の向上を阻む様々な要因はあろうが、それらは監査事務所に限った話ではない。業種を問わず、日本中の中小企業がこれらの制約と戦いながら、高品質な製品を作って競争力と存在感を保ち、日本の評判を高めている。
CPAAOBの報告書でも何度も触れられているように、我が国の監査事務所や経営者、一人一人の構成員は、法人の規模の大小を問わず、当事者意識を持って自ら主体的に知見や経験を深め、品質管理システムの整備運用の責任を担い、日常の監査業務を遂行していく必要があろう。監査事務所や責任者に対して非常に手厳しい言葉が並んでいるが、多くのことを教えてくれるCPAAOBの報告書を熟読し、他山の石として銘記すべきと考える。
参考文献
公認会計士・監査審査会パンフレット(令和4年度版)
金融庁、公認会計士・監査審査会及び日本公認会計士協会のウェブサイト掲載の文書
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















