解説記事2025年04月28日 巻頭特集 企業実務の現場から見たCFC税制の課題(後編)(2025年4月28日号・№1072) −国際最低課税額の制度導入も踏まえて
巻頭特集
対談
企業実務の現場から見たCFC税制の課題(後編)
−国際最低課税額の制度導入も踏まえて
北海道大学大学院法学研究科教授 元国税審判官 佐藤修二
外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所 弁護士 片平享介
CFC税制のオーバーインクルージョンの問題について、CFC税制の実務に精通する外国法共同事業 ジョーンズ・デイ法律事務所の片平享介弁護士と、元国税審判官で、弁護士時代にはCFC税制を巡る税務訴訟の代理人を務めた経験も有する北海道大学大学院法学研究科の佐藤修二教授に語っていただく本対談の【後編】(前編は前号参照)では、まず、厳しい利用制限がかかる繰越欠損金控除を取り上げる。そして、この繰越欠損金控除と、【前編】でテーマとなったCFC税制上の非課税所得、異常所得を巡る問題点の全てが顕在化する「外国関係会社の清算」について、事例を交えてご説明いただく。
さらに、トランプ政権下での国際課税の今後の展開についてもお考えを示していただいた。 (本文中、敬称略)
※なお、本対談で取り上げるのはあくまで一般的な問題であり、対談者が担当した特定の案件を念頭に置いたものではないこと、また対談の内容は対談者の個人的見解であり、所属する組織の見解とは無関係であることを念のためお断りさせていただく。
4.繰越欠損金
佐藤:次に、CFC税制における繰越欠損金をめぐる問題について同様に伺いたいと思います。
片平:CFC税制においても、外国関係会社の所得(適用対象金額)の計算上、過去の事業年度において生じた欠損金額を控除できるという制度はあります。しかしながら、この欠損金額の控除は、外国関係会社の本店所在地国の税制上のルールに従うのではなく、飽くまでCFC税制上のルールに従って行わなければならず、しかも、控除が認められる繰越欠損金の範囲は、極めて限定的です。
具体的には、適用対象金額の計算過程において、外国関係会社の本店所在地国の税制に従い繰越欠損金を損金の額に算入していた場合には、これを足し戻す必要があります。そのうえで、CFC税制上、前7年以内に開始した事業年度において生じた外国関係会社の欠損金額であれば、当年度の適用象金額の計算上控除できるのですが、その際の重要な前提条件は、欠損金額が発生した過去の事業年度における外国関係会社の区分と、当年度における外国関係会社の区分が、一致していることです。どういうことかというと、例えば適用対象金額が発生した当年度において、全体合算が問題となるペーパーカンパニー等の状態であれば、欠損金額が発生した過去の事業年度においても、同じように全体合算が問題となる状態(ペーパーカンパニー等又は経済活動基準を満たさない状態)であったことが要求されます。また、部分合算が問題となる当年度において、経済活動基準を満たす状態であれば、欠損金額が発生した過去の事業年度においても、同じように経済活動基準を満たす状態であったことが要求されます。これらの状況が一致していなければ、その繰越欠損金の利用は認められないというわけです(図表5参照)。
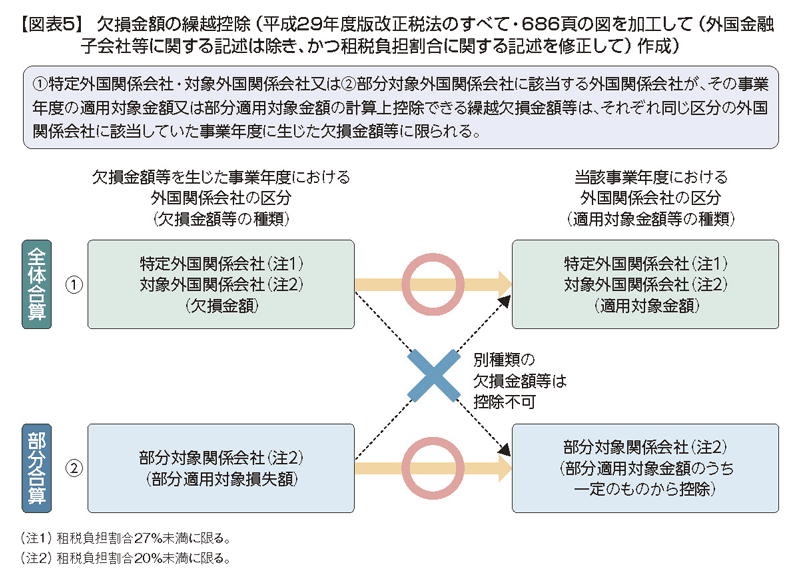
さらに後者の場合、すなわち当年度において部分合算が問題となるケースにおいては、会社としての区分の一致にかかわらず、問題となる特定所得の類型次第では、そもそも欠損金の控除が認められない場合があります。先ほどお話しした異常所得がその例です。つまり、経済活動基準を満たす当年度において異常所得が生じた場合には、CFC税制上の繰越欠損金の利用は一切認められないことになります。
佐藤:ありがとうございます。繰越欠損金の利用につき、かなり制約がかかっていることが分かりました。そのことで、具体的に問題となる場面があれば、お伺いしたいと思います。
片平:はい。
このような制約が会社清算に与える影響を見たいと思います。例えば外国関係会社の清算事業年度において、固定施設も処分ずみで、ペーパーカンパニーの状態になったとします。そして、同じ清算事業年度において債権者が債務免除を行い、債務者たる外国関係会社に債務免除益が生じるものとします。この場合、現地税制上は過去に発生した欠損金額を当年度の損金の額に算入することが認められていたとしても、CFC税制上の適用対象金額の計算上は、これを足し戻さなければいけないことは前述のとおりです。そして、CFC税制上、当該欠損金が発生したのが前7年以内であれば当年度の適用対象金額から控除できるはずなのですが、欠損金が発生した過去の事業年度において経済活動基準を満たす実態のある状態であったというのであれば、その事業年度から生じた欠損金額を、ペーパーカンパニーである当年度の適用対象金額からは控除できない、ということになります。
CFC税制上の外国関係会社の分類は人為的なものであり、年度によって変化することはあり得ますし、とりわけ事業を清算するフェーズにおいて往年の実態を備えていないことは、企業のライフサイクルとして当然のことです。しかし、CFC税制上の繰越欠損金制度は、こういった変化を容認していません。これはあまりに厳しいものであり、CFC税制において繰越欠損金を活用できる余地を、必要以上に減殺しているように見えます。特に、経済実態があり正常な事業活動の過程で発生した欠損金を、後の清算事業年度における固定施設を処分した状態で発生した適用対象金額から控除できないという制約を設けることが、CFC税制の趣旨から合理的に説明できるのか、強い疑問があります。
佐藤:法人税が、1年を課税期間としていることは便宜的なものにすぎないと考えると、繰越欠損金はなるべく使えるようにする、という方向にも考えられると思います。私自身も、基本的にはそのように考えるのが良いのではないかという感覚を持ちます。そのような立場から見れば、CFC税制では、ずいぶん繰越欠損金の利用制限をしているなと感じます。次に、この点に関する国際最低課税額制度の対応を伺いたいと思います。
片平:国際最低課税額制度のもとでは、構成会社等に税務上の欠損金が発生した場合、その発生年度において繰延税金資産を計上し、将来所得が発生した年度においてその取崩しによる繰延税金費用の計上を認めることで、実際の税額がゼロであっても、実効税率は15%を下回らないような調整がされています。しかも、本来の税効果会計であれば、繰延税金資産は将来の回収可能性が認められる範囲でしか計上できないのですが、国際最低課税額制度ではそのような制限もなく、欠損金額の全額について(ただし15%の税率を上限に)繰延税金資産の計上が認められています。このような国際最低課税額制度と比較しても、CFC税制上の繰越欠損金制度が、非常に限定的な範囲でしか控除を認めていないことが見て取れると思います。
5.具体的事例−会社清算の場面
佐藤:以上の各論で論じた項目が総合的に問題となる事例として、会社の清算の場面があると片平先生から伺っています。以上で論じた各点を踏まえて、具体的事例に基づいてご説明いただければと思います。
片平:これまで、CFC税制上の非課税所得、異常所得及び繰越欠損金控除の問題点を議論してきました。そして、これらの問題点の全てが顕在化するのが、外国関係会社の清算の場面なのです。例えば以下のような事例を想定します(図表6参照)。
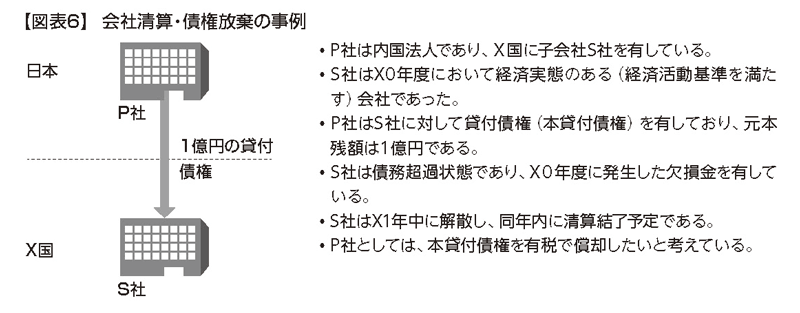
X1年度にて1億円の本貸付債権を放棄する場合、日本の税法の観点からは、S社に同額の債務免除益が発生することになります。しかし、仮にX国の法令上、1億円の債務免除益が課税標準から恒久的に除外されるとした場合、当該1億円は非課税所得となり、X1年度の租税負担割合は、以下のとおり0%となります。
租税負担割合の計算:
0(X国で課される租税の額)/(0+1億円)(債務免除益1億円を非課税所得として加算)= 0%
仮にS社がX1年度においてペーパーカンパニーに該当する場合、1億円の債務免除益が適用対象金額となり、全体合算の対象となります。そして、X1年度におけるS社がペーパーカンパニーであるのに対し、欠損金が生じたX0年度においては経済実態のある(経済活動基準を満たす)状態であった以上、会社としての区分が一致せず、従ってX0年度に発生した欠損金について、X1年度の適用対象金額から控除することはできません。
他方、仮にS社がX1年度において経済活動基準を満たす状態を維持できていたとしても、租税負担割合がゼロであるため、特定所得の金額の部分合算が依然問題となります。そして、債務免除益がX1年度の会計上の税引後当期利益を構成するとすれば、所得控除額(総資産の額、減価償却累計額、及び人件費の総額の50%)を差し引いた残額について異常所得の問題が生じます。なお、問題となる事業年度が残余財産確定を含む事業年度である場合、総資産の額及び減価償却累計額については、その前事業年度の末日時点の金額を用いて所得控除額を計算できる旨の特例があります。この場合においてもCFC税制上の欠損金控除の利用可能性は問題となりますが、先ほどお話しした通り異常所得はそもそもCFC税制上の欠損金控除の対象とならないため、結局、欠損金の繰越控除は認められません。
このように、債務超過の外国子会社について、親会社が債権放棄をしたうえで清算するという単純な事例であっても、CFC税制の適用による合算課税を避けることが難しいことが分かると思います。同じ状況が日本で生じていれば、S社に生じる債務免除益は、期限切れを含めた欠損金による繰越控除の対象となり、S社に対する課税は生じなかった一方、P社は(寄附金の問題がないことを前提に)債権放棄による損金算入が認められていたはずです。会社清算の場面においては、CFC税制は、外国子会社等を利用した租税回避の抑止どころか、我が国税制と比較した場合でも課税強化につながっているとすらいえます。
佐藤:どうもありがとうございます。問題状況が良く分かりました。
6.まとめ−企業の立場から見た今後のCFC税制の在り方
佐藤:以上ご説明いただいたところにより、とりわけBEPS対応によりCFC税制が強化される中で、企業にとっては負担感が増しているということが具体的事例によって見て取れたと思います。また、柱2の最低税率の導入に伴い、それに加えてCFC税制の網がかかっていることについては、(課税上の弊害の観点からはやむを得ないという理解もありますが)やはり企業側としてはより負担が増したという声もあるようです。このような点につき、片平先生に、企業の声に直接に接する実務家のお立場からお考えをお聞かせいただければ幸いです。
片平:私は国際最低課税額制度の適用対象となる多国籍企業グループの税務担当の方々とお話しする機会が多いのですが、国際最低課税額制度の最大の問題点は、実効税率の計算方法が著しく複雑であることだと思います。国際最低課税額制度の実効税率の計算が会計をベースにしていることは先ほど述べた通りですが、欠損金に係る繰延税金資産の例を見ても分かるように、会計とも従来の税制とも異なる、全く新しい、かつ極めて複雑なルールが規定されています。計算方法が複雑というだけではなく、その計算の前提となる情報についても、これまでの連結決算や国別報告事項(CbCR)の作成に必要だった情報とは質・量ともに異なる情報を、海外子会社等から収集する必要があります。そのため、国際最低課税額制度の適用対象となる多国籍企業グループは、新ルールの把握や制度に対応するための体制作りに追われているというのが現状だと思います。それでも最初の数年間は経過措置(移行期間CbCRセーフハーバー)があるため、制度の本格的な始動までにはしばらく時間的猶予があるとは言い得るものの、国際最低課税額制度に対応するための多国籍企業グループの事務手間の増加は、深刻な問題であると考えています。
佐藤:私も、企業の負担が重いという話を聞くことがありましたが、思っていた以上に大変そうな印象を受けます。
片平:はい。そして、これら多国籍企業グループについては、国際最低課税額制度対応に加えてCFC税制対応が重畳的に要求されることになります。これまで見てきたところからもお分かりのとおり、国際最低課税額制度とCFC税制は、全く異なるルールから成り立っています。無論、佐藤先生が的確にコメントされている通り、両者の趣旨は異なるため、両者の制度を完全に一本化することは難しいと思いますし、それは適当ではないとも思います。
佐藤:税制を作る方の立場からすれば、もちろんそうなのでしょうね。とはいえ、私も企業をクライアントとする弁護士でしたから、企業の負担も無視できないという点で、片平先生に共感します。
片平:ありがとうございます。趣旨の違いはあれど、両者が類似の課税制度(すなわち、外国子会社等の活動に起因して、日本の親会社に課税するという制度)を採用していることも事実であり、国際最低課税額制度導入の結果として、外国子会社等を利用した租税回避の抑止というCFC税制の目的が、部分的にせよ果たされる面を否定できないように思います。このような理由に加え、企業の事務手間の観点からも、既に巷でいわれている通り、やはりCFC税制を簡素化すべきだと思います。また、CFC税制にはこれまで見てきたような様々な問題点があるため、簡素化とともに、ルールを合理的なものに改正することも必要だと思います。とりわけ外国子会社の清算の場面におけるCFC税制の弊害は顕著であり、最低限、清算の場面において債務免除益を合算の対象から除外し、あるいは欠損金額の控除をより柔軟に認めるなどの改正は必須であるように考えています。
佐藤:どうもありがとうございます。最後に、せっかくなので、今回のテーマと直接には関係しませんが、国際課税をめぐるマクロ的な状況について伺いたいと思います。すなわち、OECDのいわゆる柱1については、従来から米国の合意を得ることが難しいと思われる状況がありましたが、トランプ政権への移行で、その状況が確定的になったように思います。そのような中で、柱1が問題としているデジタル経済における国際的租税回避については、今後、いわゆる独自課税を含めて、欧州や日本でどのような対応がされていくのか、また、2016年からのトランプ政権下で米国はさまざまな新しい国際課税の制度を導入しましたが、今後、それらはどのように展開していくのか。そういったことへの関心が世の中にはあるかもしれません。先の予想なので難しいところかとは思いますが、せっかくの機会ですので、米国や欧州の動向にも詳しい片平先生のお考えがあれば、お聞きできればと思います。
片平:ありがとうございます。この問題に詳しい方にはおさらいになりますが、まずバックグラウンドから簡単に説明させていただきます。先ほども少し触れましたが、多国籍企業による租税回避の問題に対処すべく、「BEPSプロジェクト」と呼ばれる国際的な取り組みが進められています。現在は「BEPS 2.0」と呼ばれる第二フェーズに入っている段階ですが、このBEPS 2.0には、柱1と柱2という二つのイニシアチブがあります。柱1の中核は、市場国に物理的拠点を置かずに事業を行う企業が増加する中で市場国の課税権を確保しようという動きであり、柱2の方は、法人税率の引き下げによって外国企業を誘致する動きを抑止しようというものです。本日の対談でたびたび言及のあった国際最低課税額制度は、後者の柱2のイニシアチブの一部を国内法制化したものですが、もともとのBEPS 2.0の発端は、むしろ前者の柱1の問題意識であったと理解しています。特に、米国の大手IT企業が、多くの市場国で十分な法人税を支払わないまま莫大な収益を上げるなか、フランスをはじめとする欧州の国々は、いわゆるDST(デジタルサービス課税)を導入することで対抗しようとしました。このDSTは、一定の消費者向けデジタルサービスに対し、収入額ベースで課税しようとするものです。このDSTに対しては、「PEなければ課税なし」という原則を規定する二国間租税条約やWTOルールに違反する一方的措置であるという批判があり、当時のオバマ政権は、DSTを実施する国に対しては報復関税などの対抗措置をとることを示唆していました。
このように、BEPS 2.0は、デジタル課税の問題に関する米国と欧州間の争いを解決するという面があります。柱1と柱2に関する国際的合意が成立したのはバイデン政権時の2021年10月のことですが、柱1と柱2の内容を見ると、米国に対する配慮が随所で見られます。例えば柱1は、米国の大手IT企業を狙い撃ちにしないような形で制度設計されており、柱2についても、第一次トランプ政権時の2017年に米国で新たに導入されたCFC制度(いわゆるGILTI制度)が模範になっているといわれています。そして、欧州各国をはじめ、2021年10月の国際的合意に参加した国々は、柱1の進展を条件に、一定の期間DSTの発動を控えるというモラトリアムに同意したのです。ただ、国内税法の制定・改正によって導入できる柱2のグローバル・ミニマム課税と異なり、柱1の導入のためには「PEなければ課税なし」を規定する二国間租税条約の改正が必要となるため、米国をはじめとする国々が多国間租税条約に署名・批准しなければなりません。ところが、米国では、条約の批准のためには上院の出席議員の3分の2の賛成が必要であり、柱1の導入はもともと政治的に困難であることが指摘されていました。他方、柱2についても、バイデン政権時にGILTI制度を柱2の内容に沿った形で改正することなどが議論されていましたが、そのような改正は実現せず、2023年に新たに導入された15%の法人税代替ミニマム税も、柱2の内容に沿ったものとはなりませんでした。
このような状況の中、2025年になって第二次トランプ政権が始動しました。そして、トランプ大統領が就任初日に署名した大統領令では、柱1と柱2双方について米国内で効力を有しないことが宣言され、さらに米国企業に対して差別的かつ域外適用として行われる課税措置につき、対抗措置を検討することが表明されました。非常に長くなりましたが、以上が昨今の国際課税の動きについての説明となります。
このような動きを受け、欧州や日本としてどのような対応をとっていくことが予想されるかというのが、ご質問の趣旨だと理解しています。まず柱1については、欧州各国としてDSTの実施を進めていく動きが当然予想されます。実は、先ほど説明したDSTの発動を控えるというモラトリアムは、すでに失効しています。なので、欧州はじめ世界の国々は、DSTを導入しようと思えばいつでもできる状態です。実際、カナダは、もともとモラトリアムから距離を置いていたという事情もありますが、DSTの実施をすでに昨年の段階で始めており、米国との間で紛争となっています。他の国々は、今のところトランプ大統領の動きを静観しているようですが、カナダに続いてDSTを導入する国がそのうち出てきてもおかしくないと思います。日本については、どうなのでしょう。日本はBEPSプロジェクトを立ち上げ時から一貫して主導してきたという自負があり、税制改正大綱などをみても、この問題については国際的議論が重要であることが繰り返し強調されています。米国との関係性や二国間租税条約の法的制約の問題もありますし、日本がDSTに踏み切るというのは、個人的にはなかなか簡単ではないように思います。他方、柱2については、基本的に国内税法として運用していくものであるため、米国が反対しても、欧州各国や日本としては粛々と進めていくというのが基本スタンスにはなると思います。ただし、米国は、柱2の一つである軽課税所得ルール(UTPR)を敵視しています。細かい話はここでは省略しますが、米国を拠点とする多国籍企業グループが欧州や日本に子会社を持つというケースで、このUTPRが発動されると、米国の視点からは、米国企業の所得が、米国以外の欧州や日本によって課税されると見られます。米国は、このような課税が二国間租税条約に違反した違法な措置であると主張し、欧州や日本に対して、懲罰的課税などの報復的措置をとる可能性があります。日本は、すでにUTPRに相当する制度の国内法制化を進めており、令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用するとしています。日本としては、欧州各国と協働しつつ、米国との摩擦を避けるための恒久的方策を考えていくことになるのではないかと予想しています。
このように、米国の大手企業の課税問題に端を発した国際的租税プロジェクトなのですが、結局米国は参加しないために柱1の中核はとん挫し、柱2についても米国を除いた国々の間で、しかも米国に迷惑をかけない範囲で行うというのでは、非常にもやもやしたものを感じざるを得ません。
佐藤:丁寧なご説明をありがとうございました。私自身は、数年前から、果たして米国は、自国企業の課税強化につながる話を受け入れるのだろうか、という点が疑問ではあり、私に限らず専門家の方々も、心のどこかではそういう不安を持っておられたかもしれません。国際協調ができるならば素晴らしいことだと思いますし、それを目指すべきだろうと思うのですが、課税に限らず安全保障の問題でも、歴史を振り返れば国際協調がうまく行く時代もあればそうではない時代もあり、人間社会は、やはり一筋縄では行かないのだろうということを改めて実感しています。今日のCFC税制のお話でも、日本の税制当局や課税当局は、課税上の弊害を除去しようという意図で動いており、企業の邪魔をしようという考えがあるわけではないのでしょうけれども、結果的に、企業サイドから見れば不都合を感じる場面が多い、ということが分かりました。制度設計というのもなかなか難しいものですね。私は、弁護士として実務現場に接する立場から、少し引いた立場でじっくり考えることが期待されるのであろう大学の場に転じましたので、片平先生のような実務の最前線にいらっしゃる方に教えていただきながら、いろいろと考えていきたいと思います。改めまして、貴重なお話をありがとうございました。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年 東京大学法学部卒業。2000年 弁護士登録。2005年 ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.)。2011年~14年 東京国税不服審判所(国税審判官)。2019年~22年 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授。2022年~現在 北海道大学大学院法学研究科教授。著書に、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、 『夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話』(共著、中央経済社、2020)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『対話でわかる租税「法律家」入門』(編著、中央経済社、2024)など。
片平享介 (かたひら きょうすけ)
ジョーンズ・デイ法律事務所オブカウンセル。2007年入所以来、15年以上にわたり、主に日本や米国の多国籍企業に対して国際税務に関するアドバイスを提供する。税務調査対応などの紛争解決のみならず、組織再編成、リストラクチャリング、CFC税制及び不動産取引などの分野において、プランニング段階や税制改正時の税務アドバイスを日常的に行っている。2014年ニューヨーク大学ロースクール卒業(修士、国際租税プログラム)後、ワシントンD.C.オフィスおよびニューヨークオフィスにて米国税務プラクティスにも従事した経験がある。Chambers Asia-Pacific、The Legal 500 Asia Pacific及びThe Best Lawyers in Japanにて日本の税務弁護士として選出されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























