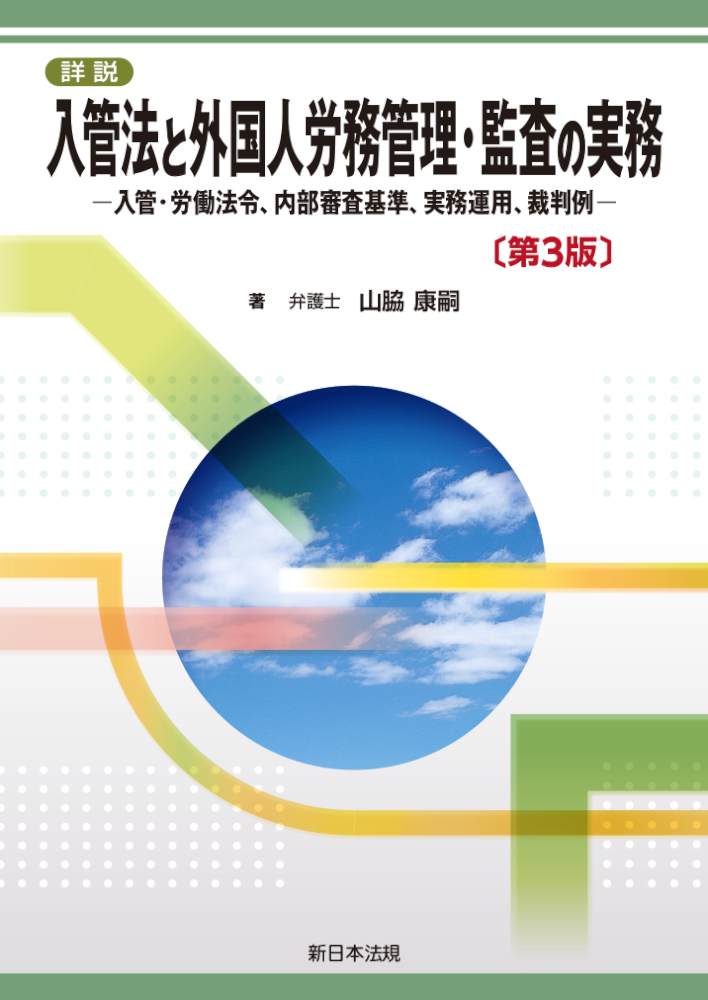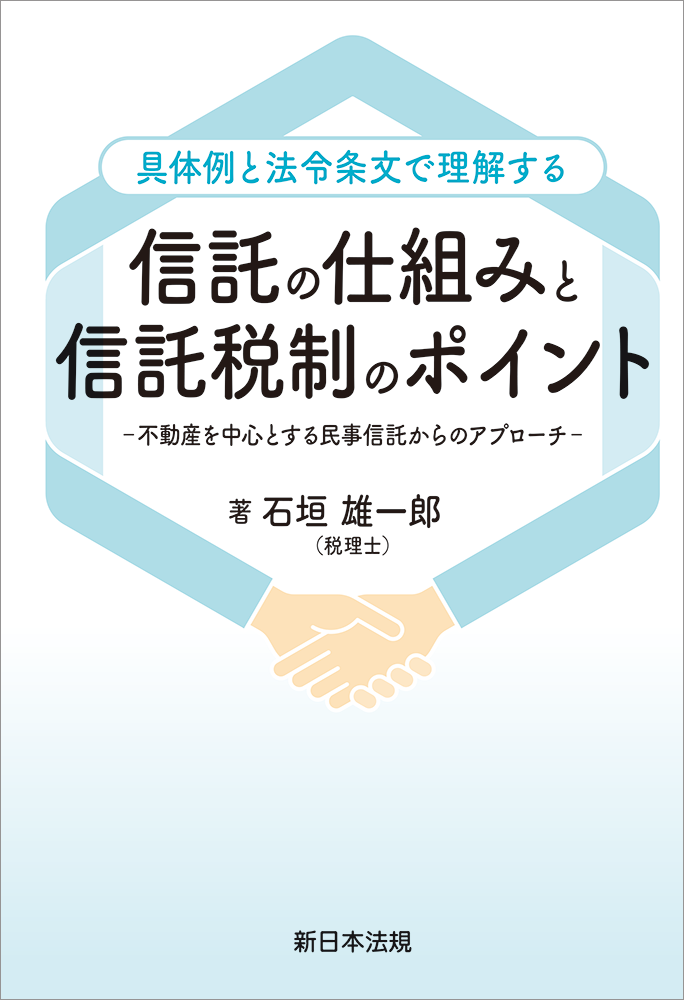解説記事2025年05月19日 解説 SSBJによるサステナビリティ開示基準の概要(1)(2025年5月19日号・№1074)
解説
SSBJによるサステナビリティ開示基準の概要(1)
サステナビリティ基準委員会 ディレクター 小西健太郎
サステナビリティ基準委員会 ディレクター 桐原和香
Ⅰ はじめに
2025年3月5日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、我が国最初のサステナビリティ開示基準(以下あわせて「SSBJ基準」という。)を公表した。
SSBJ基準は、SSBJのウェブサイト(脚注1)より入手可能である(日本語のみ)。また、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が開発したIFRSサステナビリティ開示基準(以下「ISSB基準」という。)との差異の一覧(脚注2)及び項番対照表(脚注3)も、日本語及び英語で公表している。
・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」(以下「適用基準」という。)
・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」(以下「一般基準」という。)
・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」(以下「気候基準」という。)
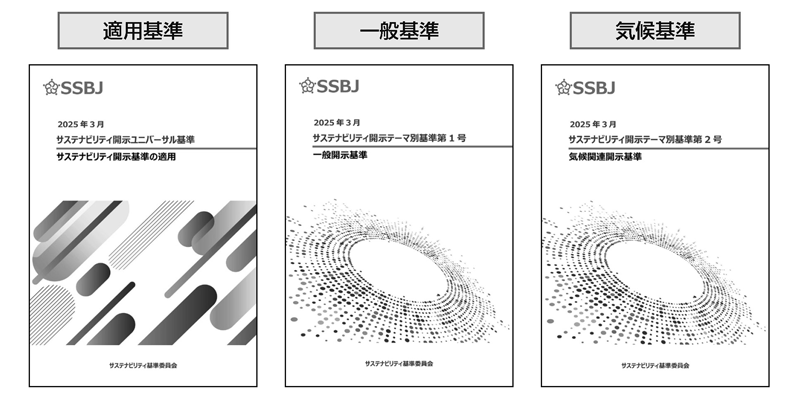
本稿では、SSBJ基準について3回に分けて概説する予定であり、第1回となる今回は、適用基準(適用時期及び経過措置を除く。)について説明する。
なお、本稿の意見にわたる部分は筆者の私見であり、SSBJの公式見解ではないことをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 適用基準の概要
※以下、本節の項番号は適用基準の項番号を示している。
1 目 的
適用基準の目的は、SSBJ基準に準拠したサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告する場合において、基本となる事項を示すことにある(第1項)。
2 範 囲
サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表に含まれる情報を補足し、補完するものであり、関連する財務諸表と一体で利用されることを想定している。
このため、SSBJ基準は、SSBJ基準に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告するにあたり、関連する財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(日本基準)に準拠して作成されているか、その他の一般に認められた会計原則又は実務に準拠して作成されているかにかかわらず、適用しなければならない(第2項及び第3項)。
3 報告企業及び関連する財務諸表
「報告企業」とは、財務諸表の作成を要求される又はこれを選択する企業をいう(第4項(1))。サステナビリティ関連財務開示は、図表1に示したように、関連する財務諸表と同じ報告企業に関するものでなければならない(第5項)。
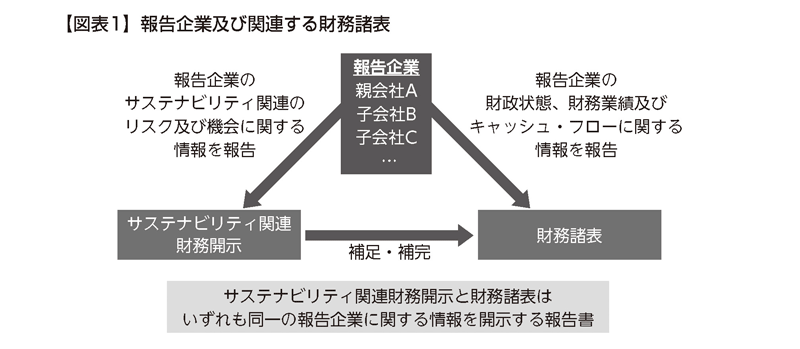
企業は連結財務諸表と個別財務諸表の両方を作成することがあるが、報告企業は、連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表に含まれる企業集団を意味しており(図表2参照)、連結すべき子会社が存在しないため連結財務諸表を作成していない場合は個別財務諸表を作成する企業を意味している(BC32項)。報告企業が連結財務諸表を作成している場合、サステナビリティ関連財務開示は、親会社とその子会社のサステナビリティ関連のリスク及び機会が理解できるものでなければならない(第6項)。
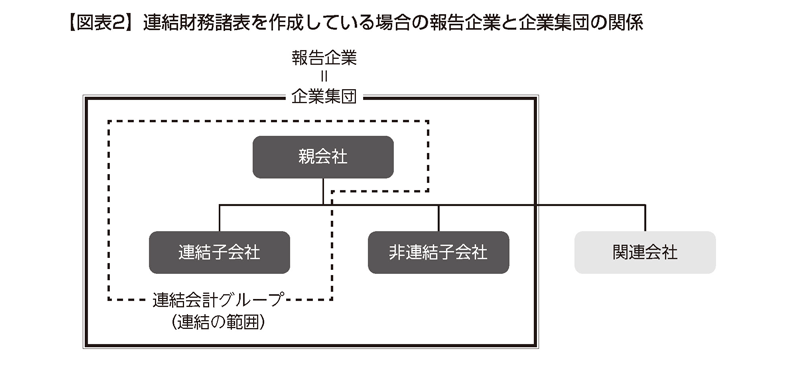
サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表を特定できるようにしなければならない。サステナビリティ関連財務開示と同じ文書において関連する財務諸表が報告されていない場合には、関連する財務諸表の入手方法及び関連する財務諸表の作成にあたり準拠した会計基準の名称を開示しなければならない(第7項)。なお、主要な利用者が、関連する財務諸表を特定できるのであれば、サステナビリティ関連財務開示の有用性は大きく変わらないと考えられるため、必ずしも同じ文書において報告することは要求されない(BC35項)。
4 法令との関係
SSBJ基準で要求する情報が、企業が活動する法域の法令によって開示することが禁止されている場合、これを開示する必要はない(第11項)。
5 商業上の機密情報
一定の要件を満たす場合、かつ、その場合に限り、サステナビリティ関連の機会に関する情報が商業上の機密であると企業が判断したときには、当該情報がSSBJ基準で要求する情報であり、また、当該情報に重要性があったとしても、これを開示しないことができる(第13項)。この定めはサステナビリティ関連のリスクに関する情報には適用されない(第16項)。
6 適正な表示
サステナビリティ関連財務開示は、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を適正に表示しなければならない(第20項)。SSBJ基準における具体的な定めを適用しただけでは、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を理解するうえで不十分である場合には、追加的な情報を開示しなければならない(第21項)。
7 集約及び分解
SSBJ基準の適用にあたり、すべての事実及び状況を考慮し、サステナビリティ関連財務開示において情報をどのように集約及び分解するのかを決定しなければならない。重要性がある情報を重要性がない情報で不明瞭にしたり、類似していない重要性がある項目を集約したりすることによって、サステナビリティ関連財務開示の理解可能性を低下させてはならない(第28項)。
8 つながりのある情報
次の種類のつながりを理解できるように情報を開示しなければならない(第29項)(図表3参照)。
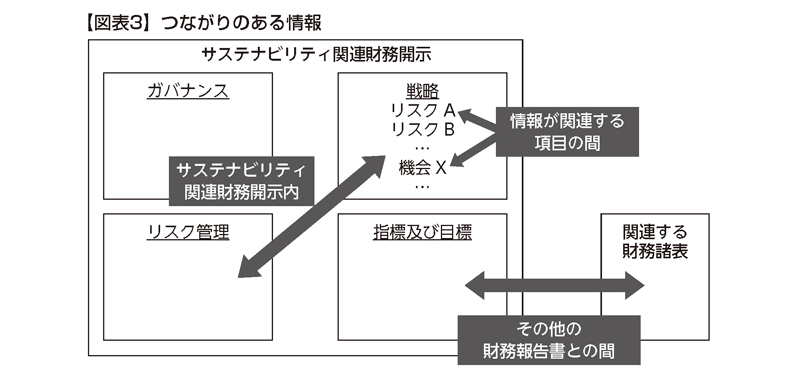
(1)その情報が関連する項目の間のつながり(企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得る、さまざまなサステナビリティ関連のリスク及び機会の間のつながりなど)
(2)サステナビリティ関連財務開示内の開示の間のつながり(ガバナンス、戦略、リスク管理並びに指標及び目標に関する開示の間のつながりなど)
(3)サステナビリティ関連財務開示と、その他の財務報告書(関連する財務諸表など)の情報との間のつながり
9 合理的で裏付け可能な情報
SSBJ基準が合理的で裏付け可能な情報を用いることを求めている場合、当該定めに従わなければならない(第32項)(図表4参照)。合理的で裏付け可能な情報は、外部環境の一般的な状況のみならず、企業に固有の要因も対象としなければならず、これには、過去の事象、現在の状況及び将来の状況の予想に関する情報が含まれる(第33項)。
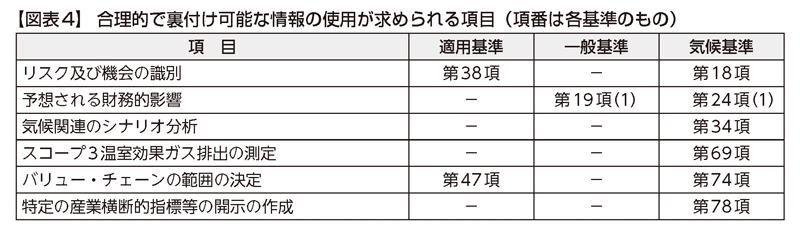
何が合理的で裏付け可能な情報であるかを判断するにあたり、次のことを行うことが考えられる(BC65項)。
(1)合理的に利用可能なすべての情報(企業が既に有している情報を含む。)を考慮しなければならない。また、既知の情報を無視することは禁じられる。
(2)情報を使用するための適切な基礎を有し、情報が裏付け可能となるように、SSBJ基準の定めを満たさなければならない。
(3)報告期間の末日において利用可能な情報(過去の情報、現在の情報又は将来予測的な情報(将来の状況の予想を含む。)など)を考慮しなければならない。
(4)情報の網羅的な探索を実施することは求められない(情報は過大なコストや労力をかけずに利用可能であるべきである。)。
10 サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示
(1)原則
サステナビリティ関連財務開示は、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を開示しなければならない。また、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得ないサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報については、開示する必要はない(第34項)。
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報を開示するにあたっては、まず、さまざまなサステナビリティ関連のリスク及び機会の中から、企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、そのうえで、識別したリスク及び機会に関する情報を識別するという2ステップの検討を行うことになる(図表5参照)。そのうえで、重要性の判断を踏まえ、サステナビリティ関連財務開示において開示する情報を決定する。
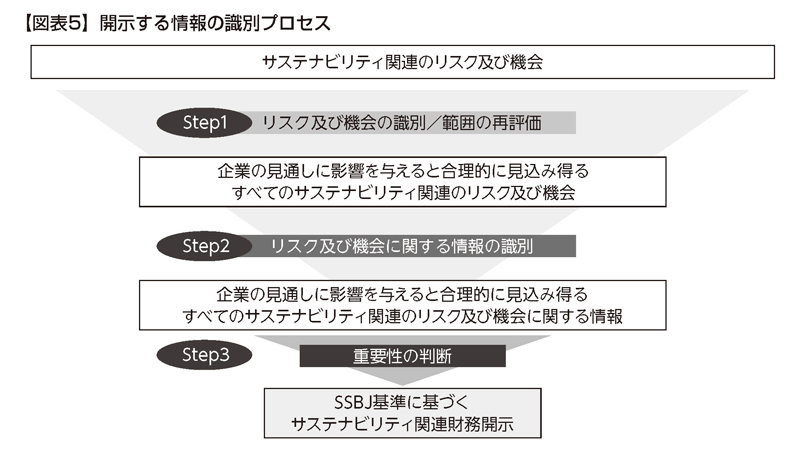
(2)サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別
① ガイダンスの情報源
企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別するにあたり、企業は次のことを行わなければならない。
(1)SSBJ基準を適用しなければならない(第40項)。
(2)IFRS財団が公表する「SASBスタンダード」(2023年12月最終改訂)における開示トピックを参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用する場合と適用しない場合とがある(第41項)。なお、「SASBスタンダード」が改訂された場合、SSBJ基準の改正前であっても、「SASBスタンダード」の原文を参照し、その適用可能性を考慮することができることとした(第42項)。
(3)次のガイダンスの情報源を参照し、その適用可能性を考慮することができる(第43項)。
i. ISSBが公表するISSB基準及び付属するガイダンス
ii. IFRS財団が公表する「水関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」及び「生物多様性関連開示のためのCDSBフレームワーク適用ガイダンス」(以下あわせて「CDSBフレームワーク適用ガイダンス」という。)
iii. 主要な利用者の情報ニーズを満たすように要求事項が設計されている他の基準設定主体(ISSBを含む。)による直近の公表文書
iv. 同じ産業又は地理的地域において事業を営む企業によって識別されたサステナビリティ関連のリスク及び機会
SSBJ基準は、ガイダンスの情報源に関する定めとして、「適用しなければならない」と定めているもの、「参照し、その適用可能性を考慮しなければならない」と定めているもの及び「参照し、その適用可能性を考慮することができる」と定めているものがある。それぞれの定めの違いを図表6にまとめている(適用基準BC78項)。
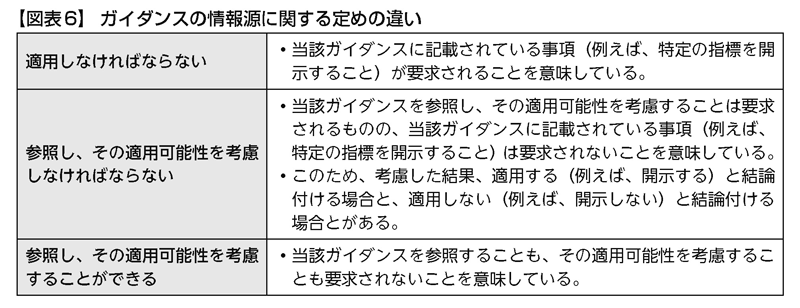
上述の「適用可能性を考慮しなければならない」という定めに関して、SSBJ基準は、考慮したガイダンスに記載されている事項について網羅的に検討することを想定していない。このため、例えば、どの産業に関するガイダンスを参照することとしたのか、当該産業に関するガイダンスに記載されているリスク及び機会のうち、どれを企業のリスク及び機会として識別したのか、当該産業に関するガイダンスにおけるリスク及び機会について記載されている指標等のうち、どれについて開示することとしたのか等について、その理由を検討することが考えられる(BC81項)。
なお、2024年3月に公表した公開草案では、企業がガイダンスの情報源を考慮した証跡を残すことが有用と考えられることから、SSBJ基準独自の定めとして、「適用可能性を考慮しなければならない」という定めを満たすために企業がどのような検討を行ったのか、その考慮の過程についての概要が理解できるものを、報告期間ごとに文書として明確にすることが考えられるという記載を結論の背景に含めることを提案していたが、SSBJ基準の内容を可能な限りISSB基準にあわせるため、この定めは削除している。
② サステナビリティ関連のリスク及び機会の範囲の再評価
重大な事象が発生した場合又は状況に重大な変化が発生した場合、バリュー・チェーンを通じて、影響を受けるすべてのサステナビリティ関連のリスク及び機会の範囲を再評価しなければならない(第44項)。より頻繁に再評価することもできる(第45項)。
(3)バリュー・チェーンの範囲の決定
サステナビリティ関連のリスク及び機会のそれぞれに関連して、バリュー・チェーンの範囲を決定しなければならない(第46項)。この範囲の決定にあたり、合理的で裏付け可能な情報を用いなければならない(第47項)。
(4)識別したリスク及び機会に関する重要性がある情報の識別
① 重要性がある情報の識別
識別したリスク及び機会に関して、重要性がある情報を開示しなければならない(第48項)。この際、まず、そのリスク又は機会に具体的に適用されるSSBJ基準を適用し、そのような基準が存在しない場合には、ガイダンスの情報源に関する定めを適用しなければならない(第49項)。
識別したリスク又は機会に具体的に適用されるSSBJ基準が存在しない場合、次のような情報を識別するために判断を適用しなければならない(第51項)。
(1)主要な利用者の意思決定に関連性がある情報
(2)そのリスク又は機会を忠実に表現する情報
この判断を行うにあたり、企業は次のことを行わなければならない。
(1)IFRS財団が公表する「SASBスタンダード」(2023年12月最終改訂)における開示トピックに関連する指標を参照し、その適用可能性を考慮しなければならない。考慮した結果、適用する場合と適用しない場合とがある(第52項)。なお、サステナビリティ関連のリスク及び機会の識別と同様に、「SASBスタンダード」が改訂された場合に、SSBJ基準の改正前であっても、「SASBスタンダード」の原文を参照し、その適用可能性を考慮することができることとした(第53項)。
(2)次のガイダンスの情報源を参照し、その適用可能性を考慮することができる(第54項)。
i. ISSBが公表するISSB基準及び付属するガイダンス
ii. IFRS財団が公表する「CDSBフレームワーク適用ガイダンス」
iii. 主要な利用者の情報ニーズを満たすように要求事項が設計されている他の基準設定主体(ISSBを含む。)による直近の公表文書
iv. 同じ産業又は地理的地域において事業を営む企業によって開示された情報
(3)主要な利用者が企業に資源を提供するかどうかに関する意思決定を行うにあたり有用であり、また、SSBJ基準と矛盾しない範囲で、次の情報源を参照し、その適用可能性を考慮することができる(第55項)。
i. GRIグローバル・サステナビリティ基準審議会(GSSB)が公表する「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード」(GRIスタンダード)
ii. 欧州連合(EU)の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に定められる「欧州サステナビリティ報告基準」(ESRS)
② 重要性の判断の行使
情報に重要性があるかどうか、すなわち、情報が主要な利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込み得るかどうかを評価するにあたり、それらの利用者の特性及び企業自身の状況を考慮しなければならない(第56項)。
重要性のある情報であるかどうかは、個別に又は他の情報と組み合わせて、企業のサステナビリティ関連財務開示全体の文脈において評価しなければならない。この評価にあたり、定量的要因と定性的要因の両方を考慮しなければならない(第57項)。
なお、情報に重要性がない場合、その情報を開示する必要はない(第22項)。
11 情報の記載場所
サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表とあわせて開示しなければならない(第62項)。
SSBJ基準で要求する情報は、一定の要件を満たす場合、相互参照によりサステナビリティ関連財務開示に含めることができる(第64項)。
12 報告のタイミング
(1)同時の報告
サステナビリティ関連財務開示は、原則として、関連する財務諸表と同時に報告しなければならない(第67項)。
(2)報告期間
サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表と同じ報告期間を対象としなければならない(第68項)(図表7参照)。
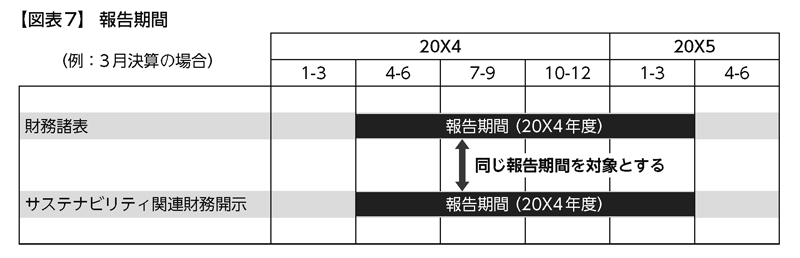
報告企業が連結財務諸表を作成している場合、親会社の財務情報の報告期間と、子会社等の財務情報の報告期間が異なるときには、サステナビリティ関連財務開示に取り込まれる親会社及び子会社等のサステナビリティ関連財務情報の報告期間は、それぞれの財務情報の報告期間と同じ期間を対象とすることになる(BC131項)(図表8参照)。
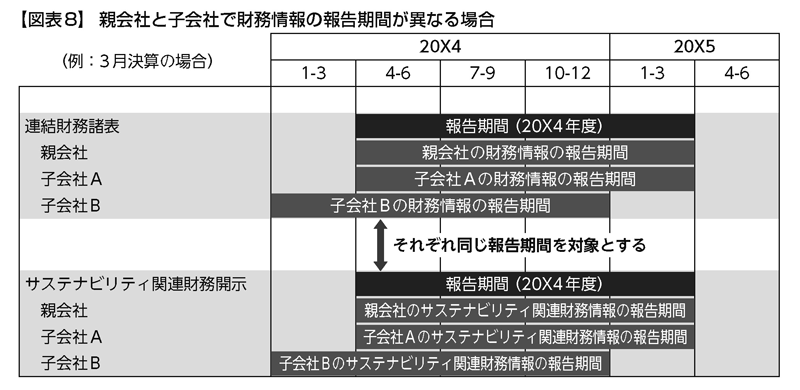
なお、2024年3月に公表した公開草案では、SSBJ基準独自の定めとして、企業が活動する法域の法令の要請により指標を報告することが要求されており、当該指標の報告のための算定期間がサステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と異なる場合、一定の要件をすべて満たすときは、当該指標の報告のための算定期間を用いて当該指標について報告することができるとする定めを追加することを提案していたが、SSBJ基準の内容を可能な限りISSB基準にあわせるため、この定めは削除している。
このため、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関連する指標として、企業が活動する法域の法令の要請により報告することが要求されている指標を用いることを選択する場合で、かつ、法令において定められている指標の報告のための算定期間が、サステナビリティ関連財務開示の報告期間とは異なるときでも、親会社及び親会社と同じ決算期の子会社については、指標の報告のための算定期間について、サステナビリティ関連財務開示の報告期間を対象とすることになると考えられる。
(3)公表承認日
サステナビリティ関連財務開示の公表承認日及び承認した機関又は個人の名称を開示しなければならない(第70項)。
(4)後発事象
報告期間の末日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までに報告期間の末日現在で存在していた状況について情報を入手した場合、新規の情報に照らして、当該情報に関連する開示を更新しなければならない(第71項)。
また、報告期間の末日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までに発生する取引、その他の事象及び状況に関する情報について、当該情報を開示しないことにより、主要な利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込み得る場合には、当該情報を開示しなければならない(第72項)。
13 比較情報
(1)比較情報の開示
当報告期間に開示されるすべての数値について、前報告期間に係る比較情報を開示しなければならない。また、当報告期間におけるサステナビリティ関連財務開示を理解するうえで有用である場合、説明的及び記述的なサステナビリティ関連財務情報に関する比較情報を開示しなければならない(第73項)。
(2)比較情報の更新
前報告期間に開示された見積りの数値に関連して、当報告期間において新規の情報を入手し、当該情報が前報告期間に存在していた状況に関する証拠を提供する場合、比較情報を更新し、関連する情報を開示しなければならない(第74項)。
14 準拠表明
サステナビリティ関連財務開示が、SSBJ基準のすべての定めに準拠している場合、明示的かつ無限定の準拠の旨を開示することにより表明しなければならない。SSBJ基準のすべての定めに準拠しない限り、サステナビリティ関連財務開示がSSBJ基準に準拠していると記述してはならない(第79項)。
法令の要請に基づきSSBJ基準に従った開示を行う場合、当該法令の名称を開示しなければならない。法令の要請に基づかず任意でSSBJ基準に従った開示を行う場合、その旨を開示しなければならない(第78項)。
15 判 断
数値の見積りを伴うもの(「16. 測定の不確実性」参照)とは別に、サステナビリティ関連財務開示を作成する過程で企業が行った判断のうち、サステナビリティ関連財務開示に含まれる情報に最も重大な影響を与える判断に関する情報を開示しなければならない(第81項)。
この定めに基づき開示する判断には、次のものが含まれると考えられる(BC158項)。
(1)企業の見通しに影響を与えると合理的に見込み得るサステナビリティ関連のリスク及び機会の識別
(2)どのガイダンスの情報源を適用するかの決定
(3)事象又は状況の変化が重大であり、企業のバリュー・チェーンを通じて、影響を受けるすべてのサステナビリティ関連のリスク及び機会の範囲の再評価が要求されるかどうかの評価
(4)サステナビリティ関連財務開示に含める重要性がある情報の識別
16 測定の不確実性
サステナビリティ関連財務開示で報告される数値に影響を与える最も重大な不確実性に関する情報を開示しなければならない(第83項)。
測定の不確実性に関して開示しなければならない可能性がある情報の種類及び範囲は、サステナビリティ関連財務開示で報告される数値の性質(すなわち、不確実性及びその他の状況の源泉並びにそのような不確実性及びその他の状況に寄与する要因)に応じて異なることが考えられるが、例えば、次のような開示を行う必要がある場合がある(BC162項)。
(1)仮定又はその他の測定の不確実性の源泉の性質
(2)開示された数値の、その計算の基礎となる手法、仮定及び見積りに対する感応度(その感応度の理由を含む。)
(3)不確実性について見込まれる解消方法及び開示された数値に対して合理的に考えられる結果の範囲
(4)開示された数値に関する過去の仮定について行った変更の説明(その不確実性が未解消のままである場合)
17 誤 謬
重要性がある過去の報告期間の誤謬について、これを訂正することが実務上不可能でない限り、開示された過去の報告期間の比較対象の数値を修正再表示することによって訂正しなければならない。ただし、法令において、開示された過去の報告期間の比較数値を修正再表示することによって訂正することで、過去の誤謬の解消ができない場合に該当するときは、修正再表示を行わず、当該法令に基づく取扱いに従う(第86項)。
Ⅲ 小 括
今回は、適用基準(適用時期及び経過措置を除く。)について概説した。次回は、一般基準(適用時期及び経過措置を除く。)及び気候基準(指標及び目標並びに適用時期及び経過措置を除く。)について説明する予定である。
脚注
1 https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html
2 (日本語)https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/ssbj_20250331_01.pdf
(英語)https://www.ssb-j.jp/en/wp-content/uploads/sites/7/ssbj_20250331_01_e.pdf
3 (日本語)https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/ssbj_20250331_02.pdf
(英語)https://www.ssb-j.jp/en/wp-content/uploads/sites/7/ssbj_20250331_02_e.pdf
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -