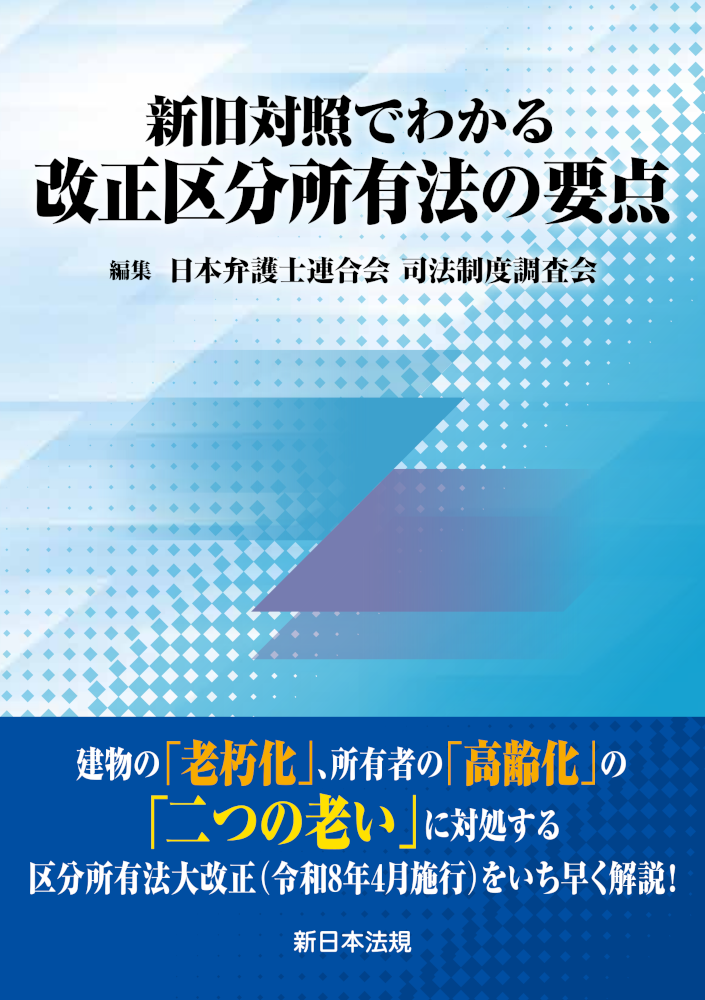解説記事2020年07月20日 最新判決研究 役員給与のうち「不相当に高額な部分」の算定方法(2020年7月20日号・№843)
最新判決研究
役員給与のうち「不相当に高額な部分」の算定方法
東京地裁令和2年1月30日判決(平成29年(行ウ)第371号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告)は、平成9年9月に設立、自動車の輸出入事業等を目的とする内国法人であるが、平成23年7月期から平成27年7月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)分法人税について、代表取締役甲に支給した定期同額給与(以下「本件役員給与」という。)の全額を損金の額に算入して確定申告をした。これに対し、処分行政庁は、本件役員給与には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分があり、同部分の損金算入を否認する各更正(以下「本件各更正」という。)等をした。Xは、本件各更正等を不服として、前審手続を経て、同(被告)に対し、当該処分の取消しを求めて本訴を提起した。
(2)甲は、Xの設立以来代表取締役を務めており、Xの発行済株式の総数を保有している。また、Xの役員は、甲のほか、その妻乙(取締役)及び乙の妹丙(代表取締役)である。本件各事業年度における甲らに対する役員給与の支給状況及び本件各更正において「不相当に高額な部分」とされた金額は、別表のとおりである。
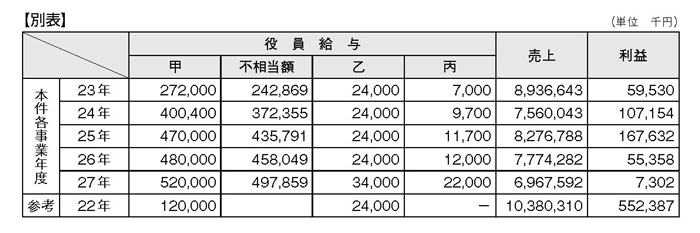
二、争点と当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件役員給与のうち「不相当に高額な部分」(法法34②)の有無及びその金額である。本件役員給与については、形式基準の金額を超える部分が存在しないため、実質基準の金額(同業類似法人の役員給与の支給状況等に照らして相当と認められる金額)を超える部分の有無及びその金額が問題となる。
2 国の主張
(1)Xにおける甲の職務の内容は、業務の全般的な指揮監督を行うとともに、マレーシアにおいて自動車販売事業者の新規取引先の開拓営業などを行うといったものであるから、中古自動車販売等を目的とする一般的な法人の役員において想定される職務の範囲内にあるということができる。また、別表のとおり、Xの売上金額、売上総利益、営業利益は、いずれも減少傾向にあり、平成22年7月期と平成27年7月期を比較すると、売上金額は約3分の2に、売上総利益は約7割に、営業利益は約75分の1にそれぞれ大きく減少している。
さらに、Xの使用人に対する給与(9~12名、1人当たり205万円~280万円)も減少傾向にあり、平成22年7月期と比較すると、総額で平成27年7月期は2分の1以下に大きく減少しており、他方で、別表のとおり、甲に対する役員給与は、大幅な増加傾向にあり、平成22年7月期(1億2000万円)と比較すると、平成23年7月期は2倍以上、平成27年7月期は4倍以上となっている。本件役員給与は、使用人給与の合計額と比較すると、平成23年7月期は約8倍、平成27年7月期は約23倍と大きな差があり、また、後述するように、Xが所在する埼玉県下から抽出した類似法人6~8法人(以下「本件各抽出法人」という。)の役員給与の平均額と比較すると、約9倍から約23倍、本件各抽出法人の役員給与の最高額と比較しても、約4倍から約11倍というやはり大きな差があることが認められる。
以上の諸点に鑑みれば、甲が現実に果たした役割、使用人との職務の違い、同業類似法人における役員の職務の内容等と多少の差異があり得ること等を考慮しても、本件役員給与に「不相当に高額な部分」があることは明らかである。
(2)主位的主張
役員給与として相当と認められる金額の算定に当たっては、本件各抽出法人の役員給与が参考となるところ、一般に、①職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性を排除することによって適正な課税を実現するという法人税法34条2項の趣旨や、②当該同業類似法人に存在する諸要素の差異やその個々の特殊性を捨象し、より平準化された数値を得るのが望ましいこと、③更には上記(1)で検討した諸要素をも併せ考慮すれば、同業類似法人における役員給与の平均額を超える部分が「不相当に高額な部分」の金額に当たると解するのが相当である。
(3)予備的主張
仮に、前記主位的主張が認められないとしても、本件各抽出法人の役員給与の最高額を超える部分が「不相当に高額な部分」の金額に当たると解すべきである。
3 Xの主張
(1)国は、その検討過程において、①前記のとおり、甲の職務の内容が中古自動車販売等を目的とする一般的な法人の役員において想定される職務の範囲内にあるとの事実誤認をしており、また、②後記のとおり、Xの同業類似法人とは認められない本件各抽出法人を比較の対象としているのであるから、国の検討結果が合理的な根拠を欠くものであることは明らかであって、本件役員給与の額に「不相当に高額な部分」があるとは認められない(主位的主張)。
仮に、本件役員給与の額に「不相当に高額な部分」があるとしても、本件各事業年度における売上金額や改定営業利益が、平成21年7月期及び平成22年7月期(本件各事業年度のうち最も早い平成23年7月期の前年度及び前々年度)の平均額(売上金額83億3560万3292円、改定営業利益4億4567万7524円)とおおむね同水準又はそれ以上であることに鑑みれば、役員給与として相当と認められる金額は、平成21年7月期及び平成22年7月期において甲に支給された役員給与の平均額(1億2800万円)を下回るものではないから、「不相当に高額な部分」の金額は、上記平均額を超える部分に限られるというべきである(予備的主張)。
(2)甲の職務の内容について検討すると、Xの顧客の大半はマレーシアの中古自動車販売業者であるところ、甲は、マレーシアに在留し、①顧客の意向把握、②把握した意向に沿う中古自動車をオークションで落札するための使用人への指示、③落札した自動車の顧客への売却等の中古自動車販売に必要な業務を一手に行うとともに、④広告宣伝活動、⑤顧客との信頼関係構築活動、⑥顧客から寄せられたクレームへの対応、⑦顧客に対する支払の催促といった附随業務についても自ら行っていた。また、マレーシアに在留しているXの役員ないし使用人は、甲のほか乙のみであった。このように、甲は、Xの事業面における業務全般を1人で担当していたのであって、その結果、Xは、上場企業等と資本関係が一切ないにもかかわらず、本件各事業年度において、極めて高い業績(売上金額が約69億6000万円~約89億3000万円、改定営業利益が約3億3000万円~約6億3000万円)を達成したのであるから、甲の職務の内容が、中古自動車販売等を目的とする一般的な法人の役員において想定される職務の範囲を大きく超えるものであったことは明らかである。このことは、売上金額がXと同規模である同地域・同業種の法人の一般的な従業員数(92名~118名程度)に比べ、Xの従業員数(9名~12名)が著しく少ないことからもうかがわれるというべきである。したがって、甲の職務の内容が「中古自動車販売等を目的とする一般的な法人の役員において想定される職務の範囲内にある」ことを前提に行われた国の検討結果は、合理的な根拠を欠くものというべきである。
(3)本件各抽出法人は、後記①~⑤のとおり、Xと「同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの」に当たらないことは明らかである。また、本件各抽出法人の抽出に用いられた本件抽出基準の内容自体も不合理というべきである。
① 従業員数が著しく異なること
Xが9~12人であるのに対し、本件各抽出法人は48人から385人となっているなど、従業員数が著しく異なる。
② 改定営業利益が著しく異なること
Xが約4億3000万円~約6億4000万円であるのに対し、本件各抽出法人の中には、赤字法人もあり、本件事業年度を通じて約600万円から約3800万円というのもある。
③ 従業員単位売上等が著しく異なること
Xが従業員1人当たりの改定営業利益が約3億5000万円~約7億円であるのに対し、本件各抽出法人は全体的に低く、中には、約24万円~約46万円のものもある。
④ 他の企業からの独立性を欠くこと
Xが他の企業から完全に独立しているのに対し、本件各抽出法人の5社は他の企業から独立性を有せず、実質的には、企業グループの一部門にすぎないものもある。
⑤ 主たる事業の内容が異なること
本件各抽出法人の7社は、Xとは仕入方法、商品、販売先等の主たる事業内容が大幅に異なる。
三、判決要旨
請求棄却。
(1)当裁判所は、本件役員給与には法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分」があり、Xの同業類似法人と認められる本件各抽出法人の役員給与の最高額を超える部分がその金額に当たるため、同部分を損金の額に算入することはできず、このことを前提に計算された本件各事業年度の本件各更正は適法であり、Xの請求はいずれも理由がなく棄却すべきものと判断する。その理由は、以下のとおりである。
(2)法人税法34条1項は、同法22条3項2号の別段の定めとして、内国法人がその役員に対して支給する給与(役員給与)のうち、所定の例外として定める給与に該当しないものの額は、損金の額に算入しない旨規定する。さらに、上記例外に係る役員給与(例えば、同項1号に定める定期同額給与)についても、同条2項は、「不相当に高額な部分の金額」として政令で定める金額は損金の額に算入しない旨規定する。役員給与は、同法22条3項2号に規定された費用の一種ではあるものの、法人と役員との関係に鑑みると、役員給与の額を無制限に損金の額に算入することとすれば、法人において役員給与の支給額をほしいままに決定し、法人の所得の金額を殊更に少なくすることにより、法人税の課税を回避するなどの弊害が生ずるおそれがある。そこで、法人税法34条は、上記別段の定めを設け、損金の額に算入される役員給与を上記のような弊害がないと考えられるものに限定することにより、役員給与の金額決定における恣意性の排除を図り、もって課税の公平性を確保したものと解される。
そして、法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条1号は、同項にいう「不相当に高額な部分の金額」につき、①内国法人が各事業年度において役員に対して支給した役員給与の額が、(a)当該役員の職務の内容、(b)当該内国法人の収益及び使用人に対する給与の支給の状況、(c)当該内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの(同業類似法人)の役員給与の支給状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額(実質基準の金額。同号イ)を超える額又は②同号ロに定める形式基準の金額(株主総会の決議等により定められた役員給与の限度額)を超える額のうち、いずれか多い金額とするものと規定している。
そこで、形式基準の金額を超える額が存在しない本件役員給与については、法人税法施行令70条1号イの規定する実質基準に従って、同基準の金額を超える場合に当たるか否か、これに当たる場合の超える部分の金額はいくらであるかが問題となる。
(3)甲は、Xの一人株主であり、設立当時から代表取締役として、Xの業務の全般的な指揮監督を行っている。その業務内容を具体的にみると、甲は、中古自動車の輸出先国であるマレーシアに居住して、クライアントに対する事実上の受注獲得業務である意向聴取業務を行い、Xにおける受注の8~9割を獲得しているところ、このような受注の獲得は、甲がクライアントのプロモーションイベントの企画を発案するなどしてその販売促進に協力することによって可能となったものであり、Xが本件各事業年度において60億円を超える売上げを得ることができた大きな要因となったものといえる。また、販売に必要な中古自動車のオークションにおける落札業務は、オークション担当の従業員が行っているが、甲はこれらの従業員に対して必要な指示を行い、これにより、クライアントの意向に沿った中古自動車をできるだけ利益の出る価格で落札することが可能となったといえる。さらに、甲は、このように落札した中古自動車を販売するほか、販売後にクライアントから寄せられたクレームに対応し、売買代金の支払が滞っているクライアントに対して支払の督促をするなどの業務も行っているところ、甲の迅速かつ適切なクレーム対応によりクライアントのXに対する信頼は一層強固なものとなり、また、甲による小まめな売掛金回収により、貸倒れ損失等の発生を防ぐことができたといえる。
これらの事実関係からすれば、甲は、Xのオーナー経営者として、Xの主たる業務(マレーシアへの輸出業務)全般を差配するとともに、クライアントに対する営業を行って受注の大半を自ら獲得するなどしてXの収益に多大な貢献をしたと評価することができる(なお、甲の妻である乙及び甲の弟である丁も意向聴取業務や販売業務等を行っているが、上記の事実に照らせば、Xの業務における両名の役割は限定的なものにとどまると考えられるから、両名の業務活動をもって、甲の職務内容に係る上記の評価が左右されるものではない。)。
他方、Xの本社は日本国内にあり、Xの従業員は、その全員が日本国内において、中古自動車のオークションにおける落札業務のほか、クライアントとの書類のやり取り、自動車部品の調達、中古自動車の輸出に係る各種の手続、経理処理といった業務に従事している。
そして、①甲はマレーシアに居住しており、本件各事業年度において日本に入国したのは、3~6か月に1回程度であり、夏季を除くと、日本における滞在期間もそれほど長くはないこと、甲が、自己と姻戚関係を有するもの(妻の妹)であり、金融機関の中間管理職という職歴を有している丙を代表取締役として迎え入れ、財務、経理、人事、総務等の管理業務を任せていること等の事実関係に照らせば、Xの日本国内における業務は、上記で触れた落札業務の点を除き、専ら丙が差配していると認めるのが相当である。
以上のとおり、甲は、マレーシアにおいてXの業務の全般的な指揮監督を行い、クライアントに対する営業を行って受注の大半を自ら獲得するなどしていた一方、Xの日本国内における業務の多くを、丙や従業員に委ねていたものであるところ、このような甲の職務の内容は、中古自動車販売業を目的とする法人において、営業や販売を担当する役員について一般的に想定される職務の範囲内にあるものであって、これと質的に異なるものとはいえない。甲が、受注の大半を自ら獲得していた点についても、Xのような小規模の同族会社においては、必ずしも珍しいことではない。
もっとも、本件各事業年度におけるXの売上金額が約69億円から約89億円に及んでいたことや、各業務において甲が行っていた具体的な活動の内容に鑑みれば、Xの売上げを得るために甲が果たした職責及び達成した業績は、中古自動車販売業を目的とする法人において一般的に想定される職務の範囲内でも、相当高い水準にあったということができる。
(4)次に、使用人(従業員)に対する給与の支給額についてみると、本件各事業年度を通じて横ばいないし緩やかな減少傾向となっており、その平均支給額(使用人1人当たりの金額)は、最も高額なときでも年間300万円に満たない。また、他の役員である乙及び丙に係る役員給与をみても、最も高額となった平成27年7月期で、それぞれ3400万円と2200万円であり、本件各事業年度を通じた増加幅も、それぞれ1.4倍(1000万円)と3.1倍(1500万円)にとどまっている。
一方で、本件役員給与は、本件各事業年度の最初の年度(平成23年7月期)が2億7200万円であったのを除き、いずれの年度も4億円を超えており、最後の年度(平成27年7月期)に至っては5億2000万円に達し、平成22年7月期の1億2000万円と比べても、本件各事業年度を通じて約2~4倍、金額にして4億円増加している。
このように、売上金額及び売上総利益が減少傾向にある一方で、本件役員給与が増加していることから、改定営業利益に占める本件役員給与の割合は、平成22年7月期が17.8%であったのに対し、平成25年7月期が73.7%、平成27年7月期は98.6%と急伸している。その結果、Xの営業利益は大きく圧迫され、平成22年7月期が約5億5000万円であったのに対し、本件各事業年度では、最も高額であった平成25年7月期ですら約1億6700万円(平成22年7月期の30.3%)にすぎず、最も低額であった平成27年7月期に至っては約730万円(平成22年7月期の1.3%)となっている。
以上のとおり、本件役員給与は、他の役員に支給された役員給与と比べて著しく高額であるばかりでなく、Xの収益が、本件各事業年度を通じて減少傾向にあり、使用人に対する給与の支給額も横ばいないし緩やかな減少傾向にある中で、これに逆行する形で急増しており、その結果、Xの改定営業利益の大部分を占めることとなって、Xの営業利益を大きく圧迫するに至っているのである。このことに鑑みると、上記のような甲の職務内容やXの売上げを得るために甲が果たした職責等に照らしても、本件役員給与の額の高さ及び増加率は著しく不自然であると評価せざるを得ない。
(5)国は、本件抽出基準等に基づいて本件各抽出法人を抽出しているところ、その概要は、①埼玉県内の各税務署の管轄区域を対象に、②日本標準産業分類における大分類「Ⅰ-卸売業、小売業」の中分類「54-機械器具卸売業」の小分類「542 自動車卸売業」を基幹の事業とし、③売上金額がXの売上金額の2分の1から2倍までの範囲にある法人で、④代表取締役に対して役員給与の支給があり、かつ、争訟の係属していないものであることを要するというものである。
そこで、本件抽出基準等の合理性を検討すると、①Xは、埼玉県幸手市に本店を置く株式会社であるところ、Xと所在地域を同じくする埼玉県内の各税務署の管轄区域を対象に同業類似法人を抽出することは合理的といえる。また、②Xは中古自動車の輸出販売を主な事業とする株式会社であるところ、日本標準産業分類は、統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として設定された統計基準であり、全ての経済活動を産業別に分類したものであるから、同分類においてXと同種の事業と考えられる小分類「542 自動車卸売業」を基幹の事業とする法人を抽出の対象とすることは合理的といえる。さらに、③事業規模を測るに当たっては、売上金額が一つの指標となると考えられるから、売上金額がXの売上金額の2分の1から2倍までの範囲にある法人を抽出の対象とすることは合理的といえる。加えて、④Xの同業類似法人を抽出する目的は、代表取締役である甲の役員給与に「不相当に高額な部分」があるか否かを判断する際の比較対象を得る点にあるのだから、代表取締役に対して役員給与の支給があり、かつ、争訟によって比較対象に係る事実関係が変動する可能性のない法人を抽出の対象とすることは合理的といえる。
以上のとおりであるから、本件抽出基準等は、Xの同業類似法人を抽出する基準及び抽出対象区域として合理的なものである。
(6)Xの同業類似法人である本件抽出法人の役員給与の支給状況は、各期を通じ684万円~7725万円である。本件役員給与の支給状況と本件抽出法人の役員給与の支給状況とを比較すると、平成23年7月期に係る本件役員給与の額は、これに対応する調査対象事業年度における本件各抽出法人の最高額と比較しても約4倍、金額にして約2億円高額となっている。しかも、本件役員給与は本件各事業年度を通じて2~4倍増加したため、両者の較差は年度ごとに拡大し、平成27年7月期に係る本件役員給与の額は、本件各抽出法人の最高額の約10倍、金額にして約4億7000万円高額となるに至っている。このような役員給与の支給状況の較差は、上記のような甲の職務内容やXの売上げを得るために甲が果たした職責等を踏まえても、合理的な範囲を超えるものといわざるを得ない。
(7)以上検討したところによれば、Xにおける甲の職務の内容は、中古自動車販売業を目的とする法人において営業や販売を担当する役員について一般的に想定される職務の範囲内にあるとはいえ、Xの売上げを得るために甲が果たした職責及び達成した業績は相当高い水準にあったということができる。
しかしながら、Xの収益が、本件各事業年度を通じて減少傾向にあり、使用人に対する給与の支給額も横ばいないし緩やかな減少傾向にある中で、本件役員給与は、これに逆行する形で急増し、Xの改定営業利益の大部分を占め、Xの営業利益を大きく圧迫するに至っており、その額の高さ及び増加率は著しく不自然であるし、合理的な抽出過程により抽出されたXの同業類似法人である本件各抽出法人の役員給与の最高額と比較しても、その較差は合理的な範囲を超えるものとなっている。そして、このように不自然に高額な本件役員給与によって、Xが本件各事業年度において納付した法人税の額は、本来よりも大きく圧縮されることとなっているのであるから、Xが本件役員給与の全額を損金の額に算入したことにより、課税の公平性は著しく害されているというほかない。
以上によれば、本件役員給与に「不相当に高額な部分」があることは明らかというべきである。そして、その部分の金額は、上記のとおりXの売上げを得るために甲が果たした職責及び達成した業績が相当高い水準にあったことに鑑み、当該調査対象事業年度における本件各抽出法人の役員給与の最高額を超える部分がこれに当たると認めるのが相当である。
この点、国は、その主位的主張として、本件役員給与のうち「不相当に高額な部分」に当たるのは、本件各抽出法人の役員給与の平均額を超える部分であると主張する。しかしながら、本件抽出基準等によるXの同業類似法人の抽出が必ずしも厳密な事業の規模ないし性質の同一性の要求の下にされたものではないことは、上記に説示したとおりであるところ、Xの売上げを得るために甲が果たした職責及び達成した業績等の本件における事業に鑑みると、上記の平均額を超える部分を全て「不相当に高額な部分」に当たるものとした場合、甲の職務に対する対価として不相当と認めるべきでない部分が含まれることになってしまうおそれがある。そうすると、上記のような本件の事情の下では、本件各抽出法人の役員給与の最高額を超える部分をもって「不当等に高額な部分」に当たると認めるのが相当であるから、国の上記主張は採用することができない。
四、解説
はじめに
50年程前、筆者は、国税局調査査察部で法人税の調査を担当したことがある。従業員300人程の製造会社を調査した際、経理課長に対し、「社長の報酬が類似法人に比し相当多額であるので、不相当に高額な部分を否認する」と告げたことがある。その時、経理課長から、「あなたに社長の働きが解りますか? 社長の卓抜した経営手腕によって他社よりもはるかに業績もよく、従業員を満足させている。他社の社長と比較してとやかく言われる筋合は無い」と言われた。その剣幕に引き下がった苦い思い出がある。
それ以降、役員報酬課税に関する裁判例・判決例を普く調べ何冊か本にまとめたことがある。しかし、今もって、役員報酬(給与)の適正額(相当額)が幾許であるかについて、正確には理解できないでいる。
本件においては、いわばワンマン会社と言える中小企業の代表取締役の役員給与(本件役員給与)のうち、損金不算入となる「不相当に高額な部分」が幾許であるかが争われたものである。国の主張も、本判決の判示も、従前の裁判例に沿った月並なものと言えるが、これによって、筆者の冒頭に述べた疑問が晴れたわけではない。また、本件の会社代表者が非居住者と想定されるところ、その場合の役員給与の否認方法にも考えさせられるところがある。
以下、本件の事実関係に沿って、役員給与の相当額の算定方法等について論じることとする。
1 役員給与の損金不算入
(1)平成18年改正前の旧法人税法では、役員報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺい仮装して経理したものは、損金不算入とされ(旧法34①②)、役員賞与は損金不算入とされ(旧法35①)、役員退職給与の額のうち、損金経理をしなかった金額及び損金経理をした金額で不相当に高額な金額は、損金不算入とされていた(旧法36)(注1)。
ところが、平成17年に制定された会社法の下では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価が一括して「報酬等」として括られ、その報酬等が定款の定め又は株主総会の決議によって律せられることとなった(会社法361)。これは、役員賞与が利益処分でないこと、そして、退職慰労金も職務執行の対価である限り、報酬等に含まれることを意味している。そのため、企業会計基準委員会も、平成17年11月29日付で、「役員賞与に関する会計基準」を発し、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。」(同基準3)ことを明確にした(注2)。
かくして、平成18年に法人税法が改正され、同法34条は、そのタイトルを「過大役員報酬の損金不算入」から「役員給与の損金不算入」に改められ、同条が定める定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与以外の給与を損金不算入とし(法法34①)、かつ、役員給与の額のうち不相当に高額な部分の金額及び事実を隠蔽・仮装して支給する給与の額を損金不算入とした(法法34②③)。更に、同法35条は、特殊支配同族会社の業務主宰役員に支給する給与については、当該給与に係る所得税法28条3項に定める給与所得控除額相当額について損金不算入とした(旧法法35)。
(2)かくして、平成18年改正法の法人税法34条以下の役員給与課税の規定については、前述のように、会社法及び企業会計基準が、従前利益処分と解されてきた役員賞与を含めて役員報酬全額を費用処理としているにもかかわらず、役員給与を原則損金不算入とするなどの不合理性を指摘されてきたところであり(注3)、同法35条については、平成22年に廃止されたところである。その後も、法人税法34条の規定については、違憲論争を惹起することもある。
例えば、東京地裁平成28年4月22日判決(平成25年(行ウ)第5号)(注4)及び東京高裁平成29年2月23日判決(平成28年(行コ)第205号)では、法人税法34条2項及び同法施行令70条が納税者の予測可能性等が保障されていないことを事由に憲法84条、31条及び14条に違反することが争われたが、前掲各判決は、納税者側の主張を排斥している。
もっとも、租税法規の違憲問題については、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)(注5)が、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないというべきである。」と判示して以降、それが判例法として機能し、各裁判所は違憲判断について極めて消極的になっている(注6)。そのため、前掲の東京地裁平成28年4月22日判決も、法人税法34条2項等の規定につき、当該「規定の趣旨に照らして考慮すれば、納税申告の時点において、「不相当に高額な部分の金額」について、必ずしも確定的な金額までは判示しないとしても相応の予測は可能であるというべきである。」と判示し、違憲主張を退けている。
もっとも、このような法廷での合憲判断はともかくとして、法人税法34条に規定する「役員給与損金不算入」については、前述のように、種々の問題点を有しているところであるので、当該立法政策の合理性の有無と解決の方向性については引き続き検討する余地がある(注7)。
2 役員給与の「不相当に高額な部分」の算定方法
(1)法人税法34条2項は、「内国法人がその役員に対して支給する給与(〈略〉)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。そして、同法施行令70条1号イは、役員に対する退職給与以外の給与の相当額につき、「当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額」と定めている。
また、同条1号ロは、定款の規定又は株主総会等の決議によって役員給与の限度額等を定めているときは、当該限度額を超える役員給与の額を損金不算入と定めている。この規定については、形式基準と称されるのであるが、本件においては、当該基準が満たされているので、問題にはなっていない。
(2)かくして、役員給与(退職給与を除く。)の相当額については、①当該役員の職務内容、②当該法人の収益状況、③使用人に対する給与の支給状況、④類似法人における役員給与の支給状況等に照らして判断されることになるが、実務的には、④の類似法人との比較が最も多用される。この場合、類似法人の範囲をどのように選定するか、選定した類似法人の役員給与支給額と比準する場合に、その最高値を採るのか、平均値を採るのか、あるいは、他の数値を採るのか、等が問題となる。
一般的には、類似法人の選定については、同じ国税局管内等において、類似する業種に属する法人のうち、主として、売上規模等において倍半基準が採用される場合が多く、比準する給与額については、平均値を採用する場合が多い。この場合に問題となるのは、そもそも類似法人の選定が不透明であるということである。国(処分行政庁)は、課税処分又は争訟過程において、然るべき類似法人を選定することができるが、納税者側からすると、そのような類似法人が存在するか否かも確認できないわけである。そのため、前記1で述べたように、類似法人との比準を中核とする法令それ自体が明確性を欠き、納税者側の予測可能性が保障されていないということで、違憲問題を惹起することになる。また、売上規模のみを基にした倍半基準による類似法人の選定については、役員給与が売上に応じて支給されるものではないので、常に合理性があるとは言い難いであろう。
更に、比準すべき給与額について類似法人の平均値を採用することについては、そもそも各役員の役務提供力の個別性を否定することになるので、到底合理性があるとは認め難い。そのため、そのような平均値との比準そのものを否定する裁判例(注8)も見受けられ、あるいは、課税段階でも、当該平均値に相当のアローアンスを見込んで相当額を算定している事例(注9)も見受けられる。
3 税負担を考慮した適正額
(1)ところで、本訴において直接問題になっているわけではないが、本件におけるXのように、代表取締役が発行済株式数の全額を所有し、他の役員も全て親族で占めているような個人類似法人においては、役員報酬の支給額の決定において、当該役員報酬に係る所得税額と法人税額の合計額が最小になるようにするのが得策であると考えられる。この場合、通常、当該所得税の税率よりも当該法人税の税率の方が低いため、一般に、役員報酬や配当の支払いを抑えて、当該法人に所得を留保しておく必要がある。そのため、むしろ、その弊害を是正するために、同族会社に対する留保金課税制度が設けられているはずである。
本件におけるXの平成27年7月期において、甲に対する給与が5億2000万円で、Xの所得が1079万円余で納付すべき税額が121万円となっている。この5億2000万円に単純に所得税と住民税の最高税率55%を適用すると、甲は、2億8600万円の所得税負担が生じ、前述の法人税額121万円余を合計すると、Xと甲の所得課税総額は2億8721万円余となる。他方、法人税の否認を受けないように、甲の給与を7000万円に抑え、差額の4億5000万円をXの所得とすると、概算で、所得税の平均税率50%、法人税の実効税率28%とすると、甲の所得税額が3300万円程度で、Xの法人税額1億2900万円程度と見積もられるので、合計1億6200万円となる。本件各抽出法人の役員給与の支給額が相対的に低いのは、このようなことも考慮されているはずである。そうすると、Xと甲の税負担は、1億2500万円程軽減することができる。そうなると、法人税法34条2項が、役員給与のうち「不相当に高額な部分の金額」を損金不算入とする意義も薄れることになる。
(2)このように、一般的には、個人類似法人においては、代表者個人と当該法人の税負担の最小化(数値的には、当該個人の所得税の限界税率と当該法人の法人税の限界税率を同一にすればよい。)を図るため、代表者の報酬を不当に高額にしない方が得策となる。にもかかわらず、本件の場合には、甲が高額な報酬を得ているため、そのような最小化が図られていない。
その理由は、本訴で問題にされているわけではないが、甲が所得税法上の非居住者に該当するからであると考えられる。本訴で審理にされているわけではないので、詳しい事実関係は承知できないが、甲は、乙と共にマレーシアに滞在し、年数回しか来日していないようであるので、非居住者に該当するものと考えられる。そうなると、甲が負担する我が国の所得税額は、Xが源泉徴収する報酬の20%の源泉所得税で済むことになる。そして、甲とXの所得課税額の合計は、Xに所得を留保しないで、甲ができる限り多くの報酬を得た方が最小化になる。もっとも、このような仮説が成立するためには、甲が得た本件役員給与がマレーシアで国外源泉所得として累進税率の対象にならないことを前提にしている。
ともあれ、このような問題は、不相当に高額な役員給与の損金不算入を定める法人税法34条2項の規定のあり方と解釈のあり方に一石を投じるものと考えられる。
4 本件役員給与の相当額
(1)本件においては、別表にみられるように、本件各事業年度になってから、Xの売上、利益がそれ以前よりも減少・停滞しているにもかかわらず、甲の役員給与のみそれ以前の2倍強から4倍強に引き上げられ、その支給額も数億単位で他の中小法人では考えられない程の金額となっている。そのため、処分行政庁は、Xが所在する埼玉県内に所在する同業類似法人(本件各抽出法人)計10社を選定し、本件各事業年度のそれぞれの事業年度において、本件各抽出法人の役員給与支給額の最高額を上回る部分を「不相当に高額な部分」と認定し、本件各更正を行ったのである。かくして、本訴において、本件各更正の違法性が争われたのであるが、国は、「不相当に高額な部分」につき、主位的には、本件各抽出法人の代表者に対する役員給与支給額の平均値を上回る部分であると主張し、予備的には、当該役員給与支給額の最高値であると主張した。そのほか、本訴では、本件各抽出法人の選定の合理性、甲の職務の内容の特殊性(他の法人の役員に対する優位性)等が争われた。
本判決は、本件の事実関係を具さに認定した上で、本件各抽出法人に係る抽出基準の合理性を認定し、甲のXにおける職責、業績が高かったことを容認しながらも、「本件役員給与に「不相当に高額な部分」があることは明らかというべきである。そして、その部分の金額は、上記のとおりXの売上げを得るために甲が果たした職責及び達成した業績が相当高い水準にあったことに鑑み、当該調査対象事業年度における本件抽出法人の役員給与の最高額を超える部分がこれに当たると認めるのが相当である。」旨結論を下し、国の予備的主張を採用し、Xの主張を退けた。
(2)このような本判決については、役員給与の相当額が争われた従前の裁判例に準ずるものであって、然程目新しいものでもない。しかし、本判決は、本件の特殊性ともいえる二つの論点について、軽視又は見落としているように考えられる。一つは、甲の職務内容である。本判決は、甲のXにおける功績について、「Xの売上げを得るために甲が果たした職責及び達成した業績が相当高い水準にあったこと」を認め、本件役員給与について、本件抽出法人の中での最高支給額までは相当額であるとして、当該金額の損金算入を相当と認めている。しかし、本件の事実関係から推測すると、Xの存在と業績は、甲の資本とマレーシア人としての人脈等によって成り立っており、甲の存在なくして語れない状態になっている。そうであれば、Xに類似する法人は埼玉県内には存在しないのかも知れないし、仮に、本件各抽出法人と比準を認めるにしても、当該法人における最高支給額の一定の倍数を乗じた金額を相当額と認める方法も考えられる(注10)。
(3)次に、前記3で述べたように、本件においては、甲が我が国の非居住者に該当するが故に、甲に対し不当とも考えられる高額な役員給与を支払ったものと推測できることである。会社代表者が居住者に該当し、かつ、Xのような個人類似法人においては、会社代表者に過大な役員給与を支給することは、当該代表者が最高55%という所得税及び住民税の税負担を負うことになるので、代表者及び当該法人を通じて決して得策ではないはずである。そういう点では、法人税法34条2項の存在意義も薄れることになる。
にもかかわらず、本件役員給与のような過大な役員給与が支払われたことは、甲が我が国の非居住者に該当すると推定されるため、源泉所得税の20%負担で済むという計算が成立していたものと考えられる。そうであれば、会社役員が非居住者に該当し、過大な役員給与が支払われている場合に、それを法人税の上で否認する必要があるときには、従前とは別の法理又は解釈論によって対応する必要があるものと考えられる。
5 本判決の意義と問題点
法人が役員に対して退職給与以外の役員給与を支給した場合に、法人税法34条2項が損金不算入と定める「不相当に高額な部分の金額」を同法施行令70条1号イに定める実質基準によって算定することは、当該役員の「職務の内容」等の判定が困難であるということで、当該各条項を適用する課税処分は比較的少ない。そのため、訴訟事件まで発展することは稀である。その中で、本判決も、数少ない事件の一つであるということでは意義がある。
しかし、本件においては、前述のような本件役員給与の支給をめぐる特殊性があるにもかかわらず、本判決は、従前の裁判例の延長線の事案ととらえ、判決内容も従前の裁判例に準じた判断が下されているにすぎない。よって、前述した本件役員給与の支給をめぐる特殊性については、今後も、役員給与課税の問題点として検討されるべきである。
(注1)旧法時代の役員報酬課税の問題点等については、品川芳宣「役員報酬課税の問題点と方向性」JICPAジャーナル2006年2月号39頁等参照。
(注2)これらの経緯については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(前)」本誌2008年4月14日号27頁参照。
(注3)平成18年改正の役員給与課税規定の問題点については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(後)」本誌2008年4月21日号24頁等参照。
(注4)同判決の評釈については、品川芳宣・本誌2016年9月26日号18頁参照。
(注5)同判決は、給与所得者が事業所得者等に対し不平等に扱われているということで、所得税法28条の憲法14条違反の有無が争われた事案につき、合憲判断を示したものである(詳細については、品川芳宣ほか「戦後重要租税判例の再検証-税務事例創刊400号記念-」(財経詳報社 2003年)2頁、12頁等参照)。
(注6)最近の租税法規に係る違憲訴訟の動向については、前出(注3)32頁等参照。
(注7)これらの問題の解決の方向性については、前出(注3)31頁等参照。
(注8)名古屋地裁平成6年6月15日判決(税資201号485頁)、名古屋高裁平成7年3月30日判決(同208号1081頁)、最高裁平成9年3月25日第三小法廷判決(同222号1226頁)等参照。
(注9)岐阜地裁昭和56年7月1日判決(税資120号1頁)、昭和48年10月8日裁決(品川芳宣「役員報酬の税務事例研究」(財経詳報社 平成14年)128頁)等参照。
(注10)例えば、東京地裁平成29年10月13日判決(平成27年(行ウ)第730号)は、役員退職給与の相当額の算定につき、国が主張する類似法人の平均功績倍率の適用を否定し、当該倍率の1.5倍(最高功績倍率を相当上回る。)を適用すべきである旨判示している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.