解説記事2020年10月12日 税制改正解説 令和2年度における連結納税制度の見直しに関する国際課税関係の改正について(2020年10月12日号・№853)
税制改正解説
令和2年度における連結納税制度の見直しに関する国際課税関係の改正について
堀越聖啓
令和2年度税制改正において連結納税制度が見直され、法人格を有する各法人を納税単位として、課税所得金額及び法人税額の計算並びに申告は各法人がそれぞれ行うこととし、同時に企業グループの一体性に着目し、課税所得金額及び法人税額の計算上、企業グループをあたかも一つの法人であるかのように捉え、損益通算等の調整を行う仕組み(以下「グループ通算制度」という。)とされた。
連結納税制度の見直しに伴う国際課税関係の改正について、主として以下のような見直しを行っている。
まず、グループ通算制度における外国税額控除に係る控除限度額の計算については、平成13年度税制改正における連結納税制度の導入以降、企業はその連結納税制度を前提に、単一法人による経営から100%子会社を通じたグループ経営(いわゆる分社化)を推進してきた事実や、控除限度額のグループ調整計算の廃止がこのような企業経営の実態に与える影響を考慮し、また、今般の連結納税制度の見直しの全体的な趣旨も踏まえ、連結納税制度と同様に、グループ調整計算を維持することとされた。
次に、当初申告における外国税額控除額と再計算後のあるべき外国税額控除額との間に過不足額が生ずることとなった場合には、外国税額控除の適用を受けた過去の事業年度の外国税額控除額は当初申告における外国税額控除額で固定され、その過不足額については、進行事業年度において調整を行う仕組みが新たに措置された。これは、個別申告方式を基礎とするグループ通算制度の下で控除限度額のグループ調整計算を引き続き行うため、外国税額控除を適用する通算法人は、同一の事業年度について何度も修正申告を行ったり更正処分を受けることとなる事態が想定され、改正前の制度以上に事務負担が過重になることが懸念された。そのため、納税者及び税務当局の事務負担の軽減を図るための措置として導入されている。
また、グループ通算制度における外国子会社配当益金不算入制度の適用については、外国子会社の要件の判定について、他の通算法人を含めて行うこととされた。
これらの改正を含む国際課税の改正は、次の法令により行われている。
・所得税法等の一部を改正する法律(令2.3.31法律第8号)
・法人税法施行令等の一部を改正する政令(令2.6.26政令第207号)
・法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令2.6.30財務省令第56号)
1 法人税法関係の改正
(1)外国税額控除
① 控除限度額の計算方法の見直し
イ 控除限度額
通算法人の各事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下「通算事業年度」という。)の控除限度額は、その通算事業年度の所得の金額につき法人税法第66条第1項、第3項及び第6項の規定を適用して計算した金額並びにその通算事業年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下「他の通算法人」という。)のその終了の日に終了する各事業年度(以下「他の事業年度」という。)の所得の金額につき同条第1項、第3項及び第6項の規定を適用して計算した金額の合計額のうち、その通算法人のその通算事業年度の国外所得金額に対応するものとして計算した金額とされた(法法69⑭)。
具体的には、通算法人の通算事業年度の調整前控除限度額からその通算事業年度の控除限度調整額を控除した金額(その調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とされた(法令148①)。
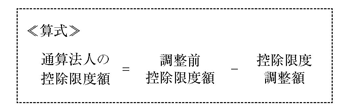
ロ 調整前控除限度額
調整前控除限度額とは、(イ)に掲げる金額に(ロ)に掲げる金額のうちに(ハ)に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう(法令148②)。
(イ)次に掲げる金額の合計額
A 通算法人のその通算事業年度の所得に対する法人税の額
B 他の通算法人の他の事業年度の所得に対する法人税の額の合計額
(注1)上記A及びBの法人税の額とは、税額関係規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法人税法第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)並びに租税特別措置法第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)及び第66条の9の3第3項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除くものとされている。
(注2)税額関係規定とは、次に掲げる規定をいう。
・法人税法第67条(特定同族会社の特別税率)
・法人税法第68条(所得税額の控除)
・法人税法第69条(外国税額の控除)
・法人税法第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)
・法人税法第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)
・租税特別措置法第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)
・租税特別措置法第42条の14第1項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の4の2第1項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項
・租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
・租税特別措置法第62条の3第1項及び第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
・租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
・租税特別措置法第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
・租税特別措置法第66条の9の3第3項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(ロ)次に掲げる金額の合計額
A 通算法人のその通算事業年度の所得金額
B 他の通算法人の他の事業年度の所得金額の合計額
(注)上記A及びBの所得金額とは、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の所得の金額をいう。
・法人税法第57条(欠損金の繰越し)
・法人税法第64条の4(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
・法人税法第64条の5(損益通算)
・法人税法第64条の7(欠損金の通算)
・法人税法第64条の8(通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入)
・租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
・租税特別措置法第67条の12及び第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
(ハ)通算法人のその通算事業年度の調整国外所得金額(その通算事業年度の調整前国外所得金額からその通算事業年度の調整金額を控除した金額(その調整前国外所得金額が零を下回る場合には、その調整前国外所得金額)をいう。以下同じ。)
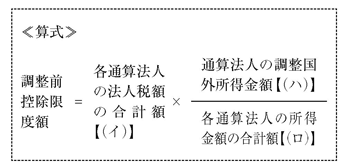
なお、上記の調整前控除限度額の計算は、マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人についても行うことになるので、その通算法人についてはマイナスの調整前控除限度額が算出されることになる。
ハ 調整前国外所得金額
上記ロ(ハ)の調整前国外所得金額とは、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額(以下「非課税国外所得金額」という。)のうち零を超えるものを減算した金額(以下「加算前国外所得金額」という。)に、加算調整額を加算した金額をいう(法令148④)。
・法人税法第57条(欠損金の繰越し)
・法人税法第64条の4(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
・法人税法第64条の5(損益通算)
・法人税法第64条の7(欠損金の通算)
・法人税法第64条の8(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
・租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
・租税特別措置法第67条の12及び第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
なお、法人税法施行令第142条第4項及び第5項(控除限度額の計算)の規定は、非課税国外所得金額について準用することとされている(法令148⑧)。
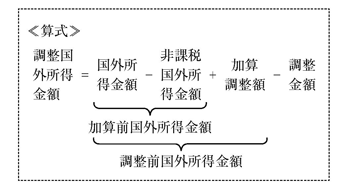
ニ 加算調整額
上記ハの加算調整額とは、通算法人のその通算事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額が零を下回る場合のその下回る額の合計額のうちその通算法人のその通算事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)及び他の通算法人の他の事業年度の非課税国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額に達するまでの金額に、次に掲げる金額の合計額のうちに(イ)に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう(法令148⑤)。
(イ)その通算法人のその通算事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)
(ロ)他の通算法人の他の事業年度の加算前国外所得金額(零を超えるものに限る。)の合計額
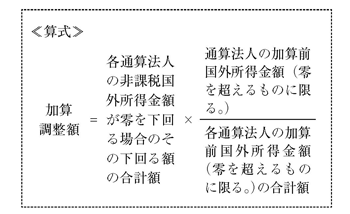
これは、マイナスの非課税国外所得金額を有する通算法人が存在する場合には、そのマイナスの非課税国外所得金額をグループ全体のプラスの非課税国外所得金額を上限として各通算法人に加算前国外所得金額の比で配分することにより、調整国外所得金額の計算における加算要素として勘案するためのものである。
ホ 調整金額
上記ニの調整金額とは、通算法人のその通算事業年度の調整前国外所得金額及び他の通算法人の他の事業年度の調整前国外所得金額の合計額が上記ロ(ロ)に掲げる金額の100分の90に相当する金額を超える場合において、その超える部分の金額に上記ニの割合を乗じて計算した金額をいう(法令148⑥)。
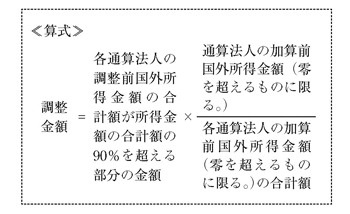
これは、グループ通算制度においても連結納税制度と同様に、グループ全体の調整国外所得金額がグループ全体の所得金額の90%を超える場合には、その90%相当額が上限となるよう比例的に調整するためのものである。
ヘ 控除限度調整額
上記イの控除限度調整額とは、(イ)に掲げる金額に(ロ)に掲げる金額のうちに(ロ)Aに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう(法令148⑦)。
(イ)他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
(ロ)次に掲げる金額の合計額
A 通算法人のその通算事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
B 他の通算法人の他の事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
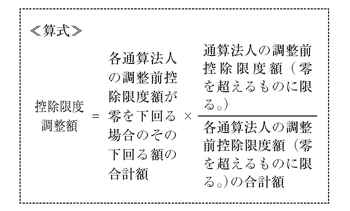
すなわち、マイナスの調整国外所得金額を有する通算法人が存在する場合には、その通算法人のマイナスの調整国外所得金額に対応したマイナスの調整前控除限度額を各通算法人にプラスの調整前控除限度額の比で配分することにより、グループ全体の控除限度額の計算において勘案することとなる。
ト 通知義務
通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、その通算法人の通算事業年度後において、その通算事業年度の期限内申告書に添付された書類に法人税額等(上記ロ(イ)Aに掲げる金額、上記ロ(ロ)Aに掲げる金額、非課税国外所得金額又は加算前国外所得金額をいう。トにおいて同じ。)として記載された金額とその通算事業年度の法人税額等とが異なることとなった場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなった法人税額等を通知しなければならないこととされた(法令148⑨)。
なお、外国税額控除の適用を受けていない通算法人や通算グループから離脱した法人についても過去の通算事業年度の法人税額等がその後に変動した場合には、本通知義務の対象となる。
② 期限内申告書の申告期限後において当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合の調整方法
イ 適用事業年度における当初申告税額控除額の固定措置(当初申告税額控除額固定措置)
通算法人が外国税額控除(法人税法第69条第1項から第3項までの規定による控除をいう。以下同じ。)の適用を受ける場合において、通算法人のその適用を受ける各事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下「適用事業年度」という。)の税額控除額(適用事業年度における外国税額控除をされるべき金額をいう。以下同じ。)が、当初申告税額控除額(その適用事業年度の期限内申告書に添付された書類にその適用事業年度の税額控除額として記載された金額をいう。以下同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除額を税額控除額とみなすこととされている(法法69⑮)。
すなわち、通算法人の適用事業年度に係る期限内申告における当初申告税額控除額の計算に誤りがあった場合であっても、その適用事業年度に係る外国税額控除額は変わらないことになり、その適用事業年度に係る修正申告又は更正は不要とされる。
ロ 税額控除額と当初申告税額控除額の差額に関する対象事業年度(進行事業年度)における調整
上記イの適用がある場合には、適用事業年度に係る期限内申告書の申告期限後に税額控除額と当初申告税額控除額が異なることとなったときであっても、適用事業年度に係る修正申告又は更正は不要とされる。その税額控除額と当初申告税額控除額の差額については、進行事業年度における法人税の額から控除し、又は加算することにより、その調整を行うこととされている。
(イ)税額控除不足額相当額に関する対象事業年度の法人税の額からの控除措置(進行事業年度控除措置)
通算法人(通算法人であった内国法人(公益法人等に該当することとなった内国法人を除く。)を含む。以下ハまでにおいて同じ。)の各事業年度(以下「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(その対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で当初申告税額控除額固定措置(上記イの措置をいう。以下同じ。)の適用を受けた事業年度をいう。以下同じ。)における税額控除額(その対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下「対象前各事業年度」という。)においてその過去適用事業年度(当初申告税額控除額固定解除措置(下記ハ(イ)の措置をいう。以下同じ。)の適用を受けた事業年度を除く。)に係る税額控除額につき進行事業年度控除措置((イ)の措置をいう。以下同じ。)又は進行事業年度加算措置(下記(ロ)の措置をいう。以下同じ。)の適用があった場合には、進行事業年度加算措置によりその対象前各事業年度の法人税の額に加算した金額の合計額から進行事業年度控除措置によりその対象前各事業年度の法人税の額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額をいう。以下(ロ)までにおいて「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(その過去適用事業年度の期限内申告書に添付された書類にその過去適用事業年度の外国税額控除をされるべき金額として記載された金額をいう。以下同じ。)を超える場合には、税額控除不足額相当額(その調整後過去税額控除額からその過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。以下同じ。)をその対象事業年度の所得に対する法人税の額から控除することとされている(法法69⑰)。
(ロ)税額控除超過額相当額に関する対象事業年度の法人税の額への加算措置(進行事業年度加算措置)
通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、その対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(その過去当初申告税額控除額からその調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。以下同じ。)を加算した金額とすることとされている(法法69⑱)。
(ハ)対象事業年度における当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額の固定措置(当初申告税額控除不足額相当額等固定措置)
進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置の適用がある場合において、通算法人の対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額が当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額(それぞれその対象事業年度の期限内申告書に添付された書類にその対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額として記載された金額をいう。以下同じ。)と異なるときは、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額をその対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額とみなすこととされている(法法69⑲)。
すなわち、進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置の適用があった通算法人の対象事業年度に係る期限内申告書の当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額の計算に誤りがあった場合においても、その対象事業年度に係る修正申告又は更正は不要とされる。
その対象事業年度の税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額と当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額との差額とについては、その対象事業年度後の事業年度において進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置を適用することにより調整を行うこととされている。
(ニ)進行事業年度控除措置及び進行事業年度加算措置と除斥期間との関係
法人税に係る更正又は決定(以下「更正決定」という。)は、原則として法人税の法定申告期限から5年を経過した日以後においてはすることができないこととされている(通法70①一)。
そのため、過去適用事業年度に係る法人税の法定申告期限から5年を経過した日以後に当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合には、除斥期間を徒過していることから、税務当局は税額控除額と当初申告税額控除額との差額について進行事業年度控除措置及び進行事業年度加算措置の適用を求めることはできない。
他方、過去適用事業年度に係る法人税の法定申告期限から5年を経過する日までに当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合には、当初申告税額控除額固定解除措置の適用がある場合を除き、納税者は税額控除額と当初申告税額控除額との差額についてその発覚した日の属する事業年度において、進行事業年度控除措置及び進行事業年度加算措置を適用する必要がある。
ただし、これらの措置が調整しようとする税額控除額と当初申告税額控除額の差額は過去適用事業年度における数値であることに相違はないが、進行事業年度の法人税の額から控除し、又は加算することにより調整を行うため、あくまでその進行事業年度における新たな税額として除斥期間を計算することになる。すなわち、進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置の適用に係る除斥期間は、その進行事業年度の法定申告期限の翌日から新たに起算することになる。したがって、過去適用事業年度の法定申告期限から5年を経過した日以後は税額控除額と当初申告税額控除額との差額につき変動が生ずることはないが、その差額につき進行事業年度控除措置及び進行事業年度加算措置が適正に適用されていない場合には、進行事業年度の法定申告期限から5年を経過する日までの間、その適用を求めることが可能である。
なお、上記は除斥期間が原則である場合のものである。例えば、偽りその他不正の行為により税額を免れた法人税についての更正決定は、その法人税の法定申告期限から7年を経過した日以後においてはすることができないこととされている(通法70⑤一・二)。そのため、このような偽りその他不正の行為があった場合の進行事業年度控除措置及び進行事業年度加算措置と除斥期間との関係については、上記において「5年」として記載されている部分は「7年」であるものとして取り扱われることになる。
ハ 当初申告税額控除額固定措置又は当初申告税額控除不足額相当額等固定措置の不適用
(イ)当初申告税額控除額固定措置の適用がない場合(当初申告税額控除額固定解除措置)
当初申告税額控除額固定措置は、適用事業年度に係る期限内申告書の申告期限後に当初申告税額控除の誤りが発覚した場合には、本来であれば適用事業年度に係る修正申告又は更正を行うべきところ、申告事務に係る負担に配慮する観点から設けられているものである。他方、AからCまでの場合に該当するときは、当初申告税額控除額固定措置による利便を享受する必要性は認められない。
そのため、通算法人の適用事業年度について、AからCまでの場合のいずれかに該当するときは、その適用事業年度については、当初申告税額控除額固定措置は不適用とされる(法法69⑯)。その結果、原則に則り、適用事業年度に係る修正申告又は更正が行われることになる。
A 通算法人又は他の通算法人が、適用事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
(注)ここでいう「税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装」とは、例えば、実際には納付していない外国法人税をあたかも納付したかのように仮装して外国税額控除の適用を受けるケースなど、まさに外国税額控除制度の適用そのものに関する仮装又は隠蔽行為をいう。
B 法人税法第64条の5第8項(損益通算)の規定の適用がある場合
C 地方法人税法における外国税額控除において、通算法人又は他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
(ロ)当初申告税額控除不足額相当額等固定措置の不適用(当初申告税額控除不足額相当額等固定解除措置)
当初申告税額控除不足額相当額等固定措置も当初申告税額控除額固定措置と同様に、当初申告税額控除不足額相当額又は当初申告税額控除超過額相当額における誤りが発覚した場合には、本来であればその事業年度において修正申告又は更正を行うべきところ、申告事務に係る負担に配慮する観点から設けられているものである。他方、AからCまでの場合に該当するときは、当初申告税額控除不足額相当額等固定措置による利便を享受する必要性は認められない。
そのため、通算法人の対象事業年度について、AからCまでに掲げる場合のいずれかに該当するときは、その対象事業年度については、当初申告税額控除不足額相当額等固定措置は不適用とされる(法法69⑳)。その結果、原則に則り、当初申告税額控除不足額相当額等固定措置を適用した事業年度に係る修正申告又は更正が行われることになる。
A 税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、その税額控除不足額相当額を増加させ、又はその税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
B 進行事業年度控除措置の適用により法人税の額から控除した税額控除不足額相当額又は進行事業年度加算措置の適用により法人税の額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度について当初申告税額控除額固定解除措置の適用がある場合
C 地方法人税法における外国税額控除において、その地方法人税法における外国税額控除に係る税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、その税額控除不足額相当額を増加させ、又はその税額控除超過額相当額を減少させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合に該当することにより、地方法人税法における外国税額控除に係る当初申告税額控除額固定解除措置の適用がある場合
(ハ)期限内申告額の洗替え
過去適用事業年度について当初申告税額控除額固定解除措置の適用により修正申告書の提出又は更正がされた後における進行事業年度控除措置及び進行事業年度加算措置の適用については、その修正申告書又はその更正に係る更正通知書に添付された書類にその過去適用事業年度の外国税額控除をされるべき金額として記載された金額をその過去適用事業年度の期限内申告書に添付された書類に外国税額控除をされるべき金額として記載された金額とみなすこととされている(法法69⑰)。
ニ 合併により解散した場合又は通算法人の残余財産が確定した場合における調整措置
通算法人(通算法人であった内国法人を含む。ニ及びホにおいて同じ。)につき合併の日以後又は残余財産の確定の日の翌日以後に、過去の事業年度における当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合には、その通算法人の進行事業年度が存在しないため、そのままでは進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置を適用することができない。
そのため、合併の日以後又は残余財産の確定の日の翌日以後に過去の事業年度における当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合には、合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度(最終事業年度)において税額控除額と当初申告税額控除額との差額の調整を行うこととされている(法法69 )。この場合において、最終事業年度の税額控除額、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額については、当初申告税額控除額固定措置及び当初申告税額控除不足額相当額等固定措置は適用されない。
)。この場合において、最終事業年度の税額控除額、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額については、当初申告税額控除額固定措置及び当初申告税額控除不足額相当額等固定措置は適用されない。
ホ 公益法人等に該当することとなった場合における調整措置
通算法人が公益法人等に該当することとなった日以後に過去の事業年度における当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合には、その公益法人等が収益事業を行わない限り法人税の申告義務が生じないため、進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置が確実に適用されない可能性がある。
そのため、公益法人等に該当することとなった日以後に過去の事業年度における当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合には、その該当することとなった日の前日の属する事業年度(最終事業年度)において税額控除額と当初申告税額控除額との差額の調整を行うこととされている(法法69 )。この場合において、最終事業年度の税額控除額、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額については、当初申告税額控除額固定措置及び当初申告税額控除不足額相当額等固定措置は適用されない。
)。この場合において、最終事業年度の税額控除額、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額については、当初申告税額控除額固定措置及び当初申告税額控除不足額相当額等固定措置は適用されない。
ヘ 進行事業年度控除措置の適用に関する添付書類等
(イ)進行事業年度控除措置の適用に関する添付書類及び保存書類
進行事業年度控除措置は、申告書等(確定申告書、修正申告書又は更正請求書をいう。以下同じ。)にAからEまでの書類(以下「明細書」という。)の添付があり、かつ、Fの書類を保存している場合に限り、適用することとされている(法法69 前段、法規30の2①②)。
前段、法規30の2①②)。
A 進行事業年度控除措置による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類
B 進行事業年度控除措置による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額、税額控除額及びその計算に関する明細を記載した書類
C その過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類(これらの書類が対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度の申告書等に添付されている場合におけるその書類を除く。)
D 対象前各事業年度においてその過去適用事業年度に係る税額控除額につき進行事業年度控除措置又は進行事業年度加算措置の適用があった場合には、その対象前各事業年度の進行事業年度控除措置により法人税の額から控除した金額の合計額及び進行事業年度加算措置により法人税の額に加算した金額の合計額に関する明細を記載した書類
E その過去適用事業年度における繰越控除限度額を用いた控除及び繰越控除対象外国法人税額を用いた控除をされるべき金額に係る繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(以下「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の控除限度額及びその繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を記載した書類(これらの書類が対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度の申告書等に添付されている場合におけるその書類を除く。)
F その過去適用事業年度の法人税法施行規則第29条の4第2項各号及び第30条第2項各号に掲げる書類
(ロ)進行事業年度控除措置の適用に係る上限額
進行事業年度控除措置による控除をされるべき金額の計算の基礎となるAからCまでの金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、その明細書にそのAからCまでの金額として記載された金額を限度とすることとされている(法法69 後段、法規30の2③)。
後段、法規30の2③)。
A その過去適用事業年度の控除対象外国法人税の額(控除対象外国法人税の額の減額に伴う控除措置の適用があった場合には、その控除後の金額)
B 繰越控除限度額等に係る各事業年度の控除限度額
C 繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(その繰越控除限度額等に係る各事業年度において控除対象外国法人税の額の減額に伴う控除措置の適用があった場合には、その控除後の金額)
ト 進行事業年度加算措置に関する書類添付義務
進行事業年度加算措置の適用を受ける通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、申告書等にその進行事業年度加算措置により法人税の額に加算されるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないこととされている(法法69 )。
)。
③ 外国税額控除の選択
今回の改正において、グループ通算制度における外国税額控除に係る控除限度額は、引き続きグループ調整計算を認めることとされた。そのため、外国税額控除の選択についても連結納税制度と同様に、通算グループとして行う仕組みとされている。
これに伴い、通算法人又は他の通算法人が、控除対象外国法人税の額につき外国税額控除(進行事業年度控除措置を含む。③において同じ。)の適用を受ける場合には、その通算法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額は、その通算法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされている(法法41②)。すなわち、通算グループ内の1社でも外国税額控除の適用を受ける場合には、他の通算法人において控除対象外国法人税の額の損金算入は認められない。
(2)外国子会社配当益金不算入制度
今回の改正では、グループ通算制度における外国税額控除制度について、控除限度額について引き続きグループ調整計算を認めることとされた。そのため、グループ通算制度における外国子会社配当益金不算入制度の適用についても、過去に外国税額控除制度の一部を構成していた経緯や今回のグループ通算制度の改正の全体的な趣旨を踏まえ、外国子会社の要件(持株割合25%以上かつ6月以上保有)の判定について、他の通算法人を含めて行うこととされている(法令22の4①)。
(3)適用関係及び経過措置
① 原則
原則として、連結納税制度の廃止及びグループ通算制度への移行に関する改正は、法人の令和4年4月1日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、従来どおり適用することとされている(改正法附則14、令和2年6月改正法令等附則2、令和2年6月改正法規等附則2)。
② 連結納税に関する規定の削除に伴う経過措置
上記(1)及び(2)の改正は、単体納税制度の条項において、その法人が過去において連結納税制度を適用していた場合又は取引の相手方において連結納税制度を適用している場合にこれらの連結納税制度の適用上生じた金額や事象を用いている規定は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する規定の削除に伴い削除されているが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においても過去において又は取引の相手方において連結納税制度の適用上生じた金額や事象を考慮する必要があるものについては、原則として、従来どおり適用することとされている(改正法附則32、令和2年6月改正法令等附則8、9、34〜38、令和2年6月改正法規等附則6〜8)。
2 地方法人税法関係の改正
(1)外国税額控除
① 控除限度額の計算方法の見直し
イ 地方法人税控除限度額
通算法人の各課税事業年度(その通算法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものに限る。以下「通算課税事業年度」という。)の地方法人税控除限度額は、その通算法人のその通算課税事業年度の地方法人税法第10条の規定を適用して計算した所得地方法人税額及びその通算課税事業年度終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下「他の通算法人」という。)のその終了の日に終了する各課税事業年度(以下「他の課税事業年度」という。)の同条の規定を適用して計算した所得地方法人税額の合計額のうち、その通算法人のその通算課税事業年度の国外所得金額に対応するものとして計算した金額とされた(地法法12④)。
具体的には、通算法人の通算課税事業年度の調整前控除限度額からその通算課税事業年度の控除限度調整額を控除した金額(その調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とされた(地法令3④)。
なお、基本的な仕組みは法人税の控除限度額の計算と同様である。
ロ 調整前控除限度額
調整前控除限度額とは、次に掲げる金額の合計額にその通算課税事業年度に係る法人税法施行令第148条第3項から第8項までの規定を適用して計算した同条第2項に規定する割合(上記1(1)①ロの割合)を乗じて計算した金額をいう(法令148②)。
(イ)通算法人のその通算課税事業年度の地方法人税法第9条に規定する課税標準法人税額につき同法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額から、法人税法第67条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第69条の2、地方法人税法第12条の2並びに租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項並びに第66条の9の3第3項及び第9項の規定を適用した場合に地方法人税法第12条の2並びに租税特別措置法第66条の7第10項及び第66条の9の3第9項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額
(ロ)他の通算法人の他の課税事業年度の地方法人税法第9条に規定する課税標準法人税額につき同法第10条の規定を適用して計算した地方法人税の額から、法人税法第67条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第69条の2、地方法人税法第12条の2並びに租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項並びに第66条の9の3第3項及び第9項の規定を適用した場合に地方法人税法第12条の2並びに租税特別措置法第66条の7第10項及び第66条の9の3第9項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額の合計額
(注1)上記(イ)及び(ロ)の地方法人税の額は、その通算課税事業年度の基準法人税額のうちに税額加算規定により加算された金額がある場合には、その基準法人税額からその加算された金額を控除した金額をその通算課税事業年度の基準法人税額とみなして地方法人税法第9条及び第10条の規定を適用して計算した金額とされている。
(注2)税額加算規定とは、次に掲げる規定をいう。
・租税特別措置法第42条の4第8項第6号ロ又は第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)
・租税特別措置法第42条の14第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の4の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項
・地方法人税法第3章第5節又は第5節の2
ハ 控除限度調整額
控除限度調整額とは、(イ)に掲げる金額に(ロ)に掲げる金額のうちに(ロ)Aに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう(地法令3⑥)。
(イ)他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額
(ロ)次に掲げる金額の合計額
A 通算法人のその通算課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)
B 他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額
ニ 通知義務
通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、その通算法人の通算課税事業年度後において、その通算課税事業年度の期限内申告書に添付された書類に地方法人税額(上記ロ(イ)に掲げる金額をいう。ニにおいて同じ。)として記載された金額とその通算課税事業年度の地方法人税額とが異なることとなった場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなった地方法人税額を通知しなければならないこととされた。なお、外国税額控除の適用を受けていない通算法人や通算グループから離脱した法人についても過去の通算課税事業年度の地方法人税額がその後に変動した場合には、本通知義務の対象となる(地法令3⑦)。
② 期限内申告書の申告期限後において当初申告税額控除額の誤りが発覚した場合の調整方法
イ 適用課税事業年度における当初申告税額控除額の固定措置(当初申告税額控除額固定措置)
法人税法における外国税額控除に係る当初申告税額控除額固定措置と基本的に同様の仕組みが措置されている(地法法12⑤)。
また、法人税法における当初申告税額控除額固定解除措置と同様の制度も措置されている。具体的には、通算法人の適用課税事業年度について、(イ)又は(ロ)のいずれかの場合に該当するときは、その適用課税事業年度については、地方法人税法における当初申告税額控除額固定措置は適用されない(地法法12⑥)。
(イ)通算法人又は他の通算法人が、適用課税事業年度における税額控除額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して税額控除額を増加させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
(ロ)法人税法における外国税額控除に係る当初申告税額控除額固定解除措置の適用がある場合(上記(イ)に該当することによりその当初申告税額控除額固定解除措置が適用される場合を除く。)
ロ 税額控除額と当初申告税額控除額の差額に関する進行事業年度における調整
法人税法における外国税額控除に係る進行事業年度控除措置、進行事業年度加算措置及び当初申告税額控除不足額相当額等固定措置と基本的に同様の仕組みを措置している(地法法12⑦〜⑨)。
また、通算法人の対象課税事業年度について、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その対象課税事業年度については、地方法人税法における当初申告税額控除不足額相当額等固定措置は、適用されない(地法法12⑩)。
(イ)税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、その税額控除不足額相当額を増加させ、又はその税額控除超過額相当額を減少させることによりその地方法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合
(ロ)対象課税事業年度において地方法人税法における進行事業年度控除措置により所得地方法人税額から控除した税額控除不足額相当額又は地方法人税法における進行事業年度加算措置により所得地方法人税額に加算した税額控除超過額相当額に係る過去適用課税事業年度について当初申告税額控除額固定解除措置の適用がある場合
(ハ)法人税法における当初申告税額控除不足額相当額等固定解除措置の適用がある場合(税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して、その税額控除不足額相当額を増加させ、又はその税額控除超過額相当額を減少させることによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合に該当することにより、その措置の適用がある場合に限る。)
(2)外国税額の還付規定の創設等
① 地方法人税確定申告書の記載事項の整備
法人が、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に対して提出する地方法人税確定申告書の記載事項に、外国税額控除による控除をされるべき金額で地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額が追加されている(地法法19①)。
② 地方法人税に係る外国税額の還付規定の創設
イ 外国税額の還付
地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に外国税額控除による控除をされるべき金額で地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、その地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、その金額に相当する税額を還付することとしている(地法法22①)。
ロ 外国税額の還付の手続
税務署長は、外国税額控除による控除をされるべき金額で地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載がある地方法人税確定申告書の提出があった場合には、その金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、上記イによる還付又は充当の手続をしなければならない(地法令8)。
ハ 還付加算金の計算
上記イによる還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、地方法人税確定申告書の提出期限(その地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、その地方法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間となる(地法法22②)。
ニ 充当等
上記イによる還付金を地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとしている(地法法22③)。
また、上記イによる還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、まずその課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(その還付金が外国税額控除による控除をされるべき金額で地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、その地方法人税に充当する。そして、その地方法人税に充当してもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当することとしている(地法令9)。
③ 更正等による地方法人税に係る外国税額の還付規定の創設
イ 更正等による外国税額の還付
内国法人の提出した地方法人税確定申告書に係る地方法人税につき更正(その地方法人税についての更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。ロまでにおいて「更正等」という。)があった場合において、その更正等により外国税額控除による控除をされるべき金額で地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付することとされている(地法法27の2①)。
ロ 還付加算金の計算
上記イによる還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、その更正等の日の翌日以後1月を経過した日(その更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日とその更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間となる(地法法27の2②)。
ハ 充当等
上記イによる還付金を地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとしている(地法令27の2③)。
また、上記イによる還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、まずその課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(その還付金が外国税額控除による控除をされるべき金額で地方法人税の額の計算上控除しきれなかった金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、その地方法人税に充当する。そして、その地方法人税に充当してもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当することとしている(地法令14による地法令9の準用)。
(3)税額控除の順序
今回の改正において、外国税額の還付規定が創設されたことに伴い、地方法人税における税額控除の順序について、外国税額控除の順序を劣後することとされた。具体的には、次の順序により控除することとされている(地法法14)。
① 分配時調整外国税相当額の控除
② 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除
③ 外国税額の控除
(4)適用関係及び経過措置
原則として、連結納税制度の廃止及びグループ通算制度への移行に関する改正は、法人の令和4年4月1日以後に開始する課税事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、従来どおり適用することとされている(改正法附則14、令和2年6月改正法令等附則2、令和2年6月改正法規等附則2)。
3 租税特別措置法関係の改正
(1)過大支払利子税制
① 対象純支払利子等の額の損金不算入額
通算法人に係る過大支払利子税制の適用については、通算法人ごとに対象純支払利子等の額と調整所得金額を比較して損金不算入額の計算を行うこととされた(措法66の5の2①)。
② 適用免除基準
通算法人が次のいずれかに該当する場合には、本制度の適用はないこととされた(措法66の5の2③)。
イ 通算法人及びその通算法人のその事業年度(その通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日においてその通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のその事業年度及びその終了の日に終了する事業年度に係る対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額(控除対象受取利子等合計額から対象支払利子等合計額を控除した残額をいう。ロ(イ)において同じ。)の合計額を控除した残額が2,000万円以下であるとき。
ロ 内国法人及びその内国法人との間に特定資本関係(一の内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係等をいう。)のある他の内国法人(その事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれその開始の日を含むその内国法人の事業年度開始の日及び終了の日であるものに限る。)のその事業年度に係る(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額の20%に相当する金額を超えないとき。
(イ)対象純支払利子等の額の合計額から対象純受取利子等の額の合計額を控除した残額
(ロ)調整所得金額の合計額から調整損失金額(調整所得金額の計算において零を下回る金額が算出される場合のその零を下回る金額をいう。)の合計額を控除した残額
上記イの基準については、連結納税制度と同様にグループ全体での判定を維持することとされた。
上記ロの基準については、上記①のとおり通算法人ごとに対象純支払利子等の額と調整所得金額を比較して損金不算入額の計算を行うこととされたことから通算法人の場合も適用することとされた。
(2)その他の国際課税関係
法人税法における連結納税制度の廃止及びグループ通算制度への移行に関する改正に伴い、上記(1)の過大支払利子税制の改正のほか、連結法人の移転価格税制、過少資本税制及び外国子会社合算税制等の規定が削除されるとともに、これらの制度の条項において、その法人が過去において連結納税制度を適用していた場合又は取引の相手方において連結納税制度を適用している場合にこれらの連結納税制度の適用上生じた金額や事象を用いている規定等を削除するなどの所要の整備が行われた(措法66の4、66の5、66の6〜66の8、旧措法68の88〜68の89、68の90〜68の93等)。
(3)適用関係及び経過措置
① 原則
上記(1)及び(2)の改正は、法人の令和4年4月1日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、従来どおり適用することとされている(改正法附則14、令和2年6月改正法令等附則2、令和2年6月改正法規等附則2)。
② 連結納税に関する規定の削除に伴う経過措置
移転価格税制、過少資本税制、過大支払利子税制及び外国子会社合算税制等の条項において、その法人が過去において連結納税制度を適用していた場合又は取引の相手方において連結納税制度を適用している場合にこれらの連結納税制度の適用上生じた金額や事象を用いている規定等は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する規定の削除に伴い削除されているが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度においても過去において又は取引の相手方において連結納税制度の適用上生じた金額や事象等を考慮する必要があるものについては、原則として、従来どおり適用することとされている(改正法附則124〜126、令和2年6月改正法令等附則53〜55、令和2年6月改正法規等附則12⑧等)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























