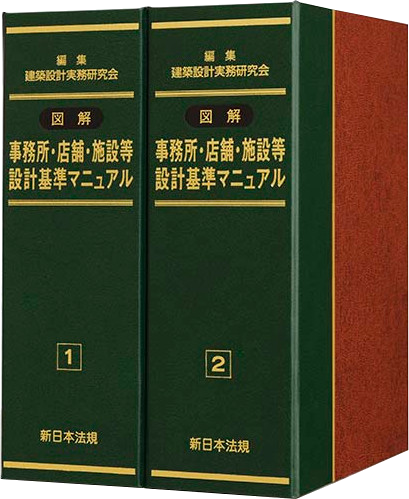建設・運輸2008年04月03日 「建」と「築」のコラボレーション 執筆者:戸田敬里
私は、このたび発刊された「図解 事務所・店舗・施設等設計基準マニュアル」の編集に携わりました。その際、建築物は、ときとして「器」にたとえられることから、この器という文字の意味するところを白川静氏の「常用字解」から調べてみました。
口に当たるところは、神への祈り文である祝詞を入れるところで (さい)というものだそうです。大と思われるところはもともと犬であったとのことです。犬は清めのための犠牲(いけにえ)として用いるもので、器とは儀礼のときに使用される清められた「うつわ」をいうことを知り、
(さい)というものだそうです。大と思われるところはもともと犬であったとのことです。犬は清めのための犠牲(いけにえ)として用いるもので、器とは儀礼のときに使用される清められた「うつわ」をいうことを知り、 を適法な状態にある種々の用途別建築物にたとえてこの図書の「はしがき」を書きました。
このようなことから、建築に携わる者として建と築の2文字について、それぞれの文字の成り立ち、持つ意味合い及び建築という語句がどのような意味を持つものかは大いに興味を持つところです。
まず、「常用字解」から「建」と「築」を見てみます。
「建」は、
を適法な状態にある種々の用途別建築物にたとえてこの図書の「はしがき」を書きました。
このようなことから、建築に携わる者として建と築の2文字について、それぞれの文字の成り立ち、持つ意味合い及び建築という語句がどのような意味を持つものかは大いに興味を持つところです。
まず、「常用字解」から「建」と「築」を見てみます。
「建」は、 (いつ)(筆を意味します。)と
(いつ)(筆を意味します。)と (いん)(儀礼を行う中廷(中庭)の周囲の壁を意味します。)を組み合わせた形で、その意味するところは、中廷に筆を立て、方位や地相を占って都の位置を定めるというものです。ここで、筆を立てることは、いわゆる「まちかた」を書くという意味を持つということですから、都を定めることを意味するのは理解できるところです。定まった都に標柱を立て、奠基(てんき)(建物の基壇にいけにえを埋めてその土地を祓い清めることです。)の儀礼を行い、儀礼が終わると工具を執り、土を固めて建築物の土台を築きあげます。これを築(きずく)というのだそうです。建築が終わると、都の造営が始まり、建国(新しく国をつくること)に至ることになります。このことから、建はもともと測量をし、区画し、都の設営をいう字であったようだとあります。後に建物をつくることを建設・建造・建築といい、「たてる」の意味となるとあります。
「築」のもとの字は
(いん)(儀礼を行う中廷(中庭)の周囲の壁を意味します。)を組み合わせた形で、その意味するところは、中廷に筆を立て、方位や地相を占って都の位置を定めるというものです。ここで、筆を立てることは、いわゆる「まちかた」を書くという意味を持つということですから、都を定めることを意味するのは理解できるところです。定まった都に標柱を立て、奠基(てんき)(建物の基壇にいけにえを埋めてその土地を祓い清めることです。)の儀礼を行い、儀礼が終わると工具を執り、土を固めて建築物の土台を築きあげます。これを築(きずく)というのだそうです。建築が終わると、都の造営が始まり、建国(新しく国をつくること)に至ることになります。このことから、建はもともと測量をし、区画し、都の設営をいう字であったようだとあります。後に建物をつくることを建設・建造・建築といい、「たてる」の意味となるとあります。
「築」のもとの字は で、
で、 (ちく)に木をあわせたものです。
(ちく)に木をあわせたものです。 の下部は
の下部は (きょう)と同じで、工具の工を両手で強く持つ形であり、竹はおそらく竹籠(たけかご)で、これに土を入れ、工具で打ち固めること、建造物の土台を築きあげることを
(きょう)と同じで、工具の工を両手で強く持つ形であり、竹はおそらく竹籠(たけかご)で、これに土を入れ、工具で打ち固めること、建造物の土台を築きあげることを というのだそうです。
というのだそうです。 に木を加えているのは、土をつき固めるのに、版築(はんちく)(城壁などの建築法で、板と板との間に入れた土をつき固めていく方法)の方法をとるという意味と推測しています。「きずく、建てる」の意味に用いるとあります。
したがって、同義の字で構成された「建築」は、都あるいは国という一定の広さを持つエリアを本(もと)にした、そこで生活する人々が利用する建築物の土台に連なることで、現在の言葉では都市あるいは都市計画から建築物へと繋がるものではないでしょうか。
今日、都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本としています。このため、都市計画法では「都市計画」を、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画としています。
このうち、土地利用と市街地開発事業は建築物を建てることに関与するもので、特に私が担当したことのある高層住居誘導地区(注1)、特定街区(注2)、都市再生特別地区(注3)、市街地再開発事業(注4)及び地区計画等(注5)等の都市計画の内容は、建築物ありきです。まさに「都市計画から建築物へと繋がる」意味で「建」と「築」のコラボレーションであり大いに頷けるものです。
確かに道路等の交通施設や公園等の公共空地等の都市施設も都市計画ではありますが、どちらかといえば「土木」という語句に連なるものであり、亀甲や獣骨に刻まれた甲骨文字や青銅器に刻まれた金文から作り出された「建築」の語源に結びつく都市計画ではないのが残念なことです。
文字ができたときの持つ意味から、都市計画の本質は建築に連なることが分かり、建築を職能とする身として都市計画に係っていることは全くもって至福なことであります。
に木を加えているのは、土をつき固めるのに、版築(はんちく)(城壁などの建築法で、板と板との間に入れた土をつき固めていく方法)の方法をとるという意味と推測しています。「きずく、建てる」の意味に用いるとあります。
したがって、同義の字で構成された「建築」は、都あるいは国という一定の広さを持つエリアを本(もと)にした、そこで生活する人々が利用する建築物の土台に連なることで、現在の言葉では都市あるいは都市計画から建築物へと繋がるものではないでしょうか。
今日、都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本としています。このため、都市計画法では「都市計画」を、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画としています。
このうち、土地利用と市街地開発事業は建築物を建てることに関与するもので、特に私が担当したことのある高層住居誘導地区(注1)、特定街区(注2)、都市再生特別地区(注3)、市街地再開発事業(注4)及び地区計画等(注5)等の都市計画の内容は、建築物ありきです。まさに「都市計画から建築物へと繋がる」意味で「建」と「築」のコラボレーションであり大いに頷けるものです。
確かに道路等の交通施設や公園等の公共空地等の都市施設も都市計画ではありますが、どちらかといえば「土木」という語句に連なるものであり、亀甲や獣骨に刻まれた甲骨文字や青銅器に刻まれた金文から作り出された「建築」の語源に結びつく都市計画ではないのが残念なことです。
文字ができたときの持つ意味から、都市計画の本質は建築に連なることが分かり、建築を職能とする身として都市計画に係っていることは全くもって至福なことであります。
(2008年4月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.