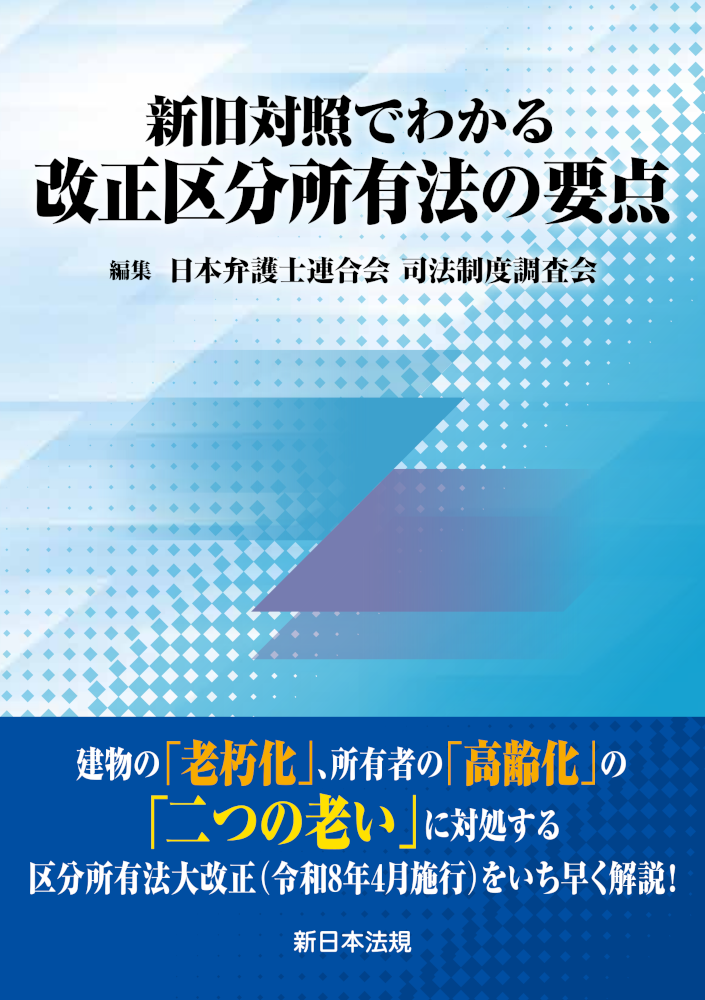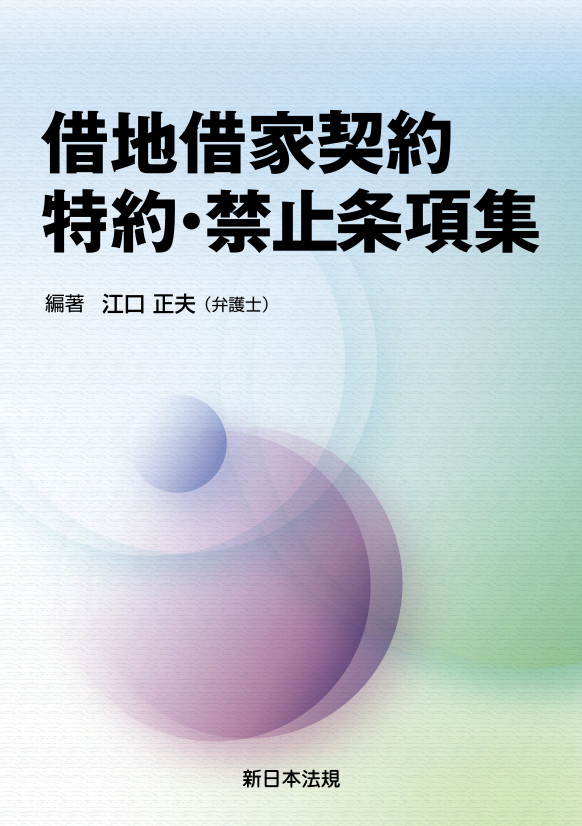民事2014年04月24日 賃貸借契約を理解するポイント 執筆者:伊豆隆義
借地借家法が制定されて、既に20年余が経過した。この間、我が国の不動産をめぐる状況は一変し、土地建物の価値もこれをどう利用できるかの点に力点が置かれるようになってきている。土地建物の利用形態の中で、もっとも典型的なものが賃貸借契約ではあるが、既に借地借家法制定から20年余を経ても、なお、通常の契約類型と異なる難易度は変わらない。
私のここ数年の取扱事例として、ロードサイドにある店舗所有のための賃貸借契約につき、その終了と明渡しを求めたが、事業用定期借地契約を締結するとの和解をした例があった。この事例では、裁判上の和解において、合意に、いざ終了時に明渡しがなされない場合に備えての執行力を持たせることに注意を払いつつ、事業用的借地契約の成立要件が公正証書による契約であることを要件としていることから(借地借家法23条)、裁判上の和解のみならず、公証役場での公正証書作成をすることで、その要件を充足することに意を払った。
また、定期建物賃貸借について、その成立要件や終了要件について、疑義ある事案の相談も頻繁にある。定期建物賃貸借では、その成立要件として、賃貸借契約締結「前」に、これから契約する賃貸借契約が、更新型の契約ではなく、期間満了により終了する定期建物賃貸借であることを、賃貸人が賃借人に書面事前説明することとされているが(借地借家法38条2項)、それがないままに、なされた契約についてどう取り扱うか。また、成立要件には問題なかったものの、終了要件としての期間満了6ヶ月前までの通知(同条4項)がなされなかった場合に、当該定期建物賃貸借は、終了するのか、また、終了するとしてもそれは何時なのか、等法令や判例を正確に理解していない場合に、判断を誤る場面が多々ありうる。前者の点については、判例は、「法38条2項所定の書面は,賃借人が,当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。」としており(最判平成24年9月13日民集66巻9号3263頁)、事前説明がない場合は、定期建物賃貸借ではなく、更新型の賃貸借と解される。また、後者の点についても、裁判例は、「借地借家法38条4項の終了通知を賃貸人が期間満了までに行わなかった場合、定期建物賃貸借契約は期間満了によって確定的に終了するが、賃借人に終了通知がされてから6か月後までは、賃貸人は賃借人に対して定期建物賃貸借契約の終了を対抗することができないため、賃借人は明渡しを猶予されると解するのが相当であると」としており(東京地判平成21年3月19日判時2054号98頁)、定期建物賃貸借が終了要件を満たしていない場合は、これを満たしたときに終了するとすべきであり、終了の通知をしてから6ヶ月後に契約終了による明渡しが請求できると考えるべきである。
更には、保証金名目で授受した金銭について、賃貸借契約終了時にこれの返還が問題となる事案について、賃貸人が返還しないで良い場合はあるのか、それはいかなる要件によるのかなども、近時、相談の多い案件といえる。裁判例も多数あるところである。
そして、更新型賃貸借においては、依然として、その明渡しに正当事由を補完するための立退料を要するとする事案が多いが、その額や正当事由の要件成立の有無が多くの事案で争点となっている。
また、近時、経済状況の変動に対応して、地代や家賃の増減請求も数多くみられるところである。この点、定期建物賃貸借契約においては、家賃増減について予めルールを決めておくことが有効とされており、賃貸人は安定的な賃料収入が、賃借人も安定的なコスト負担が可能となっているが、思ったほど普及していないというのが実感である。
以上、いくつか例をあげたが、いずれも、賃貸借契約のつくり、特約や禁止条項のつくりをどうするかにより、後に紛争が生じたときの解決の指標が異なってくる。その意味で、借地・借家契約は、一見日常的なシンプルな契約のようにみえて、奥が深く、十分に注意を払わないと弁護士も間違えることが多い。
借地・借家の契約に関して、誤ったアドバイスをしないためには、裁判例を踏まえた特約や禁止条項について、日常から研究しておくことが重要と考える。
(2014年4月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.