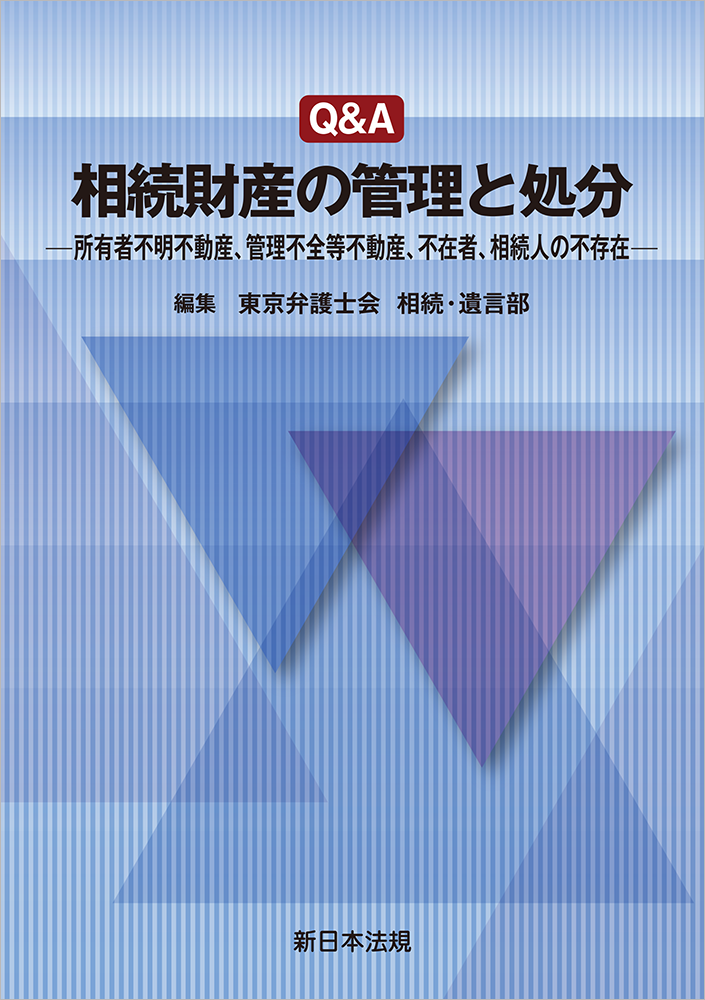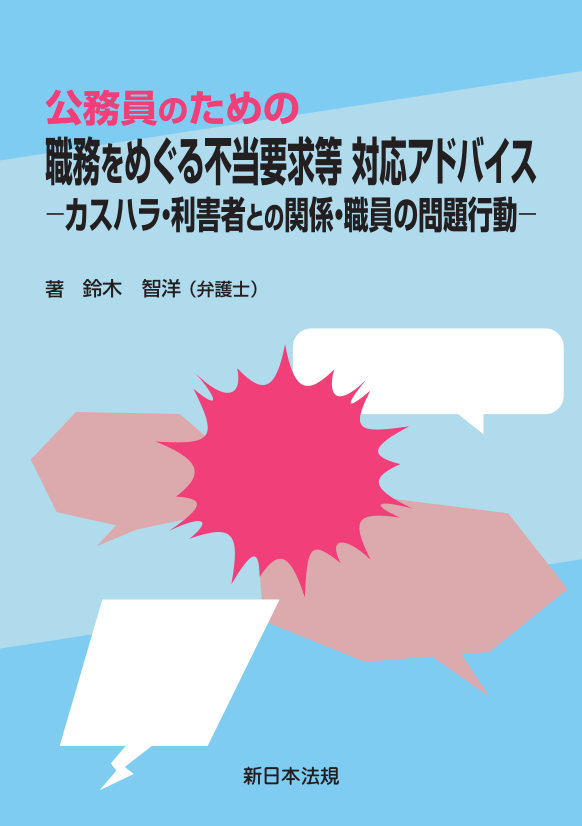一般2025年01月14日 震災の石綿被害、拡大懸念 危険周知試みも、浸透せず 長期潜伏「健診不可欠」 提供:共同通信社

1995年の阪神大震災から30年を控え、被災地で飛散したアスベスト(石綿)による健康被害の拡大が懸念されている。建築材料に広く使われ、潜伏期間は数十年に及ぶ。このため、建物の損壊で飛散した石綿を吸い込んだ人が今後新たに中皮腫などを発症する恐れがある。専門家は危険性の周知と健康診断が欠かせないと指摘するが、対策は道半ばだ。
「石綿はがんを発病させる。マスクで守って!」。震災の約2カ月後、市民グループが神戸市長田区でチラシを配っていたことが分かった。調査した同市のNPO法人「ひょうご労働安全衛生センター」によると、倒壊建物やがれきで多量の粉じんが飛散したとみられる地点も示されていた。
ただ、実際の復旧作業は対策が不十分なまま進められた。被災地の石綿飛散状況を調べてきた中地重晴(なかち・しげはる)熊本学園大教授(環境化学)によると、震災で倒壊した神戸市内のビル1224棟中、少なくとも100棟以上で石綿が露出したとみられる。行政による飛散防止の周知は半年以上がたってから。防じんマスクの着用や事前協議をせず、石綿除去作業をした事例も多く確認された。
センターによると、震災が原因とされる石綿関連疾患での労災・公務災害認定は計8件。申請しても認められないケースがあるほか、災害ボランティアや被災者が吸い込むリスクもあり、被害の全容はつかめないままだ。建物被害が生じる他の災害でも同様の懸念があるものの、防災計画に石綿対策を盛り込む自治体は少ないのが現状だ。
災害時の石綿による健康被害を調べるチーム「災害とアスベスト―阪神淡路30年プロジェクト」によると、2011年の東日本大震災では、仮置き場のがれきが乾燥して粉じんが飛散した。昨年の能登半島地震で大規模な火災に見舞われた石川県輪島市でも、石綿が使われた建物が確認されている。
センターの西山和宏(にしやま・かずひろ)事務局長は「まだ埋もれている被害者がいるかもしれない。行政は健康診断の実施などの対策を至急取ってほしい」と訴える。
アスベスト(石綿)被害
石綿は極細の繊維状天然鉱物。安価で断熱性や耐火性に優れるため建築材料に広く使われたが、粉じんを吸い込むと、中皮腫や肺がんの原因になると判明し、使用が規制された。潜伏期間は平均約40年で、発症すると多くは数年で死亡するため「静かな時限爆弾」とも呼ばれる。2005年に兵庫県尼崎市のクボタ旧神崎工場の周辺で健康被害が判明し、06年に石綿健康被害救済法が施行された。製造・加工工場や建設現場での被害を巡る訴訟で国の賠償責任が認められている。
(2025/01/14)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.