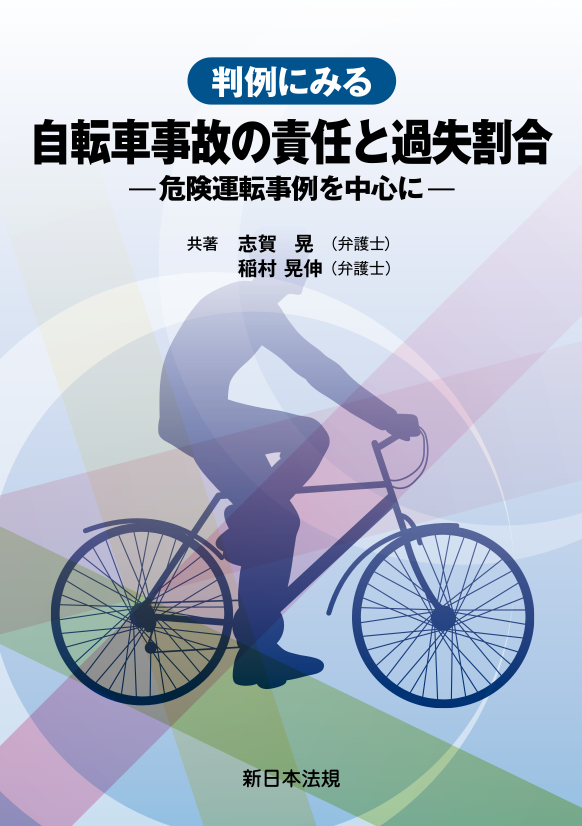民事2025年05月11日 主張整理1年弱、最長に 迅速化進まず、最高裁懸念 公判前手続き 提供:共同通信社

刑事裁判の前に争点や証拠を絞り、公判審理を迅速化する目的で導入された公判前整理手続きが長期化傾向にある。証拠開示を巡って検察側と弁護側が対立する事件も多く、手続きに要した平均期間は2024年、過去最長の1年弱に及んだ。最高裁長官も懸念を示し、制度運営の在り方の見直しに言及するなど、短縮が課題となっている。
▽入らぬ期日
「公判の期日が全然入らない」。刑事弁護が専門の赤木竜太郎(あかぎ・りゅうたろう)弁護士は、現状をこう明かす。過去には起訴から初公判まで約5年要したケースもあった。「『こんなに時間がかかるのか』と被告に言われることも多い」
制度開始は05年。裁判員裁判事件などが対象で、裁判官、検察官、弁護人が主張内容や公判日程を整理する。手続きの期間は、裁判員裁判事件で09年に平均2・8カ月だったのが、昨年は同11・8カ月に延びた。
22年7月に起きた安倍晋三元首相銃撃事件は、23年10月に始まった手続きが今も続く。否認事件や争点が多い事件は特に延びる傾向がある。最高裁によると、24年10月末までに手続きを終えた公判のうち最も長いケースで7年7カ月かかった。
▽新しい証拠
最高裁の有識者懇談会や法曹関係者が主因に挙げるのが、制度導入時には普及していなかった交流サイト(SNS)の電子データや、防犯カメラ映像といった証拠の急増だ。検察側が保管する証拠を幅広く開示するよう求める弁護側に対し、検察幹部は「膨大な情報の中から証拠として出せるかは判断が必要」と慎重な姿勢を示す。証拠を警察が保管している場合もあり、開示判断だけで数カ月かかることもある。
最高裁の今崎幸彦(いまさき・ゆきひこ)長官は昨年8月の就任記者会見で、手続きの長期化は重要な課題だと強調した。「全体としては、非常に丁寧で綿密な検討をしている」と評価した上で、丁寧さが長期化を招いている可能性も示唆。「小手先の対応で期間を短くできたとしても、根本的な解決にならない」とも述べた。
▽薄れる記憶
手続きの長期化は被告の拘束期間に影響し、公判を待つ被害者らの心理的負担も増えかねない。ベテラン刑事裁判官は「時間がたつほど証拠は散逸するし、証人の記憶も薄れる。裁判の質や信頼に関わる問題だ」と危機感をあらわにする。
国会では、捜査書類を電子化し、オンラインで開示できるようにする刑事訴訟法などの改正案が審議中だ。赤木弁護士は、手続き期間の短縮策として、法改正を踏まえたデータベース化による全面証拠開示の促進や、関わる裁判官の増員などを提案する。「IT化を活用して情報を円滑に共有できれば、期間はおのずと短くなる」と話した。
(2025/05/11)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.