解説記事2004年04月26日 【実務解説】 日本経団連の「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の解説(2004年4月26日号・№064)
実務解説
日本経団連の「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の解説
日本経済団体連合会経済本部経済法制グループ長 岩間芳仁
日本経済団体連合会産業本部 正木義久
日本経済団体連合会総務本部 清家武彦
日本経済団体連合会経済本部 魚住康博
一 はじめに
日本経団連では、昭和56年の商法改正に伴う法務省令に対応して、計算書類等の記載に関する、いわゆる「経団連ひな型」を作成した。さらに平成15年4月の改正商法施行規則の施行を契機に、経済法規委員会企画部会(部会長 西川元啓新日本製鐵常任顧問)として、これを全面的に見直し、同年5月27日、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型(以下、従前ひな型)」としてとりまとめ、関係者の参考に供した。その後、同年7月23日に議員立法で、定款授権による取締役会での自己株式取得の解禁等の改正商法が成立し、それに伴い9月25日に商法施行規則が改正・施行された。また、本年に入り、委員会等設置会社における初の決算期が到来するとともに、連結計算書類に関する規定(大会社連結特例規定及び委員会等設置会社連結特例規定)に基づき、4月決算期から連結計算書類制度も始まった。
そこで、会社、株主などの関係者がこうした状況変化に的確に対応できるよう、このほど、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版をとりまとめた。今回の改訂に当たっては、わが国を代表する企業の専門家である日本経団連経済法規委員会の企画部会ならびに企業会計部会(部会長 八木良樹日立製作所取締役)委員による検討をベースとし、法務省、太田洋弁護士をはじめとする西村ときわ法律事務所の先生方、斎藤昇公認会計士をはじめとするあずさ監査法人の先生方、さらには東京株式懇話会など、法律・会計関係の実務家団体から格別のご助言・ご協力を得た。また、従前ひな型に関する利用者の皆様からのお問い合わせやご指摘も踏まえた。
日本経団連ひな型の特徴は、コスト・ベネフィットの観点から、簡潔、明快かつ実質を重視していることにある。例えば、経済界全体としての統一的なフォームを定めるのではなく、作成会社において、業種・業態の実情や企業秘密等に配慮しつつ、自らの創意工夫によって、会社の概況、財産、損益などの状態を正しく、かつ、わかりやすく記載し、株主の容易な理解と迅速な判断に供することができるようにしてある。さらに、法定記載事項であっても、作成会社にとって記載すべき事項がない場合には記載を要しないとしている。
各社が自らの方針に基づき、創意工夫によって各種書類を作成される際に、本ひな型を参考資料のひとつとして活用していただければ幸いである。
このひな型は、平成15年9月25日以降に終了する営業年度に係る計算書類に適用する。ただし、連結計算書類については、平成15年4月1日より後の最初に到来する決算期に関する定時総会の終結時までは適用されない。したがって、3月決算会社は、平成17年3月期の決算期から適用となる(早期適用は不可)。
なお、今回の改訂は書式を含め、従前ひな型全体について見直しを行っているが、本解説は紙幅の関係上、改訂のポイントだけを記載するに過ぎない。ひな型全体については、日本経団連のホームページhttp://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/index04.htmlで公開しているのでご覧いただきたい。
二 営業報告書
営業報告書については、連結特例規定や昨年9月25日施行の商法施行規則の改正内容を反映させるため、平成15年5月策定の従前ひな型の記述を全面的に改訂している。
まず構成については、従前ひな型の商法施行規則第103条第1項各号の順に従った記述を改め、「営業の概況→会社の概況→決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実→その他会社の状況に関する重要な事実」とした。その上で、①営業の概況を「計算書類作成会社の状況について記載する場合」と「企業集団の状況について記載する場合」とに分け、②会社の概況のうち「主要な事業内容(あるいは企業集団の主要なセグメント)」「主要な営業所及び工場(あるいは企業集団の主要拠点)」「従業員の状況(あるいは企業集団の従業員の状況)」をまとめて冒頭に位置付け、連結計算書類作成会社とそれ以外の会社で混乱が生じないように工夫した。
「営業の概況」のうち、営業の経過及び成果、設備投資の状況を企業集団について記載する場合に、複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別に状況を記載する(ただし、事業セグメント別の損益は不要)が、記載が困難な事項についてはこの限りではない。企業集団の資金調達の状況についても、グループ全体で外部から資金調達をしている場合にはその内容を記載すればよく、例えば子会社が発行した社債の大部分を親会社が引き受けた場合は、企業集団として重要な意味のある「グループ外からの資金調達」に当たらなければ記載する必要はない。
なお、業績及び財産の状況の推移並びにその説明については、企業集団について記載する場合であっても計算書類作成会社についての記載を省略することはできない。
「会社の概況」のうち、企業集団の従業員の状況を記載する場合には、国内・海外別従業員数(就業者数で可)などを記載する。計算書類作成会社の従業員の状況に関する記載事項の解説の中には、男女別、平均年齢、平均勤続年数、年齢構成、総人件費、平均給与、定年制などの記載を例に挙げるものがあり(弥永真生「コンメンタール商法施行規則」298頁参照)、本ひな型でもそのいくつかを考えられる項目として挙げているが、企業集団全体についてこれらの数値を把握することは困難であることはもとより、雇用形態の多様化する中で男女比や各種平均値の開示などに意味があるのかは計算書類作成会社においても再検討の余地があり、各社・各グループの事情に応じて検討することが必要であろう。
自己株式の取得、処分等及び保有については、商法施行規則第103条第1項第9号に基づき記載例を改訂した(表形式を採用)。「最終決算期後、当該決算期に係る計算書類を会計監査人、監査役に提出する取締役会開催時(特例会社の場合、執行役が会計監査人、監査委員会へ提出する時)」までに取得した自己株式については、その株式数や取得金額に鑑みて、重要性がある場合には後発事象として記載する旨を、記載方法の説明に加えている。
新株予約権に関する事項については、商法施行規則第103条第2項に基づき記載例を改訂した。ストック・オプション等を目的として、新株予約権を特に有利な条件で発行した場合の「有利な条件の内容」としては、商法第280条ノ21により決議した内容等を記載することとした。具体的な記載内容としては「対象者に新株予約権が無償で付与された旨」や「対象者にその公正価値(ブラック・ショールズ式等で算出された理論値)とその発行価額との差額分だけ有利な新株予約権が付与された旨」などが考えられる。
取締役等に支払った報酬等については、財務会計基準機構企業会計基準委員会が平成16年3月9日に公表した実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」に加え、非金銭報酬やストック・オプションに関する実務の取扱いを踏まえ、従前ひな型を変更した(記載例1参照)。
具体的には①商法第283条第1項に基づき利益処分として支給した役員賞与は別途記載するが、商法269条第1項及び第279条第1項に基づく役員賞与については、当期支払額に含めて記載することとした。②非金銭報酬については、金銭的価値を算定できるものは当期支払額に含めるか摘要欄に当該金額を記載するが、算定が困難な場合(例えば家賃の推定が困難な役員社宅等の提供)については摘要欄にその内容を簡潔に記載することとした。また、③実務では、「報酬その他職務遂行の対価」とは扱っていない(インセンティブとして付与している)ストック・オプションを開示対象に含まない取扱いも見受けられ、そうした実務に沿った記載とした。
従前ひな型では採り上げていなかった特例会社の記載事項「監査委員会の職務遂行のために必要な事項」「取締役・執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針」については、記載方法の説明を示すにとどめた。
会計監査人に対する報酬等については[記載例2]のように示し、以下のような補足説明を付した。
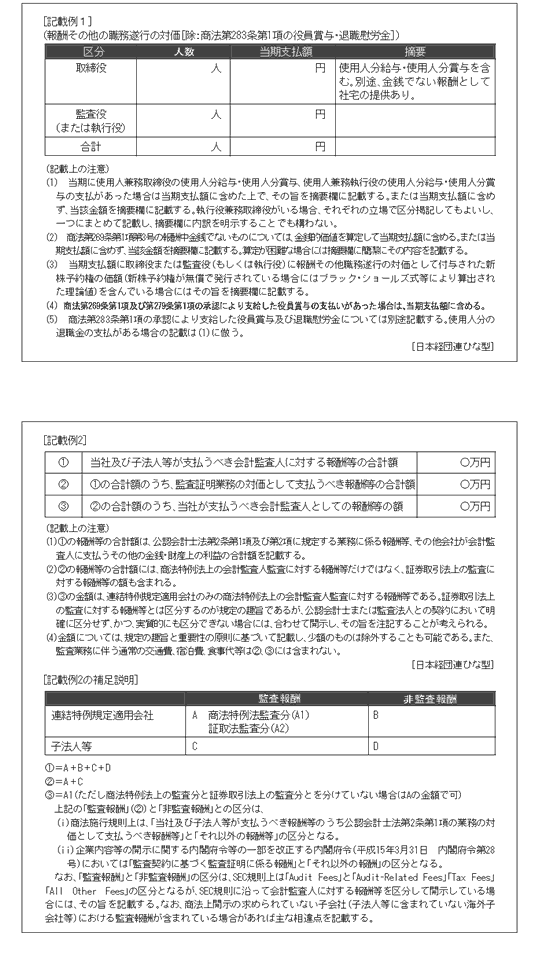
なお、商法及び同施行規則は、実務で対応可能なレベルの開示を求めているのであり、無理な開示を強いるものではない。「取締役等に支払った報酬等」や「会計監査人に対する報酬等」についても金銭換算が容易でないものや、実際の契約に照らして施行規則に沿った分類を示すことのできないものについては、支払われたものの内容や契約内容に沿った分類など、可能なレベルの開示をすればよい。また、「大株主」への議決権比率などについても営業報告書作成段階での把握は困難な場合も考えられ、そうした場合には概算の数値を記載することも可能である。
三 附属明細書
附属明細書については、固定資産と引当金の明細に係る記載上の注意、および取締役等の報酬の記載内容を改訂した。
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細については、平成16年3月31日に終了する事業年度から適用できるようになった固定資産の減損に係る会計基準に対応するため、減損損失を認識した場合の取扱いを明らかにしている。具体的には、財務諸表等規則における記載方法を参考に、貸借対照表において、直接控除形式または間接控除形式で記載する。また、研究開発費等に係る会計基準において定められる市場販売目的のソフトウエアの評価損も同様に処理される。本ひな型の記載例では、直接控除形式を取り上げているが、当期の減損損失の金額を当期減少額に含めて記載し、その金額は内書き(かっこ書き)する。
引当金の明細については、記載上の注意の内容を2点追加している。第一に、会計方針としてその計上理由及び額の算定方法が貸借対照表に注記されている場合には、附属明細書において、計上理由及び算定方法の記載が不要である。第二に、退職給付引当金の記載について、財務諸表等規則を踏まえた注記を貸借対照表上行い、その旨を附属明細書に注記している場合には、省略することができる。
取締役等の報酬について、定款に責任軽減や社外取締役の責任限定に関する規定を置いていない場合には、附属明細書において開示が求められるが、その記載内容は、営業報告書と平仄を併せている(営業報告書のひな型記載例1を参照)。
四 連結計算書類
1 全般的事項
今般の全面改訂における目玉の一つとして、連結計算書類を追加している。貸借対照表等のひな型と同様、大株式会社等である製造会社を前提にしているが、連結計算書類の計上科目は大幅に簡素化することが可能であるため、最低限の記載を想定している(記載例3参照)。当然のことながら、各社の業種・業態等に応じて、科目を細分化することも考えられる。有報提出大会社については、商法施行規則第197条により、貸借対照表、損益計算書又は連結計算書類の用語又は様式の全部又は一部について、財務諸表等規則又は連結財務諸表規則の用語又は様式を用いることができる。
また、営業報告書で企業集団の状況について記載する場合など、連結情報を重点的に開示するために、本ひな型とは順番を逆にして、連結貸借対照表等を先に記載し、貸借対照表等を後に記載することも考えられる。
記載金額については、商法施行規則第157条が同規則第49条を準用しており、貸借対照表及び損益計算書と同様に、四捨五入、切り上げ、切捨てなどの方式が認められている。端数処理の方法については、その注記が重要な意味を持つとは考え難いこと、有価証券報告書においても端数処理の注記が不要とされていること(財務会計基準機構「有価証券報告書の作成の仕方」参照)を踏まえ、今般の改訂にあたり、貸借対照表等の注記事項からも削除しているが、必要な場合には、注記することも考えられる。
注記の方法については、貸借対照表及び損益計算書のひな型のように、それぞれの末尾に注記事項を記載する方法のほか、連結貸借対照表及び連結損益計算書のひな型のように、最後に注記事項だけをまとめて、①連結計算書類作成のための基本となる事項の注記と②連結貸借対照表に関係する注記及び③連結損益計算書に関係する注記を記載する方法も可能であるため、本ひな型においては、個別と連結で別々の方法を採用している。実際に記載するにあたっては、個別と連結で統一した方法を用いることも考えられる。
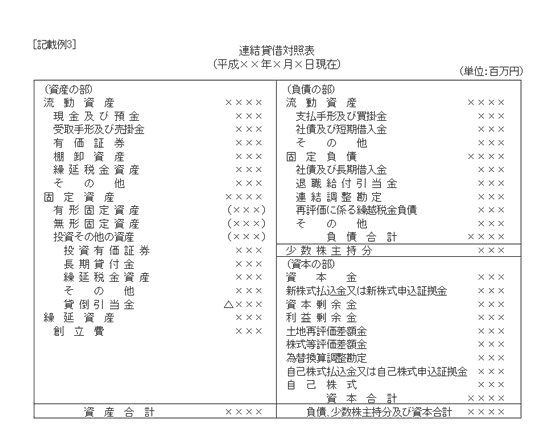
2 連結計算書類に固有の事項
連結計算書類特有の科目としては、連結貸借対照表における「連結調整勘定」、「少数株主持分」、連結損益計算書における「連結調整勘定償却額」、「持分法による投資利益」、「少数株主持分利益」などが挙げられる。これらは個別の貸借対照表及び損益計算書に計上されることはなく、持分法適用関係会社や少数株主が存在する場合など、連結上で必要な場合にのみ計上される科目である。
連結計算書類に固有の問題として、いわゆる米国SEC基準による用語、様式及び作成方法がある。商法施行規則第179条によれば、連結財務諸表規則第87条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項の規定に基づき、金融庁長官が認めた場合、連結財務諸表提出会社は、準拠している用語、様式及び作成方法を注記した上で(商法施行規則第179条第3項)、かかる米国SEC基準に基づく連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成が許容される。また、その際には、商法施行規則で求める開示レベルと証券取引法で求める開示レベルが完全に一致するものではないと考えられるため、商法施行規則で定める連結貸借対照表等に記載又は注記をすべき事項に相当するものを除くその他の事項(証券取引法上でのみ求められる開示項目等)は、その記載は又は注記を省略することができると考えられる。
なお、米国SEC基準の採用の他、連結貸借対照表等に注記すべき事項としては、「連結の範囲・持分法の適用」(商法施行規則第144条第3項、第152条第1~3項)、「連結決算期又は連結会計年度」(同規則第145条第3項)、「会計方針等」(同規則第153条第1~3項)、「重要な後発事象」(同規則第154条)、「追加情報」(同規則第155条)、「金銭債権等から直接控除した取立不能見込額」(同規則第163条第3項)、「有形固定資産から直接控除した減価償却累計額」(同規則第163条第3項)、「担保資産等」(同規則第166条)、「1株当たり当期純利益等」(同規則第177条)が定められている。ただし、同規則第156条第2項により、これらの事項を営業報告書に記載した場合においては、その注記を省略することができる。
その他、連結貸借対照表等においては、連結会社間に会計方針の差異があり、かつ、適用している複数の会計方針の中で主なものがある場合等も想定されるため、重要な会計方針について、例えば、棚卸資産の評価方法及び評価基準を「主として移動平均法による低価法」として記載するなどの方法で注記することも考えられる。
3 その他
企業会計基準委員会の実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」においては、役員賞与について、会計上は発生時に費用として会計処理することが適当であるとの考え方を示しつつ、当面の間、これまでの実務慣行通りに費用処理を行わず、未処分利益の減少として会計処理する方法も認めている。ただし、本実務対応報告においては、「役員への支給を費用として処理した場合において、当期末後の株主総会においてその役員への支給額を決議しようとするときには、当該支給は株主総会決議が前提となるので、当期の費用として引当金(商法施行規則第43条の引当金)に計上することが適当である。この場合、当該引当金の計上基準については、会計方針として記載することとなる。」とされているため、留意が必要である。【なお、当該株主総会決議に関連して、例えば、費用処理した場合に当該支給を利益処分の議案として取り扱うことの可否については、法務省の担当官によれば、1つの経済事象である当該支給に対して、2つの異なる会計処理をする(費用処理及び利益処分)ことになるため、取締役及び会計監査人の対応が必要になる場合があるとされている。(注)】
(注)濱克彦「『役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い』についての商法上の考え方」 T&Amaster4月19日号18頁参照。
五 決算公告要旨
決算公告の要旨については、今般のひな型改訂にあたり、大株式会社の貸借対照表及び損益計算書の要旨と小株式会社の貸借対照表の要旨のほかに、中株式会社の貸借対照表の要旨を追加した。
株式会社の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、100万円単位で表示することも可能であり、大株式会社等については、1億円単位で表示することも可能である。ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、適切な単位をもって表示しなければならないので、留意が必要である(商法施行規則第113条第1~3項)。
六 株主総会参考書類・議決権行使書面
株主総会参考書類については、特例会社の実務や役員賞与金に関する取扱いの変更、従前ひな型に対する指摘などを踏まえた修正のほか、自己株式取得に係る議案について記載例を追加している。
議決権行使書面については、電磁的方法による議決権行使を合理的な時間(例:会社の営業時間終了時)で締め切ることを予め株主に知らせることにより、会社は株主の議決権行使期限の限定をすることができるとの見解(郡谷大輔「平成13年改正商法(11月改正)の解説[ⅩⅠ・完]」『旬刊商事法務』No.1664・37頁)に沿った変更を、従前ひな型に加えている。
七 監査報告書
監査報告書のひな型については、今般の改訂で、特例会社監査報告書及び連結計算書類に係る監査報告書を追加している。監査役会監査報告書については、監査対象の限定例示として誤解されないよう、従前ひな型の冒頭部分に記載されていた「商法施行規則第133条第1項に掲げる事項その他」を削除した以外、変更を加えていない。
1 特例会社監査報告書
特例会社監査報告書の記載事項は、監査役会監査報告書とほぼ同様の内容を求めている(記載例4参照)。監査報告書作成の基本原則については、商法施行規則第135条第2項により、監査役会監査報告書の規定が準用されている。後発事象(商法施行規則第137条)、電磁的記録による作成を規定する署名等(商法施行規則第139条)についても、準用規定が置かれている。
また、個々の記載事項に関して、商法特例法第21条の29第2項の各号において、営業報告書や附属明細書の会計に関する部分以外の部分や利益処分案等を定めているが、これらも監査役会監査報告書とほぼ同様の内容である。さらに、取締役または執行役に競業避止や利益相反取引等に関する義務違反があった場合には、商法施行規則第138条により、事項ごとに記載し、その監査の方法の概要を記載する必要があるが、これについても監査役会監査報告書とほぼ同様である。
しかし、商法特例法第21条の29第2項第4号により、商法特例法第21条の7第1項第2号に規定する「監査委員会の職務の遂行のために必要なものとして定める事項」についての取締役会決議の内容の相当性について、監査役会監査報告書と異なり、監査委員会の意見を記載することが求められている。本ひな型では、監査委員会の監査の方法の概要において、上記取締役会決議の内容の監査を行う旨を明記するとともに、監査の結果において、内容の相当に係る意見を記載することにした。
なお、特例会社の監査は、独任制を残す監査役会と異なり、組織的に行うことになっているため、監査報告書の主文において、何に基づく監査報告書なのかを明示する必要はない。
2 連結計算書類監査報告書
連結計算書類の監査報告書の記載事項については、個別計算書類との相違点に留意する必要がある。
第一に、会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当であると認めた場合についてもその旨を記載する必要がある(商法施行規則第183条第3項第1号)。
第二に、会計以外の業務監査が連結計算書類の監査に存在しないため、商法特例法第14条第3項第2号に掲げる事項は記載事項に含まれていない。
第三に、連結計算書類には営業報告書、利益処分案、附属明細書が含まれないため、それらに関連する記載事項は存在しない。
第四に、連結計算書類の監査等については、署名等を規定した商法施行規則第134条および第139条の準用規定が設けられていない。従って、法令上、署名押印は不要と考えられ、本ひな型では、連結計算書類監査報告書において、印および署名の記載を求めないこととした。
[記載例4]
監査報告書
当監査委員会は、平成××年×月×日から平成××年×月×日までの第××期営業年度における取締役及び執行役の職務の執行に関する監査の結果につき、協議した結果、次のとおり報告いたします。
Ⅰ.監査委員会の監査の方法の概要
監査委員会は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」)」第21条の7第1項第2号及び商法施行規則第193条に掲げる取締役会決議の内容を監査し、かつ監査委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、重要な会議に出席し、取締役、執行役及び使用人から職務の執行に関する事項の報告を受けまたは聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況の調査を行いました。
また、会計監査人から報告及び説明を受け、これに基づき計算書類及び附属明細書につき検証いたしました。
Ⅱ.監査の結果
1. 会計監査人○○監査法人(または公認会計士○○○○氏)の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。
2. 営業報告書の会計に関する部分以外の部分は、法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
3. 監査委員会の職務遂行のために必要なものとして、商法施行規則第193条に列記されている事項について、取締役会が決議した内容は、相当であると認めます。
4. 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし、指摘すべき事項は認められません。
5. 附属明細書の会計に関する部分以外の部分は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
6. 取締役または執行役の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
平成×年×月×日
○○○○株式会社 監査委員会
監査委員 ○○○○ 印
監査委員 ○○○○ 印
監査委員 ○○○○ 印
(自署)
(注)監査委員〇〇〇〇及び〇〇〇〇は、商法特例法第21条の8第4項ただし書き及び同法第1条の3第1項第2号に定める社外取締役であります。
[日本経団連ひな型]
日本経団連の「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の解説
日本経済団体連合会経済本部経済法制グループ長 岩間芳仁
日本経済団体連合会産業本部 正木義久
日本経済団体連合会総務本部 清家武彦
日本経済団体連合会経済本部 魚住康博
一 はじめに
日本経団連では、昭和56年の商法改正に伴う法務省令に対応して、計算書類等の記載に関する、いわゆる「経団連ひな型」を作成した。さらに平成15年4月の改正商法施行規則の施行を契機に、経済法規委員会企画部会(部会長 西川元啓新日本製鐵常任顧問)として、これを全面的に見直し、同年5月27日、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型(以下、従前ひな型)」としてとりまとめ、関係者の参考に供した。その後、同年7月23日に議員立法で、定款授権による取締役会での自己株式取得の解禁等の改正商法が成立し、それに伴い9月25日に商法施行規則が改正・施行された。また、本年に入り、委員会等設置会社における初の決算期が到来するとともに、連結計算書類に関する規定(大会社連結特例規定及び委員会等設置会社連結特例規定)に基づき、4月決算期から連結計算書類制度も始まった。
そこで、会社、株主などの関係者がこうした状況変化に的確に対応できるよう、このほど、「商法施行規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版をとりまとめた。今回の改訂に当たっては、わが国を代表する企業の専門家である日本経団連経済法規委員会の企画部会ならびに企業会計部会(部会長 八木良樹日立製作所取締役)委員による検討をベースとし、法務省、太田洋弁護士をはじめとする西村ときわ法律事務所の先生方、斎藤昇公認会計士をはじめとするあずさ監査法人の先生方、さらには東京株式懇話会など、法律・会計関係の実務家団体から格別のご助言・ご協力を得た。また、従前ひな型に関する利用者の皆様からのお問い合わせやご指摘も踏まえた。
日本経団連ひな型の特徴は、コスト・ベネフィットの観点から、簡潔、明快かつ実質を重視していることにある。例えば、経済界全体としての統一的なフォームを定めるのではなく、作成会社において、業種・業態の実情や企業秘密等に配慮しつつ、自らの創意工夫によって、会社の概況、財産、損益などの状態を正しく、かつ、わかりやすく記載し、株主の容易な理解と迅速な判断に供することができるようにしてある。さらに、法定記載事項であっても、作成会社にとって記載すべき事項がない場合には記載を要しないとしている。
各社が自らの方針に基づき、創意工夫によって各種書類を作成される際に、本ひな型を参考資料のひとつとして活用していただければ幸いである。
このひな型は、平成15年9月25日以降に終了する営業年度に係る計算書類に適用する。ただし、連結計算書類については、平成15年4月1日より後の最初に到来する決算期に関する定時総会の終結時までは適用されない。したがって、3月決算会社は、平成17年3月期の決算期から適用となる(早期適用は不可)。
なお、今回の改訂は書式を含め、従前ひな型全体について見直しを行っているが、本解説は紙幅の関係上、改訂のポイントだけを記載するに過ぎない。ひな型全体については、日本経団連のホームページhttp://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/index04.htmlで公開しているのでご覧いただきたい。
二 営業報告書
営業報告書については、連結特例規定や昨年9月25日施行の商法施行規則の改正内容を反映させるため、平成15年5月策定の従前ひな型の記述を全面的に改訂している。
まず構成については、従前ひな型の商法施行規則第103条第1項各号の順に従った記述を改め、「営業の概況→会社の概況→決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実→その他会社の状況に関する重要な事実」とした。その上で、①営業の概況を「計算書類作成会社の状況について記載する場合」と「企業集団の状況について記載する場合」とに分け、②会社の概況のうち「主要な事業内容(あるいは企業集団の主要なセグメント)」「主要な営業所及び工場(あるいは企業集団の主要拠点)」「従業員の状況(あるいは企業集団の従業員の状況)」をまとめて冒頭に位置付け、連結計算書類作成会社とそれ以外の会社で混乱が生じないように工夫した。
「営業の概況」のうち、営業の経過及び成果、設備投資の状況を企業集団について記載する場合に、複数の事業セグメントを有している場合には、事業セグメント別に状況を記載する(ただし、事業セグメント別の損益は不要)が、記載が困難な事項についてはこの限りではない。企業集団の資金調達の状況についても、グループ全体で外部から資金調達をしている場合にはその内容を記載すればよく、例えば子会社が発行した社債の大部分を親会社が引き受けた場合は、企業集団として重要な意味のある「グループ外からの資金調達」に当たらなければ記載する必要はない。
なお、業績及び財産の状況の推移並びにその説明については、企業集団について記載する場合であっても計算書類作成会社についての記載を省略することはできない。
「会社の概況」のうち、企業集団の従業員の状況を記載する場合には、国内・海外別従業員数(就業者数で可)などを記載する。計算書類作成会社の従業員の状況に関する記載事項の解説の中には、男女別、平均年齢、平均勤続年数、年齢構成、総人件費、平均給与、定年制などの記載を例に挙げるものがあり(弥永真生「コンメンタール商法施行規則」298頁参照)、本ひな型でもそのいくつかを考えられる項目として挙げているが、企業集団全体についてこれらの数値を把握することは困難であることはもとより、雇用形態の多様化する中で男女比や各種平均値の開示などに意味があるのかは計算書類作成会社においても再検討の余地があり、各社・各グループの事情に応じて検討することが必要であろう。
自己株式の取得、処分等及び保有については、商法施行規則第103条第1項第9号に基づき記載例を改訂した(表形式を採用)。「最終決算期後、当該決算期に係る計算書類を会計監査人、監査役に提出する取締役会開催時(特例会社の場合、執行役が会計監査人、監査委員会へ提出する時)」までに取得した自己株式については、その株式数や取得金額に鑑みて、重要性がある場合には後発事象として記載する旨を、記載方法の説明に加えている。
新株予約権に関する事項については、商法施行規則第103条第2項に基づき記載例を改訂した。ストック・オプション等を目的として、新株予約権を特に有利な条件で発行した場合の「有利な条件の内容」としては、商法第280条ノ21により決議した内容等を記載することとした。具体的な記載内容としては「対象者に新株予約権が無償で付与された旨」や「対象者にその公正価値(ブラック・ショールズ式等で算出された理論値)とその発行価額との差額分だけ有利な新株予約権が付与された旨」などが考えられる。
取締役等に支払った報酬等については、財務会計基準機構企業会計基準委員会が平成16年3月9日に公表した実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」に加え、非金銭報酬やストック・オプションに関する実務の取扱いを踏まえ、従前ひな型を変更した(記載例1参照)。
具体的には①商法第283条第1項に基づき利益処分として支給した役員賞与は別途記載するが、商法269条第1項及び第279条第1項に基づく役員賞与については、当期支払額に含めて記載することとした。②非金銭報酬については、金銭的価値を算定できるものは当期支払額に含めるか摘要欄に当該金額を記載するが、算定が困難な場合(例えば家賃の推定が困難な役員社宅等の提供)については摘要欄にその内容を簡潔に記載することとした。また、③実務では、「報酬その他職務遂行の対価」とは扱っていない(インセンティブとして付与している)ストック・オプションを開示対象に含まない取扱いも見受けられ、そうした実務に沿った記載とした。
従前ひな型では採り上げていなかった特例会社の記載事項「監査委員会の職務遂行のために必要な事項」「取締役・執行役の個人別の報酬の内容の決定に関する方針」については、記載方法の説明を示すにとどめた。
会計監査人に対する報酬等については[記載例2]のように示し、以下のような補足説明を付した。
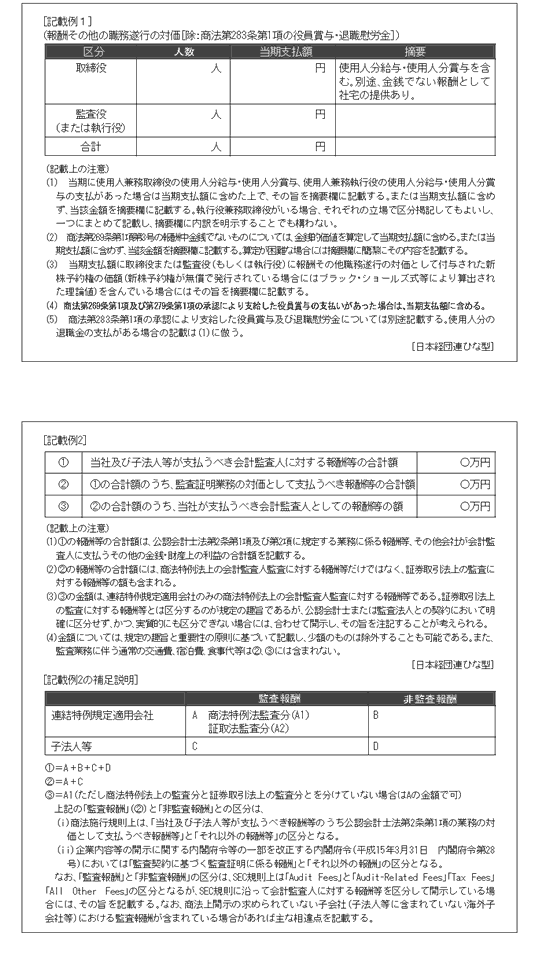
なお、商法及び同施行規則は、実務で対応可能なレベルの開示を求めているのであり、無理な開示を強いるものではない。「取締役等に支払った報酬等」や「会計監査人に対する報酬等」についても金銭換算が容易でないものや、実際の契約に照らして施行規則に沿った分類を示すことのできないものについては、支払われたものの内容や契約内容に沿った分類など、可能なレベルの開示をすればよい。また、「大株主」への議決権比率などについても営業報告書作成段階での把握は困難な場合も考えられ、そうした場合には概算の数値を記載することも可能である。
三 附属明細書
附属明細書については、固定資産と引当金の明細に係る記載上の注意、および取締役等の報酬の記載内容を改訂した。
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細については、平成16年3月31日に終了する事業年度から適用できるようになった固定資産の減損に係る会計基準に対応するため、減損損失を認識した場合の取扱いを明らかにしている。具体的には、財務諸表等規則における記載方法を参考に、貸借対照表において、直接控除形式または間接控除形式で記載する。また、研究開発費等に係る会計基準において定められる市場販売目的のソフトウエアの評価損も同様に処理される。本ひな型の記載例では、直接控除形式を取り上げているが、当期の減損損失の金額を当期減少額に含めて記載し、その金額は内書き(かっこ書き)する。
引当金の明細については、記載上の注意の内容を2点追加している。第一に、会計方針としてその計上理由及び額の算定方法が貸借対照表に注記されている場合には、附属明細書において、計上理由及び算定方法の記載が不要である。第二に、退職給付引当金の記載について、財務諸表等規則を踏まえた注記を貸借対照表上行い、その旨を附属明細書に注記している場合には、省略することができる。
取締役等の報酬について、定款に責任軽減や社外取締役の責任限定に関する規定を置いていない場合には、附属明細書において開示が求められるが、その記載内容は、営業報告書と平仄を併せている(営業報告書のひな型記載例1を参照)。
四 連結計算書類
1 全般的事項
今般の全面改訂における目玉の一つとして、連結計算書類を追加している。貸借対照表等のひな型と同様、大株式会社等である製造会社を前提にしているが、連結計算書類の計上科目は大幅に簡素化することが可能であるため、最低限の記載を想定している(記載例3参照)。当然のことながら、各社の業種・業態等に応じて、科目を細分化することも考えられる。有報提出大会社については、商法施行規則第197条により、貸借対照表、損益計算書又は連結計算書類の用語又は様式の全部又は一部について、財務諸表等規則又は連結財務諸表規則の用語又は様式を用いることができる。
また、営業報告書で企業集団の状況について記載する場合など、連結情報を重点的に開示するために、本ひな型とは順番を逆にして、連結貸借対照表等を先に記載し、貸借対照表等を後に記載することも考えられる。
記載金額については、商法施行規則第157条が同規則第49条を準用しており、貸借対照表及び損益計算書と同様に、四捨五入、切り上げ、切捨てなどの方式が認められている。端数処理の方法については、その注記が重要な意味を持つとは考え難いこと、有価証券報告書においても端数処理の注記が不要とされていること(財務会計基準機構「有価証券報告書の作成の仕方」参照)を踏まえ、今般の改訂にあたり、貸借対照表等の注記事項からも削除しているが、必要な場合には、注記することも考えられる。
注記の方法については、貸借対照表及び損益計算書のひな型のように、それぞれの末尾に注記事項を記載する方法のほか、連結貸借対照表及び連結損益計算書のひな型のように、最後に注記事項だけをまとめて、①連結計算書類作成のための基本となる事項の注記と②連結貸借対照表に関係する注記及び③連結損益計算書に関係する注記を記載する方法も可能であるため、本ひな型においては、個別と連結で別々の方法を採用している。実際に記載するにあたっては、個別と連結で統一した方法を用いることも考えられる。
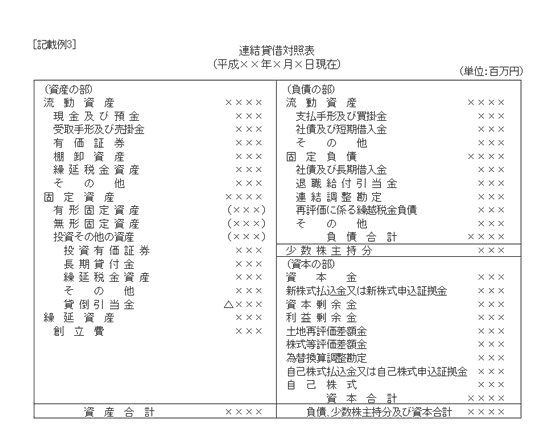
2 連結計算書類に固有の事項
連結計算書類特有の科目としては、連結貸借対照表における「連結調整勘定」、「少数株主持分」、連結損益計算書における「連結調整勘定償却額」、「持分法による投資利益」、「少数株主持分利益」などが挙げられる。これらは個別の貸借対照表及び損益計算書に計上されることはなく、持分法適用関係会社や少数株主が存在する場合など、連結上で必要な場合にのみ計上される科目である。
連結計算書類に固有の問題として、いわゆる米国SEC基準による用語、様式及び作成方法がある。商法施行規則第179条によれば、連結財務諸表規則第87条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項の規定に基づき、金融庁長官が認めた場合、連結財務諸表提出会社は、準拠している用語、様式及び作成方法を注記した上で(商法施行規則第179条第3項)、かかる米国SEC基準に基づく連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成が許容される。また、その際には、商法施行規則で求める開示レベルと証券取引法で求める開示レベルが完全に一致するものではないと考えられるため、商法施行規則で定める連結貸借対照表等に記載又は注記をすべき事項に相当するものを除くその他の事項(証券取引法上でのみ求められる開示項目等)は、その記載は又は注記を省略することができると考えられる。
なお、米国SEC基準の採用の他、連結貸借対照表等に注記すべき事項としては、「連結の範囲・持分法の適用」(商法施行規則第144条第3項、第152条第1~3項)、「連結決算期又は連結会計年度」(同規則第145条第3項)、「会計方針等」(同規則第153条第1~3項)、「重要な後発事象」(同規則第154条)、「追加情報」(同規則第155条)、「金銭債権等から直接控除した取立不能見込額」(同規則第163条第3項)、「有形固定資産から直接控除した減価償却累計額」(同規則第163条第3項)、「担保資産等」(同規則第166条)、「1株当たり当期純利益等」(同規則第177条)が定められている。ただし、同規則第156条第2項により、これらの事項を営業報告書に記載した場合においては、その注記を省略することができる。
その他、連結貸借対照表等においては、連結会社間に会計方針の差異があり、かつ、適用している複数の会計方針の中で主なものがある場合等も想定されるため、重要な会計方針について、例えば、棚卸資産の評価方法及び評価基準を「主として移動平均法による低価法」として記載するなどの方法で注記することも考えられる。
3 その他
企業会計基準委員会の実務対応報告第13号「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」においては、役員賞与について、会計上は発生時に費用として会計処理することが適当であるとの考え方を示しつつ、当面の間、これまでの実務慣行通りに費用処理を行わず、未処分利益の減少として会計処理する方法も認めている。ただし、本実務対応報告においては、「役員への支給を費用として処理した場合において、当期末後の株主総会においてその役員への支給額を決議しようとするときには、当該支給は株主総会決議が前提となるので、当期の費用として引当金(商法施行規則第43条の引当金)に計上することが適当である。この場合、当該引当金の計上基準については、会計方針として記載することとなる。」とされているため、留意が必要である。【なお、当該株主総会決議に関連して、例えば、費用処理した場合に当該支給を利益処分の議案として取り扱うことの可否については、法務省の担当官によれば、1つの経済事象である当該支給に対して、2つの異なる会計処理をする(費用処理及び利益処分)ことになるため、取締役及び会計監査人の対応が必要になる場合があるとされている。(注)】
(注)濱克彦「『役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い』についての商法上の考え方」 T&Amaster4月19日号18頁参照。
五 決算公告要旨
決算公告の要旨については、今般のひな型改訂にあたり、大株式会社の貸借対照表及び損益計算書の要旨と小株式会社の貸借対照表の要旨のほかに、中株式会社の貸借対照表の要旨を追加した。
株式会社の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、100万円単位で表示することも可能であり、大株式会社等については、1億円単位で表示することも可能である。ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、適切な単位をもって表示しなければならないので、留意が必要である(商法施行規則第113条第1~3項)。
六 株主総会参考書類・議決権行使書面
株主総会参考書類については、特例会社の実務や役員賞与金に関する取扱いの変更、従前ひな型に対する指摘などを踏まえた修正のほか、自己株式取得に係る議案について記載例を追加している。
議決権行使書面については、電磁的方法による議決権行使を合理的な時間(例:会社の営業時間終了時)で締め切ることを予め株主に知らせることにより、会社は株主の議決権行使期限の限定をすることができるとの見解(郡谷大輔「平成13年改正商法(11月改正)の解説[ⅩⅠ・完]」『旬刊商事法務』No.1664・37頁)に沿った変更を、従前ひな型に加えている。
七 監査報告書
監査報告書のひな型については、今般の改訂で、特例会社監査報告書及び連結計算書類に係る監査報告書を追加している。監査役会監査報告書については、監査対象の限定例示として誤解されないよう、従前ひな型の冒頭部分に記載されていた「商法施行規則第133条第1項に掲げる事項その他」を削除した以外、変更を加えていない。
1 特例会社監査報告書
特例会社監査報告書の記載事項は、監査役会監査報告書とほぼ同様の内容を求めている(記載例4参照)。監査報告書作成の基本原則については、商法施行規則第135条第2項により、監査役会監査報告書の規定が準用されている。後発事象(商法施行規則第137条)、電磁的記録による作成を規定する署名等(商法施行規則第139条)についても、準用規定が置かれている。
また、個々の記載事項に関して、商法特例法第21条の29第2項の各号において、営業報告書や附属明細書の会計に関する部分以外の部分や利益処分案等を定めているが、これらも監査役会監査報告書とほぼ同様の内容である。さらに、取締役または執行役に競業避止や利益相反取引等に関する義務違反があった場合には、商法施行規則第138条により、事項ごとに記載し、その監査の方法の概要を記載する必要があるが、これについても監査役会監査報告書とほぼ同様である。
しかし、商法特例法第21条の29第2項第4号により、商法特例法第21条の7第1項第2号に規定する「監査委員会の職務の遂行のために必要なものとして定める事項」についての取締役会決議の内容の相当性について、監査役会監査報告書と異なり、監査委員会の意見を記載することが求められている。本ひな型では、監査委員会の監査の方法の概要において、上記取締役会決議の内容の監査を行う旨を明記するとともに、監査の結果において、内容の相当に係る意見を記載することにした。
なお、特例会社の監査は、独任制を残す監査役会と異なり、組織的に行うことになっているため、監査報告書の主文において、何に基づく監査報告書なのかを明示する必要はない。
2 連結計算書類監査報告書
連結計算書類の監査報告書の記載事項については、個別計算書類との相違点に留意する必要がある。
第一に、会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当であると認めた場合についてもその旨を記載する必要がある(商法施行規則第183条第3項第1号)。
第二に、会計以外の業務監査が連結計算書類の監査に存在しないため、商法特例法第14条第3項第2号に掲げる事項は記載事項に含まれていない。
第三に、連結計算書類には営業報告書、利益処分案、附属明細書が含まれないため、それらに関連する記載事項は存在しない。
第四に、連結計算書類の監査等については、署名等を規定した商法施行規則第134条および第139条の準用規定が設けられていない。従って、法令上、署名押印は不要と考えられ、本ひな型では、連結計算書類監査報告書において、印および署名の記載を求めないこととした。
[記載例4]
監査報告書
当監査委員会は、平成××年×月×日から平成××年×月×日までの第××期営業年度における取締役及び執行役の職務の執行に関する監査の結果につき、協議した結果、次のとおり報告いたします。
Ⅰ.監査委員会の監査の方法の概要
監査委員会は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」)」第21条の7第1項第2号及び商法施行規則第193条に掲げる取締役会決議の内容を監査し、かつ監査委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、重要な会議に出席し、取締役、執行役及び使用人から職務の執行に関する事項の報告を受けまたは聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況の調査を行いました。
また、会計監査人から報告及び説明を受け、これに基づき計算書類及び附属明細書につき検証いたしました。
Ⅱ.監査の結果
1. 会計監査人○○監査法人(または公認会計士○○○○氏)の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。
2. 営業報告書の会計に関する部分以外の部分は、法令・定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
3. 監査委員会の職務遂行のために必要なものとして、商法施行規則第193条に列記されている事項について、取締役会が決議した内容は、相当であると認めます。
4. 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らし、指摘すべき事項は認められません。
5. 附属明細書の会計に関する部分以外の部分は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
6. 取締役または執行役の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
平成×年×月×日
○○○○株式会社 監査委員会
監査委員 ○○○○ 印
監査委員 ○○○○ 印
監査委員 ○○○○ 印
(自署)
(注)監査委員〇〇〇〇及び〇〇〇〇は、商法特例法第21条の8第4項ただし書き及び同法第1条の3第1項第2号に定める社外取締役であります。
[日本経団連ひな型]
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























