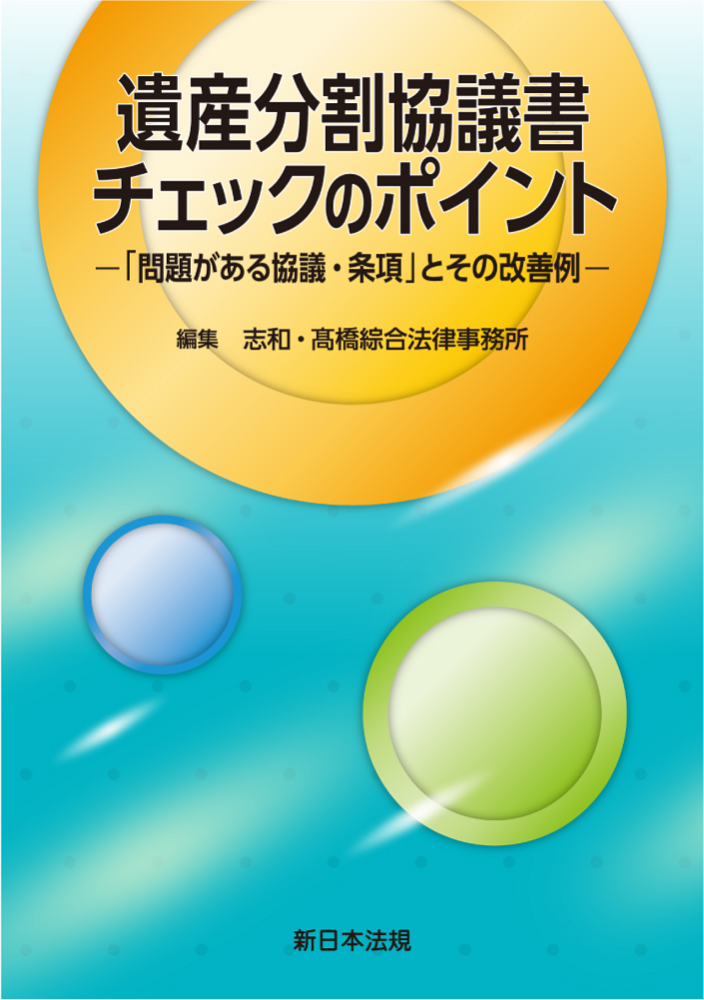解説記事2005年03月28日 【編集部レポート】 敵対的買収防衛策は会社法のここで読む!(2005年3月28日号・№108)
レポート
敵対的買収防衛策は会社法のここで読む!
会社法改正でポイズン・ピルや黄金株が可能
ライブドアによるニッポン放送の買収など、連日、企業買収に関する報道がテレビや新聞、雑誌などで行われている。今までは一部の専門家しか知らなかった「ポイズン・ピル」などといった専門用語が一般の人にまで知られることとなっている状況だ。一方、企業にとっては、ニッポン放送をめぐる争いは、対岸の火事として簡単に見過ごすわけにはいかないであろう。商法を抜本改正する会社法案が3月18日に閣議決定され、22日に国会に提出されたからだ。新しい会社法の下では、今まで以上に敵対的企業買収防衛策が容易になるが、今後、その対応に迫られることになる。本レポートでは、会社法における防衛策の概要とその根拠条文などについて解説する。
防衛策は来年の株主総会での対応が必要
会社法案では、合併対価の柔軟化が盛り込まれている。合併対価の柔軟化とは、吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合において、消滅会社等の株主等に対して、存続会社等の株式を交付せず、金銭や他社株式等を交付することを認めるもの。
注目すべきは、日本法人が合併等する場合に、外国の親会社の株式等を交付することも可能になる点だ。このため、3月9日に開催された自民党の法務部会では、外資系企業による日本企業の買収が促進されるとして、会社法案の了承が見送られる経緯があった。
最終的には、施行日について、合併対価の柔軟化に関する部分のみを他の部分よりも1年遅らせることで合意している。会社法案の施行日は、「公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から」とされており、加えて合併等の対価として、社債、新株予約権、新株予約権付社債、その他の財産(例えば、外国の親会社株式など)を交付する場合については、会社法施行の日から1年を経過する日までは適用されないことになっている。
このため、企業については、会社法施行後1年以内に防衛策に関する対応を迫られることになる。
商法上可能なのか不明確との声
経済産業省がまとめたアンケート調査によると、調査対象企業の85%が敵対的企業買収に「脅威」を感じていると回答。また、79%の企業が何らかの防衛策が必要との認識を持っている。しかし、実際に防衛策を講じていると回答した企業は38%にすぎず、その防衛策の中味については、「友好的第三者との株式持合」(35%)や「従業員持株会の活用」(31%)といったものにすぎない(図1参照)。
防衛策を講じようとしたができなかったと回答した企業は全体の35%。導入できなかった理由としては、「市場の反応に対する懸念」(33%)、「商法上可能なのか不明確」(31%)といった点が挙げられている(図2参照)。
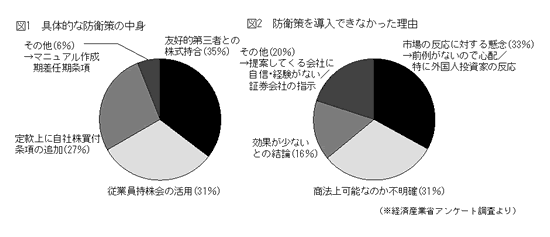
法務省は現行法でも防衛策が可能と説明
従来、企業が防衛策を導入してこなかった背景には、持合株式という日本独特の風土や商法上、防衛策が可能かどうか分からないといった点があったようだ。法務省では、2月1日に開催された自民党の商法に関する小委員会において、現行の商法でも、株主の利益を損なわない限り、種類株式や新株予約権等を用いることにより、欧米で認められる企業買収防衛策は可能であると説明している。また、特に会社法改正後については、今まで以上に防衛策の導入が可能としている。
具体的には、現行の商法でも、①ポイズン・ピル(新株予約権を利用して買収者の議決権比率を下げる方法及び全部取得条項付種類株式を利用し買収者の議決権比率を下げる方法の2種類)、②黄金株(拒否権付株式を使う方法)が可能であり、会社法改正後は、さらに使いやすくなるとしている。
新株予約権を利用したポイズン・ピルも容易に
まず、新株予約権を利用したポイズン・ピル。これは、買収が開始された場合において、買収者以外の株主の株式数が増加するように買収者以外の株主(例えば、議決権比率20%以下の株主)だけが行使することができる新株予約権を発行するというもの。これにより、買収者だけの議決権比率を下げることが可能となる。最近では、JASDAQ上場の株式会社ニレコが株主全員に新株予約権の無償発行を行うことを明らかにしている(本誌No.107参照)。
しかし、現行法での問題は、新株予約権を行使するかどうかは株主の判断に委ねられている点。株主に新株予約権を行使してもらわなければ、株式数が増加せず、議決権を下げることができないからだ。
このため、会社法では、買収者が一定割合以上の株式を買い占めた場合には、買収者の新株予約権は消滅し、かつ、買収者以外の株主には自動的に株式が発行されるような新株予約権を発行することが可能になる。
取得条項を定める
具体的に、新株予約権を利用してポイズン・ピルを作成するには、取得条項(236条1項七号)として、例えば、「株主が20%以上の株式を取得したこと」等を定めて、株主に株式数に応じて無償で割り当てることになる(277条)。その後、敵対的買収者が20%以上の株式を取得した時点で、その敵対的買収者以外の株主の新株予約権を取得し(274条)、その株主に対価として株式を交付(275条3項一号)。その結果、敵対的買収者以外の株主の株式数が増加し、敵対的買収者の議決権比率は低下することになる。
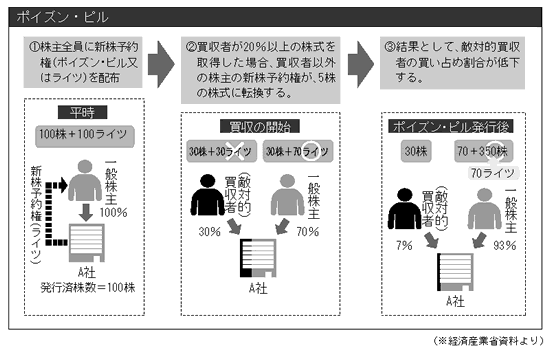
(新株予約権の内容) ※該当部分のみ掲載
第236条 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
(新株予約権無償割当て)
第277条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
(取得する新株予約権の決定等)
第274条 株式会社は、新株予約権の内容として第236条第1項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
(効力の発生等)
第275条
3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第236条第1項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第236条第1項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
全部取得条項付種類株式を利用したポイズン・ピル
全部取得条項付種類株式を利用したポイズン・ピルとは、一定割合以上の株式(例えば、20%以上の株式)を買い占めた買収者の株式を会社が強制的に取得して、議決権制限株式に転換してしまうことができるような強制転換条項付株式を発行するというもの。
しかし、現行法の問題は、既に発行された普通株式について、強制転換条項付株式に一挙に変更するための手続がないという点だ。新規上場であれば導入することが可能だが、既存の企業の場合は、株主全員の同意がない限り、実質的に導入することは不可能となっている。このため、会社法では、既に発行している普通株式を防衛策の施された強制転換条項付株式に一挙に変更するための手続を設けるとしている。
(異なる種類の株式) ※該当部分のみ掲載
第108条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なるニ以上の種類の株式を発行することができる。(略)
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なるニ以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
次に掲げる事項
イ 第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
第171条 全部取得条項付種類株式(第108条第1項第7号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
第309条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分のニ(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
三 第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
強制転換条項付株式は普通株式の対価として
具体的に、全部取得条項付種類株式(108条1項七号)によるポイズン・ピルを行う場合には、条件として、例えば、「敵対的買収者が20%以上の株式を取得しない限り、全部取得のための株主総会の決議をすることができない。」等と定める(108条2項七号ロ)。
仮に20%以上の株式を取得する敵対的買収者が現れるなどの条件が揃った場合には、株主総会を開催し(171条1項・309条2項三号)、特別決議により、すべての株式を取得した上で、その対価として20%以上の株式を保有する株主は議決権を行使することができない株式(108条1項3号・2項3号)を交付することになる。
なお、既に発行済みの普通株式に全部取得条項をつける場合には、定款変更(466条)を行うが、その手続は株主総会の特別決議及び種類株主総会の特別決議(111条2項・324条2項一号)が必要となる。
ただし、会社法上は発行済みの普通株式に全部取得条項をつけることが可能だが、普通株式が全くない株式を上場できるかどうかは、現時点では、東京証券取引所の上場規則等では明確にされていないので留意したい点だ。
第6章 定款の変更 ※該当部分のみ掲載
第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
第111条
2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第108条第1項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類がニ以上ある場合にあっては、当該ニ以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りではない。
第324条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分のニ(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第111条第2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第108条第1項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
黄金株~種類の株式の一部を譲渡制限可能
黄金株(拒否権付株式を使う方法)とは、株主総会の合併承認決議や取締役の解任決議に対して拒否権を持つ特殊な株式(黄金株)を友好的企業に対して発行するというもの。
しかし、友好的企業から他の者に譲渡されると悪用される危険性があるため、譲渡制限をかけることが必要になる。しかし、現行法では、会社が一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をすることができない点が問題となっている。このため、会社法では、会社が拒否権付株式など、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をすることが可能になる。
具体的に、黄金株については、会社法108条1項八号で規定されている。これを根拠に株主総会の決議について拒否権をもつ株式を発行することができ、黄金株についてだけを対象に譲渡制限できる旨は、108条1項四号で読むことになる。なお、黄金株の発行や譲渡制限をつけるには、定款でその旨(108条2項四号・八号)を定める必要があり、定款変更については、株主総会の特別決議(309条2項十一号)が必要となる。

会社法案を国会に提出・法務省
(異なる種類の株式) ※該当部分のみ掲載
第108条 (略)
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なるニ以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第一号に定める事項
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
(株主総会の決議)
第309条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分のニ(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
敵対的買収防衛策は会社法のここで読む!
会社法改正でポイズン・ピルや黄金株が可能
ライブドアによるニッポン放送の買収など、連日、企業買収に関する報道がテレビや新聞、雑誌などで行われている。今までは一部の専門家しか知らなかった「ポイズン・ピル」などといった専門用語が一般の人にまで知られることとなっている状況だ。一方、企業にとっては、ニッポン放送をめぐる争いは、対岸の火事として簡単に見過ごすわけにはいかないであろう。商法を抜本改正する会社法案が3月18日に閣議決定され、22日に国会に提出されたからだ。新しい会社法の下では、今まで以上に敵対的企業買収防衛策が容易になるが、今後、その対応に迫られることになる。本レポートでは、会社法における防衛策の概要とその根拠条文などについて解説する。
防衛策は来年の株主総会での対応が必要
会社法案では、合併対価の柔軟化が盛り込まれている。合併対価の柔軟化とは、吸収合併、吸収分割及び株式交換の場合において、消滅会社等の株主等に対して、存続会社等の株式を交付せず、金銭や他社株式等を交付することを認めるもの。
注目すべきは、日本法人が合併等する場合に、外国の親会社の株式等を交付することも可能になる点だ。このため、3月9日に開催された自民党の法務部会では、外資系企業による日本企業の買収が促進されるとして、会社法案の了承が見送られる経緯があった。
最終的には、施行日について、合併対価の柔軟化に関する部分のみを他の部分よりも1年遅らせることで合意している。会社法案の施行日は、「公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から」とされており、加えて合併等の対価として、社債、新株予約権、新株予約権付社債、その他の財産(例えば、外国の親会社株式など)を交付する場合については、会社法施行の日から1年を経過する日までは適用されないことになっている。
このため、企業については、会社法施行後1年以内に防衛策に関する対応を迫られることになる。
商法上可能なのか不明確との声
経済産業省がまとめたアンケート調査によると、調査対象企業の85%が敵対的企業買収に「脅威」を感じていると回答。また、79%の企業が何らかの防衛策が必要との認識を持っている。しかし、実際に防衛策を講じていると回答した企業は38%にすぎず、その防衛策の中味については、「友好的第三者との株式持合」(35%)や「従業員持株会の活用」(31%)といったものにすぎない(図1参照)。
防衛策を講じようとしたができなかったと回答した企業は全体の35%。導入できなかった理由としては、「市場の反応に対する懸念」(33%)、「商法上可能なのか不明確」(31%)といった点が挙げられている(図2参照)。
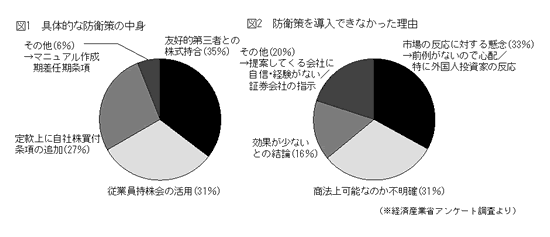
法務省は現行法でも防衛策が可能と説明
従来、企業が防衛策を導入してこなかった背景には、持合株式という日本独特の風土や商法上、防衛策が可能かどうか分からないといった点があったようだ。法務省では、2月1日に開催された自民党の商法に関する小委員会において、現行の商法でも、株主の利益を損なわない限り、種類株式や新株予約権等を用いることにより、欧米で認められる企業買収防衛策は可能であると説明している。また、特に会社法改正後については、今まで以上に防衛策の導入が可能としている。
具体的には、現行の商法でも、①ポイズン・ピル(新株予約権を利用して買収者の議決権比率を下げる方法及び全部取得条項付種類株式を利用し買収者の議決権比率を下げる方法の2種類)、②黄金株(拒否権付株式を使う方法)が可能であり、会社法改正後は、さらに使いやすくなるとしている。
新株予約権を利用したポイズン・ピルも容易に
まず、新株予約権を利用したポイズン・ピル。これは、買収が開始された場合において、買収者以外の株主の株式数が増加するように買収者以外の株主(例えば、議決権比率20%以下の株主)だけが行使することができる新株予約権を発行するというもの。これにより、買収者だけの議決権比率を下げることが可能となる。最近では、JASDAQ上場の株式会社ニレコが株主全員に新株予約権の無償発行を行うことを明らかにしている(本誌No.107参照)。
しかし、現行法での問題は、新株予約権を行使するかどうかは株主の判断に委ねられている点。株主に新株予約権を行使してもらわなければ、株式数が増加せず、議決権を下げることができないからだ。
このため、会社法では、買収者が一定割合以上の株式を買い占めた場合には、買収者の新株予約権は消滅し、かつ、買収者以外の株主には自動的に株式が発行されるような新株予約権を発行することが可能になる。
取得条項を定める
具体的に、新株予約権を利用してポイズン・ピルを作成するには、取得条項(236条1項七号)として、例えば、「株主が20%以上の株式を取得したこと」等を定めて、株主に株式数に応じて無償で割り当てることになる(277条)。その後、敵対的買収者が20%以上の株式を取得した時点で、その敵対的買収者以外の株主の新株予約権を取得し(274条)、その株主に対価として株式を交付(275条3項一号)。その結果、敵対的買収者以外の株主の株式数が増加し、敵対的買収者の議決権比率は低下することになる。
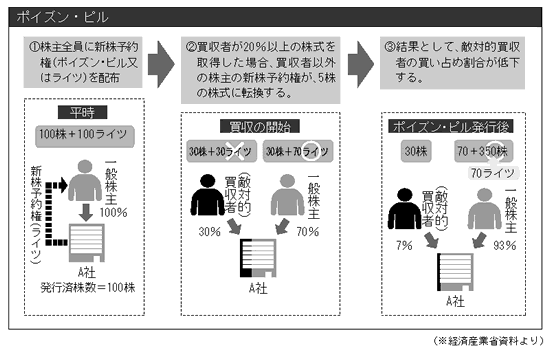
(新株予約権の内容) ※該当部分のみ掲載
第236条 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
(新株予約権無償割当て)
第277条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
(取得する新株予約権の決定等)
第274条 株式会社は、新株予約権の内容として第236条第1項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。
(効力の発生等)
第275条
3 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第236条第1項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第236条第1項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの株式の株主
全部取得条項付種類株式を利用したポイズン・ピル
全部取得条項付種類株式を利用したポイズン・ピルとは、一定割合以上の株式(例えば、20%以上の株式)を買い占めた買収者の株式を会社が強制的に取得して、議決権制限株式に転換してしまうことができるような強制転換条項付株式を発行するというもの。
しかし、現行法の問題は、既に発行された普通株式について、強制転換条項付株式に一挙に変更するための手続がないという点だ。新規上場であれば導入することが可能だが、既存の企業の場合は、株主全員の同意がない限り、実質的に導入することは不可能となっている。このため、会社法では、既に発行している普通株式を防衛策の施された強制転換条項付株式に一挙に変更するための手続を設けるとしている。
(異なる種類の株式) ※該当部分のみ掲載
第108条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なるニ以上の種類の株式を発行することができる。(略)
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なるニ以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること
次に掲げる事項
イ 第171条第1項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
第171条 全部取得条項付種類株式(第108条第1項第7号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(以下この条において「取得対価」という。)についての次に掲げる事項
イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
第309条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分のニ(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
三 第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
強制転換条項付株式は普通株式の対価として
具体的に、全部取得条項付種類株式(108条1項七号)によるポイズン・ピルを行う場合には、条件として、例えば、「敵対的買収者が20%以上の株式を取得しない限り、全部取得のための株主総会の決議をすることができない。」等と定める(108条2項七号ロ)。
仮に20%以上の株式を取得する敵対的買収者が現れるなどの条件が揃った場合には、株主総会を開催し(171条1項・309条2項三号)、特別決議により、すべての株式を取得した上で、その対価として20%以上の株式を保有する株主は議決権を行使することができない株式(108条1項3号・2項3号)を交付することになる。
なお、既に発行済みの普通株式に全部取得条項をつける場合には、定款変更(466条)を行うが、その手続は株主総会の特別決議及び種類株主総会の特別決議(111条2項・324条2項一号)が必要となる。
ただし、会社法上は発行済みの普通株式に全部取得条項をつけることが可能だが、普通株式が全くない株式を上場できるかどうかは、現時点では、東京証券取引所の上場規則等では明確にされていないので留意したい点だ。
第6章 定款の変更 ※該当部分のみ掲載
第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
第111条
2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第108条第1項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類がニ以上ある場合にあっては、当該ニ以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りではない。
第324条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分のニ(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第111条第2項の種類株主総会(ある種類の株式の内容として第108条第1項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
黄金株~種類の株式の一部を譲渡制限可能
黄金株(拒否権付株式を使う方法)とは、株主総会の合併承認決議や取締役の解任決議に対して拒否権を持つ特殊な株式(黄金株)を友好的企業に対して発行するというもの。
しかし、友好的企業から他の者に譲渡されると悪用される危険性があるため、譲渡制限をかけることが必要になる。しかし、現行法では、会社が一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をすることができない点が問題となっている。このため、会社法では、会社が拒否権付株式など、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をすることが可能になる。
具体的に、黄金株については、会社法108条1項八号で規定されている。これを根拠に株主総会の決議について拒否権をもつ株式を発行することができ、黄金株についてだけを対象に譲渡制限できる旨は、108条1項四号で読むことになる。なお、黄金株の発行や譲渡制限をつけるには、定款でその旨(108条2項四号・八号)を定める必要があり、定款変更については、株主総会の特別決議(309条2項十一号)が必要となる。

会社法案を国会に提出・法務省
(異なる種類の株式) ※該当部分のみ掲載
第108条 (略)
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なるニ以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第一号に定める事項
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
(株主総会の決議)
第309条
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分のニ(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
十一 第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.