解説記事2005年07月04日 【ニュース特集】 個人所得課税に関する論点整理を徹底分析(2005年7月4日号・№121)
ニュース特集
これが4~5年後の個人所得課税?!
個人所得課税に関する論点整理を徹底分析
政府税制調査会(石 弘光会長)は、6月21日、「個人所得課税に関する論点整理」(以下「論点整理」)を公表した。論点整理は、国・地方の財政の危機的状況を受けて、結果的に「増税項目の羅列」との見方ができる反面、政府税調は、現行個人所得課税の構造的なひずみ、ゆがみを是正するという視点で、個人所得課税の改革にあたってきた(論点整理の本文は24頁参照)。
「消費税増税」との関係で実施時期を明示していないものが多いが、論点整理に見られる現行税制の「ゆがみ」の指摘は、正鵠を射たものであり、石会長のいう4~5年後はともかく、今後の個人所得課税の改革の方向性を示したものといえるだろう。
平成18年度税制改正の課題
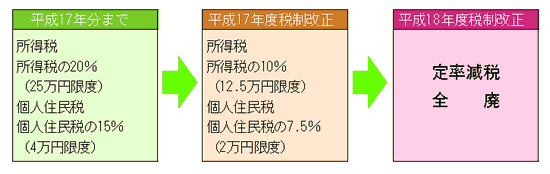
論点整理は、目指すべき個人所得課税の改革のグランドデザインを描くものであるが、その前提として、「平成18年度においては、定率減税を廃止するとともに、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行う必要がある。」としている。
石政府税調会長は、「平成17年度の税制改正に関する答申」において、「税源移譲と定率減税につきまして、はっきりした姿勢を出した。」と会見しており、論点整理は、いずれも既定の路線の堅持を求めている。
定率減税の廃止
平成17年度税制改正において、所得税・個人住民税の定率減税の1/2が縮減されているが、論点整理は、「平成18年度において、定率減税の廃止が必要である。」としている(上図参照)。
個人所得課税の抜本的見直しを行う上で、付加的な異質なもの(定率減税)を取り払ったところでの、個人所得課税のあるべき姿を論議する姿勢を示している。
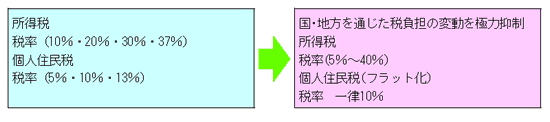
所得税から個人住民税への本格的な税源移譲
論点整理は、「平成18年度において、所得税から個人住民税への税率構造を中心とした抜本的な見直しが必要である。」としている。
税源移譲については、①国・地方を通じた税負担の変動を極力抑制、②個人住民税の所得割の税率をフラット化する方向が明らかにされている。また、個人住民税の税率を一律10%とする案を土台に検討されている(前頁下図参照)。
将来的に国・地方ともに税率の引上げが不可避との認識(石政府税調会長)もあり、ブラケットの見直し・課税ベースの拡大も併せて検討される。
所得区分毎の問題点
現行税制は、所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類している。論点整理は、「経済社会の構造変化により、これらの所得区分のあり方が税負担のバランスを損なっている面も生じてきている。制度の簡素化の要請も踏まえ、これらの見直しを行っていく必要がある。」としている。
所得控除・税額控除等の問題点
論点整理は、わが国の個人所得課税においては、課税単位を「個人」としていることを指摘した上で、「人的控除について、制度が相当複雑化しており、対象となる政策課題の根本まで遡った見直しを行うことが必要である。」としている。
世帯構成と税負担のあり方について、特に夫婦や子育てについて税制面でどのような配慮を行うかとの観点から、当面する課題を検討している。
個人住民税
論点整理は、「所得税から個人住民税への本格的な税源移譲においても、税率のフラット化が基本となっており、個人住民税の応益性などがより明確になる。引き続き応益性を明確にしつつ、地方税において中核的役割を果たすものとして充実確保を図る必要がある。」としている。
納税環境の整備
論点整理は、「税負担の歪みを是正し、公平に負担を分かち合う『あるべき税制』の構築にあたっては、個人所得課税の納税を支える諸制度について、経済社会の変化に対応しつつ、適正な執行により役立つものとなるよう見直しを行っていく必要がある。こうした観点から、以下のような課題に取り組んでいくべきである。」としている。
結びにかえて
論点整理の「結びにかえて」では、「このような改革は、今後、他税目の見直しとも適切に連携しつつ、また経済情勢も見極めながら、段階的かつ着実に実施していくべきである。」としている。残されたテーマである「消費税の増税」と個人所得課税の改革がどのようにリンクし、優先順位がつけられて実行されることになるのかが、重要なポイントであるといえるだろう。
また、論点整理は、「納税者の理解と支持なくしてはこの改革は実現し得ない。特に、国民に負担増を求めることとなる場合には、国・地方を通じた徹底した行財政改革が必要である。」としている。 現在の国・地方の財政状況が、国民の負担増の前提として、行財政改革の進展を待っている余裕があるのかどうかは、不明だが、論点整理は、「民主国家」・「租税国家」である以上、相応の負担増が免れない現実から目を反らしてはならないこと・積極的な議論を求めている。
これが4~5年後の個人所得課税?!
個人所得課税に関する論点整理を徹底分析
政府税制調査会(石 弘光会長)は、6月21日、「個人所得課税に関する論点整理」(以下「論点整理」)を公表した。論点整理は、国・地方の財政の危機的状況を受けて、結果的に「増税項目の羅列」との見方ができる反面、政府税調は、現行個人所得課税の構造的なひずみ、ゆがみを是正するという視点で、個人所得課税の改革にあたってきた(論点整理の本文は24頁参照)。
「消費税増税」との関係で実施時期を明示していないものが多いが、論点整理に見られる現行税制の「ゆがみ」の指摘は、正鵠を射たものであり、石会長のいう4~5年後はともかく、今後の個人所得課税の改革の方向性を示したものといえるだろう。
平成18年度税制改正の課題
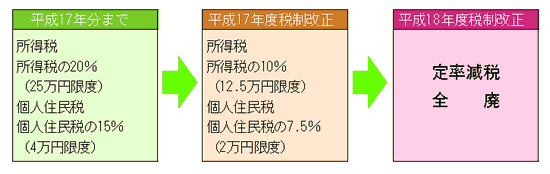
論点整理は、目指すべき個人所得課税の改革のグランドデザインを描くものであるが、その前提として、「平成18年度においては、定率減税を廃止するとともに、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行う必要がある。」としている。
石政府税調会長は、「平成17年度の税制改正に関する答申」において、「税源移譲と定率減税につきまして、はっきりした姿勢を出した。」と会見しており、論点整理は、いずれも既定の路線の堅持を求めている。
定率減税の廃止
平成17年度税制改正において、所得税・個人住民税の定率減税の1/2が縮減されているが、論点整理は、「平成18年度において、定率減税の廃止が必要である。」としている(上図参照)。
個人所得課税の抜本的見直しを行う上で、付加的な異質なもの(定率減税)を取り払ったところでの、個人所得課税のあるべき姿を論議する姿勢を示している。
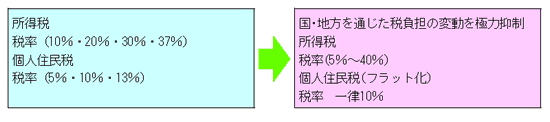
所得税から個人住民税への本格的な税源移譲
論点整理は、「平成18年度において、所得税から個人住民税への税率構造を中心とした抜本的な見直しが必要である。」としている。
税源移譲については、①国・地方を通じた税負担の変動を極力抑制、②個人住民税の所得割の税率をフラット化する方向が明らかにされている。また、個人住民税の税率を一律10%とする案を土台に検討されている(前頁下図参照)。
将来的に国・地方ともに税率の引上げが不可避との認識(石政府税調会長)もあり、ブラケットの見直し・課税ベースの拡大も併せて検討される。
所得区分毎の問題点
現行税制は、所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類している。論点整理は、「経済社会の構造変化により、これらの所得区分のあり方が税負担のバランスを損なっている面も生じてきている。制度の簡素化の要請も踏まえ、これらの見直しを行っていく必要がある。」としている。
所得の区分 | 論点整理における記述 | 効果 |
| 利子所得 | 利子、配当、株式等譲渡益など様々な法定の所得区分に属する金融資産の運用から生じる所得については、金融所得として一体化し、課税する仕組みを検討中。 金融所得課税の一体化を着実に進めていくべき。 | 損益通算の範囲拡大には減税効果も期待できる。 |
| 配当所得 | ||
| 不動産所得 | 独立の所得区分としての不動産所得を廃止。 事業所得と雑所得に区分。 | 雑所得に区分されると他の所得との損益通算・専従者給与適用なし⇒増税 |
事業所得
| 売上げ、必要経費の記帳に基づく申告納税の趣旨の重要性を再認識する必要。 | 税負担の不公平感(クロヨン)を除去する⇒実質的な増税?
|
| 給与所得 | 給与所得も事業所得も、勤労を通じた経常的所得である点では差異はない。 給与所得者であることを理由として、所得の計算にあたって特別の斟酌を行う必要性は乏しくなっている。 給与所得控除の見直しが課題。 職務遂行上の経費として認められる特定支出控除の対象範囲の拡大について検討。 フリンジベネフィットに適正な課税を行っていく必要。 。 | 給与所得控除の引下げ⇒増税 特定支出控除の拡大⇒減税だが効果不明 |
| 退職所得 | 全体として多様な就労選択に対し中立的な制度となるよう課税のあり方を見直すべき。 何らかの平準化措置・所要の経過措置も含めた適切な工夫が必要 | 退職所得課税の見直し⇒増税の方向で見直し |
| 譲渡所得 | 損益通算による租税回避に用いられ易い。 長期譲渡の1/2課税は、譲渡損の取扱いと不均衡。 土地・株式以外の資産の譲渡益についても分離課税に。 | 長期譲渡所得課税の見直しは増税の方向 ゴルフ会員権の分離課税(他の所得との損益通算廃止)は実質的な増税効果 |
| 一時所得 | 対価性の有無をもって雑所得と区分することに合理性はない。 | 1/2課税の見直し(廃止)は増税 |
| 雑所得 | 公的年金等については独立の所得区分を設けるべき。 資産運用関連の雑所得は、分離課税に一本化すべき。 | 公的年金控除のあり方見直しは増税の方向 |
所得控除・税額控除等の問題点
論点整理は、わが国の個人所得課税においては、課税単位を「個人」としていることを指摘した上で、「人的控除について、制度が相当複雑化しており、対象となる政策課題の根本まで遡った見直しを行うことが必要である。」としている。
世帯構成と税負担のあり方について、特に夫婦や子育てについて税制面でどのような配慮を行うかとの観点から、当面する課題を検討している。
検討項目 | 論点整理における記述 | 効果 |
| 配偶者との関係 | 配偶者に関する現行の人的控除のあり方については、根本的な見直しが必要。 課税単位の問題(2分2乗方式の採用など)については、夫婦のあり方、財産制度、配偶者の就労に対する中立性確保の要請といった観点を踏まえ、引き続き検討。 | 配偶者控除の廃止(縮減)は課税ベースの拡大(増税) 課税単位の見直しは、専業主婦のいる高所得世帯が有利 |
| 子育て支援 | 税制での支援(所得控除・税額控除など)について、少子化対策全体の議論の中で、他の政策手段との関係、諸外国の事例も踏まえ、引き続き検討。 扶養控除のあり方として、対象者に年齢制限を導入。 子育てと課税単位の問題(N分N乗方式)について引き続き検討。 特定扶養控除の存立趣旨は失われつつある。 | 非課税世帯には税制支援は効果なし。 一般的に税額控除は低所得者に有利で減税効果が認められる。特定扶養控除の廃止は増税 |
| 実効税率 | わが国の実効税率は諸外国と比べて極めて低い状況にあり、個人所得課税の本来機能の回復の観点からは、課税ベースや税率構造の見直しにより、その水準を引き上げる。 | 増税の方向での検討 |
| 課税ベース(各種控除) | 課税ベースの拡大が今後の課題となる。 広く公平に負担を分かち合うとの観点から、課税ベース縮小の原因となる非課税所得、各種控除のあり方を議論することが重要。 | 増税の方向での検討 |
| 税率構造 | 平成18年度において、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲(税率構造の抜本的見直しを伴う)。 税源移譲のために10%よりも低い税率区分を設ける必要。 最高税率の現行水準(50%)は基本的に妥当。 実効税率の水準引き上げのために、現在の最低税率のブラケットの幅を狭めていくことが必要。 | 国・地方を通じた税負担の変動を極力抑制する方向で検討中 |
個人住民税
論点整理は、「所得税から個人住民税への本格的な税源移譲においても、税率のフラット化が基本となっており、個人住民税の応益性などがより明確になる。引き続き応益性を明確にしつつ、地方税において中核的役割を果たすものとして充実確保を図る必要がある。」としている。
検討項目 | 論点整理における記述 | 効果 |
| 所得割 | 税率のフラット化が基本。 人的控除をはじめ各種の所得控除について、所得税とは独立して、整理合理化を図ることが望ましい。 生命保険料控除、損害保険料控除など政策誘導的な色彩の強い控除については、速やかに整理すべき。 | 国・地方を通じた税負担の変動を極力抑制する方向で検討中 その他は増税 |
| 均等割 | 税率の引上げを図る必要。 基礎自治体である市町村を重視すべき。 | 増税 |
税務執行面 | 現年課税の可能性について検討すべき。 | 納付への理解が得られ易い |
納税環境の整備
論点整理は、「税負担の歪みを是正し、公平に負担を分かち合う『あるべき税制』の構築にあたっては、個人所得課税の納税を支える諸制度について、経済社会の変化に対応しつつ、適正な執行により役立つものとなるよう見直しを行っていく必要がある。こうした観点から、以下のような課題に取り組んでいくべきである。」としている。
検討項目 | 論点整理における記述 | 効果 |
| 納税者番号制度 | 金融所得課税一体化の一環として損益通算の範囲を拡大するにあたっては、損益通算を希望する者の選択による金融番号の導入は不可欠。 納税者番号制度の導入には、官民を通じたコスト・ベネフィットの観点にも十分留意。 早急の導入には、「住民基本台帳方式」を採ることが現実的。 | 当面は金融所得課税一体化の一環。 制度の活用によっては、実質的な増税効果も期待? |
| 記録及び記帳に基づく申告制度 | 記帳義務について、申告納税制度の本旨に則した見直しを行うべき。 事業所得について必要経費に係る「概算控除制度」を導入 | 実質増税? |
| 立証責任 | 納税者が自ら説明責任を果たすことが相応しいと思われる項目について、個別に制度的枠組みを。 税務当局が十分な資料を収集できるような環境整備。 | 納税者の事務負担増? |
源泉徴収・年末調整
| 給与所得者が自ら確定申告を行う機会を拡大していくことが望ましい。 | 社会共通の費用を分かち合う意識向上に効果を期待 |
| 公示制度 | 廃止を検討すべき。 | |
| 罰則 | 脱税への動機付けを減少させ、適正な納税を促す観点から、罰則の強化を検討すべき。 |
結びにかえて
論点整理の「結びにかえて」では、「このような改革は、今後、他税目の見直しとも適切に連携しつつ、また経済情勢も見極めながら、段階的かつ着実に実施していくべきである。」としている。残されたテーマである「消費税の増税」と個人所得課税の改革がどのようにリンクし、優先順位がつけられて実行されることになるのかが、重要なポイントであるといえるだろう。
また、論点整理は、「納税者の理解と支持なくしてはこの改革は実現し得ない。特に、国民に負担増を求めることとなる場合には、国・地方を通じた徹底した行財政改革が必要である。」としている。 現在の国・地方の財政状況が、国民の負担増の前提として、行財政改革の進展を待っている余裕があるのかどうかは、不明だが、論点整理は、「民主国家」・「租税国家」である以上、相応の負担増が免れない現実から目を反らしてはならないこと・積極的な議論を求めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















