解説記事2005年10月24日 【ニュース特集】 小室裕一自治税務局長に聞く(2005年10月24日号・№135)
ニュース特集
自治体の行財政改革の推進が大きな課題に
小室裕一自治税務局長に聞く

総務省自治税務局の小室裕一局長は、このほど会見に応じ、官の構造改革の必要性を述べるとともに、その一環が地方分権であると強調。三位一体改革による税源移譲が行われることで、地方税の役割が高まることに言及するとともに、自治体は国民・納税者から情報公開を求められるだろう、との認識を示した。一方で小室局長は、昨年4月から導入された外形標準課税について、昨今の経済状況を反映して円滑な導入が図られたと述べた。来年度に予定されている固定資産税の評価替えについては、非木造家屋の基準表の簡素化に触れるなど、評価の適正化・均衡化を図っていく姿勢を明らかにした。
1 経済状況にも支えられ外形標準課税は円滑に導入
――就任の抱負を。
小泉内閣による構造改革が軌道に乗り、その成果として経済情勢が好転してきた。次は官の構造改革だ。その一つの柱が地方分権と言える。特に税財政の話では、地方が国に頼っていた補助金・負担金から地方税へ切り替えていくのが根本になり、地方税の占める責任が増すことであるし、精いっぱい取り組んでまいりたい。
――外形標準課税が平成16年4月から導入されて1年半が経過したが、現在の執行状況は。
平成16年4月1日以後に開始される事業年度から執行され、最も大きなウエートを占める3月決算法人の場合、3月の決算後、実際の申告は5月以降であり、監査を受ける大法人は6月、連結の場合は7月であったりすることから、7月の時点で初めて全体像が見えてきたと思う。
制度の導入に際しては、さまざまな議論があったが、導入段階における経済状況の好転もあり、円滑な導入が図られたと判断している。この背景には、法案通過後から都道府県の税務行政として、電算システムをはじめ、課税法人に対する丁寧な説明会などを行っていただいた結果であると考えている。引き続き、課税団体の都道府県と協力を図りながら、円滑な運営を行っていきたい。
COLUMN 外形標準課税とは
平成16年度4月1日以後開始する事業年度から、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人を対象に都道府県税である法人事業税に外形標準課税が導入された。全普通法人247万社のうち3万3千社が対象となる。資本金1億円以下の法人や公益法人・特別法人・人格なき社団・投資法人などは対象外。
外形標準課税は、新たな課税標準として付加価値割と資本割が導入されたため、従来は課税されなかった赤字法人に対しても課税されることから、一定の要件を満たす場合、徴収猶予が認められる措置が講じられている。
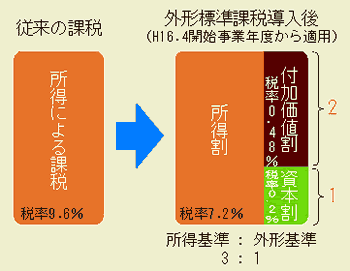
2 均衡かつ適正な評価を推進
――来年度は固定資産税の評価替えの年だが。
固定資産税は地方税独自の分野であり、非常に重要であると認識している。固定資産税は市町村税収の中でも約半分という大きなウエートを占めており、固定資産税の安定的な確保がなければ、市町村の税収や行政サービスの原資に不安が出てくる。インフラ整備をはじめ福祉・ごみ収集・教育などを円滑に機能させるためにも、固定資産税を確保してまいりたい。18年度は3年ごとの評価替えの時期であり、適正かつ均衡の取れた評価を推進していかなければならない。
具体的には土地の話がある。宅地については、地価公示価格を活用しながら、7割を目途に評価をしている。評価の均衡化・適正化を推進していくことが公平な税制のためにも必要であり、納税者からも納得を得られるように、出来る限り簡素で分かりやすい評価方法にする必要がある。
18年の評価替えにおいては非木造家屋について基準表を変更し、これまでも同様に、合理化・簡素化を図っていきたい。
土地の負担調整については、15年度改正時も商業地の固定資産税について要望があったのだが、当時は財政状況が厳しく減収につながるため、下げるという話は難しかった。そういったこともあり、16年度改正で条例減額制度を適用した。栃木県宇都宮市などが固定資産税の課税標準額の割合の引き下げを行ったのをはじめ、東京都23区については負担水準を70%から65%に引き下げるなど、条例減額制度についても十分に機能していると思っている。
18年度においては、さまざまな議論があると思う。東京・大阪・名古屋などの一部で地価が上がったものの、全国平均では依然としてマイナス傾向となっている。固定資産税については、平成6年度に7割評価が導入されているが、負担調整措置が手当てされているため、全国ベースで見ると、地価が下落している地域で税収が上がるというところもでてくると思われる。
家屋についても建築物価など、再建築価格方式なので、自然体でも減収が相当数でてくると思われることから、それを前提として対応していきたい。土地の仕組みの中で、前年度の課税標準額を基に負担調整をしていくなど、複雑なところがあるため、将来的には分かりやすく、より均衡化・簡素化に向けて工夫していくことが、これからの課題といえるだろう。
商業地等に係る負担調整措置と条例減額精度の仕組み
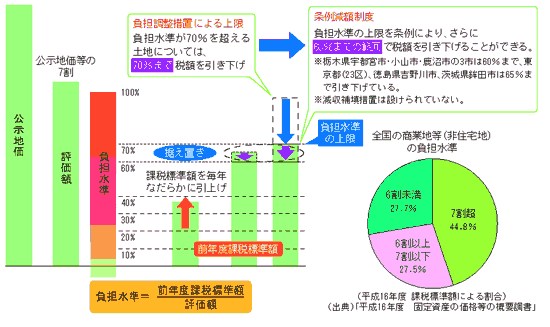
3 市町村合併が行財政改革の柱に
――三位一体改革により、所得税から住民税への税源移譲が行われる。地方税の占める役割が重要となるが。
国からの補助金を削り地方税に移すことで、受益と負担の関係が明確になる。これにより、国・地方を通じてトータルに歳出を効率的・効果的にできる。三位一体改革により、地方には3兆円、補助金ベースで4兆円規模の税源移譲がされ、国そのものもスリム化が図られることになる。
一方、地方税・住民税にとっては増収になるという意味で、住民税への負担が移るということから、納税者である国民・住民からタックスペイヤーとして自治体に対するチェックが入ることは歓迎すべきことではないか。身近で納税者がチェックすることで、行政としては、分かりやすい形での情報開示を求められるようになるだろう。また、自治体に対しては、いっそうの行財政改革が求められることになる。
自治体の行財政改革については、今後の大きな柱が市町村合併である。平成11年3月末現在で3232市町村であったが、18年3月31日の時点において1821市町村に推移していく。市町村数は6割くらいになるが、日本全国のほとんどの自治体において「平成の大合併」に携わったことになる。
この大合併によって、行政においては、サービス水準などについて議論、総点検されるようになる。行財政改革についても17年度から21年度までの5年間に集中的に改革を行っていくということで、「集中改革プラン」を今年度中に作成していくことになっている。地方税・税務行政に対する信頼を高めるためにも、こうした議論は重要であると認識している。
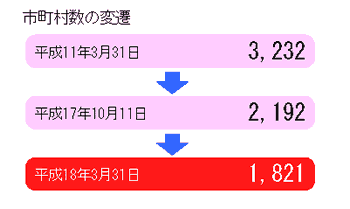
4 現年課税は今後の検討課題に
――現年課税の議論についてどう見ているか。
所得税と住民税の違いなどは周知の通りだが、特別徴収義務者に計算してもらい、年末調整までしてもらうというのは、事務負担が大きい。所得税と違う仕組みもあるとは思うが、所得の発生時点と税負担時点をできるだけ近づけるというのは望ましい考えだ。
現年課税については、自治省のころから「できませんよ」という言い方をしていたが、年功序列で所得が上がっていくような時代ではなく、雇用形態も多様化している時代背景から、頭から拒否する時代ではなくなり、検討をする時期にきたのではないかと思っている。
IT化を活用し、年末調整の仕組みを導入しても、大きな事務負担にならない方法があるのではないか、という指摘もあることから、給与支払い者や納税者の事務負担に留意しながら現年課税の可能性について検討していこうと考えている。ただし、現在、税源移譲の問題や多くの自治体が抱えている合併などの話もあり、いますぐに出来るという話ではなく、まずは税源移譲を行っていくということを優先し、そのあと、現年課税についてのさまざまな課題を検討していきたい。
一方、地方税電子化協議会では今年から法人事業税と法人住民税の電子申告を行っている。電子納税にもつながっていく話であり、公的個人認証など体制整備をしっかりと行ってまいりたい。

プロフィール
小室裕一(こむろ・ゆういち)
昭和25年東京都生まれ。群馬県財政課長、大阪市経済局中小企業部参事(ジェトロデュッセルドルフ事務所)、自治省官房広報室長、同行政局公務員部福利課長、同行政局振興課長、同税務局企画課長、総務省自治税務局企画課長、同大臣官房審議官(税務担当)、同自治大学校長などを歴任。17年8月から現職。
自治体の行財政改革の推進が大きな課題に
小室裕一自治税務局長に聞く

総務省自治税務局の小室裕一局長は、このほど会見に応じ、官の構造改革の必要性を述べるとともに、その一環が地方分権であると強調。三位一体改革による税源移譲が行われることで、地方税の役割が高まることに言及するとともに、自治体は国民・納税者から情報公開を求められるだろう、との認識を示した。一方で小室局長は、昨年4月から導入された外形標準課税について、昨今の経済状況を反映して円滑な導入が図られたと述べた。来年度に予定されている固定資産税の評価替えについては、非木造家屋の基準表の簡素化に触れるなど、評価の適正化・均衡化を図っていく姿勢を明らかにした。
1 経済状況にも支えられ外形標準課税は円滑に導入
――就任の抱負を。
小泉内閣による構造改革が軌道に乗り、その成果として経済情勢が好転してきた。次は官の構造改革だ。その一つの柱が地方分権と言える。特に税財政の話では、地方が国に頼っていた補助金・負担金から地方税へ切り替えていくのが根本になり、地方税の占める責任が増すことであるし、精いっぱい取り組んでまいりたい。
――外形標準課税が平成16年4月から導入されて1年半が経過したが、現在の執行状況は。
平成16年4月1日以後に開始される事業年度から執行され、最も大きなウエートを占める3月決算法人の場合、3月の決算後、実際の申告は5月以降であり、監査を受ける大法人は6月、連結の場合は7月であったりすることから、7月の時点で初めて全体像が見えてきたと思う。
制度の導入に際しては、さまざまな議論があったが、導入段階における経済状況の好転もあり、円滑な導入が図られたと判断している。この背景には、法案通過後から都道府県の税務行政として、電算システムをはじめ、課税法人に対する丁寧な説明会などを行っていただいた結果であると考えている。引き続き、課税団体の都道府県と協力を図りながら、円滑な運営を行っていきたい。
COLUMN 外形標準課税とは
平成16年度4月1日以後開始する事業年度から、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人を対象に都道府県税である法人事業税に外形標準課税が導入された。全普通法人247万社のうち3万3千社が対象となる。資本金1億円以下の法人や公益法人・特別法人・人格なき社団・投資法人などは対象外。
外形標準課税は、新たな課税標準として付加価値割と資本割が導入されたため、従来は課税されなかった赤字法人に対しても課税されることから、一定の要件を満たす場合、徴収猶予が認められる措置が講じられている。
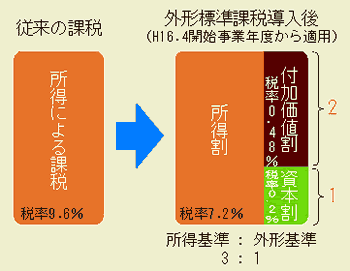
2 均衡かつ適正な評価を推進
――来年度は固定資産税の評価替えの年だが。
固定資産税は地方税独自の分野であり、非常に重要であると認識している。固定資産税は市町村税収の中でも約半分という大きなウエートを占めており、固定資産税の安定的な確保がなければ、市町村の税収や行政サービスの原資に不安が出てくる。インフラ整備をはじめ福祉・ごみ収集・教育などを円滑に機能させるためにも、固定資産税を確保してまいりたい。18年度は3年ごとの評価替えの時期であり、適正かつ均衡の取れた評価を推進していかなければならない。
具体的には土地の話がある。宅地については、地価公示価格を活用しながら、7割を目途に評価をしている。評価の均衡化・適正化を推進していくことが公平な税制のためにも必要であり、納税者からも納得を得られるように、出来る限り簡素で分かりやすい評価方法にする必要がある。
18年の評価替えにおいては非木造家屋について基準表を変更し、これまでも同様に、合理化・簡素化を図っていきたい。
土地の負担調整については、15年度改正時も商業地の固定資産税について要望があったのだが、当時は財政状況が厳しく減収につながるため、下げるという話は難しかった。そういったこともあり、16年度改正で条例減額制度を適用した。栃木県宇都宮市などが固定資産税の課税標準額の割合の引き下げを行ったのをはじめ、東京都23区については負担水準を70%から65%に引き下げるなど、条例減額制度についても十分に機能していると思っている。
18年度においては、さまざまな議論があると思う。東京・大阪・名古屋などの一部で地価が上がったものの、全国平均では依然としてマイナス傾向となっている。固定資産税については、平成6年度に7割評価が導入されているが、負担調整措置が手当てされているため、全国ベースで見ると、地価が下落している地域で税収が上がるというところもでてくると思われる。
家屋についても建築物価など、再建築価格方式なので、自然体でも減収が相当数でてくると思われることから、それを前提として対応していきたい。土地の仕組みの中で、前年度の課税標準額を基に負担調整をしていくなど、複雑なところがあるため、将来的には分かりやすく、より均衡化・簡素化に向けて工夫していくことが、これからの課題といえるだろう。
商業地等に係る負担調整措置と条例減額精度の仕組み
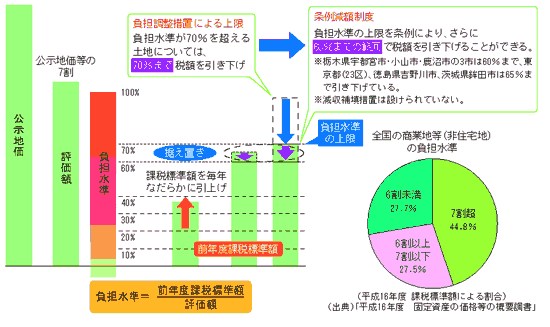
3 市町村合併が行財政改革の柱に
――三位一体改革により、所得税から住民税への税源移譲が行われる。地方税の占める役割が重要となるが。
国からの補助金を削り地方税に移すことで、受益と負担の関係が明確になる。これにより、国・地方を通じてトータルに歳出を効率的・効果的にできる。三位一体改革により、地方には3兆円、補助金ベースで4兆円規模の税源移譲がされ、国そのものもスリム化が図られることになる。
一方、地方税・住民税にとっては増収になるという意味で、住民税への負担が移るということから、納税者である国民・住民からタックスペイヤーとして自治体に対するチェックが入ることは歓迎すべきことではないか。身近で納税者がチェックすることで、行政としては、分かりやすい形での情報開示を求められるようになるだろう。また、自治体に対しては、いっそうの行財政改革が求められることになる。
自治体の行財政改革については、今後の大きな柱が市町村合併である。平成11年3月末現在で3232市町村であったが、18年3月31日の時点において1821市町村に推移していく。市町村数は6割くらいになるが、日本全国のほとんどの自治体において「平成の大合併」に携わったことになる。
この大合併によって、行政においては、サービス水準などについて議論、総点検されるようになる。行財政改革についても17年度から21年度までの5年間に集中的に改革を行っていくということで、「集中改革プラン」を今年度中に作成していくことになっている。地方税・税務行政に対する信頼を高めるためにも、こうした議論は重要であると認識している。
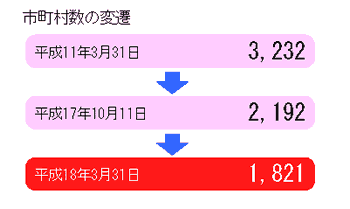
4 現年課税は今後の検討課題に
――現年課税の議論についてどう見ているか。
所得税と住民税の違いなどは周知の通りだが、特別徴収義務者に計算してもらい、年末調整までしてもらうというのは、事務負担が大きい。所得税と違う仕組みもあるとは思うが、所得の発生時点と税負担時点をできるだけ近づけるというのは望ましい考えだ。
現年課税については、自治省のころから「できませんよ」という言い方をしていたが、年功序列で所得が上がっていくような時代ではなく、雇用形態も多様化している時代背景から、頭から拒否する時代ではなくなり、検討をする時期にきたのではないかと思っている。
IT化を活用し、年末調整の仕組みを導入しても、大きな事務負担にならない方法があるのではないか、という指摘もあることから、給与支払い者や納税者の事務負担に留意しながら現年課税の可能性について検討していこうと考えている。ただし、現在、税源移譲の問題や多くの自治体が抱えている合併などの話もあり、いますぐに出来るという話ではなく、まずは税源移譲を行っていくということを優先し、そのあと、現年課税についてのさまざまな課題を検討していきたい。
一方、地方税電子化協議会では今年から法人事業税と法人住民税の電子申告を行っている。電子納税にもつながっていく話であり、公的個人認証など体制整備をしっかりと行ってまいりたい。

プロフィール
小室裕一(こむろ・ゆういち)
昭和25年東京都生まれ。群馬県財政課長、大阪市経済局中小企業部参事(ジェトロデュッセルドルフ事務所)、自治省官房広報室長、同行政局公務員部福利課長、同行政局振興課長、同税務局企画課長、総務省自治税務局企画課長、同大臣官房審議官(税務担当)、同自治大学校長などを歴任。17年8月から現職。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























