コラム2005年12月12日 【SCOPE】 過少資本税制の利子の範囲や非永住者制度を見直しへ(2005年12月12日号・№142)
18年度税制改正における国際課税の見直しの方向
過少資本税制の利子の範囲や非永住者制度を見直しへ
現在、自民党税制調査会では、平成18年度税制改正大綱のとりまとめに向けた議論が行われているが、このうち、国際課税制度の見直しの方向が明らかになった。非永住者制度の見直しや過少資本税制の見直しなどが検討される模様だ。
過去10年間のうち国内にいた期間が5年以下
国際課税制度については、まずは、非永住者制度の見直しがあげられる。同制度は、居住外国人のうち、国外に生活拠点があり、一定の滞在期間後に出国する者については、わが国の課税範囲を制限する制度。具体的に、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人とされており、課税所得の範囲は国内源泉所得、国外源泉所得(国内払い、国内送金分に限る)に限定されている。しかし、中には、非永住者制度の適用を受けるために、いったん帰国し、その後、再来日するといった事例などが見受けられている。このため、①日本国籍を有する者には制度の適用を認めない、②過去10年間のうち国内にいた期間が5年以下である間のみ、制度の適用を認めるなどの見直しを行う方向だ。
過少資本税制の対象となる利子の範囲に保証料など
過少資本税制の対象となる利子等の範囲も見直す方針だ。過少資本税制とは、資本に係る配当と負債に係る利子との課税上の相違点を利用した租税回避を規制するための税制のこと。出資により資金調達の場合には、配当を受けても損金に算入できないため、課税所得を減少させることはできないが、借入れによる資金調達の場合における利子については、損金算入できるため、課税所得を減少させることができるからだ。このため、海外の関連企業との間において、出資に代えて貸付けを多くすることによって税負担の軽減を防止するために、一定割合を超える支払利子の損金算入を認めないこととしている(右上図参照)。
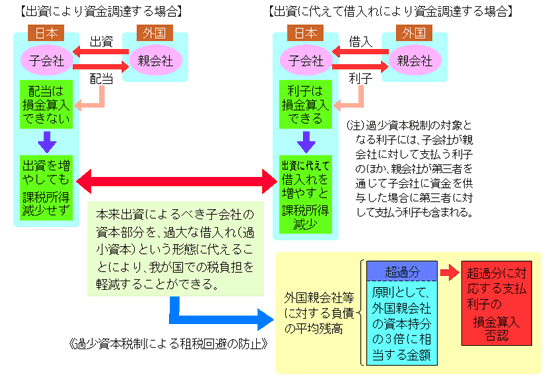
しかし、本来過少資本税制の対象となるべき利子について、名目上は保証料や使用料に組み換える取引を組成し、過少資本税制の適用を免れている事例が散見されているとしている。このため、改正の方向としては、過少資本税制の適用を免れている一定の取引について、その取引の利子と保証料、利子と使用料を一体として捉え、過少資本税制の対象に加えるとしている。
移転価格税制における推定課税の方法を追加
移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じる所得の海外移転を防止するため、その移転価格を通常の取引価格(独立企業間価格)に引き直して課税する制度。現在、独立企業間価格の算定方法については、下記の5つの方法が認められているが、納税者が独立企業間価格の算定に必要な帳簿書類を提出しない場合には、税務署長は、一定の方法により算定した金額を独立企業間価格として推定して、課税を行うことができるとされている。しかし、昨今の取引形態の多様化に伴い、現在認められている推定課税における算定方法だけでは、独立企業間価格を算定することが困難な状況があるとしている。このため、推定課税において用いることができる算定方法に、取引単位営業利益法及び利益分割法に対応する方法を追加する方向だ。
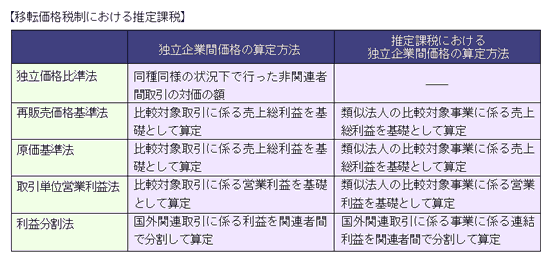
過少資本税制の利子の範囲や非永住者制度を見直しへ
現在、自民党税制調査会では、平成18年度税制改正大綱のとりまとめに向けた議論が行われているが、このうち、国際課税制度の見直しの方向が明らかになった。非永住者制度の見直しや過少資本税制の見直しなどが検討される模様だ。
過去10年間のうち国内にいた期間が5年以下
国際課税制度については、まずは、非永住者制度の見直しがあげられる。同制度は、居住外国人のうち、国外に生活拠点があり、一定の滞在期間後に出国する者については、わが国の課税範囲を制限する制度。具体的に、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人とされており、課税所得の範囲は国内源泉所得、国外源泉所得(国内払い、国内送金分に限る)に限定されている。しかし、中には、非永住者制度の適用を受けるために、いったん帰国し、その後、再来日するといった事例などが見受けられている。このため、①日本国籍を有する者には制度の適用を認めない、②過去10年間のうち国内にいた期間が5年以下である間のみ、制度の適用を認めるなどの見直しを行う方向だ。
過少資本税制の対象となる利子の範囲に保証料など
過少資本税制の対象となる利子等の範囲も見直す方針だ。過少資本税制とは、資本に係る配当と負債に係る利子との課税上の相違点を利用した租税回避を規制するための税制のこと。出資により資金調達の場合には、配当を受けても損金に算入できないため、課税所得を減少させることはできないが、借入れによる資金調達の場合における利子については、損金算入できるため、課税所得を減少させることができるからだ。このため、海外の関連企業との間において、出資に代えて貸付けを多くすることによって税負担の軽減を防止するために、一定割合を超える支払利子の損金算入を認めないこととしている(右上図参照)。
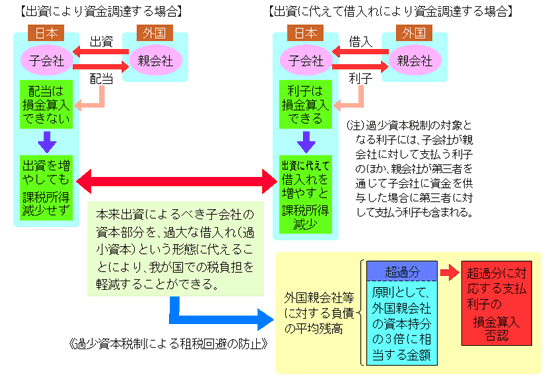
しかし、本来過少資本税制の対象となるべき利子について、名目上は保証料や使用料に組み換える取引を組成し、過少資本税制の適用を免れている事例が散見されているとしている。このため、改正の方向としては、過少資本税制の適用を免れている一定の取引について、その取引の利子と保証料、利子と使用料を一体として捉え、過少資本税制の対象に加えるとしている。
移転価格税制における推定課税の方法を追加
移転価格税制とは、海外の関連企業との間の取引を通じる所得の海外移転を防止するため、その移転価格を通常の取引価格(独立企業間価格)に引き直して課税する制度。現在、独立企業間価格の算定方法については、下記の5つの方法が認められているが、納税者が独立企業間価格の算定に必要な帳簿書類を提出しない場合には、税務署長は、一定の方法により算定した金額を独立企業間価格として推定して、課税を行うことができるとされている。しかし、昨今の取引形態の多様化に伴い、現在認められている推定課税における算定方法だけでは、独立企業間価格を算定することが困難な状況があるとしている。このため、推定課税において用いることができる算定方法に、取引単位営業利益法及び利益分割法に対応する方法を追加する方向だ。
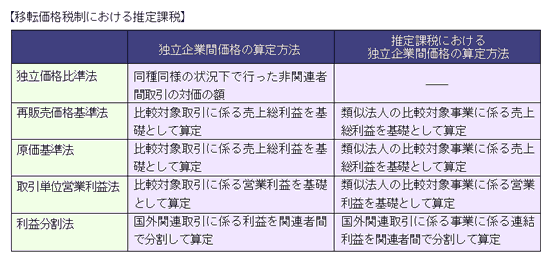
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























