コラム2006年10月23日 【SCOPE】 監査法人の強制的ローテーションの導入は否定的(2006年10月23日号・№184)
日本監査研究学会の研究報告で明らかに
監査法人の強制的ローテーションの導入は否定的
金融審議会の公認会計士制度部会(部会長:関哲夫新日本製鐵(株)常任監査役)では、現在、監査法人制度の見直しに着手している。見直しの論点の1つとして、監査法人のローテーション(交代)が挙げられているが、ローテーションについては、これに否定的な意見が多いことがわかった。日本監査研究学会の特別委員会(委員長:高田敏文東北大学会計大学院教授)がまとめた「監査事務所の強制的ローテーションに関する実態調査研究報告」で明らかになったものである。
自民党は「監査法人のローテーションが必要」
平成16年4月施行の公認会計士法の改正により、同一の監査人による継続監査は7年(その後、2年間のインターバルあり)とされている。その後、日本公認会計士協会の自主規制として、平成18年4月1日以後開始事業年度から大手監査法人の主任会計士において、継続監査期間を5年、インターバルを5年とすることをルールとして定めている。これは、カネボウの粉飾決算事件を受けた対応であるが、企業と監査人との癒着を防ぐには、監査法人自体のローテーション(同一の監査法人等が継続して上場企業の監査を実施できる年数に制限を設けること)を行うべきとの意見が自民党を中心に出されていた。
これを受け、公認会計士制度部会では、監査法人制度の見直しに着手し、論点の1つとして監査法人のローテーションを挙げている。
米国でも導入せず
監査法人のローテーションについては、当初から日本公認会計士協会が、①従前の監査によって得られた知識、経験等が喪失し、効果的ではない、②海外で上場している会社などでは、海外で監査契約を締結している監査法人と提携している日本の監査法人との間で監査契約を締結している例がほとんどであるなどの理由を挙げ、強く反対していた。
また、米国の企業改革法においても、監査法人のローテーションについて検討が行われているが、監査の効率性からみて不適当との調査結果を受け、導入を見送っている。
今回、日本監査研究学会特別委員会がまとめた「監査事務所の強制的ローテーションに関する実態調査研究報告」でも、監査事務所のローテーションを導入することは難しいとの結論を裏付ける結果がでている。以下、主だった点を紹介する。
コストが便益を上回る
まず、企業経営者に対して、監査事務所のローテーションを実施した場合、従来見過ごされていた不正等を発見できる可能性が高まるか否かについてのアンケート調査結果では、「高まる」との回答は全部で34.1%で、「変わらない」との回答が39.5%となっている(表1参照)。また、ローテーションにより発生する可能性のあるコストと便益については、コストが便益を上回るとの回答が69.3%にのぼっている(表2参照)。
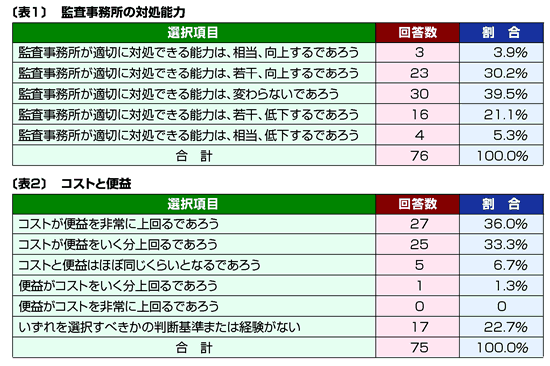
ローテーション反対派が多いが……
次に上場企業の監査役・監査委員会に対して、監査事務所のローテーションが行われた場合に4大監査法人を監査人として選任することへの制限が加えられることに関するアンケート調査結果では、ローテーションを支持しないとの回答が37.7%と最も多く、次いで、支持するが企業側のコストは便益を超えるとの回答が33.8%となっている(表3参照)。
両者の見解は拮抗しているものの、企業側のコストに対する意識は高いものとなっている。この点、米国では、監査事務所のローテーションを支持しない回答が68%と圧倒的に多くなっている。
ローテーションの初年度はリスクが増加する
監査事務所に対して、ローテーションが実施された場合の重要な虚偽表示等を発見できないリスクについては、仮に新たな監査人がクライアントの業務等について有する知識が少ない場合、リスクを増加させるとの回答は、「いくらか増大させる」が62.1%、「非常に増大させる」が28.8%と約9割を占めた。その他、上場企業に対する財務諸表監査の業務の獲得競争も約6割が激しくなると回答している。
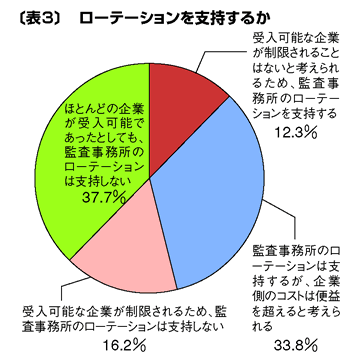
監査法人の強制的ローテーションの導入は否定的
金融審議会の公認会計士制度部会(部会長:関哲夫新日本製鐵(株)常任監査役)では、現在、監査法人制度の見直しに着手している。見直しの論点の1つとして、監査法人のローテーション(交代)が挙げられているが、ローテーションについては、これに否定的な意見が多いことがわかった。日本監査研究学会の特別委員会(委員長:高田敏文東北大学会計大学院教授)がまとめた「監査事務所の強制的ローテーションに関する実態調査研究報告」で明らかになったものである。
自民党は「監査法人のローテーションが必要」
平成16年4月施行の公認会計士法の改正により、同一の監査人による継続監査は7年(その後、2年間のインターバルあり)とされている。その後、日本公認会計士協会の自主規制として、平成18年4月1日以後開始事業年度から大手監査法人の主任会計士において、継続監査期間を5年、インターバルを5年とすることをルールとして定めている。これは、カネボウの粉飾決算事件を受けた対応であるが、企業と監査人との癒着を防ぐには、監査法人自体のローテーション(同一の監査法人等が継続して上場企業の監査を実施できる年数に制限を設けること)を行うべきとの意見が自民党を中心に出されていた。
これを受け、公認会計士制度部会では、監査法人制度の見直しに着手し、論点の1つとして監査法人のローテーションを挙げている。
米国でも導入せず
監査法人のローテーションについては、当初から日本公認会計士協会が、①従前の監査によって得られた知識、経験等が喪失し、効果的ではない、②海外で上場している会社などでは、海外で監査契約を締結している監査法人と提携している日本の監査法人との間で監査契約を締結している例がほとんどであるなどの理由を挙げ、強く反対していた。
また、米国の企業改革法においても、監査法人のローテーションについて検討が行われているが、監査の効率性からみて不適当との調査結果を受け、導入を見送っている。
今回、日本監査研究学会特別委員会がまとめた「監査事務所の強制的ローテーションに関する実態調査研究報告」でも、監査事務所のローテーションを導入することは難しいとの結論を裏付ける結果がでている。以下、主だった点を紹介する。
コストが便益を上回る
まず、企業経営者に対して、監査事務所のローテーションを実施した場合、従来見過ごされていた不正等を発見できる可能性が高まるか否かについてのアンケート調査結果では、「高まる」との回答は全部で34.1%で、「変わらない」との回答が39.5%となっている(表1参照)。また、ローテーションにより発生する可能性のあるコストと便益については、コストが便益を上回るとの回答が69.3%にのぼっている(表2参照)。
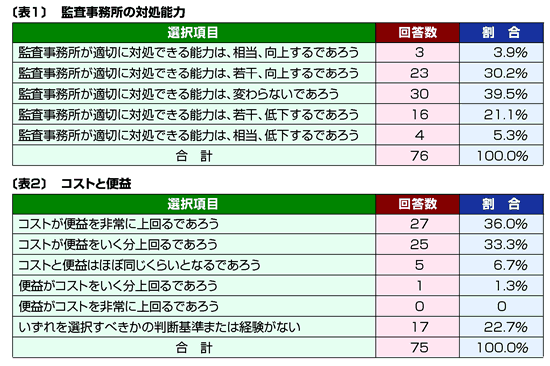
ローテーション反対派が多いが……
次に上場企業の監査役・監査委員会に対して、監査事務所のローテーションが行われた場合に4大監査法人を監査人として選任することへの制限が加えられることに関するアンケート調査結果では、ローテーションを支持しないとの回答が37.7%と最も多く、次いで、支持するが企業側のコストは便益を超えるとの回答が33.8%となっている(表3参照)。
両者の見解は拮抗しているものの、企業側のコストに対する意識は高いものとなっている。この点、米国では、監査事務所のローテーションを支持しない回答が68%と圧倒的に多くなっている。
ローテーションの初年度はリスクが増加する
監査事務所に対して、ローテーションが実施された場合の重要な虚偽表示等を発見できないリスクについては、仮に新たな監査人がクライアントの業務等について有する知識が少ない場合、リスクを増加させるとの回答は、「いくらか増大させる」が62.1%、「非常に増大させる」が28.8%と約9割を占めた。その他、上場企業に対する財務諸表監査の業務の獲得競争も約6割が激しくなると回答している。
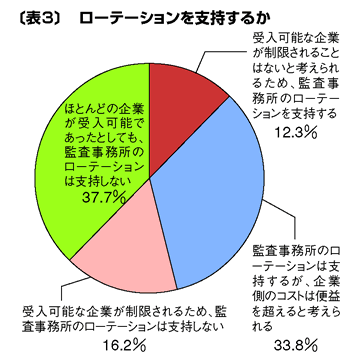
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























