コラム2006年12月25日 【間違いやすい税務事例集】 遺言執行者が換価処分を行い公益法人に寄付した場合(2006年12月25日号・№192)
間違いやすい税務事例集13
遺言執行者が換価処分を行い公益法人に寄付した場合
中村税法研究会 税理士 渡邉正則
質 問
被相続人甲は、所有する土地および上場株式の一部を処分しX財団法人に寄付する遺言書を作成していました。遺言執行者は甲の知人である弁護士が指定されていました。
遺言執行者は遺言の内容に基づき、一部の遺産を処分しX財団法人に寄付しました。
甲には相続人である子(乙、丙)がいます。相続人が相続財産の一部を特定の公益法人に寄付した場合、非課税の特例がありますが、このような場合もその特例の適用があるでしょうか。また、譲渡所得税の申告を行う場合、取得費に相続税が加算され税額を軽減できる相続税の取得費加算の特例は適用できるでしょうか。
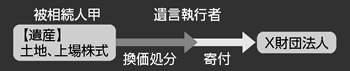
回 答
① 相続人が相続財産を特定の公益法人に寄付した場合の非課税の特例(措置法70)については、相続財産そのものを寄付したわけではありませんので、特例は適用できないものと考えられます。
なお、相続人である乙、丙は取得した換価処分前の財産について相続税が課税されます。この場合の課税価格は、換価処分代金相当額ではなく、換価前の財産の相続税評価額となります。
② 土地および上場株式の換価処分により発生する譲渡所得に対しては、配分された価額の割合に応じて、乙、丙に課税されます。この際、換価処分が相続税の法定申告期限から3年以内に行われた場合は、相続税の取得費加算の特例(措置法39条)の適用があります。
解 説
(1)相続財産を特定の公益法人に寄付した場合
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続や遺贈についての相続税の申告書の提出期限までに、その相続や遺贈によって取得した財産を、国もしくは地方公共団体または民法34条の規定によって設立された法人その他の公益事業を行う法人のうち教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定のもの(特定の公益法人)に対して寄付をした場合には、その寄付したことによって、その寄付者または親族その他これらの人と特別の関係にある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合を除いて、その寄付した財産の価額は、その相続や遺贈についての相続税の課税価格の計算に算入されません。
ただ、この特例は相続財産を寄付することが要件となっているため、ご質問のように相続財産を処分しその代金を寄付したとしても、適用を受けることはできないことになります。
(2)遺言執行者が換価処分を行う場合
遺言執行者が遺産の換価処分とその換価代金の分配を行うといった遺言の場合、換価処分の行為は、遺言執行者の職務権限としてなされ(民法1012条)、相続人または包括受遺者の代理人として行うものである(民法1015条)ため、その行為の効果は相続人または包括受遺者に帰属することになると考えられます。
そのため、ご質問のケースで遺言執行者が行った換価処分は相続人乙、丙の代理人として行ったことになり、その効果は乙、丙に帰属すると考えれば、相続人乙、丙の課税関係は上記のようになります。
遺言執行者が換価処分を行い公益法人に寄付した場合
中村税法研究会 税理士 渡邉正則
質 問
被相続人甲は、所有する土地および上場株式の一部を処分しX財団法人に寄付する遺言書を作成していました。遺言執行者は甲の知人である弁護士が指定されていました。
遺言執行者は遺言の内容に基づき、一部の遺産を処分しX財団法人に寄付しました。
甲には相続人である子(乙、丙)がいます。相続人が相続財産の一部を特定の公益法人に寄付した場合、非課税の特例がありますが、このような場合もその特例の適用があるでしょうか。また、譲渡所得税の申告を行う場合、取得費に相続税が加算され税額を軽減できる相続税の取得費加算の特例は適用できるでしょうか。
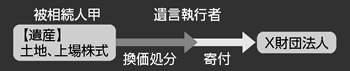
回 答
① 相続人が相続財産を特定の公益法人に寄付した場合の非課税の特例(措置法70)については、相続財産そのものを寄付したわけではありませんので、特例は適用できないものと考えられます。
なお、相続人である乙、丙は取得した換価処分前の財産について相続税が課税されます。この場合の課税価格は、換価処分代金相当額ではなく、換価前の財産の相続税評価額となります。
② 土地および上場株式の換価処分により発生する譲渡所得に対しては、配分された価額の割合に応じて、乙、丙に課税されます。この際、換価処分が相続税の法定申告期限から3年以内に行われた場合は、相続税の取得費加算の特例(措置法39条)の適用があります。
解 説
(1)相続財産を特定の公益法人に寄付した場合
相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続や遺贈についての相続税の申告書の提出期限までに、その相続や遺贈によって取得した財産を、国もしくは地方公共団体または民法34条の規定によって設立された法人その他の公益事業を行う法人のうち教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定のもの(特定の公益法人)に対して寄付をした場合には、その寄付したことによって、その寄付者または親族その他これらの人と特別の関係にある人の相続税や贈与税の負担が不当に減少すると認められる場合を除いて、その寄付した財産の価額は、その相続や遺贈についての相続税の課税価格の計算に算入されません。
ただ、この特例は相続財産を寄付することが要件となっているため、ご質問のように相続財産を処分しその代金を寄付したとしても、適用を受けることはできないことになります。
(2)遺言執行者が換価処分を行う場合
遺言執行者が遺産の換価処分とその換価代金の分配を行うといった遺言の場合、換価処分の行為は、遺言執行者の職務権限としてなされ(民法1012条)、相続人または包括受遺者の代理人として行うものである(民法1015条)ため、その行為の効果は相続人または包括受遺者に帰属することになると考えられます。
そのため、ご質問のケースで遺言執行者が行った換価処分は相続人乙、丙の代理人として行ったことになり、その効果は乙、丙に帰属すると考えれば、相続人乙、丙の課税関係は上記のようになります。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















