解説記事2008年05月05日 【会計基準等解説】 企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」について(2008年5月5日号・№257)
企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」について
企業会計基準委員会 専門研究員 二宮正裕
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)は、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。また本会計基準と本適用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。)を平成20年3月21日に公表している(脚注1)。
ここでは、本会計基準等の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.本会計基準等の全般的事項
1 公表の経緯 これまで我が国においては、連結財務諸表の注記事項として、「事業の種類別セグメント情報」「所在地別セグメント情報」及び「海外売上高」の3つのセグメント情報が開示されてきた。これらの情報は、財務諸表利用者が多角化、国際化した企業の過去の業績及び将来の見込みについて適切な判断を下すために有用な情報を提供するものとされてきたが、一方で、「我が国を代表する大企業の2割近くが単一セグメント、もしくは重要性が低いとの理由で事業の種類別セグメントを作成しておらず、現行制度が十分に機能していないと思われる。」という指摘(脚注2)もなされていた。
また、ASBJが現在進めている国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)との会計基準の国際的なコンバージェンスに向けた共同プロジェクトの中でも、セグメント情報の開示は、平成17年3月に開催された共同プロジェクトの第1回会合において、第1フェーズの検討項目とされた。
こうした状況を受けて、ASBJは、平成17年5月にセグメント情報開示に関するワーキング・グループを設置し、我が国におけるマネジメント・アプローチの導入について検討した後、平成18年12月にセグメント情報開示専門委員会を設置し、従来基準の見直しに向けた審議を行った。本会計基準等は、平成19年9月に公表した公開草案に対して寄せられたコメントを検討し、公開草案を一部修正した上で公表に至ったものである。
2 本会計基準等の目的 本会計基準等は、次の開示に関する取扱いを定めることを目的としている(以下(1)から(4)を合わせて「セグメント情報等」という。)(本会計基準第1項)。
| (1)セグメント情報 |
3 マネジメント・アプローチ 国際的な会計基準においては、経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎とする「マネジメント・アプローチ」が導入されている。
このマネジメント・アプローチの特徴は次の点にあるとされている(本会計基準第46項)。
| (1)企業の組織構造、すなわち、最高経営意思決定機関が経営上の意思決定を行い、また、企業の業績を評価するために使用する事業部、部門、子会社又は他の内部単位に対応する企業の構成単位に関する情報を提供すること |
ASBJは、マネジメント・アプローチの長所(本会計基準第47項)と短所(本会計基準第48項)を比較検討した結果、財務諸表利用者が経営者の視点で企業を理解できる情報を開示することによって、財務諸表利用者の意思決定により有用な情報を提供することができると判断し、マネジメント・アプローチを採用することとした(本会計基準第50項)。なお、本会計基準等に基づくセグメント情報と従来のセグメント情報との比較についても、本会計基準第51項に示されている。
4 基本原則 本会計基準では、企業がセグメント情報等を開示するにあたっての基本原則として、「セグメント情報等の開示は、財務諸表利用者が、企業の過去の業績を理解し、将来のキャッシュ・フローの予測を適切に評価できるように、企業が行う様々な事業活動の内容及びこれを行う経営環境に関して適切な情報を提供するものでなければならない。」旨を定めている(本会計基準第4項)。基本原則は、本会計基準の具体的な適用にあたって常に留意すべきものであり(本会計基準第58項)、この内容として、次のような記載がある。
| (1)本会計基準の定めであっても、重要性が乏しく、財務諸表利用者の判断を誤らせる可能性がないと考えられる定めについては、これを適用することを要しない(本会計基準第59項)。 |
Ⅲ.セグメント情報の開示
1 事業セグメントの識別 マネジメント・アプローチでは、経営者が経営上の意思決定を行い、また、業績を評価するために、企業の事業活動を区分した方法に基づいて、単一の区分方法によるセグメント情報を連結財務諸表又は個別財務諸表(以下「財務諸表」という。)に開示することとしているが、本会計基準では、当該目的で経営者の設定する企業の構成単位を「事業セグメント」と称し、次の要件のすべてに該当するものとしている(本会計基準第6項)。
| (1)収益を稼得し、費用が発生する事業活動に関わるもの(同一企業内の他の構成単位との取引に関連する収益及び費用を含む。) |
2 報告セグメントの決定 企業は、識別された事業セグメント又は集約基準によって集約された事業セグメントの中から、量的基準に従って、報告すべきセグメント(以下「報告セグメント」という。)を決定するとされている(本会計基準第10項)。
(1)集約基準 複数の事業セグメントが次の要件のすべてを満たす場合、企業は当該事業セグメントを1つの事業セグメントに集約することができる(本会計基準第11項)。
| (1)当該事業セグメントを集約することが、セグメント情報を開示する基本原則と整合していること |
| (1)売上高(事業セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)がすべての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上であること(売上高には役務収益を含む。以下同じ。) |
また、本会計基準では、当該基準を満たさない複数の事業セグメントを結合して報告セグメントとすることができる要件についても、国際的な会計基準と同様に定めている(本会計基準第13項)。
本会計基準では、報告セグメントの外部顧客への売上高の合計額が連結損益計算書又は個別損益計算書(以下「損益計算書」という。)の売上高の75%未満である場合には、損益計算書の売上高の75%以上が報告セグメントに含まれるまで、報告セグメントとする事業セグメントを追加して識別しなければならないとされている(本会計基準第14項)。この結果、報告セグメントに含まれないこととされた事業セグメント及びその他の収益を稼得する事業活動に関する情報は、「報告セグメントの各開示項目の合計額とこれに対応する財務諸表計上額との間の差異調整に関する事項」の中で、他の調整項目とは区分して、「その他」の区分に一括し、当該区分に含まれる主要な事業の名称等と合わせて開示することとされている(本会計基準第15項)。
また、ある事業セグメントの量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨及びセグメント情報に与える影響を開示しなければならないとされている(本会計基準第16項)。ただし、量的基準によって報告セグメントを決定する場合、相当期間にわたりその継続性が維持されるよう配慮する必要がある(本適用指針第9項)。
3 セグメント情報の開示項目と測定方法
(1)セグメント情報の開示項目 企業は、セグメント情報として次の項目を開示することとされている(本会計基準第17項)。
| (1)報告セグメントの概要 |
| (1)報告セグメントの決定方法 |
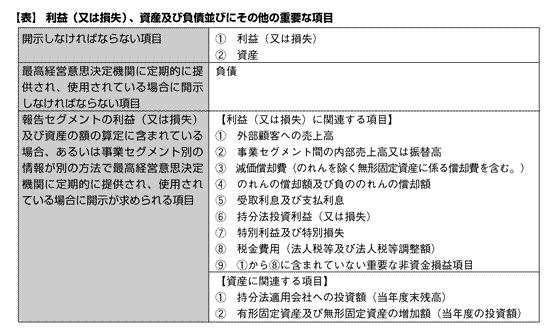
表の項目の開示は、事業セグメントに資源を配分する意思決定を行い、その業績を評価する目的で、最高経営意思決定機関に報告される金額に基づいて行わなければならないとされ、このため、財務諸表の作成にあたって行った修正や相殺消去、又は特定の収益、費用の配分は、最高経営意思決定機関が使用する事業セグメントの利益(又は損失)、資産又は負債の算定に含まれている場合にのみ、報告セグメントの各項目の額に含めることができる(本会計基準第23項)。ただし、特定の収益、費用、資産又は負債を各事業セグメントの利益(又は損失)、資産又は負債に配分する場合、企業は合理的な基準に従って配分しなければならない(本会計基準第23項ただし書き)。
なお、本適用指針では、本会計基準第23項の定めにかかわらず、複数の事業セグメントを1つの事業セグメントに集約又は結合して報告セグメントとして開示する場合、本会計基準の基本原則に基づいて、同一の報告セグメント内の複数の事業セグメント間の取引及び債権債務の相殺消去や未実現利益の消去等を反映した金額により、報告セグメントの各項目を開示することができるとされている(本適用指針第14項)。
また、企業は、本会計基準第19項から第22項に基づいて開示する項目の測定方法について、次の事項を開示しなければならないとされている(本会計基準第24項)。
| (1)報告セグメント間の取引がある場合、その会計処理の基礎となる事項 |
| (1)報告セグメントの売上高の合計額と損益計算書の売上高計上額 |
4 組織変更等によるセグメントの区分方法の変更 企業の組織構造の変更等、企業の管理手法が変更されたために、報告セグメントの区分方法を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示するものとする(本会計基準第27項)。ただし、前年度のセグメント情報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示することが実務上困難な場合には、当年度のセグメント情報を前年度の区分方法により作成した情報を開示することができる(本会計基準第27項ただし書き)。
公開草案では、企業の組織変更等により報告セグメントの区分方法を変更する場合には、その旨及びセグメント情報に与える影響を開示することとされ、この影響の開示方法を特に定めていなかった。しかし、公開草案に対し、当該影響の開示方法として、前年度のセグメント情報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示することが適当であるとするコメントが寄せられたため、再度検討した結果、本会計基準の取扱いとされている。
また、企業が従来とは大きく異なる組織体制を採用した場合など、これらの開示を行うことが実務上困難な場合も想定され、こうした場合には、当該開示に代えて、当該開示を行うことが実務上困難な旨及びその理由を記載することとなる(本会計基準第28項)。また、これらの開示は、セグメント情報に開示するすべての項目について記載するものとするが、一部の項目について記載することが実務上困難な場合は、その旨及びその理由を記載することとなる(本会計基準第28項また書き)。
Ⅳ.関連情報の開示
1 関連情報の開示 企業は、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合を除き、次の事項をセグメント情報の関連情報として開示しなければならないとされている。当該関連情報に開示される金額は、当該企業の財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によるものとする。なお、報告すべきセグメントが1つしかなく、セグメント情報を開示しない企業であっても、当該関連情報を開示しなければならない(本会計基準第29項)。
| (1)製品及びサービスに関する情報 |
2 製品及びサービスに関する情報 企業は、主要な個々の製品又はサービスあるいはこれらの種類や性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づく同種・同系列のグループごとに、外部顧客への売上高を開示することとされている。なお、当該事項を開示することが実務上困難な場合には、当該事項の開示に代えて、その旨及びその理由を開示しなければならない(本会計基準第30項)。
3 地域に関する情報 企業は、地域に関する情報として、次の事項を開示することとされている。なお、当該事項を開示することが実務上困難な場合には、当該事項に代えて、その旨及びその理由を開示しなければならない(本会計基準第31項)。
| (1)国内の外部顧客への売上高に分類した額と海外の外部顧客への売上高に分類した額 |
4 主要な顧客に関する情報 企業は、主要な顧客がある場合には、その旨、当該顧客の名称又は氏名、当該顧客への売上高及び当該顧客との取引に関連する主な報告セグメントの名称を開示することとされている(本会計基準第32項)。
なお、同一の企業集団に属する顧客への売上高については、企業が知り得る限り、これを集約して主要な顧客に該当するか否かを判断することが望ましいとされている(本会計基準第93項)。
Ⅴ.固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報の開示
企業は、損益計算書に固定資産の減損損失を計上しており、セグメント情報の中で同様の情報を開示していない場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によって、その報告セグメント別の内訳を開示しなければならないとされている(本会計基準第33項)。このとき、報告セグメントに含まれない事業セグメント等に配分された固定資産や本適用指針第12項の全社資産とされた固定資産について減損損失を計上することも想定される。このため、報告セグメントに配分されていない減損損失がある場合には、その額及びその内容を記載しなければならないとされている。
Ⅵ.のれんに関する報告セグメント別情報の開示
企業は、損益計算書にのれんの償却額又は負ののれんの償却額を計上しており、セグメント情報の中で同様の情報を開示していない場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によって、のれんの償却額及び未償却残高並びに負ののれんの償却額及び未償却残高について報告セグメント別の内訳を開示しなければならないとされている(本会計基準第34項)。このとき、報告セグメントに含まれない事業セグメント等に配分されたのれん又は負ののれんがある場合、あるいは、ケースとしては限定的であると考えられるものの、全社資産又は全社負債とされたのれん又は負ののれんがある場合も想定される。このため、上記Ⅴの固定資産の減損損失に関する開示の取扱いと同様、報告セグメントに配分されていないのれん又は負ののれんがある場合には、その償却額及び未償却残高並びにその内容を記載しなければならないとされている。
Ⅶ.適用時期等
1 適用時期 本会計基準等は、財務諸表作成者ほか各関係者における受入準備が必要であることを考慮して、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用することとされている(本会計基準第35項及び第98項)。
2 適用初年度の取扱い 本会計基準等の適用初年度の取扱いとして、次のような事項が定められている(本会計基準第36項から第38項)。
| (1)適用初年度においては、当年度のセグメント情報とともに本会計基準に準拠して作り直した前年度のセグメント情報を開示するものとするが、これを開示することが実務上困難な場合には、当年度のセグメント情報を前年度のセグメント情報の取扱いに基づき作成した情報を開示することができる。 |
3 四半期財務諸表の取扱い 四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報等の取扱いについては、引き続き、ASBJにて必要な検討を行うことが予定されている。
Ⅷ.開示例
本適用指針の末尾には、本会計基準等で示された内容の理解を深めるための開示例が参考として示されており、実際のセグメント情報等の開示のイメージはこちらを参照して頂きたい。なお、これらは例示であり、具体的な記載内容は各企業の実情により異なると考えられる。
ここでは2つの開示例が示されているが、開示例1のセグメント情報は製品及びサービスの種類別に区分し、セグメント利益と営業利益の間の差異を調整している例であり、開示例2は地域別に区分し、セグメント利益と税金等調整前当期純利益の間の差異を調整している例である。また、報告セグメントの開示項目の合計額と対応する財務諸表計上額との間の差異調整に関する数値情報について、開示例1では、報告セグメント別の数値情報と合わせて一表により開示しているが、開示例2では、当該情報を別表により開示している。この点について、開示例では、差異調整に関する事項の内容が多岐にわたる場合などにおいては、開示例2のように別表を設けて記載することが考えられるとされている。
Ⅸ.おわりに
ASBJのセグメント情報の検討は、会計基準の国際的なコンバージェンスの観点を重視して進められた。今回導入した国際的な会計基準のマネジメント・アプローチは、経営者が実際に経営上の意思決定等に用いている情報を基礎としたセグメント情報の開示を企業に求めるものである。このような情報が開示されることで、財務諸表利用者が経営者の視点で企業をみることができるようになり、財務諸表の有用性がより高まるものと期待される。
(にのみや・まさひろ)
(脚注)
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/)を参照。
2 平成13年11月に、テーマ協議会がASBJに対して提言した「第1回テーマ協議会提言書」より抜粋。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















