解説記事2008年12月15日 【編集部解説】 持分プーリング法を廃止する企業結合会計基準等の概要(2008年12月15日号・№287)
実務解説
持分プーリング法を廃止する企業結合会計基準等の概要
編集部
企業会計基準委員会(ASBJ)は12月18日にも、企業結合会計基準等を決定する。年内にも公表される予定である。これらの会計基準等は平成20年6月30日に公開草案として公表されたものであり、持分プーリング法を廃止することなどが大きな柱となっている。国際的な会計基準とのコンバージェンスを行う目的である。新しい企業結合会計基準等は、平成22年4月1日以後実施される企業結合等から適用することとされており、早期適用も認められている。本稿では、新企業結合会計基準等の概要を紹介する。
Ⅰ.企業結合会計基準の6つの論点
企業会計基準委員会が公表する予定の会計基準等は、「企業結合に関する会計基準」「事業分離等に関する会計基準」「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」「研究開発費等に係る会計基準の一部改正」「連結財務諸表に関する会計基準」「持分法に関する会計基準」である。以下では、同委員会が平成19年12月27日に公表した「企業結合会計の見直しに関する論点の整理」に示された6つの論点を中心にみることとする。
具体的には、①持分プーリング法の取扱い、②株式を対価とする場合の測定日、③負ののれんの会計処理、④少数株主持分の測定、⑤段階取得における会計処理、⑥外貨建てのれんの取扱いである。
1 持分プーリング法の廃止 ①に関しては、公開草案どおり、持分プーリング法は廃止することとされている。わが国の企業結合会計基準は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されており、現行の取扱いでは、パーチェス法のほかに、一定の要件のもとで持分プーリング法が認められている。しかし、国際的な会計基準では、持分プーリング法を認めていないため、その差異の解消が必要になっていたものである。
企業結合会計基準によれば、持分プーリング法を廃止することとし、共同支配企業の形成や共通支配下の取引以外の企業結合はパーチェス法を適用することとされている。これにより、国際的な会計基準とのコンバージェンスが行われることになる。
また、現行の会計基準が定める持分の結合に該当するようなケースであっても、パーチェス法が適用されることになるため、必ずどちらかの結合当事企業を取得企業としなければならない。実務上、取得企業が明確でないこともあるため、取得企業の決定方法が規定されている。
具体的には、結合後企業に支配株主が存在しない場合において、主な対価の種類として、現金あるいは他の資産を引き渡すまたは負債を引き受けることになる企業結合の場合には、原則として、現金あるいは他の資産を引き渡すまたは負債を引き受ける企業が取得企業になる。
また、主な対価の種類が株式である企業結合の場合には、原則として株式を発行する企業が取得企業となる。
ただし、逆取得のように、必ずしも株式を発行した企業が取得企業にならない場合もあるため、①相対的な議決権比率の大きさ、②最も大きな議決権比率を有する株主の存在、③取締役等を選解任できる株主の存在、④取締役会等の構成、⑤株式の交換条件を総合的に勘案して決定することになる。
2 株式を対価とする場合の測定日 ②の株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日については、国際的な会計基準に合わせ、企業結合日における時価を基礎として算定することとしている。
現行の取扱いでは、企業結合の主要条件が合意されて公表された日前の合理的な期間における株価を算定しなければならないとされているところである。
3 負ののれんの会計処理 ③の負ののれんの会計処理については、現行の取扱いによれば、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却するものとされている。
しかし、今回の改正では、負ののれんが生じると見込まれる場合には、取得企業は、すべての識別可能資産および負債が識別されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直すこととし、見直しても取得原価が取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理することになることとされている。
4 少数株主持分の測定 ④の少数株主持分の測定については、全面時価評価法により評価しなければならないことにした。
現行の取扱いでは、連結財務諸表の作成にあたって、子会社の資産および負債を評価する方法として、親会社の持分に相当する部分については、株式の取得日ごとの時価により評価し、少数株主持分に相当する部分については、子会社の個別貸借対照表上の金額による方法(部分時価評価法)と、子会社の資産および負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)の2つの方法が認められている。
5 段階取得における会計処理 ⑤の段階取得における会計処理については、公開草案とは取扱いが異なる部分である。
公開草案では、被取得企業の取得原価は、原則として取得時点における取得の対価(支払対価)となる財の時価で算定するものとし、当該支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、個別損益計算書および連結損益計算書のいずれにおいても損益として処理することとされている。
しかし、連結財務諸表上は公開草案のとおり、取得の対価となる財の企業結合日における時価で算定することになるが、個別財務諸表上は、現行の取扱いどおり、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額によるものとされた。
6 外貨建てのれんの取扱い ⑥の外貨建てのれん(在外子会社株式の取得により生じたのれんの会計処理)の会計処理については、現行の取扱いでは発生時の為替相場で換算する方法とされているが、決算日の為替相場により換算する方法に変更することとされている。
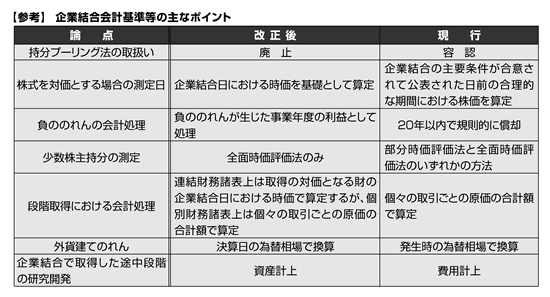
Ⅱ.研究開発費等会計基準の論点
そのほかの主な改正点としては、企業結合により取得した研究開発の途中段階の成果の会計処理がある。
現行の研究開発費等会計基準の取扱いでは、取得対価の一部を研究開発費等に配分した場合には、当該金額を配分時に費用処理することとされているが、当該会計処理を廃止している。また、被取得企業から受け入れた資産に識別可能な無形資産が含まれる場合には、取得原価を当該無形資産等に配分することができるとされているが、無形資産が識別可能なものであれば、原則として識別して資産計上することとされている。
また、研究開発費等会計基準では、企業結合により取得した資産(受注制作、市場販売目的および自社利用のソフトウェアを除く)については、同会計基準を適用しない旨が定められている。
Ⅲ.適用時期
企業結合会計基準、事業分離等会計基準および企業結合会計基準等適用指針については、平成22年4月1日以後に実施される企業結合または事業分離等からとされている。平成21年4月1日以後実施される企業結合等からの早期適用も認められている。
また、連結財務諸表会計基準、研究開発費等会計基準、持分法会計基準についても、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度から適用される。早期適用も可能である。
持分プーリング法を廃止する企業結合会計基準等の概要
編集部
企業会計基準委員会(ASBJ)は12月18日にも、企業結合会計基準等を決定する。年内にも公表される予定である。これらの会計基準等は平成20年6月30日に公開草案として公表されたものであり、持分プーリング法を廃止することなどが大きな柱となっている。国際的な会計基準とのコンバージェンスを行う目的である。新しい企業結合会計基準等は、平成22年4月1日以後実施される企業結合等から適用することとされており、早期適用も認められている。本稿では、新企業結合会計基準等の概要を紹介する。
Ⅰ.企業結合会計基準の6つの論点
企業会計基準委員会が公表する予定の会計基準等は、「企業結合に関する会計基準」「事業分離等に関する会計基準」「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」「研究開発費等に係る会計基準の一部改正」「連結財務諸表に関する会計基準」「持分法に関する会計基準」である。以下では、同委員会が平成19年12月27日に公表した「企業結合会計の見直しに関する論点の整理」に示された6つの論点を中心にみることとする。
具体的には、①持分プーリング法の取扱い、②株式を対価とする場合の測定日、③負ののれんの会計処理、④少数株主持分の測定、⑤段階取得における会計処理、⑥外貨建てのれんの取扱いである。
1 持分プーリング法の廃止 ①に関しては、公開草案どおり、持分プーリング法は廃止することとされている。わが国の企業結合会計基準は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されており、現行の取扱いでは、パーチェス法のほかに、一定の要件のもとで持分プーリング法が認められている。しかし、国際的な会計基準では、持分プーリング法を認めていないため、その差異の解消が必要になっていたものである。
企業結合会計基準によれば、持分プーリング法を廃止することとし、共同支配企業の形成や共通支配下の取引以外の企業結合はパーチェス法を適用することとされている。これにより、国際的な会計基準とのコンバージェンスが行われることになる。
また、現行の会計基準が定める持分の結合に該当するようなケースであっても、パーチェス法が適用されることになるため、必ずどちらかの結合当事企業を取得企業としなければならない。実務上、取得企業が明確でないこともあるため、取得企業の決定方法が規定されている。
具体的には、結合後企業に支配株主が存在しない場合において、主な対価の種類として、現金あるいは他の資産を引き渡すまたは負債を引き受けることになる企業結合の場合には、原則として、現金あるいは他の資産を引き渡すまたは負債を引き受ける企業が取得企業になる。
また、主な対価の種類が株式である企業結合の場合には、原則として株式を発行する企業が取得企業となる。
ただし、逆取得のように、必ずしも株式を発行した企業が取得企業にならない場合もあるため、①相対的な議決権比率の大きさ、②最も大きな議決権比率を有する株主の存在、③取締役等を選解任できる株主の存在、④取締役会等の構成、⑤株式の交換条件を総合的に勘案して決定することになる。
2 株式を対価とする場合の測定日 ②の株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日については、国際的な会計基準に合わせ、企業結合日における時価を基礎として算定することとしている。
現行の取扱いでは、企業結合の主要条件が合意されて公表された日前の合理的な期間における株価を算定しなければならないとされているところである。
3 負ののれんの会計処理 ③の負ののれんの会計処理については、現行の取扱いによれば、20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却するものとされている。
しかし、今回の改正では、負ののれんが生じると見込まれる場合には、取得企業は、すべての識別可能資産および負債が識別されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直すこととし、見直しても取得原価が取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を下回り、負ののれんが生じる場合には、当該負ののれんが生じた事業年度の利益として処理することになることとされている。
4 少数株主持分の測定 ④の少数株主持分の測定については、全面時価評価法により評価しなければならないことにした。
現行の取扱いでは、連結財務諸表の作成にあたって、子会社の資産および負債を評価する方法として、親会社の持分に相当する部分については、株式の取得日ごとの時価により評価し、少数株主持分に相当する部分については、子会社の個別貸借対照表上の金額による方法(部分時価評価法)と、子会社の資産および負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)の2つの方法が認められている。
5 段階取得における会計処理 ⑤の段階取得における会計処理については、公開草案とは取扱いが異なる部分である。
公開草案では、被取得企業の取得原価は、原則として取得時点における取得の対価(支払対価)となる財の時価で算定するものとし、当該支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、個別損益計算書および連結損益計算書のいずれにおいても損益として処理することとされている。
しかし、連結財務諸表上は公開草案のとおり、取得の対価となる財の企業結合日における時価で算定することになるが、個別財務諸表上は、現行の取扱いどおり、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額によるものとされた。
6 外貨建てのれんの取扱い ⑥の外貨建てのれん(在外子会社株式の取得により生じたのれんの会計処理)の会計処理については、現行の取扱いでは発生時の為替相場で換算する方法とされているが、決算日の為替相場により換算する方法に変更することとされている。
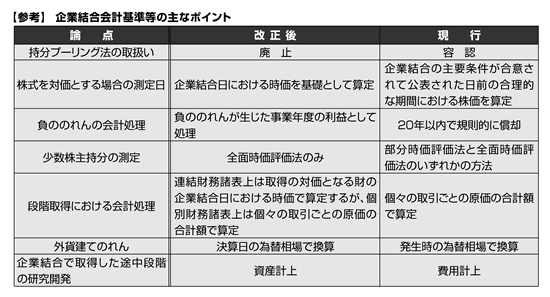
Ⅱ.研究開発費等会計基準の論点
そのほかの主な改正点としては、企業結合により取得した研究開発の途中段階の成果の会計処理がある。
現行の研究開発費等会計基準の取扱いでは、取得対価の一部を研究開発費等に配分した場合には、当該金額を配分時に費用処理することとされているが、当該会計処理を廃止している。また、被取得企業から受け入れた資産に識別可能な無形資産が含まれる場合には、取得原価を当該無形資産等に配分することができるとされているが、無形資産が識別可能なものであれば、原則として識別して資産計上することとされている。
また、研究開発費等会計基準では、企業結合により取得した資産(受注制作、市場販売目的および自社利用のソフトウェアを除く)については、同会計基準を適用しない旨が定められている。
Ⅲ.適用時期
企業結合会計基準、事業分離等会計基準および企業結合会計基準等適用指針については、平成22年4月1日以後に実施される企業結合または事業分離等からとされている。平成21年4月1日以後実施される企業結合等からの早期適用も認められている。
また、連結財務諸表会計基準、研究開発費等会計基準、持分法会計基準についても、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度から適用される。早期適用も可能である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















