解説記事2009年01月19日 【実務解説】 日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂について~(1)事業報告・附属明細書(2009年1月19日号・№291)
実務解説
日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂について~(1)事業報告・附属明細書
(社)日本経済団体連合会経済第二本部経済法制グループ長 小畑良晴
はじめに
日本経団連経済法規委員会企画部会(部会長:八丁地隆日立製作所顧問)は昨年11月25日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版(以下「ひな型」という)を公表した。
旧ひな型は、2006年5月1日の会社法施行を機に、それまでの商法に基づくものを全面的に刷新し、2007年2月9日に公表したものであったが、今般、旧ひな型の公表以後に施行あるいは改正された関係法令等を踏まえて、2008年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告(計算書類及び事業報告の附属明細書については、2008年4月1日以後に開始した事業年度に関するもの)を念頭に置いて、改正事項に即して必要最小限の修正を加えた(今号30頁以下の新旧対照表参照)。
今回の改訂にあたっては、法務省民事局参事官室小松岳志局付のご協力を得て、澤口実先生・石井裕介先生はじめ森・濱田松本法律事務所の先生方、布施伸章先生・阿部光成先生はじめ監査法人トーマツの先生方のご助言・ご協力と、わが国を代表する企業実務の専門家である日本経団連経済法規委員会企画部会及び同委員会企業会計部会委員による検討結果を踏まえて作成したものである。
主な改正のポイントは以下の通りである(編注:本文の参照頁及び参照項目番号は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」のものを表す。原文は(社)日本経済団体連合会のホームページ(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf)からダウンロードすることができる)。
Ⅰ 事業報告
1 会社役員に関する事項(記載の対象となる会社役員の範囲)(ひな型17頁参照) 事業報告における会社役員に関する開示規定について、改正前の会社法施行規則では、記載対象となる「会社役員」は、一律に「直前の定時総会の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む」(改正前会社法施行規則119条2号)とされており、事業報告の対象となる事業年度中に在任していた者であっても、直前の定時株主総会の終結の日までに退任した者は含まれないものとされていた。
この点について、会社役員に対する報酬等の額が適正なものであるかどうかについての情報を株主に対して提供する趣旨から、会社役員の就任及び退任の時期を問わず、ある事業年度において会社役員が受け、または受ける見込みとなった報酬等の額は、そのすべてが開示されるべき性質のものであるという考え方に基づき、この開示対象となる「会社役員」の範囲について会社法施行規則が改正された(平成20年法務省令第12号、2008年3月19日公布)。
本改正により、「会社役員」についての在任時期の限定(当該事業年度の開始の日後から直前の定時株主総会の終結の日までの間に退任した会社役員が含まれないという限定)は、報酬等に関する開示に及ばないこととなるとともに、辞任の理由又は解任の意見等の開示の対象となる会社役員についてもこの限定の対象とならず、全ての役員が開示の対象となることとなった。
その結果、事業報告における記載の対象となる会社役員の範囲については、記載事項により、在任時期の限定が付されているもの(4-1.氏名、4-2.地位及び担当、4-3.他の法人等の代表状況、4-5.財務及び会計に関する相当程度の知見、4-6.重要な兼職の状況)と、限定が付されていないもの(4-4.事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項、4-7.取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額、4-8.各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する事項、4-9.その他会社役員に関する重要な事項)とに大きく分けることができ、それぞれにおいて取扱いが異なることになる(表1参照)。
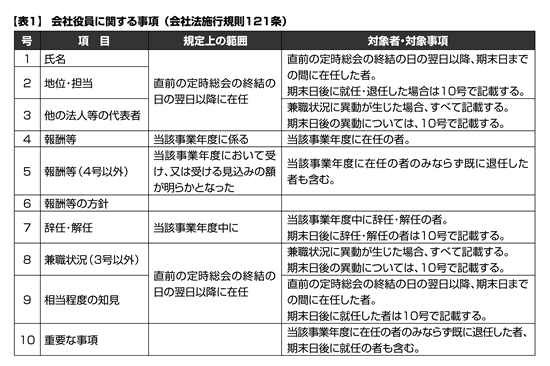 なお、社外役員に関する記載事項についても、同様の趣旨の改訂を行った(【社外役員に関する開示】(ひな型23頁)参照。)。
なお、社外役員に関する記載事項についても、同様の趣旨の改訂を行った(【社外役員に関する開示】(ひな型23頁)参照。)。
社外役員に関する記載事項のうち、①他の会社の業務執行者との兼職状況、②他の株式会社の社外役員との兼任状況、③会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係、④各社外役員の主な活動状況、及び⑤責任限定契約に関する事項(ひな型4-10~4-14参照)については、対象となる社外役員につき、「直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る」との限定が付されている(会社法施行規則124条1号~5号)。
一方、⑥社外役員の報酬等の額、⑦親会社又は当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等の総額、及び記載内容についての社外役員の意見(ひな型4-15~4-17参照)については、対象となる会社役員につき、在任時期の限定が付されておらず(会社法施行規則124条6号~9号)、事業報告の対象となる事業年度において在任していない社外役員についても記載が求められる可能性があることに注意しなければならない。
2 氏名、地位及び担当、他の法人等の代表状況(ひな型18頁参照) 旧ひな型では、当該事業年度の「末日における」取締役及び監査役(委員会設置会社の場合は取締役及び執行役)の氏名、会社における地位及び担当、他の法人等の代表状況を記載することとしていたが、規定上、「末日」現在在任の者のみを書くこととは明記されておらず、現在の実務では、「期中において兼職状況に変動が生じた場合には、事業報告の趣旨から、その内容を全て記載すべき」という取扱いが有力であるとみられることから、今回の改訂では、当該事業年度の末日のみならず、当該事業年度に係るすべての状況(異動)を記載することとした。
なお、事業年度中に地位や担当が変更された場合には、原則として、事業年度末日時点のものを一覧表に記載し、期中の変動は欄外に注記することが考えられる。
3 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(ひな型20頁参照) 会社法施行規則の改正により、特に、会社役員の報酬等の記載について従前と取扱いが大きく変わり、事業報告の対象となる事業年度にまったく在任していない会社役員についての記載も必要な場合があることに注意しなければならない。
具体的には、当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等については、事業報告の対象となる事業年度においてまったく在任していなかった会社役員であっても事業報告の記載対象となることがある(会社法施行規則121条5号)。
たとえば、事業報告の対象となる事業年度の開始前に退任した会社役員に対して、当該事業年度になって退職慰労金を支給した場合において、当該退職慰労金につき、事業報告への記載が必要となる場合がある(特に、4-7.(4)退職慰労金の項目(ひな型21頁)参照)。この規定の文言上、「当該事業年度において受け……た役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等……を除く)」とされていることから、当該事業年度前の事業報告で開示(会社法施行規則121条4号)されていない部分のみが、支給年度に係る事業報告において、会社法施行規則第121条5号に関する記載対象となる。
また、会社法施行規則121条5号後段の「当該事業年度において……受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等」とは、ある事業年度に客観的に対応する報酬等であるものの、その事業年度においては金額が判明しない場合に、それが明らかになった事業年度において同号に基づき開示を行うという趣旨で設けられた規定である。この開示についても、「当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く」と規定されていることから、いったん開示されれば後年度において、開示された部分(それを超過する部分は同号に基づく開示が別途必要となる)に関する開示の重複は避けられる。なお、この規定の文言上は「事業報告の内容」とされているが、規定の趣旨からすれば、会社法施行前において、事業報告に相当する書類(営業報告書、貸借対照表等の計算書類)に、引当金等として開示してきた金額についても、重複記載は不要と解することができよう。
このほか、会社法施行規則の改正により、会社役員の報酬等の開示方法の明確化を図るため、その開示方法を①会社役員の役職ごとの報酬等の総額を開示する方法(総額開示)、②会社役員の全部につき報酬等の個別金額を開示する方法(個別開示)、③会社役員の一部につき報酬等の個別金額を示し、その他について役職ごとの報酬等の総額を開示する方法(一部個別開示)に分けて規定し、これら3つの方法のいずれかを採ることができることが明確化され(会社法施行規則121条4号)、①、③の場合には、新たに「員数」を開示しなければならないこととなった。もっとも、旧ひな型でも人数を記載することとしており、特段の変更はない。なお、ここで規定されている会社役員の報酬等の開示の目的は、株主に対して、会社役員に支給される報酬が適正であるかどうかを判断する材料を提供することにあることから、報酬等の開示における員数には、無報酬の会社役員は含まれないと解されることから、記載上の注意(ひな型22頁参照)において、そのことを改めて明記し、その点を明確にするために記載例中「人数」を「支給人数」に改めた。
4 当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項(ひな型28頁参照) 会社法施行規則126条9号ニにおいて、会計監査人であった者が述べる事項の開示が規定されている。会社法施行規則改正前は「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」のうち「理由」のみが事業報告の開示対象とされていたため、解任についての意見が開示対象であるかどうかが明らかでなかった。
会社法施行規則の改正により、辞任理由だけでなく、「解任についての意見」についても開示の対象とされることが明確化されたため(表2参照)、そのことを記載方法の説明(ひな型28頁参照)において明らかにした。
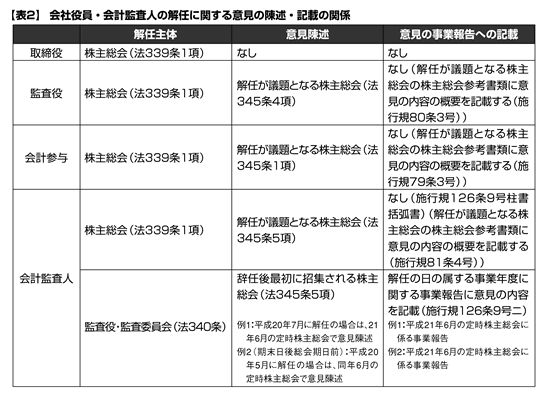
Ⅱ 附属明細書(事業報告関係)(ひな型32頁参照)
従前は、事業報告作成会社と会社役員又は支配株主以外の第三者との間の取引(間接取引)のうち、事業報告作成会社と会社役員又は支配株主との利益が相反するものについては、重要でないものを除き、附属明細書に取引の明細を記載することとなっていた(改正前会社法施行規則128条2号)。
しかし、会計慣行上は、関連当事者取引のなかに間接取引も含むものとされ、実務上もこれに従った運用がなされてきたことを踏まえ、会社計算規則の改正により、間接取引が「関連当事者取引」に含まれる旨が確認的に明記されたため(会社計算規則140条1項本文括弧書)、事業報告に係る附属明細書記載事項から計算書類の注記表の関連当事者取引の記載に移すこととなった(表3参照)。
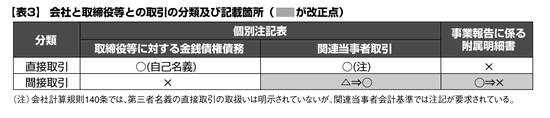 その結果、事業報告の附属明細書の記載事項は、事業報告の内容を補足する重要な事項及び公開会社における会社役員(会計参与を除く)の兼務状況の明細のみとなったので、ひな型において、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を削除した(ひな型32頁参照)。
その結果、事業報告の附属明細書の記載事項は、事業報告の内容を補足する重要な事項及び公開会社における会社役員(会計参与を除く)の兼務状況の明細のみとなったので、ひな型において、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を削除した(ひな型32頁参照)。
(おばた・よしはる)
日本経団連「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂について~(1)事業報告・附属明細書
(社)日本経済団体連合会経済第二本部経済法制グループ長 小畑良晴
はじめに
日本経団連経済法規委員会企画部会(部会長:八丁地隆日立製作所顧問)は昨年11月25日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版(以下「ひな型」という)を公表した。
旧ひな型は、2006年5月1日の会社法施行を機に、それまでの商法に基づくものを全面的に刷新し、2007年2月9日に公表したものであったが、今般、旧ひな型の公表以後に施行あるいは改正された関係法令等を踏まえて、2008年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告(計算書類及び事業報告の附属明細書については、2008年4月1日以後に開始した事業年度に関するもの)を念頭に置いて、改正事項に即して必要最小限の修正を加えた(今号30頁以下の新旧対照表参照)。
今回の改訂にあたっては、法務省民事局参事官室小松岳志局付のご協力を得て、澤口実先生・石井裕介先生はじめ森・濱田松本法律事務所の先生方、布施伸章先生・阿部光成先生はじめ監査法人トーマツの先生方のご助言・ご協力と、わが国を代表する企業実務の専門家である日本経団連経済法規委員会企画部会及び同委員会企業会計部会委員による検討結果を踏まえて作成したものである。
主な改正のポイントは以下の通りである(編注:本文の参照頁及び参照項目番号は「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」のものを表す。原文は(社)日本経済団体連合会のホームページ(http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/087.pdf)からダウンロードすることができる)。
Ⅰ 事業報告
1 会社役員に関する事項(記載の対象となる会社役員の範囲)(ひな型17頁参照) 事業報告における会社役員に関する開示規定について、改正前の会社法施行規則では、記載対象となる「会社役員」は、一律に「直前の定時総会の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む」(改正前会社法施行規則119条2号)とされており、事業報告の対象となる事業年度中に在任していた者であっても、直前の定時株主総会の終結の日までに退任した者は含まれないものとされていた。
この点について、会社役員に対する報酬等の額が適正なものであるかどうかについての情報を株主に対して提供する趣旨から、会社役員の就任及び退任の時期を問わず、ある事業年度において会社役員が受け、または受ける見込みとなった報酬等の額は、そのすべてが開示されるべき性質のものであるという考え方に基づき、この開示対象となる「会社役員」の範囲について会社法施行規則が改正された(平成20年法務省令第12号、2008年3月19日公布)。
本改正により、「会社役員」についての在任時期の限定(当該事業年度の開始の日後から直前の定時株主総会の終結の日までの間に退任した会社役員が含まれないという限定)は、報酬等に関する開示に及ばないこととなるとともに、辞任の理由又は解任の意見等の開示の対象となる会社役員についてもこの限定の対象とならず、全ての役員が開示の対象となることとなった。
その結果、事業報告における記載の対象となる会社役員の範囲については、記載事項により、在任時期の限定が付されているもの(4-1.氏名、4-2.地位及び担当、4-3.他の法人等の代表状況、4-5.財務及び会計に関する相当程度の知見、4-6.重要な兼職の状況)と、限定が付されていないもの(4-4.事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員に関する事項、4-7.取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額、4-8.各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する事項、4-9.その他会社役員に関する重要な事項)とに大きく分けることができ、それぞれにおいて取扱いが異なることになる(表1参照)。
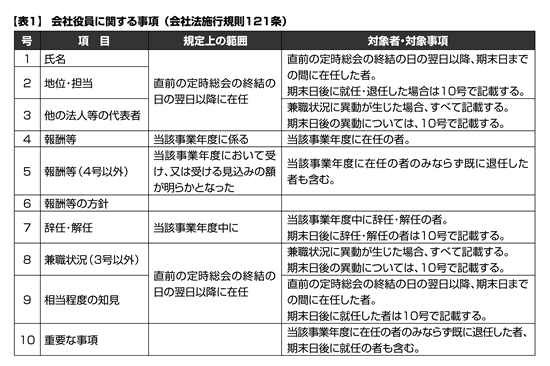 なお、社外役員に関する記載事項についても、同様の趣旨の改訂を行った(【社外役員に関する開示】(ひな型23頁)参照。)。
なお、社外役員に関する記載事項についても、同様の趣旨の改訂を行った(【社外役員に関する開示】(ひな型23頁)参照。)。社外役員に関する記載事項のうち、①他の会社の業務執行者との兼職状況、②他の株式会社の社外役員との兼任状況、③会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係、④各社外役員の主な活動状況、及び⑤責任限定契約に関する事項(ひな型4-10~4-14参照)については、対象となる社外役員につき、「直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る」との限定が付されている(会社法施行規則124条1号~5号)。
一方、⑥社外役員の報酬等の額、⑦親会社又は当該親会社の子会社の役員を兼任している場合の親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等の総額、及び記載内容についての社外役員の意見(ひな型4-15~4-17参照)については、対象となる会社役員につき、在任時期の限定が付されておらず(会社法施行規則124条6号~9号)、事業報告の対象となる事業年度において在任していない社外役員についても記載が求められる可能性があることに注意しなければならない。
2 氏名、地位及び担当、他の法人等の代表状況(ひな型18頁参照) 旧ひな型では、当該事業年度の「末日における」取締役及び監査役(委員会設置会社の場合は取締役及び執行役)の氏名、会社における地位及び担当、他の法人等の代表状況を記載することとしていたが、規定上、「末日」現在在任の者のみを書くこととは明記されておらず、現在の実務では、「期中において兼職状況に変動が生じた場合には、事業報告の趣旨から、その内容を全て記載すべき」という取扱いが有力であるとみられることから、今回の改訂では、当該事業年度の末日のみならず、当該事業年度に係るすべての状況(異動)を記載することとした。
なお、事業年度中に地位や担当が変更された場合には、原則として、事業年度末日時点のものを一覧表に記載し、期中の変動は欄外に注記することが考えられる。
3 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(ひな型20頁参照) 会社法施行規則の改正により、特に、会社役員の報酬等の記載について従前と取扱いが大きく変わり、事業報告の対象となる事業年度にまったく在任していない会社役員についての記載も必要な場合があることに注意しなければならない。
具体的には、当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等については、事業報告の対象となる事業年度においてまったく在任していなかった会社役員であっても事業報告の記載対象となることがある(会社法施行規則121条5号)。
たとえば、事業報告の対象となる事業年度の開始前に退任した会社役員に対して、当該事業年度になって退職慰労金を支給した場合において、当該退職慰労金につき、事業報告への記載が必要となる場合がある(特に、4-7.(4)退職慰労金の項目(ひな型21頁)参照)。この規定の文言上、「当該事業年度において受け……た役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等……を除く)」とされていることから、当該事業年度前の事業報告で開示(会社法施行規則121条4号)されていない部分のみが、支給年度に係る事業報告において、会社法施行規則第121条5号に関する記載対象となる。
また、会社法施行規則121条5号後段の「当該事業年度において……受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等」とは、ある事業年度に客観的に対応する報酬等であるものの、その事業年度においては金額が判明しない場合に、それが明らかになった事業年度において同号に基づき開示を行うという趣旨で設けられた規定である。この開示についても、「当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く」と規定されていることから、いったん開示されれば後年度において、開示された部分(それを超過する部分は同号に基づく開示が別途必要となる)に関する開示の重複は避けられる。なお、この規定の文言上は「事業報告の内容」とされているが、規定の趣旨からすれば、会社法施行前において、事業報告に相当する書類(営業報告書、貸借対照表等の計算書類)に、引当金等として開示してきた金額についても、重複記載は不要と解することができよう。
このほか、会社法施行規則の改正により、会社役員の報酬等の開示方法の明確化を図るため、その開示方法を①会社役員の役職ごとの報酬等の総額を開示する方法(総額開示)、②会社役員の全部につき報酬等の個別金額を開示する方法(個別開示)、③会社役員の一部につき報酬等の個別金額を示し、その他について役職ごとの報酬等の総額を開示する方法(一部個別開示)に分けて規定し、これら3つの方法のいずれかを採ることができることが明確化され(会社法施行規則121条4号)、①、③の場合には、新たに「員数」を開示しなければならないこととなった。もっとも、旧ひな型でも人数を記載することとしており、特段の変更はない。なお、ここで規定されている会社役員の報酬等の開示の目的は、株主に対して、会社役員に支給される報酬が適正であるかどうかを判断する材料を提供することにあることから、報酬等の開示における員数には、無報酬の会社役員は含まれないと解されることから、記載上の注意(ひな型22頁参照)において、そのことを改めて明記し、その点を明確にするために記載例中「人数」を「支給人数」に改めた。
4 当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項(ひな型28頁参照) 会社法施行規則126条9号ニにおいて、会計監査人であった者が述べる事項の開示が規定されている。会社法施行規則改正前は「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」のうち「理由」のみが事業報告の開示対象とされていたため、解任についての意見が開示対象であるかどうかが明らかでなかった。
会社法施行規則の改正により、辞任理由だけでなく、「解任についての意見」についても開示の対象とされることが明確化されたため(表2参照)、そのことを記載方法の説明(ひな型28頁参照)において明らかにした。
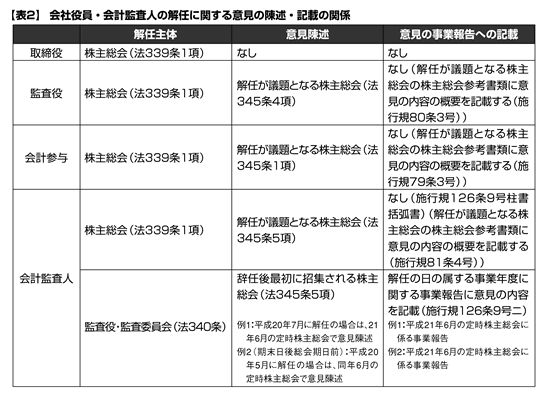
Ⅱ 附属明細書(事業報告関係)(ひな型32頁参照)
従前は、事業報告作成会社と会社役員又は支配株主以外の第三者との間の取引(間接取引)のうち、事業報告作成会社と会社役員又は支配株主との利益が相反するものについては、重要でないものを除き、附属明細書に取引の明細を記載することとなっていた(改正前会社法施行規則128条2号)。
しかし、会計慣行上は、関連当事者取引のなかに間接取引も含むものとされ、実務上もこれに従った運用がなされてきたことを踏まえ、会社計算規則の改正により、間接取引が「関連当事者取引」に含まれる旨が確認的に明記されたため(会社計算規則140条1項本文括弧書)、事業報告に係る附属明細書記載事項から計算書類の注記表の関連当事者取引の記載に移すこととなった(表3参照)。
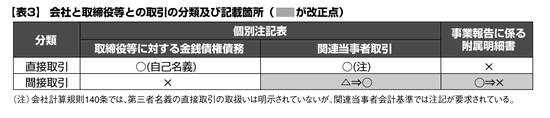 その結果、事業報告の附属明細書の記載事項は、事業報告の内容を補足する重要な事項及び公開会社における会社役員(会計参与を除く)の兼務状況の明細のみとなったので、ひな型において、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を削除した(ひな型32頁参照)。
その結果、事業報告の附属明細書の記載事項は、事業報告の内容を補足する重要な事項及び公開会社における会社役員(会計参与を除く)の兼務状況の明細のみとなったので、ひな型において、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」を削除した(ひな型32頁参照)。(おばた・よしはる)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























