解説記事2013年10月28日 【事例で学ぶ資産税】 教育資金の一括贈与に係る「残額」の税務処理について(2013年10月28日号・№521)
事例で学ぶ資産税
第5回
教育資金の一括贈与に係る「残額」の税務処理について
税理士 塩野入文雄
はじめに
平成25年4月1日から施行されている「教育資金一括贈与の特例」(措法70条の2の2:教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)については、当初、信託銀行により商品化された「教育資金贈与信託」を中心に顧客(納税者)に対して提供されていましたが、現在は、地方銀行なども、この特例に対応した商品を提供しており、施行直後に比べ、その拡がりが見られるようになってきています。
一括贈与された教育資金について、基本的には、贈与税の課税対象となる「残額」を生じないように教育資金への支払いが行われていくと考えられますが、その商品化の拡がりに伴い、次のような事例が生じることも皆無ではないと思われます〔また、次の事例は、相続税法などの条文をどのように読み込むのかとの視点からも、検討が必要と思われます〕(脚注1)。
なお、筆者が、この連載の第4回目のテーマとして寄稿した「特定居住用宅地等の特例<二世帯住宅関係>」(本誌No.506 2013.7.8 18頁)の記述内容について、今号24頁のとおりお詫びして訂正させていただくとともに、第5回目のテーマとして予定していた「老人ホーム入所等事案」については、関連する措置法通達の改正内容等を確認した後に寄稿させていただきます。
Q 次のケースにおいて、甲は、平成45年分の贈与税の申告が必要か?
① 平成25年7月に、国外に住所がある受贈者甲(孫:日本国籍あり)は、国内に住所がある贈与者乙(祖父)から教育資金1,500万円の一括贈与を受け、X銀行□支店(国内の取扱金融機関)を経由して、Y税務署長に「教育資金非課税申告書」を提出した。
② その後、乙も国外に住所を移して5年を経過した。
③ 甲は、引き続き、国外に在住していたところ、平成45年○月に甲が30歳となったため教育資金管理契約が終了した。
④ その終了日において、「残額」300万円を生じていた。
A 甲は、平成45年分の贈与税の申告を行うことが必要です。この場合、乙が生存しているか否かにかかわらず、特例税率(措法70条の2の4)を適用することができます(脚注2)。もっとも、課税価格(基礎控除額の控除後)300万円以下のケースは、本則税率と同率となっています(表1参照)。
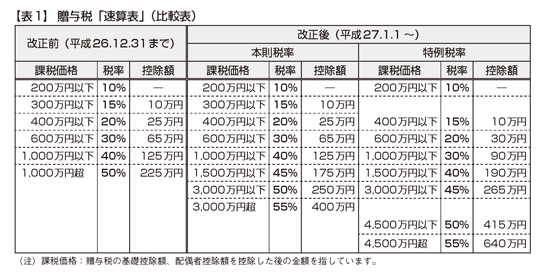
なお、「残額」が生じている場合における贈与税の処理については、後記(参考図1・2)(23頁)のとおりです。
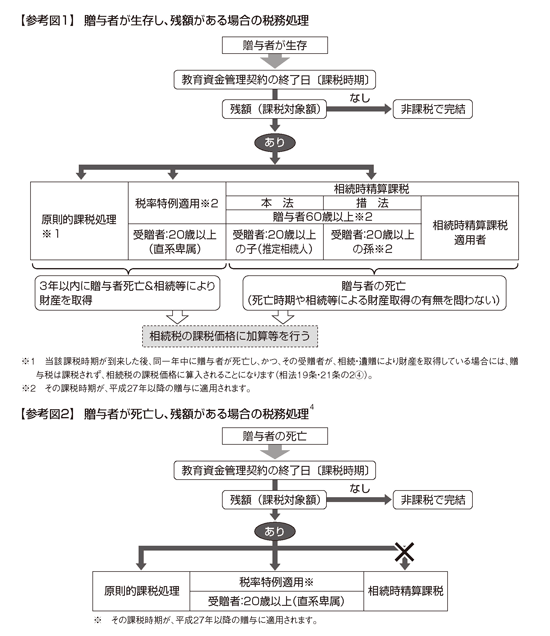
解 説
1.問題の所在 贈与税の課税範囲(納税義務の範囲)は、相続税法1条の4及び同法2条の2の規定に基づき、その判断を行います。その際、(a)贈与者の住所及び(b)受贈者の住所・国籍並びに(c)財産の所在(相法10条)の三者関係に基づき、その具体的判断を行います(表2参照)。
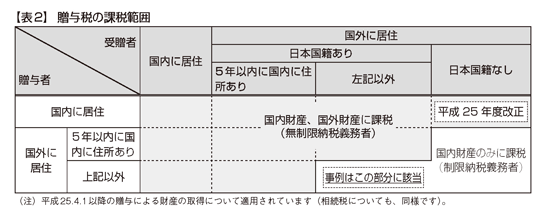
上記事例のように、その課税時期(事例においては、教育資金管理契約の終了した日(平成45年○月))において、受贈者が5年超国外に居住し、かつ、贈与者も国外に5年超居住しているケースについては、甲(受贈者)について、我が国の贈与税の課税対象となるのは「国内財産」のみに限られています。そこで、300万円の「残額」が国内財産に該当するか否かを検討する必要が生じてきます。
2.「残額」は国内財産か 措置法施行令40条の4の3第19項には、本特例の適用における「個人」(故人)の住所に関するみなし規定が、「……相続税法第1条の4の規定の適用については、……」と設けられている上に、同項一号の柱書として、「……相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。」とされていることから、課税時期における贈与税の処理についても、上記の一般的な「課税範囲」に関する判断を行うように、これらの規定を読むことができます(また、立法担当者も、当該意図の下に条文を立案したと思われます)。
上記のケースでは、「残額」が贈与税の課税時期となる教育資金管理契約の終了した日において、贈与者、受贈者ともに国外に居住していることから(5年以内に国内に住所なし)、「残額」が国内財産か否かの点を判断します。
この場合において、「残額」は、措置法70条の2の2第11項の規定に基づくものであり、いわば、税務上、創出されている非課税拠出額と教育資金支出額との『差額概念』であって、「財産」そのものではない点を看過してはならないと、筆者は考えます。この点を更に敷衍すると、相続税法基本通達11の2-1は、「法に規定する『財産』とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、……」と定め、相続税法における「財産」の意義を明らかにしていますが、「残額」そのものには、当該経済価値はなく、「財産」の範疇にあるものとはいえないと考えられます。したがって、「財産」をその規定対象としている相続税法10条に基づく「財産の所在」に関する判定を行う対象となり得ないことになります。
しかしながら、「残額」に関する税務処理を規定している措置法施行令40条の4の3第19項には、当該関連の各種のみなし規定が設けられているものの、残額を「財産」とみなす規定、あるいは、国内に所在する財産とみなす規定などは、一切、設けられていません。
このことは、措置法70条の2の2第11項において、残額を「贈与税の課税価格に算入する」としていることによるものと考えざるを得ず、〔措置法施行令40条の4の3第19項の規定との整合性等の点で難がある面は否めないものの、〕いわば、措置法70条の2の2第11項が、「残額」の課税に関する相続税法2条の2の規定に関する特則規定となっているものと捉えざるを得ないと考えられます。
したがって、上記の事例については、贈与者及び受贈者が5年超国外に住所がある場合であっても、甲は、「残額300万円」の贈与税の申告が必要としたところです。
3.まとめ 残額を「国内財産」とみなす規定が設けられていない点については、国内に所在する取扱金融機関に係るものであることから、条理等から当然に導き出される解釈等であるとすることも可能とも思われます。また、措置法施行令40条の4の3第19項二号の規定は、同項一号の柱書と相俟って、単に申告書に記載すべき贈与者(個人(故人))の住所の扱いを定めたものに留まるものではないと思われることから、立法担当者の意図は、残額が「国内財産」であるとしていることが推察されるところですが、上述したように、少なくとも残額を「財産」とする解釈には難があると、筆者は考えます。
平成25年度税制改正において、本特例の導入と同時に、相続税・贈与税の課税範囲の見直し(納税義務の見直し:相法1条の3、1条の4)が措置されたところですが、個人納税義務者レベルにおける、いわゆる「国際化」の進展も著しく、また、もとより課税範囲に係る問題は、贈与税(相続税)の課税根拠に係る問題に根源を有するものと考えられますので、その意味においても、上記の論点についての明確化が図られることが望まれます(脚注3)。
お詫びと訂正
筆者が、本連載の第4回として寄稿した「特定居住用宅地等の特例<二世帯住宅関係>」(本誌No.506 2013.7.8 18頁)において、区分所有権の目的となっている二世帯住宅に関する特定居住用宅地等(以下、「本特例」とします)の適用について、筆者の改正条文等についての誤解(誤読)がありましたので、お詫びして次のとおり訂正させていただきます。
1「Q&A<ケースB>」関連の訂正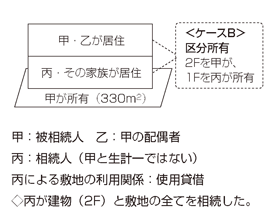
(答) 対象建物が「区分所有権」の目的となっていることから、改正前と同様に、甲が居住していた独立部分(2F)に居住していた親族(「同居親族」)が取得した当該部分に対応した敷地(地積)が本特例の適用対象となります(措法69条の4③二イ・措令41条の2⑩一)。
したがって、同居親族に該当しない丙が対象地を取得したとしても、本特例を適用することはできません。
ただし、例えば、(i)丙が、自宅等非居住の別居親族(措法69条の4③二ロ)に該当する場合には(脚注5)、被相続人の居住部分(2F)に対応する敷地(165㎡)が本特例の対象となり、また、(ii)丙が、甲の生計一の別居親族(措法69条の4③二ハ)に該当する場合には、丙の居住部分(1F)に対応する敷地(165㎡)が本特例の対象となり得ます。
なお、配偶者である乙が、その敷地の全部を取得するケースについても、2Fに対応する部分の面積(165㎡)が特例対象となってきます(ただし、乙に関する本特例の適用については、措置法69条の4第3項二号柱書きの規定に基づくものとなります)。
また、仮に、丙が甲の生計一親族であった場合、1F対応部分の敷地も含めて、その全体(330㎡)が本特例の対象となってきます(脚注6・7)。
2.「解説」関連の訂正 平成25年度税制改正により、いわゆる「二世帯住宅」に係る本特例の適用要件の緩和が措置され、平成26年以降の相続開始事案に適用されます。
改正前は、対象家屋の構造により、本特例の適用範囲に関する取扱いが区々となっていたものが、「完全分離独立型の二世帯住宅」の敷地についても、その建物の構造上の区分にかかわらず、被相続人が居住していた建物に関して、「被相続人及びその親族が居住していた部分」(一棟の建物基準)、すなわち、両者の居住の用に供されていた部分の全てが本特例の対象となることになりました。
しかしながら、区分所有権に関する新たな要件(区分所有基準)が導入されたことによって、区分所有権の目的となっている二世帯住宅(脚注8)の敷地に関しては、本特例対象となるケースが、引き続き同居親族に『限定』されていると解され(以下、「区分所有建物に係る同居親族要件存置」とします)、今後、公表される措置法通達の改正などを注視していくことが必要です。
なお、当該存置を端的に表現するならば、税制改正の大綱等によって緩和措置を講じるとされた『二世帯住宅』に関して、区分所有権の目的となっているものは、本特例の適用上、「二世帯住宅」の範疇にはないと捉えられていることになります。いうならば、例え、一般的な二世帯住宅であったとしても、区分所有権の目的となっている建物(の敷地)である以上は、「平成25年度税制改正の解説」に例示されている、いわゆる分譲マンションと同様の位置づけにあることになります(この区分所有基準の導入に関する筆者の疑問等については、既述のとおりです(前掲本誌25頁参照))。
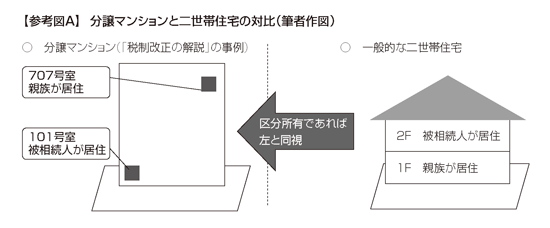
ちなみに、区分所有基準の導入の趣旨について、「平成25年度税制改正の解説」589頁(財務省)には、次のとおり説明されています。
(注)波線は、筆者が付したものです。
なお、仮に、区分所有建物に係る同居親族要件存置によらないとした場合、一棟の建物に係る措置法69条の4第3項二号の「イ」~「ハ」の適用の相互関係に関する規定が不備なものとなってしまいますので(イとロ又はイとハに重複が生じ得ることから、選択適用の可否などに関する規定の整備が必要となってきます)、この点からも、措置法69条の4第3項二号イは、当該存置による規定であることが首肯されるものと考えます。
なお、当該存置による場合、措置法施行令40条の2第10項の適用関係は、参考図B・Cのとおりです。
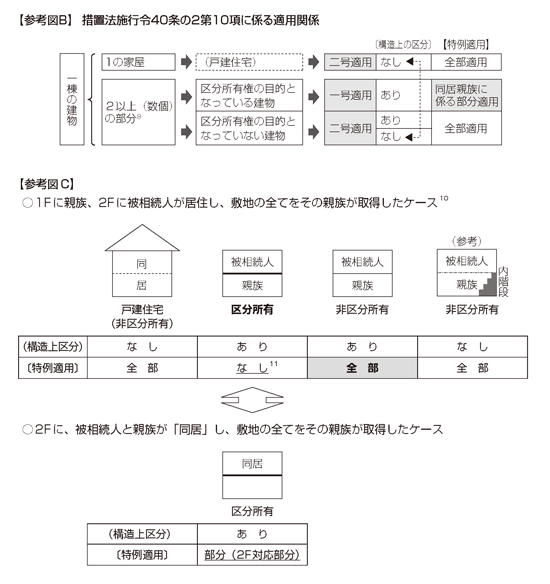
脚注
1 本稿は、塩野入・鈴木共著「Q&A 教育資金一括の贈与の特例―財産の三世代間継承に向けてⅡ―」164頁(法令出版)に加筆等を行ったものです。
2 贈与者が生存している場合には、相続時精算課税を適用することもできます。
3 一方では、この非課税制度の本質をどのように捉えるのかとの論点等(解除条件付非課税制度と捉えるか否かなど)も関連してくると、筆者は考えます。
4 その課税時期より前に、贈与者が死亡しているケースです。
5 甲の配偶者又は他の相続人が2Fに同居しておらず、また、1Fを丙又はその配偶者が所有していない(丙が、相続開始前3年以内に、国内にある丙又はその配偶者が所有する家屋(甲が居住していた家屋を除く)に居住していない)ケース。
6 配偶者による取得については、「被相続人等」(被相続人又はその生計一親族)の居住の用に供されていた宅地等が本特例の対象となっています。
7 限度面積が330㎡となるのは、平成27年以降の相続開始事案です。
8 区分所有権の目的となっていることから、完全分離独立型の二世帯住宅となります。
9 建物の構造上区分されている場合と区分されていない場合を含んでいる広い意味での「部分」を意図した用語として使用しています。
10 措置法通達69の4-21の「なお書き(後段)」(被相続人が単独居住の場合の緩和措置)に関する通達改正の有無などによる影響も生じてきます。
11 その親族について、自宅等非居住の別居親族又は生計一の別居親族の適用の可否についての検討が必要な場面もあります。
第5回
教育資金の一括贈与に係る「残額」の税務処理について
税理士 塩野入文雄
はじめに
平成25年4月1日から施行されている「教育資金一括贈与の特例」(措法70条の2の2:教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)については、当初、信託銀行により商品化された「教育資金贈与信託」を中心に顧客(納税者)に対して提供されていましたが、現在は、地方銀行なども、この特例に対応した商品を提供しており、施行直後に比べ、その拡がりが見られるようになってきています。
一括贈与された教育資金について、基本的には、贈与税の課税対象となる「残額」を生じないように教育資金への支払いが行われていくと考えられますが、その商品化の拡がりに伴い、次のような事例が生じることも皆無ではないと思われます〔また、次の事例は、相続税法などの条文をどのように読み込むのかとの視点からも、検討が必要と思われます〕(脚注1)。
なお、筆者が、この連載の第4回目のテーマとして寄稿した「特定居住用宅地等の特例<二世帯住宅関係>」(本誌No.506 2013.7.8 18頁)の記述内容について、今号24頁のとおりお詫びして訂正させていただくとともに、第5回目のテーマとして予定していた「老人ホーム入所等事案」については、関連する措置法通達の改正内容等を確認した後に寄稿させていただきます。
Q 次のケースにおいて、甲は、平成45年分の贈与税の申告が必要か?
① 平成25年7月に、国外に住所がある受贈者甲(孫:日本国籍あり)は、国内に住所がある贈与者乙(祖父)から教育資金1,500万円の一括贈与を受け、X銀行□支店(国内の取扱金融機関)を経由して、Y税務署長に「教育資金非課税申告書」を提出した。
② その後、乙も国外に住所を移して5年を経過した。
③ 甲は、引き続き、国外に在住していたところ、平成45年○月に甲が30歳となったため教育資金管理契約が終了した。
④ その終了日において、「残額」300万円を生じていた。
A 甲は、平成45年分の贈与税の申告を行うことが必要です。この場合、乙が生存しているか否かにかかわらず、特例税率(措法70条の2の4)を適用することができます(脚注2)。もっとも、課税価格(基礎控除額の控除後)300万円以下のケースは、本則税率と同率となっています(表1参照)。
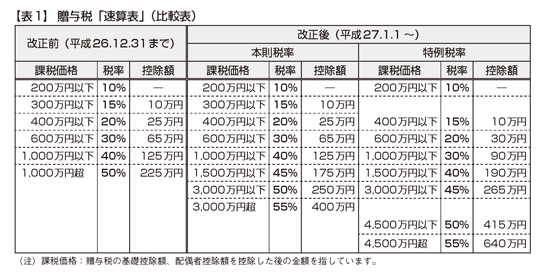
なお、「残額」が生じている場合における贈与税の処理については、後記(参考図1・2)(23頁)のとおりです。
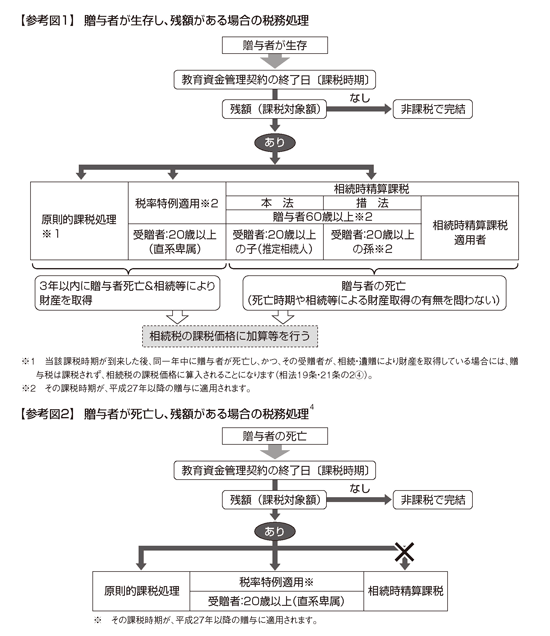
解 説
1.問題の所在 贈与税の課税範囲(納税義務の範囲)は、相続税法1条の4及び同法2条の2の規定に基づき、その判断を行います。その際、(a)贈与者の住所及び(b)受贈者の住所・国籍並びに(c)財産の所在(相法10条)の三者関係に基づき、その具体的判断を行います(表2参照)。
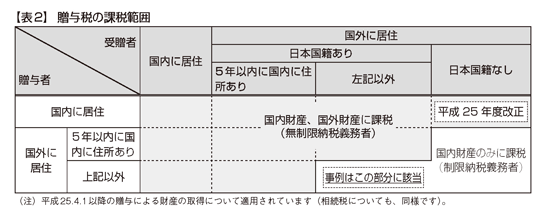
上記事例のように、その課税時期(事例においては、教育資金管理契約の終了した日(平成45年○月))において、受贈者が5年超国外に居住し、かつ、贈与者も国外に5年超居住しているケースについては、甲(受贈者)について、我が国の贈与税の課税対象となるのは「国内財産」のみに限られています。そこで、300万円の「残額」が国内財産に該当するか否かを検討する必要が生じてきます。
2.「残額」は国内財産か 措置法施行令40条の4の3第19項には、本特例の適用における「個人」(故人)の住所に関するみなし規定が、「……相続税法第1条の4の規定の適用については、……」と設けられている上に、同項一号の柱書として、「……相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。」とされていることから、課税時期における贈与税の処理についても、上記の一般的な「課税範囲」に関する判断を行うように、これらの規定を読むことができます(また、立法担当者も、当該意図の下に条文を立案したと思われます)。
上記のケースでは、「残額」が贈与税の課税時期となる教育資金管理契約の終了した日において、贈与者、受贈者ともに国外に居住していることから(5年以内に国内に住所なし)、「残額」が国内財産か否かの点を判断します。
この場合において、「残額」は、措置法70条の2の2第11項の規定に基づくものであり、いわば、税務上、創出されている非課税拠出額と教育資金支出額との『差額概念』であって、「財産」そのものではない点を看過してはならないと、筆者は考えます。この点を更に敷衍すると、相続税法基本通達11の2-1は、「法に規定する『財産』とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、……」と定め、相続税法における「財産」の意義を明らかにしていますが、「残額」そのものには、当該経済価値はなく、「財産」の範疇にあるものとはいえないと考えられます。したがって、「財産」をその規定対象としている相続税法10条に基づく「財産の所在」に関する判定を行う対象となり得ないことになります。
しかしながら、「残額」に関する税務処理を規定している措置法施行令40条の4の3第19項には、当該関連の各種のみなし規定が設けられているものの、残額を「財産」とみなす規定、あるいは、国内に所在する財産とみなす規定などは、一切、設けられていません。
このことは、措置法70条の2の2第11項において、残額を「贈与税の課税価格に算入する」としていることによるものと考えざるを得ず、〔措置法施行令40条の4の3第19項の規定との整合性等の点で難がある面は否めないものの、〕いわば、措置法70条の2の2第11項が、「残額」の課税に関する相続税法2条の2の規定に関する特則規定となっているものと捉えざるを得ないと考えられます。
したがって、上記の事例については、贈与者及び受贈者が5年超国外に住所がある場合であっても、甲は、「残額300万円」の贈与税の申告が必要としたところです。
3.まとめ 残額を「国内財産」とみなす規定が設けられていない点については、国内に所在する取扱金融機関に係るものであることから、条理等から当然に導き出される解釈等であるとすることも可能とも思われます。また、措置法施行令40条の4の3第19項二号の規定は、同項一号の柱書と相俟って、単に申告書に記載すべき贈与者(個人(故人))の住所の扱いを定めたものに留まるものではないと思われることから、立法担当者の意図は、残額が「国内財産」であるとしていることが推察されるところですが、上述したように、少なくとも残額を「財産」とする解釈には難があると、筆者は考えます。
平成25年度税制改正において、本特例の導入と同時に、相続税・贈与税の課税範囲の見直し(納税義務の見直し:相法1条の3、1条の4)が措置されたところですが、個人納税義務者レベルにおける、いわゆる「国際化」の進展も著しく、また、もとより課税範囲に係る問題は、贈与税(相続税)の課税根拠に係る問題に根源を有するものと考えられますので、その意味においても、上記の論点についての明確化が図られることが望まれます(脚注3)。
お詫びと訂正
筆者が、本連載の第4回として寄稿した「特定居住用宅地等の特例<二世帯住宅関係>」(本誌No.506 2013.7.8 18頁)において、区分所有権の目的となっている二世帯住宅に関する特定居住用宅地等(以下、「本特例」とします)の適用について、筆者の改正条文等についての誤解(誤読)がありましたので、お詫びして次のとおり訂正させていただきます。
1「Q&A<ケースB>」関連の訂正
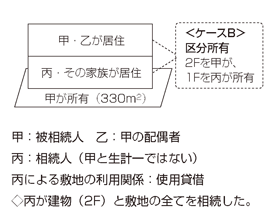
(答) 対象建物が「区分所有権」の目的となっていることから、改正前と同様に、甲が居住していた独立部分(2F)に居住していた親族(「同居親族」)が取得した当該部分に対応した敷地(地積)が本特例の適用対象となります(措法69条の4③二イ・措令41条の2⑩一)。
したがって、同居親族に該当しない丙が対象地を取得したとしても、本特例を適用することはできません。
ただし、例えば、(i)丙が、自宅等非居住の別居親族(措法69条の4③二ロ)に該当する場合には(脚注5)、被相続人の居住部分(2F)に対応する敷地(165㎡)が本特例の対象となり、また、(ii)丙が、甲の生計一の別居親族(措法69条の4③二ハ)に該当する場合には、丙の居住部分(1F)に対応する敷地(165㎡)が本特例の対象となり得ます。
なお、配偶者である乙が、その敷地の全部を取得するケースについても、2Fに対応する部分の面積(165㎡)が特例対象となってきます(ただし、乙に関する本特例の適用については、措置法69条の4第3項二号柱書きの規定に基づくものとなります)。
また、仮に、丙が甲の生計一親族であった場合、1F対応部分の敷地も含めて、その全体(330㎡)が本特例の対象となってきます(脚注6・7)。
2.「解説」関連の訂正 平成25年度税制改正により、いわゆる「二世帯住宅」に係る本特例の適用要件の緩和が措置され、平成26年以降の相続開始事案に適用されます。
改正前は、対象家屋の構造により、本特例の適用範囲に関する取扱いが区々となっていたものが、「完全分離独立型の二世帯住宅」の敷地についても、その建物の構造上の区分にかかわらず、被相続人が居住していた建物に関して、「被相続人及びその親族が居住していた部分」(一棟の建物基準)、すなわち、両者の居住の用に供されていた部分の全てが本特例の対象となることになりました。
しかしながら、区分所有権に関する新たな要件(区分所有基準)が導入されたことによって、区分所有権の目的となっている二世帯住宅(脚注8)の敷地に関しては、本特例対象となるケースが、引き続き同居親族に『限定』されていると解され(以下、「区分所有建物に係る同居親族要件存置」とします)、今後、公表される措置法通達の改正などを注視していくことが必要です。
なお、当該存置を端的に表現するならば、税制改正の大綱等によって緩和措置を講じるとされた『二世帯住宅』に関して、区分所有権の目的となっているものは、本特例の適用上、「二世帯住宅」の範疇にはないと捉えられていることになります。いうならば、例え、一般的な二世帯住宅であったとしても、区分所有権の目的となっている建物(の敷地)である以上は、「平成25年度税制改正の解説」に例示されている、いわゆる分譲マンションと同様の位置づけにあることになります(この区分所有基準の導入に関する筆者の疑問等については、既述のとおりです(前掲本誌25頁参照))。
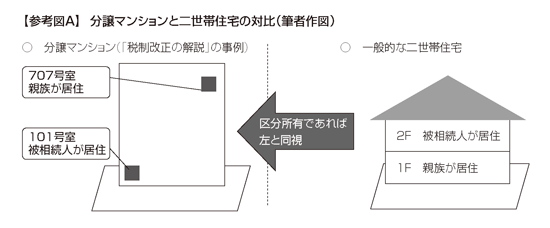
ちなみに、区分所有基準の導入の趣旨について、「平成25年度税制改正の解説」589頁(財務省)には、次のとおり説明されています。
| また、上記の「一棟の建物」には、いわゆる分譲マンションのように区分所有され、複数の所有権の目的となっているものもありえます。しかし、例えば同じ分譲マンションの101に被相続人、707に親族が居住していた場合には、それぞれの専有部分が別々に取引される権利であり、いわゆる「二世帯住宅」とは同視できないと考えられるため、上記の「一定の部分」については、専有部分ごとに判断することとされています。 |
なお、仮に、区分所有建物に係る同居親族要件存置によらないとした場合、一棟の建物に係る措置法69条の4第3項二号の「イ」~「ハ」の適用の相互関係に関する規定が不備なものとなってしまいますので(イとロ又はイとハに重複が生じ得ることから、選択適用の可否などに関する規定の整備が必要となってきます)、この点からも、措置法69条の4第3項二号イは、当該存置による規定であることが首肯されるものと考えます。
なお、当該存置による場合、措置法施行令40条の2第10項の適用関係は、参考図B・Cのとおりです。
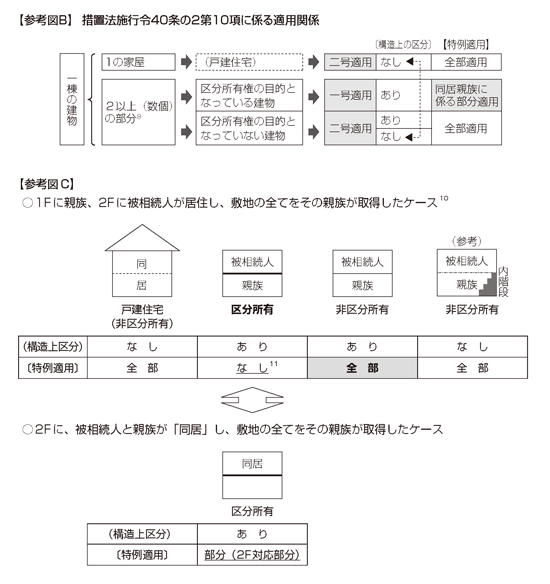
脚注
1 本稿は、塩野入・鈴木共著「Q&A 教育資金一括の贈与の特例―財産の三世代間継承に向けてⅡ―」164頁(法令出版)に加筆等を行ったものです。
2 贈与者が生存している場合には、相続時精算課税を適用することもできます。
3 一方では、この非課税制度の本質をどのように捉えるのかとの論点等(解除条件付非課税制度と捉えるか否かなど)も関連してくると、筆者は考えます。
4 その課税時期より前に、贈与者が死亡しているケースです。
5 甲の配偶者又は他の相続人が2Fに同居しておらず、また、1Fを丙又はその配偶者が所有していない(丙が、相続開始前3年以内に、国内にある丙又はその配偶者が所有する家屋(甲が居住していた家屋を除く)に居住していない)ケース。
6 配偶者による取得については、「被相続人等」(被相続人又はその生計一親族)の居住の用に供されていた宅地等が本特例の対象となっています。
7 限度面積が330㎡となるのは、平成27年以降の相続開始事案です。
8 区分所有権の目的となっていることから、完全分離独立型の二世帯住宅となります。
9 建物の構造上区分されている場合と区分されていない場合を含んでいる広い意味での「部分」を意図した用語として使用しています。
10 措置法通達69の4-21の「なお書き(後段)」(被相続人が単独居住の場合の緩和措置)に関する通達改正の有無などによる影響も生じてきます。
11 その親族について、自宅等非居住の別居親族又は生計一の別居親族の適用の可否についての検討が必要な場面もあります。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























