解説記事2014年01月13日 【税制改正解説】 消費税額の計算方法(端数処理の特例)について(2014年1月13日号・№530)
税制改正解説
消費税額の計算方法(端数処理の特例)について
上竹良彦
はじめに
昨年10月1日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」においては、経済再生を進めながら財政再建との両立を図っていくことの重要性並びに増大する社会保障の持続性と安心の確保及び我が国の信認維持といった社会保障と税の一体改革の趣旨を踏まえつつ、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第18条等の規定に基づき、消費税(国・地方)については、平成26年4月1日に5%から8%に引き上げることが確認されたところである。
また、昨年6月12日に公布された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「転嫁対策特別措置法」という。)が同年10月1日に施行されている。
各事業者においては、本年4月1日に実施される消費税率及び地方消費税率の引上げに向けて様々な準備・対応に追われているのではないだろうか。
本稿では、本年4月1日以降における消費税額の計算方法について改めて確認いただく観点から、消費税額の原則的な計算方法及び消費税の端数処理の特例について概観したい。
なお、本稿においては、本年4月1日以降の税率を前提に記述すること、及び文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることを念のため申し添える。
Ⅰ 基本的な考え方
消費税は、事業者の売上げに対して課されるが、課された消費税額及び地方消費税額に相当する額(以下単に「消費税額相当額」という。)は、コストとしてその取引に係る資産又は役務の価格に織り込まれ、最終的には消費者に転嫁されることが予定される間接税であるとされている。しかし、消費税法上の納税義務者は事業者である。すなわち、その取引に際して、事業者が消費者等から受領する消費税額相当額は、資産又は役務の価格の一部を構成するものに過ぎないのである。
消費税法においては、このような基本的考え方に基づき、事業者の価格表示、転嫁の程度や経理処理の方法如何にかかわらず、各課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき受領すべき金額(消費税額相当額込みの課税売上高)の合計額に108分の100を乗じて課税標準額を算出し、当該課税標準額に税率を乗じて課税売上に係る消費税額を計算することを原則としている。
(注)租税法(金子宏:弘文堂)では、「一般には、法律上の納税義務者と担税者とが一致することを立法者が予定している租税を直接税と呼び、税負担の転嫁が行われ両者が一致しないことを立法者が予定している租税を間接税と呼んでいる。(略)しかし、転嫁の有無は、必ずしも租税の種類によって一様ではなく、その時の経済的諸条件によって左右されるから、転嫁の有無を区別の基準とするのは正確であるとはいいがたい。」とされている。
Ⅱ 消費税額の原則的な計算方法について
課税売上に係る消費税額は、課税標準額に税率を乗じて算出することになるが、前述のとおり、事業者の経理処理方法等の如何にかかわらず、各課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき受領すべき金額(消費税額相当額込みの課税売上高)の合計額に108分の100を乗じて算出した金額が課税標準額となり、当該課税標準額に税率を乗じて課税標準額に対する消費税額を計算することになる。
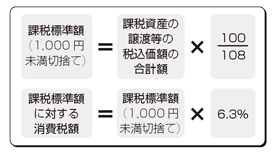
Ⅲ 消費税の端数処理の特例について
【特例1】内税レジ方式における特例(全事業者向け)
〔対象〕 税込価格を基礎として代金決済を行う取引を対象としている。適用事業者や価格表示の方法に制限はない。
〔具体的な取扱い〕 代金決済の都度、レシート、領収書、請求書等において、「税込価格の合計額」と「税込価格の合計額に含まれる消費税額相当額の1円未満の端数を処理した後の金額」とを明示しているときは、その端数処理後の消費税額相当額の累計額を基礎として、その課税期間における課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる。
本特例における消費税額相当額とは、レシート等に明示した「税込価格の合計額」に108分の8を乗じて算出した額をいう。
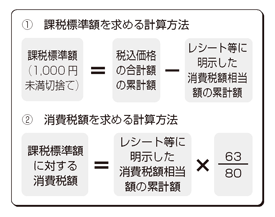
〔経緯及び適用関係〕 この特例は、平成16年4月の総額表示義務の施行に併せて、当分の間の措置として設けられた税額計算の特例であるが、現時点において具体的な適用期限の定めはないことから、本年4月1日以後に行われる資産の譲渡等にも引き続き適用可能である。
〔根拠規定〕 平成15年財務省令第92号(以下「15年省令」という。)附則第2条第3項
〔適用に当たっての注意点〕 ① 後述する【特例2】のような価格表示要件(総額表示を行っていること)はない。したがって、消費者や取引先との関係を考えると現実的ではないかもしれないが、税抜価格のみを表示しながらレジ計算は「税込価格」を基に行うというケースであっても本特例措置の適用は認められる。
② この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
③ レシートや請求書等において、「税込価格の合計額」と「その合計額に含まれる1円未満の端数を処理(切り捨て、切り上げ、四捨五入)した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
【特例2】外税レジ方式における特例A(消費者取引向け)
〔対象〕 消費税法第63条(価格の表示)に規定する総額表示義務の適用を受ける取引を対象とした端数処理の特例である。不特定かつ多数の者を取引相手とする取引、すなわち一般的には対消費者取引がその対象となる。
なお、本特例の適用を受けるためには、総額表示義務を満たしていることが必要となる。
〔具体的な取扱い〕 代金決済の都度、レシート、領収書、請求書等において、「税抜価格の合計額」と「これに課されるべき消費税額相当額の1円未満の端数を処理した後の金額」とを明示しているときは、その端数処理後の消費税額相当額の累計額を基礎として、その課税期間における課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる。
本特例における消費税額相当額とは、レシート等に明示した「税抜価格の合計額」に税率(8%)を乗じて算出した額をいう。
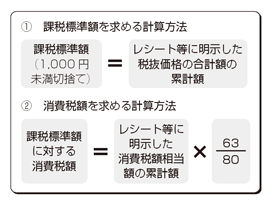
〔根拠規定〕 15年省令附則第2条第4項(平成25年財務省令37号による15年省令の改正により措置)
〔経緯及び適用関係〕 総額表示を行っていながら在庫管理に関する特殊な商慣行の存在等を理由に“外税レジ方式”を採らざるを得ない事業者の実態等を踏まえ、平成25年度税制改正において措置された特例であり、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用することとされている。なお、適用期限については、「当分の間」とされているが、現時点において具体的な適用期限の定めはない。
(注)この特例は、平成19年3月末に適用期限を迎えていた端数処理の特例(改正前の15年省令附則第2条第4項の措置)を平成25年財務省令第37号によって改正し、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から当分の間の措置として新たに設けられたものである。
〔適用に当たっての注意点〕 ① 総額表示義務の適用を受ける取引が対象となる(総額表示が適用要件)。
② この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
③ レシートや請求書等において、「税抜価格の合計額」と「1円未満の端数を処理した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
【特例3】特例2の特例(転嫁対策特別措置法10条1項の適用を受ける取引を対象とした特例)
〔対象〕 消費税法第63条に規定する総額表示義務の適用を受ける取引を行う事業者は、平成26年4月1日から前述の【特例2】の適用対象となるが、そうした事業者が転嫁対策特別措置法第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用を受ける場合(税込価格を表示しない場合)であっても、端数処理の特例の適用が妨げられないようにするために設けられた特例である。
すなわち、一定の誤認防止措置(表示価格がその時の税率に基づく税込価格であると誤認させないための措置)を講じて税抜価格のみを表示しているときは、税込価格を表示しているものとして【特例2】の適用を受けることができる。
〔具体的な取扱い〕 課税売上に係る消費税額の計算方法は、【特例2】と同様なので省略する。
〔根拠規定〕 15年省令附則第2条第5項(平成25年財務省令45号による15年省令附則の改正により措置)
〔経緯及び適用関係〕 平成25年6月12日に公布された「転嫁対策特別措置法」においては、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための特別措置の一つとして、消費税の総額表示義務に関する特例措置が設けられた。
具体的には、同法第10条第1項において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない」とされている。これにより、同法の施行日である平成25年10月1日から同法の期限である平成29年3月31日までの間に行う価格表示(消費税法第63条の規定の適用を受ける価格表示に限る。)については、一定の要件を満たす場合に限り、総額表示義務が解除される。
他方、平成25年度税制改正で措置された上記【特例2】は、総額表示義務の履行が適用要件とされているため、転嫁対策特別措置法第10条第1項の適用を受けると端数処理の特例が適用できないという事態が生じてしまう。こうした事態は、端数処理の特例の適用を受けるために、同法第10条第1項の適用を見合わせるといった判断にもつながりかねないことから、同法第10条第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る消費税額の計算については、総額表示義務を履行しているものとして【特例2】の適用を認めることとする省令改正が行われたところである(消費税法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成25年6月28日公布。財務省令第45号)。
この特例は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用され、転嫁対策特別措置法の期限である平成29年3月31日がその適用期限となる。
〔適用に当たっての注意点〕 ① 総額表示義務の適用を受ける取引が対象となるが、転嫁対策特別措置法第10条第1項に規定する要件を満たしていることが必要(一定の誤認防止措置を講じた上で“税抜価格”あるいは“旧税率における税込価格”を表示している。)。
② 転嫁対策特別措置法の適用期限(平成29年3月31日)後に行う取引には適用できない。
③ この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
④ レシートや請求書等において「税抜価格の合計額」と「1円未満の端数を処理した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
【特例4】外税レジ方式における特例B(事業者間取引向け)
〔対象〕 消費税法第63条に規定する総額表示義務の適用を受けない取引(一般的には事業者間取引)を対象とした端数処理の特例である。対消費者取引であっても予め価格を表示していない場合は総額表示義務の対象外となるため、本特例の適用対象となる。
〔具体的な取扱い〕 代金決済の都度、レシート、領収書、請求書等において、「税抜価格の合計額」と「これに課されるべき消費税額相当額の1円未満の端数を処理した後の金額」とを明示しているときは、その端数処理後の消費税額相当額の累計額を基礎としてその課税期間における課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる。
本特例における消費税額相当額とは、レシート等に明示した「税抜価格の合計額」に税率(8%)を乗じて算出した額をいう。
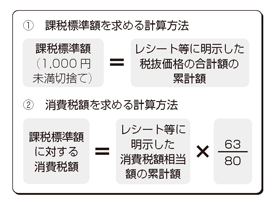
〔根拠規定〕 15年省令附則第2条第2項(旧消費税法施行規則第22条第1項)
〔経緯及び適用期限〕 この特例は、平成16年4月の総額表示義務の施行の際に廃止された旧端数処理の特例(旧消規22①)について、平成16年4月以降も当分の間その適用を認めることとしたものである。
すなわち、現時点において具体的な適用期限の定めはないことから、本年4月1日以後に行われる資産の譲渡等にも引き続き適用可能である。
〔適用に当たっての注意点〕 ① 総額表示義務の対象となる取引には適用されない。すなわち、一般的には事業者間取引を対象とした措置であるが、対消費者取引であっても予め価格を表示せずに行う取引(総額表示義務の対象外)であれば、本措置の適用を受けることができる。
② この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
③ レシートや請求書等において「税抜価格の合計額」と「1円未満の端数を処理した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
Ⅳま と め
Ⅲで示した各端数処理の特例について、価格表示及び採用するレジ計算方式との関係から整理すると上記の図表1のとおりである。
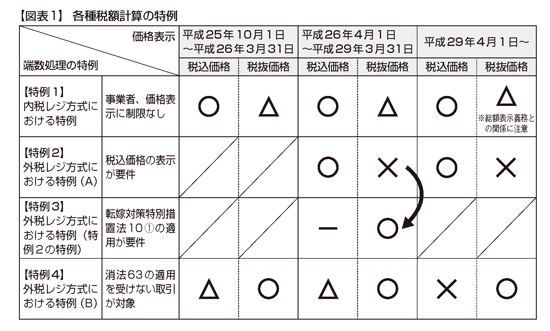
上記の表中、「税込価格」又は「税抜価格(税込価格を表示していない)」を表示している事業者における適用可能な端数処理の特例を「○」又は「△」で表示しているが、「△」は、「商品やカタログなどに表示されている価格(税抜価格)」と「レシート等に表示される価格(税込価格)」とが異なるため、消費者との関係で注意を要する組み合わせである。
なお、【特例2】は、「税込価格」の欄に「○」が付されているため違和感を持つかもしれないが、これは同特例が、税込価格表示を適用要件としているためである。実際、“外税レジ方式”に対応するためには、「税抜価格」が併せて表示されると考えられる。
これら端数処理の特例の仕組みや適用要件等については、前述のとおりであるが、改めて注意すべき点を整理する。
(1)【特例1】(内税レジ方式における特例)は、価格表示について要件が設けられていないため、現在、「税込価格」を表示し、“内税レジ方式”を採っている事業者が、転嫁対策特別措置法第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用により「税抜価格のみの表示」とした場合であっても、本特例の適用は引き続き可能である。
しかし、その場合には、「商品等に表示される価格(税抜価格)」と「レシート等に表示される価格(税込価格)」とが異なるため、消費者等への丁寧な説明等が不可欠になると考える。
(2)【特例2】(外税レジ方式における端数処理の特例A)は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されるが、現時点において適用期限は定められていない。また、税込価格を表示していることがその適用要件とされている。
なお、本特例の適用に当たっては、『「レシート等に明示する税抜価格の合計額」+「税抜価格の合計額」×税率』と『表示する税込価格の合計額』とが一致しないケースが生じるため注意を要する。そうした問題を避けるためには、「税込価格」を設定する際に工夫が必要となる(図表2参照)。
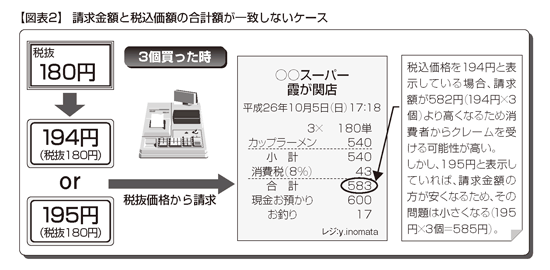
○【特例3】(特例2の特例)は、転嫁対策特別措置法第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用を受ける取引を対象として、【特例2】の適用を認めるものである。その適用は平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等からであり、適用期限は平成29年3月31日(転嫁対策特別措置法の適用期限)とされている。
したがって、本特例の適用を受ける事業者にあっては、平成29年4月以降に向けた準備を進めておくことが必要となる。
○【特例4】(外税レジ方式における特例B)は、総額表示義務の適用対象外の取引、すなわち一般的には、事業者のみを相手に商売を行っている者が対象となるのであるが、対消費者取引であっても予め価格を表示せずに行っている取引については、本特例の適用を受けることができる。なお、『業務用卸』といった業態は、通常、不特定多数の者に(相手が事業者でも消費者でも)商品を販売しているため注意を要する(本特例の対象外となる可能性が高い。)
おわりに
税率8%への引上げまで2か月余りとなるが、事業者においては、価格転嫁や新税率を前提とした事業戦略の構築などに意識が向きがちだと思われる。しかし、本稿において概観した端数処理の特例は、取引の都度発行するレシート、領収書や請求書等の記載内容によってその適用関係が決まってしまう面があることから、この機会に今一度点検しておく必要がある。
特に、取引回数の多い小売業やサービス業においては、納税額への影響も無視できない額になるため、そうした顧問先を抱える税理士等においても注意を要すると考える。
消費税額の計算方法(端数処理の特例)について
上竹良彦
はじめに
昨年10月1日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」においては、経済再生を進めながら財政再建との両立を図っていくことの重要性並びに増大する社会保障の持続性と安心の確保及び我が国の信認維持といった社会保障と税の一体改革の趣旨を踏まえつつ、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第18条等の規定に基づき、消費税(国・地方)については、平成26年4月1日に5%から8%に引き上げることが確認されたところである。
また、昨年6月12日に公布された「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「転嫁対策特別措置法」という。)が同年10月1日に施行されている。
各事業者においては、本年4月1日に実施される消費税率及び地方消費税率の引上げに向けて様々な準備・対応に追われているのではないだろうか。
本稿では、本年4月1日以降における消費税額の計算方法について改めて確認いただく観点から、消費税額の原則的な計算方法及び消費税の端数処理の特例について概観したい。
なお、本稿においては、本年4月1日以降の税率を前提に記述すること、及び文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることを念のため申し添える。
Ⅰ 基本的な考え方
消費税は、事業者の売上げに対して課されるが、課された消費税額及び地方消費税額に相当する額(以下単に「消費税額相当額」という。)は、コストとしてその取引に係る資産又は役務の価格に織り込まれ、最終的には消費者に転嫁されることが予定される間接税であるとされている。しかし、消費税法上の納税義務者は事業者である。すなわち、その取引に際して、事業者が消費者等から受領する消費税額相当額は、資産又は役務の価格の一部を構成するものに過ぎないのである。
消費税法においては、このような基本的考え方に基づき、事業者の価格表示、転嫁の程度や経理処理の方法如何にかかわらず、各課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき受領すべき金額(消費税額相当額込みの課税売上高)の合計額に108分の100を乗じて課税標準額を算出し、当該課税標準額に税率を乗じて課税売上に係る消費税額を計算することを原則としている。
(注)租税法(金子宏:弘文堂)では、「一般には、法律上の納税義務者と担税者とが一致することを立法者が予定している租税を直接税と呼び、税負担の転嫁が行われ両者が一致しないことを立法者が予定している租税を間接税と呼んでいる。(略)しかし、転嫁の有無は、必ずしも租税の種類によって一様ではなく、その時の経済的諸条件によって左右されるから、転嫁の有無を区別の基準とするのは正確であるとはいいがたい。」とされている。
Ⅱ 消費税額の原則的な計算方法について
課税売上に係る消費税額は、課税標準額に税率を乗じて算出することになるが、前述のとおり、事業者の経理処理方法等の如何にかかわらず、各課税期間中に行った課税資産の譲渡等につき受領すべき金額(消費税額相当額込みの課税売上高)の合計額に108分の100を乗じて算出した金額が課税標準額となり、当該課税標準額に税率を乗じて課税標準額に対する消費税額を計算することになる。
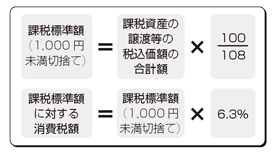
Ⅲ 消費税の端数処理の特例について
【特例1】内税レジ方式における特例(全事業者向け)
〔対象〕 税込価格を基礎として代金決済を行う取引を対象としている。適用事業者や価格表示の方法に制限はない。
〔具体的な取扱い〕 代金決済の都度、レシート、領収書、請求書等において、「税込価格の合計額」と「税込価格の合計額に含まれる消費税額相当額の1円未満の端数を処理した後の金額」とを明示しているときは、その端数処理後の消費税額相当額の累計額を基礎として、その課税期間における課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる。
本特例における消費税額相当額とは、レシート等に明示した「税込価格の合計額」に108分の8を乗じて算出した額をいう。
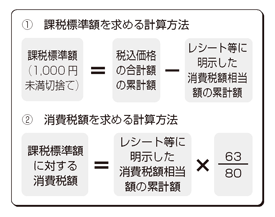
〔経緯及び適用関係〕 この特例は、平成16年4月の総額表示義務の施行に併せて、当分の間の措置として設けられた税額計算の特例であるが、現時点において具体的な適用期限の定めはないことから、本年4月1日以後に行われる資産の譲渡等にも引き続き適用可能である。
〔根拠規定〕 平成15年財務省令第92号(以下「15年省令」という。)附則第2条第3項
〔適用に当たっての注意点〕 ① 後述する【特例2】のような価格表示要件(総額表示を行っていること)はない。したがって、消費者や取引先との関係を考えると現実的ではないかもしれないが、税抜価格のみを表示しながらレジ計算は「税込価格」を基に行うというケースであっても本特例措置の適用は認められる。
② この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
③ レシートや請求書等において、「税込価格の合計額」と「その合計額に含まれる1円未満の端数を処理(切り捨て、切り上げ、四捨五入)した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
【特例2】外税レジ方式における特例A(消費者取引向け)
〔対象〕 消費税法第63条(価格の表示)に規定する総額表示義務の適用を受ける取引を対象とした端数処理の特例である。不特定かつ多数の者を取引相手とする取引、すなわち一般的には対消費者取引がその対象となる。
なお、本特例の適用を受けるためには、総額表示義務を満たしていることが必要となる。
〔具体的な取扱い〕 代金決済の都度、レシート、領収書、請求書等において、「税抜価格の合計額」と「これに課されるべき消費税額相当額の1円未満の端数を処理した後の金額」とを明示しているときは、その端数処理後の消費税額相当額の累計額を基礎として、その課税期間における課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる。
本特例における消費税額相当額とは、レシート等に明示した「税抜価格の合計額」に税率(8%)を乗じて算出した額をいう。
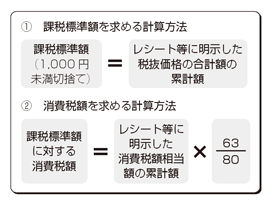
〔根拠規定〕 15年省令附則第2条第4項(平成25年財務省令37号による15年省令の改正により措置)
〔経緯及び適用関係〕 総額表示を行っていながら在庫管理に関する特殊な商慣行の存在等を理由に“外税レジ方式”を採らざるを得ない事業者の実態等を踏まえ、平成25年度税制改正において措置された特例であり、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用することとされている。なお、適用期限については、「当分の間」とされているが、現時点において具体的な適用期限の定めはない。
(注)この特例は、平成19年3月末に適用期限を迎えていた端数処理の特例(改正前の15年省令附則第2条第4項の措置)を平成25年財務省令第37号によって改正し、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から当分の間の措置として新たに設けられたものである。
〔適用に当たっての注意点〕 ① 総額表示義務の適用を受ける取引が対象となる(総額表示が適用要件)。
② この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
③ レシートや請求書等において、「税抜価格の合計額」と「1円未満の端数を処理した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
【特例3】特例2の特例(転嫁対策特別措置法10条1項の適用を受ける取引を対象とした特例)
〔対象〕 消費税法第63条に規定する総額表示義務の適用を受ける取引を行う事業者は、平成26年4月1日から前述の【特例2】の適用対象となるが、そうした事業者が転嫁対策特別措置法第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用を受ける場合(税込価格を表示しない場合)であっても、端数処理の特例の適用が妨げられないようにするために設けられた特例である。
すなわち、一定の誤認防止措置(表示価格がその時の税率に基づく税込価格であると誤認させないための措置)を講じて税抜価格のみを表示しているときは、税込価格を表示しているものとして【特例2】の適用を受けることができる。
〔具体的な取扱い〕 課税売上に係る消費税額の計算方法は、【特例2】と同様なので省略する。
〔根拠規定〕 15年省令附則第2条第5項(平成25年財務省令45号による15年省令附則の改正により措置)
〔経緯及び適用関係〕 平成25年6月12日に公布された「転嫁対策特別措置法」においては、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するための特別措置の一つとして、消費税の総額表示義務に関する特例措置が設けられた。
具体的には、同法第10条第1項において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要しない」とされている。これにより、同法の施行日である平成25年10月1日から同法の期限である平成29年3月31日までの間に行う価格表示(消費税法第63条の規定の適用を受ける価格表示に限る。)については、一定の要件を満たす場合に限り、総額表示義務が解除される。
他方、平成25年度税制改正で措置された上記【特例2】は、総額表示義務の履行が適用要件とされているため、転嫁対策特別措置法第10条第1項の適用を受けると端数処理の特例が適用できないという事態が生じてしまう。こうした事態は、端数処理の特例の適用を受けるために、同法第10条第1項の適用を見合わせるといった判断にもつながりかねないことから、同法第10条第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る消費税額の計算については、総額表示義務を履行しているものとして【特例2】の適用を認めることとする省令改正が行われたところである(消費税法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成25年6月28日公布。財務省令第45号)。
この特例は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用され、転嫁対策特別措置法の期限である平成29年3月31日がその適用期限となる。
〔適用に当たっての注意点〕 ① 総額表示義務の適用を受ける取引が対象となるが、転嫁対策特別措置法第10条第1項に規定する要件を満たしていることが必要(一定の誤認防止措置を講じた上で“税抜価格”あるいは“旧税率における税込価格”を表示している。)。
② 転嫁対策特別措置法の適用期限(平成29年3月31日)後に行う取引には適用できない。
③ この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
④ レシートや請求書等において「税抜価格の合計額」と「1円未満の端数を処理した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
【特例4】外税レジ方式における特例B(事業者間取引向け)
〔対象〕 消費税法第63条に規定する総額表示義務の適用を受けない取引(一般的には事業者間取引)を対象とした端数処理の特例である。対消費者取引であっても予め価格を表示していない場合は総額表示義務の対象外となるため、本特例の適用対象となる。
〔具体的な取扱い〕 代金決済の都度、レシート、領収書、請求書等において、「税抜価格の合計額」と「これに課されるべき消費税額相当額の1円未満の端数を処理した後の金額」とを明示しているときは、その端数処理後の消費税額相当額の累計額を基礎としてその課税期間における課税標準額に対する消費税額の計算を行うことができる。
本特例における消費税額相当額とは、レシート等に明示した「税抜価格の合計額」に税率(8%)を乗じて算出した額をいう。
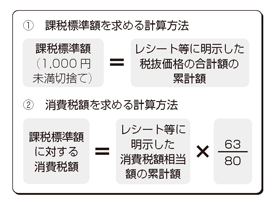
〔根拠規定〕 15年省令附則第2条第2項(旧消費税法施行規則第22条第1項)
〔経緯及び適用期限〕 この特例は、平成16年4月の総額表示義務の施行の際に廃止された旧端数処理の特例(旧消規22①)について、平成16年4月以降も当分の間その適用を認めることとしたものである。
すなわち、現時点において具体的な適用期限の定めはないことから、本年4月1日以後に行われる資産の譲渡等にも引き続き適用可能である。
〔適用に当たっての注意点〕 ① 総額表示義務の対象となる取引には適用されない。すなわち、一般的には事業者間取引を対象とした措置であるが、対消費者取引であっても予め価格を表示せずに行う取引(総額表示義務の対象外)であれば、本措置の適用を受けることができる。
② この端数処理の特例は、一領収単位ごと(例えば一つのレシートごと)に認められるものであり、個々の商品やサービスごとに消費税額相当額を計算して1円未満の端数処理を行ったとしても認められない。
③ レシートや請求書等において「税抜価格の合計額」と「1円未満の端数を処理した後の消費税額相当額」とを区分して明示している必要がある。
Ⅳま と め
Ⅲで示した各端数処理の特例について、価格表示及び採用するレジ計算方式との関係から整理すると上記の図表1のとおりである。
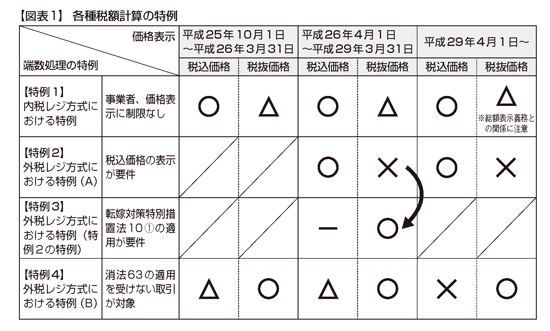
上記の表中、「税込価格」又は「税抜価格(税込価格を表示していない)」を表示している事業者における適用可能な端数処理の特例を「○」又は「△」で表示しているが、「△」は、「商品やカタログなどに表示されている価格(税抜価格)」と「レシート等に表示される価格(税込価格)」とが異なるため、消費者との関係で注意を要する組み合わせである。
なお、【特例2】は、「税込価格」の欄に「○」が付されているため違和感を持つかもしれないが、これは同特例が、税込価格表示を適用要件としているためである。実際、“外税レジ方式”に対応するためには、「税抜価格」が併せて表示されると考えられる。
これら端数処理の特例の仕組みや適用要件等については、前述のとおりであるが、改めて注意すべき点を整理する。
(1)【特例1】(内税レジ方式における特例)は、価格表示について要件が設けられていないため、現在、「税込価格」を表示し、“内税レジ方式”を採っている事業者が、転嫁対策特別措置法第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用により「税抜価格のみの表示」とした場合であっても、本特例の適用は引き続き可能である。
しかし、その場合には、「商品等に表示される価格(税抜価格)」と「レシート等に表示される価格(税込価格)」とが異なるため、消費者等への丁寧な説明等が不可欠になると考える。
(2)【特例2】(外税レジ方式における端数処理の特例A)は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されるが、現時点において適用期限は定められていない。また、税込価格を表示していることがその適用要件とされている。
なお、本特例の適用に当たっては、『「レシート等に明示する税抜価格の合計額」+「税抜価格の合計額」×税率』と『表示する税込価格の合計額』とが一致しないケースが生じるため注意を要する。そうした問題を避けるためには、「税込価格」を設定する際に工夫が必要となる(図表2参照)。
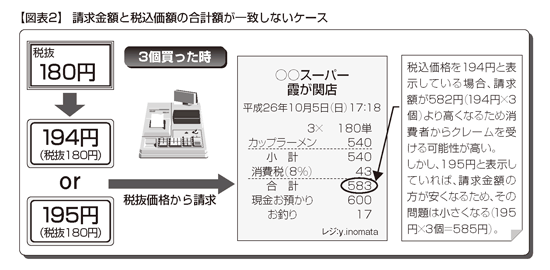
○【特例3】(特例2の特例)は、転嫁対策特別措置法第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の適用を受ける取引を対象として、【特例2】の適用を認めるものである。その適用は平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等からであり、適用期限は平成29年3月31日(転嫁対策特別措置法の適用期限)とされている。
したがって、本特例の適用を受ける事業者にあっては、平成29年4月以降に向けた準備を進めておくことが必要となる。
○【特例4】(外税レジ方式における特例B)は、総額表示義務の適用対象外の取引、すなわち一般的には、事業者のみを相手に商売を行っている者が対象となるのであるが、対消費者取引であっても予め価格を表示せずに行っている取引については、本特例の適用を受けることができる。なお、『業務用卸』といった業態は、通常、不特定多数の者に(相手が事業者でも消費者でも)商品を販売しているため注意を要する(本特例の対象外となる可能性が高い。)
おわりに
税率8%への引上げまで2か月余りとなるが、事業者においては、価格転嫁や新税率を前提とした事業戦略の構築などに意識が向きがちだと思われる。しかし、本稿において概観した端数処理の特例は、取引の都度発行するレシート、領収書や請求書等の記載内容によってその適用関係が決まってしまう面があることから、この機会に今一度点検しておく必要がある。
特に、取引回数の多い小売業やサービス業においては、納税額への影響も無視できない額になるため、そうした顧問先を抱える税理士等においても注意を要すると考える。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























