解説記事2014年03月31日 【税務マエストロ】 新設分割等があった場合の納税義務の免除の特例(その1)(2014年3月31日号・№540)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
新設分割等があった場合の納税義務の免除の特例(その1)
#108 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#109 移転価格税制への対応①
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 会社分割等の形態には「新設分割等」と「吸収分割」があるが、分割等があった場合においても、相続や合併の場合と同じように、分割法人などの実績を考慮した上で納税義務を判定しなければならない。
今月は、新設分割等の範囲と営業譲渡との関係、簡易課税制度の適用判定を整理するとともに、新設分割子法人の納税義務の免除の特例について確認する。
1 新設分割等の範囲 分割があった場合の納税義務免除の特例規定は、旧商法及び関連法が整備されるまでは、現物出資による会社設立の場合に限り、適用することとされていた。
こういった理由から、特例規定の対象となる「分割等」の範囲には、「新設分割」だけでなく、「現物出資」や「事後設立」も含むこととされている(消法12⑦)。
(1)現物出資 現物出資とは、次の①から③までの全ての要件を満たす法人の設立をいう。
① 新設分割親法人が新設分割子法人を設立するため、その有する金銭以外の資産を出資するものであること。
② 新設分割子法人の設立時において、上記①の資産の出資その他その設立のための出資により、発行済株式の総数又は出資金額の全部を新設分割親法人が有することとなる分割であること。
③ その出資により新設分割子法人に事業の全部又は一部を引き継ぐものであること。
(2)事後設立 事後設立とは、次の①から⑤までの全ての要件を満たす法人の設立をいう。
① 新設分割親法人が新設分割子法人を設立するため金銭の出資をするものであること。
② 新設分割子法人と会社法467条1項5号(事業譲渡等の承認等)に掲げる契約を締結すること。
③ 上記②の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡であること。
④ 新設分割子法人の設立時において、発行済株式の総数又は出資金額の全部を新設分割親法人が保有していること。
⑤ 上記③の金銭以外の資産の譲渡が、新設分割子法人の設立時において予定されており、かつ、その設立の時から6月以内に行われたものであること(消令23⑨)。
ちなみに、「事後設立」とは、旧法人税法では「変態現物出資」と呼ばれていた会社の設立形態である。当初金銭を払い込んで株式又は出資を取得し、その後に、土地や建物などの資産を譲渡して当初の払い込み金銭を回収するというもので、その実態は現物出資と変わらないことからこのような(怪しい)俗称が付けられたものと思われる。
2 分割等に伴う資産の移転があった場合の取扱い
(1)分割等に伴う資産の移転があった場合の課税関係 事後設立は現実の資産の譲渡であり、当然に課税の対象となる。
また、現物出資についても、出資した資産の売却代金で株式を取得したものと実態は変わらないことから、現物出資による資産の移転は資産の譲渡等に類する行為として課税の対象に組み込むこととされている(消令2①二)。
これに対し、会社分割は、合併の場合における被合併法人の権利義務の承継と同様の法的性格を有する「包括承継」であり、個々の財産の譲渡とは本質的に異なるものである。
したがって、法人税法上の適格分割に該当するか否かを問わず、分割に伴う資産の移転は資産の譲渡等には該当せず、課税関係は生じないことになる。
(2)分割等に伴う資産の移転があった場合の売上(仕入)高
現物出資による資産の移転は資産の譲渡として取り扱われ、譲渡対価として取得する株式又は出資の価額(時価)が対価の額となる(消令45②三)。
例えば、分割法人が土地付建物を現物出資して分割承継法人の株式を取得した場合には、その株式の取得時の時価が出資した土地付建物の譲渡対価となる。したがって、その価額を時価比率などにより按分し、建物部分は課税売上高、土地部分は非課税売上高として処理をする(消令45③)。
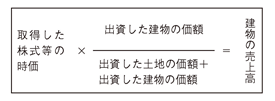
分割承継法人は、土地付き建物を取得したものとして扱われるので、建物部分は課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とすることができる。
会社分割が行われると、分割法人(新設分割親法人)の営業の全部又は一部が包括的に分割承継法人(新設分割子法人)に承継され、分割承継法人の株式又は出資が分割法人又は分割法人の株主又は出資者に割り当てられることになる。しかし、会社分割の際の株式又は出資の割り当ては、分割承継法人が承継した営業に対して明確な対価性を有しているとは言い難いところがあるため、現物出資とはその取扱いを異にしているものと思われる。
(3)営業譲渡との関係
会社分割と営業譲渡とは、いずれも営業を単位として権利義務が承継されるという点では共通している。しかしながら、会社分割が会社法に定める組織の再編成であるのに対し、営業譲渡は商人が行う取引行為の一つであって、民法の売買や商法の商行為に関する規定によって要件及び効果が制限されるものである。
したがって、営業譲渡においては、譲受会社から譲渡会社に対して対価としての金銭が当然に支払われることとなる。
また、会社分割に基づく権利義務の承継は、前述のように包括承継に当たると解されており、その資産などの移転は法律上当然に生じることとされている。これに対し、営業譲渡に基づく権利義務の承継は、法律上は特定承継としての性質を有するところに大きな違いがある。
(注)特定承継とは、他人の権利義務を個別的に取得することをいい、特定承継により権利義務を承継する者を特定承継人という。
売買、交換、贈与などによる資産などの使用収益権の承継は特定承継に該当し、売買契約に基づく資産の買主などが特定承継人の典型例である。
3 簡易課税制度との関係 納税義務の判定に用いる課税売上高と簡易課税制度の適用判定は、合併の場合と分割等の場合で異なっている(図表1参照)。合併法人の簡易課税制度の適用の有無については、被合併法人の実績は一切考慮せずに、合併法人の基準期間における課税売上高のみによって判定することとされている(消基通13-1-2)。
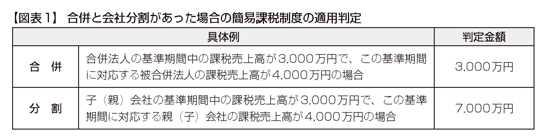
これに対し、「会社分割」があった場合の簡易課税制度の適用の有無については、納税義務判定に用いる金額がそのまま簡易課税制度の適用判定にも連動することとされているので注意が必要だ(消法37①、消令55)。
4 新設分割子法人の判定 新設分割子法人は、設立事業年度とその翌事業年度は基準期間そのものが存在しないことになる。しかし、会社分割により設立された法人については、基準期間がないという理由だけで、単純に納税義務を免除することはできない。新設分割親法人の実績を考慮した上で、納税義務を判定することとされている。
納税義務の判定に用いる課税売上高は図表2のように計算する。なお、判定に用いる課税売上高は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月とする(消令23⑧)。
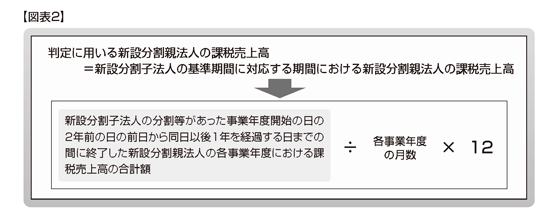
また、分割等による事業承継があったことにより、分割承継法人などが納税義務者となった場合には、「課税事業者届出書」とともに「相続・合併・分割等があったことにより納税義務者となる場合の付表」の提出が義務付けられている。
(1)分割事業年度の取扱い 分割事業年度においては、「新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高」が1,000万円を超える場合には、新設分割子法人は、分割等があった日から分割事業年度終了の日までの期間については課税事業者となる(消法12①、消令23①)。
また、新設分割親法人が2社以上ある場合には、最も大きい課税売上高により判定することとされており、新設分割親法人同士の課税売上高を合算する必要はない。
(2)分割等があった日 「分割等があった日」とは、新設分割及び現物出資については新設分割子法人の設立登記の日となるが、事後設立の場合には、契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日となる(消基通1-5-9)。
したがって、新設分割子法人の設立登記の日から契約に基づく資産の譲渡が行われた日の前日までの期間については分割の特例規定は適用されない(図表3参照)。
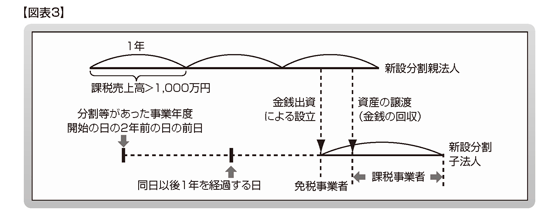
(3)分割事業年度の翌事業年度の取扱い
新設分割子法人の、納税義務判定の対象事業年度開始の日の1年前の日の前日から対象事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、「新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高」が1,000万円を超える場合には、新設分割子法人は、その事業年度において課税事業者となる。(消法12②、消令23②)。
また、新設分割親法人が2社以上ある場合には、最も大きい課税売上高により判定することとされており、新設分割親法人同士の課税売上高を合算する必要はない(図表4参照)。
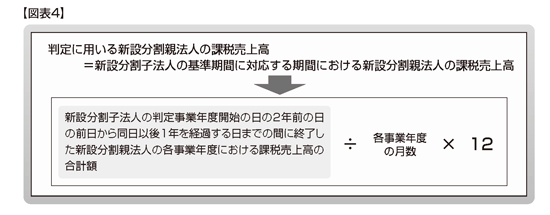
(4)新設分割子法人の基準期間がある場合
新設分割子法人の、納税義務判定の対象事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合には、図表5・6の「(イ)+(ロ)」の算式により、新設分割子法人の納税義務を判定する(消法12③、消令23③④)。
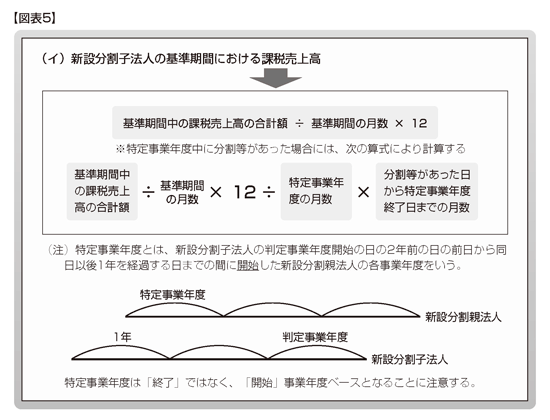
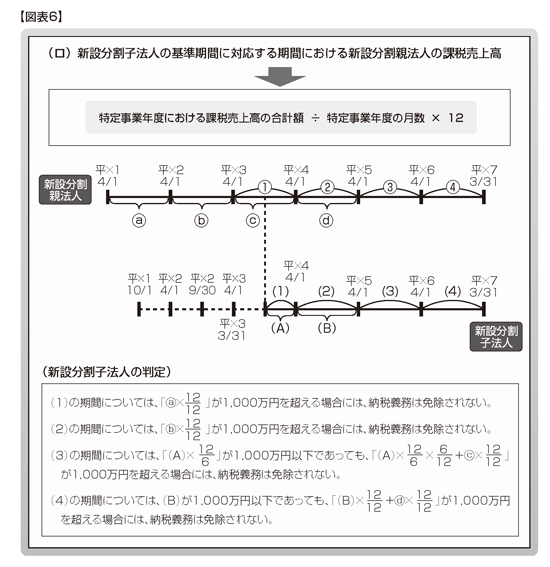
ただし、次のいずれかに該当する場合には、納税義務免除の特例規定は適用されない。
図表6中(3)の期間の考え方は、新設分割親法人の特定事業年度(基準期間)における課税売上高(c)は、4月1日から9月30日までの6ヶ月分だけ、新設分割子法人の実績が欠けていることになる。そこで、新設分割子法人の課税売上高により、欠けている部分を計算するということである(図表7参照)。
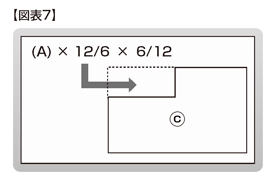
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
新設分割等があった場合の納税義務の免除の特例(その1)
#108 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#109 移転価格税制への対応①
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 会社分割等の形態には「新設分割等」と「吸収分割」があるが、分割等があった場合においても、相続や合併の場合と同じように、分割法人などの実績を考慮した上で納税義務を判定しなければならない。
今月は、新設分割等の範囲と営業譲渡との関係、簡易課税制度の適用判定を整理するとともに、新設分割子法人の納税義務の免除の特例について確認する。
1 新設分割等の範囲 分割があった場合の納税義務免除の特例規定は、旧商法及び関連法が整備されるまでは、現物出資による会社設立の場合に限り、適用することとされていた。
こういった理由から、特例規定の対象となる「分割等」の範囲には、「新設分割」だけでなく、「現物出資」や「事後設立」も含むこととされている(消法12⑦)。
(1)現物出資 現物出資とは、次の①から③までの全ての要件を満たす法人の設立をいう。
① 新設分割親法人が新設分割子法人を設立するため、その有する金銭以外の資産を出資するものであること。
② 新設分割子法人の設立時において、上記①の資産の出資その他その設立のための出資により、発行済株式の総数又は出資金額の全部を新設分割親法人が有することとなる分割であること。
③ その出資により新設分割子法人に事業の全部又は一部を引き継ぐものであること。
(2)事後設立 事後設立とは、次の①から⑤までの全ての要件を満たす法人の設立をいう。
① 新設分割親法人が新設分割子法人を設立するため金銭の出資をするものであること。
② 新設分割子法人と会社法467条1項5号(事業譲渡等の承認等)に掲げる契約を締結すること。
③ 上記②の契約に基づく金銭以外の資産の譲渡であること。
④ 新設分割子法人の設立時において、発行済株式の総数又は出資金額の全部を新設分割親法人が保有していること。
⑤ 上記③の金銭以外の資産の譲渡が、新設分割子法人の設立時において予定されており、かつ、その設立の時から6月以内に行われたものであること(消令23⑨)。
ちなみに、「事後設立」とは、旧法人税法では「変態現物出資」と呼ばれていた会社の設立形態である。当初金銭を払い込んで株式又は出資を取得し、その後に、土地や建物などの資産を譲渡して当初の払い込み金銭を回収するというもので、その実態は現物出資と変わらないことからこのような(怪しい)俗称が付けられたものと思われる。
2 分割等に伴う資産の移転があった場合の取扱い
(1)分割等に伴う資産の移転があった場合の課税関係 事後設立は現実の資産の譲渡であり、当然に課税の対象となる。
また、現物出資についても、出資した資産の売却代金で株式を取得したものと実態は変わらないことから、現物出資による資産の移転は資産の譲渡等に類する行為として課税の対象に組み込むこととされている(消令2①二)。
これに対し、会社分割は、合併の場合における被合併法人の権利義務の承継と同様の法的性格を有する「包括承継」であり、個々の財産の譲渡とは本質的に異なるものである。
したがって、法人税法上の適格分割に該当するか否かを問わず、分割に伴う資産の移転は資産の譲渡等には該当せず、課税関係は生じないことになる。
(2)分割等に伴う資産の移転があった場合の売上(仕入)高
現物出資による資産の移転は資産の譲渡として取り扱われ、譲渡対価として取得する株式又は出資の価額(時価)が対価の額となる(消令45②三)。
例えば、分割法人が土地付建物を現物出資して分割承継法人の株式を取得した場合には、その株式の取得時の時価が出資した土地付建物の譲渡対価となる。したがって、その価額を時価比率などにより按分し、建物部分は課税売上高、土地部分は非課税売上高として処理をする(消令45③)。
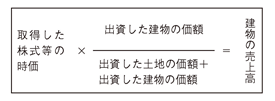
分割承継法人は、土地付き建物を取得したものとして扱われるので、建物部分は課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とすることができる。
会社分割が行われると、分割法人(新設分割親法人)の営業の全部又は一部が包括的に分割承継法人(新設分割子法人)に承継され、分割承継法人の株式又は出資が分割法人又は分割法人の株主又は出資者に割り当てられることになる。しかし、会社分割の際の株式又は出資の割り当ては、分割承継法人が承継した営業に対して明確な対価性を有しているとは言い難いところがあるため、現物出資とはその取扱いを異にしているものと思われる。
(3)営業譲渡との関係
会社分割と営業譲渡とは、いずれも営業を単位として権利義務が承継されるという点では共通している。しかしながら、会社分割が会社法に定める組織の再編成であるのに対し、営業譲渡は商人が行う取引行為の一つであって、民法の売買や商法の商行為に関する規定によって要件及び効果が制限されるものである。
したがって、営業譲渡においては、譲受会社から譲渡会社に対して対価としての金銭が当然に支払われることとなる。
また、会社分割に基づく権利義務の承継は、前述のように包括承継に当たると解されており、その資産などの移転は法律上当然に生じることとされている。これに対し、営業譲渡に基づく権利義務の承継は、法律上は特定承継としての性質を有するところに大きな違いがある。
(注)特定承継とは、他人の権利義務を個別的に取得することをいい、特定承継により権利義務を承継する者を特定承継人という。
売買、交換、贈与などによる資産などの使用収益権の承継は特定承継に該当し、売買契約に基づく資産の買主などが特定承継人の典型例である。
3 簡易課税制度との関係 納税義務の判定に用いる課税売上高と簡易課税制度の適用判定は、合併の場合と分割等の場合で異なっている(図表1参照)。合併法人の簡易課税制度の適用の有無については、被合併法人の実績は一切考慮せずに、合併法人の基準期間における課税売上高のみによって判定することとされている(消基通13-1-2)。
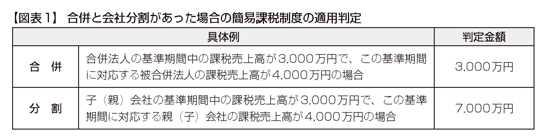
これに対し、「会社分割」があった場合の簡易課税制度の適用の有無については、納税義務判定に用いる金額がそのまま簡易課税制度の適用判定にも連動することとされているので注意が必要だ(消法37①、消令55)。
4 新設分割子法人の判定 新設分割子法人は、設立事業年度とその翌事業年度は基準期間そのものが存在しないことになる。しかし、会社分割により設立された法人については、基準期間がないという理由だけで、単純に納税義務を免除することはできない。新設分割親法人の実績を考慮した上で、納税義務を判定することとされている。
納税義務の判定に用いる課税売上高は図表2のように計算する。なお、判定に用いる課税売上高は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月とする(消令23⑧)。
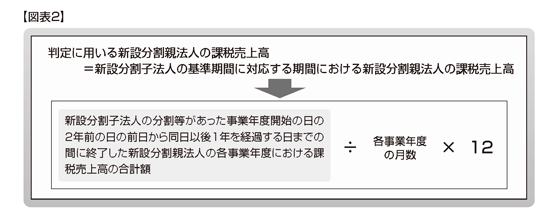
また、分割等による事業承継があったことにより、分割承継法人などが納税義務者となった場合には、「課税事業者届出書」とともに「相続・合併・分割等があったことにより納税義務者となる場合の付表」の提出が義務付けられている。
(1)分割事業年度の取扱い 分割事業年度においては、「新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高」が1,000万円を超える場合には、新設分割子法人は、分割等があった日から分割事業年度終了の日までの期間については課税事業者となる(消法12①、消令23①)。
また、新設分割親法人が2社以上ある場合には、最も大きい課税売上高により判定することとされており、新設分割親法人同士の課税売上高を合算する必要はない。
(2)分割等があった日 「分割等があった日」とは、新設分割及び現物出資については新設分割子法人の設立登記の日となるが、事後設立の場合には、契約に基づく金銭以外の資産の譲渡が行われた日となる(消基通1-5-9)。
したがって、新設分割子法人の設立登記の日から契約に基づく資産の譲渡が行われた日の前日までの期間については分割の特例規定は適用されない(図表3参照)。
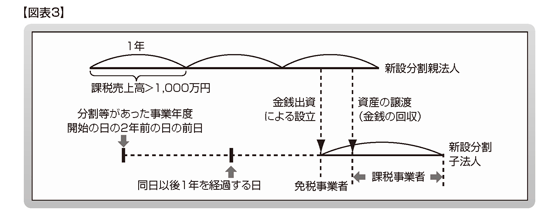
(3)分割事業年度の翌事業年度の取扱い
新設分割子法人の、納税義務判定の対象事業年度開始の日の1年前の日の前日から対象事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、「新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高」が1,000万円を超える場合には、新設分割子法人は、その事業年度において課税事業者となる。(消法12②、消令23②)。
また、新設分割親法人が2社以上ある場合には、最も大きい課税売上高により判定することとされており、新設分割親法人同士の課税売上高を合算する必要はない(図表4参照)。
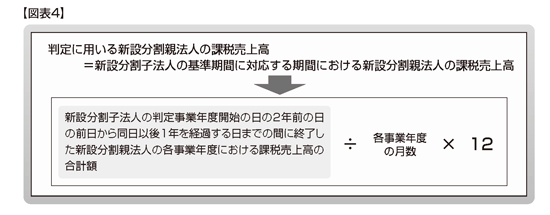
(4)新設分割子法人の基準期間がある場合
新設分割子法人の、納税義務判定の対象事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合には、図表5・6の「(イ)+(ロ)」の算式により、新設分割子法人の納税義務を判定する(消法12③、消令23③④)。
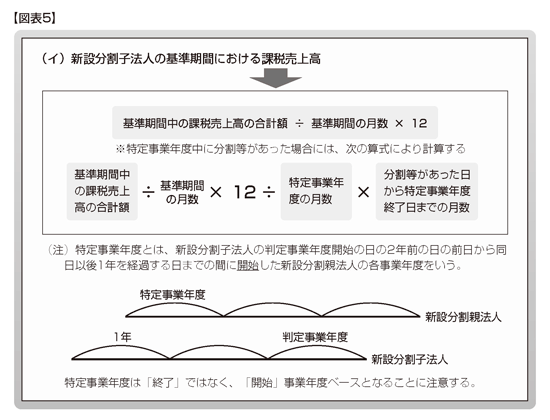
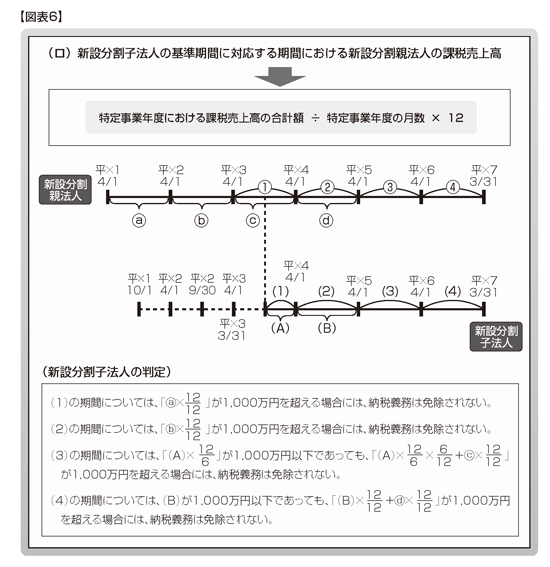
ただし、次のいずれかに該当する場合には、納税義務免除の特例規定は適用されない。
| ○適用除外となる場合 ・新設分割子法人が基準期間の末日において「特定要件」に該当しない場合 ・新設分割親法人が2社以上ある場合 (注)特定要件とは、新設分割子法人の発行済株式等の50%超を新設分割親法人とその特殊関係者が保有する場合をいう。ただし、新設分割子法人が保有する自己株式等は除外して判定する。 |
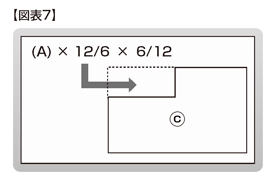
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















