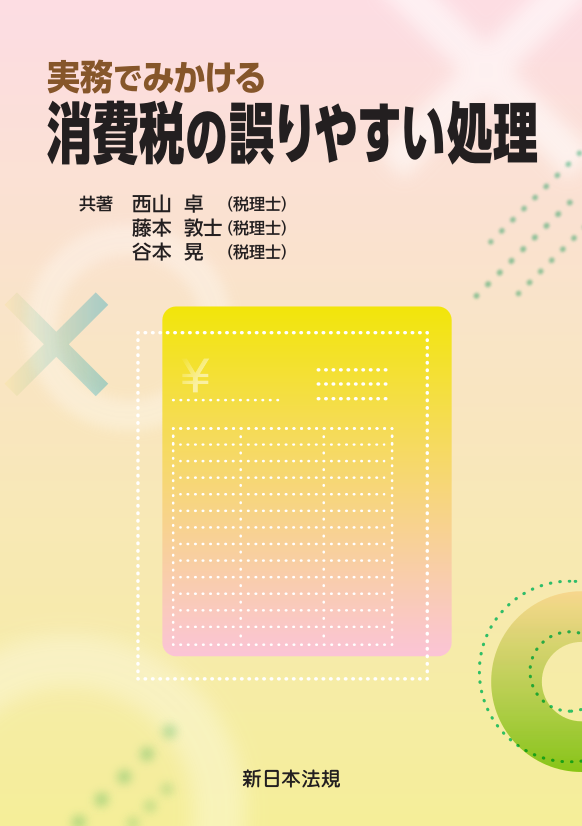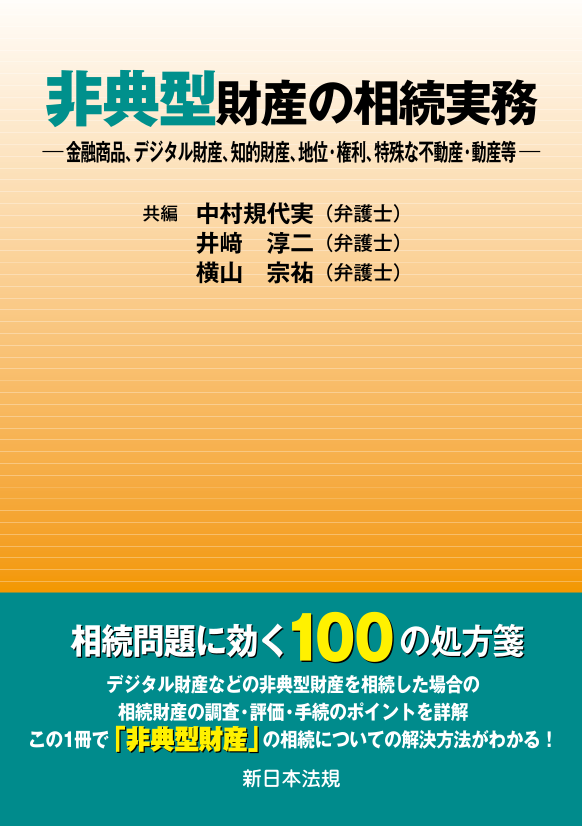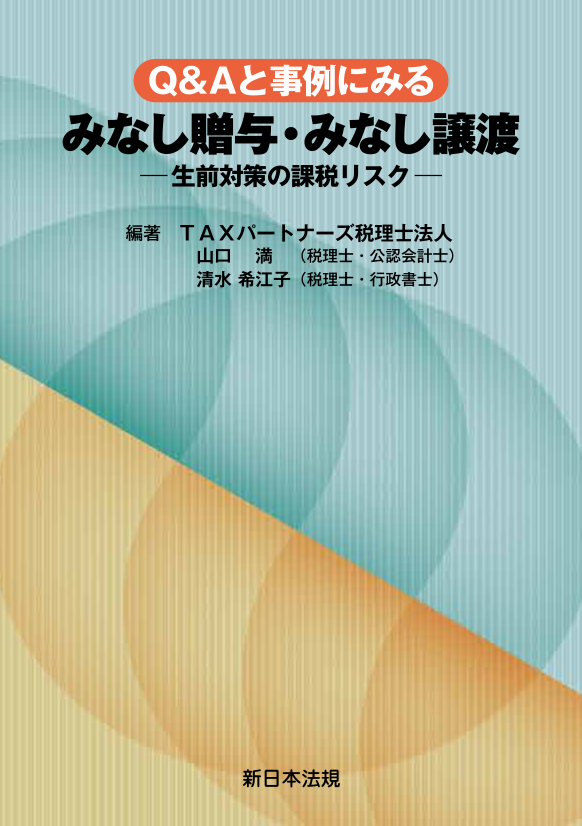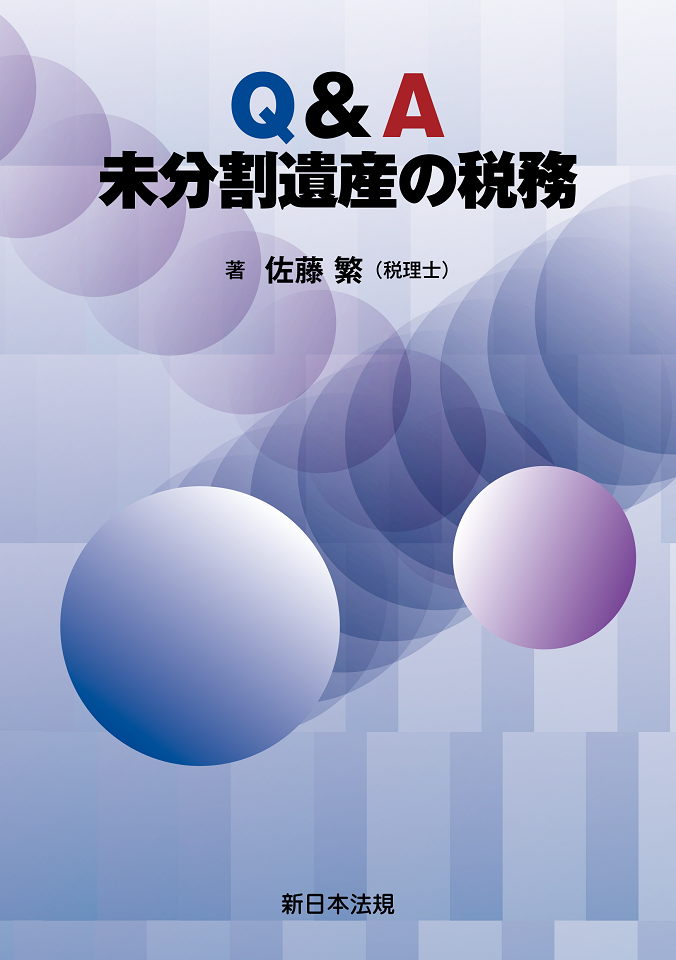コラム2015年02月09日 【資料解説】 使用人の不正行為で税理士に懲戒処分も(2015年2月9日号・№582)
資料解説:
税理士会の会費滞納者への懲戒処分は「戒告」
使用人の不正行為で税理士に懲戒処分も
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」が1月30日に公表された(次頁参照)。今回の一部改正は税理士法改正を踏まえ、税理士や税理士法人の使用人等が不正行為を行った場合の懲戒処分を明確化するもの。税理士が使用人の不正行為を認識していなくても内部管理体制に不備があり、相当の責任があれば懲戒処分の対象になるだけに注目すべき改正といえよう。適用は、平成27年4月1日以後にした不正行為等に係る懲戒処分等について適用されることになる。
責任あれば他の社員税理士が懲戒処分に 「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正では、使用人等の不正行為を使用者税理士等(使用者である税理士又は税理士法人の社員税理士)が認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為を行ったものとして懲戒処分を行うこととしている。また、使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していなかったときであっても内部規律や内部管理体制に不備があったことにより、認識できなかったことについて使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、使用者税理士等が過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をすることとされている。加えて、このケースに該当しない場合であっても使用者税理士等の監督が適切でなかった場合には、使用人等に対する監督義務(税理士法41条の2)に違反したものとして懲戒処分がなされる。
税理士法人の社員税理士が不正行為を行った場合も、他の社員税理士に対して懲戒処分がなされることがある。前述と同様、社員税理士の不正行為を認識していたときや、認識していなくても税理士法人の内部規律等に不備があることにより、他の社員税理士に相当の責任があると認められる場合には、他の社員税理士も過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分されることになる。
税理士業務の停止期間の上限が2年に 懲戒処分の業務停止期間の延長に伴い、税理士業務の停止の上限が「2年」に引き上げられる。また、懲戒処分の明確化として、税理士会の会費滞納者に対する懲戒処分については、「戒告」とすることが明記された。税理士法人の会費滞納も同様だ。そのほか、税理士業務の停止処分がされているにも関わらずこれに違反し、税理士業務を行った場合には、「税理士業務の禁止」にすることとされている(税理士法人についても同様)。
なお、平成26年7月31日に公表した一部改正(案)からの変更点としては、税理士法人が解散の届出をしなかった場合には「戒告」となる旨が追加されたのみとなっている。
税理士会の会費滞納者への懲戒処分は「戒告」
使用人の不正行為で税理士に懲戒処分も
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」が1月30日に公表された(次頁参照)。今回の一部改正は税理士法改正を踏まえ、税理士や税理士法人の使用人等が不正行為を行った場合の懲戒処分を明確化するもの。税理士が使用人の不正行為を認識していなくても内部管理体制に不備があり、相当の責任があれば懲戒処分の対象になるだけに注目すべき改正といえよう。適用は、平成27年4月1日以後にした不正行為等に係る懲戒処分等について適用されることになる。
責任あれば他の社員税理士が懲戒処分に 「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正では、使用人等の不正行為を使用者税理士等(使用者である税理士又は税理士法人の社員税理士)が認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為を行ったものとして懲戒処分を行うこととしている。また、使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していなかったときであっても内部規律や内部管理体制に不備があったことにより、認識できなかったことについて使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、使用者税理士等が過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をすることとされている。加えて、このケースに該当しない場合であっても使用者税理士等の監督が適切でなかった場合には、使用人等に対する監督義務(税理士法41条の2)に違反したものとして懲戒処分がなされる。
税理士法人の社員税理士が不正行為を行った場合も、他の社員税理士に対して懲戒処分がなされることがある。前述と同様、社員税理士の不正行為を認識していたときや、認識していなくても税理士法人の内部規律等に不備があることにより、他の社員税理士に相当の責任があると認められる場合には、他の社員税理士も過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分されることになる。
税理士業務の停止期間の上限が2年に 懲戒処分の業務停止期間の延長に伴い、税理士業務の停止の上限が「2年」に引き上げられる。また、懲戒処分の明確化として、税理士会の会費滞納者に対する懲戒処分については、「戒告」とすることが明記された。税理士法人の会費滞納も同様だ。そのほか、税理士業務の停止処分がされているにも関わらずこれに違反し、税理士業務を行った場合には、「税理士業務の禁止」にすることとされている(税理士法人についても同様)。
なお、平成26年7月31日に公表した一部改正(案)からの変更点としては、税理士法人が解散の届出をしなかった場合には「戒告」となる旨が追加されたのみとなっている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.