解説記事2015年07月13日 【税理士のための相続法講座】 承認と放棄(1)-熟慮期間と相続の承認(2015年7月13日号・№602)
税理士のための相続法講座
第5回
承認と放棄(1)-熟慮期間と相続の承認
弁護士 間瀬まゆ子
今回から2回に分けて、実務上問題となることの多い相続の承認と放棄をテーマにお話させて頂きます。
1 単純承認・限定承認・放棄 まず、基本知識を確認します。
「相続に際して選択し得る方法には、単純承認、限定承認及び相続放棄の3つがあります。」というのが一般的な説明ですが、世の中の大多数のケースは、法的には単純承認の効果が生じつつ、当事者がそれを意識することなく処理がなされていることが多いと思われます。この場合に適用されているのは、民法921条です。同条2号は、3ケ月の熟慮期間内に限定承認も放棄もしないと、単純承認をしたものとみなす旨を定めています。この3ケ月という期間には、税理士の先生方も敏感になられていることでしょう。
これに対し、被相続人が多額の負債を負っていたり、あるいは負債の存在や金額が不明であったりする場合には、単純承認するか、あるいは相続放棄や限定承認をするかの判断を余儀なくされます。
このうち相続放棄は、ご存知のとおり、財産も債務も一切承継しないという相続形態であり、相続の放棄をした人は、はじめから「相続人とならなかった」ことになります(民法939条)。相続放棄の手続等については、次回に改めて解説する予定です。
もう一つの限定承認は、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務等について責任を負えばよいというもので、一見素晴らしい制度に見えます。しかし、実際には、使い勝手が良くないため、あまり使われていません(司法統計によると、平成25年の新受件数は、全国で約800件に過ぎません。)。この点については後述します。
2 熟慮期間の伸長
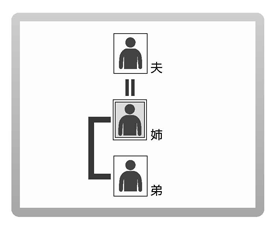
様々な事情により、3ケ月の熟慮期間内ではとても財産の調査を完了できないということがあります。そのような場合に民法は、利害関係人の請求により、家庭裁判所が熟慮期間を伸長することを認めています(915条1項但書)。上記の事例でも、相談を受けた時点で未だ熟慮期間内であれば、その伸長の申立てを検討することになるでしょう。
具体的に伸長が認められる期間について、法の定めはありませんが、実務上、当初の熟慮期間と同じ3ケ月が基準とされることが多いようです。また、2回目、3回目の伸長が認められることもあります。
この伸長の申立てを行う時期ですが、熟慮期間の3ケ月以内(再度の伸長の場合は前回伸長された期限まで)であればよいとされています。しかし、伸長は必ず認められるものではありませんので、期限内に裁判所の判断をもらえるよう、それに要する期間を考慮して、早めに申立てをするのが妥当でしょう。
3 法定単純承認
相続放棄(または限定承認)の方針が決まっているか、あるいはその可能性があるケースにおいて、非常に神経を使うのが、「法定単純承認」にあたる行為を当事者にさせないという点です。
民法は、法定単純承認に該当する事由として、以下の3つを挙げており、このいずれかに該当してしまうと、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄(または限定承認)ができなくなってしまうからです(921条)。
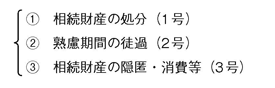
このうち②は、前述のとおり、3ケ月の熟慮期間内に、相続放棄も限定承認もしなかった場合です。
③は、相続財産を「隠匿し」「私に…消費し」または「悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき」に単純承認したものとみなすもので、不誠実な行為に対する制裁の色合いが濃いものです。当事者にきちんと伝えておけば、これらはある程度防げるのではないかと思います。
それに対し、①の「処分」は注意が必要です。「処分」にあたらない管理行為のほか、解釈によりこの「処分」にあたらないとされる行為もあり、「処分」にあたりそうな行為をしても法定単純承認に至らない場合もあります。しかし、その境界はあいまいで、判断を当事者に任せるのは危険です。
例えば、上記の事例の洋服の処分についていえば、一般的経済的価値を失う程度に着古した洋服を人に渡したケースや、洋服や時計を形見分けしたケースについて、「処分」にはあたらないと裁判で救済された例もありますが、どの程度なら救済されるのかの基準はありません。一度、「その程度なら大丈夫」と言ってしまうと、当事者がその後自己判断で処分してしまい、ヒヤッとするということもあり得ます。
そのようなことを避けるため、処分と言われそうな行為は一切しないようにと繰り返し指導しておく必要があります。
なお、「生命保険金を受け取っていいか」と当事者から質問を受けることもあります。生命保険金については、例えば、受取人が特定の相続人に指定されている場合、当該保険金請求権は相続財産ではなく受取人固有の財産と解されますので、法定単純承認の問題は生じません。
ただ、①の「処分」については限定承認・放棄前になされたものに限ると解されており(3号は限定承認・放棄後の行為も含むことを明示しています。)、また、元々これらの手続は限られた熟慮期間内に行わなければならないものですから、疑義が生じ得る行為はできるだけ避け、早急に手続をとることが肝要でしょう。
4 限定承認
先ほど、限定承認は使いにくいと説明しましたが、それはなぜでしょうか。
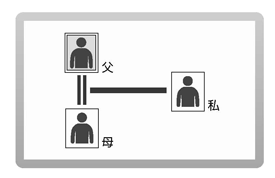
理由の一つは、共同相続人の全員の共同でなければできない点にあります(民法923条)。一人でも反対する相続人がいると、限定承認を選択することができません。ただし、一部の相続人が相続放棄をし、残りの相続人全員で限定承認することは可能です。
また、手続が煩雑ということも言われます。債務の弁済に充てるために財産を換価しなければならない場合、競売によることが原則とされており、例外的に競売手続によらずに相続人が財産を買い受けることが認められているものの、その場合も、裁判所が選任した鑑定人による鑑定を経なければならないことになっています(民法932条)。
なお、法に反して任意売却した場合、その売買の効力自体は有効と解されていますが、後に、不当に安い価格で売却したとして、相続債権者らから損害賠償の責任を問われるリスクがあります。
更に、限定承認の場合の問題として、よく指摘されるのが「みなし譲渡所得」の課税が生じる点です。ご存知のとおり、現行の所得税法において、限定承認の場合に限り、相続時に、時価で被相続人が譲渡したものとして、譲渡所得課税が行われます(所得税法59条1項1号)。そのため、仮に、相続した資産を譲渡せずに済んだ場合でも課税が生じ、思わぬ負担が生じてしまうことがあり得ます(取得費が時価まで引き上げられますので、後に実際に譲渡した際に値上がりしていれば、全体として損は生じませんが。)。
これらの理由から、あまり使われていない限定承認ですが、上記の事例のように、どうしても特定の財産を残したいという意向が相続人にある場合には、限定承認を選択する合理的な理由があると言えます。前述のとおり、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の価額を弁済すれば、競売手続によらずに当該財産を買い受けることができるからです。
ただし、抵当権の実行を止められるわけではありませんので、抵当権が付いている場合には、抵当権者との交渉が必要になります。
第5回
承認と放棄(1)-熟慮期間と相続の承認
弁護士 間瀬まゆ子
今回から2回に分けて、実務上問題となることの多い相続の承認と放棄をテーマにお話させて頂きます。
1 単純承認・限定承認・放棄 まず、基本知識を確認します。
「相続に際して選択し得る方法には、単純承認、限定承認及び相続放棄の3つがあります。」というのが一般的な説明ですが、世の中の大多数のケースは、法的には単純承認の効果が生じつつ、当事者がそれを意識することなく処理がなされていることが多いと思われます。この場合に適用されているのは、民法921条です。同条2号は、3ケ月の熟慮期間内に限定承認も放棄もしないと、単純承認をしたものとみなす旨を定めています。この3ケ月という期間には、税理士の先生方も敏感になられていることでしょう。
これに対し、被相続人が多額の負債を負っていたり、あるいは負債の存在や金額が不明であったりする場合には、単純承認するか、あるいは相続放棄や限定承認をするかの判断を余儀なくされます。
このうち相続放棄は、ご存知のとおり、財産も債務も一切承継しないという相続形態であり、相続の放棄をした人は、はじめから「相続人とならなかった」ことになります(民法939条)。相続放棄の手続等については、次回に改めて解説する予定です。
もう一つの限定承認は、相続によって得た財産の限度においてだけ被相続人の債務等について責任を負えばよいというもので、一見素晴らしい制度に見えます。しかし、実際には、使い勝手が良くないため、あまり使われていません(司法統計によると、平成25年の新受件数は、全国で約800件に過ぎません。)。この点については後述します。
2 熟慮期間の伸長
| 子どものいない姉が亡くなった。相続人は姉の夫と弟である私の2人。姉は複数の不動産を所有していたが、借金もあったようで、実態は全く分からない。財産の開示を義兄に求めているが、義兄はなかなかこれに応じてくれない。 |
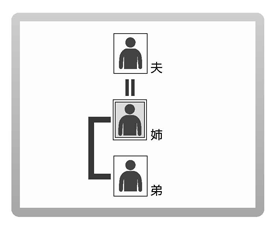
様々な事情により、3ケ月の熟慮期間内ではとても財産の調査を完了できないということがあります。そのような場合に民法は、利害関係人の請求により、家庭裁判所が熟慮期間を伸長することを認めています(915条1項但書)。上記の事例でも、相談を受けた時点で未だ熟慮期間内であれば、その伸長の申立てを検討することになるでしょう。
具体的に伸長が認められる期間について、法の定めはありませんが、実務上、当初の熟慮期間と同じ3ケ月が基準とされることが多いようです。また、2回目、3回目の伸長が認められることもあります。
この伸長の申立てを行う時期ですが、熟慮期間の3ケ月以内(再度の伸長の場合は前回伸長された期限まで)であればよいとされています。しかし、伸長は必ず認められるものではありませんので、期限内に裁判所の判断をもらえるよう、それに要する期間を考慮して、早めに申立てをするのが妥当でしょう。
3 法定単純承認
| 夫が多額の借金を残して亡くなった。親族全員で放棄をしようという話になっている。親族に頭を下げて回る日々で、家に帰って夫の服を見ると腹立たしくなる。どうせ古い物ばかりだし、みんな捨ててしまおう。 |
民法は、法定単純承認に該当する事由として、以下の3つを挙げており、このいずれかに該当してしまうと、単純承認したものとみなされ、もはや相続放棄(または限定承認)ができなくなってしまうからです(921条)。
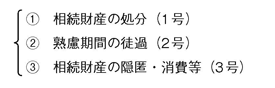
このうち②は、前述のとおり、3ケ月の熟慮期間内に、相続放棄も限定承認もしなかった場合です。
③は、相続財産を「隠匿し」「私に…消費し」または「悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき」に単純承認したものとみなすもので、不誠実な行為に対する制裁の色合いが濃いものです。当事者にきちんと伝えておけば、これらはある程度防げるのではないかと思います。
それに対し、①の「処分」は注意が必要です。「処分」にあたらない管理行為のほか、解釈によりこの「処分」にあたらないとされる行為もあり、「処分」にあたりそうな行為をしても法定単純承認に至らない場合もあります。しかし、その境界はあいまいで、判断を当事者に任せるのは危険です。
例えば、上記の事例の洋服の処分についていえば、一般的経済的価値を失う程度に着古した洋服を人に渡したケースや、洋服や時計を形見分けしたケースについて、「処分」にはあたらないと裁判で救済された例もありますが、どの程度なら救済されるのかの基準はありません。一度、「その程度なら大丈夫」と言ってしまうと、当事者がその後自己判断で処分してしまい、ヒヤッとするということもあり得ます。
そのようなことを避けるため、処分と言われそうな行為は一切しないようにと繰り返し指導しておく必要があります。
なお、「生命保険金を受け取っていいか」と当事者から質問を受けることもあります。生命保険金については、例えば、受取人が特定の相続人に指定されている場合、当該保険金請求権は相続財産ではなく受取人固有の財産と解されますので、法定単純承認の問題は生じません。
ただ、①の「処分」については限定承認・放棄前になされたものに限ると解されており(3号は限定承認・放棄後の行為も含むことを明示しています。)、また、元々これらの手続は限られた熟慮期間内に行わなければならないものですから、疑義が生じ得る行為はできるだけ避け、早急に手続をとることが肝要でしょう。
4 限定承認
| 父が突然亡くなった。相続人は母と私。負債がかなりあるようだが、具体的にどの程度なのかは分からない。母は、父名義の自宅に愛着を持っており、自分が実家から相続した資産を使ってもいいので、何としても住み続けたいと言っている。 |
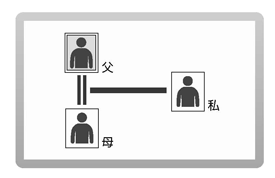
理由の一つは、共同相続人の全員の共同でなければできない点にあります(民法923条)。一人でも反対する相続人がいると、限定承認を選択することができません。ただし、一部の相続人が相続放棄をし、残りの相続人全員で限定承認することは可能です。
また、手続が煩雑ということも言われます。債務の弁済に充てるために財産を換価しなければならない場合、競売によることが原則とされており、例外的に競売手続によらずに相続人が財産を買い受けることが認められているものの、その場合も、裁判所が選任した鑑定人による鑑定を経なければならないことになっています(民法932条)。
なお、法に反して任意売却した場合、その売買の効力自体は有効と解されていますが、後に、不当に安い価格で売却したとして、相続債権者らから損害賠償の責任を問われるリスクがあります。
更に、限定承認の場合の問題として、よく指摘されるのが「みなし譲渡所得」の課税が生じる点です。ご存知のとおり、現行の所得税法において、限定承認の場合に限り、相続時に、時価で被相続人が譲渡したものとして、譲渡所得課税が行われます(所得税法59条1項1号)。そのため、仮に、相続した資産を譲渡せずに済んだ場合でも課税が生じ、思わぬ負担が生じてしまうことがあり得ます(取得費が時価まで引き上げられますので、後に実際に譲渡した際に値上がりしていれば、全体として損は生じませんが。)。
これらの理由から、あまり使われていない限定承認ですが、上記の事例のように、どうしても特定の財産を残したいという意向が相続人にある場合には、限定承認を選択する合理的な理由があると言えます。前述のとおり、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、相続財産の価額を弁済すれば、競売手続によらずに当該財産を買い受けることができるからです。
ただし、抵当権の実行を止められるわけではありませんので、抵当権が付いている場合には、抵当権者との交渉が必要になります。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























