解説記事2015年11月23日 【実務解説】 受益権複層化信託の相続課税(2015年11月23日号・№619)
実務解説
受益権複層化信託の相続課税
高橋倫彦
Ⅰ 本稿の趣旨
本稿は2015年6月15日号の本誌に掲載した「受益権複層化信託の所得課税」の後編として受益権複層化信託の相続・贈与課税について検討したものである。複層化した信託受益権やその受益者連続型信託の権利の税務上の取り扱いについては議論があり、その税制改正の要望もなされているが、本稿は、現行法を忠実に適用した場合の税務上の取り扱いの明確化を目的とする。筆者は長年信託業務に従事した経験を基に、手元の事例に基づき、利用者の意図(信託目的)に照らして、信託の権利の内容と、経済合理性とを根拠に、実務的観点から現行法の適用の可能性を検討した。実務的観点からの文献がほとんど公表されていないなか、本稿は、今後の税務の専門家の方々による研究の一助になることを期待し執筆した。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 受益権複層化信託の相続課税の原則
受益権複層化信託とは収益受益権や元本受益権のように受益権の質が異なる受益権が複数ある信託を言う(相基通9-13)。受益権を優先・劣後構造にする法人信託もこれに近い。税法上は受益者が2以上ある場合は、信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその権利の内容に応じて有するものとされる(法令15条4項、所令52条4項)。つまり、信託財産に二重所有(複層化)を認めつつ、それぞれの権利は異なるものとされる。なお、本稿は受益者等課税信託を検討の対象とする。
1 受益権の課税時期 相続・贈与による受益権の取得は適正な対価を負担していないので相続・贈与税が課税される。委託者以外の者が受益権を取得した場合は、実体法にとらわれずにその経済的実質を見ると委託者又は前の受益者等から受益権が相続・贈与されているので、相続税法では第1章第3節に「信託に関する特例」を設けて、このような場合の信託受益権の取得を相続・贈与による取得とみなしている。
(1)受益者としての権利を現に有する者
(相法9条の2第1項) 受益者等とは受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者を言うものとされる(相法9条の2第1項)。この権利を現に有する者には、残余財産受益者(信託法182条1項1号)は含まれるが、受益権に停止条件又は効力発生の始期が付されている場合、受益者がまだ存在(生誕)しない場合、又は特定されていない場合の受益者は含まない(相基通9の2-1)。従って遺言代用信託(信託法90条1項各号)の委託者死亡前の受益者や帰属権利者(信託法182条1項2号)は含まれない。
受益権複層化信託の元本受益者は、信託が終了した時に、収益受益権の消滅により信託財産を受領するが、元本受益権に停止条件が付されていないので、受益者としての権利を現に有する者に含まれる。しかし受益者連続型信託の権利の第二次以後の承継受益者は、信託の効力が生じたときに指定されているが、既存の受益者が死亡し、その受益権が消滅した時に、新たに受益権を取得するので、この権利を現に有する者ではない。
(2)新たに受益権を取得した場合
(相法9条の2第1項及び第2項) 他益信託の設定による受益権の取得は、当該信託の効力が生じた時において、受益権を委託者から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなされる(相法9条の2第1項)。
自益信託等の受益者等の存する信託について新たに受益者等となる者は、受益者等となった時に、当該信託の受益権を前の受益者等から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなされる(相法9条の2第2項)。自益信託の受益権が複層化され、複層化された受益権を取得した場合は、委託者から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなされる。受益者連続型信託(相法9条の3第1項、相令1条の8)の定めに従って、新たに当該信託の受益者等が存するに至った場合、実体法的に見ると継伝的な遺贈ではない場合であっても、前の受益者から継伝的に取得したものとみなされる。跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託(信託法91条)の受益者の死亡により新たに受益者になる場合も、受益者指定権の行使(信託法89条)により新たに当該信託の受益者となる場合も、受益者連続型信託に該当する。
(3)受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった場合(相法9条の2第3項) 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった場合、既存の受益者等がその受益権について新たに利益を受けることとなるときは、その者が存しなくなった時において、当該利益を受ける者は、当該利益を、その者から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなす。信託の一部の受益者が受益権を放棄した場合、受益者指定権の行使(信託法89条)により既存の受益者がその受益権を失った場合等のように、一部の受益者が存しなくなり、代わりの受益者が指名されないか、指名されたが不存在の場合に本条の適用がある(相基通9の2-4)。停止条件付の受益者は権利を現に有する者ではないので受益者等に入らない。この場合、残余の受益者等が信託に関する権利の全部を有するものとみなされる(相法9条の6、相令1条の12第3項)。所得税法にも同様の規定がある(所法67条の3第5項、所令197条の3第5項、所基通13-1)。
(4)受益者等の存する信託が終了した場合
(相法9条の2第4項) 残余財産の給付受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、そのような者となった時において、そのような者は当該信託の残余財産を当該信託の受益者等から贈与(又は遺贈)により取得したもの(既有の受益権に相当する財産は除く)とみなされる。受益権複層化信託が満期に終了した時に、元本受益者が信託財産を受領するのは、既有の元本受益権に基づいて信託財産を受領するのであって、収益受益者であった者から、信託財産の贈与を受けるわけではない。しかし、受益権複層化信託が中途解約により終了した時に、収益受益権が消滅し、元本受益者が信託元本を受領した場合は、中途解約時点で収益受益者が有していた収益受益権の価額に相当する利益をその収益受益者から贈与を受けたものとして課税される(相基通9-13)。
(5)受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合(相法9条の4第1項) 受益者等が一人も存しない信託は法人課税信託になる(法法2条29号の2ロ)。受益者等の存する信託について、一部の受益者等が存しなくなったとしても、法人課税信託にはならない。受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が、その信託の委託者の親族である場合は、その信託の効力が生ずる時において、その信託の受託者は、その信託に関する権利を贈与により取得したものとみなす。
また、当該信託の受益者等の次に受益者等になる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又はその前の受益者等の親族である場合は、当該受益者等が存しないこととなった時に、その信託の受託者は、その前の受益者等からその信託に関する権利を贈与により取得したものとみなす(相法9条の4第2項)。
(6)受益者連続型信託の特例
(相法9条の3第1項) 個人の受益者が、受益者連続型信託の権利を取得した場合において、この信託が受益権複層化信託であり、当該受益者が取得した信託に関する権利に収益に関する権利が含まれるときは、信託の利益を受ける期間の制限その他の権利の価値に作用する要因としての制約はないものとみなす。受益者連続型信託の権利の価額は、個人の受益者が収益受益権の全部を取得した場合は、信託財産の全部の価額とされ、元本受益権の全部を取得した場合は零と解釈されている。当該信託の元本受益者がその信託の終了時にその信託の残余財産を取得した時は、相続税法9条の2第4項の適用があるので課税される(相基通9の3-1)。但し、収益受益者等が法人である場合又は収益受益者等が存しない場合は、元本受益権の価額は零とはみなされない。
2 信託受益権の評価方法 相続税法9条の2第1項から3項までの規定に基づき、みなし贈与または遺贈により信託の権利または利益を取得した者は当該信託財産に属する資産及び負債を取得し、継承したものとみなされる(相法9条の2第6項)ので、受益権の評価は信託財産に属する資産及び負債の評価になる。但し、債務控除は確実なものに限る(相法14条)。
信託財産が租税特別措置法の小規模宅地の評価の特例対象宅地等である場合、受益者が特例対象宅地等を取得したものとみなして、相続税の課税価額の計算の特例が適用される(措法69条の4、措令40条の2第15項、措通69の4-2)。
相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価とされている(相法22条)。時価とは取得した財産の流通市場における取引価額であるが、受益権複層化信託の受益権には流通市場がない。相続税法には定期金給付契約等の評価規定はあるが(相法24条)、受益権複層化信託の受益権の評価方法については規定がない。そこで、財産評価基本通達202は収益還元法により求めた価額を採用する。米国も同様の評価方法を採用している(脚注1)。
収益受益権の評価は、課税時期の現況において、信託財産に属する資産及び負債から推算した受益者の将来受けるべき利益の価額ごとに、課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額、元本受益権の評価は課税時期における信託財産の価額から収益受益権の価額を差し引いた価額(差し引き計算方式)とされる(評基通202)。
元本受益権の評価において、収益受益権の評価額を控除項目とする理由は、信託収益が残余財産に優先して支払われるためであり、また元本受益権の受贈者は、一定期間にわたり収益受益者に一定の給付をする負担とともに通常の(複層化されていない)信託受益権の贈与を受けた場合に類似した経済的利益を(負担付贈与を受けた場合の経済的利益)を受けることになるからと説明されている(脚注2)。
Ⅲ 典型例による当初信託財産の種類毎の問題点
信託実務で遭遇する受益権複層化信託の受益権の相続・贈与の事例は複雑であるが、典型例を基に、当初信託財産の種類毎にその問題点を洗い出す。
典型例: 資産家が遺言代用信託を設定する。資産家の生前は資産家が当初受益者であるが、その死後その受益権は遺言や代襲相続によらず、その信託証書の定めに従って跡継ぎ遺贈により承継される。資産家が亡くなると、その配偶者(収益受益権を取得)とその長男(元本受益権を取得)が第1次承継受益者になる。同配偶者が亡くなると障害のある次男(収益受益権を取得)が、同長男が亡くなるとその三男(元本受益権を取得)が第2次承継受益者になる。この受益者連続型信託の期間は20年とし、次男(2次承継収益受益者)が亡くなると、満期前であっても信託は終了するが、元本受益者が亡くなっても、信託は終了しない。
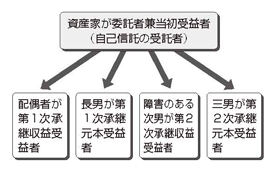
1 信託財産が債券の場合 信託財産が債券の場合、年次のクーポン収益が一定であるから、このキャッシュフローを年金として収益受益者に給付することが多い。典型例では配偶者に収益受益権を遺贈し、その老後の生活保障を行う。配偶者の受益期間はその生涯である。配偶者がもし信託開始後5年後に受益権を取得し10年後に死亡したとすれば、配偶者の受益期間は5年である。仮に配偶者が長生きしたとしても、信託の満期が信託開始後20年後に到来するので、受益期間は最長15年である。信託の満期は収益受益権に限らず元本受益権に対しても適用されるので、収益受益権の内部的制約ではなく、所与の外部的要因である。人間の命は永遠ではない。跡継ぎ遺贈の受益者連続型信託は永久に存続することはできない(信託法91条)。したがって、収益受益者の担税力は無限ではなく、外部的要因の制約を受ける。それにもかかわらず、受益者連続型信託の収益受益権は期間等の制約がない(永遠に収益を享受する)ものとされ、収益受益権の評価額は信託財産の全額になると解釈されている。しかしこのような所与の外部的要因を無視できるのであろうか(脚注3)。
また、信託債券を市場売却し譲渡所得が発生した場合、平成28年度からは譲渡所得税が課税され、収益受益者にこの納税義務があるが、譲渡所得は収益受益者に帰属しない。
信託財産が外貨建債券の場合、高利回りは魅力的であるが、為替リスクがある。その収益受益権の評価に際しては、基準年利率が円建て金利であるから、外貨建て収益を先物の為替相場により円換算額を推算した後に、基準年利率を適用して現在価値を算出すべきと考える。
信託財産が高利回りのジャンク債券の場合、債務不履行リスクをカバーするために、年次のクーポン収益にプレミアムが上乗せされている。収益受益権の評価額はこのために高くなり、元本受益権の評価額がその分低くなる。元本受益権の贈与は評価額が低くなるので、節税ができるように見えるが、債務不履行になり債券元本が償還されないリスクを考慮すると、経済的には元本受益権の評価額が低くなって当然である。
信託債券の満期が信託の満期より短い場合は、債券満期後の残存信託期間の信託収益額が当初と同じ水準に維持できるとは限らない。逆に信託の満期より長い場合は信託満期に信託債券を期待した価格で換金できるとは限らない。年金給付型の公社債投資信託は年次収益が不足する時は信託元本を取り崩して(特別分配金を)給付している。
2 信託財産が株式の場合 株式配当は必ずしも安定しない。また自社株信託では年次配当を恣意的に決めることができるので、その将来の信託収益額の見積もりによる収益受益権評価が難しい。
しかし、米国の委託者定期金留保信託(Grantor Retained Annuity Trust =GRAT)では、年次の信託収益額ではなく、一定額の定期金を給付する場合に限って税制適格とされ、残余財産受益権の評価額は信託財産を構成する資産の評価額から定期金の現在価値相当額を控除して算出する。委託者はこの評価額で残余財産受益権を委託者の親族に対して贈与することができる(内国歳入法2702条)。定期金の給付は、実際の信託収益額が定期金額より少なかった場合は不足額を信託元本から取り崩して行い、定期金額より多かった場合は余剰額を信託元本に追加する。
これに対して、委託者収益留保信託(Grantor Retained Income Trust = GRIT)では、年次の信託収益額をその多寡にかかわらずそのまま給付することができるが、委託者が元本受益権を委託者の親族に贈与することはできない。この信託の収益受益権の評価は内国歳入庁の年金数理評価表(Actuarial Valuation)を適用して求める(脚注4)。同表は信託財産の収益率を米国の基準年利率(内国歳入法7520条)と同利率と想定している。
3 信託財産が金銭の場合 信託金を有価証券にポートフォリオ運用した場合、運用益はインカムゲインのみではなく、キャピタルゲインもある。金銭信託では満期にはポートフォリオを換金し、信託元本相当額(当初信託金額)の金銭を元本受益者に交付する。信託満期の残余金又は不足金は収益受益者に帰属する。ポートフォリオ運用の場合、運用益が不確実で信託収益額の見積もりが困難であるが、信託元本は変動しない。
4 信託財産が不動産の場合 収益不動産は、収益が比較的安定しているので、受益権複層化信託の信託財産になる。収益受益者への収益配当は減価償却費控除前のキャッシュフローであることが多い。この場合、収益受益権の評価は、その純利益ではなく、減価償却費控除前の収益を計算基礎とするので、減価償却費相当額のキャッシュフロー分だけ高くなり、その結果元本受益権の評価額がその分だけ安くなる。しかし収益受益者は経済的には信託建物を、元本受益者は底地を有していると考えられる。信託満期に元本受益者に返還される信託財産は償却済みの建物と底地になり、当初の信託財産の金額ではない。元本受益権の評価額が安いからと言って節税になるわけではない。
収益受益者が受益者連続型信託の権利を取得した場合、信託の利益を受ける期間の制限等の制約はないものとみなされるが、収益不動産の信託は一般には賃貸建物が償却済みになると終了するから、収益受益権の価値が信託建物の価値以上の、底地を含む信託財産の全体にまで及ぶとは考えにくい。相続税等の資産税は納税者が取得する資産の担税力に対して課税する。収益受益権の担税力は信託建物の価値以上ではない。
Ⅳ 受益権複層化信託の相続課税に関する論点
1 複層化された受益権の評価
(1)不確実な信託収益額の見積もり 投資の自由が保障されている資本市場では、もし市場金利以上の利回りの投資商品があれば多くの市場参加者がこれを買い付けるので、この商品が値上がりし、その投資利回りが市場金利まで低下する。逆に市場金利以下の投資商品を所有する投資家は市場でこれを売り付けるので、その商品の値が下がり、その投資利回りが市場金利まで上昇する。この結果、すべての投資商品の利回りは市場金利に収斂する。相続税評価においては信託財産の見かけ上の利回りが市場金利からかい離していても、信託財産の信託満期までの利回りは結局市場金利になると想定し、相続税評価における収益受益権の割引率は市場金利に相当する基準年利率を使用することになっている。なお基準年利率は安全利子率である。
信託財産の利回りが基準年利率の場合、信託財産の評価額から収益受益権の評価額を控除して算出した元本受益権の評価額と、直接信託元本を基準年利率で割り引いて算出した元本受益権の評価額とが一致するから、信託収益額の見積もりが困難な場合の元本受益権の評価は、直接信託元本を基準年利率で割り引けばよいと考えられる(脚注5)。
(2)定期金の評価 財産評価基本通達202による収益受益権の相続税評価の基になる「受益者が将来受けるべき利益の価額」は必ずしも税務会計上の信託収益ではなく、そのキャッシュフローを指すと考えられる。利益の価額は減価償却費控除前利益の場合もあれば、定期金の場合もあると考えられる。受益権複層化信託の収益受益権は委託者亡き後のその配偶者の老後の生活の保障やその障害を持った子の療養生活の保障を目的として遺贈されることが多く、その信託給付は定額のキャッシュフロー(定期金)が望ましい。また、信託収益の見積もりが困難な場合は、定期金により信託収益の推算の困難性を排除できる。
定期金受益権は信託給付を残余財産受益権に優先して受領する点で収益受益権と変わりがない。また信託給付の時期を見ると、収益受益者には信託決算後速やかに信託収益として分配されるのに対して、定期金受益者には信託決算後一旦信託収益を元本に追加した後に元本の一部交付として分配されるので、給付の時期に差はあっても、経済的実質において差はない。
定期金受益権の権利の内容はこのように収益受益権のそれと類似しているのでその相続税評価は財産評価基本通達202の収益受益権の評価方法を準用して計算することが望ましい。相続税法の定期金給付契約の評価方法は財産評価基本通達の収益受益権の評価方法に類似する。すなわち、当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額とされる(相法24条1項1号ハ)。
(3)終身定期金の評価 高齢化社会においては生涯にわたって(終身)年金給付を受ける(生涯権)ことが望まれる。信託受益権による終身年金受給権の評価方法は財産評価基本通達202には記載がないが、平成22年度改正法によれば、信託受益権と同じく終身年金を給付する定期金給付契約の評価は、その権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数(厚生労働省が発表する完全生命表)に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額と、当該契約の解約返戻金の金額または一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額とを比較し、いずれか多い金額である(相法24条1項1号ハ)。信託受益権には予定利率、解約返戻金や一時金はないが、定期金給付契約の評価と同様に基準年利率と余命年数を用いて評価して差支えがないのではないかと思う。
定期金給付契約の評価においては、受給者の生存中の一定期間に定期金を給付する場合は、有期定期金の評価額と終身定期金の評価額のいずれか少ない金額による(相法24条3項)。定期金受益権の評価は定期金給付契約と同様にすべきであると思われる。ちなみに、米国では信託受益権の評価も定期金給付契約の評価も統一的に同一の基準年利率で行われている。
(4)受益権複層化信託の租税回避行為の事例 1つ事例を紹介する。委託者が土地に長期の信託を設定して、通常と比べて高い賃料の賃貸借契約を締結することにより、収益受益権を過大に評価し、差し引き計算で過少に評価された元本受益権をその家族に贈与した。委託者はその3年後にこの賃貸借契約を解除し、通常と比べて安い賃料の賃貸借契約を再締結し、その1年後この信託を合意解除し、元本受益者が信託財産の土地を受領した(脚注6)。
財産評価基本通達の評価は信託の効力発生の時点で見積った信託収益が満期まで継続することが前提であり、その計算基礎となる賃料が市場の水準でなければ長続きしない。収益受益者は長期に信託収益を享受することを期待しているので、受託者が中途で賃貸借契約を更改し、市場より安い賃料に切り替えることは、その善管注意義務に違反する。長期の受益権複層化信託には、適正な信託収益の見積りと信託財産の管理が必要であり、受託者に課せられる責任が重い。この事例のような不正を防止するためには、金融庁の監督のある商事信託を使うことが望ましいが、民事信託を使う場合は信託監督人の設置が望ましい。
しかし、この通達を適用する信託契約はそもそも変更不能でなければならない。米国でも同様の評価方法を適用する場合は変更不能信託(irrevocable trust)でなければならないとされる。
信託満期までの長期に渡る収益の見積もりが困難な場合は、前述の米国の委託者定期金留保信託に倣って定期金給付にすることにより、その恣意性を排除することが望ましい。
2 受益権の所得課税の偏頗性と受益権評価
(1)受益権の所得課税の偏頗性 信託収益の所得課税は、税法に明文規定はないが、実務においては担税力を理由に収益受益者に対してのみ行われ、信託満期に発生する元本受益権の評価益の所得課税は元本受益者に対しては行われない。この所得課税における収益受益者と元本受益者との間の偏頗性については、贈与者課税の米国ではほとんど問題にされていない。これに対し、元本と利息を分離するストリップ債(分離振替国債等)の場合は、評価益課税方式をとっている。信託収益の所得課税においても評価益課税方式をとるとすれば、各受益者の所得はその受領する信託利益額からその受益権の相続税評価額を差し引いた純額になり、両受益者とも所得課税を受けることになる。しかし、この課税方式をとると元本部分の課税所得を満期まで繰り延べることになるので、ストリップ債は個人には販売されていないし、個人の受益者に対する信託収益の所得課税には適用しにくい。
なお、譲渡所得は通常は元本受益者に対して課税される。
(2)所得課税の偏頗性の受益権評価に対する影響 資産承継計画では、財産を今直ちに単純贈与すべきか、相続時まで待って移転すべきか、もしくは、元本受益権の贈与が良いかが議論される。単純贈与では贈与税負担が大きいがその後の資産所得は受贈者に帰属する。相続では贈与税負担はないが相続税負担があり、相続時点までの資産所得は被相続人に帰属するが、相続により相続人に帰属する。元本受益権の贈与では元本受益権の贈与税負担が軽く、信託満期までの資産所得は委託者に帰属するが、相続により相続人に帰属する。財産の移転をこれらの3ケースに分けて、税率を同じと仮定して受贈者等の資産承継者の受領する税引き後の金額を試算してみると、財産の収益力が信託受益権評価の基準となる基準年利率と同じ場合は3ケースにおいてほとんど変わらなかったが、財産の収益力が基準年利率より高い場合は、相続より単純贈与が有利であり、元本受益権の贈与は更に有利となった。単純贈与が有利になるのは当然として、元本受益権の贈与がなぜ更に有利となったのか。この原因は、試算では税込みの信託収益額を計算基礎として収益受益権を評価したので、収益受益権の評価額が割高になり、その結果、元本受益権の評価額が割安になったためと考えられる。
信託収益が源泉分離課税の場合、所得課税の偏頗性から収益受益者は税引き後の信託収益額しか受領しない。そこで税引き後の信託収益額を計算基礎として評価すると、収益受益権の評価額が適正になり、その結果、元本受益権の評価額も適正になり、元本受益権の贈与が有利にならなかった。現行の財産評価基本通達202は「受益者が将来受け取るべき利益の額」としているので、税引き後の信託収益額を計算基礎とすべきと思われる。税引き後の信託収益額は信託所得の種類、受益者の所得水準により異なり、将来の税制改正によっても変わるので、将来受け取るべき利益の額の算定は困難であるが、課税時期の源泉分離課税率が将来も適用されるものと想定して、税引き後の信託収益額を推算する方法も考えられる。この場合の割引率は税引き割引率を使用すべきである(脚注7)。なお、実務的には値上がりしそうな資産でも、本当に値上がりするかどうかはわからないし、見かけの収益力が高い資産はリスクも高い。資産の移転時期は受贈者の浪費防止等の資産家の家庭の事情を考慮すべきであり、税務だけから資産承継時期を判断すべきではない。
3 受益者連続型信託の相続課税に関する論点
(1)受益者連続型信託の利用目的 受益者連続型信託は直系卑属の法定相続人への承継や、世代飛ばしをして資産承継の税金を節税するために使われると思われているようであるが、現実にはそうではない。例えば、事業承継においては、事業承継者の適格性が問われるので、親から子、子から孫へと言う通常の直系卑属の法定相続人への自社株承継が必ずしも適当でなく、委託者の兄弟等への承継が必要とされる場合がある。また配偶者に先立たれた資産家が前妻の子への資産承継、後妻の老後の生活保障等を行うことが必要とされる場合がある。このような場合は民法による法定相続が使えない。受益者連続型信託は、多くの場合、民法による法定相続ではなく、むしろ同世代内で望ましい資産移転を行おうとするために使われる。
(2)信託の一部の受益者が存しなくなった場合(相法9条の2第3項)と受益者連続型信託の特例(相法9条の3第1項)との関係 受益者連続型信託の第1次承継元本受益者が信託の満期前に信託財産を引き出すと、信託収益が減少し、第2次承継元本受益者の承継財産も減少するので、第1次承継元本受益者の権利を満期まで停止する場合がある(条件付の信託財産受給権)。この元本受益者は満期まで長生きしないと信託財産を受給できないので、受益者としての権利を現に有する者に該当しないと思われる(相基通9の2-1)。この場合は信託の一部の受益者等が存しないので、相続税法9条の2第3項及び相続税法施行令1条の12第3項により、収益受益者が信託に関する権利の全部を有する者とみなされ、収益受益者が信託財産の全部について課税されると思われる。
これに対し第1次承継元本受益者に信託の満期前に払い戻しを認め、信託財産を費消する権利がある場合は、この元本受益者は現に権利を有する者に該当するが、受益者連続型信託の特例(相法9条の3第1項)により、第1次承継収益受益者の収益受益権の期間その他の制約はないものとみなされるので、収益受益者が信託財産の全部の価額について課税される(相基通9の3-1)。
相基通9-13の事例は、受益権複層化信託であるが、受益者連続型信託以外の信託である。受益者連続型信託の定めによらない信託受益権の取得には、受益者連続型信託の特例の適用はない。例えば、他益信託の設定により収益の受益権を取得した場合や、受益権複層化信託の権利を相続により取得した場合は、この特例の適用がないものと思われる。受益者連続型信託に関する権利になるかならないかは、権利の内容によって判断する必要がある(脚注8)。
信託の一部の受益者が存しない場合は、相続税法9条の2第3項及び相続税法施行令1条の12第3項により、収益受益者が信託に関する権利の全部を有する者とみなされるので、相続税法基本通達9の2-4は収益受益者が残余の信託の権利を贈与により取得したものとみなされると解釈しているが、この場合、収益受益者はあらたに利益を受けることとならないので、相続税法9条の2第3項の取得の条件に当てはまらないのではないかと思われる。このみなし課税があるとすると、その後に、新たに受益者が指名されるか、停止条件付の受益権の条件が成就すると、その者に再度贈与税が課税されるリスクがある。また、信託財産が譲渡されると、譲渡の利益は元本受益者に帰属するにもかかわらず、譲渡所得税が収益受益者に課税されるリスクもある。
(3)受益者連続型信託の受益権は「収益に関する権利を含む権利」 相続税法9条の3第1項により受益権の期間その他の制約はないものとみなされる受益権は収益受益権と解釈されている(相基通9の3-1)が、「収益を含む元本受益権」ではないかと思われる。平成19年度改正税法のすべてでは、受益者連続型信託の具体例として、委託者Aの相続人B、C、Dが順番に受益権を取得する信託であって、受益者Bの受益権はその未消費分を受益者Cに残すという制約条件が付されているが、この制約条件はないものとして課税すると解説している(脚注9)。この具体例の受益者Bは元本を消費する権利があるので、収益に関する権利を含む元本受益権を有している。ちなみに、税法の条文は第1次受益者と第2次受益者以降の受益者とを区別せずに、単に「収益に関する権利が含まれる」権利と言っている。跡継ぎ遺贈を受ける受益者はいずれも信託財産の処分権がある元本受益者であるが、そのうち「収益に関する権利が含まれる」権利を現に有する受益者は第一次受益者のみであり、第二次受益者以降はその権利が確定していないので、この条文は第一次受益者のみに課税すると言っているように思われる。
(4)元本受益者が信託の満期前に元本を引き出した場合 受益者連続型信託の元本受益権を取得した時は、元本受益権の評価額が零とされるので、元本受益者は相続税を課税されないが、その後信託の満期前に信託財産を引き出した場合、相続税法9条の2第4項により引き出し額について課税されると解される(相基通9の3-1(注))。これに対し、元本受益者が通常の信託の元本受益権を取得した時は、その評価額は零とされないので、相続税を課税されるが、その後信託財産を引き出しても課税されない。典型例(今号17頁参照)の第1次承継元本受益者の権利が当初から確定し、信託財産を費消することができるのであれば、元本受益者が受益者としての権利を現に有するので、当初に元本受益者に課税すべきであるとする意見がある(脚注10)。
(5)受益者連続型信託の特例(相法9条の3第1項)の相続税法内の位置 相続税法9条の3第1項は、受益者連続型信託の受益権の評価を定めたものと解説されているが、この規定の位置は相続税法第1章総則にあり、第3章財産評価ではない。この規定は受益権の価格の計算方法を示しているだけで、その課税価額を信託財産の全部とすると規定しているわけではない。
相続税の財産評価は相続税法第3章に定めがあり、その課税は財産評価額に基づく。相続財産の評価は相続税法22条によればその時価に基づくことになっている。時価とは取引価額であり、経済的価値と考えられる。収益受益権の権利の価額が相続税法9条の3第1項により信託財産の評価額の全部となるとしても、収益受益者は元本受益者に対し信託財産から元本を支払う債務を確実に負っているので、その経済的価値は負担付遺贈の評価と同じように負担部分(元本受益権の評価額)を差し引いた(債務控除後の)純額になると思われる(脚注11)。
(6)信託の受託者課税(相法9条の4第2項)の可能性 相続税法9条の4第2項は受益者等が存する信託について、受益者等が存しないこととなった場合について、次の受益者等が前の受益者等の親族である場合は、受益者等が存しないこととなった時に、当該信託の受託者は、前の受益者等から、当該信託に関する権利を贈与(又は遺贈)により取得したものとみなす。この規定は部分的に受益者等が不存在になる場合には適用がない。しかし、もし受益者連続型信託の元本受益者への課税が適切でない場合は、この条文を適用して、受託者が委託者又は前の受益者等から、元本受益権を贈与(又は遺贈)により取得したものとみなして、受託者に課税してはどうであろうか。収益受益者に対し、収益受益権の担税力を超過する(信託財産全体に対する)課税を強化するよりも、受託者にその超過分(元本受益権相当分)を課税した方が課税の公平性を確保できる。この場合、信託財産は受託者の納税額分減少し、元本受益者への残余財産の交付額がこの分減少するので、経済的には元本受益者が納税額を負担したことになる。この受託者課税は一部の受益者等が存しなくなった場合(相法9条の2第3項)にも応用できるのではないか。
Ⅴ 結 語
筆者が米国の信託税制を勉強したのは今から約40年前のことである。その時印象に残ったことは、米国では受益権複層化信託が広く利用されていること、信託が法人(entity)として課税主体になること、世代飛び越し税の導入が議論されていたことである。それから約30年経過し、日本では、平成19年度の税制改正で、法人課税信託が認められ、米国では1976年に世代を飛び越し移転税(Generation-skipping transfer tax)が創設された。しかし、日本ではまだ受益権複層化信託が広く利用されていないので、本稿がその利用のためにお役に立てば幸甚である。受益者連続型信託の問題に関しては複雑であり、税務当局の検討を待ちたい。
脚注
1 現行の相続税財産評価基本通達は昭和39年に遡るが、収益還元法は26年1月に制定された富裕税財産評価事務取扱通達に遡る。このとき米国も既に収益還元法であった。評価に使われる割引率は日米共に当初は固定金利であったが、米国では1988から米国国債の利回りに基づく基準年利率に、日本も平成11年(1999年)から日本国債の利回りに基づく基準年利率に改定された。また当初は収益受益権と元本受益権とを別々に評価し、両受益権の合計額が信託財産を構成する資産及び負債の評価額からかけ離れるケースがあったが、平成12年6月に現行の差し引き計算方式に改正され、両受益権の合計額が常に同資産の評価額に一致するようになったので、節税が封じられたと報道された(「週刊税務通信」平成12年8月28日号)。
2 平成12年12月、財団法人大蔵財務協会発行、横山恒美編「財産評価基本通達逐条解説」全訂版P755。
3 橋本守次先生は「ゼミナール相続税法」大蔵財務協会P677~678において、このような受益権の評価は理解できないと書いておられる。
4 連邦歳入法7520条には、有期定期金、終身定期金、不動産生涯権、残余財産受益権等の多様な権利毎に複利表が用意されている。
5 山田煕「月刊税理」平成12年Vol43、No.10。
6 川口幸彦「信託法改正と相続税・贈与税の諸問題」(税務大学校論叢2008)事例13、P428~429。川口先生は、この事例では収益受益権の計算基礎となる賃料の見積もりが適正ではなかった。長期の信託の収益受益権を短期の賃料見積りにより評価すべきはない、と指摘している。
7 税引き割引率は源泉分離課税等を適用して求める。
8 信託協会松永和美「財産の管理・承継に利用される信託の税制に関する一考察」信託法研究32号2007年、P105。
9 この解説は相続税法9条の3第1項の受益者連続型信託の権利の説明とされているが、その内容は相続税法9条の2第2項の説明に過ぎず、収益受益権の制約条件はないものとして課税することの説明ではない。
10 橋本康平「受益者連続信託における資産税課税の検討」立命館法政論集9号2011、P147:遺言代用信託において親の死亡により妻が収益受益権、子が元本受益権を取得した場合に、子も不確定期限付きの残余財産受益権を確定的に取得するので、妻と子の両方に課税すべきであり、受益者連続型信託の課税の特例の適用はないとしている。
11 横山恒美編、注2前掲書P757。
受益権複層化信託の相続課税
高橋倫彦
Ⅰ 本稿の趣旨
本稿は2015年6月15日号の本誌に掲載した「受益権複層化信託の所得課税」の後編として受益権複層化信託の相続・贈与課税について検討したものである。複層化した信託受益権やその受益者連続型信託の権利の税務上の取り扱いについては議論があり、その税制改正の要望もなされているが、本稿は、現行法を忠実に適用した場合の税務上の取り扱いの明確化を目的とする。筆者は長年信託業務に従事した経験を基に、手元の事例に基づき、利用者の意図(信託目的)に照らして、信託の権利の内容と、経済合理性とを根拠に、実務的観点から現行法の適用の可能性を検討した。実務的観点からの文献がほとんど公表されていないなか、本稿は、今後の税務の専門家の方々による研究の一助になることを期待し執筆した。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 受益権複層化信託の相続課税の原則
受益権複層化信託とは収益受益権や元本受益権のように受益権の質が異なる受益権が複数ある信託を言う(相基通9-13)。受益権を優先・劣後構造にする法人信託もこれに近い。税法上は受益者が2以上ある場合は、信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその権利の内容に応じて有するものとされる(法令15条4項、所令52条4項)。つまり、信託財産に二重所有(複層化)を認めつつ、それぞれの権利は異なるものとされる。なお、本稿は受益者等課税信託を検討の対象とする。
1 受益権の課税時期 相続・贈与による受益権の取得は適正な対価を負担していないので相続・贈与税が課税される。委託者以外の者が受益権を取得した場合は、実体法にとらわれずにその経済的実質を見ると委託者又は前の受益者等から受益権が相続・贈与されているので、相続税法では第1章第3節に「信託に関する特例」を設けて、このような場合の信託受益権の取得を相続・贈与による取得とみなしている。
(1)受益者としての権利を現に有する者
(相法9条の2第1項) 受益者等とは受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者を言うものとされる(相法9条の2第1項)。この権利を現に有する者には、残余財産受益者(信託法182条1項1号)は含まれるが、受益権に停止条件又は効力発生の始期が付されている場合、受益者がまだ存在(生誕)しない場合、又は特定されていない場合の受益者は含まない(相基通9の2-1)。従って遺言代用信託(信託法90条1項各号)の委託者死亡前の受益者や帰属権利者(信託法182条1項2号)は含まれない。
受益権複層化信託の元本受益者は、信託が終了した時に、収益受益権の消滅により信託財産を受領するが、元本受益権に停止条件が付されていないので、受益者としての権利を現に有する者に含まれる。しかし受益者連続型信託の権利の第二次以後の承継受益者は、信託の効力が生じたときに指定されているが、既存の受益者が死亡し、その受益権が消滅した時に、新たに受益権を取得するので、この権利を現に有する者ではない。
(2)新たに受益権を取得した場合
(相法9条の2第1項及び第2項) 他益信託の設定による受益権の取得は、当該信託の効力が生じた時において、受益権を委託者から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなされる(相法9条の2第1項)。
自益信託等の受益者等の存する信託について新たに受益者等となる者は、受益者等となった時に、当該信託の受益権を前の受益者等から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなされる(相法9条の2第2項)。自益信託の受益権が複層化され、複層化された受益権を取得した場合は、委託者から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなされる。受益者連続型信託(相法9条の3第1項、相令1条の8)の定めに従って、新たに当該信託の受益者等が存するに至った場合、実体法的に見ると継伝的な遺贈ではない場合であっても、前の受益者から継伝的に取得したものとみなされる。跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託(信託法91条)の受益者の死亡により新たに受益者になる場合も、受益者指定権の行使(信託法89条)により新たに当該信託の受益者となる場合も、受益者連続型信託に該当する。
(3)受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった場合(相法9条の2第3項) 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなった場合、既存の受益者等がその受益権について新たに利益を受けることとなるときは、その者が存しなくなった時において、当該利益を受ける者は、当該利益を、その者から贈与(又は遺贈)により取得したものとみなす。信託の一部の受益者が受益権を放棄した場合、受益者指定権の行使(信託法89条)により既存の受益者がその受益権を失った場合等のように、一部の受益者が存しなくなり、代わりの受益者が指名されないか、指名されたが不存在の場合に本条の適用がある(相基通9の2-4)。停止条件付の受益者は権利を現に有する者ではないので受益者等に入らない。この場合、残余の受益者等が信託に関する権利の全部を有するものとみなされる(相法9条の6、相令1条の12第3項)。所得税法にも同様の規定がある(所法67条の3第5項、所令197条の3第5項、所基通13-1)。
(4)受益者等の存する信託が終了した場合
(相法9条の2第4項) 残余財産の給付受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、そのような者となった時において、そのような者は当該信託の残余財産を当該信託の受益者等から贈与(又は遺贈)により取得したもの(既有の受益権に相当する財産は除く)とみなされる。受益権複層化信託が満期に終了した時に、元本受益者が信託財産を受領するのは、既有の元本受益権に基づいて信託財産を受領するのであって、収益受益者であった者から、信託財産の贈与を受けるわけではない。しかし、受益権複層化信託が中途解約により終了した時に、収益受益権が消滅し、元本受益者が信託元本を受領した場合は、中途解約時点で収益受益者が有していた収益受益権の価額に相当する利益をその収益受益者から贈与を受けたものとして課税される(相基通9-13)。
(5)受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合(相法9条の4第1項) 受益者等が一人も存しない信託は法人課税信託になる(法法2条29号の2ロ)。受益者等の存する信託について、一部の受益者等が存しなくなったとしても、法人課税信託にはならない。受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が、その信託の委託者の親族である場合は、その信託の効力が生ずる時において、その信託の受託者は、その信託に関する権利を贈与により取得したものとみなす。
また、当該信託の受益者等の次に受益者等になる者が当該信託の効力が生じた時の委託者又はその前の受益者等の親族である場合は、当該受益者等が存しないこととなった時に、その信託の受託者は、その前の受益者等からその信託に関する権利を贈与により取得したものとみなす(相法9条の4第2項)。
(6)受益者連続型信託の特例
(相法9条の3第1項) 個人の受益者が、受益者連続型信託の権利を取得した場合において、この信託が受益権複層化信託であり、当該受益者が取得した信託に関する権利に収益に関する権利が含まれるときは、信託の利益を受ける期間の制限その他の権利の価値に作用する要因としての制約はないものとみなす。受益者連続型信託の権利の価額は、個人の受益者が収益受益権の全部を取得した場合は、信託財産の全部の価額とされ、元本受益権の全部を取得した場合は零と解釈されている。当該信託の元本受益者がその信託の終了時にその信託の残余財産を取得した時は、相続税法9条の2第4項の適用があるので課税される(相基通9の3-1)。但し、収益受益者等が法人である場合又は収益受益者等が存しない場合は、元本受益権の価額は零とはみなされない。
2 信託受益権の評価方法 相続税法9条の2第1項から3項までの規定に基づき、みなし贈与または遺贈により信託の権利または利益を取得した者は当該信託財産に属する資産及び負債を取得し、継承したものとみなされる(相法9条の2第6項)ので、受益権の評価は信託財産に属する資産及び負債の評価になる。但し、債務控除は確実なものに限る(相法14条)。
信託財産が租税特別措置法の小規模宅地の評価の特例対象宅地等である場合、受益者が特例対象宅地等を取得したものとみなして、相続税の課税価額の計算の特例が適用される(措法69条の4、措令40条の2第15項、措通69の4-2)。
相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価とされている(相法22条)。時価とは取得した財産の流通市場における取引価額であるが、受益権複層化信託の受益権には流通市場がない。相続税法には定期金給付契約等の評価規定はあるが(相法24条)、受益権複層化信託の受益権の評価方法については規定がない。そこで、財産評価基本通達202は収益還元法により求めた価額を採用する。米国も同様の評価方法を採用している(脚注1)。
収益受益権の評価は、課税時期の現況において、信託財産に属する資産及び負債から推算した受益者の将来受けるべき利益の価額ごとに、課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額、元本受益権の評価は課税時期における信託財産の価額から収益受益権の価額を差し引いた価額(差し引き計算方式)とされる(評基通202)。
元本受益権の評価において、収益受益権の評価額を控除項目とする理由は、信託収益が残余財産に優先して支払われるためであり、また元本受益権の受贈者は、一定期間にわたり収益受益者に一定の給付をする負担とともに通常の(複層化されていない)信託受益権の贈与を受けた場合に類似した経済的利益を(負担付贈与を受けた場合の経済的利益)を受けることになるからと説明されている(脚注2)。
Ⅲ 典型例による当初信託財産の種類毎の問題点
信託実務で遭遇する受益権複層化信託の受益権の相続・贈与の事例は複雑であるが、典型例を基に、当初信託財産の種類毎にその問題点を洗い出す。
典型例: 資産家が遺言代用信託を設定する。資産家の生前は資産家が当初受益者であるが、その死後その受益権は遺言や代襲相続によらず、その信託証書の定めに従って跡継ぎ遺贈により承継される。資産家が亡くなると、その配偶者(収益受益権を取得)とその長男(元本受益権を取得)が第1次承継受益者になる。同配偶者が亡くなると障害のある次男(収益受益権を取得)が、同長男が亡くなるとその三男(元本受益権を取得)が第2次承継受益者になる。この受益者連続型信託の期間は20年とし、次男(2次承継収益受益者)が亡くなると、満期前であっても信託は終了するが、元本受益者が亡くなっても、信託は終了しない。
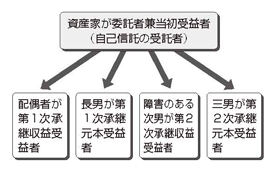
1 信託財産が債券の場合 信託財産が債券の場合、年次のクーポン収益が一定であるから、このキャッシュフローを年金として収益受益者に給付することが多い。典型例では配偶者に収益受益権を遺贈し、その老後の生活保障を行う。配偶者の受益期間はその生涯である。配偶者がもし信託開始後5年後に受益権を取得し10年後に死亡したとすれば、配偶者の受益期間は5年である。仮に配偶者が長生きしたとしても、信託の満期が信託開始後20年後に到来するので、受益期間は最長15年である。信託の満期は収益受益権に限らず元本受益権に対しても適用されるので、収益受益権の内部的制約ではなく、所与の外部的要因である。人間の命は永遠ではない。跡継ぎ遺贈の受益者連続型信託は永久に存続することはできない(信託法91条)。したがって、収益受益者の担税力は無限ではなく、外部的要因の制約を受ける。それにもかかわらず、受益者連続型信託の収益受益権は期間等の制約がない(永遠に収益を享受する)ものとされ、収益受益権の評価額は信託財産の全額になると解釈されている。しかしこのような所与の外部的要因を無視できるのであろうか(脚注3)。
また、信託債券を市場売却し譲渡所得が発生した場合、平成28年度からは譲渡所得税が課税され、収益受益者にこの納税義務があるが、譲渡所得は収益受益者に帰属しない。
信託財産が外貨建債券の場合、高利回りは魅力的であるが、為替リスクがある。その収益受益権の評価に際しては、基準年利率が円建て金利であるから、外貨建て収益を先物の為替相場により円換算額を推算した後に、基準年利率を適用して現在価値を算出すべきと考える。
信託財産が高利回りのジャンク債券の場合、債務不履行リスクをカバーするために、年次のクーポン収益にプレミアムが上乗せされている。収益受益権の評価額はこのために高くなり、元本受益権の評価額がその分低くなる。元本受益権の贈与は評価額が低くなるので、節税ができるように見えるが、債務不履行になり債券元本が償還されないリスクを考慮すると、経済的には元本受益権の評価額が低くなって当然である。
信託債券の満期が信託の満期より短い場合は、債券満期後の残存信託期間の信託収益額が当初と同じ水準に維持できるとは限らない。逆に信託の満期より長い場合は信託満期に信託債券を期待した価格で換金できるとは限らない。年金給付型の公社債投資信託は年次収益が不足する時は信託元本を取り崩して(特別分配金を)給付している。
2 信託財産が株式の場合 株式配当は必ずしも安定しない。また自社株信託では年次配当を恣意的に決めることができるので、その将来の信託収益額の見積もりによる収益受益権評価が難しい。
しかし、米国の委託者定期金留保信託(Grantor Retained Annuity Trust =GRAT)では、年次の信託収益額ではなく、一定額の定期金を給付する場合に限って税制適格とされ、残余財産受益権の評価額は信託財産を構成する資産の評価額から定期金の現在価値相当額を控除して算出する。委託者はこの評価額で残余財産受益権を委託者の親族に対して贈与することができる(内国歳入法2702条)。定期金の給付は、実際の信託収益額が定期金額より少なかった場合は不足額を信託元本から取り崩して行い、定期金額より多かった場合は余剰額を信託元本に追加する。
これに対して、委託者収益留保信託(Grantor Retained Income Trust = GRIT)では、年次の信託収益額をその多寡にかかわらずそのまま給付することができるが、委託者が元本受益権を委託者の親族に贈与することはできない。この信託の収益受益権の評価は内国歳入庁の年金数理評価表(Actuarial Valuation)を適用して求める(脚注4)。同表は信託財産の収益率を米国の基準年利率(内国歳入法7520条)と同利率と想定している。
3 信託財産が金銭の場合 信託金を有価証券にポートフォリオ運用した場合、運用益はインカムゲインのみではなく、キャピタルゲインもある。金銭信託では満期にはポートフォリオを換金し、信託元本相当額(当初信託金額)の金銭を元本受益者に交付する。信託満期の残余金又は不足金は収益受益者に帰属する。ポートフォリオ運用の場合、運用益が不確実で信託収益額の見積もりが困難であるが、信託元本は変動しない。
4 信託財産が不動産の場合 収益不動産は、収益が比較的安定しているので、受益権複層化信託の信託財産になる。収益受益者への収益配当は減価償却費控除前のキャッシュフローであることが多い。この場合、収益受益権の評価は、その純利益ではなく、減価償却費控除前の収益を計算基礎とするので、減価償却費相当額のキャッシュフロー分だけ高くなり、その結果元本受益権の評価額がその分だけ安くなる。しかし収益受益者は経済的には信託建物を、元本受益者は底地を有していると考えられる。信託満期に元本受益者に返還される信託財産は償却済みの建物と底地になり、当初の信託財産の金額ではない。元本受益権の評価額が安いからと言って節税になるわけではない。
収益受益者が受益者連続型信託の権利を取得した場合、信託の利益を受ける期間の制限等の制約はないものとみなされるが、収益不動産の信託は一般には賃貸建物が償却済みになると終了するから、収益受益権の価値が信託建物の価値以上の、底地を含む信託財産の全体にまで及ぶとは考えにくい。相続税等の資産税は納税者が取得する資産の担税力に対して課税する。収益受益権の担税力は信託建物の価値以上ではない。
Ⅳ 受益権複層化信託の相続課税に関する論点
1 複層化された受益権の評価
(1)不確実な信託収益額の見積もり 投資の自由が保障されている資本市場では、もし市場金利以上の利回りの投資商品があれば多くの市場参加者がこれを買い付けるので、この商品が値上がりし、その投資利回りが市場金利まで低下する。逆に市場金利以下の投資商品を所有する投資家は市場でこれを売り付けるので、その商品の値が下がり、その投資利回りが市場金利まで上昇する。この結果、すべての投資商品の利回りは市場金利に収斂する。相続税評価においては信託財産の見かけ上の利回りが市場金利からかい離していても、信託財産の信託満期までの利回りは結局市場金利になると想定し、相続税評価における収益受益権の割引率は市場金利に相当する基準年利率を使用することになっている。なお基準年利率は安全利子率である。
信託財産の利回りが基準年利率の場合、信託財産の評価額から収益受益権の評価額を控除して算出した元本受益権の評価額と、直接信託元本を基準年利率で割り引いて算出した元本受益権の評価額とが一致するから、信託収益額の見積もりが困難な場合の元本受益権の評価は、直接信託元本を基準年利率で割り引けばよいと考えられる(脚注5)。
(2)定期金の評価 財産評価基本通達202による収益受益権の相続税評価の基になる「受益者が将来受けるべき利益の価額」は必ずしも税務会計上の信託収益ではなく、そのキャッシュフローを指すと考えられる。利益の価額は減価償却費控除前利益の場合もあれば、定期金の場合もあると考えられる。受益権複層化信託の収益受益権は委託者亡き後のその配偶者の老後の生活の保障やその障害を持った子の療養生活の保障を目的として遺贈されることが多く、その信託給付は定額のキャッシュフロー(定期金)が望ましい。また、信託収益の見積もりが困難な場合は、定期金により信託収益の推算の困難性を排除できる。
定期金受益権は信託給付を残余財産受益権に優先して受領する点で収益受益権と変わりがない。また信託給付の時期を見ると、収益受益者には信託決算後速やかに信託収益として分配されるのに対して、定期金受益者には信託決算後一旦信託収益を元本に追加した後に元本の一部交付として分配されるので、給付の時期に差はあっても、経済的実質において差はない。
定期金受益権の権利の内容はこのように収益受益権のそれと類似しているのでその相続税評価は財産評価基本通達202の収益受益権の評価方法を準用して計算することが望ましい。相続税法の定期金給付契約の評価方法は財産評価基本通達の収益受益権の評価方法に類似する。すなわち、当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額とされる(相法24条1項1号ハ)。
(3)終身定期金の評価 高齢化社会においては生涯にわたって(終身)年金給付を受ける(生涯権)ことが望まれる。信託受益権による終身年金受給権の評価方法は財産評価基本通達202には記載がないが、平成22年度改正法によれば、信託受益権と同じく終身年金を給付する定期金給付契約の評価は、その権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数(厚生労働省が発表する完全生命表)に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額と、当該契約の解約返戻金の金額または一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき一時金の金額とを比較し、いずれか多い金額である(相法24条1項1号ハ)。信託受益権には予定利率、解約返戻金や一時金はないが、定期金給付契約の評価と同様に基準年利率と余命年数を用いて評価して差支えがないのではないかと思う。
定期金給付契約の評価においては、受給者の生存中の一定期間に定期金を給付する場合は、有期定期金の評価額と終身定期金の評価額のいずれか少ない金額による(相法24条3項)。定期金受益権の評価は定期金給付契約と同様にすべきであると思われる。ちなみに、米国では信託受益権の評価も定期金給付契約の評価も統一的に同一の基準年利率で行われている。
(4)受益権複層化信託の租税回避行為の事例 1つ事例を紹介する。委託者が土地に長期の信託を設定して、通常と比べて高い賃料の賃貸借契約を締結することにより、収益受益権を過大に評価し、差し引き計算で過少に評価された元本受益権をその家族に贈与した。委託者はその3年後にこの賃貸借契約を解除し、通常と比べて安い賃料の賃貸借契約を再締結し、その1年後この信託を合意解除し、元本受益者が信託財産の土地を受領した(脚注6)。
財産評価基本通達の評価は信託の効力発生の時点で見積った信託収益が満期まで継続することが前提であり、その計算基礎となる賃料が市場の水準でなければ長続きしない。収益受益者は長期に信託収益を享受することを期待しているので、受託者が中途で賃貸借契約を更改し、市場より安い賃料に切り替えることは、その善管注意義務に違反する。長期の受益権複層化信託には、適正な信託収益の見積りと信託財産の管理が必要であり、受託者に課せられる責任が重い。この事例のような不正を防止するためには、金融庁の監督のある商事信託を使うことが望ましいが、民事信託を使う場合は信託監督人の設置が望ましい。
しかし、この通達を適用する信託契約はそもそも変更不能でなければならない。米国でも同様の評価方法を適用する場合は変更不能信託(irrevocable trust)でなければならないとされる。
信託満期までの長期に渡る収益の見積もりが困難な場合は、前述の米国の委託者定期金留保信託に倣って定期金給付にすることにより、その恣意性を排除することが望ましい。
2 受益権の所得課税の偏頗性と受益権評価
(1)受益権の所得課税の偏頗性 信託収益の所得課税は、税法に明文規定はないが、実務においては担税力を理由に収益受益者に対してのみ行われ、信託満期に発生する元本受益権の評価益の所得課税は元本受益者に対しては行われない。この所得課税における収益受益者と元本受益者との間の偏頗性については、贈与者課税の米国ではほとんど問題にされていない。これに対し、元本と利息を分離するストリップ債(分離振替国債等)の場合は、評価益課税方式をとっている。信託収益の所得課税においても評価益課税方式をとるとすれば、各受益者の所得はその受領する信託利益額からその受益権の相続税評価額を差し引いた純額になり、両受益者とも所得課税を受けることになる。しかし、この課税方式をとると元本部分の課税所得を満期まで繰り延べることになるので、ストリップ債は個人には販売されていないし、個人の受益者に対する信託収益の所得課税には適用しにくい。
なお、譲渡所得は通常は元本受益者に対して課税される。
(2)所得課税の偏頗性の受益権評価に対する影響 資産承継計画では、財産を今直ちに単純贈与すべきか、相続時まで待って移転すべきか、もしくは、元本受益権の贈与が良いかが議論される。単純贈与では贈与税負担が大きいがその後の資産所得は受贈者に帰属する。相続では贈与税負担はないが相続税負担があり、相続時点までの資産所得は被相続人に帰属するが、相続により相続人に帰属する。元本受益権の贈与では元本受益権の贈与税負担が軽く、信託満期までの資産所得は委託者に帰属するが、相続により相続人に帰属する。財産の移転をこれらの3ケースに分けて、税率を同じと仮定して受贈者等の資産承継者の受領する税引き後の金額を試算してみると、財産の収益力が信託受益権評価の基準となる基準年利率と同じ場合は3ケースにおいてほとんど変わらなかったが、財産の収益力が基準年利率より高い場合は、相続より単純贈与が有利であり、元本受益権の贈与は更に有利となった。単純贈与が有利になるのは当然として、元本受益権の贈与がなぜ更に有利となったのか。この原因は、試算では税込みの信託収益額を計算基礎として収益受益権を評価したので、収益受益権の評価額が割高になり、その結果、元本受益権の評価額が割安になったためと考えられる。
信託収益が源泉分離課税の場合、所得課税の偏頗性から収益受益者は税引き後の信託収益額しか受領しない。そこで税引き後の信託収益額を計算基礎として評価すると、収益受益権の評価額が適正になり、その結果、元本受益権の評価額も適正になり、元本受益権の贈与が有利にならなかった。現行の財産評価基本通達202は「受益者が将来受け取るべき利益の額」としているので、税引き後の信託収益額を計算基礎とすべきと思われる。税引き後の信託収益額は信託所得の種類、受益者の所得水準により異なり、将来の税制改正によっても変わるので、将来受け取るべき利益の額の算定は困難であるが、課税時期の源泉分離課税率が将来も適用されるものと想定して、税引き後の信託収益額を推算する方法も考えられる。この場合の割引率は税引き割引率を使用すべきである(脚注7)。なお、実務的には値上がりしそうな資産でも、本当に値上がりするかどうかはわからないし、見かけの収益力が高い資産はリスクも高い。資産の移転時期は受贈者の浪費防止等の資産家の家庭の事情を考慮すべきであり、税務だけから資産承継時期を判断すべきではない。
3 受益者連続型信託の相続課税に関する論点
(1)受益者連続型信託の利用目的 受益者連続型信託は直系卑属の法定相続人への承継や、世代飛ばしをして資産承継の税金を節税するために使われると思われているようであるが、現実にはそうではない。例えば、事業承継においては、事業承継者の適格性が問われるので、親から子、子から孫へと言う通常の直系卑属の法定相続人への自社株承継が必ずしも適当でなく、委託者の兄弟等への承継が必要とされる場合がある。また配偶者に先立たれた資産家が前妻の子への資産承継、後妻の老後の生活保障等を行うことが必要とされる場合がある。このような場合は民法による法定相続が使えない。受益者連続型信託は、多くの場合、民法による法定相続ではなく、むしろ同世代内で望ましい資産移転を行おうとするために使われる。
(2)信託の一部の受益者が存しなくなった場合(相法9条の2第3項)と受益者連続型信託の特例(相法9条の3第1項)との関係 受益者連続型信託の第1次承継元本受益者が信託の満期前に信託財産を引き出すと、信託収益が減少し、第2次承継元本受益者の承継財産も減少するので、第1次承継元本受益者の権利を満期まで停止する場合がある(条件付の信託財産受給権)。この元本受益者は満期まで長生きしないと信託財産を受給できないので、受益者としての権利を現に有する者に該当しないと思われる(相基通9の2-1)。この場合は信託の一部の受益者等が存しないので、相続税法9条の2第3項及び相続税法施行令1条の12第3項により、収益受益者が信託に関する権利の全部を有する者とみなされ、収益受益者が信託財産の全部について課税されると思われる。
これに対し第1次承継元本受益者に信託の満期前に払い戻しを認め、信託財産を費消する権利がある場合は、この元本受益者は現に権利を有する者に該当するが、受益者連続型信託の特例(相法9条の3第1項)により、第1次承継収益受益者の収益受益権の期間その他の制約はないものとみなされるので、収益受益者が信託財産の全部の価額について課税される(相基通9の3-1)。
相基通9-13の事例は、受益権複層化信託であるが、受益者連続型信託以外の信託である。受益者連続型信託の定めによらない信託受益権の取得には、受益者連続型信託の特例の適用はない。例えば、他益信託の設定により収益の受益権を取得した場合や、受益権複層化信託の権利を相続により取得した場合は、この特例の適用がないものと思われる。受益者連続型信託に関する権利になるかならないかは、権利の内容によって判断する必要がある(脚注8)。
信託の一部の受益者が存しない場合は、相続税法9条の2第3項及び相続税法施行令1条の12第3項により、収益受益者が信託に関する権利の全部を有する者とみなされるので、相続税法基本通達9の2-4は収益受益者が残余の信託の権利を贈与により取得したものとみなされると解釈しているが、この場合、収益受益者はあらたに利益を受けることとならないので、相続税法9条の2第3項の取得の条件に当てはまらないのではないかと思われる。このみなし課税があるとすると、その後に、新たに受益者が指名されるか、停止条件付の受益権の条件が成就すると、その者に再度贈与税が課税されるリスクがある。また、信託財産が譲渡されると、譲渡の利益は元本受益者に帰属するにもかかわらず、譲渡所得税が収益受益者に課税されるリスクもある。
(3)受益者連続型信託の受益権は「収益に関する権利を含む権利」 相続税法9条の3第1項により受益権の期間その他の制約はないものとみなされる受益権は収益受益権と解釈されている(相基通9の3-1)が、「収益を含む元本受益権」ではないかと思われる。平成19年度改正税法のすべてでは、受益者連続型信託の具体例として、委託者Aの相続人B、C、Dが順番に受益権を取得する信託であって、受益者Bの受益権はその未消費分を受益者Cに残すという制約条件が付されているが、この制約条件はないものとして課税すると解説している(脚注9)。この具体例の受益者Bは元本を消費する権利があるので、収益に関する権利を含む元本受益権を有している。ちなみに、税法の条文は第1次受益者と第2次受益者以降の受益者とを区別せずに、単に「収益に関する権利が含まれる」権利と言っている。跡継ぎ遺贈を受ける受益者はいずれも信託財産の処分権がある元本受益者であるが、そのうち「収益に関する権利が含まれる」権利を現に有する受益者は第一次受益者のみであり、第二次受益者以降はその権利が確定していないので、この条文は第一次受益者のみに課税すると言っているように思われる。
(4)元本受益者が信託の満期前に元本を引き出した場合 受益者連続型信託の元本受益権を取得した時は、元本受益権の評価額が零とされるので、元本受益者は相続税を課税されないが、その後信託の満期前に信託財産を引き出した場合、相続税法9条の2第4項により引き出し額について課税されると解される(相基通9の3-1(注))。これに対し、元本受益者が通常の信託の元本受益権を取得した時は、その評価額は零とされないので、相続税を課税されるが、その後信託財産を引き出しても課税されない。典型例(今号17頁参照)の第1次承継元本受益者の権利が当初から確定し、信託財産を費消することができるのであれば、元本受益者が受益者としての権利を現に有するので、当初に元本受益者に課税すべきであるとする意見がある(脚注10)。
(5)受益者連続型信託の特例(相法9条の3第1項)の相続税法内の位置 相続税法9条の3第1項は、受益者連続型信託の受益権の評価を定めたものと解説されているが、この規定の位置は相続税法第1章総則にあり、第3章財産評価ではない。この規定は受益権の価格の計算方法を示しているだけで、その課税価額を信託財産の全部とすると規定しているわけではない。
相続税の財産評価は相続税法第3章に定めがあり、その課税は財産評価額に基づく。相続財産の評価は相続税法22条によればその時価に基づくことになっている。時価とは取引価額であり、経済的価値と考えられる。収益受益権の権利の価額が相続税法9条の3第1項により信託財産の評価額の全部となるとしても、収益受益者は元本受益者に対し信託財産から元本を支払う債務を確実に負っているので、その経済的価値は負担付遺贈の評価と同じように負担部分(元本受益権の評価額)を差し引いた(債務控除後の)純額になると思われる(脚注11)。
(6)信託の受託者課税(相法9条の4第2項)の可能性 相続税法9条の4第2項は受益者等が存する信託について、受益者等が存しないこととなった場合について、次の受益者等が前の受益者等の親族である場合は、受益者等が存しないこととなった時に、当該信託の受託者は、前の受益者等から、当該信託に関する権利を贈与(又は遺贈)により取得したものとみなす。この規定は部分的に受益者等が不存在になる場合には適用がない。しかし、もし受益者連続型信託の元本受益者への課税が適切でない場合は、この条文を適用して、受託者が委託者又は前の受益者等から、元本受益権を贈与(又は遺贈)により取得したものとみなして、受託者に課税してはどうであろうか。収益受益者に対し、収益受益権の担税力を超過する(信託財産全体に対する)課税を強化するよりも、受託者にその超過分(元本受益権相当分)を課税した方が課税の公平性を確保できる。この場合、信託財産は受託者の納税額分減少し、元本受益者への残余財産の交付額がこの分減少するので、経済的には元本受益者が納税額を負担したことになる。この受託者課税は一部の受益者等が存しなくなった場合(相法9条の2第3項)にも応用できるのではないか。
Ⅴ 結 語
筆者が米国の信託税制を勉強したのは今から約40年前のことである。その時印象に残ったことは、米国では受益権複層化信託が広く利用されていること、信託が法人(entity)として課税主体になること、世代飛び越し税の導入が議論されていたことである。それから約30年経過し、日本では、平成19年度の税制改正で、法人課税信託が認められ、米国では1976年に世代を飛び越し移転税(Generation-skipping transfer tax)が創設された。しかし、日本ではまだ受益権複層化信託が広く利用されていないので、本稿がその利用のためにお役に立てば幸甚である。受益者連続型信託の問題に関しては複雑であり、税務当局の検討を待ちたい。
| 高橋倫彦 たかはし ともひこ 東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)、外資系の信託銀行を経て、最近までベルニナ信託(現FPG信託)の取締役。富裕層向けの信託の設計では15年以上の経験を有す。家族信託の分野では日本でも数少ない専門家。 著書に『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』日本法令(共著)がある。 |
脚注
1 現行の相続税財産評価基本通達は昭和39年に遡るが、収益還元法は26年1月に制定された富裕税財産評価事務取扱通達に遡る。このとき米国も既に収益還元法であった。評価に使われる割引率は日米共に当初は固定金利であったが、米国では1988から米国国債の利回りに基づく基準年利率に、日本も平成11年(1999年)から日本国債の利回りに基づく基準年利率に改定された。また当初は収益受益権と元本受益権とを別々に評価し、両受益権の合計額が信託財産を構成する資産及び負債の評価額からかけ離れるケースがあったが、平成12年6月に現行の差し引き計算方式に改正され、両受益権の合計額が常に同資産の評価額に一致するようになったので、節税が封じられたと報道された(「週刊税務通信」平成12年8月28日号)。
2 平成12年12月、財団法人大蔵財務協会発行、横山恒美編「財産評価基本通達逐条解説」全訂版P755。
3 橋本守次先生は「ゼミナール相続税法」大蔵財務協会P677~678において、このような受益権の評価は理解できないと書いておられる。
4 連邦歳入法7520条には、有期定期金、終身定期金、不動産生涯権、残余財産受益権等の多様な権利毎に複利表が用意されている。
5 山田煕「月刊税理」平成12年Vol43、No.10。
6 川口幸彦「信託法改正と相続税・贈与税の諸問題」(税務大学校論叢2008)事例13、P428~429。川口先生は、この事例では収益受益権の計算基礎となる賃料の見積もりが適正ではなかった。長期の信託の収益受益権を短期の賃料見積りにより評価すべきはない、と指摘している。
7 税引き割引率は源泉分離課税等を適用して求める。
8 信託協会松永和美「財産の管理・承継に利用される信託の税制に関する一考察」信託法研究32号2007年、P105。
9 この解説は相続税法9条の3第1項の受益者連続型信託の権利の説明とされているが、その内容は相続税法9条の2第2項の説明に過ぎず、収益受益権の制約条件はないものとして課税することの説明ではない。
10 橋本康平「受益者連続信託における資産税課税の検討」立命館法政論集9号2011、P147:遺言代用信託において親の死亡により妻が収益受益権、子が元本受益権を取得した場合に、子も不確定期限付きの残余財産受益権を確定的に取得するので、妻と子の両方に課税すべきであり、受益者連続型信託の課税の特例の適用はないとしている。
11 横山恒美編、注2前掲書P757。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















