解説記事2018年01月22日 【最新判決研究】 個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(配当還元価額適用の可否)(2018年1月22日号・№723)
最新判決研究
個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(配当還元価額適用の可否)
東京地裁平成29年8月30日判決(平成24年(行ウ)第185号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実 (1)甲は、A社の代表取締役を務めていたが、平成19年8月1日、A社の株式72万5000株(以下「本件株式」という。)を、B社に対し、代金1株当たり75円、合計5437万円余で譲渡し(以下「本件株式譲渡」という。)、同年12月Y日に死亡した。甲の相続人は、配偶者であるX1、子であるX2、X3、X4及びX5(原告、以下「Xら」という。)並びに代襲相続人であるAの6名であり、同人らは、甲を相続した(以下「本件相続」という。)。
Xらは、本件相続に伴い、平成20年3月13日、所轄税務署長に対し、甲の平成19年分所得税につき、本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)188-2に定める配当還元方式による評価額(1株当たり75円)によって算定し、所得税の準確定申告書を提出した(以下「本件申告」という。)。
所轄税務署長は、平成22年4月20日、Xらに対し、甲の平成19年分所得税につき、本件株式の価額は評価通達180に定める類似業種比準方式による評価額1株当たり2990円であるとして、各更正等(以下「本件更正等」という。)をした。Xらは、本件更正等を不服として、国(被告)に対し、それらの取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)A社は、昭和25年9月に設立され、金属製品等の製造、販売等を業とする資本金4億6000万円の株式会社であり、平成19年1月期の売上金額は約236億円、従業員数は449人である。また、A社は、本件株式譲渡時の発行済株式総数は920万株であり、株主は1株につき1個の議決権を有し、定款において、その株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めていた。
本件株式譲渡の時点において、A社は、評価通達178に定める「大会社」に該当し、A社の株式は、所得税基本通達23~35共-9(4)二に定める株式に、また、評価通達に定める取引相場のない株式に該当する。
B社は、平成16年2月に金銭の貸付業、株式投資業等を目的として設立されたものであるが、A社の持株会の補完的機能を有している。
なお、本件に関しては、本件相続に係るXの相続税につき、本件相続によってXが取得したA社の株式の「時価」が幾許であるかが別訴で争われ、本判決と同日に判決(東京地裁平成24年(行ウ)第184号、平成29年8月30日判決)が下されているので、その内容と本判決との関係について、後記「解説」において説明する。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点 本件の主たる争点は、本件株式譲渡が所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるか否か(本件株式の価額を配当還元方式によって評価すべきか類似業種比準方式によって評価すべきか)であり、具体的には、次の2点にある。
(1)所得税基本通達59-6の(1)の条件下における評価通達188の議決権割合の判定方法
(2)本件株式譲渡における譲渡代金額をもって時価といえるか。
なお、本訴においては、本件各更正等によりX2らがそれぞれ納付すべき税額についての国の主張変更の当否が争われたが、X2らの主張は排斥されており、詳述は省略する。
2 国の主張 (1)所得税基本通達59-6の(1)の趣旨は、譲渡人に帰属する資産の保有期間中の増加益を所得として課税する点にあることからすれば、その増加益は株式の譲渡人の譲渡直前の議決権割合により判定することが最も合理的といえるためである。本件株式譲渡の直前において、自己及びその同族関係者の有するA社の議決権の合計数が同社の議決権総数の30%以上である株主(同族株主)はいないから、本件株式は、評価通達188の(1)及び(2)の株式に該当しない。また、本件株式譲渡の直前において、甲及びその同族関係者は、A社の議決権総数の15%以上(22.79%)の議決権を有し、かつ、甲個人も、A社の議決権総数の5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188の(3)及び(4)の株式にも該当しない。
したがって、本件株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないから、評価通達178本文、179の(1)により、原則的評価方法である類似業種比準方式により評価すべきことになり、本件株式の価額は、1株当たり2505円となる。
(2)甲は、A社の株主でもあるC社及びA社の役員らが甲の実効支配下にあったことなどから、A社のみならず、A社の役員らが株主であるB社においても極めて強い権限を有しており、これらの会社では、本件株式譲渡の前後を通じて株主総会や取締役会が開催されたことはなく、株式の移動や人事、報酬などの株主総会や取締役会で決定される事項は、全て甲が意思決定をするという甲に実効支配体制が確立していた。
そして、本件株式譲渡の譲渡価額を決定するに当たり、甲やB社において合理的な検討はされておらず、本件株式譲渡は、甲一族が有するA社の議決権割合を15%未満にして相続税負担を軽減させることを目的に行われたものである。
以上によれば、本件株式譲渡における譲渡価額は、純然たる第三者間で種々の経済性を考慮して算定されたものではなく、時価であるとはいえない。よって、本件株式譲渡は、時価による取引であるとはいえず、前記のとおり、譲渡の時の価額の2分の1に満たない金額によるものであるから、所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たる。
3 Xらの主張 (1)評価通達188の(3)のうち、「同族株主のいない会社」であるかどうかの判定(会社区分の判定)は、所得税基本通達59-6の(1)により株式譲渡直前の議決権の数により行うことになるとしても、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定(株主区分の判定)は、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うのが相当である。このような評価通達の文言に忠実な解釈は、実務上、通達も法律に準じ広く一般に周知され、納税者の指針となっていることに鑑みれば、租税法律主義の下で課税に関する予測可能性を保障するという要請に適うものといえる。
(2)本件の場合、B社は、既存のA社の持株会を補完するものとしてA社の役員や従業員の福利厚生を目的に設立され、現に株主の負担においてB社への出資がされており、B社から株主への配当もされている等、B社は、甲とは独立した第三者であり、本件株式譲渡は、利害相反する第三者間で行われたものである。
そして、A社の少数株主となるにすぎないB社にとって、本件株式の実質的な経済的価値は配当への期待のみであり、このような買主の主観的事情を考慮すれば、本件株式を配当還元方式により評価することは当然であるから、本件株式譲渡は「時価」によりなされたものである。
三、判決要旨
請求棄却。 (1)所得税法59条1項にいう「その時における価額」とは、当該譲渡の時における当該資産の客観的交換価値を言うものと解される。そして、所得税基本通達59-6は、所得税法59条1項の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が評価通達における取引相場のない株式に相当する株式であって売買実例のある株式等に該当しないものである場合の「その時における価額」とは、原則として、一定の条件の下に、評価通達の178から189-7までの例により算定した価額とする旨を定めており、これらの通達はいずれも公開されている。
所得税基本通達59-6がこのような取扱いを定めている趣旨は、取引相場のない株式は通常売買実例等に乏しく、その客観的交換価値を的確に把握することが容易ではないため、その評価方法についての国税当局の内部的な取扱いを相続税等の課税対象となる財産の評価について定めた評価通達の例に原則として統一することで、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処理に資するとともに、公開された画一的な評価によることで、納税者間の公平を期し、また納税者の申告・納税の便宜を図るという点にあると解される。
このような上記通達の趣旨に鑑みれば、取引相場のない株式について、所得税基本通達59-6が定める条件の下に適用される評価通達に定められた評価方法が、取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算において当該株式のその譲渡の時における客観的交換価値を算定する方法として一般的な合理性を有するものであれば、その評価方法によってはその客観的交換価値を適正に算定することができない特別な事情がある場合でない限り、その評価方法によって算定された価額は、当該譲渡に係る取引相場のない株式についての所得税法59条1項にいう「その時における価額」として適正なものであると認めるのが相当である。
(2)そこでまず、評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法の合理性について検討すると、評価通達178以下では、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模に応じて場合分けし、大会社については、類似業種比準方式を原則的評価方法とすることを定める(同179、180)一方、「同族株主以外の株式等が取得した株式」については、例外的に配当還元方法によることを定める(同188、188-2)。
類似業種比準方式は、評価会社と事業の種類が類似する上場会社の株価に比準して株式の価額を求めるものであり、具体的には、株価構成要素のうち基本的かつ直接的なもので計数化が可能な1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額の3要素につき、評価会社のそれらと、当該会社と事業内容が類似する業種目に属する上場会社のそれらの平均値とを比較の上、上場会社の株価の平均値に比準して評価会社の1株当たりの価額を算定するというものである。この方式を大会社の取引相場のない株式の原則的評価方法とした趣旨は、大会社が上場株式や気配相場等のある株式の発行会社に匹敵するような規模の会社であって、その株式が通常取引されるとすれば上場株式や気配相場等のある株式の取引価格に準じた価額が付されることが想定されることから、現実に流通市場において価格形成が行われている株式の価額に比準して評価することが合理的であることによるものと解される。
他方で、配当還元方式は、株式の価額をその株式に係る年配当金額を還元率10%で除して計算した元本に相当する配当還元価額によって評価するものである。この方式を「同族株主以外の株主等が取得した株式」の評価方法とした趣旨は、事業経営への影響の少ない同族株主の一部や従業員株主等の少数株主においては、会社支配力が小さく、単に配当を期待するにとどまるという実情があることから、評価手続の簡便性をも考慮して、この評価方法を相当としたものと解される。
以上の諸点に鑑みれば、評価通達178以下に定めるこれらの評価方法は、取引相場のない株式につき実情等を踏まえたものとして一般的な合理性を有すると認められる。
(3)次に、所得税基本通達59-6が上記の評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法を適用する際の一定の条件として規定した内容の合理性について検討すると、そもそもそのような一定の条件を設けたのは、評価通達が本来的には相続税や贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであって、譲渡所得の収入金額の計算とは適用場面が異なることから、評価通達を譲渡所得の収入金額の計算の趣旨に則して用いることを可能にするためであると解される。
すなわち、相続税や贈与税が、相続や贈与による財産の移転があった場合にその財産の価額を課税価格としてその財産の取得した者に課される税であるのに対し、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益(キャピタル・ゲイン)を所得として、その資産が所得者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算してその譲渡人である元の所有者に課税する趣旨のものと解されるのであって、そのような課税の趣旨からすれば、譲渡所得の基因となる資産についての低額譲渡の判定をする場合の計算の基礎となる当該資産の価額は、当該資産を譲渡した後の譲受人にとっての価値ではなく、その譲渡直前において元の所有者が所有している状態における当該所有者(譲渡人)にとっての価値により評価するのが相当であるから、評価通達188の(1)~(4)の定めを取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算上当該株式のその譲渡の時における価額の算定に適用する場合には、各定め中「(株主の)取得した株式」とあるのを「(株式の)有していた株式で譲渡に供されたもの」と読み替えるのが相当であると解される。
(4)以上によれば、前記前提事実のとおり、本件株式譲渡直前の時点において、A社には合計して30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者がおらず、A社は「同族株主のいない会社」に当たるから、本件株式は、評価通達188の(1)及び(2)の株式には該当しない。また、本件株式譲渡直前の時点において、譲渡人である甲及びその同族関係者である甲親族らは、合計して15%以上(22.79%)の議決権を有し、甲個人も5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188の(3)及び(4)の株式にも該当しない。
よって、本件株式は、評価通達188の株式のいずれにも該当しないから、類似業種比準方式により評価すべきこととなり、その評価額は1株当たり2505円となることが認められる。
(5)上記認定事実のとおり、B社の株主は自己の資金の出捐してB社の株式を取得しており、その株式の譲渡も行われていたことや、B社では、本件株式譲渡によりA社の株式を取得するのみならず、設立後間もなくC社の株式も取得していること、本件株式譲渡が行われた事業年度の翌事業年度から配当が行われていたこと等からすれば、B社には、その関連会社の株式の取得及び保有を通じて利益を上げ、株主であるA社の役員や従業員にこれを還元するという活動実態があるということができる。そして、本件株式譲渡について、B社の側から見れば、B社が取得した本件株式に係るA社での議決権割合は7.88%にすぎず、評価通達188を適用すれば同項の(3)の株式に該当し、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するから、配当還元方式による評価額を譲渡対価とした本件株式譲渡が、B社にとって不合理な取引であったとはいえない。
しかしながら、本件株式の譲渡人である甲の側から見れば、甲は、本件株式譲渡前には、単独でも15.88%の議決権割合となる株式を有していたものであり、これを一括して他に譲渡するか、又はその一部に限って譲渡するとしても、その譲渡する議決権を合わせたA社での議決権割合が15%以上となるような株主に対してこれを譲渡していれば、本件株式譲渡の譲渡対価(1株当たり75円)よりも高額の類似業種比準方式による評価額(1株当たり2505円)に相当する金額程度の対価を得られる可能性があり、また、甲が株主としての会社支配力の低下等を懸念してそのような譲渡を望まず、あるいはそのような譲渡に応じる者がいないというのであれば、譲渡しないこともできたのに、あえてその有する株式のうちの一部のみをB社に対して譲渡したことによって、本件株式が事業経営への影響力が著しく減退した少数株式となり、配当還元方式による評価額相当の低額な対価を得るにとどまったものである。このような譲渡をしたことの目的としては、甲の側では、自己が代表取締役社長を務めるA社の役員及び従業員が株主になっていて、平時においては敵対的な議決権行使等をしないことが一般的に期待できるB社に本件株式のみを譲渡することによって、A社における経営の安定を一定程度保持しつつ、本件株式の譲渡による対価収入を減らしてでも、自身の相続人の相続税の負担を軽減するということ以外には考え難く、譲渡対価による収益を目的とする通常の取引としての合理性には乏しいものといわざるを得ない。また、本件株式譲渡において、甲の有する資産としての価値が真摯に検討されて、B社との交渉を経るなどして本件株式の譲渡価額が決定されたといった事情も認められない。
以上のような本件株式譲渡の経緯や実態等に鑑みると、本件株式譲渡をXらのいう利害相反する第三者間の取引(正常な株式の売買)とみることはできず、その対価をもって本件株式の時価(客観的交換価値)ということはできない。
四、解説
はじめに 本件は、会社の代表取締役が、自社の株式(非上場株式、本件株式)を関係会社に対して、評価通達に定める配当還元価額で譲渡した場合に、当該譲渡価額が所得税法59条1項2号に定める「著しく低い価額」に当たるとする課税処分が行われ、当該課税処分の適否が争われたものである。個人と当該個人の関係会社に対する資産の売買については、所得税法59条1項2号の適用の可否がまま問題となるが、その場合に、最も問題となるのが、当該売買価額が当該資産の同項に定める「その時における価額」に当たるかであり、当該価額をどう評価すべきかである。
特に、本件のように、当該売買の対象となる資産が非上場株式である場合には、元々、当該株式について市場価格が存在していないだけに、「その時における価額」の評価が困難となる。そのため、実務においては、所得税基本通達と評価通達の取扱いに依存することになるが当該通達の取扱いの適用のあり方も問題になることがある。しかも、本件に関しては、本件株式を譲渡した甲が、当該譲渡約4月後に死亡し、その相続税に関しても、本件株式と同じ会社の株式の評価額の是非が別訴で争われることになったので、両事件の関係も問題となる。
そこで、本稿では、上記の各問題に関し、関係する法律、通達を検討し、別訴の判決も参照することによって、本件の理解に資することとする。
1 所得税法上のみなし譲渡に係る「価額」の評価 (1)かつて、シャウプ勧告は、「生前によると死亡によるとを問わず、資産が無償移転された場合、その時までにその資産につき生じた利得又は損失は、その年の所得税申告書に計上しなくてはならない」旨を勧告し(注1)、それを受けて昭和25年の所得税法改正では、相続、遺贈又は贈与により資産の移転があった場合にも、その時の時価により譲渡があったものとして、譲渡所得等の課税を行うこととした。しかし、このような課税が納税者の理解を得られ難かったことや税務執行が困難であることから、上記課税制度は、徐々に変更され、昭和48年以降、現行の所得税法59条及び60条の規定となり、限定的にみなし譲渡課税が行われることとなった。そして、当該みなし譲渡課税が行われていない場合には、当該資産の取得価額の引継ぎが行われることとなった(注2)。
すなわち、所得税法59条1項は、「次に掲げる事由により居住者の有する山林(〈略〉)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。」と定めている。そして、本件に即すると、その2号に「著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)」と定めている。そして、所得税法施行令169条は、「法第59条第1項第2号(〈略〉)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。」と定めている(注3)。
(2)かくして、上記条項の解釈については、本件に即すると、「その時における価額」が問題となる。この「価額」の意義については、判例等において、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち客観的交換価値(客額的交換価額)であると解されている(注4)。そして、この「価額」の意義については、相続税法上の「時価」(同法7、22)、法人税法上の「価額」に共通するものと解されている(注5)。
しかしながら、当該「価額」を客観的交換価値であると解し得るとしても、特に、非上場株式のように、市場取引がない資産については、それのみでは「価額」の解釈(認定)が困難である。そこで、所得税基本通達23~35共-9(4)では、いわゆる非上場株式の「価額」については、次に掲げる区分に応じて、次のように評価する旨定めている。
① 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
② 公開途上にある株式 公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
③ 売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
④ ①から③までに該当しないもの 権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3)所得税法上の非上場株式の価額は、上記の取扱いによって評価されるのであるが、実務上は当該取扱いのうち④に該当する場合が最も多いと言えるところ、所得税基本通達59-6では、次のように取り扱うとしている。
「法第59条第1項の規定の適用について、譲渡所得の基因となる株式(〈略〉)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)二に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで(〈略〉)の例により算定した価額とする。」
この規定により、評価通達上の取引相場のない株式の評価方法によって評価することができる条件を4つ定めているが、本件に関しては、「評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」である。
かくして、所得税法において非上場株式の価額を評価する場合にも、原則として、相続税法において適用される評価通達の評価方法に準ずる場合が多いが、当該評価通達の評価方法は、次のとおりである。
2 評価通達における取引相場のない株式の評価方法 (1)評価通達では、株式等の評価単位につき、上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式を「取引相場のない株式」として区分し(評基通168(1)~(3))、取引相場のない株式の評価区分につき、当該株式の発行会社(以下「評価会社」という。)を大会社、中会社又は小会社に区分する(評基通178)。そして、大会社の株式の価額は、原則として、類似業種比準価額(純資産価額も可)で評価し、中会社の株式の価額は、類似業種比準価額と純資産価額の折衷方式(価額)で評価し、小会社の株式の価額は、原則として、純資産価額(類似業種比準価額の2分の1併用も可)で評価する(評基通179)。
ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ評価通達188又は189の定めにより評価する(評基通178ただし書)。
かくして、本件に即すると、本件株式の発行会社であるA社が上記の大会社に区分されることについては、当事者間に争いがないが、甲が上記の「同族株主以外の株主等」に該当し、本件株式の価額を配当還元価額で評価し得るか否かが、問題となる。よって、「同族株主以外の株主等」の範囲を明らかにする必要がある。
(2)評価通達188は、「178(〈略〉)の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。」と定めている。上記の株式は、次のとおりである。
① 同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(〈略〉)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
② 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令71条1項1号、2号及び4号に掲げる者をいう。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株式の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻続(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
③ 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
④ 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(②の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。
以上の取扱いにおいて、特に、問題となるのが、「同族関係者」の範囲及び議決権数の数え方であるが、それらの問題は、本件に直接関係がないので、別稿に譲る(注6)。
(3)次に、前記取扱いによって、「同族株主以外の株主等が取得した株式」と区分された株式の価額については、配当還元方式によって評価されるのであるが、当該配当還元方式は、次のとおりである(評基通188-2)。
すなわち、当該株式の価額は、その株式に係る年配当金額(評価通達183の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を評価通達179に定める原則的評価方式によって計算した金額を超える場合には、当該原則的評価方式によって計算した金額によって評価する。
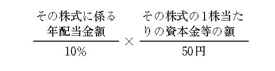
上記の配当還元方式は、元々、額面株式の額面額が50円であったことが主流であったことに起因し、当該株式の価額は、1割配当であれば50円で評価することになる。ただし、平成18年の評価通達の改正によって、「資本金の額」を「資本金等の額」に変更したため、配当還元価額が類似業種比準価額を上回ることが生じるようになった(注7)。
3 本件株式の価額の評価 (1)本件の争点は、結局、前記(2)及び(3)で述べた所得税基本通達と評価通達のそれぞれの取扱いの適用のあり方にあった。
それらの適用に当たって、国は、所得税基本通達59-6(1)が評価通達の準用に当たって同族株主等の判定において当該株式の譲渡直前の議決権割合によって判定することにしているとし、当該譲渡直前において、甲及びその同族関係者は22.79%の議決権数を有し、かつ、甲個人も15.88%の議決権数を有していたので、本件株式は評価通達188の(1)から(4)に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないから、本件株式の価額につき配当還元方式によって評価できない旨主張した。また、甲は、A社、B社らの株式の持ち合いは、甲による実効支配体制を維持しつつ、相続税負担を軽減するためにあること等も指摘した。
他方、Xらは、所得税基本通達59-6が準用する評価通達188の(3)について、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うのが相当であるとし、そう解するのが租税法律主義の下での予測可能性を保障することになる旨主張した。また、Xらは、B社は実質的にもA社に対しては配当期待権を有する少数株主にすぎず、このような譲受人側の事情により本件株式の取引価格が決定される旨主張した。
(2)かくして、本判決は、所得税法59条1項に定める「その時における価額」が客観的交換価値をいうものと解されるとし、所得税基本通達59-6が、当該客観的交換価値の算定する方法として適正である旨判示し、譲渡所得課税の趣旨にも敷衍し、前述の国とXらの主張の対立等に関して、次のように判示し、Xの主張を斥けた。
「譲渡所得の基因となる資産についての低額譲渡の判定をする場合の計算の基礎となる当該資産の価額は、当該資産を譲渡した後の譲受人にとっての価値ではなく、その譲渡直前において元の所有者が所有している状態における当該所有者(譲渡人)にとっての価値により評価するのが相当であるから、評価通達188の(1)~(4)の定めを取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算上当該株式のその譲渡の時における価額の算定に適用する場合には、各定めの中「(株主の)取得した株式」とあるのを「(株主の)有していた株式で譲渡に供されたもの」と読み替えるのが相当であり、また、各定め中のそれぞれの議決権の数も当該株式の譲渡直前の議決権の数によることが相当であると解される。」
また、本判決は、本件株式の譲渡価額の相当性については、A社(甲)の関係会社であるB社、C社及びD社の設立の経緯等の事実関係を検討し、「本件株式譲渡の経緯や実態等に鑑みると、本件株式譲渡をXらのいう利害相反する第三者間の取引(正常な株式の売買)とみることはできず、その対価をもって本件株式の時価(客観的交換価値)ということはできない。」と判示し、結局、前述した所得税基本通達59-6の(1)等を文言どおり適用して類似業種比準方式によって本件株式の譲渡価額を算定したのは相当である旨判示した。
(3)以上のように、本件においては、所得税法59条1項の適用に当たって、本件株式譲渡の譲渡価額の適否が争われたものであるが、当該価額の適否につき、所得税基本通達59-6の(1)を文言どおり適用するのであれば、国側の主張どおりとなり、評価通達が定める原則的評価方法である類似業種比準価額で算定して判定すれば足りることになる。
しかしながら、所得税59条1項にいう「その時の価額」が客観的交換価値を意味するわけであるから、本件株式の価値についても、譲渡人側の価値論のみによって判断すべきではなく、譲受人側の価値論についても検討を要することになる。そして、双方の価値が交錯して、客観的交換価値が成立することになる。
この点につき、本件判決は、前述のように、本件株式譲渡の背景と実態を具さに検討し、甲一族及び関係会社間の株式の持ち合いは、甲らにとって、評価通達上の評価の有利性を得るために行われたものであるから、結局、本件株式譲渡直前の甲の保有割合によって本件株式の価値を判断すれば足りる旨判示した。このような判示は、本件株式の譲渡が甲一族の節税のために行われていることも合理的に推測できるから、相当であると考えられる。
4 第184号(相続税更正処分取消等請求事件)との関係 (1)東京地方裁判所民事3部は、本判決と同時に、本件と原告が同じである第184号相続税更正処分取消等請求事件(以下「相続税事件」という。)についても、判決を下しているが、相続税事件については、本件とは異なって配当還元方式の適用を認めている。すなわち、本件においては、甲が、本件株式をB社に譲渡した4月後に死亡し、Xらが甲を相続することになるが、相続人の1人である甲の配偶者乙(本件のX1)は、A社株式18万3925株(以下単に「A株式」という。)を取得することとなり、当該相続税の申告においても、当該株式の価額を配当還元価額である1株当たり75円で課税価格を計算した。乙は、その根拠について、A株式を取得した段階(課税時期)において、乙及びその同族関係者である親族らの有する議決権の合計割合は14.91%であり、15%未満であるから、評価通達188の(3)に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当する旨主張した。
他方、所轄税務署長は、当該株式の価額を1株当たり2292円で評価すべきであるとして、更正処分等をした。国は、当該更正等が適法である論拠として、評価通達188における同族株主の定義に関する法人税法施行令4条6項は、形式上の議決権行使者と実質上の議決権行使者とが異なる場合には、実質上の議決権行使者が議決権を有しているとみなして保有議決権割合の判定をするという趣旨であるところ、乙およびその親族らとA社の関係会社のC社及びD社(両社ともA社の議決権につきA社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している。)の議決権数を合計すると、A社の議決権総数の21.94%になるから、評価通達188に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しない、ことを主張している。
以上の当事者の主張は、要するに、乙は、A株式については評価通達188の(3)を文言どおり適用すれば配当還元方式で評価できると主張し、国は、乙一族の税負担回避のためにB社、C社及びD社にA社株式を所有させているという特別の事情があるから、A株式を類似業種比準方式を適用して評価すべきである旨主張する。
(2)かくして、相続税事件の判決は、事実関係を認定した上で、「課税時期において、A社に合計して30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者がいないため、A社は「同族株主」のいない会社に当たる。また、乙及びその同族関係者である乙親族らの有する議決権の合計割合は14.91%であり、「株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合」にもあたる。よって、本件株式は、評価通達188の(3)の株式に該当するから、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当する。」と判示した。
そして、同判決は、国が主張する「特別の事情」の存否については、甲、乙らとA社の支配関係、乙らとA社、B社、C社及びD社の支配関係を具さに検討し、「本件株式が「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するものであるにもかかわらず、配当還元方式ではなく、類似業種比準方式により評価することが正当と是認される特別な事情があるとする国の主張は採用することはできず、本件株式につき、配当還元方式によって適正な時価を算定することができない特別の事情があるとは認められない。」と判示した。
(3)以上のように、本件の所得税事件と別件の相続税事件のそれぞれの判決は、同じA社の株式の価額が幾許であるかが争われ、いずれも実質的に当事者を同じくし、かつ、東京地方裁判所の同じ裁判官によって判決されたものであるが、結果的には、前者については、国の主張が認められ、後者については、納税者である乙の主張が認められた。
このような二つの判決を比較すると、いずれも、それぞれの株式の価額につき、所得税基本通達又は評価通達の適用に当たって、各通達を文言どおり適用して、当該文言どおりの評価を否とする「特別の事情」の存在を否定したものである。
ただし、本件の所得税事件については、甲が本件株式をB社に譲渡したことにつき、「A社の役員及び従業員が株主になっているB社に本件株式のみを譲渡することによって、A社における経営の安定を一定程度保持しつつ、本件株式の譲渡による対価収入を減らしても、自身の相続人の相続税の負担を軽減するという以外には考え難」いと判示し、関係会社の一つであるB社の議決権行使の独立性をほぼ否定している。そうであれば、相続税事件において国が主張する法人税法施行令4条6項の適用も可能であるようにも考えられる。
しかし、同じ裁判所の同じ裁判部において、本件の所得税事件については、関係会社の議決権行使の独立性が否定され(注8)、相続税事件については、関係会社の議決権行使の独立性が容認されるという相対立するような判断が下されている。このような結果については、勝手に憶測するに、同じ裁判官が両事件の判断を分かつことによって一つのバランスを採ったものとも言えるが、理解に苦しむところもある。
5 本判決の意義と問題点 資産承継又は事業承継の対策として、承継される財産(資産)の課税上の評価額を引き下げる手法が多用されている。また、そうすることが、資産税専門家の腕の見せ所であると言われている。その対策となる財産(資産)が非上場株式ともなると、その価額の評価が複雑で困難であることもあって、関係通達の取扱いの文言に適合する(文言を潜り抜ける)ように、関係者間で株式を持ち合い、発行会社の合併・分割を行い、あるいは、類似業種比準方式における比準要素を操作するなど、種々の手法が用いられることがある。
本件においても、そのような節税手法として関係会社間等において株式の持ち合い等が行われた事案といえる。本件の所得税事件においては、関係会社に譲渡した本件株式の価額が争われ、別件の相続税事件においては、本件株式が譲渡された後に、本件株式と発行会社を同じくするA株式の価額が争われたものである。よって、本件株式もA株式も、甲一族が所有している場合には、同一族にとっていずれも同じ経済的価値があるものと考えられる。その点に鑑み、いずれの事件においても、当該各課税処分において、いわゆる少数株主に適用される配当還元方式の適用が否定されたものと考えられる。
しかしながら、同じ裁判部において、所得税事件においては、配当還元方式の適用が否定されたが、相続税事件においては、当該方式の適用が容認された。それらの論拠については、前述した判決要旨において明らかにされているが、前述したように、それらの論拠付けに必ずしも整合性があるとも考えられない。ともあれ、本件のような節税対策において、その是非が問われる判決が出されたことは意義のあるところであり、同様な事案を検討している者にとって参考になるものである。
(注1)シャウプ使節団「日本税制報告書」第1編第5章第13節参照。
(注2)このような課税制度の変遷については、品川芳宣「資産の無償等譲渡をめぐる課税と徴収の交錯(1)」税理2004年1月号24頁等参照。
(注3)このみなし譲渡課税の趣旨、問題点については、前出(注2)25頁参照。なお、同族会社等に対する低額譲渡については、2分の1を上回ってもみなし譲渡課税が行われることがある(所基通59-3参照)。
(注4)所得税法に関する裁判例として、名古屋高裁昭和50年11月17日判決(税資83号502頁)、神戸地裁昭和54年5月29日判決(同105号461頁)、東京地裁平成2年2月27日判決(同175号802頁)、東京地裁平成11年11月30日判決(同245号576頁)等参照。
(注5)相続税法に関するものとして、東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等を、法人税法に関するものとして、大阪地裁昭和53年5月11日判決(行裁例集39巻5号943頁)、東京高裁平成6年2月26日判決(税資200号815頁)等を参照。
(注6)これらの問題については、品川芳宣編著「資産・事業承継対策の現状と課題」(大蔵財務協会 平成28年)(第14章事業承継と取引相場のない株式の評価)529頁以下参照。
(注7)詳細については、前出(注6)582頁参照。
(注8)取引上の関係会社の議決権行使の独立性を否定した事例として、東京地裁平成16年3月2日判決(税資254号順号9583)、東京高裁平成17年1月19日判決(同255号順号9900)(以上は、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)849頁参照)等参照。
個人が法人に非上場株式を譲渡した場合の当該株式の価額(配当還元価額適用の可否)
東京地裁平成29年8月30日判決(平成24年(行ウ)第185号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実 (1)甲は、A社の代表取締役を務めていたが、平成19年8月1日、A社の株式72万5000株(以下「本件株式」という。)を、B社に対し、代金1株当たり75円、合計5437万円余で譲渡し(以下「本件株式譲渡」という。)、同年12月Y日に死亡した。甲の相続人は、配偶者であるX1、子であるX2、X3、X4及びX5(原告、以下「Xら」という。)並びに代襲相続人であるAの6名であり、同人らは、甲を相続した(以下「本件相続」という。)。
Xらは、本件相続に伴い、平成20年3月13日、所轄税務署長に対し、甲の平成19年分所得税につき、本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)188-2に定める配当還元方式による評価額(1株当たり75円)によって算定し、所得税の準確定申告書を提出した(以下「本件申告」という。)。
所轄税務署長は、平成22年4月20日、Xらに対し、甲の平成19年分所得税につき、本件株式の価額は評価通達180に定める類似業種比準方式による評価額1株当たり2990円であるとして、各更正等(以下「本件更正等」という。)をした。Xらは、本件更正等を不服として、国(被告)に対し、それらの取消しを求めて、本訴を提起した。
(2)A社は、昭和25年9月に設立され、金属製品等の製造、販売等を業とする資本金4億6000万円の株式会社であり、平成19年1月期の売上金額は約236億円、従業員数は449人である。また、A社は、本件株式譲渡時の発行済株式総数は920万株であり、株主は1株につき1個の議決権を有し、定款において、その株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めていた。
本件株式譲渡の時点において、A社は、評価通達178に定める「大会社」に該当し、A社の株式は、所得税基本通達23~35共-9(4)二に定める株式に、また、評価通達に定める取引相場のない株式に該当する。
B社は、平成16年2月に金銭の貸付業、株式投資業等を目的として設立されたものであるが、A社の持株会の補完的機能を有している。
なお、本件に関しては、本件相続に係るXの相続税につき、本件相続によってXが取得したA社の株式の「時価」が幾許であるかが別訴で争われ、本判決と同日に判決(東京地裁平成24年(行ウ)第184号、平成29年8月30日判決)が下されているので、その内容と本判決との関係について、後記「解説」において説明する。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点 本件の主たる争点は、本件株式譲渡が所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるか否か(本件株式の価額を配当還元方式によって評価すべきか類似業種比準方式によって評価すべきか)であり、具体的には、次の2点にある。
(1)所得税基本通達59-6の(1)の条件下における評価通達188の議決権割合の判定方法
(2)本件株式譲渡における譲渡代金額をもって時価といえるか。
なお、本訴においては、本件各更正等によりX2らがそれぞれ納付すべき税額についての国の主張変更の当否が争われたが、X2らの主張は排斥されており、詳述は省略する。
2 国の主張 (1)所得税基本通達59-6の(1)の趣旨は、譲渡人に帰属する資産の保有期間中の増加益を所得として課税する点にあることからすれば、その増加益は株式の譲渡人の譲渡直前の議決権割合により判定することが最も合理的といえるためである。本件株式譲渡の直前において、自己及びその同族関係者の有するA社の議決権の合計数が同社の議決権総数の30%以上である株主(同族株主)はいないから、本件株式は、評価通達188の(1)及び(2)の株式に該当しない。また、本件株式譲渡の直前において、甲及びその同族関係者は、A社の議決権総数の15%以上(22.79%)の議決権を有し、かつ、甲個人も、A社の議決権総数の5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188の(3)及び(4)の株式にも該当しない。
したがって、本件株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないから、評価通達178本文、179の(1)により、原則的評価方法である類似業種比準方式により評価すべきことになり、本件株式の価額は、1株当たり2505円となる。
(2)甲は、A社の株主でもあるC社及びA社の役員らが甲の実効支配下にあったことなどから、A社のみならず、A社の役員らが株主であるB社においても極めて強い権限を有しており、これらの会社では、本件株式譲渡の前後を通じて株主総会や取締役会が開催されたことはなく、株式の移動や人事、報酬などの株主総会や取締役会で決定される事項は、全て甲が意思決定をするという甲に実効支配体制が確立していた。
そして、本件株式譲渡の譲渡価額を決定するに当たり、甲やB社において合理的な検討はされておらず、本件株式譲渡は、甲一族が有するA社の議決権割合を15%未満にして相続税負担を軽減させることを目的に行われたものである。
以上によれば、本件株式譲渡における譲渡価額は、純然たる第三者間で種々の経済性を考慮して算定されたものではなく、時価であるとはいえない。よって、本件株式譲渡は、時価による取引であるとはいえず、前記のとおり、譲渡の時の価額の2分の1に満たない金額によるものであるから、所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たる。
3 Xらの主張 (1)評価通達188の(3)のうち、「同族株主のいない会社」であるかどうかの判定(会社区分の判定)は、所得税基本通達59-6の(1)により株式譲渡直前の議決権の数により行うことになるとしても、「課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式」に該当するかどうかの判定(株主区分の判定)は、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うのが相当である。このような評価通達の文言に忠実な解釈は、実務上、通達も法律に準じ広く一般に周知され、納税者の指針となっていることに鑑みれば、租税法律主義の下で課税に関する予測可能性を保障するという要請に適うものといえる。
(2)本件の場合、B社は、既存のA社の持株会を補完するものとしてA社の役員や従業員の福利厚生を目的に設立され、現に株主の負担においてB社への出資がされており、B社から株主への配当もされている等、B社は、甲とは独立した第三者であり、本件株式譲渡は、利害相反する第三者間で行われたものである。
そして、A社の少数株主となるにすぎないB社にとって、本件株式の実質的な経済的価値は配当への期待のみであり、このような買主の主観的事情を考慮すれば、本件株式を配当還元方式により評価することは当然であるから、本件株式譲渡は「時価」によりなされたものである。
三、判決要旨
請求棄却。 (1)所得税法59条1項にいう「その時における価額」とは、当該譲渡の時における当該資産の客観的交換価値を言うものと解される。そして、所得税基本通達59-6は、所得税法59条1項の適用に当たって、譲渡所得の基因となる資産が評価通達における取引相場のない株式に相当する株式であって売買実例のある株式等に該当しないものである場合の「その時における価額」とは、原則として、一定の条件の下に、評価通達の178から189-7までの例により算定した価額とする旨を定めており、これらの通達はいずれも公開されている。
所得税基本通達59-6がこのような取扱いを定めている趣旨は、取引相場のない株式は通常売買実例等に乏しく、その客観的交換価値を的確に把握することが容易ではないため、その評価方法についての国税当局の内部的な取扱いを相続税等の課税対象となる財産の評価について定めた評価通達の例に原則として統一することで、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処理に資するとともに、公開された画一的な評価によることで、納税者間の公平を期し、また納税者の申告・納税の便宜を図るという点にあると解される。
このような上記通達の趣旨に鑑みれば、取引相場のない株式について、所得税基本通達59-6が定める条件の下に適用される評価通達に定められた評価方法が、取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算において当該株式のその譲渡の時における客観的交換価値を算定する方法として一般的な合理性を有するものであれば、その評価方法によってはその客観的交換価値を適正に算定することができない特別な事情がある場合でない限り、その評価方法によって算定された価額は、当該譲渡に係る取引相場のない株式についての所得税法59条1項にいう「その時における価額」として適正なものであると認めるのが相当である。
(2)そこでまず、評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法の合理性について検討すると、評価通達178以下では、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模に応じて場合分けし、大会社については、類似業種比準方式を原則的評価方法とすることを定める(同179、180)一方、「同族株主以外の株式等が取得した株式」については、例外的に配当還元方法によることを定める(同188、188-2)。
類似業種比準方式は、評価会社と事業の種類が類似する上場会社の株価に比準して株式の価額を求めるものであり、具体的には、株価構成要素のうち基本的かつ直接的なもので計数化が可能な1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額の3要素につき、評価会社のそれらと、当該会社と事業内容が類似する業種目に属する上場会社のそれらの平均値とを比較の上、上場会社の株価の平均値に比準して評価会社の1株当たりの価額を算定するというものである。この方式を大会社の取引相場のない株式の原則的評価方法とした趣旨は、大会社が上場株式や気配相場等のある株式の発行会社に匹敵するような規模の会社であって、その株式が通常取引されるとすれば上場株式や気配相場等のある株式の取引価格に準じた価額が付されることが想定されることから、現実に流通市場において価格形成が行われている株式の価額に比準して評価することが合理的であることによるものと解される。
他方で、配当還元方式は、株式の価額をその株式に係る年配当金額を還元率10%で除して計算した元本に相当する配当還元価額によって評価するものである。この方式を「同族株主以外の株主等が取得した株式」の評価方法とした趣旨は、事業経営への影響の少ない同族株主の一部や従業員株主等の少数株主においては、会社支配力が小さく、単に配当を期待するにとどまるという実情があることから、評価手続の簡便性をも考慮して、この評価方法を相当としたものと解される。
以上の諸点に鑑みれば、評価通達178以下に定めるこれらの評価方法は、取引相場のない株式につき実情等を踏まえたものとして一般的な合理性を有すると認められる。
(3)次に、所得税基本通達59-6が上記の評価通達に定められた取引相場のない株式の評価方法を適用する際の一定の条件として規定した内容の合理性について検討すると、そもそもそのような一定の条件を設けたのは、評価通達が本来的には相続税や贈与税の課税価格の計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであって、譲渡所得の収入金額の計算とは適用場面が異なることから、評価通達を譲渡所得の収入金額の計算の趣旨に則して用いることを可能にするためであると解される。
すなわち、相続税や贈与税が、相続や贈与による財産の移転があった場合にその財産の価額を課税価格としてその財産の取得した者に課される税であるのに対し、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益(キャピタル・ゲイン)を所得として、その資産が所得者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算してその譲渡人である元の所有者に課税する趣旨のものと解されるのであって、そのような課税の趣旨からすれば、譲渡所得の基因となる資産についての低額譲渡の判定をする場合の計算の基礎となる当該資産の価額は、当該資産を譲渡した後の譲受人にとっての価値ではなく、その譲渡直前において元の所有者が所有している状態における当該所有者(譲渡人)にとっての価値により評価するのが相当であるから、評価通達188の(1)~(4)の定めを取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算上当該株式のその譲渡の時における価額の算定に適用する場合には、各定め中「(株主の)取得した株式」とあるのを「(株式の)有していた株式で譲渡に供されたもの」と読み替えるのが相当であると解される。
(4)以上によれば、前記前提事実のとおり、本件株式譲渡直前の時点において、A社には合計して30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者がおらず、A社は「同族株主のいない会社」に当たるから、本件株式は、評価通達188の(1)及び(2)の株式には該当しない。また、本件株式譲渡直前の時点において、譲渡人である甲及びその同族関係者である甲親族らは、合計して15%以上(22.79%)の議決権を有し、甲個人も5%以上(15.88%)の議決権を有していたから、本件株式は、評価通達188の(3)及び(4)の株式にも該当しない。
よって、本件株式は、評価通達188の株式のいずれにも該当しないから、類似業種比準方式により評価すべきこととなり、その評価額は1株当たり2505円となることが認められる。
(5)上記認定事実のとおり、B社の株主は自己の資金の出捐してB社の株式を取得しており、その株式の譲渡も行われていたことや、B社では、本件株式譲渡によりA社の株式を取得するのみならず、設立後間もなくC社の株式も取得していること、本件株式譲渡が行われた事業年度の翌事業年度から配当が行われていたこと等からすれば、B社には、その関連会社の株式の取得及び保有を通じて利益を上げ、株主であるA社の役員や従業員にこれを還元するという活動実態があるということができる。そして、本件株式譲渡について、B社の側から見れば、B社が取得した本件株式に係るA社での議決権割合は7.88%にすぎず、評価通達188を適用すれば同項の(3)の株式に該当し、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するから、配当還元方式による評価額を譲渡対価とした本件株式譲渡が、B社にとって不合理な取引であったとはいえない。
しかしながら、本件株式の譲渡人である甲の側から見れば、甲は、本件株式譲渡前には、単独でも15.88%の議決権割合となる株式を有していたものであり、これを一括して他に譲渡するか、又はその一部に限って譲渡するとしても、その譲渡する議決権を合わせたA社での議決権割合が15%以上となるような株主に対してこれを譲渡していれば、本件株式譲渡の譲渡対価(1株当たり75円)よりも高額の類似業種比準方式による評価額(1株当たり2505円)に相当する金額程度の対価を得られる可能性があり、また、甲が株主としての会社支配力の低下等を懸念してそのような譲渡を望まず、あるいはそのような譲渡に応じる者がいないというのであれば、譲渡しないこともできたのに、あえてその有する株式のうちの一部のみをB社に対して譲渡したことによって、本件株式が事業経営への影響力が著しく減退した少数株式となり、配当還元方式による評価額相当の低額な対価を得るにとどまったものである。このような譲渡をしたことの目的としては、甲の側では、自己が代表取締役社長を務めるA社の役員及び従業員が株主になっていて、平時においては敵対的な議決権行使等をしないことが一般的に期待できるB社に本件株式のみを譲渡することによって、A社における経営の安定を一定程度保持しつつ、本件株式の譲渡による対価収入を減らしてでも、自身の相続人の相続税の負担を軽減するということ以外には考え難く、譲渡対価による収益を目的とする通常の取引としての合理性には乏しいものといわざるを得ない。また、本件株式譲渡において、甲の有する資産としての価値が真摯に検討されて、B社との交渉を経るなどして本件株式の譲渡価額が決定されたといった事情も認められない。
以上のような本件株式譲渡の経緯や実態等に鑑みると、本件株式譲渡をXらのいう利害相反する第三者間の取引(正常な株式の売買)とみることはできず、その対価をもって本件株式の時価(客観的交換価値)ということはできない。
四、解説
はじめに 本件は、会社の代表取締役が、自社の株式(非上場株式、本件株式)を関係会社に対して、評価通達に定める配当還元価額で譲渡した場合に、当該譲渡価額が所得税法59条1項2号に定める「著しく低い価額」に当たるとする課税処分が行われ、当該課税処分の適否が争われたものである。個人と当該個人の関係会社に対する資産の売買については、所得税法59条1項2号の適用の可否がまま問題となるが、その場合に、最も問題となるのが、当該売買価額が当該資産の同項に定める「その時における価額」に当たるかであり、当該価額をどう評価すべきかである。
特に、本件のように、当該売買の対象となる資産が非上場株式である場合には、元々、当該株式について市場価格が存在していないだけに、「その時における価額」の評価が困難となる。そのため、実務においては、所得税基本通達と評価通達の取扱いに依存することになるが当該通達の取扱いの適用のあり方も問題になることがある。しかも、本件に関しては、本件株式を譲渡した甲が、当該譲渡約4月後に死亡し、その相続税に関しても、本件株式と同じ会社の株式の評価額の是非が別訴で争われることになったので、両事件の関係も問題となる。
そこで、本稿では、上記の各問題に関し、関係する法律、通達を検討し、別訴の判決も参照することによって、本件の理解に資することとする。
1 所得税法上のみなし譲渡に係る「価額」の評価 (1)かつて、シャウプ勧告は、「生前によると死亡によるとを問わず、資産が無償移転された場合、その時までにその資産につき生じた利得又は損失は、その年の所得税申告書に計上しなくてはならない」旨を勧告し(注1)、それを受けて昭和25年の所得税法改正では、相続、遺贈又は贈与により資産の移転があった場合にも、その時の時価により譲渡があったものとして、譲渡所得等の課税を行うこととした。しかし、このような課税が納税者の理解を得られ難かったことや税務執行が困難であることから、上記課税制度は、徐々に変更され、昭和48年以降、現行の所得税法59条及び60条の規定となり、限定的にみなし譲渡課税が行われることとなった。そして、当該みなし譲渡課税が行われていない場合には、当該資産の取得価額の引継ぎが行われることとなった(注2)。
すなわち、所得税法59条1項は、「次に掲げる事由により居住者の有する山林(〈略〉)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。」と定めている。そして、本件に即すると、その2号に「著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)」と定めている。そして、所得税法施行令169条は、「法第59条第1項第2号(〈略〉)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。」と定めている(注3)。
(2)かくして、上記条項の解釈については、本件に即すると、「その時における価額」が問題となる。この「価額」の意義については、判例等において、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」すなわち客観的交換価値(客額的交換価額)であると解されている(注4)。そして、この「価額」の意義については、相続税法上の「時価」(同法7、22)、法人税法上の「価額」に共通するものと解されている(注5)。
しかしながら、当該「価額」を客観的交換価値であると解し得るとしても、特に、非上場株式のように、市場取引がない資産については、それのみでは「価額」の解釈(認定)が困難である。そこで、所得税基本通達23~35共-9(4)では、いわゆる非上場株式の「価額」については、次に掲げる区分に応じて、次のように評価する旨定めている。
① 売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
② 公開途上にある株式 公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
③ 売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
④ ①から③までに該当しないもの 権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(3)所得税法上の非上場株式の価額は、上記の取扱いによって評価されるのであるが、実務上は当該取扱いのうち④に該当する場合が最も多いと言えるところ、所得税基本通達59-6では、次のように取り扱うとしている。
「法第59条第1項の規定の適用について、譲渡所得の基因となる株式(〈略〉)である場合の同項に規定する「その時における価額」とは、23~35共-9に準じて算定した価額による。この場合、23~35共-9の(4)二に定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」とは、原則として、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで(〈略〉)の例により算定した価額とする。」
この規定により、評価通達上の取引相場のない株式の評価方法によって評価することができる条件を4つ定めているが、本件に関しては、「評価通達188(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかは、株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定すること。」である。
かくして、所得税法において非上場株式の価額を評価する場合にも、原則として、相続税法において適用される評価通達の評価方法に準ずる場合が多いが、当該評価通達の評価方法は、次のとおりである。
2 評価通達における取引相場のない株式の評価方法 (1)評価通達では、株式等の評価単位につき、上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式を「取引相場のない株式」として区分し(評基通168(1)~(3))、取引相場のない株式の評価区分につき、当該株式の発行会社(以下「評価会社」という。)を大会社、中会社又は小会社に区分する(評基通178)。そして、大会社の株式の価額は、原則として、類似業種比準価額(純資産価額も可)で評価し、中会社の株式の価額は、類似業種比準価額と純資産価額の折衷方式(価額)で評価し、小会社の株式の価額は、原則として、純資産価額(類似業種比準価額の2分の1併用も可)で評価する(評基通179)。
ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社の株式の価額は、それぞれ評価通達188又は189の定めにより評価する(評基通178ただし書)。
かくして、本件に即すると、本件株式の発行会社であるA社が上記の大会社に区分されることについては、当事者間に争いがないが、甲が上記の「同族株主以外の株主等」に該当し、本件株式の価額を配当還元価額で評価し得るか否かが、問題となる。よって、「同族株主以外の株主等」の範囲を明らかにする必要がある。
(2)評価通達188は、「178(〈略〉)の「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、次項の定めによる。」と定めている。上記の株式は、次のとおりである。
① 同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(法人税法施行令4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上(〈略〉)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
② 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令71条1項1号、2号及び4号に掲げる者をいう。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株式の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻続(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。
③ 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
④ 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(②の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式
この場合における「中心的な株主」とは、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいう。
以上の取扱いにおいて、特に、問題となるのが、「同族関係者」の範囲及び議決権数の数え方であるが、それらの問題は、本件に直接関係がないので、別稿に譲る(注6)。
(3)次に、前記取扱いによって、「同族株主以外の株主等が取得した株式」と区分された株式の価額については、配当還元方式によって評価されるのであるが、当該配当還元方式は、次のとおりである(評基通188-2)。
すなわち、当該株式の価額は、その株式に係る年配当金額(評価通達183の(1)に定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。ただし、その金額がその株式を評価通達179に定める原則的評価方式によって計算した金額を超える場合には、当該原則的評価方式によって計算した金額によって評価する。
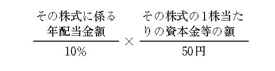
上記の配当還元方式は、元々、額面株式の額面額が50円であったことが主流であったことに起因し、当該株式の価額は、1割配当であれば50円で評価することになる。ただし、平成18年の評価通達の改正によって、「資本金の額」を「資本金等の額」に変更したため、配当還元価額が類似業種比準価額を上回ることが生じるようになった(注7)。
3 本件株式の価額の評価 (1)本件の争点は、結局、前記(2)及び(3)で述べた所得税基本通達と評価通達のそれぞれの取扱いの適用のあり方にあった。
それらの適用に当たって、国は、所得税基本通達59-6(1)が評価通達の準用に当たって同族株主等の判定において当該株式の譲渡直前の議決権割合によって判定することにしているとし、当該譲渡直前において、甲及びその同族関係者は22.79%の議決権数を有し、かつ、甲個人も15.88%の議決権数を有していたので、本件株式は評価通達188の(1)から(4)に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しないから、本件株式の価額につき配当還元方式によって評価できない旨主張した。また、甲は、A社、B社らの株式の持ち合いは、甲による実効支配体制を維持しつつ、相続税負担を軽減するためにあること等も指摘した。
他方、Xらは、所得税基本通達59-6が準用する評価通達188の(3)について、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合により行うのが相当であるとし、そう解するのが租税法律主義の下での予測可能性を保障することになる旨主張した。また、Xらは、B社は実質的にもA社に対しては配当期待権を有する少数株主にすぎず、このような譲受人側の事情により本件株式の取引価格が決定される旨主張した。
(2)かくして、本判決は、所得税法59条1項に定める「その時における価額」が客観的交換価値をいうものと解されるとし、所得税基本通達59-6が、当該客観的交換価値の算定する方法として適正である旨判示し、譲渡所得課税の趣旨にも敷衍し、前述の国とXらの主張の対立等に関して、次のように判示し、Xの主張を斥けた。
「譲渡所得の基因となる資産についての低額譲渡の判定をする場合の計算の基礎となる当該資産の価額は、当該資産を譲渡した後の譲受人にとっての価値ではなく、その譲渡直前において元の所有者が所有している状態における当該所有者(譲渡人)にとっての価値により評価するのが相当であるから、評価通達188の(1)~(4)の定めを取引相場のない株式の譲渡に係る譲渡所得の収入金額の計算上当該株式のその譲渡の時における価額の算定に適用する場合には、各定めの中「(株主の)取得した株式」とあるのを「(株主の)有していた株式で譲渡に供されたもの」と読み替えるのが相当であり、また、各定め中のそれぞれの議決権の数も当該株式の譲渡直前の議決権の数によることが相当であると解される。」
また、本判決は、本件株式の譲渡価額の相当性については、A社(甲)の関係会社であるB社、C社及びD社の設立の経緯等の事実関係を検討し、「本件株式譲渡の経緯や実態等に鑑みると、本件株式譲渡をXらのいう利害相反する第三者間の取引(正常な株式の売買)とみることはできず、その対価をもって本件株式の時価(客観的交換価値)ということはできない。」と判示し、結局、前述した所得税基本通達59-6の(1)等を文言どおり適用して類似業種比準方式によって本件株式の譲渡価額を算定したのは相当である旨判示した。
(3)以上のように、本件においては、所得税法59条1項の適用に当たって、本件株式譲渡の譲渡価額の適否が争われたものであるが、当該価額の適否につき、所得税基本通達59-6の(1)を文言どおり適用するのであれば、国側の主張どおりとなり、評価通達が定める原則的評価方法である類似業種比準価額で算定して判定すれば足りることになる。
しかしながら、所得税59条1項にいう「その時の価額」が客観的交換価値を意味するわけであるから、本件株式の価値についても、譲渡人側の価値論のみによって判断すべきではなく、譲受人側の価値論についても検討を要することになる。そして、双方の価値が交錯して、客観的交換価値が成立することになる。
この点につき、本件判決は、前述のように、本件株式譲渡の背景と実態を具さに検討し、甲一族及び関係会社間の株式の持ち合いは、甲らにとって、評価通達上の評価の有利性を得るために行われたものであるから、結局、本件株式譲渡直前の甲の保有割合によって本件株式の価値を判断すれば足りる旨判示した。このような判示は、本件株式の譲渡が甲一族の節税のために行われていることも合理的に推測できるから、相当であると考えられる。
4 第184号(相続税更正処分取消等請求事件)との関係 (1)東京地方裁判所民事3部は、本判決と同時に、本件と原告が同じである第184号相続税更正処分取消等請求事件(以下「相続税事件」という。)についても、判決を下しているが、相続税事件については、本件とは異なって配当還元方式の適用を認めている。すなわち、本件においては、甲が、本件株式をB社に譲渡した4月後に死亡し、Xらが甲を相続することになるが、相続人の1人である甲の配偶者乙(本件のX1)は、A社株式18万3925株(以下単に「A株式」という。)を取得することとなり、当該相続税の申告においても、当該株式の価額を配当還元価額である1株当たり75円で課税価格を計算した。乙は、その根拠について、A株式を取得した段階(課税時期)において、乙及びその同族関係者である親族らの有する議決権の合計割合は14.91%であり、15%未満であるから、評価通達188の(3)に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当する旨主張した。
他方、所轄税務署長は、当該株式の価額を1株当たり2292円で評価すべきであるとして、更正処分等をした。国は、当該更正等が適法である論拠として、評価通達188における同族株主の定義に関する法人税法施行令4条6項は、形式上の議決権行使者と実質上の議決権行使者とが異なる場合には、実質上の議決権行使者が議決権を有しているとみなして保有議決権割合の判定をするという趣旨であるところ、乙およびその親族らとA社の関係会社のC社及びD社(両社ともA社の議決権につきA社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している。)の議決権数を合計すると、A社の議決権総数の21.94%になるから、評価通達188に定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当しない、ことを主張している。
以上の当事者の主張は、要するに、乙は、A株式については評価通達188の(3)を文言どおり適用すれば配当還元方式で評価できると主張し、国は、乙一族の税負担回避のためにB社、C社及びD社にA社株式を所有させているという特別の事情があるから、A株式を類似業種比準方式を適用して評価すべきである旨主張する。
(2)かくして、相続税事件の判決は、事実関係を認定した上で、「課税時期において、A社に合計して30%以上の議決権を有する株主及びその同族関係者がいないため、A社は「同族株主」のいない会社に当たる。また、乙及びその同族関係者である乙親族らの有する議決権の合計割合は14.91%であり、「株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合」にもあたる。よって、本件株式は、評価通達188の(3)の株式に該当するから、「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当する。」と判示した。
そして、同判決は、国が主張する「特別の事情」の存否については、甲、乙らとA社の支配関係、乙らとA社、B社、C社及びD社の支配関係を具さに検討し、「本件株式が「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するものであるにもかかわらず、配当還元方式ではなく、類似業種比準方式により評価することが正当と是認される特別な事情があるとする国の主張は採用することはできず、本件株式につき、配当還元方式によって適正な時価を算定することができない特別の事情があるとは認められない。」と判示した。
(3)以上のように、本件の所得税事件と別件の相続税事件のそれぞれの判決は、同じA社の株式の価額が幾許であるかが争われ、いずれも実質的に当事者を同じくし、かつ、東京地方裁判所の同じ裁判官によって判決されたものであるが、結果的には、前者については、国の主張が認められ、後者については、納税者である乙の主張が認められた。
このような二つの判決を比較すると、いずれも、それぞれの株式の価額につき、所得税基本通達又は評価通達の適用に当たって、各通達を文言どおり適用して、当該文言どおりの評価を否とする「特別の事情」の存在を否定したものである。
ただし、本件の所得税事件については、甲が本件株式をB社に譲渡したことにつき、「A社の役員及び従業員が株主になっているB社に本件株式のみを譲渡することによって、A社における経営の安定を一定程度保持しつつ、本件株式の譲渡による対価収入を減らしても、自身の相続人の相続税の負担を軽減するという以外には考え難」いと判示し、関係会社の一つであるB社の議決権行使の独立性をほぼ否定している。そうであれば、相続税事件において国が主張する法人税法施行令4条6項の適用も可能であるようにも考えられる。
しかし、同じ裁判所の同じ裁判部において、本件の所得税事件については、関係会社の議決権行使の独立性が否定され(注8)、相続税事件については、関係会社の議決権行使の独立性が容認されるという相対立するような判断が下されている。このような結果については、勝手に憶測するに、同じ裁判官が両事件の判断を分かつことによって一つのバランスを採ったものとも言えるが、理解に苦しむところもある。
5 本判決の意義と問題点 資産承継又は事業承継の対策として、承継される財産(資産)の課税上の評価額を引き下げる手法が多用されている。また、そうすることが、資産税専門家の腕の見せ所であると言われている。その対策となる財産(資産)が非上場株式ともなると、その価額の評価が複雑で困難であることもあって、関係通達の取扱いの文言に適合する(文言を潜り抜ける)ように、関係者間で株式を持ち合い、発行会社の合併・分割を行い、あるいは、類似業種比準方式における比準要素を操作するなど、種々の手法が用いられることがある。
本件においても、そのような節税手法として関係会社間等において株式の持ち合い等が行われた事案といえる。本件の所得税事件においては、関係会社に譲渡した本件株式の価額が争われ、別件の相続税事件においては、本件株式が譲渡された後に、本件株式と発行会社を同じくするA株式の価額が争われたものである。よって、本件株式もA株式も、甲一族が所有している場合には、同一族にとっていずれも同じ経済的価値があるものと考えられる。その点に鑑み、いずれの事件においても、当該各課税処分において、いわゆる少数株主に適用される配当還元方式の適用が否定されたものと考えられる。
しかしながら、同じ裁判部において、所得税事件においては、配当還元方式の適用が否定されたが、相続税事件においては、当該方式の適用が容認された。それらの論拠については、前述した判決要旨において明らかにされているが、前述したように、それらの論拠付けに必ずしも整合性があるとも考えられない。ともあれ、本件のような節税対策において、その是非が問われる判決が出されたことは意義のあるところであり、同様な事案を検討している者にとって参考になるものである。
(注1)シャウプ使節団「日本税制報告書」第1編第5章第13節参照。
(注2)このような課税制度の変遷については、品川芳宣「資産の無償等譲渡をめぐる課税と徴収の交錯(1)」税理2004年1月号24頁等参照。
(注3)このみなし譲渡課税の趣旨、問題点については、前出(注2)25頁参照。なお、同族会社等に対する低額譲渡については、2分の1を上回ってもみなし譲渡課税が行われることがある(所基通59-3参照)。
(注4)所得税法に関する裁判例として、名古屋高裁昭和50年11月17日判決(税資83号502頁)、神戸地裁昭和54年5月29日判決(同105号461頁)、東京地裁平成2年2月27日判決(同175号802頁)、東京地裁平成11年11月30日判決(同245号576頁)等参照。
(注5)相続税法に関するものとして、東京地裁平成4年3月11日判決(判例時報1416号73頁)、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等を、法人税法に関するものとして、大阪地裁昭和53年5月11日判決(行裁例集39巻5号943頁)、東京高裁平成6年2月26日判決(税資200号815頁)等を参照。
(注6)これらの問題については、品川芳宣編著「資産・事業承継対策の現状と課題」(大蔵財務協会 平成28年)(第14章事業承継と取引相場のない株式の評価)529頁以下参照。
(注7)詳細については、前出(注6)582頁参照。
(注8)取引上の関係会社の議決権行使の独立性を否定した事例として、東京地裁平成16年3月2日判決(税資254号順号9583)、東京高裁平成17年1月19日判決(同255号順号9900)(以上は、品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第三版」(大蔵財務協会 平成26年)849頁参照)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















