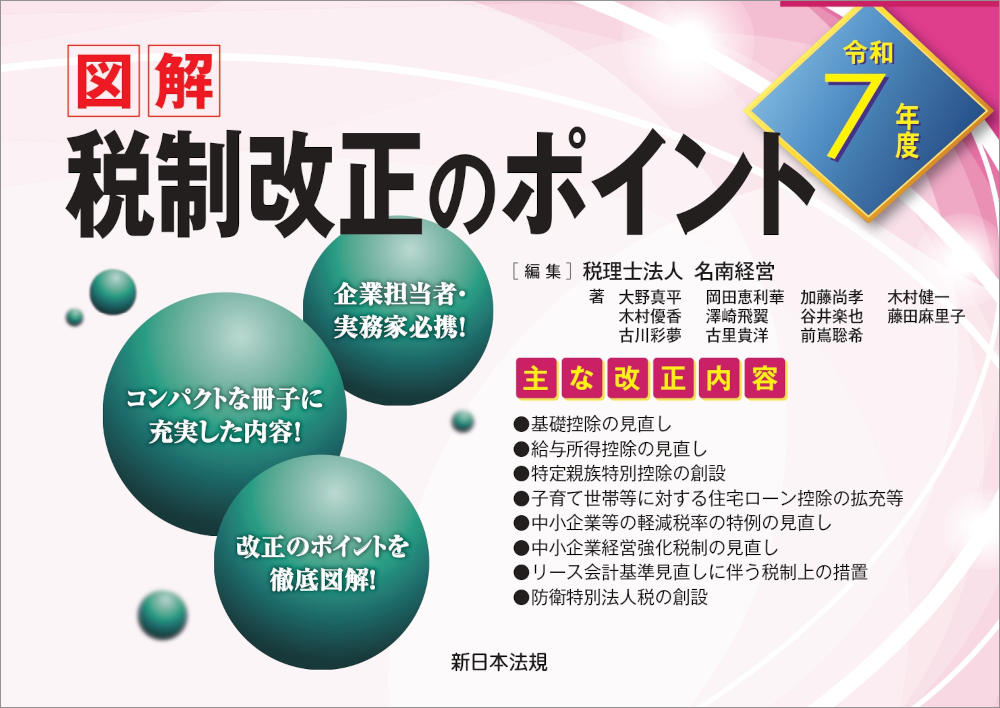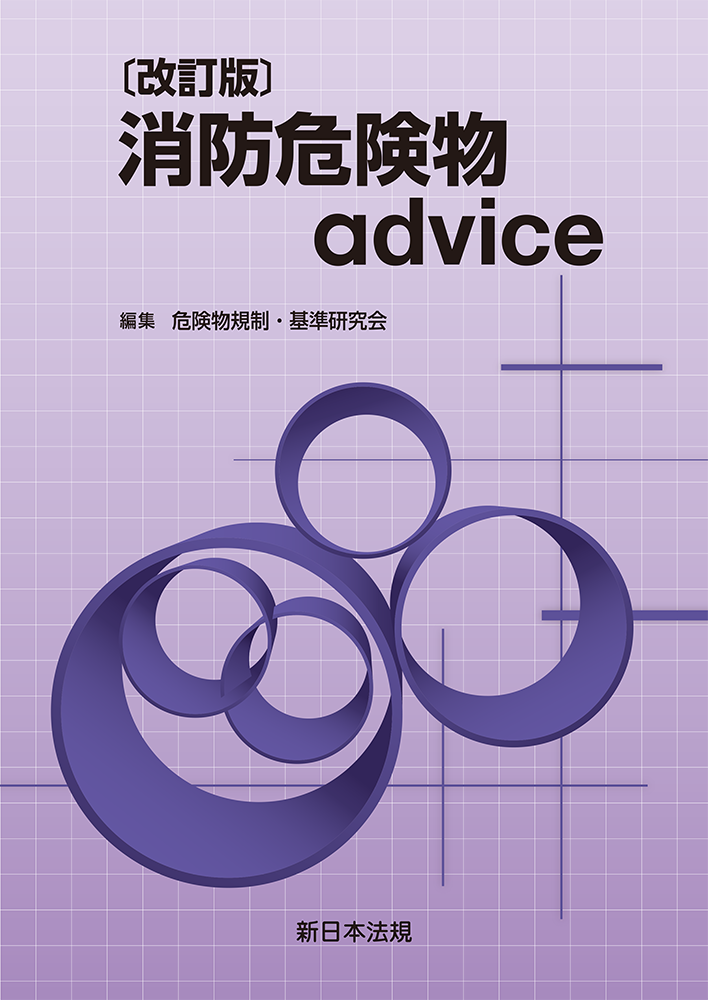解説記事2018年07月30日 【巻頭特集】 「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(1)(2018年7月30日号・№749)
巻頭特集
「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(1)
日本税制研究所 代表理事 税理士 朝長英樹
はじめに
平成30年度税制改正においては、「収益認識に関する会計基準等への対応」と題して、法人税法22条4項(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った収益の額等の計算)の改正、22条の2(収益の額)の創設、53条(返品調整引当金)の廃止、63条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の改正が行われ、さらにこれらの改正に伴う法人税基本通達の改正が行われている。
本稿では、これらの改正の内、22条4項の改正と22条の2を創設する改正の検証を行う。
22条4項の改正と22条の2を創設する改正は、その内容を良く見ると、法人税法の理論と実務にかつてない難しい問題を生じさせるものとなっている。
それにもかかわらず、これらの改正は、本稿の執筆の時点では、未だ大きな話題とはなっていないように見受けられる。
その原因が何かということを考えてみると、これらの改正が「収益認識に関する会計基準」を採用した公開会社等にしか適用されないと受け止められているためであるように思われる。
しかし、これらの改正に関しては、その改正条文や関係通達の定めを正確に読むと、「収益認識に関する会計基準」を実際に採用することが要件となっているとは解されず、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の採用前の法人にもさまざまな改正後の取扱いが適用されることとなっている。
このため、本来は、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の採用前の法人、これらの法人の顧問等となっている税理士等も、これらの改正に無関心ではいられないはずである(注)。
(注)22条4項の改正と22条の2を創設する改正の中で、「収益認識に関する会計基準」に関連して行われたものは、その殆どが収益の一部の計上を繰り延べるものであるため、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の採用前の法人も、それらの処理を行うと、課税を繰り延べることができるものが少なくないはずである。
本稿は、これらの改正の概要を確認するとともに、これらの改正が抱えるさまざまな問題点を明らかにして、今後、これらの改正によって法人税の理論と実務に生じてくることとならざるを得ないさまざまな問題を解決するための手掛かりとなるものを提示しておくことを主たる目的とするものである。
本稿の構成
Ⅰ 法人税法22条2項及び4項の確認
平成30年度税制改正における法人税法22条4項と22条の2の改正は、従前の22条2項(益金の額)と4項を改正したものとなっている。
このため、最初に、22条2項と4項が何を定めているのかということについて、確認を行うこととする。
1 法人税法22条2項は何を定めているのか 1においては、22条2項と4項について、平成30年度税制改正に関係する部分に焦点を絞り、立法過程の確認を行なった後に、これらの規定の解釈を確認することとする。
法令の規定が何を定めているのかということは、基本的には、その規定に書かれていることを読めば分かるわけであるが、その立法過程を調べることにより、なお一層、正確に確認することができる。
(1)法人税法22条2項の立法過程の確認 22条2項は、昭和40年度税制改正によって創設されたわけであるが、当時の大蔵省主税局の昭和39年11月18日の時点における試案(注)は、次のようなものとなっていた。
(注)引用部分の下線は筆者が付したものであり、以下、同様である。
この試案は、大蔵省主税局において、武田昌輔先生や吉牟田勲先生を初めとする方々が企画立案を行って創られたものであり、以下に引用する試案と現在の法人税法22条の条文案も同様である。
この昭和39年11月18日の試案は、上記引用を読むと分かるとおり、総益金の額に算入すべき収入を認識する時期について、「権利確定主義」によって判断するというものであった。
しかし、その後、この試案を示して当時の識者の方々と個別に行った協議において、忠佐市先生から「権利確定主義」にはその内容が不明確である等の問題があって適当ではないという指摘と「実現主義」を採る方がよいという助言を受けたため、再検討が行われ、その結果、「権利確定主義」は採らず、企業会計と同様に「実現主義」を採ることに変更されている。
忠佐市先生との協議の後、昭和39年11月25日と27日に連続して「実現主義」に変更した試案が創られているが、この昭和39年11月27日の試案は、次のとおりである。
この試案においては、益金の額に算入すべき収益の額を認識する時期に関する文言が昭和39年11月18日の試案における「当該事業年度において収入する権利が確定したもの」から「当該事業年度において実現した収益の額」に変わっている。
その後、この試案は更に見直しが行われ、昭和40年1月6日の時点における改正案は、次のようなものとなっている。
この改正案においては、収益の認識時期に関する文言は、昭和39年11月27日の試案と同様で、「当該事業年度において実現した収益の額」となっている。つまり、昭和39年11月18日の試案を最後に「権利確定主義」を採らないこととした後、昭和40年1月6日の改正案までの間は、企業会計と同様に、「実現主義」によって収益の認識時期を判断するということになっていたわけである。
この昭和40年1月6日の改正案においては、「別段の定めがあるものを除き」という文言が初めて入った形になっているが、この部分は、変更が行われたわけではない。この改正案の前までの試案においては、「総益金の額」や「益金の額」の定義規定を設けるものとされており、その定義規定の中で「別段の定めがあるものを除き」という文言が使われていたが、この改正案においては、その定義規定を取り込んで規定を一つにまとめることとしたため、形式上、この改正案の中に「別段の定めがあるものを除き」という文言が初めて入った形になっただけであって、内容自体に変更があったわけではない。
この改正案は、最終的には、次に掲げる現在の法人税法22条2項となった。
この現在の2項を昭和40年1月6日の改正案と比べてみると、「有償又は無償による」「無償による」という文言が追加されている点、「資本等取引以外のものに係る」という文言が追加されている点、そして、「当該事業年度において実現した収益の額」とされていたところが「当該事業年度の収益の額」となっている点が相違点となっている。
これらの相違点の中で、「有償又は無償による」「無償による」という文言が追加されたところから何が分かるかというと、商法や企業会計においては無償取引を現に行われた取引どおりに無償ということで処理するとしても、法人税法においては無償取引についても有償取引と同様に収益の額を認識して益金の額に算入するということであり、法人税法においては、益金の額に算入することとなる収益の額が商法や企業会計における収益の額とは異なることがある、ということである。
このように、2項は、収益に関して時価によって認識する必要があるという、収益の「額」に関する定めともなっているわけである。
また、「資本等取引以外のものに係る」という文言が追加されていることから、所得の金額に算入することとなる収益の「範囲」が明確に分かるようになっている。ただし、この文言を追加したことで課題も生ずることとなっているため、この部分に関しては、22条の2第6項の検証のところで改めて説明を行うこととする。
また、「当該事業年度において実現した収益の額」とされていたところが「当該事業年度の収益の額」となったことから、収益の認識時期の基準が「実現主義」ではなくなったことが明確に確認できる。
「当該事業年度の」という文言の中の「の」に関しては、『昭和40年 改正税法のすべて』(大蔵財務協会)では「帰属する」という意味であるとの説明(103頁)がなされているのみであるが、当時の大蔵省及び国税庁の職員の解説によれば、資産の販売等に関しては「引渡基準」に、役務の提供に関しては「完了基準」によることとされたことが明確である。昭和44年の法人税基本通達も、収益の認識時期の基準の原則を「引渡基準」と「完了基準」とすることとなっている(注)。
(注)「引渡基準」と「完了基準」を採っても、「権利確定主義」や「実現主義」を採っても、現実には、大部分のケースが収益認識の時期を同じ事業年度と判断することとなるわけであるが、全てのケースが同じ事業年度となるわけではないため、法人税法が収益認識の基準の原則としていずれの基準を採っているのかということは、明確にしておく必要があるわけである。
この「引渡基準」と「完了基準」は、立法過程の最後の段階で突然出てきたものではなく、立法過程の初期の段階から、具体的な基準としては「引渡し」が適当であって昭和40年前の実務も現実には「引渡基準」と「完了基準」となっていた、という話が出ており、同年前からの実務に改めて目を向けることによって浮かび上がってきたものということになる(注)。
(注)昭和40年に22条2項が創設された後、昭和44年に法人税基本通達において「引渡基準」と「完了基準」が定められる前までの間に、当時の大蔵省主税局税制第一課の職員によって起稿された記事の次の引用部分は、昭和40年に22条2項において「当該事業年度の収益の額」とすると定めた際に、同年前の実際の取扱いが「引渡基準」であって2項を定めた際にも「引渡基準」を採るべきであると考えられていた、ということを確認することができるものとなっており、同時に、同年前の通達本文の取扱いは「権利確定主義」と解されるものではあったが2項を定めた際には「権利確定主義」は採るべきでなく「引渡基準」を採るべきであると考えられていた、ということも確認することができるものとなっている。
(大蔵省税制第一課 清水延晏「税法上の収益の計上時期」税務弘報Vol.14 no.8 昭和41年)
『昭和40年 改正税法のすべて』においては、「実現主義」を採らないこととした理由について、次のように説明されている。
(103頁)
現在、法人税法における収益の認識時期の基準に関しては、「権利確定主義」であるとか「実現主義」であるとかという見解や判決も一部に見受けられる状態となっているわけであるが、22条2項の試案と改正案の変遷を辿り、『昭和40年 改正税法のすべて』等の当時の大蔵省主税局や国税庁の職員の解説を確認すれば、「権利確定主義」や「実現主義」は採らないこととされ、「引渡基準」と「完了基準」を採ることとされた、ということを容易に確認することができるわけである(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』においては、「収益認識に関する会計基準における収益の認識時期である「履行義務を充足した時に又は充足するにつれて」について、〔中略〕「実現」や権利の「確定」の時期と大幅には変わらないと考えられます」(271頁)と記述されているが、この記述に関しては、その意図が明確ではない。
また、国税庁の「「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~」においても、『平成30年度 税制改正の解説』の上記の記述に由来すると考えられる「履行義務の充足により収益を認識するという考え方は、法人税法上の実現主義又は権利確定主義の考え方と齟齬をきたすものではない」(16頁)という記述が存在するが、この記述に関しても、特に「法人税法上の実現主義又は権利確定主義」という部分について、それが何処にあるのかということが不明である。
昭和44年に改正された法人税基本通達が収益認識の時期の原則としてどのような基準(主義)を採っているのかということは、「解釈」の問題ではなく、「事実」の問題である。2項の「当該事業年度の収益の額」について、同項の条文案を作成した大蔵省主税局及び国税庁が示した「解釈」よりも説得力のある証拠や理由を示して他の「解釈」を主張するということはあり得るわけであるが、法人税基本通達が収益認識の時期の原則としてどのような基準(主義)を採っているのかということは、「事実」の問題であるため、「解釈」とは異なり、一つの明確な答えが出てくることとなる。
ところで、『昭和40年 改正税法のすべて』においては、上記の引用の後に次のような文章が存在するため、収益認識の時期の取扱いについては「今後の検討にゆだねられている事項」として再検討と法改正が必要とされる状況が昭和40年から続いていたと誤解されるおそれがあるが、この「今後の検討」とは、4年後の昭和44年に制定される法人税基本通達による対応を予定した「今後の検討」である。
(103頁)
当時の大蔵省主税局税制第一課が作成した「昭和40年法人税法の全文改正に関する検討点(久保田メモ)」においては、次のように、法人税基本通達で具体的な基準を規定することが明記されており、実際に、昭和44年に法人税基本通達の改正によって「引渡基準」と「完了基準」を採ることとされている(注)。
(20頁)
(注)財務省『平成30年度 税制改正の解説』においては、「収益の認識時期に関しても通則的な規定が設けられました」(271頁)というように、平成30年度税制改正前に「通則的な規定」が無かったと受け止められかねない記述がなされているが、同改正前には、2項で「当該事業年度の収益の額」という文言で収益の認識時期を定め、その「の」は「帰属する」と解釈すべきものであると説明した上で、その具体的な内容を法人税基本通達で「引渡基準」と「完了基準」と定める、という整理がなされていた。
収益認識の時期に関する具体的な取扱いに関しては、実務と企業会計等における取扱いを考慮しながら定める必要があることから、法令ではなく、通達によって対応することとされており、現に、平成30年度税制改正前には、会計基準の変更に対応する取扱いが必要となった場合には、法人税基本通達による対応がなされてきていたわけであり、このような整理には、妥当性があるわけである。
このため、平成30年度の22条の2第1項を創設する改正のように、従来の妥当性のある整理の仕方を変更する改正を行うという場合には、本来は、その変更の理由と変更後の整理になお一層の妥当性があるということを明確に説明する必要がある。
「別段の定め」を除く旨の定めも、試案と改正案から現在の2項にそのまま引き継がれているわけであるが、この「別段の定め」が23条以下であることは、改めて言うまでもない。
このように、立法過程における事実を確認することにより、2項は、益金の額に算入する収益の額を「引渡基準」と「完了基準」によって認識するという収益の認識時期(注)、「時価」に基づいて収益の額を計算するという収益の額の計算、そして、資本等取引に係る収益の額以外の収益の額のみを益金の額に算入するという収益の範囲の3つを定めた規定となっている、ということを明確に確認することができる。
(注)平成30年度税制改正においては、役務の提供に係る収益の認識時期の原則に関して、従前の「完了基準」を「提供基準」(「役務の提供の日の属する事業年度」(法法22の2①)に収益を認識するもの)に変更して収益を従前よりも早く認識しなければならないものとしているが、その理由も、全く説明されていない。
この改正は、平成30年4月1日以後終了する事業年度以後の事業年度について適用するというように、納税者に不利益を与える遡及適用をするものとなっている事情もあるため、本来は、遡及適用をする理由も含めて、改正の理由を明確に説明する必要がある。
(2)法人税法22条2項の条文の解釈の確認 22条2項は、上記(1)において引用したとおりであるが、(2)においては、同項の条文を見ながら、同項がどのような解釈となるのかということを確認することとする。
2項においては、当該事業年度の「益金の額」に算入すべき金額は、「収益の額」とされている。
このため、「収益の額」があれば「益金の額」に算入されるということになるわけであるが、「収益の額」と「益金の額」とは異なるものであるということを理解しておく必要がある。この「収益の額」と「益金の額」の相違は、資本等取引の取扱いを考えるに当たって非常に重要となるものであるため、22条の2第6項の検証のところで改めて述べることとする。
また、2項においては、「別段の定めがあるものを除き」、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」と規定しており、この「資産の販売〔中略〕に係る当該事業年度の収益の額とする」という文言のいずれの部分についても「別段の定め」が設けられることがあるという前提に立った上で、「別段の定め」がなければ、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額」は、全て「益金の額」となるものとされている。
この「資産の販売〔中略〕に係る当該事業年度の収益の額とする」という部分に関しては、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け」が例示であり、その例示を除けば、「その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」となるわけであるが、「以外」という用語で除かれているのは、「資本等取引に係る当該事業年度の収益の額」であり、その除かれている部分を除くと、「その他の取引に係る当該事業年度の収益の額とする」ということになる。
この「その他の取引に係る当該事業年度の収益の額とする」という部分の「当該事業年度の収益の額」の中の「の」に関しては、「帰属する」と解することとなると説明した上で、法人税基本通達(平成30年5月30日改正前)2-1-1(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)、2-1-14(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)、2-1-5(請負による収益の帰属の時期)などによって「引渡基準」と「完了基準」によることを定める、ということになっている。
この「その他の取引に係る当該事業年度の収益の額とする」という部分にある「収益の額」に関しては、「時価」に基づいて収益の額を計算することとなるわけであるが、その点に関しては、自明であるため、わざわざ通達を設けるなどというようなこともされていない(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』の説明においては、無償取引に関しても時価取引と同様の収益があると認識するということを判示した最高裁判決を挙げて、「最高裁平成7年12月19日判決の趣旨が法令上明確化されるとともに、収益認識に関する会計基準のうち対価の回収可能性や返品の可能性を法人税の所得の金額の計算における収益の額の算定上考慮することを排除するため、収益の額として益金の額に算入する金額に関する通則的な規定が設けられました。」(270・271頁)と述べられている。
しかし、法人税法においては無償取引に関しても時価取引と同様の収益があるとすることは、既に2項に明確に定められていることであって、新たな条文を創って「法令上明確化」をするなどということをする必要はない。
また、企業会計において収益の額をどのように認識してどのように会計処理をするのかということも、法人税法において「時価」に基づいて収益の額を認識することとは、何の関係もない。「収益認識に関する会計基準」において「対価の回収可能性や返品の可能性」を考慮して収益の計上額を従来とは異なる金額とする会計処理を新たに行うこととされたとしても、それによって法人税法において「時価」とする金額が変わるわけでもなければ法人税法における収益の額の計算方法などが変わるわけでもないことから、それが法人税において従来の取扱いを維持するために新たな規定を設けなければならない理由となるなどということは、ないわけである。
法人税においては、「所得の金額」の計算に関して、極力、企業会計における利益の額の計算の取扱いと同じ取扱いとするべく、法人税基本通達において企業会計を尊重したさまざまな取扱いを定めてはいるものの、企業会計を「所得の金額」の計算の手段として用いているわけではないため、会計処理が変わったとしても、法人税法の規定や法人税基本通達の定めを変えない限り、法人税における取扱いが変わることはない。
この点は、法人税法に存在しない企業会計上の各種引当金などの取扱いが変わったとしても、法人税には何の影響もないことを思い起こすと、容易に理解できるはずである。
このように、2項は、同項の文言に即して解釈したとしても、上記(1)において確認したところと同じく、「引渡基準」と「完了基準」によって収益を認識し、「時価」に基づいて収益の額を計算し、そして、資本等取引に係る収益の額以外の収益の額のみを益金の額に算入する、というものとなっているわけである。
(第2回に続く)
「収益認識に関する会計基準等への対応」として平成30年度に行われた税法・通達改正の検証(1)
日本税制研究所 代表理事 税理士 朝長英樹
はじめに
平成30年度税制改正においては、「収益認識に関する会計基準等への対応」と題して、法人税法22条4項(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従った収益の額等の計算)の改正、22条の2(収益の額)の創設、53条(返品調整引当金)の廃止、63条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の改正が行われ、さらにこれらの改正に伴う法人税基本通達の改正が行われている。
本稿では、これらの改正の内、22条4項の改正と22条の2を創設する改正の検証を行う。
22条4項の改正と22条の2を創設する改正は、その内容を良く見ると、法人税法の理論と実務にかつてない難しい問題を生じさせるものとなっている。
それにもかかわらず、これらの改正は、本稿の執筆の時点では、未だ大きな話題とはなっていないように見受けられる。
その原因が何かということを考えてみると、これらの改正が「収益認識に関する会計基準」を採用した公開会社等にしか適用されないと受け止められているためであるように思われる。
しかし、これらの改正に関しては、その改正条文や関係通達の定めを正確に読むと、「収益認識に関する会計基準」を実際に採用することが要件となっているとは解されず、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の採用前の法人にもさまざまな改正後の取扱いが適用されることとなっている。
このため、本来は、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の採用前の法人、これらの法人の顧問等となっている税理士等も、これらの改正に無関心ではいられないはずである(注)。
(注)22条4項の改正と22条の2を創設する改正の中で、「収益認識に関する会計基準」に関連して行われたものは、その殆どが収益の一部の計上を繰り延べるものであるため、中小法人や「収益認識に関する会計基準」の採用前の法人も、それらの処理を行うと、課税を繰り延べることができるものが少なくないはずである。
本稿は、これらの改正の概要を確認するとともに、これらの改正が抱えるさまざまな問題点を明らかにして、今後、これらの改正によって法人税の理論と実務に生じてくることとならざるを得ないさまざまな問題を解決するための手掛かりとなるものを提示しておくことを主たる目的とするものである。
本稿の構成
| 本稿の全体の構成は、次のとおりである。 はじめに(今号) Ⅰ 法人税法22条2項及び4項の確認(今号) 1.法人税法22条2項は何を定めているのか(今号) 2.法人税法22条4項は何を定めているのか Ⅱ 平成30年度税制改正後の法人税法22条4項と22条の2の確認と検証 Ⅲ 財務省『平成30年度 税制改正の解説』の説明の検証 1.「(6)公正処理基準と別段の定めとの関係の明確化」(「3 改正の内容」)の説明の検証 2.「(3)収益の額を益金の額に算入する時期」(「2 改正の趣旨」)の説明の検証 3.「(2)収益の額として益金の額に算入する金額」(「2 改正の趣旨」)の説明の検証 4.「(1)収益の額を益金の額に算入する時期」(「3 改正の内容」)の説明の検証 5.「(2)収益の額として益金の額に算入する金額」(「3 改正の内容」)の説明の検証 6.「(3)資本等取引との関係」(「3 改正の内容」)の検証 7.「4 適用関係及び経過措置」の説明の検証 Ⅳ 国税庁「「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~」等の説明の検証 1.「Ⅰ 収益認識会計の制定と30年度法人税法の改正」の説明の検証 2.「Ⅱ 法人税基本通達の対応」の説明の検証 3.「○ 収益認識準による場合の取扱いの例」の説明の検証 最後に |
Ⅰ 法人税法22条2項及び4項の確認
平成30年度税制改正における法人税法22条4項と22条の2の改正は、従前の22条2項(益金の額)と4項を改正したものとなっている。
このため、最初に、22条2項と4項が何を定めているのかということについて、確認を行うこととする。
1 法人税法22条2項は何を定めているのか 1においては、22条2項と4項について、平成30年度税制改正に関係する部分に焦点を絞り、立法過程の確認を行なった後に、これらの規定の解釈を確認することとする。
法令の規定が何を定めているのかということは、基本的には、その規定に書かれていることを読めば分かるわけであるが、その立法過程を調べることにより、なお一層、正確に確認することができる。
(1)法人税法22条2項の立法過程の確認 22条2項は、昭和40年度税制改正によって創設されたわけであるが、当時の大蔵省主税局の昭和39年11月18日の時点における試案(注)は、次のようなものとなっていた。
| (総益金の額に算入すべき金額の帰属事業年度) 第 条 各事業年度の総益金の額に算入すべき金額は、当該事業年度において収入する権利が確定したもの(収入を伴わないものについては当該事業年度の確定した決算において計上した金額)とする。 |
この試案は、大蔵省主税局において、武田昌輔先生や吉牟田勲先生を初めとする方々が企画立案を行って創られたものであり、以下に引用する試案と現在の法人税法22条の条文案も同様である。
この昭和39年11月18日の試案は、上記引用を読むと分かるとおり、総益金の額に算入すべき収入を認識する時期について、「権利確定主義」によって判断するというものであった。
しかし、その後、この試案を示して当時の識者の方々と個別に行った協議において、忠佐市先生から「権利確定主義」にはその内容が不明確である等の問題があって適当ではないという指摘と「実現主義」を採る方がよいという助言を受けたため、再検討が行われ、その結果、「権利確定主義」は採らず、企業会計と同様に「実現主義」を採ることに変更されている。
忠佐市先生との協議の後、昭和39年11月25日と27日に連続して「実現主義」に変更した試案が創られているが、この昭和39年11月27日の試案は、次のとおりである。
| (各事業年度の益金の額及び損金の額に算入すべき金額) 第二十三条 内国法人の各事業年度の益金の額に算入すべき金額は、当該事業年度において実現した収益の額の合計額とする。 |
その後、この試案は更に見直しが行われ、昭和40年1月6日の時点における改正案は、次のようなものとなっている。
| (各事業年度に帰属すべき益金の額及び損金の額) 第二十三条 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、譲渡若しくは貸付け、役務の提供その他の事由により当該事業年度において実現した収益の額の合計額とする。 |
この昭和40年1月6日の改正案においては、「別段の定めがあるものを除き」という文言が初めて入った形になっているが、この部分は、変更が行われたわけではない。この改正案の前までの試案においては、「総益金の額」や「益金の額」の定義規定を設けるものとされており、その定義規定の中で「別段の定めがあるものを除き」という文言が使われていたが、この改正案においては、その定義規定を取り込んで規定を一つにまとめることとしたため、形式上、この改正案の中に「別段の定めがあるものを除き」という文言が初めて入った形になっただけであって、内容自体に変更があったわけではない。
この改正案は、最終的には、次に掲げる現在の法人税法22条2項となった。
| (各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 省略 2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 |
これらの相違点の中で、「有償又は無償による」「無償による」という文言が追加されたところから何が分かるかというと、商法や企業会計においては無償取引を現に行われた取引どおりに無償ということで処理するとしても、法人税法においては無償取引についても有償取引と同様に収益の額を認識して益金の額に算入するということであり、法人税法においては、益金の額に算入することとなる収益の額が商法や企業会計における収益の額とは異なることがある、ということである。
このように、2項は、収益に関して時価によって認識する必要があるという、収益の「額」に関する定めともなっているわけである。
また、「資本等取引以外のものに係る」という文言が追加されていることから、所得の金額に算入することとなる収益の「範囲」が明確に分かるようになっている。ただし、この文言を追加したことで課題も生ずることとなっているため、この部分に関しては、22条の2第6項の検証のところで改めて説明を行うこととする。
また、「当該事業年度において実現した収益の額」とされていたところが「当該事業年度の収益の額」となったことから、収益の認識時期の基準が「実現主義」ではなくなったことが明確に確認できる。
「当該事業年度の」という文言の中の「の」に関しては、『昭和40年 改正税法のすべて』(大蔵財務協会)では「帰属する」という意味であるとの説明(103頁)がなされているのみであるが、当時の大蔵省及び国税庁の職員の解説によれば、資産の販売等に関しては「引渡基準」に、役務の提供に関しては「完了基準」によることとされたことが明確である。昭和44年の法人税基本通達も、収益の認識時期の基準の原則を「引渡基準」と「完了基準」とすることとなっている(注)。
(注)「引渡基準」と「完了基準」を採っても、「権利確定主義」や「実現主義」を採っても、現実には、大部分のケースが収益認識の時期を同じ事業年度と判断することとなるわけであるが、全てのケースが同じ事業年度となるわけではないため、法人税法が収益認識の基準の原則としていずれの基準を採っているのかということは、明確にしておく必要があるわけである。
この「引渡基準」と「完了基準」は、立法過程の最後の段階で突然出てきたものではなく、立法過程の初期の段階から、具体的な基準としては「引渡し」が適当であって昭和40年前の実務も現実には「引渡基準」と「完了基準」となっていた、という話が出ており、同年前からの実務に改めて目を向けることによって浮かび上がってきたものということになる(注)。
(注)昭和40年に22条2項が創設された後、昭和44年に法人税基本通達において「引渡基準」と「完了基準」が定められる前までの間に、当時の大蔵省主税局税制第一課の職員によって起稿された記事の次の引用部分は、昭和40年に22条2項において「当該事業年度の収益の額」とすると定めた際に、同年前の実際の取扱いが「引渡基準」であって2項を定めた際にも「引渡基準」を採るべきであると考えられていた、ということを確認することができるものとなっており、同時に、同年前の通達本文の取扱いは「権利確定主義」と解されるものではあったが2項を定めた際には「権利確定主義」は採るべきでなく「引渡基準」を採るべきであると考えられていた、ということも確認することができるものとなっている。
| 税法における収益計上の時期に関する基本的な取扱いとして、次のものがある(基本通達249)。 「資産の売買による損益は、所有権移転登記の有無及び代金支払の済否を問わず売買契約の効力発生の日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。但し、商品、製品等の販売については、商品、製品等の引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」 この取扱通達の解釈をめぐり、多くの議論がある。すなわち、この取扱通達の本文によると、商品の売買による収益の計上時期も、売買契約の効力発生時となり、民法上の所有権移転時を中心としてその計上時期を判定することとなり、それが原則であると解されるおそれがあるので、従来から多くの批判が加えられてきた。 しかし、この通達のもとにおいても、実際上は、企業の収益の中心となつている商品などの売買による損益は、この通達のただし書により取り扱われ、原則として、引渡時の損益として取り扱われてきたのである。 〔中略〕現在においては、商品などについては、税法における収益計上の時期は、その引渡しの時であり、また、その販売の事実の認識については弾力的に取り扱われており、原則として、企業会計原則における収益の計上時期と一致しているものといえる。 |
『昭和40年 改正税法のすべて』においては、「実現主義」を採らないこととした理由について、次のように説明されている。
| 当該事業年度において実現した収益の額」とするべきかどうかについて検討の行なわれたところでありますが、この実現という用語は主として企業会計の用語であって、この実現という用語の確定した内容というものも必ずしも統一的に解されているかどうかについて疑問があるのみならず、現在の税務慣行上の収益計上時期についての取り扱いがこの実現の内容にほぼ近いものと考えられるとしてもこれが一致するという保証がないため、実現という用語を用いることは避けられることとなったものです。 |
現在、法人税法における収益の認識時期の基準に関しては、「権利確定主義」であるとか「実現主義」であるとかという見解や判決も一部に見受けられる状態となっているわけであるが、22条2項の試案と改正案の変遷を辿り、『昭和40年 改正税法のすべて』等の当時の大蔵省主税局や国税庁の職員の解説を確認すれば、「権利確定主義」や「実現主義」は採らないこととされ、「引渡基準」と「完了基準」を採ることとされた、ということを容易に確認することができるわけである(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』においては、「収益認識に関する会計基準における収益の認識時期である「履行義務を充足した時に又は充足するにつれて」について、〔中略〕「実現」や権利の「確定」の時期と大幅には変わらないと考えられます」(271頁)と記述されているが、この記述に関しては、その意図が明確ではない。
また、国税庁の「「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~」においても、『平成30年度 税制改正の解説』の上記の記述に由来すると考えられる「履行義務の充足により収益を認識するという考え方は、法人税法上の実現主義又は権利確定主義の考え方と齟齬をきたすものではない」(16頁)という記述が存在するが、この記述に関しても、特に「法人税法上の実現主義又は権利確定主義」という部分について、それが何処にあるのかということが不明である。
昭和44年に改正された法人税基本通達が収益認識の時期の原則としてどのような基準(主義)を採っているのかということは、「解釈」の問題ではなく、「事実」の問題である。2項の「当該事業年度の収益の額」について、同項の条文案を作成した大蔵省主税局及び国税庁が示した「解釈」よりも説得力のある証拠や理由を示して他の「解釈」を主張するということはあり得るわけであるが、法人税基本通達が収益認識の時期の原則としてどのような基準(主義)を採っているのかということは、「事実」の問題であるため、「解釈」とは異なり、一つの明確な答えが出てくることとなる。
ところで、『昭和40年 改正税法のすべて』においては、上記の引用の後に次のような文章が存在するため、収益認識の時期の取扱いについては「今後の検討にゆだねられている事項」として再検討と法改正が必要とされる状況が昭和40年から続いていたと誤解されるおそれがあるが、この「今後の検討」とは、4年後の昭和44年に制定される法人税基本通達による対応を予定した「今後の検討」である。
| なお、この収益の額をどのような基準によって当該事業年度に帰属させるべきか、あるいはいかなる表現によって具体的にその帰属関係を明らかにするかについては、なお今後の検討にゆだねられている事項と考えられます。 |
当時の大蔵省主税局税制第一課が作成した「昭和40年法人税法の全文改正に関する検討点(久保田メモ)」においては、次のように、法人税基本通達で具体的な基準を規定することが明記されており、実際に、昭和44年に法人税基本通達の改正によって「引渡基準」と「完了基準」を採ることとされている(注)。
| 当該事業年度の益金の額に算入すべき金額、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、益金損金と帰属事業年度との関係を明らかにするものである。 具体的には取扱いで規定する。 |
(注)財務省『平成30年度 税制改正の解説』においては、「収益の認識時期に関しても通則的な規定が設けられました」(271頁)というように、平成30年度税制改正前に「通則的な規定」が無かったと受け止められかねない記述がなされているが、同改正前には、2項で「当該事業年度の収益の額」という文言で収益の認識時期を定め、その「の」は「帰属する」と解釈すべきものであると説明した上で、その具体的な内容を法人税基本通達で「引渡基準」と「完了基準」と定める、という整理がなされていた。
収益認識の時期に関する具体的な取扱いに関しては、実務と企業会計等における取扱いを考慮しながら定める必要があることから、法令ではなく、通達によって対応することとされており、現に、平成30年度税制改正前には、会計基準の変更に対応する取扱いが必要となった場合には、法人税基本通達による対応がなされてきていたわけであり、このような整理には、妥当性があるわけである。
このため、平成30年度の22条の2第1項を創設する改正のように、従来の妥当性のある整理の仕方を変更する改正を行うという場合には、本来は、その変更の理由と変更後の整理になお一層の妥当性があるということを明確に説明する必要がある。
「別段の定め」を除く旨の定めも、試案と改正案から現在の2項にそのまま引き継がれているわけであるが、この「別段の定め」が23条以下であることは、改めて言うまでもない。
このように、立法過程における事実を確認することにより、2項は、益金の額に算入する収益の額を「引渡基準」と「完了基準」によって認識するという収益の認識時期(注)、「時価」に基づいて収益の額を計算するという収益の額の計算、そして、資本等取引に係る収益の額以外の収益の額のみを益金の額に算入するという収益の範囲の3つを定めた規定となっている、ということを明確に確認することができる。
(注)平成30年度税制改正においては、役務の提供に係る収益の認識時期の原則に関して、従前の「完了基準」を「提供基準」(「役務の提供の日の属する事業年度」(法法22の2①)に収益を認識するもの)に変更して収益を従前よりも早く認識しなければならないものとしているが、その理由も、全く説明されていない。
この改正は、平成30年4月1日以後終了する事業年度以後の事業年度について適用するというように、納税者に不利益を与える遡及適用をするものとなっている事情もあるため、本来は、遡及適用をする理由も含めて、改正の理由を明確に説明する必要がある。
(2)法人税法22条2項の条文の解釈の確認 22条2項は、上記(1)において引用したとおりであるが、(2)においては、同項の条文を見ながら、同項がどのような解釈となるのかということを確認することとする。
2項においては、当該事業年度の「益金の額」に算入すべき金額は、「収益の額」とされている。
このため、「収益の額」があれば「益金の額」に算入されるということになるわけであるが、「収益の額」と「益金の額」とは異なるものであるということを理解しておく必要がある。この「収益の額」と「益金の額」の相違は、資本等取引の取扱いを考えるに当たって非常に重要となるものであるため、22条の2第6項の検証のところで改めて述べることとする。
また、2項においては、「別段の定めがあるものを除き」、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」と規定しており、この「資産の販売〔中略〕に係る当該事業年度の収益の額とする」という文言のいずれの部分についても「別段の定め」が設けられることがあるという前提に立った上で、「別段の定め」がなければ、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額」は、全て「益金の額」となるものとされている。
この「資産の販売〔中略〕に係る当該事業年度の収益の額とする」という部分に関しては、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受け」が例示であり、その例示を除けば、「その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」となるわけであるが、「以外」という用語で除かれているのは、「資本等取引に係る当該事業年度の収益の額」であり、その除かれている部分を除くと、「その他の取引に係る当該事業年度の収益の額とする」ということになる。
この「その他の取引に係る当該事業年度の収益の額とする」という部分の「当該事業年度の収益の額」の中の「の」に関しては、「帰属する」と解することとなると説明した上で、法人税基本通達(平成30年5月30日改正前)2-1-1(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)、2-1-14(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)、2-1-5(請負による収益の帰属の時期)などによって「引渡基準」と「完了基準」によることを定める、ということになっている。
この「その他の取引に係る当該事業年度の収益の額とする」という部分にある「収益の額」に関しては、「時価」に基づいて収益の額を計算することとなるわけであるが、その点に関しては、自明であるため、わざわざ通達を設けるなどというようなこともされていない(注)。
(注)『平成30年度 税制改正の解説』の説明においては、無償取引に関しても時価取引と同様の収益があると認識するということを判示した最高裁判決を挙げて、「最高裁平成7年12月19日判決の趣旨が法令上明確化されるとともに、収益認識に関する会計基準のうち対価の回収可能性や返品の可能性を法人税の所得の金額の計算における収益の額の算定上考慮することを排除するため、収益の額として益金の額に算入する金額に関する通則的な規定が設けられました。」(270・271頁)と述べられている。
しかし、法人税法においては無償取引に関しても時価取引と同様の収益があるとすることは、既に2項に明確に定められていることであって、新たな条文を創って「法令上明確化」をするなどということをする必要はない。
また、企業会計において収益の額をどのように認識してどのように会計処理をするのかということも、法人税法において「時価」に基づいて収益の額を認識することとは、何の関係もない。「収益認識に関する会計基準」において「対価の回収可能性や返品の可能性」を考慮して収益の計上額を従来とは異なる金額とする会計処理を新たに行うこととされたとしても、それによって法人税法において「時価」とする金額が変わるわけでもなければ法人税法における収益の額の計算方法などが変わるわけでもないことから、それが法人税において従来の取扱いを維持するために新たな規定を設けなければならない理由となるなどということは、ないわけである。
法人税においては、「所得の金額」の計算に関して、極力、企業会計における利益の額の計算の取扱いと同じ取扱いとするべく、法人税基本通達において企業会計を尊重したさまざまな取扱いを定めてはいるものの、企業会計を「所得の金額」の計算の手段として用いているわけではないため、会計処理が変わったとしても、法人税法の規定や法人税基本通達の定めを変えない限り、法人税における取扱いが変わることはない。
この点は、法人税法に存在しない企業会計上の各種引当金などの取扱いが変わったとしても、法人税には何の影響もないことを思い起こすと、容易に理解できるはずである。
このように、2項は、同項の文言に即して解釈したとしても、上記(1)において確認したところと同じく、「引渡基準」と「完了基準」によって収益を認識し、「時価」に基づいて収益の額を計算し、そして、資本等取引に係る収益の額以外の収益の額のみを益金の額に算入する、というものとなっているわけである。
(第2回に続く)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.