会計ニュース2003年03月17日 平成18年3月期から全面適用 どうなる!?固定資産の減損会計 ASB・固定資産の減損会計における適用指針の概要を紹介
ニュース特集
平成18年3月期から全面適用 どうなる!?固定資産の減損会計
ASB・固定資産の減損会計における適用指針の概要を紹介
企業会計基準委員会(ASB)は3月5日、「『固定資産の減損に係る会計基準の適用指針』の検討状況の整理」を公表しています。固定資産の減損会計は平成18年3月期から全面適用されることになりますが、平成16年3月期からの早期適用が認められています。このため、適用指針の策定を行っている企業会計基準委員会では、今年の秋頃を目処に適用指針を決定する予定です。ただし、今回の固定資産の減損会計は、企業にとっては大きな影響を与えることも予想されるため、適用指針を決定する前にその論点を明らかにしたものです。今回は、この適用指針の検討状況の概要をお伝えします。
※原文は財務会計基準機構のホームページで閲覧することができます!
http://www.asb.or.jp/summary_issue/impairment/impairment.html
固定資産の減損会計とは?
固定資産の減損会計は、連結範囲の見直し、金融商品会計や退職給付会計の導入など、一連のいわゆる会計ビッグバンの締めくくりの一つといえるもので、米国会計基準や国際会計基準ではすでに導入されています。固定資産の減損会計とは、資産又は資産グループの収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させるよう帳簿価額を減額する会計処理のことです。時価の変動を評価に反映させる時価会計とは異なります。
減損会計の対象となる資産は何?
固定資産の減損会計の対象となる資産は、当然のことながら固定資産となります。有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が対象になります(図1参照)。ただし、金融商品会計基準における金融資産、税効果会計基準における繰延税金資産、研究開発会計基準における市場販売目的のソフトウェアなど、他の基準に減損処理に関する定めがある資産については対象から除かれています。
それでは、固定資産の減損会計の手順に従い、それぞれの項目についてみていきます(図2参照)。
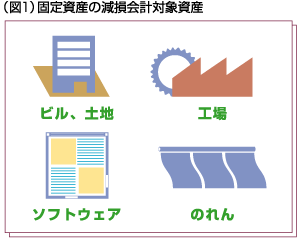
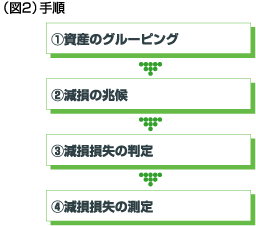
①資産のグルーピング
固定資産の減損会計を適用する際に行う手順の最初は資産のグルーピングを行うことです。個別の固定資産について、減損しているかどうかを検討することはたいへんなことです。
このため、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位(管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の最小単位)をグルーピングすることになります。この資産グループを単位として減損の有無があるかどうかを検討することになります。
なお、資産のグルーピングを大きくすれば、全体としては減損を認識しづらくなります。資産のグルーピングをどのように行うかは実務上の大きな論点になりそうです。
②減損の兆候
減損の兆候では、減損損失を認識する必要がある資産グループかどうかを判別していく作業を行います。実際には、個々の企業で判断することになりますが、実務上の指針として一定の目安も設けられています。今回公表された「適用指針の検討状況」では、右の表にある事象がある場合には、「減損の兆候あり」ということになります。
また、今回のポイントとしては、「市場価格が著しく下落した場合」の数値基準が挙げられます。減損会計専門委員会では、当初、「市場価格が帳簿価額からおおむね30%程度以上下落した場合」とされていましたが、最終的には、50%程度以上下落と30%程度以上の下落の両論併記となっています(※ただし、30%の方がよいとの提案がなされています)。
企業側からすれば、50%という数値の方が、減損会計を適用する上で減損の兆候という“網”にかからないということになります。したがって、この点は最後まで議論が続く項目であると考えられます。
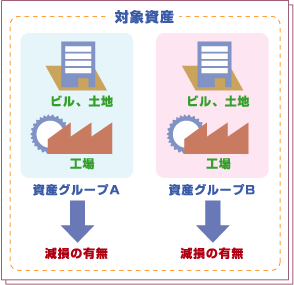
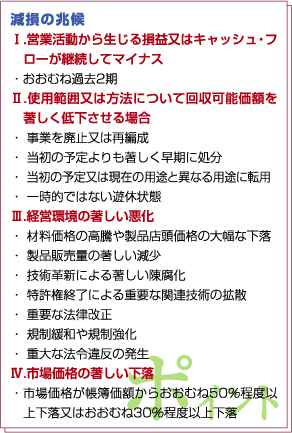
③減損損失の判定
減損の兆候がある資産又は資産グループについての減損損失を認識するかどうかの判定は、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することになります。割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識します。
さて、この割引前将来キャッシュ・フローを見積もる期間は、資産の経済的残存使用年数又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数と20年のいずれか短い方とされています。経済的残存使用年数とは、その資産が経済的に使用可能と予測される年数とされています。また、経済的残存使用年数が税法の耐用年数と大きな違いがなければ税法の耐用年数に基づく残存耐用年数を経済的残存使用年数として用いることができます。
④減損損失の測定
減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額します(右図参照)。回収可能価額とは、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいいます。
減少額については、損益計算書上では減損損失として特別損失として計上します。貸借対照表上では、①減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする(直接控除形式)、②減損損失累計額を取得原価から間接控除する(独立間接控除形式)、③減損損失累計額を減価償却累計額に合算して表示(合算間接控除形式)-することが可能になっています。
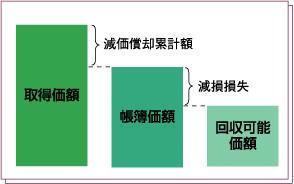
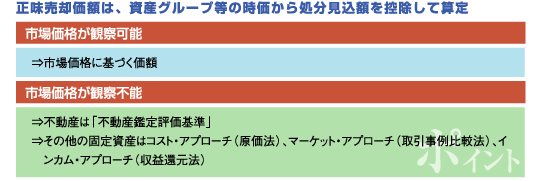
平成18年3月期から全面適用 どうなる!?固定資産の減損会計
ASB・固定資産の減損会計における適用指針の概要を紹介
企業会計基準委員会(ASB)は3月5日、「『固定資産の減損に係る会計基準の適用指針』の検討状況の整理」を公表しています。固定資産の減損会計は平成18年3月期から全面適用されることになりますが、平成16年3月期からの早期適用が認められています。このため、適用指針の策定を行っている企業会計基準委員会では、今年の秋頃を目処に適用指針を決定する予定です。ただし、今回の固定資産の減損会計は、企業にとっては大きな影響を与えることも予想されるため、適用指針を決定する前にその論点を明らかにしたものです。今回は、この適用指針の検討状況の概要をお伝えします。
※原文は財務会計基準機構のホームページで閲覧することができます!
http://www.asb.or.jp/summary_issue/impairment/impairment.html
固定資産の減損会計とは?
固定資産の減損会計は、連結範囲の見直し、金融商品会計や退職給付会計の導入など、一連のいわゆる会計ビッグバンの締めくくりの一つといえるもので、米国会計基準や国際会計基準ではすでに導入されています。固定資産の減損会計とは、資産又は資産グループの収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させるよう帳簿価額を減額する会計処理のことです。時価の変動を評価に反映させる時価会計とは異なります。
減損会計の対象となる資産は何?
固定資産の減損会計の対象となる資産は、当然のことながら固定資産となります。有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が対象になります(図1参照)。ただし、金融商品会計基準における金融資産、税効果会計基準における繰延税金資産、研究開発会計基準における市場販売目的のソフトウェアなど、他の基準に減損処理に関する定めがある資産については対象から除かれています。
それでは、固定資産の減損会計の手順に従い、それぞれの項目についてみていきます(図2参照)。
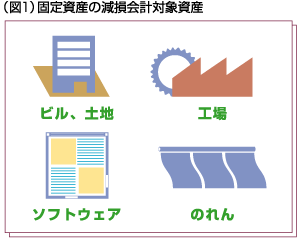
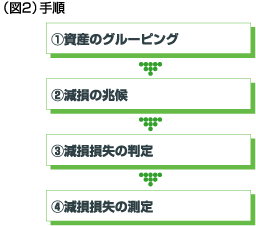
①資産のグルーピング
固定資産の減損会計を適用する際に行う手順の最初は資産のグルーピングを行うことです。個別の固定資産について、減損しているかどうかを検討することはたいへんなことです。
このため、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位(管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の最小単位)をグルーピングすることになります。この資産グループを単位として減損の有無があるかどうかを検討することになります。
なお、資産のグルーピングを大きくすれば、全体としては減損を認識しづらくなります。資産のグルーピングをどのように行うかは実務上の大きな論点になりそうです。
②減損の兆候
減損の兆候では、減損損失を認識する必要がある資産グループかどうかを判別していく作業を行います。実際には、個々の企業で判断することになりますが、実務上の指針として一定の目安も設けられています。今回公表された「適用指針の検討状況」では、右の表にある事象がある場合には、「減損の兆候あり」ということになります。
また、今回のポイントとしては、「市場価格が著しく下落した場合」の数値基準が挙げられます。減損会計専門委員会では、当初、「市場価格が帳簿価額からおおむね30%程度以上下落した場合」とされていましたが、最終的には、50%程度以上下落と30%程度以上の下落の両論併記となっています(※ただし、30%の方がよいとの提案がなされています)。
企業側からすれば、50%という数値の方が、減損会計を適用する上で減損の兆候という“網”にかからないということになります。したがって、この点は最後まで議論が続く項目であると考えられます。
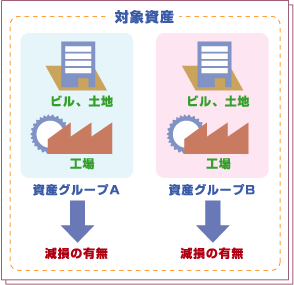
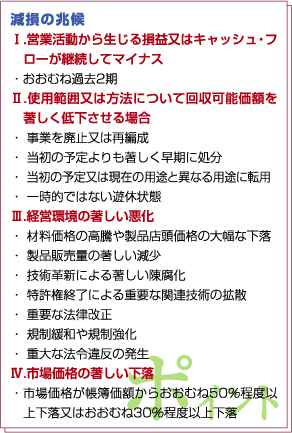
| 適用時期の先送りは? 固定資産の減損会計は平成18年3月期から全面適用(※平成16年3月期からの早期適用も可能)になりますが、最近では、自民党の一部から導入の先送りを求める声が出てきました。今後の動きにも十分注意することが必要ですが、EUでは平成17年から国際会計基準を全面的に導入することになっているため、仮に導入が先送りされることになれば、国際的な批判を受けることになるでしょう。また、適用しない会社は、市場から“あぶない会社”なのではといった烙印を押されることにもなりかねません。 |
③減損損失の判定
減損の兆候がある資産又は資産グループについての減損損失を認識するかどうかの判定は、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することになります。割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識します。
さて、この割引前将来キャッシュ・フローを見積もる期間は、資産の経済的残存使用年数又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数と20年のいずれか短い方とされています。経済的残存使用年数とは、その資産が経済的に使用可能と予測される年数とされています。また、経済的残存使用年数が税法の耐用年数と大きな違いがなければ税法の耐用年数に基づく残存耐用年数を経済的残存使用年数として用いることができます。
④減損損失の測定
減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額します(右図参照)。回収可能価額とは、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額をいいます。
減少額については、損益計算書上では減損損失として特別損失として計上します。貸借対照表上では、①減損処理前の取得原価から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得原価とする(直接控除形式)、②減損損失累計額を取得原価から間接控除する(独立間接控除形式)、③減損損失累計額を減価償却累計額に合算して表示(合算間接控除形式)-することが可能になっています。
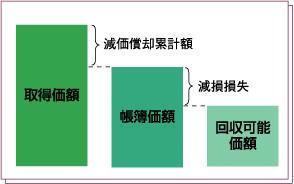
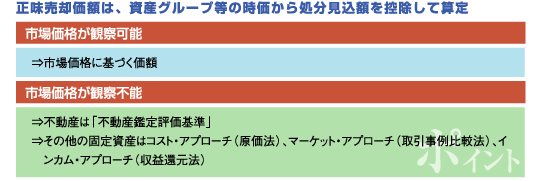
| その他の論点 ①中間会計期間で減損処理を実施した場合は? 中間会計期間で減損処理を行った場合には、年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処理は行う必要はありません。 ②土地再評価法を適用した土地を減損処理した場合の土地再評価差額金は? 多くの企業が土地再評価法を適用していますが、再評価を行った土地は再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用します。減損処理を行った部分の土地再評価差額金は取崩し、剰余金修正を通して未処分利益に繰入れることになります。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















