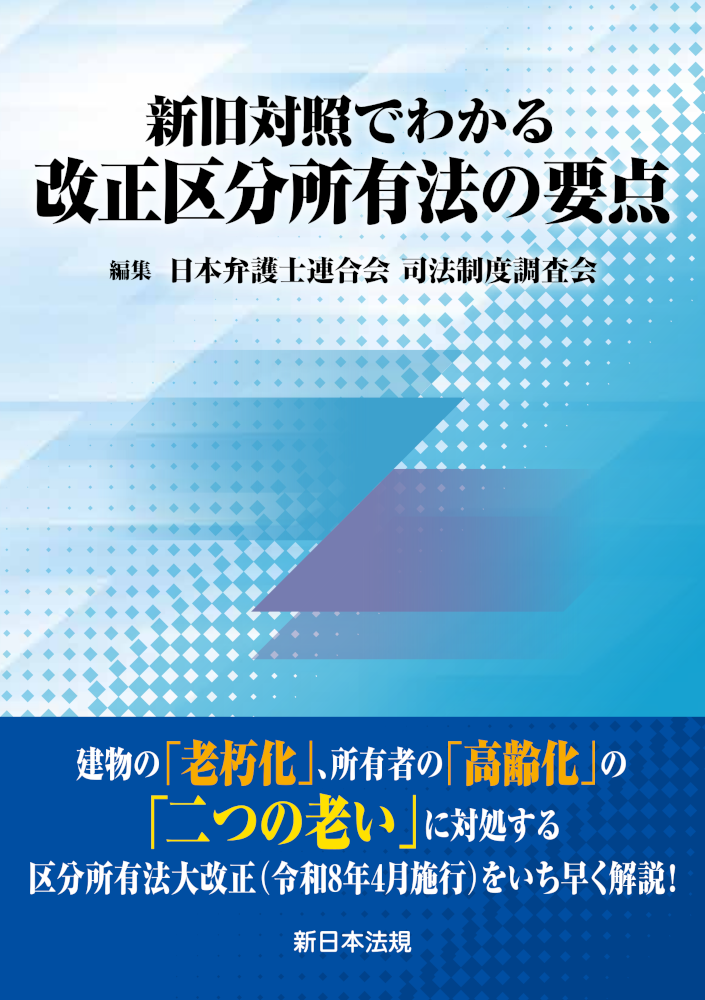解説記事2020年12月14日 ニュース特集 令和3年度法人関係税制改正の全容(2020年12月14日号・№862)
ニュース特集
コロナ・DX関連の改正が目白押し、自社株対価MAは認定要件全廃
令和3年度法人関係税制改正の全容
12月10日、令和3年度税制改正大綱が公表された。令和3年度税制改正の2大キーワードとなったのが、「コロナ」と「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」だ。改正項目には、コロナ禍を踏まえた既存制度の緩和措置や、DXを促進するための措置が目に付く。
このうち法人関係の改正では、欠損金の繰越控除制度について、産業競争力強化法に基づく「事業適応計画(仮称)」を受けることを条件に、「2年間」にわたって生じた欠損金額を、翌期以降、最長5年間、最大で100%繰越控除できる措置を設ける。同様に企業の業績悪化を背景として、研究開発税制では、十分な所得が生じない場合でも総額型における法人税額の控除上限に抵触しないよう、「基準年度比で売上が2%以上減少」かつ「基準年度比で試験研究費が増加」することを条件に、令和3年度から2年間、控除上限を現行の25%から30%に引き上げる。
また、令和2年1月1日の公示地価とコロナ禍を受けた実勢価格が乖離する中、商業地等、住宅用地、農地の区別なく、地価上昇により税額の上昇が見込まれる「すべて」の土地について、令和3年度の固定資産税の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額にする。令和3年度限りの措置とはいえ、税制改正議論の中では「負担軽減の対象を商業地等に絞るべき」などの意見も聞かれただけに、本改正は大きなサプライズと言えよう。
コロナ感染拡大防止とDXは、(国税・地方税ともに)押印義務の原則廃止、スキャナ保存制度や電子取引に係るデータ保存制度の要件緩和(861号(前号)40頁参照)、地方税共通納税システムの対象税目への固定資産税等の追加、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化(本号11頁参照)など、税務手続きのデジタル化を一気に進めることとなった(ただし、準備期間を考慮し、施行は数年先となる)。このほかDX関連では、産業競争力強化法に基づく税制措置として、カーボンニュートラル投資促進税制とDX投資促進税制が導入され、税額控除及び特別償却が認められる。さらに、自社利用ソフトウェアの研究開発費が研究開発税制の対象とされるとともに、本改正の“副産物”として、棚卸資産、繰延資産についても、その取得価額に研究開発費が含まれる場合には、それらの資産の取得価額は取得時において税額控除の対象とする。
昨年度税制改正から積み残しとなっていた自社株対価M&Aに係る税制措置(被買収企業株主における株式の譲渡損益の繰延べ)の見直しも実現し、租税特別措置として「恒久化」され、かつ産業競争力強化法に基づく「特別事業再編計画」の認定も不要となる。
本特集では、法人関係の主要改正項目の内容をどこよりも早く詳報する。
欠損金の繰越控除制度
「2年間」分の欠損金を最長5年間、最大100%繰越控除
コロナ禍で業績悪化に陥る企業が続出する中、欠損金の繰越控除制度の緩和を求める声が高まっていたが、令和3年度税制改正では、産業競争力強化法の認定(事業適応計画(仮称))を受けることを条件に、「2年間」にわたって生じた欠損金額を、翌期以降、最長で「5年間」、最大で「100%」繰越控除できる措置を設ける。
ここでいう2年間とは、「令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む事業年度」を原則とする。3月決算法人の場合、令和2年度及び令和3年度の欠損金が対象となる(特例対象欠損金額)。
なお、一定の場合には「令和2年2月1日から同年3月31日までに終了する事業年度及び翌事業年度」、すなわち令和元年度と令和2年度も対象となる。令和元年度においてコロナの影響が顕在化したのは令和2年2月以降であり、それ以前の期間に対応する赤字はコロナとは関係がないことから、当初は令和元年度を対象事業年度に含める必要はないのでないかとの指摘もあったが、最終的には当初予定より幅広い期間が対象に含まれることになった。ただし、特例対象欠損金額はあくまでも2事業年度分であり、3事業年度分をカウントできるわけではない。
この特例による控除限度額は、特例対象欠損金額のうち、事業適応計画に従って行った投資の額に達するまでの金額が上限となる。控除限度額の緩和による税負担の減少が内部留保の増加につながることがないようにという趣旨であろう。それでも、平成27年度・28年度税制改正で法人税率の引き下げの財源として相次いで控除限度額を縮減してきたという経緯から改正実現のハードルは高いと見られていただけに、コロナ禍で業績悪化に苦しむ企業からは本改正を歓迎する声が上がっている。
ただし、上述のとおり、本措置の適用を受けるには「事業適応計画」の認定を受けることが条件となる。現時点で判明している「ROAの5%向上」のほか、本事業適応計画における個別の要件については今後詳細に確認する必要がある。
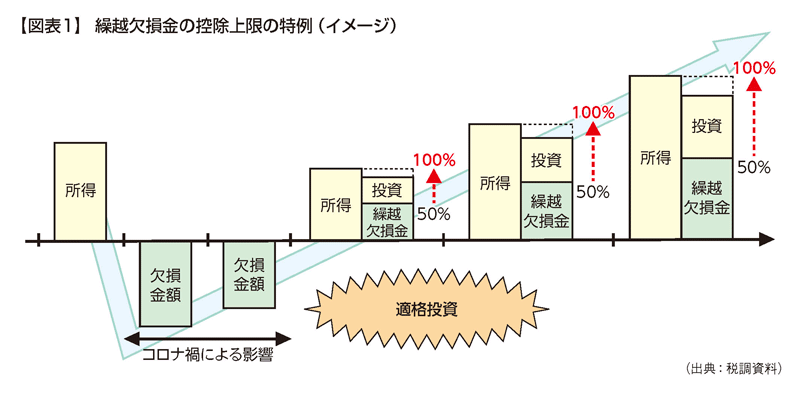
研究開発税制
総額型の控除上限、「売上減少と試験研究費増加」の同時充足要件に30%
コロナ禍により今期のみならず来期以降も十分な所得が生じない企業は、研究開発税制の「総額型」における法人税額の控除上限に抵触する可能性がある。こうした中、令和3年度税制改正では、令和3年度から2年間、総額型の控除上限を25%から「30%」に引き上げる。
ただし、そのためには「基準年度比で売上が2%減少」かつ「基準年度比で試験研究費が増加」という要件を満たす必要がある。ここでいう基準年度とは、「令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度」を指す。例えば3月決算法人であれば、「平成30年度(2018年度)」となる。上記要件のポイントは、両要件を同時に満たさなければならないという点にある。要するに、コロナ前の事業年度に比べ業績は悪化したが、それでも研究開発活動に積極的な企業については控除上限を拡充する、というのが本改正の趣旨と言えるが、不況期における企業の実態を踏まえると、売上が減少しながらも試験研究費を増やすという経営判断はなかなかとりにくいだけに、実際にどれだけの企業が本措置の適用を受けることができるかは未知数と言える。
それでも、繰越欠損金の控除限度額同様、研究開発税制の総額型における法人税額の控除上限も、平成27年度税制改正において法人税率引下げの財源として30%から25%に縮減されたという経緯を踏まえれば、改正が実現したということだけでも大きなインパクトがあろう。
試験研究費の増加インセンティブ強化、総額型の最低控除率は2%に
また、総額型については、上記控除上限の引上げに加え、試験研究費を維持・拡大するインセンティブを強化する観点から、控除率のグラフも見直す。現行制度では、試験研究費が大幅に減少した場合でも最低6%の控除率が保証されていたが、改正後はこれが「2%」に縮減される。控除率が2%となるのは、増減試験研究費割合が「マイナス37%以下」の場合となる。改正議論の中では、試験研究費の減少率が著しい企業については控除率を0%にする案も聞かれたが、それでは「総額型」とは言えないとの指摘もあり、この水準で決着した。少数ではあるが、年度によって試験研究費が乱高下する企業も見受けられる。こうした企業は本改正に抵触し、控除率が2%となる可能性があろう。
増減試験研究費割合0%の場合の控除率である8.5%は維持される。企業の控除率は同割合が0%前後(マイナス数%〜プラス数%)であることが多いことを踏まえ、改正した場合の影響の大きさに配慮したと言えそうだ。一方、現行制度では同割合8%で控除率の傾きが0.175から0.3に変わるところ、改正後は、同割合「9.4%」で控除率の傾きが「0.35」となる。結果として、同割合が8%〜12.9%の場合は控除率が現行よりも低下するのに対し、同割合12.9%以上の場合は控除率が上昇し、試験研究費の増加インセンティブが強化されることになる。9.4%という新たな「屈折点」は、現在策定中の「第6次科学技術基本計画」を念頭に置いたものであり、民間試験研究費の“あるべき姿”から逆算した数値だという。
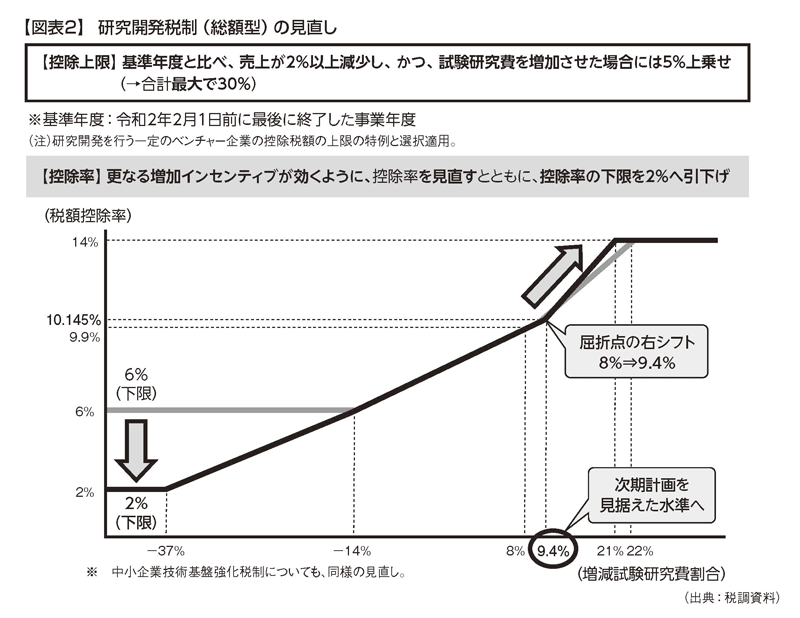
自社利用ソフトの開発費に研究開発税制 棚卸・繰延資産にも波及
DXの観点からも注目されていたのが、自社利用ソフトウェアに関する改正の行方だ。
現行制度上、自社利用ソフトウェアは、将来の収益獲得等が見込まれる場合には資産計上しなければならず、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費の損金算入は認められていない(法基通7-3-15の3(2))。しかし、ネットワーク化の進展により、パッケージソフトを客先に売切りで提供する形から、プロバイダ側が用意したクラウド環境を顧客の利用に供するサービスへとビジネスモデルの移行が進む中、現状の取扱いを放置すれば日本企業は経済のデジタル化に後れをとることになりかねないとの強い批判を受け、令和3年度税制改正では、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費も研究開発税制の対象とされることになった。
ただし、企業側が要望してきた支出時の即時損金算入は叶わなかった。即時損金算入を認めるには、単なる通達改正にとどまらず法人税法の改正が必要となることなどがネックになったものとみられる。結果として、自社利用ソフトウェアに係る研究開発費は、現行通り税務上は資産計上を維持しつつ、その取得価額を税額控除の対象とする。
このように、自社利用ソフトウェアについては、税務上は資産計上が必要という取扱いは変わらないため、会計と税務の取扱いが異なる状況が続く見通しだが、研究開発税制の対象になった意義は大きい。本改正が、クラウドサービスの提供などDXの追い風となることが期待されるところだ。
また、自社利用ソフトウェアに係る改正の“副産物”として、棚卸資産、繰延資産についても、その取得価額に損金経理した研究開発費が含まれる場合には、それらの資産の取得価額は取得時において税額控除の対象とする。現行制度上、棚卸資産に含まれる試験研究費は売上原価計上時に認識し、また、繰延資産については減価償却費が研究開発税制の対象となるが、改正後はこれらの取扱いが異なるものとなる。研究開発税制は、試験研究費の「支出」に対するインセンティブであるところ、支出時、すなわち資産の取得時に支援対象とすることを明確化する狙いがあると言えよう。
一方、研究開発用資産については、取得価額ではなく、その減価償却費を税額控除の対象に含めるという現行制度を維持する。未償却残高が多いなど、現行制度を改正すれば影響が大きいことに配慮したものとみられる。
このほかの研究開発税制の改正としては、試験研究費の範囲の適正化や、オープンイノベーション税制の拡充・要件の合理化等が行われる。控除率10%超〜14%の部分、売上高試験研究費割合が10%を超える場合の上乗せ措置は2年間延長される。
その他の投資減税
CN・DXの両投資促進税制導入の影でムチ税制も3年延長
研究開発税制以外の投資減税として、カーボンニュートラル投資促進税制とDX投資促進税制が導入され、税額控除及び特別償却が認められる。いずれも産業競争力強化法に基づく税制措置となる。
なお、令和3年度税制改正議論ではほとんど話題に上ることがなかったムチ税制も“ひっそりと”3年延長されている。ムチ税制は所得が伸びているにもかかわらず賃金や国内設備投資が低調な場合に発動されることになるが、ムチ税制が発動される場合には、研究開発税制に加え、これら税制も適用できなくなる。
固定資産税
税額上昇見込みの全土地の課税標準額を据え置く“サプライズ”
令和3年度税制改正で大きなサプライズになったのが、固定資産税の完全据え置きだ。
税制改正議論の中では、負担軽減の対象を商業地等に絞る(すなわち住宅用地を除く)べきとの意見、あるいは、地価上昇土地といってもすべての土地を救済する必要はないのではないかとの指摘があったが、次回固定資産税評価替えのベースとなる令和2年1月1日の公示地価とコロナ禍を受けた実勢価格が乖離する中、最終的には「令和3年度限りの措置」として、商業地等・住宅用地・農地の区別なく、地価上昇により税額の上昇が見込まれるすべての土地について、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額にする措置が講じられることになった。地価下落により税額が減少する土地は、そのまま減額となる。現行の負担調整措置の仕組みは継続する。
なお、評価替えに伴う固定資産税に関する議論は、本来であれば3年に一度であるところ、今回の変則的な改正の影響により、令和4年度改正でも議論されることになる。
税務手続きのデジタル化
固定資産税の電子納税化が実現も、納税通知書自体の電子化は断念
令和3年度税制改正では、国税・地方税ともに原則として押印義務を廃止、スキャナ保存制度(電子帳簿保存法)や電子取引に係るデータ保存制度の要件緩和(以上、861号(前号)40頁参照)、地方税共通納税システムの対象税目への固定資産税等の追加、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化(本号11頁参照)など、コロナの感染拡大防止とDX両方の観点から「税務手続きのデジタル化」が一気に進む。
ただし、準備期間を確保する観点から、改正法の施行は数年先となる。具体的には、電子帳簿保存法の施行は令和4年1月1日、地方税共通納税システムの対象税目に固定資産税等を追加するのは令和5年度以後、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化は令和6年度以後となる。
いずれも企業のニーズが高かった改正項目だが、このうち固定資産税の電子納税化は企業にとっては数年来の“悲願”と言える。現状、固定資産税については、自治体から送付される納税通知書に基づき企業が納付する仕組みとなっているが、納税通知書が電子化されておらず、かつ、書式も自治体によってバラバラであるため、経理担当者が一件一件、各自治体の納税通知書を識別の上、手作業でエクセルに課税情報を入力・管理するという極めて非効率かつ重い事務負担を生じさせている。令和元年10月から稼働が開始した地方税共通納税システムは、現状、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、事業所税、個人住民税(の一部)を対象としており(令和3年10月からは、対象税目に個人住民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割を追加予定)、固定資産税は対象外となっているが、令和3年度税制改正により、これに固定資産税、都市計画税、自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)が追加される。ただし、企業側がかねてから主張してきた「納税通知書自体の電子化」は、情報量が比較的多く市区町村におけるシステム投資がかさむという予算上の難題に加え、固定資産税は事業者のみならず個人も納税義務者になるところ、電子的な送付をしようにも、個人の場合には相手に確実に届くことが容易に担保できないなど、詰めるべき課題が多いことから断念。この部分は「紙」が残る。また、事業者による「納税通知書番号」などの入力も手作業となる。
スキャナ保存制度(電子帳簿保存法)に関する改正の詳細は861号(前号)40頁の通りであり基本的に変更はないが、一点、訂正履歴確保要件を満たさない場合でも「一般電子帳簿」に該当し電子的な保存が可能になるとの当初の改正案について一部事業者が異議を唱えた結果、一般電子帳簿の要件として「正規の簿記の原則に従っていること」と「税務調査でダウンロードの求めに応じること」の2つが追加されている。
自社株対価M&A
「20%以内」なら金銭等を対価とすることも可
昨年度税制改正からの積み残しであり、令和3年度税制改正の目玉の一つとなっていた自社株対価M&Aに係る税制措置(被買収企業株主における株式の譲渡損益の繰延べ)の見直しも実現する。
組織再編税制との整合性等の問題から、法人税法本則による措置は困難と整理されたが、租税特別措置として「恒久化」されることになった。これに伴い、現行の産業競争力強化法に基づく特例措置は適用期限の到来をもって廃止される。また、新たな特例においては、産業競争力強化法に基づく「特別事業再編計画」の認定も不要となる。これにより、自社株対価M&Aの使い勝手は大幅に向上することになる。
自社株対価M&Aのベースとなるのは改正会社法で導入される株式交付制度である。したがって、株式交付同様、既存子会社株式の買い増しには利用できず、「子会社でないもの」を子会社にする買収にのみ適用される。また、株式交付では、自社株のみならず金銭等も対価としてミックスできることから、税制措置においても金銭等が「20%以内」にとどまる場合は、金銭等を対価とすることを認める。
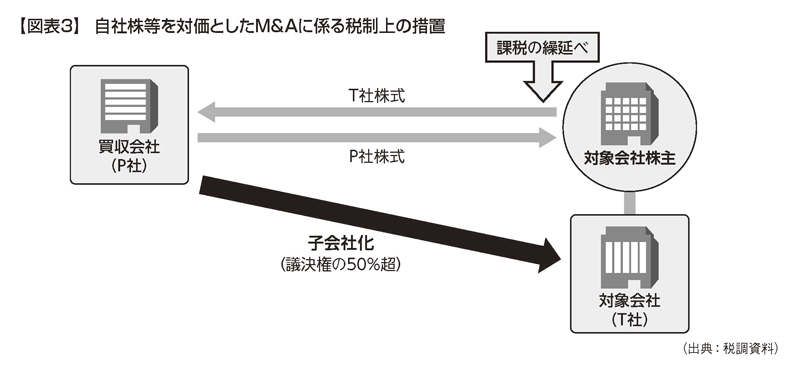
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.